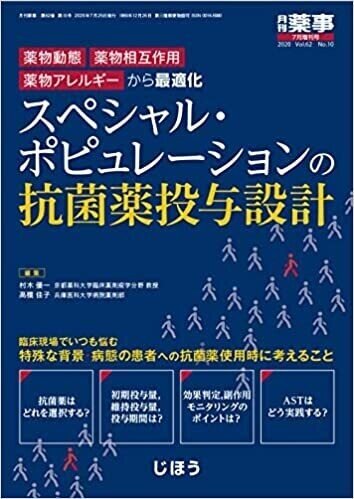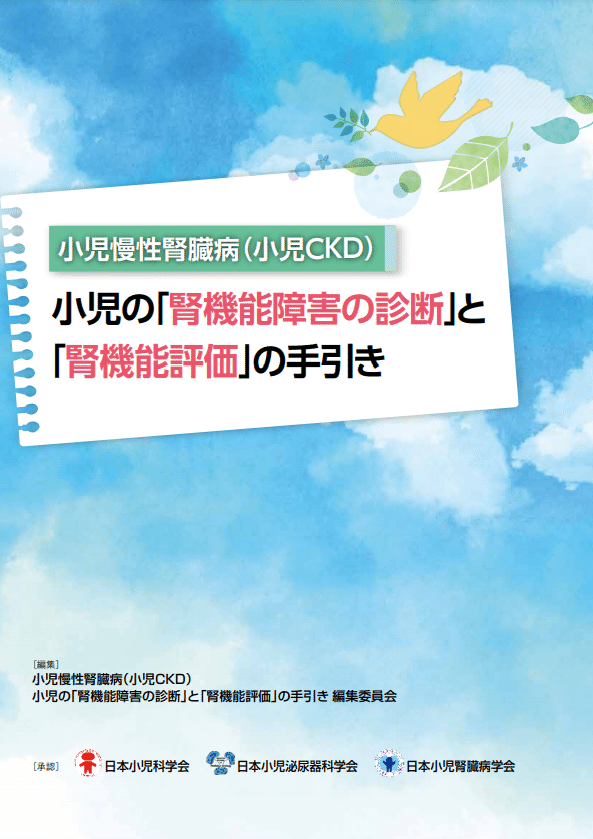【抗菌薬ミニ講座】あなたの知らない!?special populationの世界
こんにちわ、病院薬剤師だまさんです。
YouTubeチャンネル(病院薬剤師って素晴らしい【YouTube編】)のコンテンツ【睡眠学習】抗菌薬ミニ講座を1年ぶりに再開することとなりました。
今回のシリーズは下記の書籍にもとづいてお送りしていきます。
【月刊薬事 増刊】スペシャル・ポピュレーションの抗菌薬投与設計
※この記事はYouTube動画の台本となります。
第壱話 薬剤師がやらねば誰がやる
今回のテーマはスペシャル・ポピュレーション(special population)。
聞き慣れない言葉かもしれませんが、薬剤師にとっては極めて重要、医師よりも主導的に関わらなければならない領域と言えます。
以下の患者集団をご覧になり、イメージしてみてください。
「これらの患者に抗菌薬は通常量で大丈夫ですか?」
≪抗菌薬適正使用支援に関連するspecial population≫
❶薬物動態の変化
・新生児・小児
・肥満
・妊婦
・授乳婦
・高齢者・フレイル
・腎機能低下患者(AKI患者・CKD患者・間欠的血液透析患者・持続透析患者・腹膜透析患者)
・肝機能低下患者
・抗菌薬と相互作用を有する薬剤併用中の患者
・敗血症患者
・人工心肺施行患者
・四肢切断患者
❷免疫機能の低下
・臓器移植患者
・熱傷患者
・周術期患者・手術侵襲のある患者
・発熱性好中球減少症(FN)患者
・膠原病患者
❸その他
・抗菌薬アレルギー患者
ただ、2018年に実施された全国調査によれば、special populationを対象とした介入の実施率は全体の約2割に過ぎませんでした。
special populationに対する介入は、安全性を主眼に行われることが多いと思いますが、抗菌薬に関して言えば、「減量すれば済む」という単純な問題ではありません。
判断を誤れば有効性、ひいては患者の予後をも左右し得るからです。
そのためにも、薬剤師はspecial populationにおけるPPKの概念を十分に理解した上で、ベイズ解析で得られた数値は慎重に評価しなければなりません。
第弐話 新生児

新生児は在胎期間と出生後の経過期間で発達の度合いが異なります。
実務的には、在胎週数(GA)、週齢(PNA)および両者を合わせた妊娠週数(PMA)をもとに臓器機能を評価します。
在胎週数(GA)+ 週齢(PNA)= 妊娠週数(PMA)
成人と比べ体内水分量が多く、代謝能および排泄能はいずれも未熟です。
≪新生児の薬物動態の特徴≫
吸収
・胃内pH変動が激しい・腸管運動が鈍い ⇒ 原則として経口投与は避ける
・筋注や皮下注は血流の影響や筋拘縮の問題あり ⇒ 静注が原則
分布
・正期産児では体重の80%以上が水分(うち50%が細胞外液)
▶在胎期間が短いほど細胞外液の割合は上昇する
▶1歳で成人と同様(体重の60%)に
・血清アルブミン値(主に酸性薬物と結合)は1歳児より30%減
・α1-酸性糖蛋白質(主に塩基性薬物と結合)は1歳児より50%減
▶総血中濃度が低くても、遊離型薬物濃度は高めになる傾向
▶アルブミン結合能の高いSTやCTRXは核黄疸のリスクに注意
代謝
・シトクロムP450(CYP)活性(第Ⅰ相反応に関与)▶極めて低い
・抱合酵素活性(第Ⅱ相反応に関与)▶硫酸>グルクロン酸抱合
排泄
・抗菌薬は水溶性薬剤が多く、薬物動態も腎機能に左右されやすい
・日本小児腎臓病学会よりGFR推算式が提示されている(下記参照)
▶eGFRはあくまで推定値だが、経時的変化を捉えるには有用
抗菌薬の選択や投与量の調節に関する考え方は、成人とほぼ同様です。
新生児の用法・用量に関する情報は極めて少なく、仮にあったとしても参考値に過ぎません。
よって、児の状況(体内水分量や臓器の発達度)と使用抗菌薬の特性を踏まえたうえで、個別に検討するほかありません。
第参話 肥満

肥満はBMI(body mass index)で規定されますが、身長の個人差は何倍も変わる訳ではないため、多くの場合、体重で評価しても差し支えありません。
一般的に体重が増えるとV(分布容積)は増加しますが、CL(クリアランス)の増減は病態によりまちまちです。
BMI ≧ 25kg/㎡(WHOではBMI ≧ 30kg/㎡) ▶ 肥満
BMI ≧ 35kg/㎡ ▶ 高度肥満
高度肥満患者に体重換算用量式をそのまま適用すると過量投与となる恐れがあるため、「理想体重」を想定し、実測体重が理想体重の120%を超える場合には「補正体重」を採用します。
≪各種の理想体重推算式≫
抗菌薬TDMガイドライン
▶(男性)52 + 0.75 ×(身長[cm]-152.4)
(女性)49 + 0.67 ×(身長[cm]-152.4)
JAID/JSC感染症治療ガイドライン2019
▶(身長[cm])*2(二乗) × 22
サンフォード感染症治療ガイド2019
▶(男性)50 + 0.906 ×(身長[cm]-152.4)
(女性)45 + 0.906 ×(身長[cm]-152.4)
Devine式
▶(男性)49.9 + 0.89 ×(身長[cm]-152.4)
(女性)45.4 + 0.89 ×(身長[cm]-152.4)
【参考】除脂肪体重
▶(男性)(1.10×実測体重)- 0.0128 ×(実測体重/身長[cm])*2(二乗)
(女性)(1.07×実測体重)- 0.0148 ×(実測体重/身長[cm])*2(二乗)
補正体重 = 理想体重 + 係数☓(実測体重-理想体重)
▶係数は薬物により幅はあるが、一般的に0.4が用いられている。
ただ、これらはあくまで一般論であり、抗菌薬によって薬物動態は異なるため、用量設定の際には個々の情報も確認する必要があります。
また、前述の通り肥満患者のCLの変動には一定の法則はなく、確立した推算式もないため、クレアチニン値やイヌリン検査投与を用いた実測法が望ましいと言えます。
第肆話 妊婦

妊婦における基本的な治療戦略としては下記3点を考慮します。
❶投与の必要性の検討と適切な治療薬の選択
▶「有益性」「安全性」「使用実績」を重視
▶ペニシリン系・セフェム系・マクロライド系が比較的安全
❷患者への情報提供
▶添付文書以外の情報源の活用、偶発的使用への対応
❸妊婦の生理学的特性を考慮した投与設計
▶all or none期(受精~妊娠3週末) ※自然流産率:約15%
▶催奇形性リスク期(妊娠4~15週末) ※先天性異常児:約3%
▶胎児毒性リスク期(妊娠16週~分娩)
実際の薬物投与においては、妊娠中における薬物動態の変動を想定しつつ、個々の薬物における情報を収集のうえで投与設計を行い、投与中は効果と副作用について慎重にモニターを行います。
≪妊婦において想定される薬物動態の変動≫
吸収
・妊娠悪阻▶バイオアベイラビリティ・吸収速度の低下
分布
・体内水分量の増加▶分布容積の増加(水溶性薬剤)
・体内脂肪量の増加▶分布容積の増加(脂溶性薬剤)
・血中蛋白質の減少▶遊離型薬物の増加
代謝
・CYP活性の変動(増減まちまち)▶肝クリアランスの変動
排泄
・腎血流量・糸球体濾過量の増加▶腎クリアランスの増加
妊婦の領域は介入研究ができないためエビデンスが乏しく、患者や家族の警戒心も強いことから、医療従事者も思考停止になっていることがあります。
例えば治療上必須な薬を休薬してしまう、といったことも当然のように行われています。
よってこの領域では、入手しやすい情報(添付文書等)に留まらず、必要に応じて更に踏み込む姿勢が求められます。
別の意味でspecial populationと言えるかもしれません。
第伍話 授乳婦
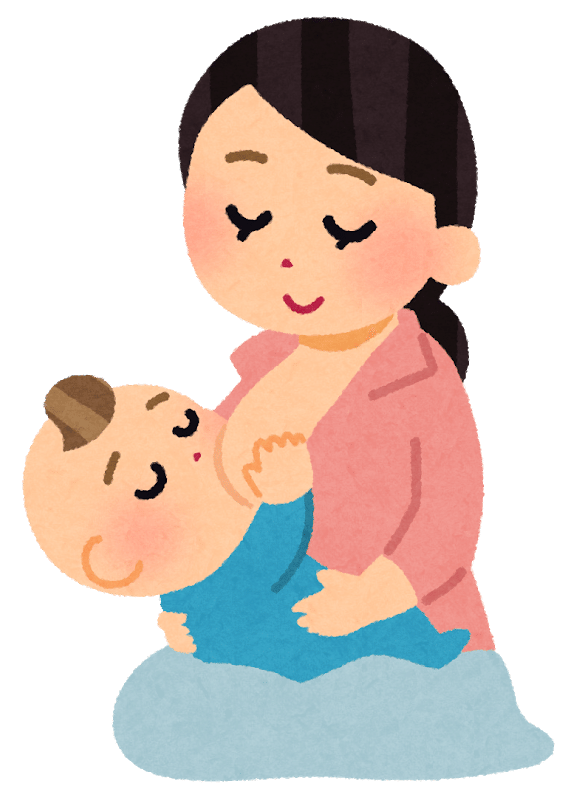
現行の添付文書は「乳汁移行あり▶授乳中止 or 禁止」となっていますが、世界的に母乳育児が推奨される時代が到来し、乳汁移行性だけでなく児への影響を総合的に判断して授乳の可否を判断する必要性が高まっています。
≪薬剤の乳汁移行性の評価と指標≫
薬剤特性と薬物動態の指標
・分子量▶低分子量(<200)ほど移行しやすい
・蛋白結合率▶結合率が高い(>90%)ほど移行しにくい
・T1/2(消失半減期)▶短い(1~3hr)ほど移行しにくい
・pKa▶イオン・非イオン性が同等なpHより低い方が移行しにくい
・バイオアベイラビリティ▶経口吸収率が低いほど移行しにくい
・Tmax▶授乳タイミングを判断する指標になる
乳汁移行と薬剤曝露の指標
・M/P比(母乳/血漿薬物濃度比)▶1未満だと移行しにくい
・RID(相対的乳児投与量)▶10以下が安全の目安
※計算式等はメインブログを参照
実務的には、授乳可否は下記媒体を複数用いて総合的に評価します。
≪医薬品の授乳可否の評価媒体≫
❶Medications and Mothers' Milk [5段階評価]
❷Drugs in Pregnancy and Lactation[7段階評価]
❸妊娠と授乳-改訂3版-[4段階評価]
❹母乳とくすりハンドブック2010[4段階評価]
❺Drugs and Lactation Database(Lact Med)
❻妊娠と薬情報センター
第陸話 高齢者・フレイル

高齢者は腎機能や肝薬物代謝能の低下などにより、若年者とは薬物動態が異なり、特にフレイル高齢者の場合はより変動が大きいと予測されます。
フレイルとは
加齢に伴う様々な臓器機能変化や予備能力低下によって外的なストレスに対する脆弱性が亢進した状態を指し、日常生活機能障害、転倒、認知症をはじめとする健康機能障害を発症するリスクが高いとされている。言い換えれば自立と要介護状態の中間(虚弱の期間)である。
J-CHS基準(フレイルの判定基準の一つ)
・体重減少:6ヶ月間で2~3kgの減少
・倦怠感:直近2週間で理由不明
・筋力低下:握力が男性26kg未満、女性18kg未満
・歩行速度:1.0m/秒未満
・活動量:1週間以内に体操・定期的な運動なし
≪高齢者において想定される薬物動態の変動≫
吸収
・消化管吸収は遅延するが、受動拡散のため加齢による影響は軽微
・初回通過効果は加齢による影響を受ける
分布
・細胞内水分量の減少▶分布容積の減少(水溶性薬剤)
・体内脂肪量の増加▶分布容積の増加(脂溶性薬剤)
・血中蛋白質は減少するが、遊離型薬物濃度は変化しない(要補正)
代謝
・肝血流速度ろ肝重量の低下等▶肝クリアランスの低下
・CYP活性▶変動は分子種によりまちまち
・抱合酵素活性▶若年者と有意差なし
排泄
・腎血流量の低下(40~50%↓)
・糸球体濾過速度の低下(20~30%↓)
・尿細管分泌能の低下(30%↓)
▶作用時間延長に注意
・胆汁排泄能の低下
▶胆汁うっ滞(閉塞性黄疸)に注意
抗菌薬は、高齢者であっても各感染症で推奨されている薬剤を選択します。
一方、投与量に関しては初回投与量は減量しないのが原則であり、維持用量を患者の状態に応じて調節します。
腎機能の評価方法は各種存在しますが、フレイル高齢者にはCysCを用いたeGFRが適しています。
肝機能は定量的な評価指標がないため、Child-Pugh分類を目安にします。
≪各種腎機能評価方法と特徴≫
❶標準化eGFR(SCr算出)
❷標準化eGFR(CysC算出)
▶体格を考慮しないため薬用量設定には不向き
❸Cockcroft-Gault(CG)式
❹個別化eGFR(SCr算出)
▶フレイル高齢者では腎機能を過大に評価
❺個別化eGFR(CysC算出)
▶筋肉量の影響を受けないためフレイル高齢者向き
第漆話 腎機能低下患者(AKI患者)

急性腎障害(AKI)患者は腎機能が短期間で大きく変動します。
≪AKI診断基準と病期分類-KDIGO診断ガイドラインより-≫
AKIの定義
1.⊿SCr≧0.3mg/dL(48時間以内)
2.SCrの基礎値から1.5倍以上の上昇(7日以内)
3.尿量0.5mL/kg/hr未満が6時間以上持続
**項目1~3のうち1つを満たせばAKIと診断する。
重症度分類
[ステージ1]
・⊿SCr≧0.3mg/dL(48時間以内)またはSCr1.5-1.9倍以上の上昇
・尿量0.5mL/kg/hr未満が6時間以上持続
[ステージ2]
・SCr2.0-2.9倍以上の上昇
・尿量0.5mL/kg/hr未満が12時間以上持続
[ステージ3]
・SCr3.0倍以上の上昇またはSCr≧4.0mg/dLまでの上昇
または腎代替療法の開始
・尿量0.3mL/kg/hr未満が24時間以上持続
または12時間以上の無尿状態の持続
**SCr基準と尿量基準で重症度分類が異なる場合は、より重症度の高い方を
採用する。
本来、腎機能に応じた薬用量調節の指標として汎用されるCcrは、腎障害の進行が緩やかなCKD患者を想定しています。
これに対し、AKI患者では腎機能の急激な変動にSCrの変化が追い付かずタイムラグが生じるため、Ccrに基づいた投与設計が困難となります。
急性腎障害の進行期間にCcrを用いると▶過大評価(過量投与のリスク)
腎機能の回復期にCcrを用いると▶過小評価(過少投与のリスク)
このため、AKI患者に対する抗菌薬の投与設計においては、副作用(特に腎障害)を最小限に抑えつつ、過度な減量による抗菌効果の不足を回避するという多面的な視点が必要になります。
安全性の広い抗菌薬▶過度な減量を避ける(遅らせる)投与設計
安全性の狭い抗菌薬▶過量投与に注意した(含TDM)投与設計
第捌話 腎機能低下患者(CKD患者)

慢性腎臓病(CKD)は腎クリアランスの低下が特徴的ですが、様々な病態変化を包括しているため、原疾患やCKDの重症度により吸収・分布・代謝にも影響を及ぼします。
≪慢性腎臓病(CKD)の定義-CKD診療ガイドライン2018-≫
①尿異常,画像診断,血液,病理で腎障害の存在が明らか
特に0.15 g/gCr以上の蛋白尿(30mg/gCr以上のアルブミン尿)の存在が重要
②GFR<60 mL/分/1.73 ㎡
**①②のいずれか、または両方が3ヶ月以上持続する疾患のこと
≪CKD患者の特徴≫
・感染がなくともCRPやプロカルシトニンが上昇
・免疫能が低下(糖尿病や免疫抑制剤服用中)
・耐性菌の保有率が高い ※海外の報告
投与設計においては、参照する情報毎に腎機能推算式の取り扱いに留意し、PK/PD理論の応用、有効性と安全性の均衡などを考慮します。
≪初回(負荷)投与量≫
腎機能正常者と同様
≪維持投与量≫
腎機能に応じて設定するが、腎機能推算式の取り扱いに留意が必要
CKD患者では、過量投与に伴う有害事象、電解質異常の助長、薬剤性腎障害などに留意するとともに、相互作用による併用薬の有害事象にも留意する必要があります。
≪CKD患者で注意すべき主な有害事象と抗菌薬≫
脳症(意識障害・けいれんなど):CFPM、IPM/CS、PAPM/BP
けいれん、低血糖、腱障害など:ニューキノロン系抗菌薬
血小板減少:LZD
CPK上昇、横紋筋融解症:DAP
高Na血症:FOM(注射剤)
高K血症:PCG、ST
カルニチン欠乏:ピボキシル基を有するセフェム系抗菌薬(CFPN-PIなど)
腎障害:[中毒性]VCM、AGs、[尿路閉塞性]ST
第玖話 腎機能低下患者(間欠的血液透析患者)

間欠的血液透析は、週当たりに換算するとCcr10mL/分程度寄与します。
血液透析(HD)患者における抗菌薬の選択は標準的な思考で差し支えありませんが、投与法の設定に関して収集すべき情報は増えます。
≪HD患者において収集すべき薬物情報≫
薬物特性を特徴づけるパラメータ
・尿中未変化体排泄率
・活性代謝物の有無とその排泄経路
・全身クリアランス(腎/非腎)
・腎機能低下による
クリアランスの低下度(AUC増加度)
半減期の延長度
バイオアベイラビリティの変化
HD除去性(予測)に関連するパラメータ
・分子量
・蛋白結合率▶高いとダイアライザを通過しない
・分布容積▶大きいと除去効率が下がる
・脂溶性(O/W係数)
有効性・安全性の評価
・使用禁忌
・治療エビデンス
・HD患者における副作用の特徴
・代替薬の有無
HD中に投与を行うべき抗菌薬はなく、HD後に投与するのが原則です。
HD除去率は重要な要素ではあるものの、評価方法はまちまちであり、厳密な計算をするより、非HD時の血中濃度推移を推測する方が臨床上は有益です。
抗菌薬は大半は腎排泄型の薬剤であり、多くはHDが有利に働きますが、イレギュラーイベントの影響も頭にいれておく必要があります。
≪HD患者のメリット≫
・時間依存性の抗菌薬(β-ラクタム系など)で%TAMを確保しやすい。
・アミノグリコシド系抗菌薬などによる腎毒性が無視できる。
・濃度依存性の抗菌薬(アミノグリコシド系など)で高用量設定が可能。
▶高用量を投与直後にHDで除去するという治療が可能
≪HD除去率に影響するイレギュラーイベント≫
・HD条件の変化
・血液再循環(20%以上で問題視される)
・HD中の抗菌薬点滴(緊急時を除き避ける)
投与設計は個別に血中濃度推移を想定してを行うべきですが、一般的なPK/PDパラメータがHD患者に適合するかは、検討が十分ではありません。
ただ、腎不全患者において安全性マージンが狭い抗菌薬は選択しません。
≪中枢毒性が高いため高用量を投与しない抗菌薬≫
・CFPM(0.5g/日以下)
・IPM/CS(0.5g/日以下)
・CTRX(1g/日以下)
**著者(西久保 拓氏)の見解
第拾話 腎機能低下患者(持続透析患者)

持続的腎代替療法(CRRT)は主に救急集中治療領域で用いられます。
HDに比べ膜面積の小さな血液濾過器を用いて24時間持続的かつ緩徐に施工するため、循環動態が不安定な重症患者や小児でも使用可能です。
≪持続的腎代替療法(CRRT)の種類≫
・持続的血液透析(CHD):拡散の原理を利用
・持続的血液濾過(CHF):濾過の原理を利用
・持続的血液濾過透析(CHDF):拡散・濾過の原理を利用
吸着しない単一の分子を想定した場合、CRRTは分子量により溶質除去能が異なり、理論的には排液流量が変化することで除去能が変化します。
CL = fu(非蛋白結合型分布)× QE(排液流量)
**一般的にfuは0~1、QEは10~35mL/分▶CLは10~35mL/分以下となる
また、CRRTは腎補助目的以外に炎症性サイトカイン除去目的で使用される場合もあり、患者自身の薬物クリアランスをも加味する必要性があり得ます。
CRRT患者において、全身クリアランス(CLtot)は肝クリアランス(CLh)と腎クリアランス(CLr)とCRRTのクリアランス(CLCRRT)の総和です。
CLtot = (CLh+CLr)+ CLCRRT
患者自身のクリアランス(CLh+CLr)と CRRTのクリアランス(CLCRRT)のどちらに基づいて投与量を設定するべきかは、薬物が「腎排泄型」か「肝代謝型」かである程度判断することができます。
CLh+CLr << CLCRRT ▶ CLtot ≒ CLCRRT(CRRTのCLで用量設定)
CLh+CLr >> CLCRRT ▶ CLtot ≒ CLh+CLr(肝・腎のCLで用量設定)
≪尿細管・集合管で分泌や再吸収の影響を受ける薬剤≫
・FLCZ ・CL(コリスチン)
**減量の必要なし
≪透析膜への吸着が報告されている薬剤≫
透析膜PS▶VCM
透析膜AN69▶AGs,VCM
透析膜PMMA▶RFP,TEIC、AMK
第拾壱話 腎機能低下患者(腹膜透析患者)

腹膜透析(PD)患者において問題となる感染症は、腹膜炎やカテーテル関連感染症(出口部感染・トンネル感染症)であり、そのマネジメントはPD離脱を避けるうえで極めて重要です。
PD関連感染症のエンピリック治療としては、グラム陽性菌とグラム陰性菌の両方をカバーする抗菌薬を腹腔内投与します(一部は経口剤も使用)。
≪腹膜炎治療で推奨されるAGsの腹腔内投与量≫
AMK
(間欠投与;1日1回)2mg/kg/日
(連続投与;交換毎)初回25mg/L、維持12mg/L
GM
(間欠投与;1日1回)0.6mg/kg/日
(連続投与;交換毎)初回8mg/L、維持4mg/L
NTL
(間欠投与;1日1回)0.6mg/kg/日
(連続投与;交換毎)維持10mg/L
TOB
(間欠投与;1日1回)0.6mg/kg/日
(連続投与;交換毎)初回3mg/L、維持0.3mg/L
PD患者におけるAGsの薬物動態を事前に予測することは困難であるため、症例毎にTDMを実施して個別最適化を図ることが重要です。
エンピリック治療が無効な出口部感染は非結核性抗酸菌(NTM)が原因であることが多く、AMKの静脈内投与か腹腔内投与が行われます。
第拾弐話 肝機能低下患者

肝機能低下患者に関しては、腎機能低下時におけるeGFRのような、肝固有クリアランスと連動する検査値は存在しません。
≪肝機能低下を推定するための検査値≫
1.ALP、ALT、AST、γ-GTP、LDH▶肝細胞の破壊を反映
2.総ビリルビン、総蛋白、アルブミン▶肝機能低下を反映
そこで、近年では肝硬変患者の重症度判定に用いられていたChild-Pugh分類を投与量調整に使用するという潮流が生じています。
肝機能低下が急性(例.虚血性肝炎)の場合、投与量調節は不要です。
一方、慢性的な低下(例.肝硬変)の場合は、副作用リスクを低減するために経験的に投与量の調整を行います。
≪肝硬変患者の薬物動態に影響を与える因子≫
[病態側]
・肝血流および門脈体循環シャント
▶初回通過時の薬物抽出率が低下するため血中濃度が上昇する。
・CYP代謝活性
▶Child-Pugh分類グレードが進むほどCYP活性は低下する。
・低アルブミン血症
▶蛋白結合率の高い薬物は遊離型の比率が増える。
・胆汁うっ滞
▶薬物クリアランスが低下するため血中濃度が上昇する。
・門脈圧亢進症の合併症
腹水▶分布容積の増加、腸の浮腫や透過性の低下
門脈胃炎▶経口剤の吸収低下
腎血流の低下▶腎クリアランスの低下(肝腎症候群)
[薬物側]
1.腎排泄型か肝代謝型か
尿中未変化体排泄率(Ac)で判定する。
Ac≧70%▶腎排泄型(腎CL=全身CL)
30%<Ac<70%▶中間型(腎CL+肝CL=全身CL)
Ac≦30%▶肝代謝型(肝CL=全身CL-腎CL)▶次項へ進む
2.血流速度依存型か消失能依存型か
肝抽出比(EH)で判定する。
EH=肝CL/1600(mL/分)×B/P比(血球に移行している薬物比)
EH>0.7▶血流速度依存型
EH<0.3▶消失能依存型▶次項へ進む
3.蛋白結合依存型か非依存型か
消失能は遊離型薬物に働くため、遊離型分率(fuB)で判定する。
fuB = 1-血漿蛋白結合率
fuB<0.2▶蛋白結合依存型(肝硬変による蛋白合成低下の影響が強い)
fuB>0.2▶蛋白結合非依存型(肝硬変による蛋白合成低下の影響が弱い)
第拾参話 抗菌薬と相互作用をもつ薬剤服用中の患者

抗菌薬が関与する代表的な薬物相互作用は下記の通りです。
・EM、CAM、VRCZ、ITCZ+CYP3A4基質薬(シンバスタチンなど)
▶CYP3A4阻害作用による基質薬の濃度上昇
・MCZ+CYP2C9基質薬(ワルファリンなど)
▶CYP2C9阻害作用による基質薬の濃度上昇
・RFP+CYP3A4基質薬、CYP2C9基質薬
▶CYP3A4・CYP2C9誘導作用による基質薬の濃度低下
・CPFX+CYP1A2基質薬(チザニジンなど)
▶CYP1A2阻害作用による基質薬の濃度上昇
・CPFX、LVFX、DOXY、MINO、CFDN+Al、Mg、Ca配合剤
▶2~3価金属カチオンとのキレート形成による抗菌薬の吸収率低下
・カルバペネム系抗菌薬+バルプロ酸
▶詳細な機序は不明だが、バルプロ酸の濃度低下
遭遇頻度が最も高い相互作用はCYPが関与するものですが、未知のものも含め膨大な組み合わせがあり、従来まではマネジメントに難渋していました。
ところが近年、CR-IR法が開発され、基質薬のAUCの変化を定量的かつ網羅的に予測することが可能になりました。
CR-IR法
基質薬のAUC上昇率 = 1/(1-CR・IR)
※CR:クリアランスへの寄与率、IR:阻害率
相互作用の影響を臨床的にどこまで対処するかは、添付文書の記載に加え、その薬剤の安全性の広さや副作用の重篤度、治療の必要性、代替薬の有無などを総合的に勘案し、症例毎に検討する必要があります。
キノロン系抗菌薬と金属カチオン含有製剤の相互作用への対応は下記の通りです。
1.両剤の服用タイミングをずらす。
2.金属カチオンを含有しない薬剤に変更する。
3.キノロン系抗菌薬を注射薬に変更する。
カルバペネム系抗菌薬とバルプロ酸の相互作用については、以下の点を留意しておきましょう。
・詳細な機序不明(グルクロン酸抱合が関与?)
・バルプロ酸の血中濃度低下は、バルプロ酸の増量では回避できない。
・相互作用の影響は併用直後がピークとなる。
・併用終了後も併用前のレベルに回復するまで数日を要する。
・経口ペネム系抗菌薬(FRPM)は併用注意(バルプロ酸TDMは必須)
第拾肆話 抗菌薬アレルギー患者

抗菌薬アレルギーの発生率と免疫原性は下記の通り報告されています。
ペニシリン系:7.9%
▶(即時型)○ (遅延型)○ (系統内での交差反応)○
サルファ剤:4.39%
▶(即時型)△ (遅延型)○ (系統内での交差反応)△
マクロライド系:1.2%
▶(即時型)△ (遅延型)△ (系統内での交差反応)不明
セフェム系:1.1%
▶(即時型)○ (遅延型)○ (系統内での交差反応)△
テトラサイクリン系:0.7%
▶(即時型)△ (遅延型)△ (系統内での交差反応)不明
キノロン系:0.46%
▶(即時型)○ (遅延型)不明 (系統内での交差反応)○
CLDM:0.2%
▶(即時型)△ (遅延型)○
MNZ:0.15%
▶(即時型)△ (遅延型)○
**Macy E.et al:J Allergy Clin Immunol Pract 5より改変
最もアレルギー発生率の高いペニシリン系抗菌薬ですが、下記の報告があることも把握しておくと慌てずに済みます。
・IgEを介した即時型反応の既往歴があっても、5年経過で50%、10年経過で80%の患者がアレルギー反応を起こさなくなる。
・ペニシリンアレルギー患者の大半は、実はウイルス感染や細菌感染によるもので、実際に皮膚テストを施行すると90%が陰性となる。
セフェム系抗菌薬の免疫原性には、β-ラクタム環よりもR1側鎖構造が関与すると考えられており、同一の側鎖構造を有する薬剤は避けるべきです。
≪β-ラクタム系抗菌薬R1側鎖構造の類似性≫
Group1:CTRX、CTX、CFPM、CPDX-PR、CDTR-PI
▶Group2・3セフェム系とも交差反応の可能性あり
Group2:CXM-AX
▶Group1・3セフェム系とも交差反応の可能性あり
Group3:CAZ(、AZT)
▶Group1・2セフェム系とも交差反応の可能性あり
Group4A:CCL、CEX(、ABPC)
Group4B:(AMPC)
Group5:CET、CXT
Group6:CEZ
β-ラクタム系薬間の交差反応で押えておくべき情報は下記の通りです。
1.ペニシリン系 vs ペニシリン系
2種類のパターン(基本骨格に感作・半合成骨格に感作)が存在する。ペニシリン系と半合成ペニシリン系の交差反応は1.3%未満に過ぎない。
2.ペニシリン系 vs セフェム系
交差反応の発生率は3%であり、側鎖構造の類似性が影響する。セフェム系の世代が古いほど交差反応を起こす頻度は高い。
3.ペニシリン系、セフェム系 vs カルバペネム系
ペニシリン系とカルバペネム系の交差反応は1%未満。セフェム系とカルバペネム系の交差反応の頻度も低く、MEPMで1%、IPMで2%である。
第拾伍話 臓器移植患者

移植患者における感染症治療では、移植後に変動する患者個々の臓器機能に応じた免疫抑制薬や抗菌薬の用量調節が必要となります。
また、免疫抑制に伴う日和見感染症の発現が移植臓器の生着や患者予後に直接影響するため、迅速かつ的確な対応が必要です。
≪代表的な日和見感染症と治療薬≫
1.サイトメガロウイルス(CMV)感染症
第一選択薬:ガンシクロビル(デノシン)、バルガンシクロビル(バリキサ)
代替薬:ホスカルネット(ホスカビル)、レテルモビル(プレバイミス)
2.侵襲性真菌症
アゾール系およびキャンディン系抗真菌薬
3.ニューモシスチス肺炎(PCP)
第一選択薬:ST合剤(バクタ・バクトラミン)
代替薬:アトバコン(サムチレール)、ペンタミジン(ベナンバックス)
免疫抑制薬(CyA・TAC・MMF)はTDMに基づいた個別投与設計が求められますが、感染症治療薬との併用時には特に注意が必要です。
≪タクロリムス(TAC)と感染症治療薬の相互作用≫
[抗菌薬]
+マクロライド系抗菌薬(EMなど)▶CYP3A4阻害(TAC↑)
+ST、AGs ▶双方の腎毒性が相互に増強
+RFP、RBT ▶CYP3A4誘導(TAC↓)
[抗真菌薬]
+アゾール系抗真菌薬(ITCZなど)▶CYP3A4阻害(TAC↑)
+AMPH-B ▶双方の腎毒性が相互に増強
[抗ウイルス薬]
+HIVプロテアーゼ阻害薬、グラゾプレビル、レテルモビル
▶CYP3A4阻害(TAC↑)
第拾陸話 熱傷患者

熱傷患者の薬物動態への影響は、主に下記の2点です。
❶細胞外液の喪失
▶低アルブミン血症▶血漿蛋白結合率の低下
▶水溶性抗菌薬の分布容積増大
▶Cmax低下・AUC減少
**ペニシリン系・セフェム系・アミノグリコシド系・AZT・TEIC・DAP・FLCZ・MCFG・AMPH-Bが影響を受けやすい。
※分布容積が小さい(≦0.3L/kg)か蛋白結合率が高い(≧80%)薬剤
❷腎クリアランスの上昇または低下
1)腎過大クリアランス(ARC)(CL↑)▶T>MIC短縮・AUC減少
2)急性腎障害(CL↓)▶T>MIC延長・AUC増大
**CEZ・CMZ・CAZ・CFPM・アミノグリコシド系・LVFX・AZT・VCM・TEIC・DAP・FLCZが影響を受けやすい。
※未変化体尿中排泄率が高い(≧70%)薬剤
熱傷患者の病態は短期間で大きく変動するため、ターニングポイントを見逃さないように注意する必要があります。
よって、TDMが可能な抗菌薬では通常よりも頻回に血中濃度を確認し、用法・用量を綿密に調節します。
第拾漆話 周術期患者・手術侵襲のある患者

周術期患者では、循環動態の破綻により分布容積が増大したり腎機能が変動し得るため、抗菌薬の投与設計はADMETを踏まえて行う必要があります。
例えば大量出血が予想される手術の場合には、出血の影響を受けにくいクリアランスの大きい薬剤を選択する、という考え方ができる。
また、中枢神経系の周術期には元々中枢移行性の高い抗菌薬を選択しない、術後循環動態が破綻して腎機能低下が想定される場合には腎毒性の高い抗菌薬を選択しない、といった視点も重要です。
第拾捌話 敗血症患者

2016年に敗血症の診断基準が変更となり、臓器障害のない病態を敗血症とは呼ばなくなりました。
臓器不全を有する敗血症の死亡率は高いため、抗菌薬の投与設計の重要性は更に高まったと言えます。
敗血症は重症病態であるため、早期(1時間以内)から十分量の有効な抗菌薬を投与することが推奨されています。
体内動態に応じた投与設計のポイントは下記の通りです。
1.クリアランス(CL)の低下
水溶性抗菌薬のCLは腎機能に依存するため用量調節は必要だが、AKI患者では腎機能が急変動するためSCrを用いた画一的な投与設計は避ける。
2.クリアランス(CL)の上昇
臓器不全を伴わない菌血症・外傷・熱傷などでは逆にCLが上昇し、過大腎クリアランス(ARC)を生じることがある。水溶性抗菌薬の血中濃度の低下に注意が必要となる。
3.分布容積(Vd)の上昇
Vd上昇時の初回投与は(腎機能にかかわらず)負荷投与を行うことが合理的だが、安全性・有効性の両面から更なる検証が待たれる。
近年では、至適血中濃度やPKパラメータ(T>MIC)に到達させる方策として抗菌薬の持続投与の報告が増加しています。
まだエビデンスが十分ではありませんが、有効性が報告されている薬剤では持続投与を検討してもよいかもしれません。
第拾玖話 発熱性好中球減少症患者

発熱性好中球減少症(FN)とは、がん化学療法で粘膜バリアが破壊された状態で、発熱(腋窩温37.5℃・口腔温38.3℃)と好中球減少症(>500/μL)が組み合わさった症候群です。
≪免疫の系統的整理と関連する病原体≫
好中球減少症
[原因]
抗がん剤、放射線、血液疾患、薬剤性、ステロイド、糖尿病
[警戒すべき病原体]
細菌全般(特に緑膿菌・黄色ブドウ球菌)
(長引いた場合)カンジダ属、アスペルギルス属
細胞性免疫低下
[原因]
リンパ性白血病、悪性リンパ腫、HIV、造血細胞移植、長期のステロイド・免疫抑制薬
[警戒すべき病原体]
リステリア菌、ノカルジア菌、サルモネラ、非定型菌、黄色ブドウ球菌、ニューモシスチス属、アスペルギルス属、クリプトコッカス属、結核、非結核性抗酸菌、トキソプラズマ原虫、ウイルス全般
液性免疫低下
[原因]
多発性骨髄腫、ネフローゼ症候群、脾臓摘出、造血幹細胞移植
[警戒すべき病原体]
肺炎球菌、クレブシエラ属、インフルエンザ菌、髄膜炎菌、カプノサイトファーガ属、クリプトコッカス属
バリア破綻
[原因]
(皮膚)手術、熱傷、化学療法、褥瘡、血管内留置カテーテル
(粘膜)化学療法、放射線、デバイス
[警戒すべき病原体]
(口腔)α溶血性レンサ球菌、嫌気性菌
(消化管)腸内細菌科細菌、腸球菌属、カンジダ属
FNで選択される抗菌薬は、CFPM、TAZ/PIPC、MEPMの3剤が代表的ですが、起因菌を想定して必要最小限のスペクトラムのものを選択します。
また、抗MRSA薬(VCM・TEIC)の併用は漫然と行うべきではありません。
≪FNで抗MRSA薬を併用すべき時≫
・血行動態が不安定な重症感染症
・血液培養でグラム陽性菌を認め、その感受性が判明するまで
・重症のカテーテル感染症が疑われる
・皮膚軟部組織感染症
・MRSA、ペニシリン耐性肺炎球菌を保菌している
・キノロン系抗菌薬を予防内服した患者で重症の粘膜炎を伴う
**発熱性好中球減少症診療ガイドライン改訂第2版より
また、FNでは腎過大クリアランス(ARC)の病態が関与しているため、十分なT>MICを確保できるような投与計画を立てることも重要です。
第弐拾話 膠原病患者

膠原病とは、真皮・靭帯・腱・骨・軟骨などを構成する蛋白質であるコラーゲンや血管に障害・炎症を生じる様々な疾患の総称です。
≪膠原病とされる疾患≫
関節リウマチ
▶悪性関節リウマチ、フェルティ症候群、カプラン症候群、若年性特発性関節炎
全身性エリトマトーデス(SLE)
全身性硬化症(強皮症)
多発性筋炎・皮膚筋炎
シェーグレン症候群
混合性結合組織病(MCTD)
抗リン脂質抗体症候群
血管炎症候群
▶結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、高安病(高安動脈炎)、巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)
成人スチル病
**太字は国指定難病
膠原病の治療薬としてステロイドやTNF阻害薬など免疫抑制作用のある薬剤が使用されるため、感染症のリスクは高くなります。
≪関節リウマチで用いられる薬剤≫
・ステロイド
・非ステロイド抗炎症薬(NSAIDs)
・疾患修飾性抗リウマチ薬(DMARDs)
▶免疫調節薬(サラゾスルファピリジンなど)、免疫抑制薬(メトトレキサートなど)
・生物学的製剤
▶TNF阻害薬(インフリキシマブなど)、IL-6阻害薬(トシリズマブ)、T細胞活性化阻害薬(アバタセプト)
・ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬
▶トファシチニブ、バリシチニブ、ペフィシチニブ
特にTNF阻害薬使用時には、結核・非結核性抗酸菌(NTM)症、ニューモシスチス肺炎(PCP)などの感染症管理が必須となります。
膠原病は腎疾患を合併していることが多く、NSAIDsの長期使用による腎症を併発している場合もあり、腎排泄型の抗菌薬の使用には注意を要します。
第弐拾壱話 人工心肺施行患者

心臓手術において、出血と拍動という問題を解決するため人工心肺(体外循環)が用いられることがあります。
人工心肺の使用を開始すると薬物動態が急激に変動するため、個々の抗菌薬の特性に基づいた投与が求められます。
≪人工心肺が薬物動態に及ぼす影響≫
・全身性炎症反応症候群(SIRS)▶分布容積・クリアランスの上昇
・人工心肺回路
▶分布容積(コンパートメントの追加)・クリアランス(吸着)の上昇
・血液希釈▶分布容積の上昇
・低体温・臓器障害▶クリアランスの低下
術中に汎用される抗菌薬はCEZとVCMです。
人工心肺導入による分布容積の上昇・蛋白結合率の低下は、抗菌薬の血中濃度を低下させるため、個々の薬剤で検証が必要です。
蛋白結合率の低下の影響を受けるCEZでは、わが国のガイドラインの投与量では用量不足となります(米国のガイドラインを適用します)。
一方、分布容積の上昇や蛋白結合率の低下の影響を受けにくいVCMの場合はどちらのガイドラインも同じ用量設定(15mg/kg/回)となっています。
≪心臓手術における術後感染予防のためのCEZ投与≫
日本(JAID/JSC)のガイドライン
▶初回1g、3~4時間毎に1gを追加投与
米国(ASHP)のガイドライン
▶初回2g、3~4時間毎に2gを追加投与
第弐拾弐話 四肢切断患者

四肢切断患者にとってクレアチニン高値は強い予後不良因子であり、腎毒性のある抗菌薬投与に際しては腎機能モニタリングは必須となります。
ただ、四肢切断患者では骨格筋組織の喪失により、血清クレアチニンを指標とした腎機能予測は過大評価の恐れがあるため不適切とされています。
そのため、血清クレアチニンではなく、血清シスタチンC(Scys-c)を用いることが推奨されており、日本腎臓学会の提唱する推定腎糸球体濾過量推算式(eGFRcys式)が有用です。
過量投与による腎障害を回避するには、実測体重や体表面積による補正を行うことが望ましいとされていますが、過少投与を回避するためのストラテジーは今後の検証を待たなくてはなりません。
おわりに
今までになかったこのような本が出版されて、当初は「ああ、もうこれからはスペシャル・ポピュレーションで悩まずに済む」と安堵したのだがとんでもなかった。むしろその逆。我々は一層悩まねばならぬと悟ったからだ。スペシャル・ポピュレーションに関する情報量は絶望的に少ない。なので入手可能なエビデンスと患者情報を元に薬学的視点をフル稼働させるしかないことがこの本を読んでよくわかった。やはり薬剤師はこれからも悩まねばならない。答えは本ではなく、薬剤師の頭の中にあるのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?