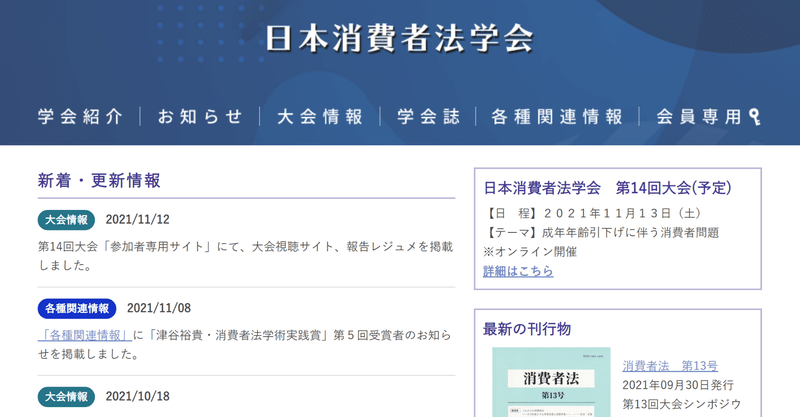
0415:成年年齢引き下げカウントダウン
今日は日本消費者法学会、全面オンライン開催で非会員にも公開されていたのでほくほくと視聴した。コロナ以前は大抵の学会や講演イベントは現地に行くしかなかったが、コロナでZOOM参加が当たり前の文化になり、今後コロナが収束して対面が原則になってもおそらくZOOM公開は残って行くのだろう。田舎住まいの身には有り難いことだ。
今日の報告ラインナップは、こんな感じ。
■日本消費者法学会 第14回大会
テーマ「成年年齢引下げに伴う消費者問題」
① 成年年齢の引下げと若年消費者 河上正二(青山学院大学)
② 若年者の契約被害の実際と消費者法の課題――成年年齢引下げを見据えて 坂東俊矢(京都産業大学)
③ 若年消費者への適正与信と成年年齢引下げ 谷本圭子(立命館大学)
④ 美容医療およびエステサービスの特性と若年者の消費者被害 高嶌英弘(京都産業大学)
⑤ 18歳成年時代の消費者教育――育成すべき資質・能力に焦点を当てて 大本久美子(大阪教育大学)
⑥ 「脆弱な消費者」概念を手がかりとした若年消費者保護に関する考察 岩本 諭(佐賀大学)
⑦ 若年者に関する消費者保護法理の展開と課題――比較法的な視点から カライスコス アントニオス(京都大学)
このうち直接お会いしてお話をしたことのあるのは、坂東先生・大本先生・岩本先生の三名。やはり岩本先生の問題意識と語りは私のツボだとあらためて認識した。
来年4月から成年年齢が引き下げられ、18歳で成人となる。どのくらいの人がそれを知っているだろう。どのくらいの人がその意味するところ(法的な状況)を知っているだろう。
司法書士試験勉強をしている人たちは知っている筈だ。未成年者は制限行為能力者に位置づけられ、保護者の許可を得ないでした契約について強力な取消権が付与されていることを。行為能力の制限とは、制限という語感に反して、対象者の保護が法的な目的だ。認知症の高齢者であったり、未熟な未成年者を、様々なトラブルから救う手立てが講じられている。成年年齢引き下げは、18歳19歳の人たちを保護対象から外すことを意味する。
今日の報告でも出てきたが、現在でも20歳未満と20歳代前半の消費者トラブルを比較すると、成人した途端にマルチとかエステとかの相談件数が激増している。未成年者は法的に保護されているから悪い連中の魔の手が伸びないが、成人した途端に未熟な若者はターゲットになる。これからは18歳、つまり高校三年生でターゲットになってしまうわけだ。
消費者行政や法律関係者の間では、当初からそのことが問題視されてきた。しかし世間の認知度は低い。18~19歳以下の家族がいない人には何の影響もないのだから、関心がなくても仕方がないのかも知れない(本当はここを入口に消費者問題に関心を向けてほしいところだ)。例外は事業者側だ。契約の考え方が変わってくるのにどのような備えをしているのか。また悪質業者は、新たな狩り場の創設を虎視眈々と狙っている筈だ。
あと4ヶ月余りで成年年齢が引き下げられる。いきなり生活が一変するわけではない。見えないところで世の中の仕組みの底流がそっと変わる。その変化が中長期的に社会をどう変えていくのか、変わらないのか。要注目だ。
--------(以下noteの平常日記要素)
■本日の司法書士試験勉強ラーニングログ
【累積153h05m/合格目安3,000時間まであと2,847時間】
実績107分、動画3本視聴。
■本日摂取したオタク成分(オタキングログ)
『エウレカセブンAO』第14~15話、ナルはララァ化してるな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
