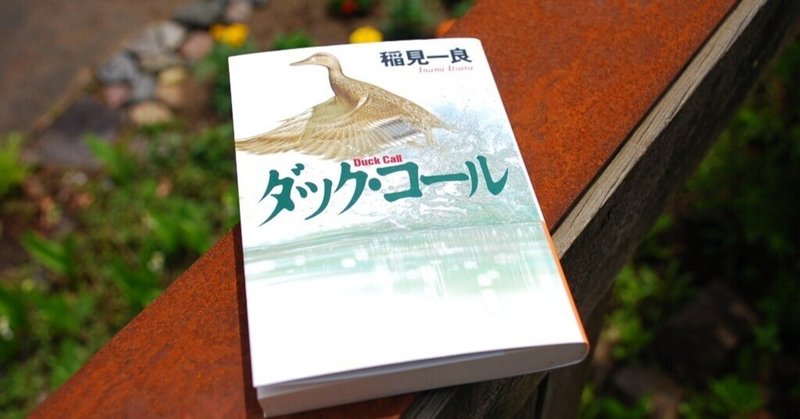
稲見一良のこと
稲見一良という作家の存在は、広く知られているというわけではないだろう。「一良」と書いて「いつら」と読むこともめずらしく、ほとんどの人はそのとおりに読めないに違いない。知っていればこそ読める名前なのだ。
ボクと稲見一良との出会いは、もう30年くらい前になる。出張時、神田・三省堂本店の一階フロアで手に取った一冊の本から、ボクにとっては稀なケースと言える付き合いが始まった。
その本が『ダック・コール』である。タイトル写真にあるのは文庫で、ボクは当時出たばかりの単行本を買い、すぐに近くの喫茶店に入り、そのまま帰りの新幹線の中でも読み耽った。特に買おうと思った理由というのは、その中の第一話『望遠』の出だしに気持ちを奪われたからだ。
“腕時計のアラームが、フィルムの空缶の上で躍るように鳴った。若者は、たった今まで熟睡していたとは思えない素早い動きで、寝袋から腕を伸ばしてアラームを止めた。「四時半」若者は夜光の文字盤を読み、頭をおこしてまずカメラの方を見た。ゆっくりと起きだした。…………………”
ボクの頭の中でもアラームが躍るように鳴っていた。そして予感は予感を呼び、これは絶対に面白いと、ボクは勝手に決め込んでいた。
やはり予感どおりだった。そのストーリーはボクの単細胞にストレートな衝撃を与えた。
まだ一人前とは言えない映像カメラマンの若者が、大プロジェクトの中のワンシーンの撮影を任される。それは、三年前に撮影されたと同じ月日、同じ時刻の日の出を撮り、街の変貌を伝えるという内容の企画だった。そして、若者の仕事と言うのは、絶対動かしてはいけない固定されたカメラのスイッチを単に入れるだけのことだったのだが、若者はその直前にカメラの向きを変えてしまう。若者が向けたカメラの先には、幻の鳥と言われる「シベリヤ・オオハシシギ」がいた……
プロダクションの中などの人間模様と、正義感や理想に燃える純粋な若者との葛藤もそれほど濃くもなく表現されており、この話は圧倒的にボクの胸を打った。
こうして、一応ボクと稲見一良との付き合いは始まったのだが、どんどん読み続けていくと言うほど作品はなく、断片的な付き合いだったと言える。
それから何年かが過ぎた頃のこと、いつもの店で、マスターから一冊の本を見せられた。これ面白いよと言ってカウンターに置かれたのが、なんと『ダック・コール』の文庫本だった。ボクの記憶では、三省堂で買って帰った後日、ボクはたしかにマスターにその本を見せていたと思う。マスターとは、よく互いに読んでいる本のことは話し合っていた。
ボクはすぐにその本のことを話したが、マスターは覚えていなかった。ただ、同じ本をマスターがボクに勧めるなんて、やはり共通の好みがあるなあと嬉しくなったりもした。
そしてその後、マスターもボクも、稲見一良の本を何となく気が付いた頃になると読んでいたということを繰り返していく。
稲見一良の物語には、大人の男の世界に少年の世界が深く沁み込んでいて、読んだ後夢を見ていたような気持ちになったりする。どこにそれを実証するものがあるのだろうと現実を考えたりするが、それは当然創作であり、幻想の世界でもあるのだと納得しながら楽しまなければならない。
📚
たとえば、『セント・メリーのリボン』に収められている『花見川の要塞』という物語には、現代から戦時中へとタイムスリップしていくカメラマンの話が綴られているが、その非現実性は、まさに少年の心があるからこそ受け入れられるものだ。
かつて敷かれていたという線路の上(当然今はない)、軍用列車が深夜、白煙を上げながら夏草や蔓に被われた現在の花見川の土手に現れる……。
どこかで聞いたような話ではあるが、稲見一良のストーリーには、自然風景はもちろん、銃や機関車やカメラなどの詳細な解説・描写が絡み、どんどんと読者をリードしていく何かがある。好奇心を煽るような、ウキウキさせてくれるパワーに酔わされていく。
『花見川のハック』という同じ花見川の名を冠した短編があるが、ハックという冒険好きで、正義感が強く、そして心優しい少年が、花見川でアヤメという少女と出会い、最後はお婆ちゃんが待つ京都へ旅立つという話だ。なんの変哲のない話に見えるが、ハックとアヤメはゴンドラに乗って京都へ行く。そのゴンドラを運ぶのが、なんとナス(野菜の)なのである。面倒なので詳しくは書かないが、そんな結末を聞かされると、かえって読む気も起きなくなるかもしれない。しかし、実際読んでいくと、これがまた実に楽しくなり、嬉しくなっていくから不思議だ。
このような世界こそが、ボクにとっての稲見一良の素晴らしき世界なのだ。自然や趣味や男臭さや少年の心や、空想や理想や夢やこだわりやと、とにかくたくさんのものが凝縮されている。
稲見一良の世界から、ボクは多くの記憶を蘇らせることができた。
10歳くらいのことだろう。裏の雑木林の斜面を登った所に、木の板で組んだ隠れ家みたいなものを作り(作ってもらったのかも)、そこで漫画本を読み、菓子を食べ、そして友達が家から持ってきたタバコを吸ったりした。クワの実やグミなどを採って来ては、そこでみなで食べた。
砂浜に埋まっていた不発弾を掘り起こし、三人がかりで抱えて友達の家の裏に埋め、自衛隊が回収に来たこともあった。自慢したくて学校で口が滑ってしまったことがボクたちだけの大騒動につながった。もちろん、もし爆発の危険性があったら、ボクたちだけの大騒動で済んでいなかったのだ。
カモの子を水辺で生け捕りにし、使われなくなった鳩小屋に入れて飼おうとした。そのカモに餌として与える虫などを、必死になって採りに行っていたことなども鮮明に思い出した。
音楽やら映画やらいろいろとませたことも身につけていたが、こういう遊びは絶対的な事としてなくなることはなかった。
本当は最初に書くべきことなのかも知れないが、稲見一良は自らが癌に侵されていることを知ってから、敢えて作家になったという稀な人だ。
1985年に発癌しデビューしたらしい。そして、その後1994年に亡くなるまでの短い作家活動で、稲見一良の独特な世界を作り上げた。
ボクは今、稲見一良のファンであると公言できるが、これまで本当にそうであったのかというと、正直どこかに単発的な読者みたいな自覚しかなかったように思う。しかし、今年に入ってから、再び無性に稲見一良の作品、いや物語を読みたくなった。
何がそうさせたのかは分からないが、自分自身を純粋に見据えていくためとか、自分の素性や血を知るためとか、どこかそういうものに近い何かが自分を動かしたように思う。
少年、オトコ…。自然、夢、憧れ…。趣味、余計な気苦労…? そんな青臭い何かが、やはりどこかに生きていないと、ニンゲン、特に男はダメなのではあるまいか?
そんなところまで考えてしまっているのである………
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
