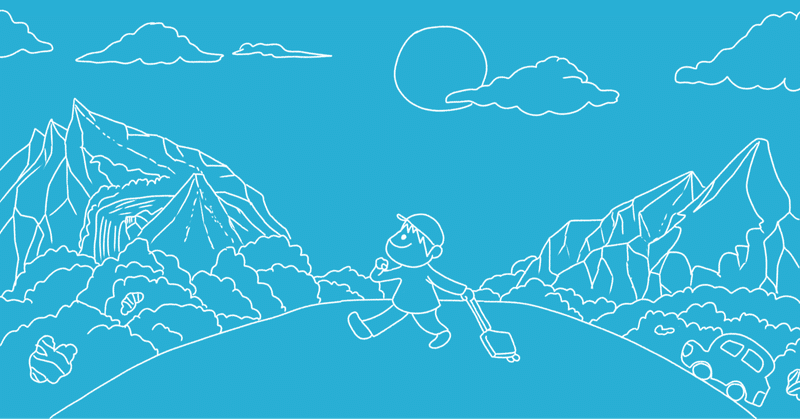
言語聴覚療法実践【総論】
【はじめに】
言語聴覚士として仕事を始めてから、16年が経とうとしている。回復期、高度急性期、独立と道を進ませてもらっていることに感謝している。日々悩み、考えながら仕事をした成果をどこかに書き留めておきたいと思いこの言語聴覚療法実践を書き進めてみる。
ここに記載しているのは、私の経験と学習過程を基に書かれている。誰かの参考になるかもしれないし、ならないかもしれない。解釈は読み手の皆様に委ねる。
【言語聴覚療法の原理原則】
今現在(2023/05/21)私が思う言語聴覚療法実践における[原理原則]は以下の5つであると考えている。
Ⅰ.観察
Ⅱ.評価
Ⅲ.分析
Ⅳ.課題抽出
Ⅴ.訓練
これらは成人・小児分野を問わず行われている。また1年目、5年目、10年目それ以上ベテランから新人、学生まで変わらずに実施される、言語聴覚療法における[原理原則]であると思う。原理原則各項目については、それぞれ章を設け説明を加えていきたいと思う。
【言語聴覚療法の習熟度を高めるには】
言語聴覚療法実践における習熟度を高めるためには、上記の5つを正確に実践することが求められる。これは当たり前と言えば当たり前だ。しかし、できているかと聞かれて胸を張れる人はどの程度いるだろうか。私も未だ自己研鑽の最中である。
この総論で触れるポイントは以下の2つだ。
[ 疑問を持つこと ] [ 常に継続すること ]
何事も「なぜ?」「どうして?」と思うことから新たな発見は始まる。その疑問を解決するために調べては考えを繰り返す。目の前の疑問に懸命に立ち向かうことが視点を増やす一助となる。
そして繰り返しを継続することで、1年、5年、10年と経験が蓄積され、考えの深さが生まれやがては習熟していくことになる。先に述べたが、私も自己研鑽の最中であると述べたのはこの先も継続することでまだまだ、習熟が増すと思っているからである。
【総論のまとめ】
①言語聴覚療法実践における原理原則が存在する
②疑問を持つこと、継続することで習熟度が高まる
ここから先は、原理原則についてシンプルにまとめてみるつもりだ。
もしよろしければ、先も読んでいただきたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
