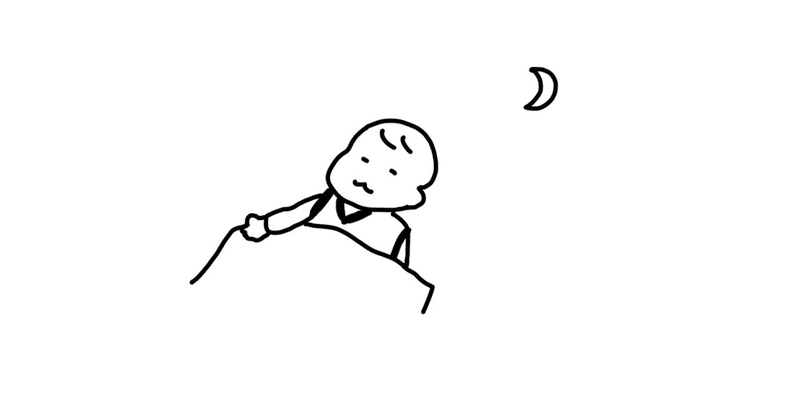
リープ8~10のどこか:睡眠退行で悩むジーナ民へ
前回の記事は実は18ヶ月以上向けを想定して書いてたのですが、思いの外12〜18ヶ月のお子さんを持つ方からの反応が多かったので、補足記事です。
まず、大前提として、どの睡眠本でも言われることですが"お昼寝が2回から1回になる12〜18ヶ月は問題が起こりやすい"です。(私が読んだ12冊のうち少なくとも7冊で言及されてました)
しかもジーナさんでさえ、「我慢するしかない」みたいなこと言ってるので、もう諦めるしか、、、
体内時計が調整されるまでは、ぐずりやすいことがあるかもしれません。2時間のお昼寝を1日1回に定着させる間、2週間ほど機嫌の悪い時期を我慢しなければいけないかもしれません。
カリスマ・ナニーが教える 1・2・3歳児とおかあさんの快適子育て講座
朝日新聞出版
p.53
なので保育者もお子さんもなんも悪くないんです、成長って大変だなって割り切りましょう。
そして対処できることは対処しよう!
ルーチンもそうですが、お子さんが夜中や早朝に起きてしまった場合の対応を前もって考えておき、保育者全員で共有し、徹底して守り抜くことも大切です。
また、この時期は良質な睡眠と発達に必要不可欠な栄養素、鉄分も不足しがちです。次回また鉄分についてはまとめますが、常に意識して摂取させましょう。
以下読み始める前に、ルーチンの基本についておさらいすることをオススメします。
また、こちらに12~18ヶ月にベストなルーチン例を解説してるので、よければどうぞ。
12〜18ヶ月向け:ジーナ先生による注意点レッスン(疲れすぎと寝すぎの狭間で)
ジーナさんの『The Complete Sleep Guide For Contented Babies & Toddlers』は幅広い月齢について書いてあり、本当なんで邦訳出てないんだよ。激おこ、って感じです。
下にまたしてもダラダラと書きますが、要はこの時期は、疲れすぎと寝すぎの両方に要注意やで!って話です。じゃあどうせいっちゅうねんというと、
疲れすぎる前に寝かせる(活動時間に気をつける)
かつ、日中のお昼寝時間総計は、その子にあった長さに調整する
ということ。当たり前かぼけえ、というツッコミは無しでお願いします。
この時期は起床から朝寝までの時間、朝寝明けからお昼寝までの時間、お昼寝明けから就寝までの疲れすぎない時間を探りつつお昼寝合計時間をギリギリまで減らすという至難のワザが必要になります(←できなくて睡眠退行させた人)
予期されること
多くの子は1歳までは14-15時間寝てる(夜と昼寝2回)
12-18ヶ月では13-14時間に減る(夜とお昼寝1回)
問題は大抵お昼寝の回数が1回に減る時に起こる
→2回は必要ないけど1回だと疲れすぎる
→この疲れすぎが夜の睡眠問題に発展する
→この時期は日中の睡眠時間を常に意識するこの問題にうまく対処しないと、0-1歳までどんなによく寝ていた子でもトドラー初期に夜泣きが始まってしまう
ベットで立ち上がったりよじ登ろうとしたりするケースもある
ねらい
12-18ヶ月の日中のお昼寝は1-2時間に減る
12-15ヶ月の夜よく寝る子は朝寝を15-20分にカットする
18ヶ月までには朝寝をカットして12時過ぎから2時間のお昼寝1回にする
トドラーがお昼寝の途中で起きてしまったり、早朝覚醒したり、夜落ち着きがない場合はおそらく日中の睡眠時間をカットする準備ができている
→朝寝を20分以上している場合、15-20分に減らす
→15-20分にした直後から、朝寝をやめてしまってもいい
→すでに15-20分しか朝寝をしていない場合、朝寝をカットしてみるのもよい日中の睡眠時間が減っても大丈夫なタイミングで、もし朝寝カットに失敗したり朝寝させすぎていたりすると、夜中に起きたり、就寝時間にベッドに行くのに抵抗したり、早朝覚醒したりする
日中の活動によって多少は異なるものの、大抵は以下のようなスケジュールが12-14ヶ月の典型的な過ごし方
7-7:30 起床、朝食
9:30 15-30分の朝寝(18ヶ月までにカット)
11:45 ランチ
12:30-13:00 2時間以下のお昼寝
17:00 夕食
17:45 入浴、ベッドタイムルーチン
19:00-19:30 就寝
ベッドタイムルーチン
19:30-20:00の遅めの就寝を確立している場合、朝寝カットすると疲れすぎるてしまうので、少し早めに就寝させる必要がある
2年目は様々なスキルを習得する時期で、精神的にも肉体的にも疲れやすくなる時期なので、疲れすぎは深刻な問題になりうる
夕食後のベッドタイムルーチンは歩くのを習得したての時期は夕方に興奮しやすく、寝る前に追いかけっこやかくれんぼをしたがる
このような遊びは最初楽しくても最後は涙に終わるのが常で、落ち着くのを拒否する
よくある問題①夜中の授乳、ミルク
この時期もまだ寝つくのにミルクなどが必要、またはいったん起きるとミルクなしに再入眠できない場合は、ネントレをする前に、まずはかなり注意深く日中の食事を見直すことが重要
(個人的な意見ですが、7ヶ月ごろ娘の場合はどんなに努力しても日中の食事量が増えず負のスパイラルになっていました、健康で体重増加にも不安がないなら、まずは夜の食事を止めることでリズムが整うタイプのお子さんもいると思います)多くの親がこの時期の子は夜食べる必要がないしすぐに結果がでると周りから言われ、日中の食事の見直しの前にネントレをはじめてみた結果、何晩も何時間も泣かれて結局止めてしまう
0歳児のときからディマンドフード(赤ちゃんが欲しがった時に食べたいだけあげる)で育った子は特に、単にお腹が空いてるから夜中起きることがよくある
単にミルクや授乳と睡眠との間違った関連付け(ミルクを飲んだら寝るという習慣になっている)だけではなく、日中の食習慣が乱れているのが根源的問題
まずは日中の食習慣を整えてから、間違った関連付けを解決すべき
よくある問題②早朝覚醒
2年目は朝寝の調整がうまくいっていないと、早朝覚醒の問題がでてくる
必要睡眠時間が減ってきているのに長い朝寝をさせ続けていると、お昼寝から早く目覚め、夕方にはヘトヘトになって6:30〜7:00の就寝直後から深い睡眠に入る。これを繰り返すとどんどん早起きするようになる
→解決するには、15〜18ヶ月のあいだに朝寝を15分まで減らす必要があ
→15分まで減らせるなら、朝寝をやめることができるはず朝寝開始時間が9:30〜9:45より前になってしまっている場合、似た問題が起こる
7:00まで寝れている子は朝寝の前まで2時間以上は起きていられるはず
9:00にベッドに置かれてしまうと、次は12:00にはお昼寝をはじめてしまい、お昼寝から目覚める時間が早いと夕方までもたない
この時期は12:30〜13:00にお昼寝を開始できるのが理想的
18〜24ヶ月によく起こる問題:それまで長めの朝寝を続けてしまってお昼寝をまったくしない、または45分以下になってしまい就寝までに疲れすぎてしまう
→この場合2〜3日おきに朝寝を10分ずつ減らして、徐々に10〜20分の朝寝時間にする(お昼寝が45分以下だと就寝までもたない)12:30〜13:00の間に開始して、1時間から1時間30分のお昼寝ができるのが理想
ちなみに疲れが溜まってしまって負のループに陥ってるな〜という場合は朝寝開始時間は気にせずこのへんの方法を試してみてください。
よくある問題③ベッドに行くのを拒否する
2年目に起こるベッドタイムバトルの主な原因は疲れすぎである
歩行や会話をはじめ、たくさんの新しいスキルを身につけていくに従って子は自信を持ち、よりはっきりと自分の意思を示すようになる
自身の行動をコントロールし責任を持ちたいという自然な欲求から、自分でベッドタイムルーチンを工夫しようとする
ベッドタイムルーチンでのバトルと動揺を避けることは重要で、ルーチンは一貫させ断固として行い、長引かせたりしないことが必要不可欠(でないと眠るのをいやがったり暴れたりする)
朝寝の構成がうまくいっていないこともベッドタイムルーチンがうまくいかない要因になりうる
→朝寝を45分以上していて、12時からもしくはそれ以降に2時間のお昼寝をしている子は、必要睡眠時間が減った際に、いつもの就寝時間に眠りたくなくて抵抗する
よくある問題④ベッドから脱出する
物理的に足を広げられないので、0歳の時からスリーピングバッグを使っている子は滅多にベッドからの脱出を試みない
ベッドからの脱出が問題にならないよう、3歳児近くになるまではベビーベッドを使った方が良い
ベビーベッドを使っていても、非常に敏捷な子は自分の身を投げるようにして脱出してしまうことがあるので、この場合は柵のないベッドにして、強く言い聞かせるしかない(決して会話せずに短く済ませる。一晩に20回以上言わないといけない場合もあるが、幾晩か一貫した姿勢で意思を強く持って行えば、そのうち子もやっても意味がないとわかり諦める)
よくある問題⑤-1 日中のお昼寝が乏しい
0歳児の時に良いお昼寝の習慣が確立されていれば、お昼寝のどれかは必ずベビーベッドで寝れていて、その場合あまり問題は起きないはず
0歳児の時にバギーや車の中で寝かせるのが常習化していると、大きくなり活発になると長い時間こういった所で寝かせるのは難しくなっていくので、大抵トドラーになると一度に15〜20分程度の睡眠を2,3回することになる
こういった子は日中きちんと長く寝れている子に比べて、イライラしやすく癇癪を起こしやすい傾向がある
0歳の時どんなによく寝ていてくれた子でも、1歳になると日中の睡眠がうまくいかなくなることはよくある
0歳の時はお昼寝がうまくできていたのに1歳になってから突然、眠ることに抵抗し出したら、まず間違いなく日中よくない時間に長く眠りすぎていることが原因
→例えば、朝7時近くまで寝ている1歳過ぎの子の朝寝は、9:30以降にさせ、お昼寝がうまくできるように段々と短くしていくべきトドラーが18ヶ月になる頃には朝寝をカットする
18ヶ月を過ぎたら、たとえほんの少しでも朝に寝かせると午後のお昼寝に響く可能性がある
よくある問題⑤-2 日中のお昼寝回数が変わる時期
2回のお昼寝は必要ないが午後のお昼寝の開始時間まで持たないステージであるとき
→このステージのときは、お昼寝開始を12:15〜12:30の間にできるようにランチタイムを調整する
→しばらく続けて、ランチタイム付近になってもまだそこまで疲れていなさそうなら、再びもとのお昼寝開始時間(12:30〜13:00)に戻すお昼の入眠前の儀式をいつも通りこなして一貫して変えないことはとても重要なので、子供がいやがったからといって、時間を引き延ばしたりしないこと
この年頃のトドラーは眠る時間にしばしば引き延ばし戦術を使って彼ら独自の儀式にしようと企てる
就寝儀式は一貫してあくまでもやり抜くことが大切
一貫して行い続ければ、トドラーもたとえ眠くなくてもいったんベッドルームにはいったら静かにする時間なのだと悟る
1歳以降、夜中と早朝に起きてしまったときの対応
起きてしまったとき、1歳以降は特に"いつも決まりきった同じ対応をとる"ことが子どもの情緒の安定にもつながるとされています。泣いたら定期的に声がけをする、泣いたら添い寝に切り替える、トントンする、などご家庭によって対処は様々かと思いますが、とにかく守備一貫して同じ対応をとりましょう。
今まで一貫していなければ、お子さんに「これからは、夜起きたらこうするよ」と説明し、有言実行し守り抜きましょう。
早朝覚醒してしまった場合、特に気をつけたいのは光を見せないことです。本来寝ていてほしい時間までは、絶対に暗闇で過ごしてもらいましょう。
(人間がいかに光に敏感かはこちらの記事で少し触れてるのでご参照ください。)
私自身は3.5ヶ月でクライイングコントロールのメソッドを使用したので、睡眠退行の時期もこのメソッドに近いことをしていました。(きちんとしたメソッドの紹介はこちらをご覧ください)
今までも、これからも、我が家では15分に一度"ママずっと見守ってるよ、大丈夫。安心してねんねしよう。ぐっすり寝てすっきり起きて、明日また遊ぼうね。"を呪文のように繰り返してます。
実は17ヶ月の睡眠退行のとき、ご縁があってふみママさん(Twitter:https://twitter.com/nentorefumimama、HP:https://nentorefumimama.com/)に助けていただいたのですが、このときかけていただいた言葉が支えになってるので共有しますね。
「夜中にお子さんが泣いてアメを欲しがったらあげますか?あげないですよね。」
師匠!そうですよね、健やかな睡眠のために一時的に子も親も泣きを回避できないこともありますよね…
まとめ
いかがでしたか?長々と書きましたが、
ルーチンと起きた時の対応は首尾一貫する
早朝覚醒の時は本来起きてほしい時間まで暗い部屋で過ごしてもらう
12~18ヶ月の睡眠トラブルは落ち着くまで待つしかない場合もある
というところですかね。
みなさまに快眠が訪れますように。
サポートありがとう!サポートしていただいたお金は湯水の如く娘のお洋服へと消えていくでしょう…
