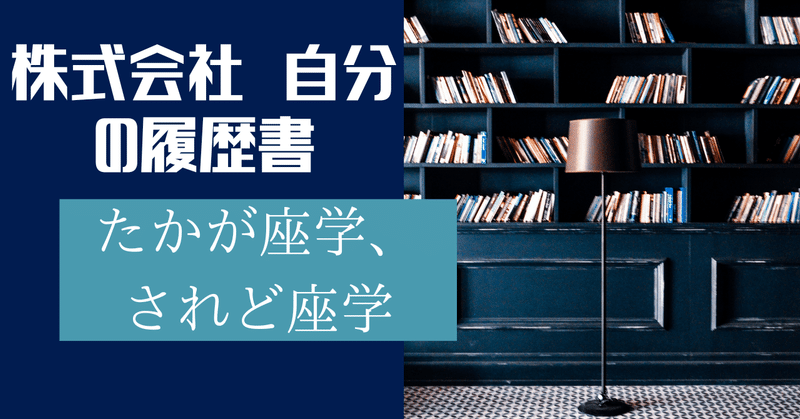
パイロットの訓練 座学①
どうも、こんにちは。
【株式会社自分の履歴書】では、僕の過去について振り返ろうと思います。自分がどんな学生時代を過ごしてきたかを知ってもらうことで、何か参考にしてもらえたらいいなと思います。
僕が大学時代に某大学のパイロット養成コースに通い、アメリカで飛行訓練を受けていたことは今までも書いてきた通りですが、今回はその中でも座学訓練について振り返ってみたいと思います。少しでもパイロットの訓練の雰囲気を味わってもらえたら嬉しいです。
↓↓ タカノハシ・ジロウのプロフィールはこちら ↓↓
https://note.com/easypendragon/n/n6ffc255c6f5c
はじめに
パイロットの訓練は辛いです。これだけ先に書かせてください。
空を飛ぶのは命懸けです。空の世界は魅力に溢れていますが、一歩間違えると命を落としかねない危険を常に孕んでいます。
そんな、美しさと残酷さが表裏一体になっている世界で自分とお客様の命を背負い、何があっても安全に降りるのがパイロットの仕事です。その使命を全うするには本当に辛い訓練を乗り越えなければいけないということだけは、改めて書いておきたいと思います。
訓練は大きく分けて2つ
というわけで本題に入っていこうと思いますが、大学時代に訓練をしていたのはもう何年も前のことなので記憶が曖昧な部分もあるかもしれません。事実と異なることを書いてしまう可能性もありますが、悪意はありませんので悪しからず。。
パイロットの訓練は大きく分けて2つです。
・座学訓練
・飛行訓練
要は、みんなで机を並べて授業を受ける訓練と、実際に飛行機に乗り込んで行う訓練に大別されます。その他、減圧室で急減圧の体験等、特殊な訓練も度々ありますが、それらはまた機会があれば触れたいと思います。
今日のテーマは座学訓練です。パイロット訓練生にとって面白みの無い部分ではありますが、実はこれが意外と長く、飛び始める前の座学訓練は半年間みっちりやりました。訓練生にとって、どんな期間なのか、紹介してみようと思います。
たかが座学されど座学
正直言って、座学訓練の期間は訓練生にとって半ば休憩の期間です。迫り来る審査のプレッシャーもなく、テストも筆記形式なので勉強すれば点が取れます。まずここで落ちることはないのでどの訓練生も油断しているわけです。
しかしながら、ほぼ全ての訓練生が審査の前にここで死ぬ気で勉強しなかったことを悔やみます。精神的にも体力的にも余裕があったこの時期に、なんでもっと知識を入れておかなかったのだろう、、、というのが典型的なパターンです。座学期間に適当に読み飛ばしていた教科書を、フライトが始まってから必死に読み返すのがオチです。
座学はゆるいので、多少舐めてかかっても痛い目を見ずに済むわけですが、知識は全ての礎になるので大変重要です。飛び始めると、全ての操作に「根拠」を求められます。コックピット内での全ての動作に「なんでそれをしたのか」という理由が必要になります。一つ一つの操作、操舵が命懸けのコックピットの中で、「理由もなくこれをやった」というのは許されません。その根拠のもとになるのはそう、座学で学んだ知識というわけです。
力学で学んだことをもとに、どのくらい舵を動かすかを決め、航空法を基に飛行する高度や速度を決めます。不具合が起きればシステムで学んだことをもとにスイッチ類を操作して、不具合を解消させなければいけません。
しかしながら、まだ空を飛んだことのない訓練生がいきなり本気になれないのもう無理ありません。この段階の訓練生は「パイロットの卵」になれたことへの喜びで浮き足立っていて、この先に待ち受けている厳しい現実をはっきりとイメージ出来ていませんから。
実はこの座学の期間は知識を蓄える以外にもやらなければいけない沢山のことがありますが、それはまた明日の記事で紹介しようと思います。
それでは今日はこの辺で。
-----------------------------------------------続く
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
もしこの記事が面白いと感じたら、他の記事も読んでみてください!
よかったらフォロー、記事のシェア等もお願いします。非常に励みになります!
https://note.com/easypendragon/n/n1e171304d0b3
もしも記事が面白いと思っていただけたら、サポートして頂けると嬉しいです。 本を読んだり、いろんな経験をしたりして、自分の学びを加速させることに使いたいと思います。よろしくお願いします!
