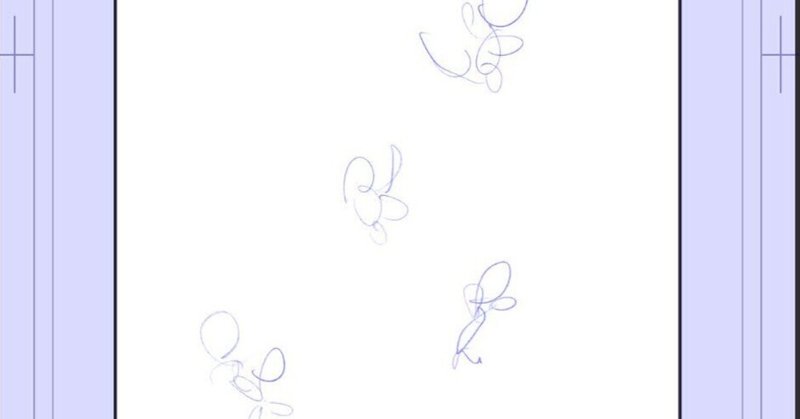
「PICHET KLUNCHUN AND MYSELF」を見てから考えたこと
2022年5月8日早朝。
自室の27インチモニターで、ジェローム・ベルのパフォーマンス作品「PICHET KLUNCHUN AND MYSELF」の映像を見た。早送りせず、一気に。
クレジットによれば、クリエイションが行われたのは2004年。いまから18年も前の作品だが、心打たれるものがあった。
この作品は、政治学や倫理学の論理の力で、舞台の複雑な現象を解析していくことを観客に要請しているタイプのダンスパフォーマンス作品である。
舞台上に、タイの伝統的な芸能、コーンの踊り手とフランスの「振付家」である<私自身>とが向き合い、ときに実際に踊ってみせながら、対話を展開していく。
このやりとりを搾取されてきた文化と搾取してきた文化との対立構造として解釈し、記号的に捉えることも可能だろう。逆説的な言い方だが、もしも、それだけの作品であったなら、私はこの作品を、わりあいによくある、平凡な主題を持つものとして受け止めたと思う。
他にもこの作品には、
・二人とも男性であること
・両者の母語ではない、英語で会話していること
・「ダンス」や「眼差し」が二重に演じられていること
・(映像作品としては)いわゆる「第四の壁」の外側から観客の笑い声が聞こえてくること
このような要素が、慎重に析出され、丁寧に配置されていて、対立構造だけで構成されているとはいえない。これらの要素を含めて観察すると、舞台上に展開する現象は複雑化していくことだろう。
構造を撹乱させることが、この時代のトレンドだったな、と思い出すこともあるかもしれない。
極私的な覚書
生きていると、その存在の基盤(身体、社会、認識システム、アイデンティティ、他者との関係など)が突然絶たれるようなインシデントの発生することがある。いま、多様なインシデントを大きく二つにわけてみる。
カテゴリーA
絶対的に一人称では語り得ないカテゴリーのインシデント。例えば死、その存在が<私>を認識することができなくなってしまうような現象。
カテゴリーB
定常的な基盤が大きく損なわれたが、その存在にとっての生活自体は続いていくようなインシデント。
事故や疾患、他の存在の死、失踪など。(注意を払うべきクライテリアは、時間的な差分が重要なファクター。間隔(その存在の基盤にとってこれまで経験されてきたことがあるインシデントかどうか)、頻度、強度。)
カテゴリーBについて考えてみる。
もしも、これまであきらかだった空間性が、ある瞬間、鏡だけになってしまうように変化した場合、そのことをどのように他の存在と共有することができるだろうか。すっかりあきらめてしまう前に何をすることができるだろうか。(あるいはできないだろうか。)
そのとき、その存在は、政治学や倫理学のような、これまで空間を立ち上げるために援用してきた、定常的な他者を前提とした論理構造について、完全に絶望することになるだろう。しかし、あきらめないで待っていれば、少しずつ少しずつ、政治学や倫理学では語りきれない残余から、深い孤独のはじまる領域が見えてくるような気がしている。
定常性が失われた領域は、厳密には、三人称の言語では語り得ないはずだ。
しかし、深い孤独におかれた存在が、別の存在に向けて、特別な指示語を発明したいと欲望するとき、すさまじい楽観を発生させてしまってきたことも確かなことだ。
楽観で世界は何度も出現し、何度も消えてきた。
パフォーマンス自体を主題とするパフォーマンスはもう、珍しいものではないけれど、いまでも、極限まで政治学や倫理学の論理を展開させた作品には誠実さを感じる。
それは私自身が残余を観察することに望みを託すしかないような状態に置かれているからなのだろう。
「PICHET KLUNCHUN AND MYSELF」は、ナンテールアマンディエ劇場のVimeoアカウントで全編が公開されている。
※この映像は、2011年にブリュッセルで上演されたもの。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
