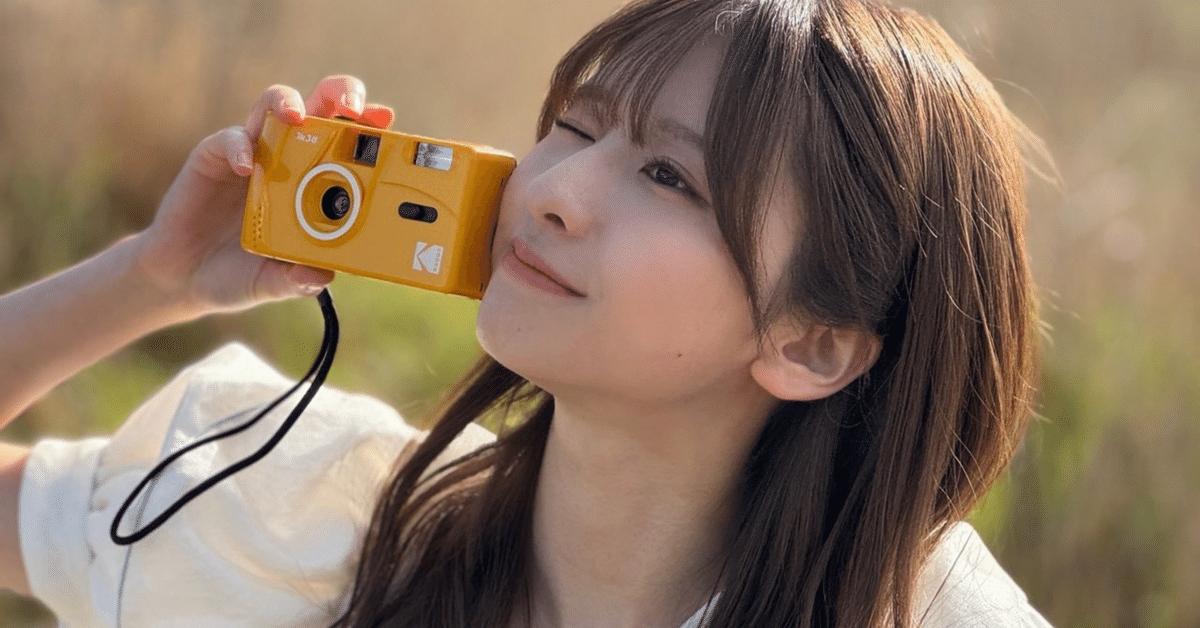
もし、今食べてるアイスの棒が『当たり』だったら...
「あたたた……」
「急いで食べるからそうなるんだよ」
オレンジに染まった空をカラスが飛び、ヒグラシの鳴き声が哀愁を感じさせる夏、夕暮れ時。
コンビニで買ったアイスを、公園のベンチで並んで頬張る学校帰り。
「もうすぐ花火大会か~。最後に○○と一緒に行ったのいつだっけ?」
「咲月が中一の時じゃなかったっけか」
「そんな前だったっけ。てかさ、最近暑すぎない?」
「咲月といると、なおさら暑く感じるな」
「ちょっと、それどういう意味?」
「にぎやかで楽しいなってこと」
「え~、そう?」
照れ臭そうに笑う咲月。
昔から、この手の皮肉は通じない。
「そうだ!もし、この食べてるアイスが当たりだったらさ、当たった方の言うことなんでも一つ聞くやつやろうよ」
「いいよ。なんでもだからな」
昔から、俺たちの間で恒例になっているゲーム。
アイスが当たった方、銀のエンゼルが出た方、ガムが当たった方、チョコバットの打席結果が良かった方。
結果を比べては、勝った方が相手に一つだけお願いができる。
お願い、というのは建前で、拒否権は用意されていない。
もちろん、その難易度に応じてお願いの厳しさの上限は上がる。
チョコバットはほぼ確実に勝負がつくから、お願いも「家まで鞄を持っていく」とかの簡単なもの。
去年、咲月のアイスが当たった時は「一週間私の分もお弁当を作ってきて」とか言われたっけ。
「……限度と節度は守ってね?」
「俺を何だと思ってんだ」
「ウソウソ。物心つく前から傍にいる○○のこと、そんな風に思うわけないじゃん」
俺たちは、幼いころからずっと一緒に居た。
母親同士の仲が良くて、家も隣。
俺の物心つく頃から傍にいた一つ下の幼馴染。
きっと、咲月にとっての俺は、たまたま別のところに住んでいる兄みたいなものなんだろう。
「当たったらどんなお願い聞いてもらっちゃおっかな~」
「咲月も限度と節度守れよ」
「わかってるって~」
一足先にソーダ味のアイスを食べ終えた俺は、棒の表裏を確認して何も書いていないことを確認してから公園に設置されているゴミ箱にゴミを捨てておく。
さて、咲月の方は……
「あたった~!」
「うわ、まじかぁ」
「ほらみて!『あたり』って書いてある!」
大はしゃぎで飛び跳ねる咲月の手に握られていたアイスの棒。
そこには間違いなく、『あたり』と彫られており、見間違いとも不正とも言えない完ぺきなものだった。

「たしかに当たりだ。お願い、何でも言ってみろよ。アイスだから、それなりのお願いきいてやるよ」
「えー!何にしようかな~」
「別に今すぐじゃなくていいぞ」
「わかった!じゃあ、明日までには考えとく」
「わかった。じゃあ、とりあえず今日は帰ろう」
並んで歩く帰り道。
小、中、高とずっと一緒の帰り道。
並んだ影の長さは、いつの間にか大きな差が付いている。
「○○、中々当たらないよね」
「そうだな。多分、大切な、ここぞという場面で当たるように運を溜めてんの」
「いつそれは解放されるのかな~」
「そのうちな」
いつまでも変わらない景色。
停滞は衰退だなんて言う人も居るけれど、変わらないことが支えになるものだってある。
俺にとっては、この一歩踏み出したら崩れて、壊れてしまうかもしれない橋の上に座っているのが心地いいのだ。
「○○~?」
「あ、わるい」
いつの間にか、俺の足は止まって、咲月の後姿に見惚れてしまっていたらしい。
もし、さっき食べていたアイスの棒に『あたり』と書いてあったら。
そうしたら、「俺と付き合って欲しい」なんて言えたのかな。
いや、きっと言えない。
結局、創作物の中でよく描かれる『関係を壊すのが怖い幼馴染』の内の一人なんだ。
・・・
「はぁ~」
意気地なし。
そんな単語が、私の頭の中で激しく主張をしてくる。
「もし、この食べてるアイスが当たりだったらさ、当たった方の言うことなんでも一つ聞くやつやろうよ」なんて勝負を仕掛けたのは私。
お願いの内容は、小学校の頃からずっとストックしてあるどでかいやつが一つある。
『私と付き合ってください』
でも、いざとなるとその一言が言えない。
言うのが、怖い。
私たちはずっと、誇張なんてないくらいにずっと一緒に居た。
雨の日、私が傘を忘れた時は○○が自分の傘にいれてくれたし、私が足首をくじいた時はおぶって家まで運んでくれたこともあった。
○○は私の傍にずっといてくれて、私はそんな○○にいつの間にか惹かれていた。
いつとか、どうしてとかはわからない。
多分、覚えてもない。
それだけ昔から、私は○○のことが好きだった。
だからこそ、この気持ちは言えない。
この関係を壊したくない。
もし、『好き』なんて伝えて。
それがダメだったら。
そうしたら、きっと○○とは普段通り接することはできないと思う。
だから、この気持ちをずっと伝えられない。
「お願い、どうしようかな……」
明後日からは夏休み。
そうしたすぐ、花火大会。
花火大会一緒に……は、ベタすぎる?
でもそれが一番いいかも。
まあ、全部明日考えればいいや。
私は一度考えるのをやめて、潔く眠りにつくことにした。
・・・
玄関口のマリーゴールドの花から朝露が落ち、程よく湿度を含んだ空気が肺を満たす。
梅雨も明けて七月。
日中はさらに湿気も増して、日差しも今より強く照り付けて、過ごしづらい気温になるんだろう。
学校指定の白のポロシャツに着替え、スラックスを履いて、トーストの匂いを感じながら脱衣所の洗面台に向かい合う。
「そろそろ髪切りに行くか……」
上げていなければ目にかかるほどに伸びた前髪を気にしながら髪の毛をセットし終えて、食卓に着く。
「早く食べちゃいなさいね」
「はーい」
用意された朝ご飯はハムエッグとサラダ、ジャムの乗ったトーストにヨーグルト。
食べ盛りの高校二年生にはちょーっと少ないようにも思えるが、そこは昼ご飯でカバーするとする。
朝食も、身支度もすべて終えた俺は、再度身だしなみが乱れていないかを確認して家を出た。
身だしなみは非常に重要だ。
なにせ、俺が家を出て一番最初に会うのは大抵……
「おはよー!」
「おはよう。肩、糸くずついてるぞ」
「えー!取って~」
俺が朝一番に合う相手は大体咲月だ。
だからこそ、一学期最後の登校日だとしても、乱れた服装で家を出られない。
「○○、今日は部活だよね」
「咲月だって委員会だろ。それより、昨日の勝負のお願いは決めたん?」
「あー……それがまだ決まってないんだよね~」
「へぇ。咲月はいつも、すぐパッて決めてるから珍しいな」
「今回はアイスだからさ~。それなりのお願いしたいじゃん?」
「そういうこと。じっくり考えていいよ」
じめっとした暑さが、顔を覗かせる。
同じ、学校指定のポロシャツで胸元を仰ぐ咲月に、ドギマギする俺の心を知ってか知らずか、咲月は「なんで目逸らすのさ」と言ってのぞき込んでくる。
「じゃあ、俺ちょっと弓道場に忘れ物取りに行くから。放課後は……先に終わったら帰ってていいよ」
「りょーかーい」
咲月は校舎に向かっていったかと思ったら、振り返ってこちらに向かって手を振る。
俺はその背中を見送って、弓道場に足を向かわせた。
「やべ、鍵……」
弓道場まであと十メートルも無いくらいの距離にきて、鍵を持ってきていなかったことに気が付く。
一度校舎に行って、鍵を持ってくるのも手間だし、一度鍵が開いていることに賭けて引き戸に手をかけた。
「お?」
どうやら賭けには勝ったらしく、弓道場の扉は力を掛けることなく開いた。
誰かが朝練でもしていたのかもしれない。
更衣室の自分のロッカーに忘れていった教科書を鞄に入れて、弓道場を出ようとした時。
「あれ、○○くん。おはよ」
「井上だったんだ……。おはよう」
「朝練してたんだ。夏の大会、悔しかったから」
六月に行われたインターハイ予選。
俺たちの中から、それを勝ち上がる者はおらず、あっけなく夏は終わった。
「すごいな、井上は」
「○○くんも、やりたかったらいつでも待ってるよ」
「夏休み中とかはやってんの?」
「先生に許可は貰ったし、やれる日はやろうかな~って思ってるよ」
「じゃあ、俺もやろうかな……」
「大歓迎だよ」
俺たちが弓道場で世間話を繰り広げていると、ずっと響いていた野球部の掛け声がぱたりとやむ。
「やば、授業始まる!」
「いそげ!」
井上と慌てて校舎に駆け込み、階段を駆け上がる。
教室に着く頃には二人とも息を切らしており、隣同士の席に座り、顔を見合わせると、自然に笑いがこみあげてきた。
「は~、危なかったね~」
「まじで疲れた……」
「○○くん、体力つけた方がいいんじゃない?」
「そうかも……。劣化が著しい……」
「中学の頃はバスケ結構本気でやってたんだもんね」
「あの頃はちゃんと走り込みとかしてたから……」
高校に入って、弓道部に所属するようになってからは走り込みもサボり気味だったし、体力はガクッと落ちている。
これは、早急に何とかしないといけない。
「じゃあ、わたしと一緒に走る?夏休みの自主練がてらさ」
「ありだなぁ。走り込みと練習を一緒にできて一石二鳥だ」
夏休みのことに思いを馳せていると、担任の先生が持っている名簿をうちわ代わりに仰ぎながら教室に入ってくる。
「あちぃな~、今日も。ほら、早く整列~!」
相変わらず、ゆるーい先生だ。
「やんなっちゃうなぁ、体育館暑いし」とかなんとか言いながら、廊下にならんだ生徒たちを先導していく。
実際、この季節の体育館はほぼサウナと変わらない状態で、空気を循環させるための扇風機こそ何台か回っていても効果はそこまで見込めない。
「校長先生のお話し。校長先生、お願いします」
それに、なによりこの時間が地獄なのだ。
うちの校長先生は、端的に言うと嫌われている。
その理由は明確で、話が長いからだ。
「え~、明日から夏休みとなりますけれども、健全な精神と肉体を育てるためには……」
じっと座っていると、汗が止まらない。
額をにじむ汗が頬や首を伝っていくのが不快だ。
十分くらい経っただろうか。
「なのでね、夏休みだからと言って、あまり学生の本文を疎かにしないようにしてほしいものですねぇ」
ようやく、話も三段落目くらいして、まだまだ話したりないよと言った面持ちの校長先生は生徒たちの早く終わらせろという空気感を察知したのか、壇上から降りて行った。
教室に戻ると、先生がクーラーを消していかないというファインプレーを魅せていたことが発覚し、今度は水風呂にでも浸かっているような気分になる。
サウナーってのはこういう気持ちを味わいにサウナに行くんだな。
俺がそんなことを変に納得していると、校長先生とは一線を画す短さで担任が一学期終了のあいさつを終わらせていた。
「○○くんはお昼食べてから部活行く?」
「そのつもり」
「じゃあ、私もここで食べて行っちゃおうかな。購買行くんでしょ?」
「よくわかったね」
「だっていつも購買のサンドイッチ食べてるし」
「よく見てる」
「だって……席、隣だし」
「それもそうか」
財布をスラックスのポケットに突っ込んで、井上と並んで教室を出る。
井上とは一年生の頃から同じクラスで、数少ない弓道部の同期。
前まではこんな美人の隣に並んで歩くなんて恐れ多い……なんて思っていたが、今ではなれたものだ。
「あら、いらっしゃい。いつものでいい?」
「はい、お願いします。あと、クリームパンもいいですか」
「もちろんよ~。じゃあ、四百円ね」
サンドイッチ二つと、クリームパン一つで四百円。
ボリュームもそこそこあるし、購買様様だ。
「どうしようかな……。カレーパンも美味しそうだし……サンドイッチも……」
「井上って、意外と優柔不断なんだな」
「前まではこうじゃなかったんだよ。でも、最近はね~。特にご飯は悩んじゃうかも。○○くんのオススメはやっぱりサンドイッチ?」
「もちろん。ここのサンドイッチは絶品だからな」
「あら、嬉しいわね~。褒めたって何にも出ないわよ~」
「じゃあ、私もサンドイッチ一つ」
「毎度~!」
購買で食料の調達を終えた俺たちは、すっかりもぬけの殻となった教室に戻ってきた。
「誰もいないね……」
「運動部はもう練習始まってるだろうし、部活がないやつらは遊びに行くだろうしな」
「なんだか、非日常みたい」
クーラーが止められて、開け放たれた窓から入ってくる風が、白いカーテンと黒い井上の髪をなびかせる。

確かに、ここだけを切り取ってしまえば青春映画の一幕と言われても不思議ではない。
「夏休みってさ、暇?」
「多分……?まだわからんのが多いかも」
「じゃあ……。いや、いいや。また今度言う」
「なんだそれ。気になるじゃん」
それ以降、この一瞬の話題については触れてもはぐらかされるだけだった。
いつの間にかグラウンドからは野球部のランニングの掛け声が聞こえてきていた。
・・・
「お腹空いた……」
久しぶりに利用する購買に向けて歩きながら、そんな言葉が自分の口から零れる。
委員会があることをすっかり忘れて、「明日はお弁当いらないから!」とお母さんに報告してしまった昨日の自分をひっぱたいてやりたい。
ぐぅと定期的になるお腹を押さえて購買に到着すると、数人の生徒の姿が確認できた。
みんな、これから部活とかなのかな。
○○も来てないかな。
そんな私の願いを聞き届けたかのように、私の視界の端に見慣れすぎた後ろ姿が映る。
「あ……!〇……」
声を掛けようとして急ブレーキがかかる。
○○の隣、柱の陰になっていて見えていなかったけれど、井上先輩がいた。
私は咄嗟に曲がり角に隠れてしまう。
どうして、隠れてるの。
別にあの二人が仲がいいのなんてそれなりに知れ渡っていて、その理由がクラスも部活も同じだからで……
私が、こんな……こんなにもモヤモヤする理由なんてないはずなのに。
なのに、胸が苦しい。
私はどうすればいいの……
「お願い……」
○○への、お願い……
・・・
放たれた矢が一直線に的に向かい、その中心を射抜く。
「よし、片付け始めろ~」
顧問の一声で、的も矢も片付けられて、まだ暑さが残る夕方には部員の談笑する声が残る。
「これで夏休みに入るから、全体での練習ってのは無くなるけど、自主練はいつでも大歓迎だ。じゃあ、解散」
しばらくは自主練か。
全体でやる練習は、見られているという感覚が強く、下手な射は見せられない緊張感があって好きだったのに。
俺が道着を着替えて外に出ると、同じく制服に着替え終わったであろう井上が弓道場の前で待っていた。
「あ、○○くん。もしよかったら……」
井上が何かを言い切る前に、ポケットに入れていた携帯がメッセージの到着を知らせるために震える。
「ちょっとごめん」
携帯を確認すると一件、咲月からのメッセージ。
『校門前で待ってるからね~』
委員会、意外と遅くまでやってたんだな。
俺は『りょーかい』とだけ返して携帯をポケットにしまう。
「わるい、咲月が待ってるらしいから、先帰るわ。じゃあ、また連絡してな~」
「あ、うん……。また、自主練で……」
井上に一言お詫びを入れてから、俺は小走りで校門に向かった。
向かった先には、小さくあくびをする咲月が背中を門に預けて待っていた。
「おまたせ」
「遅いよ~」
「部活だったんだからしょうがないだろ」
「え~?もうちょっと早く終わったの知って……いや、なんでもない!忘れて!」
何か不味いことを言ったのか、咲月は手をぶんぶんと振りながら今の発言は記憶から消すように促す。
「まあいいけど。それより、お願いは何にするか決まったん?」
「あ、それが……」
「咲月も優柔不断かよ」
「咲月”も”?」
「あぁ、昼に井上と購買に行ってさ」
「…………っ!」
「そん時、井上がパン選ぶのにめっちゃ時間かけてたんだよ」
「そ、そうなんだ……。その、井上先輩とは、どんなこと話したの……?」
お昼に井上とした会話の内容を思い返す。
いっつもアニメの話とかで意外と他愛もない会話してるんだよなぁ。
「あ、夏休みの予定聞かれたわ」
「な、なんて答えたの!」
えらく前のめりな咲月。
俺は少々気圧される。
「いや、なんも決まってないし、特にないかな~とは答えたけど……」
「もしかして、花火大会とかはもう誘われたりした……?」
「そう言うのは特にないかな。第一、井上との予定が立ったのは夏休み中の自主練だけだし」
「そっか……。そっか……!」
「なんだよその嬉しそうな顔は。……さては予定も何もない俺をバカにしてるな!」
「べ、別に喜んでなんかないですけど……!?」
「こんなとこでくっちゃべってないで、早く帰ろう。腹減った」
しかし、帰り道を歩き始めた途端、咲月はどこか思い詰めた顔をしている。
お願いの内容、そんなに考えるもんなのか。
結局、咲月が迷い中で、今日には決めると言っていたお願いは家の前まで来ても伝えられることはなかった。
「明日から夏休み……って言っても、どうせ家隣だし顔合わせるだろ。例年通り」
「…………」
「咲月?」
お互いの家の前。
しんと咲月が黙りこむ。
「あのさ……お願い、決めたよ」
「おぉ、何にしたんだ?」
「花火大会、一緒に行きたい」
「久々だなぁ、咲月と行くの。家に甚平あるし、それ着てこうかな」
「じゃあ、私も浴衣借りてくる……!」
「楽しみにしてる。じゃあな」
「うん!」
ようやく晴れやかな顔になった咲月と別れて、荷物を自分の部屋に置いて携帯のカレンダーアプリを開く。
一週間後の土曜日。
【花火大会 咲月と ※甚平着用】
しっかりと予定を入れておく。
・・・
「最初の一週間は皆勤賞だな」
「二人しかいないけどね~」
夏休みに入って、毎日のように午前中からお昼過ぎまで井上と自主練をするのも日課になりつつある。
結局、最初の一週間が終了して、自主練の参加者は俺と井上の二人だけ。
そこまで本気で力を入れているタイプの部活でもないのでしょうがないが、二人きりの静かな弓道場で、蝉の鳴き声と野球部の掛け声を聞きながらっていうのも結構いいもんだ。
「今日はこれくらいにしよっか」
「そうだな。にしてもあっちいな」
「一日晴れらしいからね。花火もよく見えそう」
「確かにな」
「その……さ、この間言えなかったこと、言ってもいい?」
井上が腕を後ろに組んで、視線を斜め下に逸らす。
「ハ、花火大会と、か……!一緒にどうかな……って」
「あー……花火大会はちょっと先約がありまして……」
「そ、そうだよね……!友達と行くよね……!わ、忘れてくれていいから!じゃあね!」
そう言って、井上は足早に駆けていった。
蝉の声と、野球部の声が遠く響いて、俺の首筋には汗が伝った。
・・・
集合場所は神社の狛犬前。
隣同のはずなのに、昔にやっていた習慣が抜けていない。
階段の下に並ぶ屋台に照る提灯の光と、遠くからかすかに聞こえてくる笛と太鼓の音色。
小学校の頃は仲の良かった男女混合のグループで、中学の時は仲のいい男友達数人と、去年は確か自分の部屋で。
未だ二人きりでの花火大会というのは経験がないため、少々落ち着きが無くなっている俺はずっときょろきょろと周囲を見渡してしまっている。
「おまたせ」
そんな俺の目と耳に飛び込んできた情報は、処理するのに多少の時間を要して落とし込まれる。
白をベースに白い花の模様をあしらって、ほんのり緑の葉の色が丁度いいアクセントとなった浴衣に身をまとった咲月。
「どうかな?」
「似合ってる……」
急に大人びて見えた咲月に、俺は思わず口ごもってしまう。
「ありがと」
陽が落ちて、暑さは幾分かマシになったというのに、額には汗が滲む。
多分、恐らく、いや確実に緊張のせいからだ。
「花火始まるまで時間あるよね」
「屋台まわるか」
「うん」
中一年だから当然と言えば当然だが、屋台の顔触れは変わっておらず、定番の焼きそばやらたこ焼きやら、お好み焼きやらには懐かしさすら感じてしまう。
「あれやりたい!」
咲月が指をさしたのはスーパーボールすくいの屋台。
小学生たちがゴムプールを囲んでやいのやいのと盛り上がっている。
「あんなの、いつ振りに見たかな」
「○○もやろうよ」
「えぇ、恥ずかしいから俺はいいよ」
「いいからいいから」
一人百円。
良心的な価格を払ってポイを一つ店主のおっちゃんから受け取る。
「まずは○○のを見させてもらおうかな」
俺はポイを構え、集中してスーパーボールを狙い、水中でそっとポイを動かした。
しかし、紙が思ったよりも遥かに脆く、すぐに大きな穴があいてしまう。
「難しいな……」
「よーし、私の番ね!たくさん取っちゃうぞ~」
不甲斐ない結果に終わった俺に代わって、次は咲月がポイを構える。
「こういうのは慎重かつ大胆に……」
水に漬けられたポイの隅。
手首を返すようにして跳ね上げられたアヒルの人形が二匹若干宙を舞って持っていたお皿に飛び込む。
「やった!取れた!」
よろこぶ咲月は、そのせいで力が入ったのか、第二投で狙ったスーパーボールによって穴をあけられて残念ながら挑戦終了。
「あ~、残念。でも楽しかった~」
「俺は悔しいよ」
「あはは!○○、瞬殺だったもんね~。そんな○○に、このアヒル一匹あげるよ」
「いいのか?」
「もちろん。今日の思い出!」
「じゃあ、ありがたくもらうよ」
間抜けな顔のアヒルの人形。
俺は大事に巾着にしまった。
「次は……ってもうこんな時間!?」
咲月が思い立ったようにスマホを確認すると、花火が上がる時間がすぐそこまで迫っていた。
「急がなきゃ!……いてっ!」
走り出した咲月はすぐに立ち止まり、足を押さえて座り込む。
「どうした?」
咲月の足を確認してみると、鼻緒ずれを起こしたのか、足の指の間から血が出ていた。
「歩けそう?」
「どうだろ……いたっ」
「一旦応急処置だな。人混みの中でたちっぱになるし。ただ、座れるとこも無いしな……」
この辺で座れそうなところは見渡す限りどこも空いておらず、治療ができそうな場所は見当たらない。
このあたりの場所で座れそうなところ言えば……
「公園行くか。あそこならコンビニも近いし、絆創膏も買ってこれる。歩けは……」
「ちょっと、厳しいかも……」
「じゃあ」
俺は咲月に背を向けて、かがむ。
「おぶってくから、乗って」
「うぅ……ごめんねぇ、ほんとに……」
遠慮がちに咲月が背に乗ると、羽の様に軽い感覚に驚かされた。
「っし、いくぞ~!」
俺は、力強く人の間を駆け抜けた。
もちろん注目はすごい浴びたし、恥ずかしくもあった。
「はっや!」
「最近ランニングしてたんだよ。その成果かな!」
だけど、さっきまで自分のケガのせいで暗い顔をしていた咲月の声色が明るくなったならそれでよかった。
・・・
「はぁ……。結局、逃げちゃったなぁ」
電気を消して、雰囲気だけでも近づけた自分の部屋。
ベッドに横になって、ぼーっと窓の外を眺める。
「誘うのが遅すぎたかな……」
当日のお昼じゃ、予定なんて埋まってるに決まってる。
ここぞという時に勇気を出せなかった自分が恨めしい。
「なんか食べたいな……」
自分の部屋を出て、キッチンの冷凍庫を開けると、アイスが一つ残っていた。
「これって、あたりとかあるやつだよね……」
あたりなんて滅多に出るものでもない。
だからこそ、あたりが出た時はそれにあやからせてもらおう。
もし、このアイスであたりが出たら、その時は彼をデートに誘うんだ。
お願い。
お願い。
部屋に戻り、願いながらアイスを食べ進める。
あたって。
窓の外から花火の音が聞こえ始める。
花火が上がり始めてしばらくするころにはアイスは食べ終わって。

都合よく、あたりなんて出るはずもなく。
「はぁ……頭いた……」
残されたのは、何も書かれていないアイスの棒と、アイスクリーム頭痛に悩まされる私だけだった。
・・・
一キロもない距離を駆け抜けて、ぼんやりと明かりが照らす公園のベンチに咲月を下ろす。
「コンビニ行ってくるから、ちょっと待っててな。なんかいる?」
「アイス食べたい」
「おっけ」
近くのコンビニまで駆け足で向かって、絆創膏と梨味のアイスを二つかごに入れる。
レジに持っていく途中、とあるものが視界に入り、それもついでに会計を済ませた。
コンビニを出たころには、花火の第一陣の音が聞こえていた。
「お待たせ。足、見せて」
これから咲月の素足に触れるのかと思うと、とんでもない緊張で指が震えてしまいそうだが、それを深呼吸で制して手早く処置を済ませる。
「これでいいかな」
「ありがとぉ。○○がいてくれて助かったよ~」
「い、いいよ、これくらい。アイス食べよう」
咲月の隣に腰かけて、アイスを一本手渡す。
見上げると、意外にも花火が良く見え、結果的に穴場スポットを見つけた形になった。
「……なあ、いつものやるか?」
「もちろん。当たったらお願い一つね!」
同時に封を開けて、空を見上げながらアイスを頬張る。
「頭痛い……」
「そろそろ懲りろよ……」
アイスクリーム頭痛に苦しみながらも気合で食べきったらしい咲月は、わかりやすく落ち込んだ顔を見せる。
「まあ、そうそう当たるもんでもないよね」
「今回も当てられたら、神様の忖度を疑うな」
花火を眺めながら、ゆっくりと食べるアイス。
なんだか、夏の欲張りセットみたいで贅沢をした気分だ。
そして、例年通りならそろそろ……
「うわぁ!きれ~!」
予想的中。
大量の花火が一斉に打ちあがり、まるで昼間の様に明るく照らされる。
「この時間が、永遠に続けばいいのに……」
花火の音の合間。
微かに聞こえた咲月のつぶやき。
そして、明るく照らされて幾分か見えやすくなったアイスの棒。
あたりの三文字。
「咲月」
「なに?」
「アイス、当たったわ」
「神様の忖度だ!」
「おい、俺がどれだけ外して来たと思ってる」
「運貯めてたんだもんね~。約束通り、お願い聞くよ。もう決まってるの?」
このお願いには強制力なんてものはない。
それでも、ずっと言いたくて、今じゃないかなって逃げ続けてきた。
ずっとずっと、目を逸らしてきた。
「もう、決まってるよ」
「お、じゃあ聞いちゃおっかな」
「俺と、付き合って欲しい」
空にはひと際大きな花火が咲いて、さっきよりも眩しく世界を照らす。
咲月は呆けた顔のまま、目に涙を溜めて、それが花火の光をキラキラと反射していた。
「あ、いや……ごめん……!泣かせるつもりじゃなくて……!」
「わかってる……。わかってるよ……。これはうれし涙で……」
咲月の頬に、赤い光を含んだ涙が伝う。
「私もずっと、好きだったから……。もう!○○が急に告白なんてするから、涙止まらないじゃん!」
「おい、痛いって……!叩くなって!」
右手で目元を押さえて、左手で俺のことを叩く咲月。
俺はそれを甘んじて受け入れる。
いつの間にやら花火は終わっていて、空には普段通り星が輝いていた。
「泣いてたら終わっちゃったな~」
「物足りない?」
「ものたりない」
「そんなこともあろうかと……」
俺はベンチの裏に隠しておいた手持ち花火を取り出した。
「え~!買ってきてたの!」
「公園からちゃんと見えるかわからなかったから、一応ね」
「やろやろ!」
ぼんやりと明かりが照らす公園。
ゆらりと揺れるろうそくの炎。
二人ぼっち、つつましい花火大会。
「なんか、こういうのもいいね」
「ああ。落ち着くな」
先ほどの涙が嘘かの様に晴れやかな笑顔の咲月。
手持ち花火はすぐになくなり、クライマックスは線香花火。
ぱちぱちと弾ける火の玉を眺めていると、咲月が不意に口を開く。
「この時間が永遠に続いたらいいね」
「永遠にするんだよ」
次第に勢いが弱まり、ぽとりと落ちた火の玉を見つめ、願いが叶いますようにと、ろうそくの火を吹き消した。
………fin
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
