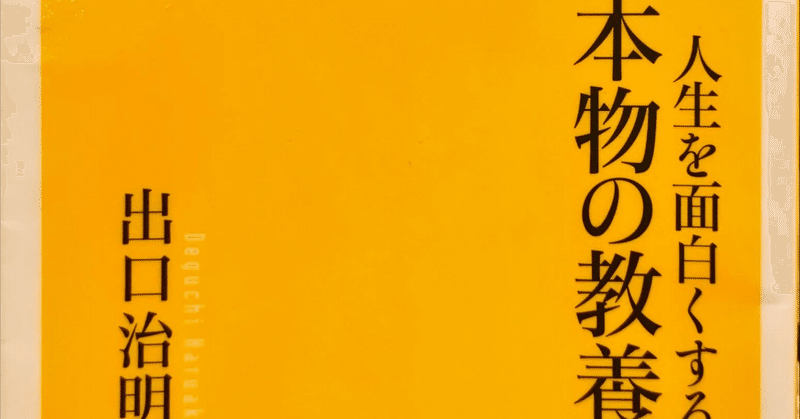
人生を面白くする本物の教養
著者、価値観の押し付けほど嫌いなものは他にない
教養とは人からの評価を高めるものではなく、自分の人生を彩り豊かなものにするもの
知識を増やすことが目的ではない。知識はその人の興味の範囲を広げてくれる。
興味の対象が多ければ多いほど自分の好きなものが見つかる確度が高まる。
面白いことは一つだと思うと、食わず嫌いに陥る可能性がある。
勉強の目的は、専門であろうがなかろうが、自分の頭で考え、意見が言えるようになるためにする。
自分の頭で考える際には腑に落ちる、つまり腹落ちするかどうかが一つのバロメーターとなる。
人の話を聞いてすぐにわかったとせず、逆に否定もせず、そういう考えもあるのかと保留にする。
意見が決められないのは考え不足が原因。
本を一冊読むなど僅かな努力を惜しんで、お手軽な答えに乗っかろうとする風潮が強すぎる。
己を知ることが何よりも大切。(他者から見てどう映っているか、自分たちはどの位置にいるか)
また、出羽の守(かみ)はもうたくさんという意見も。(アメリカでは、ヨーロッパでは)そとに正解を求めるのはやめよう。
謙虚でなければ教養は身につかない。
ソクラテスの無知の知はそれを言っている。
グローバルビジネスの人間関係はウィンウィンの関係だけが重要なのではなく、大きくモノを言うのは、この人と仕事をしたら面白そうだという属人的な部分。
ビジネスではないが漫画家ヤマザキマリさんが年下イタリア人と結婚した理由も、この人は面白そうだ、という理由。
面白さのみなもとはボキャブラリー。それは単に単語の数ではなく、話題が豊富であるという事で、引き出しの数。
グローバルスタンダードの面白いは、アホな態度や逆ギャグではなく、様々なことを知っている、話題に引き込む力があるなど、興味深いに近い。ウィットや蘊蓄などのジョーク、会話を弾ませる切り返しが好まれ、アホな態度などは相手が笑っても、笑われているに近いかも。
広く浅くではなく、広くある程度深い素養が必要。
人間は双方の関心領域がある程度重なっていないとなかなか共感を抱けない。
西洋にはギリシアローマ時代以来、リベラルアーツという概念がある。
一人前の人間が備えておくべき教養で算術、幾何、音楽、文法学、修辞学、論理学、天文学の7つの分野。(自由七科)
決定的に重要なのは自分の意見を持っていること。広く深い知識を持っていても、それだけではまだ十分でない。
日本には評論家のようにあれこれ語る事はできても、あなたはどう考えますか?となるとそれまでの舌鋒は鈍りがちになる。
日本はいろんを異論を論じにくい風潮があるが異論が存在できないしゃかいはきわめて不健全。
せかいではユニークなものの見方、パーソナリティが際立った考え方は、それだけで一目も二目も置かれる。
こんなことを言ったら恥ずかしい、周囲から浮くなどとは金輪際考えない。
むしろ、一端の大人が自分の意見の一つも持たない方が恥であると考える。
自分の意見が無いことは自分の人生の基盤がないことであり、自分の意見をもとに自分の生き方を追求し、自分の人生を謳歌する。
アメリカの人気就職先はバランスよくベンチャー、NPO NGO、公務員。
ボンストンコンサルティングなどの有名会社は40位とか50位とか。そういう会社は今がピークだと考え、明日のアップルなどを夢見てベンチャーに行く方が夢があると考えている。意欲的かつ健全。
逆に日本は寄らば大樹の陰、保守的、依存的。
欧米の学生が意欲的なのは、大学の学費が高く、借金で通っている。親が金を出さない。元を取らなければというインセンティブが強く働く。
就職の際は、大学、学部を選んだ理由、成績を説明されるので必死に勉強。
日本のように体育会系なので根性はあります、では通用しない。また、日本ではクラブは?、アルバイト?、など聞くことがそんなことなので学生も勉強しない。
また海外勤務を希望せず本社にいたがる傾向があるのも、ロールモデルであるある大人がそのような姿勢であるから。
英国の教育は考える力を身につけさせる力がすごい。
日本のように覚えることや正しい答えばかりを求めるものとは根本が違う。
英国保育園では児童を正面に相対させ外見を見させる、相手を替えて、繰り返す。
外見の違いを認識させ、中身も違うことを教え、自分が考えていることは相手はわからないから、はっきり伝えるように教育する。
第二次大戦で日本がアメリカに負けたのは生産力、工業力(航空母艦が特に)の差が大きがったから。
戦後はアメリカ(GEやGMといった電気や自動車)を目指して復興。((1)キャッチアップモデル)
官僚がアメリカに倣い設計図を書き、それが(2)高度成長という結果がついてくるので、誰も何も考えず、文句を言わなくなった。
成長は他の要因では(3)人口増と朝鮮特需などの幸福が重なったことも。
※戦後の日本は冷戦構造という大枠中で(1)〜(3)で説明ができる。
採用も高度成長=人手不足なので(1)青田買いとなる。また、高度成長し、給与も増え続けるから(2)終身雇用となる。辞める人がいなければ(3)年功序列となる。年功序列となると役付き者は高齢者で占められるので(4)定年制となる。
※(1)〜(4)がワンセットの特異な労働慣行
また、社会保障(社内預金、社宅持ち家補助制度、旅行積立、保養所)や社員食堂、忘年会、冠婚葬祭に至るまで企業が面倒を見ていた。(中国の人民公社以上に人民公社していた)
こうした閉じた世界でロイヤリティ(忠誠心)が最も評価され、その指標として労働時間で測られ、長時間労働という悪しき慣行が蔓延る。
国連をはじめとした国際機関に日本人が少ないのは、マスター(修士)をそもそも持っていないから。
※グローバル企業の役員ではマスターかドクター(博士)が必須。
人は何歳からでも学ぶことができる。何歳であっても決して遅すぎることはない。
タテ(時間軸)とヨコ(空間軸)で物事を考える。
例)歴史で言うとタテを千年単位で伸ばし、ヨコを隣国中国に向ける。
※タテの発想で先人が繰り返した試行錯誤から学び、ヨコの発想で世界から考え方や実践法を学ぶ。なお、自然の淘汰にさらされてなお残っているものは合理的な最適解である可能性が高い。
第二に、国語でなく、算数で考えるという視点が重要。(定性的だけでなく、定量的に)理屈だけでなく、常に数字を参照して考える。
算数で、は数字・ファクト・ロジックで考えることができる。
例)平家滅亡は平清盛が贅沢三昧で天才源義経が現れて滅亡。ではなく、数字ファクトロジックで考えると、西日本の天候不順(数字)、それにより飢饉(ファクト)、平家戦力ダウンで滅んだ(ロジック)。
物事の本質はシンプルなロジックでとらえるべき。最初に物事の本質を的確に掴む。
難しいことを知っていても賢そうに見えるが、何がなんだか訳がわからない人は、本質を捉えていない(幹がなく、枝葉だけ)場合がほとんど。
偽物を見抜く力も教養の一つ。
本質の部分で話し合えばどんなテーマでも1時間で終わる。
木を見て森を見ず。一般に森の議論はシンプル。
人間はそもそも賢い動物ではなく、単純。その人間が作った社会も本質は単純であるはず。
物事の本質をシンプルに捉えるにあたっては何かに例えて考えることが有効。
例)教養を身につける。これを水泳に。泳ぎは習えばたいてい泳げるようになる。しかしオリンピック選手並みはほとんどなれない。しかし、プールや水辺で泳ぐのに、オリンピック選手並みになる必要があるか?英語も通訳並みに話せる必要はなく、プアイングリッシュで世界の人々は堂々と意思疎通している。
常識を疑うことは常に重要。商売も政治も疑うことを知らない相手であれば、好き勝手ができる。常識を疑うことで、社会は健全に発展し自浄作用が機能する。それは近代国家における批判精神であり、リテラシーと呼ばれるもの。
リテラシーはたんに他人を責めることではない。政治家の人格否定や批判のための批判になることも散見。
政府を批判するときは、代案を伴うべき。市民がまずなすべきことは投票率を上げること。政府は私たち市民がつくるもの、という健全な当事者意識が必要。
結局モノをいうのは、機密情報のようなものではなく、考える力。
考える力があれば、普通に入手できる情報でも、それらを分析するだけでこれまで見えていなかった世界が見えてくる。
現代における新聞の意味は文脈であり、編集力。
出口氏は先輩から社会人の定義は朝、複数の新聞を読んで会社に来る人間だと言われた。
複数紙読むと世の中の流行や起こっていることはだいたいわかる。
まず見出しを全て読み、面白そうな記事は本文を読む。100あれば、だいたい20くらいか。
大量の情報に接して習うより慣れろ。
好きな分野であれば、四の五の言わず情報収集に努めること、ひたすら量を積み重ねること、それも知の蓄積のコツ。
自分の行動をルール化して判断を省力化。
寝る前の1時間は本を読む、朝6時から7時の間は三紙(読売、朝日、日経)新聞を読む、など。
一度決めたルールを数年黙って続けていれば、生活習慣そのものになるので守るのがとても楽になる。
身近な人を目標にすると努力が続く。
例えば、一年後にこの人より詳しくなってやろう!など。
仕事や勉強ができる人はやる気を引き出すのがうまい。他者を巻き込んだ仕掛けが必要。(Twitterで全世界に呟く、彼女に宣言するなど)
大学生の勉強不足は、企業が面接の際、アルバイトの経験やクラブ活動などくだらない質問をするからである。グローバル基準に合わせて、大学でなぜその分野を学び、どのような成績を収め、何を学んだかを聞けば良い。
健康管理の基本は健康を気にしすぎないこと。病気や健康のことを一切気にしない。病は気から。これは、精神論でもなんでもなく、エビデンスベースの話。
全力でやりたいことをやり、思ったことを口に出し、好きなモノを食べ、友人と楽しく語らい、ぐっすり眠る。
本人旅は教養を培ってくれる。しかし、自身を教養人と思ったことは一度もない(むしろ、野蛮人に近いと思っている)。
様々な本を読み、人に出会い、旅をすると自分の小ささや幼さがよく分かる。
常に自分の身の丈を思い知らせ、謙虚であらねばと思わせてくれる。
本人旅から何かを学ぼうとするのではなく、面白いかどうか。著者の価値観では面白いかが一番上にある。
著者の経験則で、最初の5ページが面白くない本は最後まで読んでも面白くない。その本はご縁がなかったと割り切って、読むのをやめる。
また、わからない部分を、より血肉化するには読み返しが結局一番近道。
アウグストゥスのゆっくり急げ。
新しい分野を勉強するときは分厚い本から借りてきて読み始め、だんだん薄い本へと進んでいく。点から面の理解へ。
逆だとなんとなく概略がわかって、分厚い本は読まなくなってしまう。1ヶ月くらいかけて10冊くらい読むと、その分野について詳しい人と話しても理解でき、会話が楽しくなる。
会社生活も天国→地獄の順より逆の方がいいという笑い話もある。
地獄から天国への読書法がおすすめ。
新聞の書評は、専門分野の署名記事なのでアホなことを書いたら同業者から笑われるので、実際、興味を掻き立てられたものはほぼ例外なく面白い。
古典は無条件で優れている。何十年も何百年も無数の人々の眼力に耐え、市場に生き残っているので。古典の定義は様々だが、岩波文庫や東洋文庫に入っている本と考えると間違いない。
本は少しでも魅力を感じたらとりあえず読んでみる。作者で選ぶ方法も。(著者は、辻邦生、高橋和巳、塩野七生、山田詠美、佐藤賢一、若桑みどり)
本はただ受け身で読むのではなく、自分で考えながら能動的に読む。鵜呑みにしないで読む。
読まないという選択肢がないという、ビジネスをやるには読むのが当たり前という本は面倒臭がっていても仕方がないからさっさと読むのが得策。
人と付き合う場合も、ワクワクするか、面白いかどうか。
出世しそうだからとか、役に立ちそうだから付き合おうといった発想では、所詮、利害を超えたグローバルな付き合いはできない。
相手に変わっているな、感覚が違うはと感じたら、たんに否定するのではなく、相手の感覚を追体験しようとするとそれまでになかった感覚を理解できる。案外心地いいかも、そうなれば、その分人間に幅ができたということ。
人生にとって時間は一番貴重なものの一つ。
人生の理想は責務ミニマム、面白いことマキシマム。
優れた歴史書とは司馬遼太郎のような物語性が強く、歴史とは言えないものでなく、(トルストイも同様)エビデンスに基づいて当時の出来事を正確に再現するもの。(半藤一利作品のような)
歴史を学ばなければ、未来を見通せない。成功だけでなく、失敗に学び、彼らが陥った落とし穴に落ちないように。
人間は次の世代のために生きている動物。子供を育て上げたら死んでもいいのに、生きているのは、人生で学んだことを次世代に伝えて、より生きやすくするため。
政治体制が違っても、人の暮らしに必要なものは変わらない。温かい家と食事、そして心を許せる友達。
※様々な出会いや別れを通じて心を許せる友達を見つけていくことが人と付き合う醍醐味。
旅は理屈ではない。面白そう、楽しそうというだけ。
ピラミッドは300万近く石が積まれているが、一つが積まれていないとか。全部を積んでしまうと崩れるという伝承から。
天地創造神の女媧が天を修復したときも、石を一つだけ残した。
このことから著者も一宮巡りは一つ、立山雄山は残してあるとか。
著者の旅の仕方は、ヨーロッパ旅行であれば安い往復チケット(航空券)とユーレイルパスを買う。あとは電車に乗りながら、この街綺麗そうだな、で降りて旅が始まる。
駅前の観光用絵葉書を見て、見るべき所のあたりをつける。または高い所にあるお城に登り、見渡して決める。
ミシュランガイド一冊で手早く地図もホテルやお店のグレードもわかる。(現地の店頭で買う)
ホテルも原則予約しない。行動が制限されるから。
旅先ではできるだけ街を歩く。
人間は二足歩行の動物だから、歩いて街を確かめるのは本性に合っている。
美術館や教会、博物館以外にも地元のスーパーや市場などに行く。それは政治が上手く行っているかがよくわかる。(商品が少なく、高値だと政治が乱れている)
若者や女性のファッションが年々キレイになっている国は政治や経済がうまく行っている。人間は動物であるから、子供が産める若い女性に男性が貢ぐという万国共通の法則がある。
旅は行けるところが限られる。旅と本は保管関係にある。
うまく、本・人・旅を組み合わせて、人生をよき思い出で満たしてください。
人生の楽しみは喜怒哀楽の総量にあるから。
北欧での選挙の教え方
選挙である有力候補を支持→
三つの方法①その人に投票②白紙③棄権
支持しない場合は一つ→
①別の候補者の名前を書くこと
チャーチル曰く、選挙とはろくでもない人の中から現時点で税金を上手く分配できそうな少しでもマシな人を選び続ける忍耐である。※選挙に出る人は異性にモテたいとか、お金を儲けたいとか、目立ちたい、権力を握りたいとかせいぜいそんなところが目的。政治家に立派な人格を勝手にイメージしてはいけない、安易に信じてはいけないない。
民主主義も決してベストではなく、ベターくらい、ワースに転げ落ちることも考える。
財産三分法
①手持ちの財布にはいくらかのお金を
②手取り収入のうちなくなっても生活に困らない分を投資に
③残りは預貯金に
国の年金が危ないというのはどういうことか。現在の日本の税収は55兆、歳出は96兆。歳入不足を国債で補う。国債が発行できれば財政は維持でき、公的年金も支払えるということ。つまり政府が破綻しない限り、公的年金も破綻しないということ。
私たちが銀行に預金するのは、その銀行を信用しているからで、それと同じく金融機関が国債を引き受けるのは国を信用しているから。つまり国の格付け以上の格付けをその国の金融機関が得ることはできない。
※国の年金が破綻すれば、国民年金を支払わず、個人で積み立てていようがそもそも銀行の預金は全て消し飛んでいる。国が存在している限り、社会保障が崩壊することはない。
国以上に安全な金融機関は存在し得ないというファクト。
年金問題について、これまでの小負担・中給付モデルは通用しない。
このモデルは1960年代の高度成長期に骨格が完成したもの。
昔の平均寿命が65歳前後なので、サッカーチームで1人の高齢者を5年間支える、から肩車で20年以上に変化。
負担が給付であるという大原則に則って負担を増やし、社会保障を増やすべき。
選択肢は2つ。中負担・中給付。もしくは大負担・大給付。これはスウェーデンなど、北欧。
小負担・小給付では大幅に医療や公的年金を削減しなければならないから、おそらく政治的に不可能。
年金問題世代間の不公平。
現在の高齢者は支払った保険料の4倍程度の公的年金を受給、若者は2倍程度しかもらえない。
この不公平をなくすには二つ。
増税して将来の公的年金を増やすか、移民を受け入れ労働人口を増やし、平均寿命を65歳に戻すか。
公的年金の問題は社会保障全てに共通。
負担を上げるか(給付が増える)、選挙に行き分配が上手い政府をつくるか、経済成長するかの三つしかない。
消費税増税抜きでは社会保障は補えない。
税金とは公共財や公共サービスの対価。負担なしに給付だけ得ようということは成り立たない。
また、社会保障は全市民対象であるから、働いている人が払う所得税では人口減少の現在やりくりはできないので、高齢化社会では消費税だということになる。(だから、高齢化の先進国であるヨーロッパでは付加価値税が中心)
所得に税を課すのは勤労を罰することになる。個人が選択的に消費する際に課税する方が公平だ。
※金持ち優遇の批判に関しては相続税100%で応じ、若い世代への贈与税率0%と組み合われると高齢者から若い世代にお金が回る。
日本が抱える諸問題の根本は少子化。
お金を注ぎ込むだけで出生率は回復するのか。子供は社会の宝であるというごく当たり前の基本認識を徹底する。家事も育児も介護も社会全体でサポートし男女が等しく分担する文化風土をつくること。
子供の声がうるさいということが問題になることがあるが、自分が次の世代のために生きているのことがわかっていない。
沈むボートを下ろす順は子供、女性、男性、高齢者の順である。
フランスの出生率回復の事例は、手厚い給付(その時の経済力にとらわれない)、待機児童ゼロと0歳児での育児休暇の給与を100%保証、3年間休職しても人事評価は変化しないなどを実現してわすが10年で1.6から2.0を超えるレベルに。
また事実婚を認める制度も。
日本は夫婦別姓もまるで進んでいない、こんなものは伝統でもなんでもない。明治からスタート。
高齢化対策
平均寿命−健康寿命=介護
であるから、健康寿命を延ばすこと。
これにはどの医者に聞いても働くことであると。
定年制を廃止し、年功序列型から同一労働、同一賃金に移行、労働の流動化。公的年金の受給開始を70歳くらいにしても問題は生じないだろう。(マイナンバーを活用して一定の資産や所得がなければ支給、これで年金財政が好転。)
医療も年齢フリーで全員3割負担、軽減措置は年齢でなく、資産、所得がないことにすべき。
35年ローンは成長神話(平均7%の実質成長)を引きずったモデル、今では所得が下がれば破綻する恐れも。
不動産価格は下落が基調の今、買えばあなたのものになるという資産志向は無意味。
不動産が資産となったのは高度成長と人口増加が前提だった。
持ち家志向の時代はおわった。
これからは欧州のような家具付き賃貸を柱に歳をとれば公営のコレクティブハウス(仲間が共同生活)に入れるのが理想。
持ち家を買うならキャッシュ主体で。そうすればローンに支配されなくて済む。
※空き家で困っているなら空き家を取得しリフォームした人に税を優遇して、新築になど優遇しなければいい。
TPPでいうと日本が儲かるか否かが判断軸になるはず。(幹)
賛成派も反対派も儲かることは認めているのであれば、賛成し、損失が出たら補填すれば良い。(枝葉)
また、TPPより日中韓FTAの方が、数字ファクトロジックでいうと有益。国語だけで見ないこと。
歴史は一つではなく、民族の数だけある、というが著者はあくまでも一つであると考えている。
中国が不安定化して一番困るのは日本。
外国をメディアが伝えるイメージだけで判断するのは危険。
原子力発電は止める・冷やす・閉じ込めるの三つをワンセットでクリアする他に安全を確保できない。
エネルギーについて、石炭を掘る重労働で今でも年間数百人規模の労働者が命を落としている。
地球温暖化については、二酸化炭素の排出量を削減し温暖化を食い止めることが何としても必要。
TOEFLで100点を取れる力があれば世界が違って見えるのも事実。
TOEFL100点はグローバル人材の最低ライン。欧米の一流大学に行きたければ、110点超え。日本にはTOEICがあるが、世界共通はTOEFL。
BS 1の早朝のワールドニュースやABCニュースシャワーではコンテンポラリーな英語表現を学べる。
海外ドラマを英語→日本語→英語で見る方法も。
また、NHKのラジオ講座を聴き続けることなど。
要はやる気の問題。
英語力とは聞いて話すだけのスキルではない。いくら話す能力やヒアリングに長けていても、話す内容がなければ何の役にも立たない。
英語は度胸、恥をかいた分だけ上達する
母語を損なわないなら英語の早期教育も有用。人間は思考の基盤となる母語(マザータング)で物事を考えるため、まずは日本語の、力をしっかりと身につけなけねばならない。
マザータングの発達を損なわない限りにおいて、英語の早期教育は前向きに考えても良い。
かつての冷戦構造を大前提とした、キャッチアップモデル、人口増加、高度成長を与件とした放っておいても成長する時代はおわり、リアルな現実が到来した。
私たち現在日本人の価値観や人生観は仕事や職場に偏り過ぎている。
仕事の話はできても文学、美術、音楽、歴史、宗教の話はできないのもその偏りに起因か。
著者自身の本音ベースの人生観、仕事観は何事であれ面白いか、ワクワクするかどうかを人生観の根底に置いている。
7、8割の食べて、寝て、遊んで、子育てをする時間を確保するための2、3割の仕事をする時間と捉えると、仕事はどうでもいいものである。
そう捉える方が、仕事を人生の最優先事項などとは捉えずに、上司に萎縮せず、かえって堂々と自分の信念に従った仕事ができる。
企業のトップは機能。出世とはたんに分担する機能が変わっただけ。決して人間的に偉いわけではないと得心すること。
職場内の序列が人間のランキングだと勘違いすることも。
どうしても仕事がうまくいかなければ、さっさと仕事を変えてしまうという選択肢も。
みんながみんな置かれた場所で咲く必要などどこにもない。
地球が誕生して46億年、ホモサピエンスの登場はわずが20万年。46億分の20万は0.00004。ほんの一瞬。人間の文明は地球の表面にこびりついたカビのようなもの。そう考えると仕事や職場のことは実に小さいことだと割り切れる。
人間が物事を考えるときの言語がマザータング(母語)。
国際結婚カップルが子供が産まれたら家で話す言語を決めるのはこのため。
精鋭を少数集めるのではなく、少数だから精鋭になる。
会議室が少ない方が良い会議ができる。
本当に必要な会議しかしなくなる。
ビジネスは本気かどうかがすべて。コンタクトセンターが大事だと思ったら、毎日オペレーターの顔を見に行くこと。そのことで従業員はここは大事な部署だ、頑張ろうという気持ちになる。
日本は今アメリカを手本にしたキャッチアップを目指した単純で幸福な時代は終わり、課題先進国(少子高齢化、財政の悪化、国際競争力の低下)となった。これからは手本なしに自ら道を拓かねばならない。
私たち個人も同じ。一人一人が自分の生き方を頭でよく考えること。考えることはごく当たり前だが、考えなくてもいい時代が戦後長く続いた余波で、当たり前のことに順応できていない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
