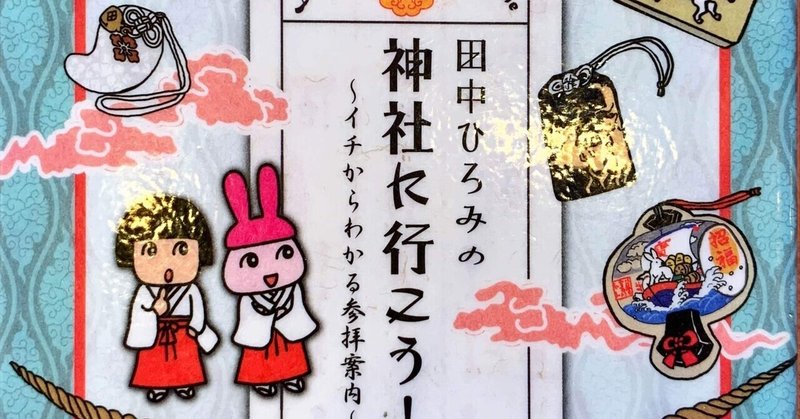
神社に行こう!〜イチからわかる参拝案内〜
鳥居
神様と人間の世界を区別するもの
※お邪魔します、の意味で礼をする
真ん中は神様が通る正中(せいちゅう)なので、両端を歩く

奈良時代から明治時代まであった神仏習合でわかりやすく例は、仏様が仮に神様の姿で現れた権現。現は仮にの意味。
灯籠には鹿や雲が掘られている。
神楽は神様に捧げる舞。
本殿以外を摂社や末社と言う。
摂社はメインの神様に関係する小さな神社。
末社はそれ以外。
神様を守るのが狛犬。口を開けているのが獅子、閉じているのが犬(角がある)。
お寺は仁王様。
拝殿は神様に参拝をするところ。(手を叩くのはこちら)
本殿は神様がいるところ。
※山そのものが神だったりして、本殿や拝殿がないところも。
賽銭の五円(ご縁)や十円(遠縁)はあまり関係ない。
参拝方法(二礼二拍手一礼)
①賽銭
②鈴(来たことをお知らせ)
③お辞儀2回(90°)
④手を合わせて、右手を少し下げる
⑤ゆっくり2回手を叩く
⑥最後にお辞儀(90°)
※出雲大社はニ礼四拍手一礼
素手で拍手をする意味
武器なしの意味や神様を振り返らせる意味
昇殿参拝
祈祷やお祓いの時に拝殿に上がって参拝すること。
大麻(おおぬさ)でお清め。
祓詞(はらえことば)は古事記のからきている。
玉串は榊の枝に紙垂(しで)という白い紙をつけたもの。
おみくじ
凶がでたら利き手じゃないで、結ぶと吉になる。
良いみくじは持ち帰ってもよい。
絵馬
乗り物として馬を神様に捧げたことから。
形は馬小屋をかたどる。
お守りは買うでなく、受ける。
お守りは守り札のことで携帯できるお札。
お札は神様の分身。
御神木にはしめ縄。相撲では横綱のみ。
しめ縄には、結界や清めの意味がある。
鳥居
明神系…笠木が上に沿っている
神明系…笠木(かさぎ)が真っ直ぐ
狛犬
守護や魔除け
巫女
未婚の若い女性
神に仕える乙女
雅楽(ががく)
世界最古のオーケストラとも
神紋
家には家紋、神社には神紋
例えば三つ巴は、武神である八幡様でよく使用される。
皇室関係は菊の御紋。皇室と関係ない菊はアレンジされる。
神主の職階
宮司
権宮司
祢宜
権祢宜
出仕
清めに塩が使われるのは
イザナギが黄泉の国から帰った時に海水で身を清めたから。
なので、清め塩は海水からとれた天然ものが良いとされる。
民間の神前結婚式は明治34年に東京大神宮で行われたのが始まり。
三々九度
新郎新婦がお酒を酌み交わす儀式。
どの盃も三口で飲み干す
伊勢の神宮大麻
天照皇大神宮に神様の印と大神宮司の印。
御幣
神様の依代(よりしろ)とされる
奈良の大神神社(おおみわ)は三輪山が御神体。
神道は自然そのものを神としていたが、仏教ご入ってきてから神社という今の形になった。
稲荷社、八幡社、天神社が多い。
祈年祭
2月17日に稲の豊作を祈る祭り
新嘗祭
11月23日
収穫を感謝する祭り
地鎮祭
土地の神様に挨拶
神葬祭
神道式のお葬式
祭りでは神様の食べ物である神饌(しんせん)をお供えする
祭りの後にお供え物を飲食するのを直会(なおらい)
神輿の起源は大仏ができた時、宇佐八幡の神様を奈良にお移ししたのが始まり
三方(さんぼう)
神饌を載せるための台
※家庭では米、塩、水の3種と酒を。
外宮には
三ツ石
亀石
寝地蔵石
がある。
内宮には
踏まぬ石(荒祭宮 あらまつりのみや)
がある。
※神馬(しんめ)は1の付く日
瀧原宮(たにはらのみや)
ミニ内宮。別宮で遙宮(とおのみや)とも。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
