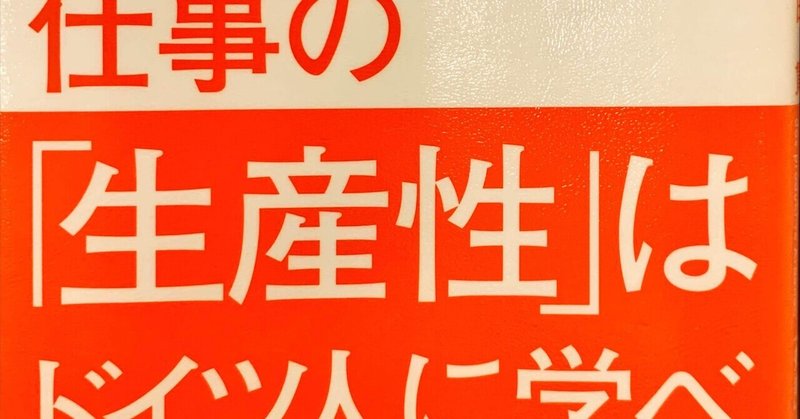
仕事の「生産性」はドイツ人に学べ
ドイツと日本の違い
ドイツは国民を労働者と捉え、労働者の権利に重きを置いてきた。
日本では消費者と捉えて、消費者の権利を重視している。
ドイツでは月〜金を働く日、週末を安息日。
ドイツは閉店法で、日曜、祝日は営業してはいけないことになっている。
※平日の夜間は18:30まで、土曜は14時まで。
人は人、自分は自分と考えることが必要。
自分軸を持たず、いかに人と同じであるかを考え傾向が強くなると、同調圧力が生まれる。
駅で遅れた時などに、アナウンスを繰り返すのは、鉄道会社の責任逃れのためにも感じてましう。
ドイツ人にとって子供の送り迎えや勉強を見ることを夫婦で分担することは当然で、なおかつ夫婦2人の時間も大切にする。
他人に変化を求めるのではなく、自分が変わることで成長しなければいけない
会社の仕組みや風土は容易に変えられないが、自分だけでも時短勤務の人をフォローしてあげる、理解するだけでも大きな変化。
残業も5回に1回は断るなど、自分の時間を優先する方法も。
ドイツのメッツラーシ社は現場の自由度が高い。
日本では求められるホウレンソウは結果、結論、判断が下されるまで相当な時間が必要になることも少なくない。
ドイツでは上司が不在の時に、案件を進めても何も言わない。
日本では怒り心頭するだろうが、それは結局、責任を負うのを避けているだけ。
ドイツメッツラー社の例
無駄な目標管理は不要。目標管理はできない理由が上がってくるだけ。
北風政策ではなく、太陽政策で社員の士気向上を図る。
部下に考えさせ、リードをとった行動を促す。いちいち報告を求めない。
自主性を重んじることは、生産性を上げるには大切。
部下の自主性を育てるには、
ただ任せるだけでなく、部下の不安に寄り添いながら、距離をうまくとることではじめて、自主性が育まれ、士気と生産性が向上する。
目的を履き違えない
野球のニ塁手であれば、ボールを味方の胸を目掛けて取りやすい球を投げることが目的でなく、一塁手に素早く投げることが目的。
日本では出る杭は打たれるが、ドイツでは出ない杭は評価されない。
協調と同調は違う。
協調は利害の違うものが力を合わせることで、同調はある人の意見などに賛同し同じ行動をとること。
同調圧力が強いと不正を見て見ぬふりをし、不正会計や産地偽装などを行っていても、何も言えないのではないか。
君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず
※優れた人物は協調はするが同調はしない、つまらない人物はやたらと同調するが協調はしない。
優れた人は他人の意見に耳は傾けるが簡単には流されない。
ドイツでは街の景観を良くするため、住宅地では特に芝刈りと雪かきについて規制がある。
同調圧力からぬけますには、本当に必要か、他に方法はないかを常に疑問に持ち、問うこと。
ドイツでは仕事でなく、家族が生活の中心。
仕事の成果よりも自分の人生をどう生きるか、家族との時間をどう過ごすのかに重きを置いている。
日本のように人気のある大企業に就職することは相対的な価値観であり、自分だけの絶対的な価値観ではない。
ドイツでは日本の新卒一括採用などでなく、在学中に休学して3〜6ヶ月程度インターンシップ研修を受ける生徒が多く、そこで適性を見極めるので、日本のように入社後3年以内に3割が辞めるなどということがない。
犬と子供の教育はドイツ人に任せろ、というくらいしつけに厳しく、日本のようにスーパーで子供が大声で泣いて、親が感情的に叱ることもない。
ただし、体罰を加えることはない。
子供が悪さをすると、なぜそれをするかの、なぜそれをしたらいけないのか、を諭す。
親の時間と子供の時間を明確に区別する。
親の集まりに子供が行くことはあまりなく、レストランも大人だけで利用する。小さい子供はベビーシッターに預ける。
食に関しても、日本みたいな好き嫌いをせず食べなさいではなく、食べたくなければ食べなくていいという教育方針。
ドイツでは公共の場で子供が騒いでいるかとに苦情は言っても、赤子が泣いていることは気にしない。
子供の誕生と発育は、親だけでなく、社会の喜びであるという考えが浸透している。
ドイツでは新しいものを次々に買うことに喜びを見出すのではなく、気に入ったものを長く使い続ける。
どこの家庭に行ってもものが溢れかえっていることはない。
ドイツでは衣食住の住にお金はかけても、衣と食には驚くくらいお金をかけない。
ドイツ人はケチではなく、お金を使うところと使わないところが明確に分かれている。
3週間のバカンスのためにはお金を惜しまない。
ドイツはいいものを高く買い、いらないものは買わない、日本もこの習慣が身につけば、デフレから脱却できるかも。
地方自治体相手に訴訟を起こせば、プライベートでシッターを雇うためのお金を払うシステムがある。
ドイツでも、少子高齢化が進んだことから、200.年頃から法律を整備。
育休は最長3年、育休中の生活を保障(平均賃金の67%)などで、父親の取得率は34%。
ドイツではリサイクルが徹底、ゴミの処理責任は生産者にあると定め、ペットボトルや瓶の料金にデポジットが上乗せされ、回収機に持ち込むとクーポンで還元される。
ドイツでは年齢や立場に関係なく、自分から元気よく挨拶をする。挨拶で互いの見えない壁を取り払うのがドイツ流。
コミュニケーションは質より、量。
エレベーターで会った時などでも、自然に声をかける。
ドイツに限らず海外では以心伝心や暗黙の了解など通用しない、全て言葉に出して相手に伝えなくてはいけない。
相手の気持ちを忖度すると余計な仕事が増えるだけ。
わからなければ、わからない、質問するのはタダと考えること。
今は魔が悪いんじゃないか、など考えない。なる早は、いつまでですか?と聞くこと。
日本人は、試験問題がそうなっているからか、答えは一つと考えがちであるが、社会ではそうではない。
日本では個人技よりチームプレー重視で、花形選手(スペシャリスト)の誕生を好まない。営業部の次が人事部といった畑違いの部署異動(ジェネラリスト)は海外ではほとんどない。
管理しすぎるのも、自身が自立していない表れ。自分の見ていないところでトラブルが起きたら困ると思っていれば、部下を信頼していない証拠。必要最低限のホウレンソウにすれば部下も上司も自立する。
失敗したら、なぜできないんだと個人批判したり、犯人探しをしたりせず、できるようにするにはどうするかを、考えさせて、議論することが必要。
上司はなぜそうしたのか、を、聞くのではなく、事後処理にベストを尽くし、報告してくれてありがとうと伝えること。
組織にとってはその方が助かるから。
ルールは守るものだが、ルールが現実に合っていなくて、うまくいかなければ改善するべき。
ルールに固執していたら、失敗を許せない組織になる。
ドイツでは何回もメールを打つくらいなら、一回会って話した方が早いという感覚。
会議では、日本のように重役だけが話して若手が黙っているということはなく、それは会議の時間を無駄にしていることと同じ。
出席したからには全員発言することが鉄則。
日本人とドイツ人は同じ真面目で勤勉であるが、違うところは、自己主張が強く、優先順位が明確であること。
社内外交で大事なのは、この仕事がチームや会社にとってどれくらい重要なのかを十分に説明して、相手の理解を得た上で仕事を手伝ってもらうこと。
同じチームだから、アサインメントに書いてあるから、上司であるからでは、成り立たない。
ドイツで虫の入ったスープを出されて、交換してもらう際に店員にはそのスープを交換するまで下げさせなかった。
そのまま虫を抜いて出されるかもしれないから。
厳しく国際社会を生き抜くには何事も闇雲に信じてはダメ。
オフィシャルとアンオフィシャルの両方でフレンドリーな関係をつくっておくことが重要。
食事だけでなく、一対一で会って話すのも社内外交の一つ。
ランチをしながら役職に関係なく、他部署の人と気軽に情報交換。
風通しのいいコミュニケーションをすれば生産性は上がる。
ドイツでは相手が話している時は遮らないのが鉄則で、頻繁に相槌を打つと却って機嫌が悪くなる。メモも聞いていないサインとなつてしまう。
文化の違う人とコミュニケートするためには下手でもその国の言語で話すこと。
通じるなら英語でいいでなく、現地の言葉、文化、歴史を理解しようとする姿勢が大事。
ドイツには時間管理が全てだ、という格言があるくらい時間には厳しい民族。
ドイツで日本人が言う忙しかったは通用しない。前からわかっていたことでは当然。ドイツ人は自分で時間を管理するのが当たり前。
仕事に追われるな、仕事を追え。
日本人はそうなっていないのでは。
今晩中にこの資料を作らなければいけないと思っているなら、敢えてその作業をやめて、自分のやりたいことをやる。
そうすると意外とスムーズに作業が進むかも。
ドイツで寝てないで仕事アピールはとんでもなく仕事ができないことをアピールしているようなもの。
しかしドイツでも経営者や管理職、自営業者は長く働いている。給料が高いので責任や仕事量が増えるのは当然。
日本は逆で給料が安い新入社員が1番働くあたりはドイツと全く違う。
ドイツではダラダラ仕事をすることがほとんどない。
徹底して仕事に集中するのは定時で終えて、プライベートの時間を楽しみたいからだろう。
日本人は自覚していないだけで、かなりの時間を浪費している。商談での世間話やネカフェや公園でサボっている。
スウェーデンでは2002年に6時間労働を取り入れたところ、健康が改善、生産性向上、利益率25%増加した。
ゾゾタウンも6時間で生産性向上。
つまり、短時間で働く方が生産性が上がる。
残業している限り、仕事ができる人間にはならないと自覚しすること。
メールにかける時間は短縮できる。シンプルなメールを心がける。
ドイツでは間違ったデータが送られてきても、次の日にただこれを受け取ってと謝罪もなくデータが送られてくるだけ。正しいデータを送ればよいのでそれ以外の言葉は不要、と考えている節がある。
ドイツでは労働時間貯蓄制度がある。これは残業した時間を貯蓄口座に貯め、有給として使える制度。
まさに、時は金なりの制度。
残業代をもらえないなら、サービス残業に甘んじる日本人とは大違い。
ドイツにはより少ない労働でより多い業績を。という標語がある。
お金の浪費は稼げば取り戻せるが、人生の浪費は取り戻せない。
時間が無制限にあるとある考えるとどうしても生産性は落ちる。
日本電産も残業ゼロを公言。
ドイツにはルーエツァイト(静かな時間)と呼ばれる時間帯がある。この時間帯には騒音を立ててはいけないという法律。
休日の昼間であっても楽器の演奏や日曜大工すらできない。なので散歩が多いのかも。
実はこれがメリハリにつながり、仕事の生産性にも結び付いているのかも。
ドイツでは上司であってもアサインメントを優先させるので、急な依頼は無条件に応諾するとは限らない。
しかし、他の仕事を割り込ませないという方法は、生産性を上げる最もシンプルな方法でもある。
その上、仕事を断られても上司は腹を立てたりしない。そこでら好き嫌いの感情は挟まない。
突発的な仕事は発生するが、もっと早い段階で対処できるはず。部下も早い段階であれば、追加でも対処してくれる。
ドイツではプレゼンの資料はパワーポイントを使うこともあるが、社外向けではこだわるが、社内向けでは簡単に仕上げる。
日本は社内向けでも凝ることが多く、生産性の観点から疑問。
今までやっていたからやるのではなく、無駄な作業をなくすことも時間をつくる有効な方法。
ドイツでは連邦休暇法があり、大抵夏に2〜4週間、冬に1〜2週間ウアラウプ(バカンス)をとり、海外旅行(カナリア諸島、クレタ島、イタリアやスペインの地中海沿岸、アフリカなど)に出かける。
日本のように複数の国の観光名所をあちこち巡るのではなく、同じ場所に2〜3週間滞在してハイキングやサイクリングなどをして過ごすのが主流。
ウアラウプ中は2〜3週間待たされるが、どうしても即座に対応しなければならない仕事などほとんどないことに気付く。
経営者も会社を休む。そもそも自分がいなくても会社を回るようにしておくことが、経営者の役割。
ドイツで同調圧力がないのは、自分も長く休むから、早く帰るからと考えているからかも。
日本も周りの人に寛容になれぼ、もう少し楽に生きられるかも。
日本では上司と部下の上下関係、同僚同士でも年齢や入社時期がとても重視されるが、ドイツに限らず一般に外国では無関係。
自分より年上だから、一年先輩だからといった理由で、威張ったり、へりくだったりすこたはない。
日本の会社では肩書きで名前を呼んだりすることも、ヒエラルキーを強固にしている元凶かも。
そうすると社内でも杓子定規な話し方しかできなくなる。
ドイツでは上司は日本ほど絶対でなく、あくまでその地位は役割でしかない。
生産性を高めたいなら、組織の上下関係をできる限りフラットに近づけることも一考の価値がある。
ドイツの著者の会社では任された範囲ではいちいち上にお伺いを立てるようなことは一切ない。決断を躊躇していれば、顧客、同僚からの信頼も失う。
人事や経費など独断を戒められているものも当然あるが、自由度が確保されておりそれがモチベーションに繋がっているのではないか。
そしてその決断に口出しはせず、最初に指示していない事項には、その決断を尊重するしかない。
意思決定(会議)の人数を減らすことはスピードを上げるための最も有効な手段。
著者の会社、会社にとってダメージを与えるようなことをしたらクビだ、ではなく、それを隠したらクビになる。
つまり、悪いニュースほど早く言いなさい、ということ。
それを隠すと企業の信用を傷つけるから。
ミスは起こり得ること。
トラブルが起きたらすぐ対応できるシステムを考えておく。
また、ボーダーラインを超える前に対処できるような方法を考えておく。
リスクはコントロールできるもの。
コントロールできないリスクを取ることが問題。
ドイツ人は合目的なコミニュケーションを好む。
なぜそれをやらなければならないのかを伝える。みんながやってきたから、は通じない。
目的、効果、理由を丁寧に説明する。
目的や理由を説明すれば全体像が見え、自然と作業効率があがる。
ドイツには、人生の半分は整理整頓であるという諺がある。
日本でも、元トリンプ社長吉越氏は人事評価以外の全ての情報は全社員で共有(社長のスケジュールまで)、残業ゼロなどして19年連続、増収増益に成長させた。
いくら偉い人であっても、わかるまで聞き返すをためらわない。
逆に聞くほどわかりやすく、伝えてくれる。
言わなくてもわかるだろうはほぼ一つの言葉を話す日本独特で、外国では言わないとわかならいが一般的。
ドイツは移民国家でわからないのが当たり前と考えているからか。
また、わからないまま進めると結局やり直しとなり、わかるまで聞く・教える方が仕事のスピードは上がる。
ドイツの会社ではオフサイト(会社を離れた場所)ミーティングがよく行われている。特にマネジメントクラス。自然豊かな保養地などで、家族を連れて。
ドイツでは飲み会はないが、17時にワインを開けてみんなで飲むちょっとした集まりはある。しかし1時間くらい談笑して終わり。上司がいるから、帰れないでなく、さっさと帰れる。
タカラトミーや北海道の六花亭製菓(日本で最初にホワイトチョコを製造販売)は子供や家族の誕生日、結婚記念日に休める、アニバーサリー休暇を設けている。
住友商事グループでは残業を減らした人に残業代を払う制度を。
ドイツ人は日本人からみると異常なくらい散歩好き。(犬の散歩でもなく、移動のためでもなく)
老若男女、雨の日も風の日も、友達の家を訪ねても散歩に行こうと誘われる。
散歩は日常生活をリセットしてくれる。
一流の人はビジネス、スポーツ問わず、何事においても切り替えが上手い。
トレーニングや健康法としてではなく、スマホも持たず、音楽も聞かず、何もしない時間が、何かを生み出す第一歩。
ドイツでは人間として当然の気持ちによって自然と家族が優先されている。
欧米の映画やドラマである様に、ドイツでも机の上に家族の写真立てを複数置いてある。
家族は社会の最小単位、家庭がうまくいっているから仕事に打ち込める。
社会の根っこを改革するのが、実は国力を1番強くする方法であるかも。
上司が率先して定時に帰り、有給を取ることが肝要。
ドイツでは街の景観を守るため洗濯物を外では干せない。選択したら乾燥機にかけてすぐに畳んでしまう。ちなみにドイツの水は硬水なので洗剤が溶けづらく、洗濯機は水温を選択する。
ドイツ人はスーパーでの横入りや車の車線規制の横入りにも寛容。
譲り合う心の余裕がある。
ドイツに限らず世界の人々は相手の実力を素直に認める。
互いの違いを認め合い、尊重する文化を持っている。
ドイツでホストファミリーの家に滞在したら娘が彼氏と同居していた。
それくらい人は人、自分は自分のという生き方が確立されている。
人は人、自分は自分という意識を持てれば、人との違いを円滑に受け入れることができる。
明日からできる、仕事術として
①他部署の人と1対1でランチをする
②会議の目的を明確にする
③今日決めて、明日作業する感覚(今できるかでなく、今やるべきかを、考える)
④毎日3つだけやるリストをつくる
⑤オフサイトミーティング
⑥意識的に変化をつくる(帰宅の道を変える、飲み屋を変えるなど)
⑦自分の時間をつくる(今日どうしてもやらなきゃならない仕事などない。寝る前に10分瞑想する、30分読書するなど)
生産性の向上は根をつめて働いて実現するものではなく、逆に余裕ができ、自分の時間を作った結果、自然と上がってくるのではないか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
