
世界のメンタルヘルス事情
こんにちは!私は、SDGs 目標10、「人や国の不平等をなくそう」に着目して、世界のメンタルヘルスケア事情について調べてみました!人の心の内面の問題であるため、ひと目で現状や対処法がわかりにくく感じられますが、国ごとにどんな違いがあるのでしょうか?ここでは、日本、アメリカ、シエラレオネを見ていきます。
精神障害とは?

そもそも精神障害とは、精神や行動に特定の症状があり、機能的な障害を伴っている状態のことです。世界での罹患者は4500万人にのぼると推測され、4人に1人は生涯に1回以上の精神障害を経験するともいわれています。
よく知られているものとして、気分の落ち込みや興味・喜びの喪失、体のだるさなど精神や体に影響が出る疾患であるうつ病や、気分の沈みなどがある抑うつ状態と、意欲が湧いて精力的に行動するようになる躁状態を繰り返す双極性障害、幻覚や妄想などが現れる統合失調症などがあります。
日本の精神医療

厚生労働省の調査によると、精神疾患のある方は平成29年度で国内に約420万人おり、生涯を通してだと約5人に1人の割合で精神疾患にかかるといわれています。さらに、日本の自殺率は世界6位と、先進国最低レベルであるという面もあります。
日本で精神医療を受けるとなると、病院での初診は予約制であることが多いです。診察で症状や患者をとりまく人間関係を問診し、医学的な検査や投薬、カウンセリングなどの患者に合った治療方法をとっていきます。日本では主に投薬による治療が中心です。
また、症状が重く自他への危害を加える可能性がある場合、入院の措置がとられることもあります。本人同意のもとでの任意入院、家族同意のもとでの医療保護入院、都道府県知事の措置入院の3種類の入院に分けられ、生活習慣の改善やリハビリ、体の検査治療などが行われます。病棟は開放病棟と閉鎖病棟があり、隔離以外の方法では危険を回避することが困難であると判断される場合、患者本人の医療や保護を目的として閉鎖病棟での隔離、拘束が行われる場合もあるそうです。
日本の助成制度

日本では、精神疾患の患者を支援するための様々な制度があります。すべての精神疾患の通院治療を対象とした自立支援医療は、医療費の助成のひとつです。所得に応じて上限はあるものの、申請をすることで医療費の負担を3割から1割負担に減らすことができます。
また、生活費の助成として、全ての精神疾患を対象に、病状が一定の状態にあることの認定を受けることで精神障害者福祉手帳が給付され、公共料金の割引、所得税や住民税の控除を受けられます。さらに、医師の証明を示すことで、特別障害者手当として月額27300円の給付を受けられる制度もあります。
労働の面でも精神疾患の患者への支援があり、精神保健福祉センターという精神疾患に特化した各都道府県の支援機関を活用したり、契約関係を維持させたまま労働の義務を免除できる休職制度を精神疾患に適用したりすることができます。
日本の問題点

それでは、このような現状にある日本の精神医療や制度にはどういった問題があるのでしょうか?まず、日本の精神医療では病床数や平均的な入院日数の多さが指摘されており、世界のOECD加盟国36ヶ国における精神病床数全体のうち、約4割を日本が占めています。入院患者平均在院日数に至っては、OECD加盟国の平均が1ヶ月程度であるのに対し、日本は9ヶ月もの多さです。精神障害当事者を隔離し、家庭や社会から排除しようとする差別や偏見があること、病院側が患者を入院させ続けることで収入を得ようとしていることなどが背景にあると推測されます。また、精神科の医師、看護師の人数減少による人員配置の不足も問題となっています。
制度面においては、そもそも制度の存在が認知されていないことで、しかるべき支援を受けられなくなってしまうという問題や、更新手続きや受給者証の交付までに時間がかかってしまうことなどの問題があり、さらに症状の回復ラインが精神疾患では見極めが難しく、休職からの職場復帰へのハードルが高いことも問題です。
アメリカの治療

つぎに、アメリカで行われている精神医療について紹介していきます。アメリカも3人から5人に1人が精神疾患を経験すると言われている国です。アメリカは、ファミリードクター制度というシステムをもとに精神医療が行われており、これはかかりつけ医による診察を受けてから精神科に受診するものです。かかりつけ医による所見を踏まえた上での受診となるので、精神科で情報収集に多くの時間を割くことなく、はじめから治療的な診察に長い時間を充てることができ、再発防止の効果が見込まれています。
また、通院での治療が中心に行われ、慢性症状用の病床はごく少数で在院日数も1週間程度に収まっています。身体の拘束などは基本的に禁止されていて、患者が医師の対応に不満を持てば裁判所に訴えられるという制度が整えられています。
さらに、「精神疾患及び知的障害に関する大統領教書(ケネディ大統領教書)」により脱施設化が大きく進み、精神科病院が解体され、地域精神保健センターの整備も進んでいます。
加えて、化学的治療方法とは異なったアプローチで患者の診断や治療を行うサイコロジスト、社会福祉的なサポートを担うソーシャルワーカーなど、心の健康に関する専門家職業が多く存在しているのも特徴です。
アメリカの制度

アメリカでの精神疾患に対する制度として、Comunity Mental Health Service Block Grant が挙げられます。これは、重度精神疾患の成人や情緒障害の子供を対象に、地域メンタルヘルスシステム構築を支援する助成金プログラムです。
アメリカの保険制度は任意となっていて、民間医療保険に加入している人が多いです。これらの多くは、特定のネットワーク内のみの医療費を安くするものになっています。治療費が高く、受診するまでのハードルも高いアメリカの精神科は、相談の絶対数を減らすことで1人当たりの診察時間を長くする方法をとっているのです。
また、自治体ごとの相談機関の設置やコールセンターへの政府の援助など、アメリカは制度として国民単位ではなく自治体やネットワーク単位での支援を中心としていることが多いように感じられます。
シエラレオネの現状

最後に、シエラレオネにおけるメンタルヘルスの現状と対策を見ていきたいと思います。シエラレオネは、アフリカの西側に位置する共和国で、10年以上内戦が続き、国民の平均寿命は37歳から40歳と、厳しい環境に置かれている国です。
精神疾患に対応できるような施設は、精神科病院、精神科クリニック、リハビリ施設がそれぞれ国に1箇所ずつのみで、精神科医も1人しか存在しません。また、精神疾患の内訳のうち、統合失調症が3%、うつ病が43%となっていて、戦争や紛争、治安の悪さゆえのトラウマなども問題になっています。
シエラレオネの治療と政府の動き
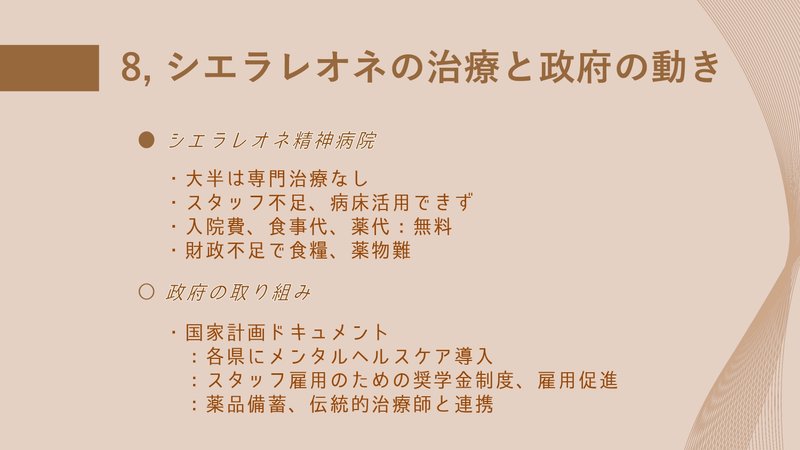
シエラレオネに置かれている精神病院には様々な問題があります。スタッフ不足により、設けられている病床のうち実質4分の1しか使えなかったり、財政不足による食糧難や薬物難が多発していたりします。そのため、患者の大半は専門治療を受けられないような状況で、日中何もすることがないような患者も多いそうです。シエラレオネ精神病院での入院費は食事代や薬代含めて無料となっていて、入院期間は原則2ヶ月と定められていますが、行く先のない人には長期の滞在を許したりと、臨機応変な対応も行われています。
このような現状に対し、シエラレオネ政府は国家計画ドキュメントを企画しました。まずは各県にメンタルヘルスケアを導入し、10床の病棟を確保することを目標にしています。また、有資格スタッフ雇用のために奨学金制度を設け、雇用促進によるスタッフ不足解消を図りました。更には、薬品備蓄の充足や、伝統的治療師との連携の強化なども計画されています。この国家計画ドキュメントの実現のためには、十分な財源の確保と全国レベルでの取り組みが必要となっており、潤滑に目標が達成できるのかが課題になっています。
おわりに
最後まで読んでいただきありがとうございました!今回のstudyで世界のメンタルヘルスケアを調べてみて、それぞれの国の違いや特徴、問題などを詳しく知ることができました。精神の問題というと難しく感じがちですが、誰にでも起こる可能性のあるものです。各国の現状や文化に合った形での治療や制度が整えられ、国による精神医療の格差の解消につながるといいなと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
