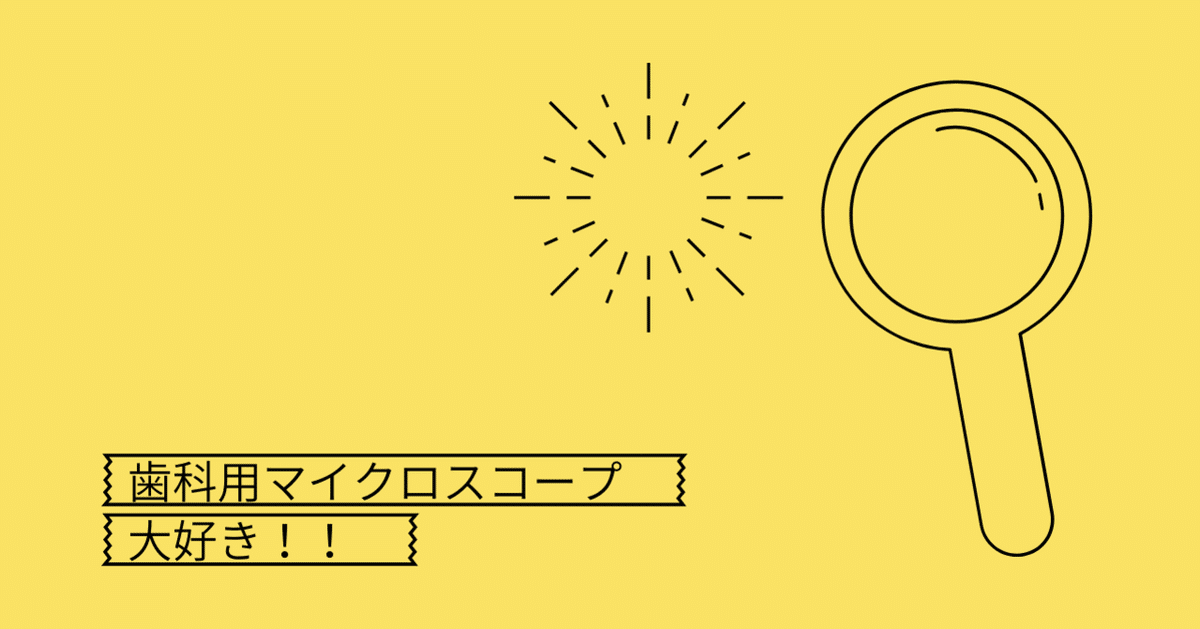
歯科用マイクロスコープ大好き!
今回は、私の大好きな歯科用マイクロスコープをご紹介いたします!クローバーデンタル院長の山岡です。

マイクロスコープとの出会い。
マイクロスコープとの出会いは、20年前になります。当時は、秋田大学歯学部附属病院歯科口腔外科に在籍していました。口腔外科は、親知らずの抜歯から口腔癌の治療まで、お口の外科治療を行う診療科です。歯科であっても、全身麻酔での手術をしますし、入院しながら術後の管理も行うので、医科全般の知識が必要です。
口腔癌の治療では、手術によって癌を切除することがあります。歯茎や舌だけじゃなく、顔の一部が手術範囲に含まれる場合もあります。手術で失った皮膚や粘膜は、再建手術といって、腕や胸などの皮膚などを切除部位に移植して、見た目や機能を補います。例えば、前腕皮弁といって、腕の内側の皮膚を移植する場合、皮膚だけじゃなく、血管を繋げて移植します。そうしないと血の巡りがない皮膚は、壊死してしまうからです。元々、腕にあった血管を首の血管とつなぎます。この際、細い血管を細い糸で縫い合わせるものですから、拡大視野での手術、いわゆるマイクロスコープを見ながらの手術になるのです。
上司である先輩の歯科医師が執刀するわけですが、医科のマイクロスコープは、手術助手も覗けるレンズが付いています。それを見ながら、水をかけたり、術者が集中できるように補助します。この時の光景(?)が目に焼き付いていて、すっかり拡大術野の施術にはまってしまったのです。
見えるようにするのがマイクロスコープ
このように私が興味を持ったマイクロスコープですが、20年前は、口腔外科以外の歯科治療でマイクロスコープを使用していることは、ごく稀でした。そこで、パイオニアと呼ばれる先生の元へ学びに行きました。「デンタルみつはし」の三橋純先生です。新潟大学の先輩ということもあって、特別なプライベートセミナーをしていただきました。(2008年10月)

三橋先生の教えの中で、特に印象的だったのは、「術野を常に見えるようにする大切さ」でした。それまでの私は、狭くて暗いお口の中ですから、見えないところがあるのは当たり前で、それを手指の感覚でカバーすると捉えていましたし、そう習ってきました。上の奥歯の裏側は、直接見ようとしても見えません。そこで「歯科用ミラー」という鏡を使うのですが、鏡を見ながら削るとなると、手の動きが逆になるので、なかなか繊細な動きが難しくなります。なので、確認の時にはミラーを使いますが、多くの作業は、感覚を頼りにしてしまいました。マイクロスコープ下で治療するのであれば、それは認められないのです。拡大して見るわけですから、見ながらできるのが当たり前。ミラーを見ながら、安全に治療する大切さを学びました。
というように、マイクロスコープと出会い、素晴らしい先生に教えていただくことで、マイクロスコープが大好きになりました。マイクロスコープとの出会いが、私の歯科人生を大きく変えることになったのです。続きは、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
