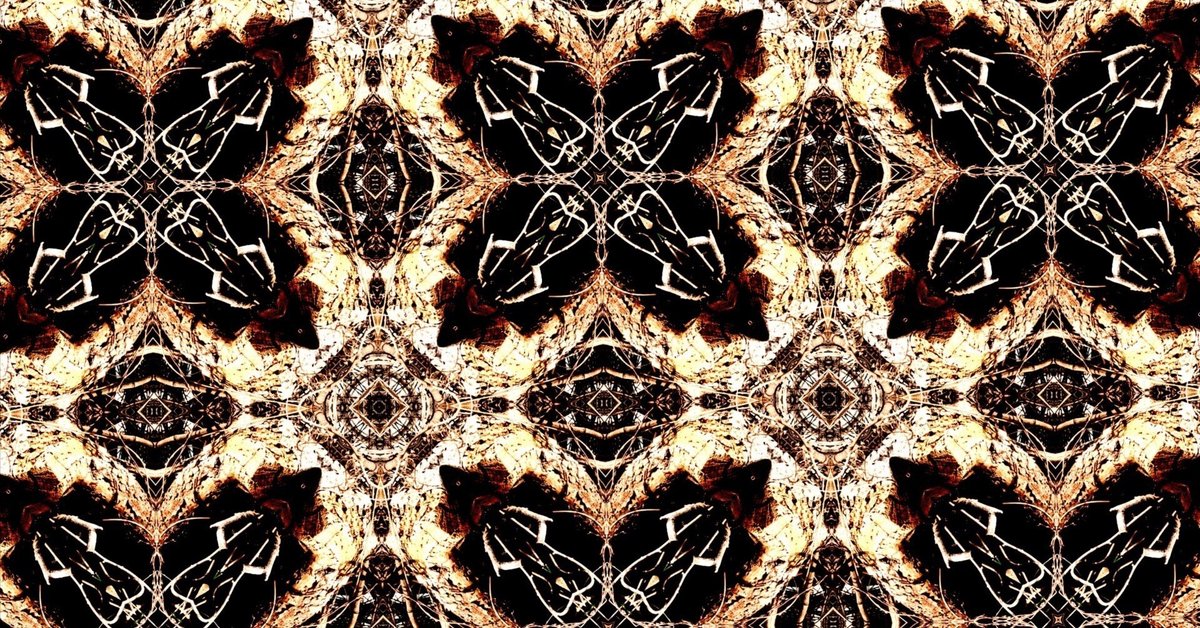
「オタク経済圏創世記」。モーツアルト、レンブラントの起業家精神に学ぶ
2019年11月に出版された「オタク経済圏創世記 GAFAの次は2.5次元コミュニティが世界の主役になる件」 (中山淳雄著)。この本は、プロレスの話から始まります。
プロレスのアメリカ展開を進めている新日本プロレスの親会社はカードゲーム・モバイルゲーム・アニメ・音楽のキャラクターコンテンツを展開するブシロード。キャラクターメーカーによるプロレス展開の物語には、日本企業の海外展開を成功に導く秘密が隠されています。
一般にオタク文化とは、コミック、アニメ、ゲーム、特撮、SF、フィギュアなど一群のサブカルチャーを指します。日本のVRアートも、一群のサブカルチャーと無縁ではありません。そして、表現スタイル以上に、オタク文化の歴史は、VRアートにとっても参考になります。
この本の第4章では、プラットフォームからコミュニティベースへの変化が強調されています。単一の大きなプラットフォームは力を失い、さまざまなプラットフォームが生まれて、ユーザーは次々に乗り換えていきます。
「人々は自分と親近性のある、「質の高いプラットフォ―ム」に次々に乗り換える。若者はツィッターからTikTokに乗り換え、高齢女性がフェイスブックからインスタグラムに乗り換えている。それらは自分と近い趣味・価値観コミュニティで固まろうとするオタク的価値観と同ーである。5G社会になったときにこの傾向はさらに加速するだろう。超高速の配信が、電気・ガス・水道のように安価・安定的につながって当然というインフラになったときに、ライブコンテンツは場所の制約から解き放たれる。コミュニティが群島のように連なり、オタク同士で集合霧散を繰り返しながら、複数のプラットフォ―ムを緩く行き来し続ける。そうなったときに注目すべきは、プラットフォームにこだわらず、コミュニティにこだわるということだろう」(p196)
プラットフォームからコミュニティへ。これは、インターネットの歴史、Web2からWeb3への方向性とも一致します。
第5章には、「後世に残る作品の共通点」という面白い文章があります。「モーツアルトの時代の音楽家、レンブラントの時代の画家は、パトロンのお抱え芸術家であった。それは現在でいう開発受託、Work For Hireのように、ただオーナーが求めるものを描き、求めるように演奏していた。モーツアルトやレンブラントなど一部の作品を除いて、その時代に秀作が出てきていない。その時代の「ハイ」カルチャーの人々の嗜好は常に保守化し、マンネリズムを生み出す。芸術は少数のお金の出し手のみで動いている限りは衰退していく」(p228-229)と、マンネリズムによる衰退の歴史を明らかにします。
そして、こう続けます。「実はレンブラントは画家としてだけではなく、美術品のバイヤー市場を確立し、多様な評価によって作品の自由さを取り戻そうと尽力する事業家であった。モーツアルトもまた音楽出版社に権利を売り、音楽レッスン料とコンサ―卜の入場料で生計をたてた起業家でもあった。後後世に残る作品をつくっているクリエイターは常にその時代のマンネリ化しがちな主流プラットフォ―ムを壊し、自由さを担保すべく新しいビジネスモデルを切り開く人間なのだ。日本のエンタメ業界、そしてその他の業界に求められているのは、こういう飽くなき情熱なのではないだろうか」(p-229)
レンブラントやモーツアルトの起業家精神は、自由な作品創造と矛盾しません。時代と向き合い、自由な作品創造を可能にするものとして、むしろ積極的に評価すべきです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
