
「アイヌ民族」と「アイヌの人々」①
4月から中学2年生になり、早くも2ヶ月が経とうとしている。平日は、学校から帰宅したら宿題や読みたい記事や本、観たい動画、メールの返信など、やることやりたいことが山ほどあり、あっという間に時間が過ぎる。
いつもはそんな感じでいいのだけれど、テスト前になるとそうはいかない。いろんなことを我慢して勉強をする時間を優先している。当たり前のことなのだろうが、ぼくにとってはなかなかきつい。しかも、こんな時に限って読みたかったものが届いたりする。テスト勉強します。
ぼくの学校の地理の教科書は帝国書院を使っている。
学校では先生が作ったパワーポイントとプリントで授業が進むので、教科書や問題集を使っての授業をあまりしない。
今回のテスト範囲が東北地方と北海道地方だったので、教科書と同じ会社の問題集を解き理解度を試す。
問題です!
【必須問題】
P173 ①
近年, (d)昔から北海道に暮らしてきた人々を, 先住民族と明記する法律も成立した。
(5)下線部dの人々を何というか【定期テスト 得点UP問題】
P174 ①
(8)北海道の先住民族を何というか。答えは出ましたか?
ぼくは、両方、「アイヌ民族」と回答しました。
回答は、両方、「アイヌの人々」です。
アイヌの人々(アイヌ民族) または、アイヌ民族(アイヌの人々)ではないので、
アイヌ民族の回答は、❌ です。
頭の中が 「?????????」となりました。
「民族」とは、文化を含む人の集まり
「人々」は、人の複数形
公益財団法人アイヌ民族文化財団 とアイヌ民族の方は自らアイヌ民族と書いている。
北海道放送も北海道の自治体のHPなどもアイヌ民族と書かれている。
なのになぜ、教科書や問題集は「アイヌの人々」なのか?

【教科書の内容】
アイヌの人々は、社会的地位の向上や民族としての名誉と尊厳の回復を求め、ねばり強く運動を続けました。
1997年、北海道旧土人保護法は廃止され、アイヌの文化振興法が新たに制定。この法律をきっかけにアイヌの人々が育んできた文化の伝承・再生を目指して、さまざまな取り組みが進められました。
2007年、国連総会で「先住民の権利に関する国際連合宣言」が採択。
2019年、国会でアイヌの人々を「先住民族」と明記する法律が成立。この法律では、アイヌの人々の誇りが尊重される地域社会づくりに対する、国からの財政的な支援も盛り込まれています。
法律が成立し先住民として認められている。
「誇り」「尊重」という言葉まで使い書かれているにも関わらず、なぜ、「アイヌ民族」の言葉を避けるのか?名誉と尊厳の回復を求め運動をされている方々は今もまだいるにも関わらず、なぜ、過去形になっているのか?ぼくには意味がわからない。
帝国書院に電話をして、「アイヌ民族」と表記せずに「アイヌの人々」と表記されていることに疑問を感じたことを伝え理由を聞いた。
帝国書院回答
中学校の地理の担当が、ただいま不在なので代わりに少し調べました。正確な、100%会社の意見ではないので恐縮なのですけども、弊社からアイヌ民族セミナー、協会さんが主催しているセミナーに毎年参加しておりまして、そちらの中で、アイヌ民族協会さんの方の中で、「アイヌ民族」という呼び方と「アイヌの人々」という呼び方、どちらの方が適しているのか弊社から質問させていただいた際に、「民族」というまとまりというよりは「人々」というように、日本の先住民族として所属していたというところで、民族として切り離さずに考えていただきたいというところで、「人々」という呼び方を推奨しているとご意見でいただいたことがございます。そちらで、地理の現代のアイヌの人々についての基準の際は、「人々」という風にしているというところかなと思うんです。
ぼくー「民族」という言葉は切り離しになるのですか?民族というのは、人々と文化を合わせているということですよね?
帝国書院回答
そうですね。確かにそれもおっしゃる通りですよね.....。ちょっと弊社の中で調べた中で、そういった回答だったので、ご担当のものが本日出社しないものでして、また後日お調べしてご回答という形でもよろしければ、お調べしたいと思うんですけども。弊社の上のものに確認して回答します。
帝国書院が毎年参加していると言っていたアイヌ民族セミナーを主催しているのは、内閣官房アイヌ総合政策室。セミナーの中で「アイヌ伝統舞踊の披露、伝統楽器の演奏」をされた公益財団法人アイヌ民族文化財団に電話。
中学校で使っている地理の教科書の北海道の勉強で、アイヌ民族について書かれているページでは、一度もアイヌ民族と表記せずにアイヌの人々と表記されていること。このことについて、教科書会社に問い合わせをしたところ、アイヌ民族セミナーに参加し、「アイヌ民族」と「アイヌの人々」の呼び方のどちらが適しているか質問をした際に、「民族」というまとまりよりは、日本の先住民族として所属していたということで、民族として切り離さずに考えて欲しいので、「人々」という呼び方を推奨していると回答をもらったとおっしゃっていました。教科書や問題集には「アイヌ民族」と一度も書かれていません。このことについて、アイヌ民族文化財団さんはどのようにお考えなのか、お聞かせいただければと思います。
アイヌ民族文化財団回答
本日、適切なご回答を差し上げられるものがおりませんので、アイヌ民族文化財団のホームページの問い合わせにご記入いただき、ご質問を投げていただければ適切な回答をできるものを入力して、ご返信差し上げる形になります。
ぼくー「アイヌ民族」と「アイヌの人々」の表記は別の意味だと考えて良いのでしょうか?
アイヌ民族文化財団回答
私の立場ではちょっとそちらについてお答えしかねますので、申し訳ありません。お問い合わせの方で、お願いいたします。
翌日、帝国書院の担当の方から回答をいただいた。
帝国書院回答
「アイヌ民族」ではなくて「アイヌの人々」という風に表記されている理由については、こちらでお調べいたしました。理由といたしましては、おそらくただいまお使いいただいている中学校の地理の教科書、こちらの教科書を作成段階においては *アイヌ施策推進法 という2019年に制定されたものが、まだ出ていない段階の時に編集していたものでございまして、そういったところで、まだ法律としてアイヌ民族の方々が日本の先住民族という風に法律で定められていなかった時期に編集したものでございまして、そういったところで、法律として制定されていない。それから教科書の学習内容を定めている指導要領ですね。学習指導要領の中で、「アイヌの人々」という風な表記がある。この2点から、私どもの教科書の方で「アイヌの人々」という風に表記させていただいております。
(*アイヌ施策推進法・・・アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の通称。施行と同時に1997年に制定されたアイヌ文化振興法が廃止)
ぼくー編集をしたのが2019年以前。だから教科書認定が2020年3月24日になっているということですか?
帝国書院回答ーはい。おっしゃる通りでございます。
ぼくー次の編集をいつするかわかりますか?
帝国書院回答ー私どものホームページに記載はしてるんですけれども。令和7年度版の教科書をちょうど今年ご案内しているところでございます。来年の4月から使われるものですね。改訂版ということになりますので、こちらの方ではアイヌ施策推進法を盛り込んだ内容になっていると思います。
ぼくー令和7年度版には「アイヌ民族」と表記しているという認識でいいですか?
帝国書院回答ーはい。そちらの認識で構わないと思います。
ぼくー2019年の今使っている教科書に「アイヌの人々」と表記しているけれども、《法律が制定され「アイヌ民族」と表記が変わりました》など、学校や生徒にお知らせする。そういうことはされましたか?
帝国書院回答ーそちらに関しましては、そうですね。なんと言いますか、来年度から教科書の内容として「アイヌ民族」という風に表記させていただくという内容、文科省に検定の方に出して、そちらが合格した後でないと直すという風に明言ができない状況になっておりまして。
ぼくー2019年以前の、この教科書の2020年3月24日の教科書検定では、「アイヌ民族」ではなく「アイヌの人々」と表記してくださいという教科書認定基準になっていたのですか?
帝国書院回答ーこういう風に表記してくださいという指定はないんですけれども、文科省が出していらっしゃる学習指導要領というものですね。指導要領の中で、「アイヌの人々」という風な、指導要領の中でそういった呼ばれ方をしていたので、そちらに倣ったというところが1番簡単なご説明の仕方かなと思うんです。
ぼくー2007年に国連の採択で「先住民の権利に関する国際連合宣言(先住民族の権利に関する宣言)が採択され、国際的に民族として認められているんですけれども、その点に関しては?
帝国書院回答ーそうですね。おっしゃる通り、国際連合の方では成立がしていると思うんですけど、国内で、あくまでも日本国内のお話として、日本政府の方で出された法律としてアイヌ民族が日本の先住民族だとして定められたのが、2019年が初めてでしたので、日本国内のお話ですね。ですので、そちらのものに合わせたというところでございます。
ぼくー国連の採択よりも、日本の現行法を優先したという認識ですね。
帝国書院回答ーそうですね...。はい。
ぼくー教科書に書いてある、《2019年に日本の国会でアイヌの人々を先住民と明記する法律が成立しました。》というのは、編集をし終わった後にできたから書いたということですか?
帝国書院回答ーはい。おっしゃる通りでございます。全ての「アイヌの人々」の記述を「民族」とするには、教科書の内容を変える際には、文部科学省の方に訂正の申請を毎回行わなければならないので、そうしますと膨大な量になってしまうということもありまして、とりあえずこちらの教科書ではそちらの文言を追加させていただいた上で、「アイヌの人々」という表記を継続させていただいたというところでございます。
こちら変えるとなると歴史ですとか公民ですとか、全ての教科でといことになりますので。
ぼくー子どもたちが「アイヌの人々」と学校で習い覚えることになるので、お知らせしないのは変だと思うんですよね。
帝国書院回答ーまあ。そうですね。そちらもおっしゃる通りだと思います。
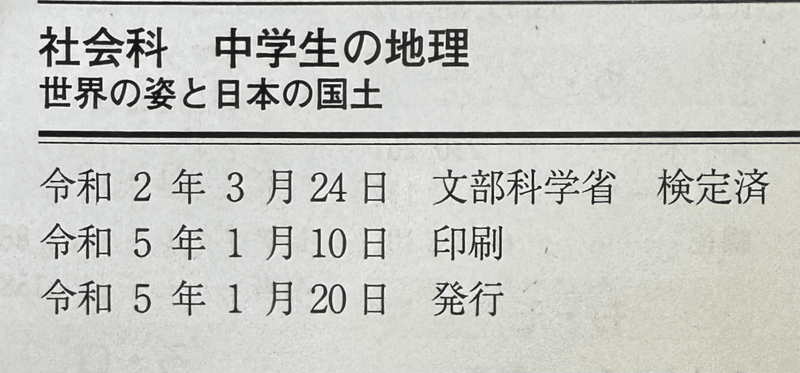
中間テストが終わった。
帝国書院の回答が腑に落ちない。
他の会社の教科書も見たいと思ったので図書館へ行く。
6月7日(金)に「アイヌ民族」と「アイヌの人々」②を、noteにアップします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
