2023年5月3日憲法記念日れいわ新撰組代表談話と旧民主党政権の避妊、不妊手術および人工妊娠中絶に関して規定し、性と生殖に関する健康を守る教育に関する法律(案)の良さから立民への政権交代がありと思えた件。
2023年5月3日憲法記念日。旧民主党政権の避妊、不妊手術および人工妊娠中絶に関して規定し、性と生殖に関する健康を守る教育に関する法律(案)の良さから立民への政権交代がありと思えた件。
旧敵国条項
— umekichi (@umekichkun) May 1, 2023
山本太郎「安保理抜きで日本を攻撃しても許され国際法違反にならない」
外務省「既に死文化してる」
山本太郎「死文化してない。それを棚上げし国民に知らせず軍備拡大30年の不況にコロナ物価高でも人々は救わず国家の私物化。経済を立て直す事が最強の安全保障」
本当の事を言っちゃった pic.twitter.com/0TXkJFg1Lf

umekichi
@umekichkun
旧敵国条項
山本太郎「安保理抜きで日本を攻撃しても許され国際法違反にならない」
外務省「既に死文化してる」
山本太郎「死文化してない。それを棚上げし国民に知らせず軍備拡大30年の不況にコロナ物価高でも人々は救わず国家の私物化。経済を立て直す事が最強の安全保障」
本当の事を言っちゃった
午後10:22 · 2023年5月1日
https://www.jicl.jp/_src/950614/k-LawJournal27_ito.pdf?v=1672978997056
http://www.seihokyo.jp/seimei/2022/20221115-6dantai.pdf
「この声が政府に届いていないのでしょうか?!」
— tokurin🐾@京都1区 (@JiTokurin) May 1, 2023
↑
マイクを握った女性の切実な様子がコチラにもグサグサ突き刺さってきて、本当にいたたまれません😢
それを聞いてる太郎さんの表情を見てるだけでコッチも辛くなってきます。#インボイス制度反対
pic.twitter.com/FeImR11QBU
2022年4月に、参議院への鞍替え挑戦を表明した際の記者会見での山本太郎代表の「予言」。
— tokurin🐾@京都1区 (@JiTokurin) May 2, 2023
この一年間の政治の、国会の流れに注視すれば、彼の言葉の持つ重みを感じ取れると思います。
今こそ一票のチカラで変えていくときがやって来ているのです
pic.twitter.com/YhoMIXE3X4

楽楽
@yukiyuta69
れいわ新選組
山本太郎の予言
ビッタリと当たっている
・国政選挙の無い3年間与党の暴走
・与党が伸び野党は伸びない
・与党にすり寄る維新や国民民主などが出てくる
・戦争に巻き込まれあるいは日本が戦地となる当事国となり得る
#高市早苗さんを総理大臣にせず国会議員辞職
#山本太郎を総理大臣に
午前10:53 · 2023年5月2日
れいわ新選組の政策おいときます@reiwashinsen pic.twitter.com/Yh1Y1JMzvV
— プリティオオマエール博士(国際政治学者・消費税廃止、一律給付金支給を🎵) (@ohmaeyell33355w) May 1, 2023



田原総一朗「『角栄ブーム』の陰にあるハト派政治家への渇望」 ギロン堂 田原総一朗 2016/05/31 07:00 田原総一朗 筆者:田原総一朗

田原総一朗「『角栄ブーム』の陰にあるハト派政治家への渇望」 ギロン堂 田原総一朗 2016/05/31 07:00 田原総一朗 筆者:田原総一朗
数多くの“田中角栄本”が書店に並び、「角栄ブーム」が起きている。ジャーナリストの田原総一朗氏は、護憲派政治家への渇望があるのではと分析する。
* * *
いま、どの書店にも田中角栄について書かれた本がやたらに目につく。「角栄ブーム」なのである。
一つには、田中が他の政治家にない、どでかい構想力を持っていたことが見直されているのだ。
田中は、1960年代の末に『都市政策大綱』という本をまとめた。
その前文で、「都市の主人は工業や機械ではなくて、人間そのものである」とうたった。そして「この都市政策は日本列島全体を改造して、高能率で均衡のとれた、一つの広域都市圏に発展させる」と述べていた。
日本列島を一つの広域都市圏にする。そのためには、北海道から九州まで、どこからどこへでも日帰りで往復できなくてはならない(当時は、沖縄は返還されていなかった)。そこで田中は、「1日生活圏」「1日経済圏」という言葉を提唱した。
当時、東京や名古屋、大阪など、太平洋側の大都市の過密と、日本海側や内陸部の過疎が深刻な問題となっていた。そこで田中は、日本列島の大構造改革をしようとしたのだ。
田中は日本列島を一つの広域都市圏にして、さきの条件が達成できれば、第2次、第3次産業を全国に配置することができ、日本海側や内陸部の過疎化に歯止めがかかると考えたのである。
そのためには北海道から九州まで、それも太平洋側にも日本海側にも新幹線を通し、全国に高速道路を張り巡らせる。そして、第2、第3の国際空港と各地の地方空港を建設し、北海道、本州、四国、九州の四つの島をトンネルか橋で結ぶ。まさに現在の日本の構造を、40年以上前に構想していたのである。
また、田中は建物の高さを制限するのではなく、低さを制限して高層化を図り、容積率を高めることを提案した。このほか、4メートルだった道路幅の最低基準を2倍に広げるなど、具体的な対策を数多く打ち出した。
田中は30本以上の法律を、いわゆる議員立法としてつくり上げているが、このような政治家は彼以前にも、以後にもいない。もちろん、田中が首相になって、まず行ったのは日中国交正常化であり、それまでの首相たちが台湾に向けていた視野を大きく切り替えたことはあらためて記すまでもないだろう。
だが意外に知られていないのは、田中がいわゆる護憲派で、憲法改正に強く反対しており、これこそが「角福戦争」、つまり福田赳夫との対立点だったことである。
田中はノモンハン事件に一兵卒としてかり出され、あやうく生命を失いそうな体験をした。それで、戦争というのはバカげたことで二度とやってはいけないと、私にも強い語調で語ったことがある。
若い世代のために記しておくが、自民党には判然と2本の異なる流れがあった。田中、大平正芳、宮沢喜一、加藤紘一とつながるのは護憲のハト派であり、岸信介、福田赳夫、小泉純一郎、さらに安倍晋三へつながるのは改憲、タカ派である。
ハト派が主流の場合はタカ派が反主流派、タカ派が主流の場合はハト派が反主流派となって、その意味では自民党はいつの時代もバランスがとれていた。ところが、小選挙区制のためもあって、いまや、タカ派の安倍主流派に対して反主流派も非主流派もいなくなってしまった。
いま田中角栄がウケるのは、少なからぬ国民がなんとかしてハト派の手がかりをつかみたいと願っているのではないか。
※週刊朝日 2016年6月3日号
田原総一朗
田原総一朗(たはら・そういちろう)/1934年、滋賀県生まれ。60年、早稲田大学卒業後、岩波映画製作所に入社。64年、東京12チャンネル(現テレビ東京)に開局とともに入社。77年にフリーに。テレビ朝日系『朝まで生テレビ!』『サンデープロジェクト』でテレビジャーナリズムの新しい地平を拓く。98年、戦後の放送ジャーナリスト1人を選ぶ城戸又一賞を受賞。早稲田大学特命教授を歴任する(2017年3月まで)。 現在、「大隈塾」塾頭を務める。『朝まで生テレビ!』(テレビ朝日系)、『激論!クロスファイア』(BS朝日)の司会をはじめ、テレビ・ラジオの出演多数
このコラムニストの記事をすべて見る
田原総一朗「『角栄ブーム』の陰にあるハト派政治家への渇望」
ギロン堂
田原総一朗
2016/05/31 07:00
筆者:田原総一朗
過去最多のペースで憲法審査会が開催され、
与党だけでなく野党も前のめりで更なる開催を求め続けている。
目的は間違いなく、憲法改正の発議のためだ。
憲法審査会を開くな、とは言わない。
ただし、開く内容や方向性に問題なければ、の話である。
そもそも、憲法審査会の役割を確認しよう。
参議院憲法審査会規程によれば、憲法審査会には二つの役割がある。
一つ目は
「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調査」
二つ目は
「憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等の審査」
簡単にいうと、
「一つ目」は
現行憲法に沿った政策立案や行政が行われているかをチェックし、
政府に改善を求めるなど。
「二つ目」は
憲法改正に向けての議論、手続きなど。
現在の憲法審査会が向かう方向は、
「二つ目」である。
改憲項目に関する合意点を探ることや、
改憲に向けた手続きの議論が今後、加速していくだろう。
現在の憲法審査会は、
「一つ目」の役割をほとんど果たせていない。
現実を見れば、
日本国憲法に定められた国民の権利をないがしろにするような、
政治・行政が溢れている。
憲法25条には、
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
とある。
一方で、日本では、子どもの7人に1人が貧困。
コロナの前、2019年の大規模調査でも
生活が苦しい世帯は54%以上。
母子世帯では86%以上。
ここにコロナと物価高が合わさっているのが現在である。
健康で文化的、最低限度の生活さえも叶わない社会。
憲法25条が何十年にも渡り反故にされ続けている。
憲法13条では、
「すべて国民は,個人として尊重される」とある。
老老介護がなぜ増え続ける?
厚労省調査では、
「70~79歳」の要介護者等では、
「70~79歳」の者が介護している割合が56.0%。
介護離職・介護殺人がなぜ減らない?
なぜ介護従事者の給与が全産業平均で100万円低い?
子ども時代を犠牲にしながら生活を送る
ヤングケアラーがなぜ社会問題に?
行政による責任放棄。
自助・共助が当たり前とされ、
果たすべき公助はコストと削られ続けている。
一人ひとりが個人として尊重され幸福を追求する社会になっていない。
憲法13条違反。
憲法15条2項には、
「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」
とある。
ここにいう公務員には国会議員も含まれる。
資本家からの政治献金や組織票欲しさに政策を売り飛ばす政治により、
税金の取り方を歪めた。
大企業や金持ちを優遇し、減税。
一方で庶民には逆進性の強い消費税を導入し、
不況の中でも増税をコンスタントに行なった。
他にも労働環境を破壊し、不安定で賃金の安い労動者を増やした。
それにより資本家は過去最高益を手にいれた。
多くの人々は社会保険料など負担だけ増え、貧しくなった。
資本家優位の社会を拡大する政策を推し進め、
一人ひとりの購買力を弱め、需要は落ち込んだ。
製造業は需要が旺盛な海外に逃げ出し、国内はさらに疲弊。
30年、所得が下がり続け、
30年、国が衰退し続けるのは、
先進国の中で日本だけである。
世界トップレベルだった国を、政治と資本家が
30年食い潰し、日本はアジアの没落国家となった。
政治が数十年に渡って、
一部の奉仕者として仕事をし、国を壊した。
憲法15条違反である。
このような状況にあっても、
憲法改正の布石として憲法審査会の開催を重ねようと腐心する者は、
現状が見えていないか、現実から目を逸せるために汗をかこうとする輩ではないか。
憲法審査会を開くな、とは言わない。
日本にはびこる数々の違憲状態、
憲法に定められた国民の権利を無視した政策をチェックし改善するための議論に集中するなら、週に何回開催しても足りない。
残念ながら、それは叶わない。
コンスタントに憲法審査会を開こうとする多数派の思惑は、
憲法改正へと進めるための動きでしかない。
審査会の開催回数をかせぎ、
「十分に議論を尽くした」と憲法改正の発議に繋げようと考えているのは明らかだ。
彼らが求める本丸は、憲法改正による緊急事態条項である。
簡単にいえば、内閣だけで全てのルールを決めることが可能になるのだ。
30年以上、日本という国を破壊してきた者に、
究極のフリーハンドを与えることは自殺行為と断言できる。
国民を守るため、と口で言いながら、自助共助を求め、
自己責任という魔法の言葉で公助を放棄する一方で、
お得意様には忖度を続け、
国を衰退、社会の底を抜けさせた輩たちに憲法を変えさせてはならない。
第12条には、
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」
とある。
国家権力の暴走を止める鎖である最高法規、
憲法を最高権力者である国民が今、間抜けな為政者たちから守る局面に来ている。
内政の崩壊から目をそらせるため、
そして絶対的な権力を手に入れるための憲法改正とは、
面の皮が厚すぎる。
今ある憲法を守れ。話はそれからだ。
れいわ新選組は改憲より経済。
30年に渡る不況に、
コロナ、物価高で苦しむ日本社会を、
徹底した積極財政で立て直し、
物作り大国日本の再興と
人間の尊厳を守れる社会の再構築を目指す。
2023年5月3日
れいわ新選組代表 山本太郎
【代表談話】憲法記念日(2023年5月3日 れいわ新選組代表 山本太郎)
投稿日: 2023年5月3日

「あらたな戦前にさせない」憲法記念日の5月3日に護憲派が集会 東京・有明で 2023年4月27日 17時53分
岸田政権が敵基地攻撃能力(反撃能力)保有など専守防衛を形骸化させる安全保障政策の大転換を進める中、護憲派グループは27日、憲法記念日の5月3日午後1時から、「あらたな戦前にさせない!守ろう平和といのちとくらし 2023憲法大集会」を、東京都江東区の有明防災公園で開くと発表した。
室蘭工業大の清末きよすえ愛砂あいさ教授(憲法学)や沖縄大地域研究所の泉川友樹特別研究員らのスピーチの他、外国人の人権擁護に取り組む「移住者と連帯する全国ネットワーク」の山岸素子事務局長、馬毛島(鹿児島県)に米軍機の訓練場となる自衛隊基地を建設する計画に反対する「馬毛島への米軍施設に反対する市民・団体連絡会」の前園美子副会長らのリレートークを行う予定。
集会前の午前11時からは、集会登壇者とのトークイベントや、音楽ライブなどもある。主催の実行委員会は「軍拡はおかしいと声を上げ、憲法9条をないがしろにし、戦争に突き進む政治をストップさせよう」と参加を呼びかけている。
問い合わせは、実行委構成団体の一つ「戦争をさせない1000人委員会」=電03(3526)2920=へ。(加藤益丈)
【関連記事】殺傷武器輸出、解禁を議論 自民、公明が非公開の場で進める「平和主義」の分かれ道
「あらたな戦前にさせない」憲法記念日の5月3日に護憲派が集会 東京・有明で 2023年4月27日 17時53分

殺傷武器輸出、解禁を議論 自民、公明が非公開の場で進める「平和主義」の分かれ道 2023年4月26日 06時00分
自民、公明両党は25日、防衛装備品の輸出ルールを定めた「防衛装備移転三原則」の見直しに向けた与党協議を始めた。ウクライナ支援や中国による台湾侵攻を念頭に、殺傷能力のある武器の輸出解禁に踏み切るかが焦点で、自民は前向きだが、公明は慎重だ。解禁なら敵基地攻撃能力(反撃能力)保有に続く安保政策の大転換となる。市民団体は「憲法9条で国際紛争に加担しないようにしてきたのに、他国に武器を輸出して日本が『殺す側の国』に変わっていいのか」と警鐘を鳴らす。(川田篤志)
防衛装備移転三原則 2014年4月に当時の安倍政権が決定した防衛装備品の輸出ルール。国際共同開発や輸出拡大に向け、従来の禁輸政策を撤廃した。輸出や供与の条件を国際協力や日本の安全保障に資することとし、国連安全保障理事会決議に違反する場合などは禁じた。運用指針では、殺傷能力を持つ武器の輸出を共同開発・生産をする国に限定。殺傷能力がない装備は、救難、輸送、警戒、監視、掃海の計5分野で認めている。
◆戦車やミサイルの輸出を解禁するか
自民の小野寺五典安全保障調査会長は国会内で開かれた初会合で「防衛装備移転の論点について、具体的な方向性を出せるよう議論したい」と強調。公明党の佐藤茂樹外交安保調査会長は「戦後の平和国家としての歩みを堅持しつつ、厳しさが増す安全保障環境の中で、望ましい制度の在り方を議論したい」と述べた。
会合では両党議員や政府関係者が三原則の歴史的経緯などについて意見交換した。主な論点は(1)非殺傷の装備品のうち輸出可能なものを「救難」「輸送」などの5類型から拡大するか(2)日本と武器を共同開発した国が第三国へ輸出する手続きを明確化して認めるか(3)戦車やミサイルなど殺傷能力のある武器の輸出を容認するか—の3点だ。
特に問題となるのは、現在は三原則の運用指針で原則認められていない殺傷能力のある武器の輸出解禁。日本は憲法の平和主義に基づき、1960〜70年代に「武器輸出三原則」を確立し、全面禁輸措置を採用してきた。第2次安倍政権は2014年、「防衛装備移転三原則」に変更して一部認めたが、政府・自民党内では殺傷能力のある武器を含め、規制緩和を求める声が強まっている。
ウクライナのような国への支援や国内の防衛産業の振興のため、岸田政権は昨年末に改定した国家安全保障戦略で、装備品輸出を友好国との防衛協力強化に向けた「重要な手段」と位置付け、三原則の見直しを「検討する」と明記。この方針を受け、与党は今回の協議に着手した。
市民団体「武器取引反対ネットワーク」の杉原浩司代表は取材に、殺傷力のある武器の輸出を解禁すれば「平和国家のイメージが崩れ、他国の信頼を失う」と指摘。紛争地での日本の非政府組織(NGO)の活動に支障が出るなど実害が出ると危ぶむ。
【関連記事】「殺傷能力ある武器輸出を」政府・自民に高まる解禁論 ゆらぐ禁輸三原則 識者「平和国家像の支え失う」
◆自民はなぜ武器を積極的に輸出したいのか
自民、公明両党が25日に始めた防衛装備品の輸出ルール「防衛装備移転3原則」の見直しに向けた与党協議では、自民党が前向きな殺傷能力のある武器の輸出解禁が最大の論点になる。敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に続く「力には力」の論理がちらつき、慎重な公明党の対応がカギを握る。(市川千晴、佐藤裕介)
自民党の与党協議メンバーの一人は会合後、記者団に「公明党の皆さんに言いたいが、韓国ですら毎年2兆円も武器を輸出している」と強調した。
自民党が目指すのは、ウクライナへの支援拡大の必要性を名目に「救難、輸送、警戒、監視および掃海」の5分野に限定している類型の拡大と、ミサイルや戦車など殺傷能力のある武器の輸出解禁だ。
理由の一つに挙げるのが、国内の防衛産業の維持。販路がほぼ自衛隊に限られ、防衛分野から撤退した国内企業は2003年以降で100社以上とされ、自民若手は「海外輸出の本格解禁が不可欠だ」と訴える。
海洋進出を強める中国に、装備品輸出でも「力には力」で対抗すべきだとの主張もある。自民中堅議員は「対中国を踏まえれば、ウクライナ以外の同志国にも、ちゃんと輸出できるようにしなければいけない」と指摘。東南アジアの民主主義国などへの提供を念頭に、輸出できる装備品の範囲を広げる必要性を唱える。
◆「平和の党」を自任する公明は
公明党は、三原則を見直すことに全面的には反対していない。非殺傷能力の分野で、地雷除去や教育訓練などに拡大することは容認できるとの立場。政府が英国、イタリアと3カ国で共同開発する次期戦闘機の第三国への輸出の手続きも「現実に即した対応に変えなければ」(党幹部)と柔軟な構えをみせる。
問題は、殺傷能力のある武器の輸出解禁。一貫して慎重な姿勢を見せ、山口那津男代表は25日も記者団に「公明党の見方だが、短時間で結論を出すのはかなり困難だ」とけん制した。過去には反対していた集団的自衛権の行使を一転して認めたこともあり、自任する「平和の党」の真価が試される。
国会など公の場でなく、与党協議という非公開の形式で議論が進んでいくことの妥当性も問われる。決定した大枠が、そのまま政府方針になる可能性が高いからだ。
日本は憲法に基づく平和主義のもと、日本の武器によって「国際紛争を助長しない」との大方針を継承してきた。殺傷能力のある武器輸出を認めれば大転換で、日本の武器が海外で使われ、紛争を拡大・助長することにもなりかねない。
日本経済新聞社の2月の世論調査では、ウクライナに「武器を提供する必要はない」との回答が76%に上った。重大な政策決定には、国民への重い説明責任が伴うのは言うまでもない。
殺傷武器輸出、解禁を議論 自民、公明が非公開の場で進める「平和主義」の分かれ道 2023年4月26日 06時00分

「殺傷能力ある武器輸出を」政府・自民に高まる解禁論 ゆらぐ禁輸三原則 識者「平和国家像の支え失う」 2023年2月23日 06時00分
ロシアによるウクライナ侵攻から1年を迎え、政府・自民党内ではウクライナ支援や友好国との関係強化を旗印に、殺傷能力のある武器の輸出解禁を目指す声が高まっている。安倍政権が「武器輸出三原則」の禁輸政策を転換し、輸出を認めた「防衛装備移転三原則」の運用指針の規制緩和を検討する。殺傷能力を持つ武器輸出を認めれば、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に続く安保関連政策の大転換となり、識者は「平和国家像の支えを失い、東アジアの軍拡につながる」と危ぶむ。(川田篤志)
◆不満を漏らす自民党議員
「不法な侵略を受けるウクライナの防衛目的でも、現行では殺傷力のある装備品を移転(輸出)できない。殺傷性ではなく、安保上、日本と関係を深めていく国かで考えては」。自民党の熊田裕通氏は今月の衆院予算委員会で、欧米が戦車や弾薬を供与する中、日本は防弾チョッキや民生車両などの支援にとどまる現状に不満を漏らした。
浜田靖一防衛相は「装備移転は日本にとって望ましい安保環境の創出や、国際法違反の侵略などを受けている国への支援のため重要な政策手段だ」と答弁。原則として殺傷能力のある武器輸出を認めていない運用指針の変更に前向きな姿勢を示した。
岸田首相
岸田政権は昨年12月に閣議決定した国家安全保障戦略で、装備品輸出は防衛協力の「重要な手段」と位置付けた。殺傷能力のある武器の輸出解禁の圧力は「ウクライナ支援」を名目に自民党内で強まっており、有志議員は21日、国内の防衛産業強化や防衛装備品の輸出拡大を目指す議員連盟を設立し、国会内で初の総会を開いた。
◆国内防衛産業の収益強化ねらう
政府・自民党にはウクライナへの軍事支援で欧米各国と足並みをそろえたい思惑がある。対中国を念頭に東南アジアへ武器輸出して安保協力を強化し、国内防衛産業の収益強化につなげる狙いもある。
一方、「平和の党」を掲げる公明党は、統一地方選挙への影響を懸念し、大幅な規制緩和に慎重姿勢を示す。政府・与党は4月以降に運用指針の見直しの議論を本格化させる構えだ。
武器輸出を巡っては、政府は1960〜70年代以降、憲法9条の平和主義に基づき、国際紛争を助長しないとの理念のもと、武器輸出三原則で事実上の禁輸政策を続けてきた。
安倍政権では2014年、全面禁輸を見直して「防衛装備移転三原則」として国際平和への貢献や日本の安全保障に資する場合、紛争当事国などを除き輸出を解禁。ただ、運用指針で、共同開発国を除き、戦車や戦闘機などの武器の輸出は認めてこなかった。
学習院大の青井未帆教授(憲法学)は、殺傷力のある武器の輸出を解禁すれば「紛争を助長せず、武器で利益を得る国ではないことで保っていた平和国家像が崩れてしまう」と指摘。「武器を送ることだけがウクライナ支援ではない。国家像を180度転換し、軍事力を背景に外交をする国になるのか、国会も含め国民的議論が必要だ」と語る。
【関連記事】武器輸出ルール「防衛装備移転三原則」の緩和を提言へ 自民党安全保障調査会
「殺傷能力ある武器輸出を」政府・自民に高まる解禁論 ゆらぐ禁輸三原則 識者「平和国家像の支え失う」 2023年2月23日 06時00分




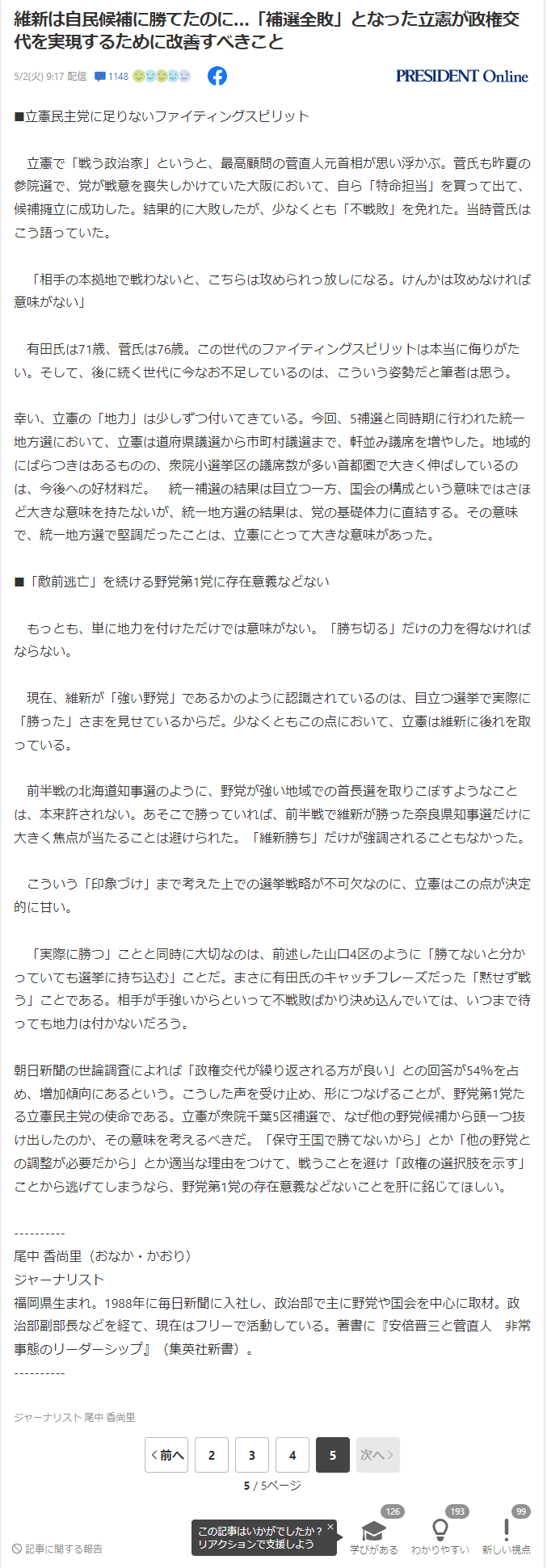
■故安倍元首相の選挙区に立憲が候補を擁立 こう書くと話はそこで終わってしまうのだが、そんななかで筆者が強く印象に残った補選がある。立憲が最も大きく負けた山口4区だ。 亡くなった安倍晋三元首相の選挙区。もともと全国屈指の厚い保守地盤を誇り、さらに安倍氏の非業の死によって、自民党は「弔い合戦」と位置付けていた。誰もが「圧勝」を疑うことのない、事実上の無風区のはずだった。 ところが、立憲が元参院議員でジャーナリストの有田芳生氏を擁立したことで、空気が変わる。 有田氏の出馬表明は、告示まで1カ月を切った3月15日。出遅れは明らかだったが、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題や北朝鮮による拉致問題に取り組んできた有田氏は、出馬表明会見で「新しい政治を作るため、安倍氏の政治を検証しなければならない」と訴えた。 いくら知名度があるからといって、筆者も失礼ながら、有田氏に勝機があるとは考えていなかった。それでも、有田氏が立候補すれば、昨年の臨時国会における被害者救済法案の成立以降、永田町でも存在が薄れかけていた旧統一教会問題に再び光が当たるだろう。そのことにはきっと意味がある。 山口4区について筆者が事前に考えていたのは、そんなことだった。しかし、選挙戦最終日の有田氏の街頭演説を聴き、そんな考えの浅はかさを思い知らされた。 ■保守王国で立憲は「不戦敗」を重ねてきた 「ここで闘っていく立憲民主党の仲間。それを支えてくれている皆さんたち。山口を切り開いていくための橋頭堡(ほ)、基盤、土台が(この補選で)できたと確信している。私がこの選挙区に立とうと思ったのは、それが目的だ」 改めて最後に語られた出馬の理由。12日間の選挙戦を走り抜いた後だからこその説得力があった。 思えばこの選挙区で、いや「自民党の岩盤」「保守王国」などと呼ばれてきた多くの選挙区で、野党第1党は旧民主党から立憲に至るまで、戦うことを「捨てて」しまうことが少なくなかった。候補擁立を諦めたり、「野党共闘」の名の下に他党の候補の陰に隠れたり……。最近では「維新王国」と化した大阪でも、同様の傾向がみられる。 自らの手で「岩盤」をうがつための努力を怠ってきた、と言われても仕方がない。
■結果は自民候補がダブルスコアで勝利だったが… しかし、公示段階でまだ安倍氏が存命だった昨年夏の参院選で、立憲は安倍氏の秘書だった秋山賢治氏を擁立し「安倍王国」に挑んだ。敗れはしたものの、秋山氏はその後、今年2月の下関市議選に初当選。こうした動きの積み重ねのなかで、今回、有田氏を迎え入れる土壌ができていたのかもしれない。 選挙戦で有田氏は、積極的に選挙区を回り、市井の人々の声に耳を傾けるとともに「山口の皆さんの生活は本当に豊かになったのか」「立憲民主党が目指す『支え合う社会』が必要だ」と訴えた。「よく選挙に出てくれた」「ありがとうございました」。陣営にはそんな声が多く届いたという。 選挙結果は、安倍氏の後継候補である自民党の新人、吉田真次氏が5万1961票で大勝。有田氏は2万5595票と、ほぼダブルスコアでの敗退だった。 ■安倍元首相の存命時と比べ着実に差は縮まった しかし、自民党の吉田陣営は、安倍氏が2021年衆院選で獲得した約8万票を目標にしていたにもかかわらず、投票率の大幅な低下も相まって、約3万票も得票を激減させた。実際の勝敗は勝敗として、自民党もさすがに、こういう結果を手放しで「大勝利」とは呼べないだろう。 有田氏は敗戦の弁で「保守王国と言われてきた山口4区において、それが溶け始めてきている、と確信を持っている」と語った。 有田氏が選挙戦で、旧統一教会問題に焦点を当てようとしたのは間違いない。だが、それ以上に伝えたかったのは「戦わなければ状況を打開できない」ということではないだろうか。 選挙は戦いだ。正しいことを気持ち良く訴えていれば、いつか有権者に振り向いてもらえるなんて考えは甘い。政権とは「戦って勝ち取るもの」であり、勝ち取った後こそが本当の勝負なのだ。 有田氏は自らの選挙戦を通じて、同党の特に若い世代に対し、体を張ってそのことを伝えようとしたのだと思う。
■立憲民主党に足りないファイティングスピリット 立憲で「戦う政治家」というと、最高顧問の菅直人元首相が思い浮かぶ。菅氏も昨夏の参院選で、党が戦意を喪失しかけていた大阪において、自ら「特命担当」を買って出て、候補擁立に成功した。結果的に大敗したが、少なくとも「不戦敗」を免れた。当時菅氏はこう語っていた。 「相手の本拠地で戦わないと、こちらは攻められっ放しになる。けんかは攻めなければ意味がない」 有田氏は71歳、菅氏は76歳。この世代のファイティングスピリットは本当に侮りがたい。そして、後に続く世代に今なお不足しているのは、こういう姿勢だと筆者は思う。 幸い、立憲の「地力」は少しずつ付いてきている。今回、5補選と同時期に行われた統一地方選において、立憲は道府県議選から市町村議選まで、軒並み議席を増やした。地域的にばらつきはあるものの、衆院小選挙区の議席数が多い首都圏で大きく伸ばしているのは、今後への好材料だ。 統一補選の結果は目立つ一方、国会の構成という意味ではさほど大きな意味を持たないが、統一地方選の結果は、党の基礎体力に直結する。その意味で、統一地方選で堅調だったことは、立憲にとって大きな意味があった。 ■「敵前逃亡」を続ける野党第1党に存在意義などない もっとも、単に地力を付けただけでは意味がない。「勝ち切る」だけの力を得なければならない。 現在、維新が「強い野党」であるかのように認識されているのは、目立つ選挙で実際に「勝った」さまを見せているからだ。少なくともこの点において、立憲は維新に後れを取っている。 前半戦の北海道知事選のように、野党が強い地域での首長選を取りこぼすようなことは、本来許されない。あそこで勝っていれば、前半戦で維新が勝った奈良県知事選だけに大きく焦点が当たることは避けられた。「維新勝ち」だけが強調されることもなかった。 こういう「印象づけ」まで考えた上での選挙戦略が不可欠なのに、立憲はこの点が決定的に甘い。 「実際に勝つ」ことと同時に大切なのは、前述した山口4区のように「勝てないと分かっていても選挙に持ち込む」ことだ。まさに有田氏のキャッチフレーズだった「黙せず戦う」ことである。相手が手強いからといって不戦敗ばかり決め込んでいては、いつまで待っても地力は付かないだろう。 朝日新聞の世論調査によれば「政権交代が繰り返される方が良い」との回答が54%を占め、増加傾向にあるという。こうした声を受け止め、形につなげることが、野党第1党たる立憲民主党の使命である。立憲が衆院千葉5区補選で、なぜ他の野党候補から頭一つ抜け出したのか、その意味を考えるべきだ。「保守王国で勝てないから」とか「他の野党との調整が必要だから」とか適当な理由をつけて、戦うことを避け「政権の選択肢を示す」ことから逃げてしまうなら、野党第1党の存在意義などないことを肝に銘じてほしい。 ---------- 尾中 香尚里(おなか・かおり) ジャーナリスト 福岡県生まれ。1988年に毎日新聞に入社し、政治部で主に野党や国会を中心に取材。政治部副部長などを経て、現在はフリーで活動している。著書に『安倍晋三と菅直人 非常事態のリーダーシップ』(集英社新書)。 ----------
ジャーナリスト 尾中 香尚里
堕胎罪廃止と中絶の配偶者同意要件のある母体保護法を廃止するリプロを実現する民主党政権時の避妊、不妊手術および人工妊娠中絶に関して規定し、性と生殖に関する健康を守る教育に関する法律(案)があることからも
旧民主党政権かつ日本国憲法護憲派寄り(立民は枝野改憲私案.山尾改憲案など戦争推進の日本国憲法9条改憲勢力がいて左派になりきれてない問題もある)がどちらかといえば日本国憲法護憲派寄りの旧民主党政権系の立民が政権交代を目指す政権選択の選択肢となるのはありだと私は思います。
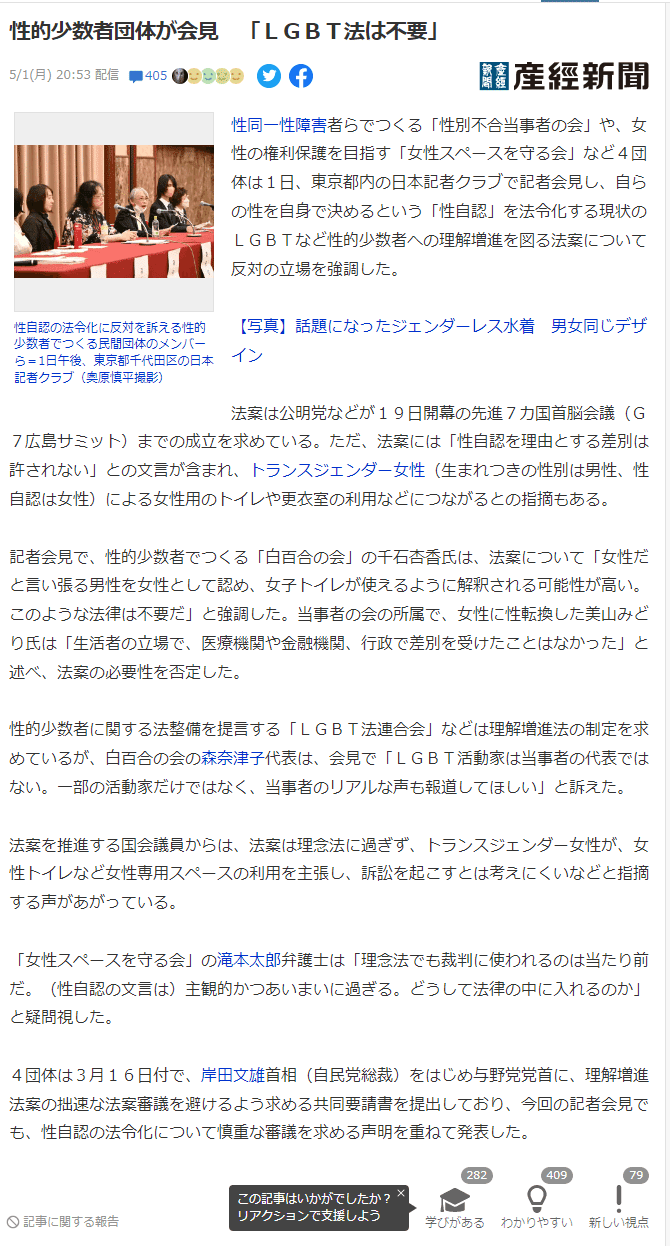
性同一性障害者らでつくる「性別不合当事者の会」や、女性の権利保護を目指す「女性スペースを守る会」など4団体は1日、東京都内の日本記者クラブで記者会見し、自らの性を自身で決めるという「性自認」を法令化する現状のLGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案について反対の立場を強調した。 【写真】話題になったジェンダーレス水着 男女同じデザイン 法案は公明党などが19日開幕の先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)までの成立を求めている。ただ、法案には「性自認を理由とする差別は許されない」との文言が含まれ、トランスジェンダー女性(生まれつきの性別は男性、性自認は女性)による女性用のトイレや更衣室の利用などにつながるとの指摘もある。 記者会見で、性的少数者でつくる「白百合の会」の千石杏香氏は、法案について「女性だと言い張る男性を女性として認め、女子トイレが使えるように解釈される可能性が高い。このような法律は不要だ」と強調した。当事者の会の所属で、女性に性転換した美山みどり氏は「生活者の立場で、医療機関や金融機関、行政で差別を受けたことはなかった」と述べ、法案の必要性を否定した。 性的少数者に関する法整備を提言する「LGBT法連合会」などは理解増進法の制定を求めているが、白百合の会の森奈津子代表は、会見で「LGBT活動家は当事者の代表ではない。一部の活動家だけではなく、当事者のリアルな声も報道してほしい」と訴えた。 法案を推進する国会議員からは、法案は理念法に過ぎず、トランスジェンダー女性が、女性トイレなど女性専用スペースの利用を主張し、訴訟を起こすとは考えにくいなどと指摘する声があがっている。 「女性スペースを守る会」の滝本太郎弁護士は「理念法でも裁判に使われるのは当たり前だ。(性自認の文言は)主観的かつあいまいに過ぎる。どうして法律の中に入れるのか」と疑問視した。 4団体は3月16日付で、岸田文雄首相(自民党総裁)をはじめ与野党党首に、理解増進法案の拙速な法案審議を避けるよう求める共同要請書を提出しており、今回の記者会見でも、性自認の法令化について慎重な審議を求める声明を重ねて発表した。
LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案に反対する性的少数者など4団体は5日、東京都内で記者会見し、拙速な法案審議を避けるよう求める共同要請書を岸田文雄首相に送付したと明らかにした。同法案を巡っては、超党派の議員連盟などが5月19日に広島市で開幕する先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)に合わせた成立を目指している。
会見したのは女性の権利保護を目指す「女性スペースを守る会」や性同一性障害の人たちでつくる「性別不合当事者の会など4団体。首相宛ての要請書には理解増進法を制定するなら、出生時の性別と自認する性が異なるトランスジェンダーの女性には女子トイレや更衣室など「女性専用スペース」の利用や女子競技への参加を認めないようにする法整備を別に求めた。
性別変更する上で性同一性障害特例法が求める性別適合手術の要件の維持も訴えた。
女性スペースを守る会の森谷みのり共同代表は、理解増進法について会見で「(女性専用スペースを使う)女児や女性の安全な暮らしを守る視点が軽視されている」と指摘した。
理解増進法案を制定する必要性に関して性別不合当事者の会の森永弥沙氏は、「(立法の)理由はない。女性として普通に働いている」と述べ、同会の美山みどり氏も「医療機関や金融機関、行政などで一切差別を感じたことはない。本当の(LGBT)当事者の声を聞いてほしい」と訴えた。
同法案を巡っては、令和3年に超党派議連がまとめたが、「性自認を理由とする差別は許されない」とする法案の表現が不明確などとして自民党内で慎重な意見が多く、党の了承を見送った経緯がある。
LGBT法「サミット前に」公明高木氏
松浦大悟氏「小手先にやれば逆に差別助長」
同性カップルをフェイクニュース攻撃する勢力
LGBT法案、当事者からも慎重論「本当の声、聞いて」
2023/4/5 14:59政治
政策
産経新聞
元首相秘書官の差別発言を機に、LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案を巡る議論が活発化し、同性婚の法整備を求める声も改めて上がる。世論は法制化の容認に傾きつつある一方で、保守系を中心に根強い反発があり、推進派、反対派の主張は平行線をたどる。こうした現状に対し、ゲイであることを公表した元参院議員、松浦大悟氏が当事者として課題や問題点を語った。
◇
時代の要請などの理由で解釈改憲で同性婚を認めるのは、ポピュリズム(大衆迎合主義)に過ぎない。同性愛者の身分を安定させるには、時流や感情に流されず、改憲で同性婚を求めていく必要がある。憲法秩序の中に同性愛者を位置付けることが重要だ。
当事者だけに同性愛者の焦る気持ちは理解できる。ただ小手先ではなく、正々堂々と国民が「同性婚を選択した」という記憶を歴史に残さなくてはいけない。
左派のLGBT活動家や一部野党は9条改正の扉を開くことにつながると警戒感を強めるが、24条1項を素直に読めば、同性婚について書かれていないのは明白だ。同性婚には賛成の立場だが、「両性の合意」を「両者の合意」に修正するなど誰が読んでも分かる憲法をつくるべきだろう。
戦後の防衛政策を大きく前進させた安全保障関連法を巡る安倍晋三政権の解釈改憲は「悪」で、左派陣営の解釈改憲を「是」とするわけにはいかないはずだ。
日本では、婚姻件数が減少し、同性愛者も異性愛者と同様に結婚の価値は相対的に低下している。マスコミは同性愛者を十把一からげに扱うが、異性愛者の未婚率の高さは逆説的にゲイやレズビアンを生きやすくしている。同性婚制度ができたとしても利用者は限定的だと感じる。
検討が進められているLGBT法案は見過ごせない。性的指向や性自認を理由とする差別を許さないとなれば、心と体の性が一致しないと「自称」する男性が女性トイレを使うことへの批判も差別と断罪されてしまう。逆にLGBT当事者への差別が広がりかねない。
LGBT問題について、安倍元首相に呼ばれて直接お話しさせてもらったことがある。その際、安倍氏は「キリスト教文化圏のような激しい同性愛差別は日本になく、急進的な運動を日本で展開しても分断を生むだけじゃないか」とおっしゃった。同じ思いだ。
左派のLGBT活動家はよく「日本は遅れている」「欧米を見習え」というが、欧米では同性愛者を狙った憎悪犯罪が後を絶たない。日本でそうした差別がなぜほとんどなかったのかをまず考え、日本の風土に合った法整備を進めるべきだ。
まつうら・だいご 昭和44年、広島市出身。神戸学院大卒業後、秋田放送にアナウンサーとして入社。平成19年の参院選で秋田選挙区から出馬し、初当選。1期務めた。自身がゲイであると公表している。著書に「LGBTの不都合な真実」(秀和システム)。
性自認至上主義に異論も 同性婚法制化、推進派と反対派で隔たり大きく
「LGBT法整備、小手先にやれば逆に差別助長」 ゲイ公表の元参議院議員、松浦大悟氏
2023/3/9 18:06政治
政局
ライフ
くらし
産経WEST
ライフ
元首相秘書官の差別発言を機に、LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案を巡る議論が活発化している。こうした中、同性婚の法整備を求める声も改めて浮上。世論は法制化の容認に傾きつつある一方、保守層を中心に根強い反発があり、推進派、反対派の主張は平行線をたどる。なぜ双方の隔たりは埋まらないのか。
若年層に賛同多く
「同性カップルに公的な結婚を認めないことは、国による不当な差別だとは考えていない」
2月28日の衆院予算委員会。野党議員から「国が同性愛者を差別している認識があるか」と問われ、岸田文雄首相はこう答弁した。
産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が2月に実施した合同世論調査では、慎重論が根強いとされる自民党の支持層でも同性婚の容認に「賛成」との回答が60・3%に達した。年代別では、18~29歳の91・4%が賛成だった。
統計上は国民の多くが認めつつ、制度化に至らない同性婚。首相は婚姻が両性の合意に基づき成立すると定めた憲法24条にも言及し「同性婚制度の容認を想定していない」とした。
政府は従来、24条が同性婚の導入を禁止または許容しているかどうか特定の立場に立っていない。
「容認するなら改憲を」
「想定していないものを禁止しようがない」とは、誰もが平等に結婚を選択できる社会の実現を目指す「マリッジ フォー オール ジャパン」の代表理事、三輪晃義弁護士(大阪弁護士会)。同性婚は「憲法の要請」との認識だ。係争中の大阪高裁の同性婚訴訟も手掛ける。
24条1項は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と規定する。同性婚の法制化に疑義を呈す麗澤大の八木秀次教授(憲法学)によると、夫婦の語句から男女間の関係のみを指すと捉えるのが通説。同性婚を「容認」と読むのは解釈に無理が生じるという。八木氏は「禁止説」を唱える。
これに対し、三輪氏は、「両性の合意のみ」は家父長的な家制度により自由な意思で結婚できなかった旧民法を改め、本人の意思のみによる婚姻を保障した文言だと指摘。同性婚反対派について「憲法の制定過程を無視している」と批判する。
保守層の中には、同性婚を容認するなら改憲を求める向きも少なくない。三輪氏はそもそも不要との立場だが、「一刻を争う問題なので改憲を待つことはできない。差別の問題を国民投票で多数決に頼っていいのか疑問もある」と危惧する。
現民法などの規定は、婚姻は男女の組み合わせを前提とする。ゆえに同性婚は認められていない。「なぜ男女間のみを法的に保護するのか。(婚姻は)子を産み、育てる制度だと本質を理解する必要がある」と八木氏。夫婦・親子の関係を法で規律してこそ、子の福祉に資するという論理だ。
男女間でも不妊などで子を産めないケースがあるが、八木氏は婚姻制度を包括的に捉えなければいけないとし「好きな者同士の合意で問題ないとして同性婚を認めれば、重婚の法的承認にもつながる」と懸念する。
同性カップルを婚姻に相当する関係と認める「パートナーシップ制度」は全国200超の自治体が導入している。ただ法的効果はなく、立憲民主党は今月6日、戸籍上で同性でも婚姻できるようにするための「婚姻平等法案」(民法改正案)を衆院に提出した。
女性の利益、簒奪の恐れ
同性婚を巡っては、荒井勝喜元首相秘書官が「(同性カップルが)隣に住んでいても嫌だ」などと記者団に発言。LGBTを含む性的少数者への政治の対応が焦点となり、令和3年に国会提出が見送られたLGBT法案も改めて制定へと動き出した。
当時は超党派の議員連盟が策定を主導し、与野党の実務者間で内容に合意したが、《性的指向及び性自認を理由とする差別は許されない》との表記に自民の党内保守派から異論が出た。
法に「差別禁止」を盛り込むとどうなるのか。反対派の主張では、体と心の性が一致しないトランスジェンダーだと「自認」する女性(体が男性)が女性トイレに入った場合、利用者の安心・安全が脅かされる。しかし問題視すれば、差別と糾弾されかねず、訴訟が乱発されるというわけだ。
性自認の法令化に反対する滝本太郎弁護士(神奈川県弁護士会)は「女性スペースの安心・安全が危うくなる」と指摘する。
実際、昨年1月には、大阪市内の商業施設の女性トイレに入ったとする建造物侵入容疑で大阪府警が、戸籍上は男性でありながら性自認が女性のトランスジェンダーを訴える40代の利用客を書類送検。滝本氏によると、英国でも近年、女性刑務所に収容されたトランス女性のレイプ犯が他の女性に性的暴行を働くという事件が起きた。
滝本氏は市井の女性らと「女性スペースを守る会」を立ち上げ、トランスジェンダリズム(性自認至上主義)に異を唱える。「『女性として遇さない』ことを『許されざる差別』としてはいけない」としている。(矢田幸己)
同性婚を巡る各訴訟の判断
同性婚を認めない現制度の違憲性を問う訴訟が全国5地裁に提起され、令和3年3月の札幌地裁判決は法の下の平等を定める憲法14条に反すると初めて判断。昨年6月の大阪地裁判決は「合憲」とし、同11月の東京地裁判決も「合憲」と結論付けたが、個人の尊厳に立脚した婚姻の立法を求める24条2項に「違反する状態」との見解を示した。名古屋、福岡の各地裁では今年、判決が言い渡される。
トランス女性の女性トイレ利用に物申す 埼玉・富士見市議
「法制化、小手先では逆に差別助長」 ゲイ公表の元参議院議員、松浦大悟氏
性自認至上主義に異論も 同性婚法制化、推進派と反対派で隔たり大きく
2023/3/9 17:47矢田 幸己政治
政局
ライフ
くらし
産経WEST
ライフ
性的少数者(LGBT)の権利保障を巡り、トランスジェンダー女性(生まれつきの性別は男性、性自認は女性)がトイレや更衣室など「女性用スペース」を利用することに懸念する声は根強い。埼玉県富士見市の加賀奈々恵市議がLGBTの理解増進に関して一般女性の権利を考慮した制度運用を動画で訴えたところ、7日までに交流サイト(SNS)で150万回超視聴されるなど反響を呼んでいる。加賀氏に問題点を聞いた。
──LGBT問題に取り組んできた
「平成29年頃からパートナーシップ制度の導入をはじめ性的少数者の権利保障に取り組んできた。一方、性自認に基づく権利を自治体の計画などに位置付けることが一般の女性に与える深刻な影響について、理解が不十分なまま推進してきてしまったと思う」
──トランス女性の女性用スペースの利用について
「心の性がどうであろうと、身体が男性の人が女性用スペースを使えるという社会的合意は作るべきではない。『心は女性だ』と偽った性犯罪者が入り込んでも判別できないし、やはり怖い。女性は盗撮やのぞきなど性暴力被害を受けやすく、女性用スペースはシェルターともいえる場所だ。女性用スペースに、男性はいないという前提が崩れると安心して利用できない」
──トランス女性の権利行使は一般女性の権利と衝突しかねない
「そうだ。レズビアンやゲイの同性愛者、バイセクシュアル(両性愛者)の権利は保障されるべきだ。トランスジェンダーに対し、就職面での差別や差別的な言動はあってはならないが、慎重に考えねばならない部分がある」
──投稿した動画の反響が大きい
「匿名で賛同してくれる人が多いのではないか。30年頃から、トランスジェンダー女性を一般女性と同様に扱うことについて一部の女性たちは懸念を示したが、黙らされてきた。LGBT推進者に『トランス差別だ』と糾弾され、バッシングを受けたためだ」
──加賀氏はどうか
「LGBTの支援者に対し、身体が男性で、女性だと自認した人による女性用スペースの利用について『実は怖いと思っている』と懸念を打ち明けたところ、『あなたは男性恐怖症なので、カウンセリングが必要だ』といわれた。市井の女性の懸念はトランス差別に置き換えられ、個人の問題に矮小(わいしょう)化されている」
──国会でLGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案が議論される
「女性用スペースの問題をはじめ性的少数者の現状について丁寧な議論が行われているとは思えない。トランスジェンダーを巡る議論で、一般の女性の意見に耳を傾けてほしい」
(聞き手 奥原慎平)
トランス女性の女性トイレ利用に物申す 埼玉・富士見市議
2023/3/7 22:18奥原 慎平政治
地方自治
地方
関東
埼玉
ライフ
くらし
知っていますか!
日本で人工妊娠中絶を受けるには、母体保護法という法律で原則「配偶者の同意」を求められます。
この法律の下では、結婚した女性が「望まない妊娠」をした場合、配偶者の許可がなければ、中絶手術を受けられません。法律が女性の自己決定権を剥奪し、望まない妊娠継続や出産強要につながっています。「妻」の身体や人生は、夫や、夫の家のものなのでしょうか?
このような法運用や婚姻関係は対等と言えるでしょうか?
また、法律が正しく運用がされず、未婚や性暴力による場合でも、産婦人科の医師が中絶の同意書に相手男性の署名・捺印を求め、それがないと手術を受けさせないということが多発しています。
「配偶者の同意」規定は、女性が中絶を希望しても、男性が「産め」と同意書への署名を拒み続けた場合は、女性は中絶できず出産しなければならないという制度なのです。
男性が「中絶の拒否権」と「出産の強制権」を持っており、このような権利を国が保証しています。
ある調査によると、今も女性が中絶する際に「配偶者同意」を求められる国はたった11ヶ国です。
2020年、アメリカでは中絶に夫の許可を求めることは「違憲」「人権侵害」という判決が出ています。韓国では堕胎罪の廃止と共に配偶者同意要件も撤廃されました。日本の母体保護法をもとに中絶法を作成した台湾でも、配偶者同意要件は不適切として廃止に向けて法案を通しており、近隣の国や先進国で、中絶の際に女性が男性の承認を得なければいけない国は日本だけになります。
日本は国内外から「配偶者同意要件」に関して批判を受けており、女性差別撤廃委員会からも幾度も中絶の配偶者同意要件を廃止するように是正勧告をされています。
WHOは「女性本人以外の第三者の承認を要求すること」で中絶にバリアを設けるような規制や法は安全な中絶を妨げるとして廃止することを勧告しています。
1995年、世界女性会議にて日本は北京宣言の内容を遵守し、女性差別を撤廃することを誓いました
北京宣言の17項目めは以下のような内容です。
すべての女性の健康のあらゆる側面,殊に自らの出産数を管理する権利を明確に認め再確認することは,女性のエンパワーメントの基本である。
20年近く経った今も、
何故私たちの「出産数を管理する権利」は守られていないのでしょうか?
なぜ、日本で女性として生きているだけで、自分の人生への自己決定権すら奪われてしまうのでしょうか?
「望まない妊娠の継続や出産は拷問である」という見解が世界的スタンダードです。
どんな理由があろうと、結婚していようといなかろうと、女性はひとりの人間であり、女性の身体や人生はその人だけのものです。
妊娠して苦しむ女性を「同意が取れない」と更に追い詰めること、
望まない妊娠の継続や出産をさせること、
自己決定権を奪い、そのような状況に追い込むことは、
全て女性に対する拷問であり、虐待であり、性暴力です。
女性の人権を侵害し続ける法律を私たち女性は黙認してて良いのでしょうか?
リプロダクティブ・ヘルスとは、
「産むか産まないか、いつ・何人子どもを持つかを自分で決める権利」であり、
妊娠、出産、中絶について十分な情報を得られ、「生殖」に関するすべてのことを自分で決める自己決定権のもと、それを実現する手段(ヘルスケア)を与えられる権利です。
私たちの「すべてのことを自分で決めて実現する権利」を国や法制度に阻まれ続けています。
私たち日本の女性にも産むか産まないか、
全てのことを自分で決められる権利が本来あるはずです。
母体保護法は私たち女性のリプロダクティブ・ヘルスを侵害し、自己決定権を奪い無力化する法律です。このような法律の運用やこのような法運用のもとの結婚は女性を幸せにするでしょうか?
「男性の許可がないと中絶させない」という運用を続け、妊娠継続や出産強要、遺棄に繋がる母体保護法は本当に私たち女性を「守って」いるでしょうか?
女性の自己決定権を法という強固なもので奪い、「女に勝手なことをさせない」という安心感を得るためだけの法律ではないでしょうか?
この法運用は女性が求めているものですか?
女性の身体の法律は女性のためにあるべきですし、女性の声を聞くべきです。
「妊娠について女性が自己決定権を持つ」という世界では当たり前の自己決定権を日本の女性にも届けませんか?
女性の身体の主人公は、女性本人です。
自分たちの身体を取り戻すために、「配偶者の同意」条項の削除に賛成してください! それを国会に届け、法律の改正を進めましょう!
ぜひ署名にもコメントを残していただき、Twitter等で #配偶者同意なくそ であなたの気持ちを聞かせてください。
賛同・拡散よろしくお願いいたします。
※ いただいたコメントは個人が特定されない形で紹介させていただくことがあります。皆さんの思いを共有して届けていきたいです。
※変更等があれば随時こちらにアップします。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
★ 活動内容・資料等はこちらから↓
国際セーフアボーションデーJapanウェブサイト: https://2020-japan.webnode.jp
ーーーーーーーーーーーーーーーー
関連記事:
★ 彼氏の同意が得られず出産強要→遺棄
女子就活生の未来を奪った「配偶者要件」
https://www.nhk.or.jp/nagoya/websp/20201127_akachan/index.html
★ レイプされ妊娠、「加害者の同意」を求められ…
https://news.yahoo.co.jp/articles/66b6d72eb9252245edb507e9b6c4d6f423162af1
★<社説>DVと中絶同意 自己決定権も考えたい
https://www.tokyo-np.co.jp/article/95354?rct=editorial
★ Japan's Abortion Rule: Get consent from your sexual predator
https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-s-abortion-rule-Get-consent-from-your-sexual-predator
★Japanese women no longer need spousal consent - if they were abused
https://www.vice.com/en/article/m7az34/japanese-women-no-longer-need-spousal-consent-for-abortions-if-they-were-abused
メディア・取材 / For media coverage
sndofwindchime@yahoo.co.jp
~ Simplified English Ver. ~
I demand that Japan abolish the law that deprives women of bodily autonomy and forces them to continue unwanted pregnancy and give birth against their will.
Japan is one of 12 countries in the world where pregnant women need to seek "permission" from their husband, which means Japanese women's decision to terminate a pregnancy first needs to be authorized by their man.
Under the law called Maternal Body Protection Law, husbands' right to force their wife to continue an unwanted pregnancy is granted. Without a male signature on the consent form, women are forced to give birth against their will. If a woman gets an abortion without male consent by fabricating the form, she can face up to 1 year in prison.
This law applies to married women. However, in reality, women are asked to get permission from their man regardless of marital status.
In some extreme cases, women were asked to get permission from their abuser or even sexual predator, which was caused due to the misconstruction of the law by each responsible medical institution.
Women should have the right to decide what they want to do with their bodies and depriving women of bodily autonomy is human right infringement and sexual abuse by the nation!
We demand the Japanese government and the Ministry of Health and Welfare abolish the male consent requirement for abortion care and let women make decisions on their bodies as independent human beings.
Sign here and leave a comment. ↓
Tweet with #配偶者同意なくそ . Please note that your comment can be shared anonymously on social media to support and empower Japanese women.
日本の女性の自己決定権を奪い望まない出産や妊娠継続に追い込む「配偶者同意」を廃止しよう
~Scroll down for English translation~
望まない妊娠は全世界で4人に1人の女性が経験しています。
海外では中絶は女性の心とからだを守るあたりまえの医療です。
現在日本では中絶薬の承認申請が進められようとしています。
日本で暮らすすべての女性たちの健康と権利を尊重するために、以下の5つを提言します。
1.望まない妊娠をした女性の選択肢のひとつとして、中絶薬を速やかに承認してください。
2.中絶薬を適正な価格で提供し、経済状況に関わらず、必要とするすべての人が使えるようにしてください。
3.女性を不当に苦しめ、中絶へのアクセスを阻んでいる刑法の堕胎罪と母体保護法の配偶者同意要件をなくしてください。
4.住んでいる地域によって中絶が受けられないことがないように、また女性のプライバシーを守るために、中絶薬のオンライン診療と自宅での服用を解禁してください。
5.中絶へのアクセスを改善し、価格を下げるために、中絶薬を取り扱える職種を増やしてください。
国連の人権規約には、必要とするすべての人が安全な中絶の情報と手段を得られること(社会権)と中絶を自分で選択できること(自由権)は基本的な人権であると明記されています。
英国やフランス、ニュージーランドなど約30カ国では、中絶薬は公的な保険や補助により実質無料で提供されています。オーストラリアや英国、フランスなどではオンライン処方が実現されています。
国際産科婦人科連合は、2020年3月のパンデミック宣言を受けて、コロナ禍の間は中絶薬のオンライン処方と自宅服用を奨励することを決めました。さらに2021年3月、「1年間運用してきたことで安全性と有効性が確認されました。各国は、全ての女性がプライバシーを守られ安全に中絶できるこの方法を恒久化すべきです」との声明を出しました。
このように海外に比べて、日本の中絶は女性に身体的に重い負担を課しています。その上、日本では中絶にスティグマを刻みつける(罪悪視する)ことで、女性たちが中絶を求める声を上げることを抑圧し続けてきました。
日本では中絶が犯罪であることを知っていますか? 日本では、一見、中絶は自由に行えるように思えますが、女性が薬を服用して自分の妊娠を自分で終わらせることは、刑法堕胎罪(212条)にあたる犯罪です。しかし、世界の多くの国々は、現在、堕胎罪を廃止する方向に動いています。たとえば、カトリック信者の多いアイルランドでさえ、2018年に国民投票で堕胎罪はなくなりました。
一方、刑法堕胎罪の例外規定を定めている母体保護法は、夫に妻の身体に関する決定権を与えています。妻が妊娠を続けたくなくても、夫は妊娠を強制することができるのです。現在、海外では、望まない妊娠の継続を強制することは拷問であり人権侵害だとみなされています。世界では中絶に配偶者同意が必要な国は日本を含めて11ヵ国のみであり、他の192ヵ国は不要だとされています。
1948年に制定された優生保護法(現在は母体保護法)は、当時の医療水準を前提に、「搔爬(そうは)」という手術器具を使って子宮内膜を掻き出す危険な中絶手術ができるのは、産婦人科医の中でも特に研鑽を重ねた「指定医師」のみだと規定しました。そのため、海外では助産師でも十分安全に行えるとされている吸引による中絶が日本でなかなか普及してきませんでした。
WHOは、搔爬は吸引よりも女性にとって痛みを伴う外科的中絶方法であると指摘しており、2012年のガイドライン『安全な中絶 第2版』では、旧態依然たる搔爬は――もし今も使われているようなら――安全な中絶方法である中絶薬か吸引法に置き換えるよう指導しています。9年後の2021年7月、厚生労働省は産婦人科医の団体に対して吸引について会員に周知するよう求めましたが、吸引に置き換えたかどうかの確認はしていません。
世界では女性の健康と権利を保障するために、中絶医療はどんどん改善されてきました。1960年代以降の女性運動の結果、中絶が合法化され、1970年頃に吸引法による中絶が導入されました。さらに1980年代には中絶薬が開発され、21世紀に入る頃までにほとんどの先進国で合法化されました。しかし、日本は長い間それらの方法を選ばず、わざわざ女性に心身の負担が大きい旧式の掻爬法が使い続けられてきたのです。
日本の懲罰的なほど高い中絶料金も女性たちを苦しめています。他国と比べて極めて高額であるばかりか、公的な医療保険もきかないため、妊娠初期でも十数万円かかることが少なくありません。2010年の調査では、自院の中期中絶の価格は60万円だと答えてきた医療機関もありました。お金がないために中絶できず、トイレで孤立出産して罪に問われる女性たちが後を絶たないのは、日本の社会構造の問題です。
中絶を比較的自由に行える世界80カ国を対象とした調査では、中絶費の全額または一部に保険が適用される国が全体の4分の3を占めています。中絶薬がWHOの必須医薬品に選ばれているのは、安全性と有効性が高いのはもちろん、原価が世界平均780円と非常に安価であることも理由の一つです。日本で中絶薬を処方するのに従来の中絶手術と同程度の値段がつく可能性を示唆した医師もいましたが、そんなことをしたら、またしても中絶医療を受けられない女性たちが出てしまいます。
すべての女性が心身の負担を負わずに、自分の人生や身体をコントロールし、安心して生きられる国にするために、賛同をお願いいたします。
協力:RHRリテラシー研究所 塚原久美 林めぐみ 伏見麻菜美
✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼
Reduce burdens imposed on women to get abortion!!
One out of every four women in the world has experienced an unwanted pregnancy. In other countries, abortion is considered a natural medical treatment that protects women's mind and bodies.
In Japan, the application for the approval of abortion pills is currently underway. In order to respect the health and rights of all women living in Japan, we demand the following 5 points.
1. Promptly approve the abortion pills as an option for women who have an unwanted pregnancy.
2. Provide abortion pills at a reasonable price and make them available to all who need them regardless of their financial situation.
3. Descriminalize abortion under the Penal Code and abolish the spousal consent requirement under the Maternal Body Protection Law as both misogynistic and patriarchal laws unfairly hurt women and prevent them from accessing abortions.
4. Lift the ban on online medical treatment and home administration of the abortion pills in order to secure the access to abortion for everyone regardless of where she lives and in order to protect her privacy.
5. Increase the number of occupations that can handle the abortion pills in order to improve access and lower the price of abortion.
The UN Human Rights Covenant clearly stipulates access to information and means of safe abortion for all who need one as the social right and the ability to choose abortion for themselves as the liberty right.
In approximately 30 countries including the UK, France, and New Zealand the abortion pills are all covered by public insurance or other kinds of subsidies. Online prescribing has been implemented in Australia, the UK, France, and other countries as well. The International Federation of Obstetrics and Gynecology has decided to encourage online prescription and home use of abortion pills during the pandemic in March 2020. In March 2021, they added, "After 1 year of the operation, the safety and effectiveness of the system has been confirmed. This method should be permanent so that all women can have a safe abortion in privacy.''
As you can see, abortion in Japan imposes heavy physical burdens on women compared to other countries. In addition, Japan has stigmatized abortion by suppressing women from speaking out for abortion. Are you aware that abortion is still criminalized in Japan? Although abortion seems to be freely available in Japan, The Penal Code (Article 212) criminalizes a woman ending her own pregnancy by taking drugs.
However, many countries around the world are now trying to decriminalize abortion. Even countries like Ireland, a predominantly Catholic country has eliminated the criminalization of abortion in a referendum in 2018.
In addition, the Maternal Body Protection Law which allows women to seek legal abortion under exceptional circumstances gives husbands the right to make decisions regarding their wives' bodies. Even if the wife does not want to continue her pregnancy, her husband can force her to do so.
Currently, in other countries, forcing a woman to continue an unwanted pregnancy is considered torture and a violation of human rights. Only 11 countries require spousal consent for abortion while the other 192 countries don't.
The Eugenic Protection Law enacted in 1948 stipulated that only "designated physicians" that had been trained in obstetrics and gynecology should be allowed to perform Dilatation and Curettage procedure, a surgical procedure in which the cervix is dilated so that the uterine lining can be scraped with a spoon-shaped instrument called curette to remove abnormal tissues as the medical field was not as advanced and developed as it is now.
As a result, suction abortion which is actually considered safe enough to be performed by midwives has not been widely performed in Japan.
The WHO points out that D&C cause more pain than aspiration and made it clear that the old-fashioned perforation is not a safe way to end a pregnancy and should be switched to safer methods in their 2012 guidelines, "Safe Abortion, Second Edition."
9 years later, in July 2021, the Ministry of Health, Labor, and Welfare (MHLW) finally asked the Association of Obstetricians and Gynecologists to inform its members about the aspiration. However, whether the method had been properly switched or not is still unclear.
Thanks to women's movements since 1960s, abortion has been legalized and the suction method was introduced around 1970.
In the 1980s, the abortion pills were developed and by the beginning of the 21st century, they had been legalized and available in most of the developed countries.
However, for a long time, Japan did not opt for these safer methods and continued to use the old-fashioned method of curettage, which has caused heavy physical and emotional burdens on women.
The punishingly high cost of abortion in Japan is also a hardship for women. In a survey conducted in 2010, some medical institutions said that the price of a mid-term abortion at their clinic was up to 600,000 JPY (about 5,250 USD). The number of women cannot have abortion due to the lack of money and are accused of having isolated births in the restroom, which deeply connects to the social structure of Japan that disregards women.
According to some survey, 80 countries around the world provide free abortion, the three quarters of those have full or partial insurance coverage for abortion costs.
The abortion pills are chosen as essential medications by WHO and proven as only because safe and effective. The pills are also quite inexpensive, whose average price is 730 JPY (about 6.5 USD) worldwide.
However, some doctors in Japan have suggested that prescribing the abortion pills should be as expensive as the conventional abortion procedure (around 100,000 yen).
The women with financial difficulties would continue to have the same difficulties affording abortion if the price was set like that.
We need your support in order to make our country a place where all women can live safely and peacefully with fundamental human rights to control their lives, bodies and destinies without physical and mental burdens.
Worked with Kumi Tsukahara, Megumi Hayashi, and Manami Fushimi from the RHR Literacy Laboratory.
中絶における女性の負担を減らしてください! ~Reduce the burden on women regarding abortion! ~
2000年の民主党法案
すぺーすアライズが翻訳したWHOの『安全でない中絶 第6版 全世界と各地域の安全でない中絶と安全でない中絶による死亡の推計(2008年現在)』(発行2011年)の中に、すぺーすアライズ独自の解説ページがあり、その中に「2000年 現与党・民主党が堕胎罪の廃止を含む「避妊、不妊手術および人工妊娠中絶に関して規定し、性と生殖に関する健康を守る教育に関する法律(案)」という記述が出てきます。この冊子の翻訳版は2012年発行(20012年となっているがおそらく間違い)となっているので、「現政権」とは野田内閣(民主党 第一次改造内閣)のことと思われます。民主党政権が続いたのは、2009年8月から2012年12月まで。
この法案名をググってみたら、次が出てきました。
2022-12-23
2000年の民主党のリプロ法案――いったい誰が作ったのか?
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条
この法律は、避妊、不妊手術および人工妊娠中絶を選択できることが個人の基本的人権であることを確認する。これらの選択が、国の人口政策(及び優生政策)の対象としてではなく、個人の意思にもとづいて行えるための措置を講ずることを目的とする。
(定義)
第二条
この法律で避妊とは、妊娠を防止するための可逆的な方法をいう。
2
この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術のことをいう。
3
この法律で人工妊娠中絶とは、妊娠した女性が妊娠の中絶によって妊娠前の状態に回復するための医療的措置をいう。
第二章 避妊
(本人の意思による避妊)
第三条
個人は、本人の意思によって避妊することができる。
2
個人は、そのための情報、相談、サービスの提供を国及び地方自治体に求める権利を有する。
3
個人は、より安全で効果があり、安価で受入れられやすい避妊法の幅広い選択肢を保障するよう国及び地方自治体に求める権利を有する。
4
国及び地方自治体は、第三条の2、3の権利を保障する義務を負う。
(避妊の指導)
第四条
避妊の指導員は、厚生大臣の定める基準に従って都道府県知事の認定する講習を
修了し、性と生殖に関する健康と権利の分野に関して経験と熱意のある者で、助産婦、保健婦/士、看護婦/士、その他とする。
2
厚生大臣が指定する避妊用の器具を使用する避妊の指導、及び厚生大臣が指定する避妊のために必要な医薬品の販売は、医師の他は上記の指導員が行うことができる。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師のみが行うことができる。
第三章 不妊手術
(本人の意思による不妊手術)
第五条
個人は、本人の意思によって不妊手術を受けることができる。
2
不妊手術を希望する者は、その意思を書面で表明し、医師による不妊手術を受けることができる。医師は、不妊手術を希望する者に、公正で十分な情報を提供しなければならない。
第四章 人工妊娠中絶
(本人の意思による人工妊娠中絶)
第六条
個人は、本人の意思によって人工妊娠中絶を受けることができる。
2
人工妊娠中絶を希望する者は、その意思を書面で表明し、医師による人工妊娠中絶を受けることができる。医師は、人工妊娠中絶を希望する者に、公正で十分な情報を提供しなければならない。
3
個人の権利に基づく人工妊娠中絶は、妊娠22週未満まで認める。
第五章 情報、サービスなどを提供する体制
第七条
国、地方自治体は、個人の性と生殖に関する問題の解決のために、情報、教育、カウンセリング、サービスを提供する相談所を設置しなければならない。相談所は、性、生殖及び避妊に関する知識の提供にあたって、作用、副作用を含めたあらゆる情報を提供しなければならない。
2
国及び地方自治体は、相談所を、保健所その他保健・医療関連施設、女性センター、民間機関などに設置しなければならない。民間機関が相談所を設置及び運営する場合は、それに要する費用について、国及び地方自治体は、政令で定めるところにより、その経費の一部を補助する。
3
国及び地方自治体は、個人が性と生殖に関して情報、教育、カウンセリング、サービスの提供を受ける権利を保障する義務を負う。
4
相談所は、職員のなかに第四条に定めた指導員を配置しなければならない。
第六章 性と生殖に関する健康を守る教育
第八条
個人が、性と生殖に関する教育を受けられるよう、国、地方公共団体は努めなければならない。
2
性と生殖に関する健康を守る教育は、学校教育、社会教育等、様々な場で行うものとする。
3
性と生殖に関する健康を守る教育を行うにあたって、市民・NGO等の協力を得るよう努め、また、こうした活動を行っている市民・NGOを支援すること。
第七章 医師、医療従事者等の義務
第九条
医師は、第五条、第六条の規定によって不妊手術または人工妊娠中絶を行った場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月10日までに都道府県知事に届け出なければならない。
第十条
不妊手術または人工妊娠中絶の施行に従事した者、及びからだと性の相談所の職員は、職務上知り得た個人情報を他者に漏らしてはならない。その職を退いたあとにおいても同様とする。
第十一条
何人も、本人の意思に反し、第五条、第六条で定める不妊手術または人工妊娠 中絶を行ってはならない。
第八章 罰則
第十二条
第十条の規定に違反して、本人の意思に反する不妊手術及び人工妊娠中絶を行った場合は*刑法の傷害罪(二〇四条)によって処罰されるものとする。ただし、本人が意思を表明できない場合、妊娠の継続または分娩が本人の生命または健康を著しく害するおそれがあるときは、その限りではない。その場合の不妊手術及び人工妊娠中絶の実施にあたっては、公正な第三者機関による審議を経なければならない。
2
第九条の規定に違反して、職員が個人情報を漏らした場合は、**刑法の秘密漏示罪(一三四条)を準用する。
*刑法の傷害罪
第二○四条
人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(平七法九一・全改)
**刑法の秘密漏示罪
第一三四条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて、知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2
宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。(平七法九一・全改)
付則
(関連法律の廃止)
第十三条
本法の成立により、刑法第二十九章堕胎の罪と母体保護法を廃止する。
2
この法律は、公布の日から起算して1ヶ月を経過した日から施行する。
2000/06/01
避妊、不妊手術および人工妊娠中絶に関して規定し、性と生殖に関する健康を守る教育に関する法律(案)民主党
