プレジデント記事読んでたら夫婦同姓合憲の判例と生殖能力要件から男女のみの法律婚合憲の判例と岸田総理の社会が変わってしまう発言は適切との指摘が出てきた件。
LGBT法廃止、同性愛は容認だけど同性の法律婚は憲法違反だからやめましょう。
なおこのnoteは生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由のプレジデント記事で紹介されている判例のリンクを張り裁判所さんのサイトの判例情報にアクセスしやすくしただけの記事です。

憲法24条1項に書かれていること
憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定している。最高裁大法廷の平成27年12月16日の判決は、この規定は、「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される」と判示した〔最高裁判所大法廷 平成26(オ)1023 判決〕。
この判旨は、「婚姻の自由」を「当事者間」に、すなわち男女のカップルだけではなく同性のカップルにも認めたものとも読めるが、そうではない。これは民法750条の夫婦同氏制度の合憲性に関する判例であり、それを判断するのに必要な限りで憲法24条1項を前記のように解釈したにすぎない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/055213_hanrei.pdf

現行法は「婚姻」をどう定義しているか
法的に「婚姻」とは何か。民法学者の犬伏由子によれば、現行家族法では「夫婦は暗黙に生殖可能な男女=異性愛カップルであることが当然とされ、婚姻が親子関係の前提をなし、法的親子関係を規律するものと捉えられている。現行法は、生殖と子育てを伴う婚姻家族(法律婚家族)=嫡出家族を中心的家族モデルとして規定していると考えられてきた」(「家族法における婚姻の位置」ジェンダー法学会編『固定された性役割からの解放』日本加除出版、2012年、89ページ)。
憲法学も憲法24条の「婚姻」についてこれと同様の理解をしてきた。憲法学者の長谷部恭男も「婚姻の自由は、当該社会において『婚姻』とされる関係が、広く認知されていることを前提としてはじめて成り立つ」としつつ、「『婚姻』外の男女関係や親子関係、婚姻しないで生きる自由なども、標準形としての『婚姻』があり、それとの距離をはかることで成立する」と婚姻が男女間のものであることを前提とした記述をしている(『憲法の理性(増補新装版)』東京大学出版会、2016年、134ページ)。標準形としての男女の婚姻があるから、それから距離のある「婚姻」外の「男女関係」が問題となるのである。
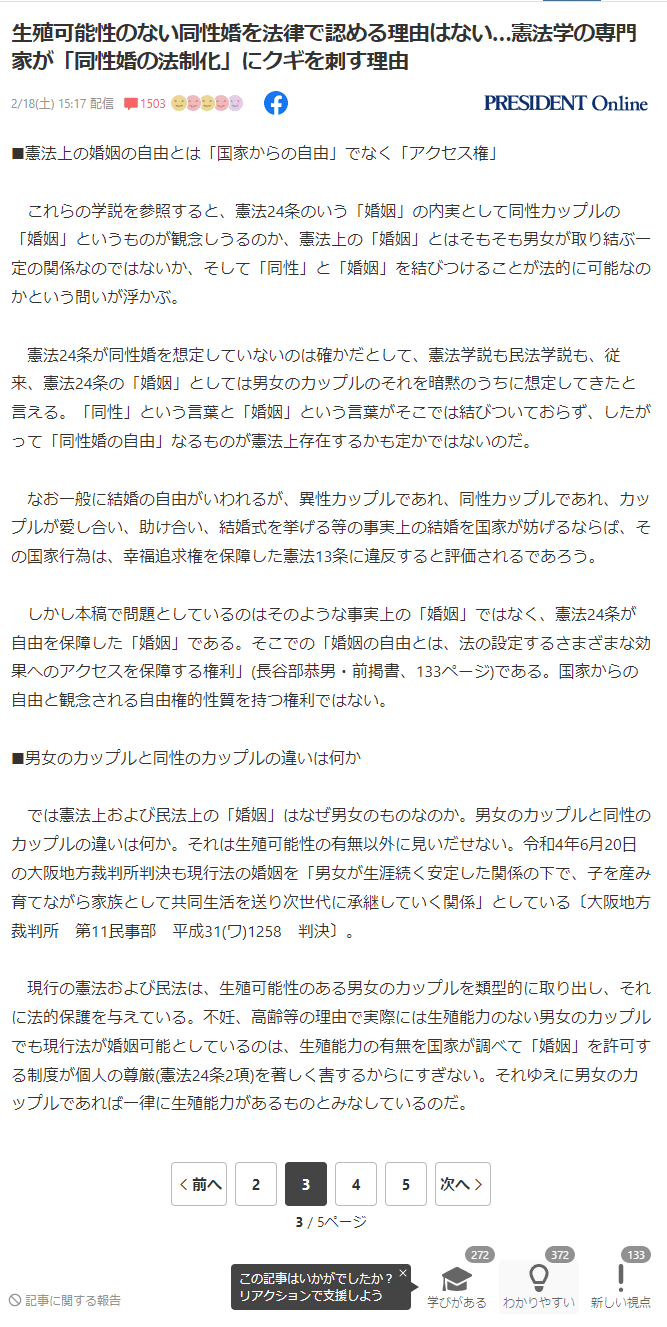
男女のカップルと同性のカップルの違いは何か
では憲法上および民法上の「婚姻」はなぜ男女のものなのか。男女のカップルと同性のカップルの違いは何か。それは生殖可能性の有無以外に見いだせない。令和4年6月20日の大阪地方裁判所判決も現行法の婚姻を「男女が生涯続く安定した関係の下で、子を産み育てながら家族として共同生活を送り次世代に承継していく関係」としている〔大阪地方裁判所 第11民事部 平成31(ワ)1258 判決〕。
現行の憲法および民法は、生殖可能性のある男女のカップルを類型的に取り出し、それに法的保護を与えている。不妊、高齢等の理由で実際には生殖能力のない男女のカップルでも現行法が婚姻可能としているのは、生殖能力の有無を国家が調べて「婚姻」を許可する制度が個人の尊厳(憲法24条2項)を著しく害するからにすぎない。それゆえに男女のカップルであれば一律に生殖能力があるものとみなしているのだ。
男女のカップルと同性のカップルの違いは何か
では憲法上および民法上の「婚姻」はなぜ男女のものなのか。男女のカップルと同性のカップルの違いは何か。それは生殖可能性の有無以外に見いだせない。令和4年6月20日の大阪地方裁判所判決も現行法の婚姻を「男女が生涯続く安定した関係の下で、子を産み育てながら家族として共同生活を送り次世代に承継していく関係」としている〔大阪地方裁判所 第11民事部 平成31(ワ)1258 判決〕。
現行の憲法および民法は、生殖可能性のある男女のカップルを類型的に取り出し、それに法的保護を与えている。不妊、高齢等の理由で実際には生殖能力のない男女のカップルでも現行法が婚姻可能としているのは、生殖能力の有無を国家が調べて「婚姻」を許可する制度が個人の尊厳(憲法24条2項)を著しく害するからにすぎない。それゆえに男女のカップルであれば一律に生殖能力があるものとみなしているのだ。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/091334_hanrei.pdf

■異性婚の優遇は「優生思想」なのか
なお、そのこと――国民の世代的再生産の担い手の保護としての婚姻制度――を肯定することは、優生思想とは異なる。優生思想とは、再生産される人口として国民の「質」を問い、「不良な子孫の出生防止」(旧優生保護法1条)を唱えることだ(石埼学「憲法25条の健康で文化的な生活と戦後日本の優生政策」遠藤美奈・植木淳・杉山有沙編『人権と社会的排除 排除過程の法的分析』成文堂、2021年参照) 。
そのような優生思想に基づく婚姻制度を整備することは、憲法24条2項のいう個人の尊厳に著しく反するというべきである。
しかし婚姻制度へのアクセスを男女に限定することは憲法の予定することであり、また国民の「質」を問題とするものではないので優生思想とは無縁である。
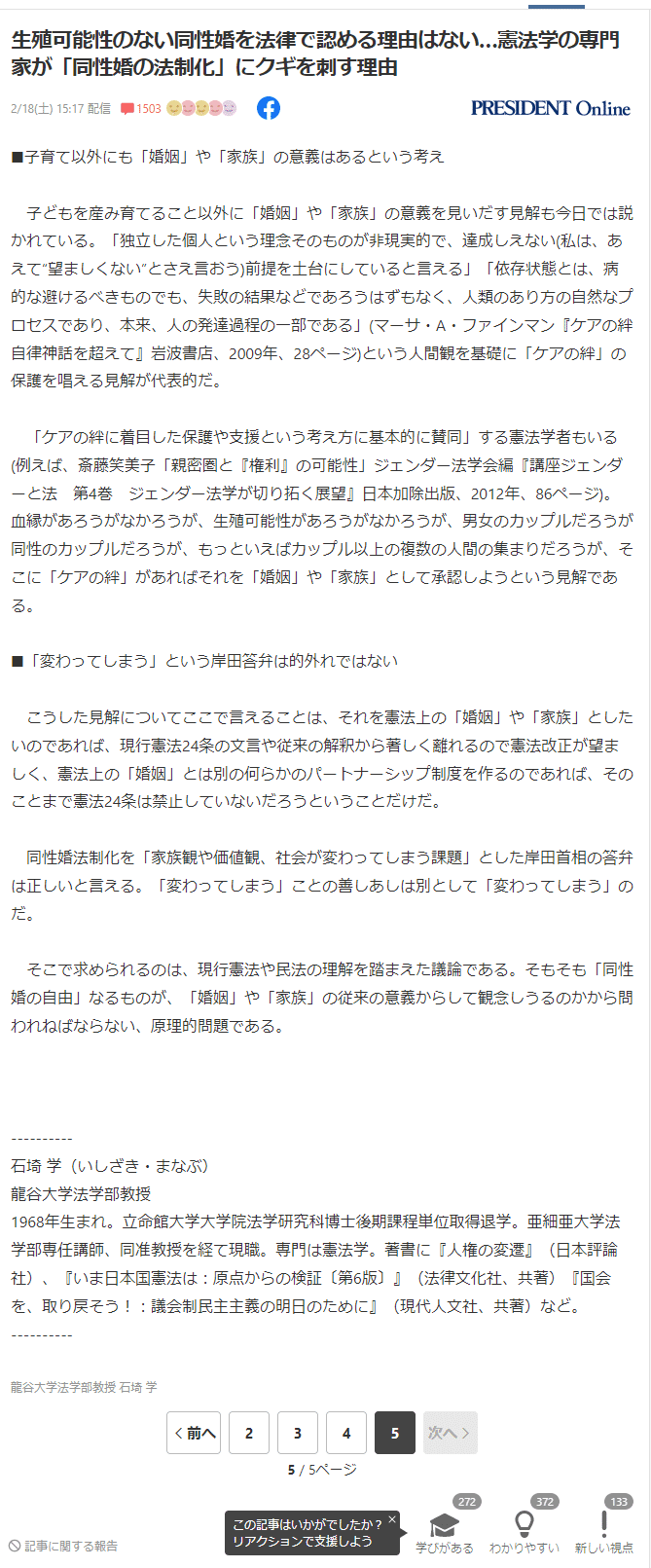
■「変わってしまう」という岸田答弁は的外れではない
こうした見解についてここで言えることは、それを憲法上の「婚姻」や「家族」としたいのであれば、現行憲法24条の文言や従来の解釈から著しく離れるので憲法改正が望ましく、憲法上の「婚姻」とは別の何らかのパートナーシップ制度を作るのであれば、そのことまで憲法24条は禁止していないだろうということだけだ。
同性婚法制化を「家族観や価値観、社会が変わってしまう課題」とした岸田首相の答弁は正しいと言える。「変わってしまう」ことの善しあしは別として「変わってしまう」のだ。
そこで求められるのは、現行憲法や民法の理解を踏まえた議論である。そもそも「同性婚の自由」なるものが、「婚姻」や「家族」の従来の意義からして観念しうるのかから問われねばならない、原理的問題である。
