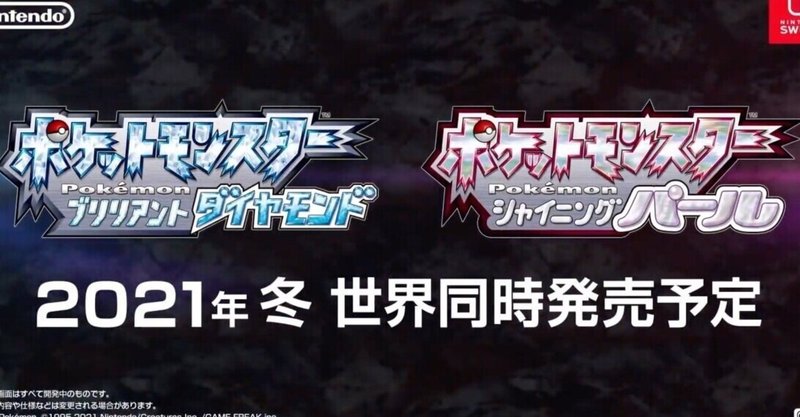
経営学からダイパリメイクの3つの懸念点を読み解く【ブリリアントダイヤモンド/シャイニングパール】
こんばんは。ダイヤモンドパール世代のポケモンファンが『ダイパキッズ』と揶揄されて久しいですね。
かくいう僕もダイパキッズの一人です。
ダイパが発売10周年を迎えた2015年ごろからダイパキッズたちは「リメイクはまだか、リメイクはまだか」と大合唱するようになり、少しでもシンオウ地方に関連する新情報があると「これはリメイクの伏線(キリッ」と鼻息を荒げてきました。
そんな高血圧なダイパキッズをなだめるかのように本日2/27(土)、遂にダイパのリメイク作品『ブリリアントダイヤモンド/シャイニングパール(以下BDSP)』が発表されました。同時に『LEGENDSアルセウス(以下アルセウス)』という新作も発表されました。
まだ発売告知PVのみの少ない情報しか公開されていないものの、既にBDSPに関しては賛否両論の嵐となっています。
この賛否両論について、現役MBA生の僕が経営上の事業戦略的にどのような懸念が考えられるかまとめてみたので、イキったダイパキッズの戯言と思って気楽に目を通して、どうぞ。
0.はじめに ~BDSPとアルセウスの基本情報~
ダイパリメイクの賛否両論を考察する前に、どういった点が賛否両論分かれているかを確認しておきましょう。
まずはこちら。
『ポケモン ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』は、原作のストーリーを忠実に再現📖✨✨
— ポケモン情報局【公式】 (@poke_times) February 26, 2021
さらに‼ 街や道路も原作のサイズ感そのままで、とってもかわいいです😊
それぞれどんな場所か、覚えていますか❓#ポケモンBDSP #ポケモンプレゼンツ #ポケモンデー pic.twitter.com/cxWcIqRc9t
BDSPは公式が『原作に忠実なリメイク』と銘打っているだけあって、マップや人物がマス目状&2等身で描かれています。これについて、
・なんか違和感ある
・コレジャナイ感…
・剣盾のようなグラフィックで出してほしかった
・いや原作を想起できて懐かしい気持ちになれるからOK
・こんなんパワプロやんけ
・ポップすぎてダイパの薄気味悪い雰囲気に合ってない
などの声が挙がっているわけですね。ストーリーもほとんど変わっていないそうです。
また、開発についてはゲームフリークではなくILCAというCG制作会社にアウトソーシングしているようです。
ポケモン本編に関してゲーフリが外注を行うのは初であり、これについて、
・ゲーフリがBDSPとアルセウスを同時開発するのは負担が大きすぎるから外注は仕方ない
・クオリティが担保されるか不安
・ダイパファンを蔑ろにしてるってことじゃ…
・外注は百歩譲って良いとして実績のある会社にしてほしかった
などの意見が挙がっています。
一方のアルセウスはといえば、
『Pokémon LEGENDS アルセウス』の舞台は、遠い昔のシンオウ地方📚
— ポケモン情報局【公式】 (@poke_times) February 26, 2021
ポケモンたちは過酷な自然環境のもと、ありのままに過ごしており、みなさんのよく知るシンオウ地方とは異なる生態系が広がっているようです🤔#PokemonLEGENDS #ポケモンプレゼンツ #ポケモンデー pic.twitter.com/NAD3hWpH88
遠い昔のシンオウ地方を舞台に、オープンワールドの冒険が楽しめる内容になっているみたいですね。こちらの方に関しては開発元がゲームフリークであり、かねてからオープンワールドのポケモンをやってみたいという声も多かったため、概ね好評な気がしています。
まとめると、ダイパをほぼそのまま再現したものがBDSPであり、ダイパを跡形もなく改変したものがアルセウスであり、原作再現を求める顧客と新要素を求める顧客の双方に応えようとした株ポケの意図が読み取れます。
その姿勢は良かったんだ…その姿勢までは…
1.人物の等身パワプロ問題
さてまずキャラが2等身になってしまったことについて考察していきます。これが事業戦略として吉と出るか凶と出るか?
僕はこれ、ゲーフリが『イノベーションのジレンマ』という状態に陥ってしまった悪手だと考えています。
イノベーションのジレンマとはクリステンセンという経営学者が提唱した理論で、噛み砕いて言うと、
業界トップの地位の優良大企業が、一部の顧客の声に耳を傾けすぎたせいで大部分の顧客の声を蔑ろにしてしまい、イノベーティブな製品の開発ができなくなってしまうこと
です。
例を挙げてみましょう。
たとえばワイヤレスイヤホンを開発している人気オーディオメーカーを想像してみてください。そのオーディオメーカーは規模も大きく、市場シェアも高いです。この企業をA社としましょう。そんな優良企業だからこそ、A社はきちんと顧客の要望に応えようとします。今、A社の熱烈なファンでコアなイヤホンオタクは、A社に対してイヤホンに最高レベルの音質を求めます。すると、A社は一念発起して、既存製品よりも更に素晴らしい音質のイヤホンを開発しようとします。
けれど、音質に極限までこだわるユーザーはほんの一部のイヤホンオタクだけで、大部分の一般ユーザーは今のA社の音質に十分満足しています。むしろ、大部分の一般ユーザーは音質よりもデザインの良さとか持ち運びやすさとか、そういう別の面を重視しているかもしれません。でもそういう一般ユーザはわざわざそういうことをA社には訴えないわけです。そういうわけでA社は大部分のユーザーが本当に求めていることに気付かず一生懸命音質向上にばかりこだわることになります。その後「今までよりも音質の良い新しいイヤホンができたよ!」と言っても、大部分の一般ユーザーの心には響かないわけです。そんなこんなしているうちに、失うもののない新参ベンチャー企業がイヤホン市場に参入してきて、誰も見たことのないような革新的な製品を発表し、一気にA社の市場シェアを食い散らかしていく。A社はそうなって初めて、音質向上にご乱心だった自社の愚かさに気づくわけですが、新参企業の新製品を開発するようなノウハウや技術はまだ持っていない…。これがイノベーションのジレンマです。
話をポケモンに戻しましょう。
ゲームフリークは今まで、数々のポケモン作品をリメイクしてきました。
赤緑⇒ファイアレッド・リーフグリーン(FRLG)
金銀⇒ハートゴールド・ソウルシルバー(HGSS)
ルビサファ⇒オメガルビー・アルファサファイア(ORAS)
そしてここで大事なのが、HGSSは金銀をゲームボーイからそのままDSに持ってきただけのような作品で大人気を博し、ORASはルビサファのストーリーやキャラをかなり改変した作品でその結果一部の過激なルビサファファンから大批判を食らった過去があるということです。
これを受けて、ゲームフリークというどんな顧客の声にも耳を傾ける優良企業が『リメイクは原作から変えなければ変えないほど良い』と判断し、あんなシルバニアファミリーみたいな絵面になってしまったものだと考えられます。
ですが、ゲーフリにはよく考えてほしかった。
いちいちネット上で刺々しくORASを批判したりしないような大部分の普通のポケモンファンが、真にリメイクに期待していることは何だったのか。リメイクから得たい感動やワクワクの本質は何なのか。
僕個人の話で恐縮ですが、
FRLGが出た小学生のころ、白黒画面だった赤緑の世界に色彩が付いたことに感動しました。
HGSSが出た中学生のころ、のっぺりした画面だった金銀の世界がちょっと立体的に描写されたことに感動しました。
ORASが出た大学生のころ、2Dだったルビサファの世界が3Dで遊べたことに感動しました。
リメイクのワクワクドキドキとは、昔の作品が現代のグラフィック水準で蘇ってくることでした。
であれば、仮に剣盾のようなグラフィックでダイパがリメイクされていたなら、その風景にファンは大盛り上がりになったはずです。
なんかそういうデータあるんですか?と言われればそれまでですが、共感してくれる人は多いと思っています。というか、2等身のままなら普通に原作をプレイすれば済む話です。原作に忠実すぎるリメイクなら、普通に原作をプレイすれば済む話です。
それに、ORASの改変も評判が悪かったものばかりではなく、ラティオスラティアスの大空を飛ぶ機能、序盤からハイドロポンプや三色牙を覚えた野生ポケモンが出てくることなど、ファンを大いに盛り上がらせた部分もあったはずです。
悪いのはファンの気持ちをリアルに想像せず安易に改変してしまうことであり、ファンの気持ちに寄り添った改変なら全然受け容れられると僕は思います。
一部の過激な要求・ネガティブ意見に囚われず、本当にダイパキッズがリメイクに求めているものは何だろうか?と考えれば、『グラフィックは最新作に準拠するよう進化させ、原作ファンが愛着を抱いているキャラやシーンには改変を加えない』という判断ができたはずです。
そもそも、あれだけ批判されたORASもキャラやストーリーの改変について叩かれたわけであって、グラフィックを3Dにしたことが叩かれたわけではありませんしね。顧客の表面的な声だけ反映させて、本質的な顧客のニーズに応えようとしない姿勢が悪いというのは当たり前のことで、経営学以前の話です。
とはいえ、『ダイパリメイクを開発する予定なんすけどどんなリメイクが欲しいっすか?w』なんて露骨な市場調査はできませんから、その判断にたどり着くのは容易ではないとも思います。
結論としては、ゲーフリがORAS発売時に受けた一部の過激な批判にビビりすぎて大部分のユーザーが暗黙の内に求めている要望に応えられなかったのではないでしょうか。キャラの等身だけに関して言えば顧客ロイヤリティを、更にはBDSPの売上を損ないかねない悪手だと思います。
(もちろん、遊んでいくうちに慣れる&ストーリーなど他要素については良い評判を受けるなどの可能性はあります。そもそもまだほとんど情報が公開されていませんからね)
2.開発外注問題
次に外注問題です。
僕はこれ、多少ブランドイメージは傷つくかもしれないけれど、製品のクオリティを決定的に下げてしまうほどの打ち手ではないかなと思います。
これは製品が世に出るまでの
企画⇒設計⇒開発⇒生産⇒販売
といったバリューチェーンの中で、大元の企業がどれを自社で手掛けどれをアウトソーシングするかという垂直統合の問題です。
この種の内製化と外注を考える際の基本的な指針は、どのフェーズが最終製品の価値を最も左右するのかを考え、そのフェーズは自社で手掛け、最終製品の価値をそれほど左右しないフェーズは外注してコストカット等のメリットを狙いにいくというものです。
さっきのA社で考えてみましょう。仮にA社が超低コストでイヤホンを量産できる設備を保有しているとしたら、そこがA社の収益力の源泉=価値の源泉となるわけですから、生産を外注するのはもってのほかです。仮にA社が製品デザインを設計するのが苦手なら、設計フェーズだけアウトソーシングするのは手かもしれません。自社の子会社として強力な物流会社を傘下に収めているなら販売は自社グループ内で行い、物流ノウハウがないなら大手物流会社に委託するのが良いでしょう。
話をポケモンに戻しましょう。
ポケモン…というよりも任天堂のゲーム全般に言えることですが、任天堂のゲームは技術力をウリにはしていません。これは日本のゲームの雌雄である任天堂とソニー(プレイステーション)を比べればわかるでしょう。プレステが年々グラフィックが進化していっているのに対し、任天堂のゲームはプレステほどグラフィックが最先端ではありません。むしろ任天堂のゲームは、グラフィックがプレステに比べて多少ショボくても、ゲームのキャラの魅力やコンテンツ力を武器にここまで世界を牛耳っているのです。
となれば、ポケモンシリーズにおいても重要なのは企画・設計フェーズであり、開発フェーズの最終製品に与える影響は相対的に小さいと言えそうです。
しかも今回の場合、開発を外注しているといってもディレクターは増田順一氏です。キャラやストーリーの企画・設計といった最も重要な部分は、増田氏によって適切に舵取りが行われることが期待でき、大きくクオリティを落としてしまう心配は無いと考えられます。
3.ポップでキュートすぎる問題
2等身問題や外注問題に比べれば否定的な意見が少ないのが、『PV見た感じシンオウ地方の雰囲気に合っていない』問題です。
正直、まだ我々はゲーム画面のほんの一部しか見せられていないので、もしかしたらシンオウ地方特有のミステリアスで不気味なシーンもたくさんあるかもしれません。
とはいえ、現段階で明らかになっているゲーム画面だけから判断すれば、絵面が明るすぎ可愛すぎて原作の雰囲気とは合っていないかなというのが僕の直感です。
マーケティングの有名な考え方に、製品の3層構造というのがあります。
製品の3層構造:製品には『核となる要素』『その要素を彩る形態(パッケージ、デザイン、名前、特徴、品質水準など)』『製品の付随機能』という3段階の要素があるというフレームワーク。
たとえばナチュラルメイクを目的としたファンデーションを考えてみましょう。ナチュラルメイクをするための道具、というのが『核となる要素』です。そのファンデーションの名前やデザインやパッケージなどが『形態』です。返品保証や公式LINEによる問い合わせサービスなどが『製品の付随機能』です。
ここで大事なのは、その製品を構成するすべての要素が互いに調和し、シンクロナイズしてこそ製品の価値が高まるということです。
たとえば、ナチュラルメイクをするためのファンデーションなのに、パッケージという要素がめちゃくちゃギラギラしてたら売れなくなりますよね。逆にケバい色の口紅だったらパッケージはギラギラしてた方が売れそうです。このように、製品の要素同士が不調和を起こすと製品価値が減退してしまうというのがマーケティングの一般的な考え方です。
これに照らし合わせると『もりのようかん』『なぞのばしょ』『テンガン山』といったミステリアスな雰囲気を持つダイパという作品に、ポップでキュートなグラフィックは不調和を起こしていると思うんですよね。
他には、
・剣盾との互換性はあるのか?
・ナナカマド博士は進化を専門に研究しているがメガシンカなどの要素は復活するのか?
などの点についても関心が寄せられていますが、概ね現状挙がっている不安の声としてはこんなところでしょうか。
書いてて思いましたが無理矢理経営の内容に結び付けている感が否めませんね。わざわざ経営用語を持ち出さなくても説明できるという…。正直、PVを見た瞬間に感じた不安感を「それってあなたの感想ですよね?」と言われたくないから経営学の基礎的な考え方をお借りして説明したというのが本音です。
とはいえ生粋のダイパキッズの僕は中高生の頃から『ダイパリメイクを遊ぶまでは死なねえ』と決めていたので、その日が来るまで生きていこうと思います。素敵な作品が手元に届くと信じて。
それでは。
ぶち
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
