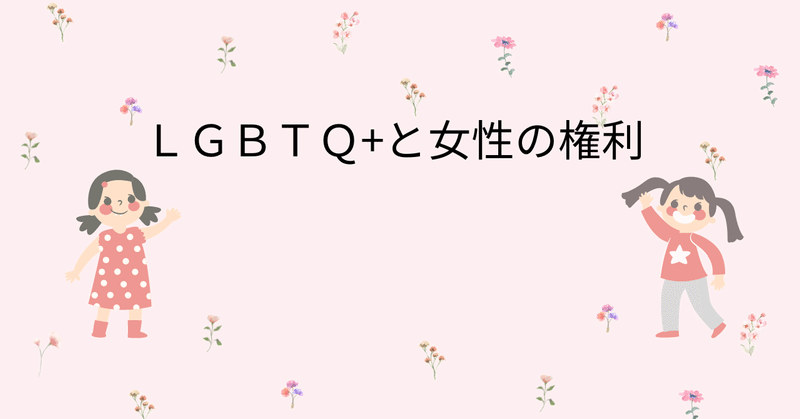
令和5年10月25日最高裁大法廷決定
性別の変更の取扱いの変更の審判(性別の取扱いの変更 | 裁判所 (courts.go.jp))について、最高裁は、生殖能力の喪失を要件とすることは違憲であると判断した(092527_hanrei.pdf (courts.go.jp))。
これにより女性の権利が侵害されるのではないかとの懸念がある(「女性は人数多くてもマイノリティー」武蔵大・千田有紀教授 性自認尊重のトレンドに懸念 - 産経ニュース (sankei.com))。
なお、多数意見は外性器除去手術等が不要とまでは判断していない。もっとも、3人の裁判官が外性器除去手術等も不要であるとする反対意見を述べている。
「性別変更する上で司法や医療の関与が薄まる」のではないかといった懸念もあるが、最高裁は、「特例法の制定後、性同一性障害に対する医学的知見が進展し、性同一性障害を有する者の示す症状及びこれに対する治療の在り方の多様性に関する認識が一般化して段階的治療という考え方が採られなくなり、性同一性障害に対する治療として、どのような身体的治療を必要とするかは患者によって異なるものとされたことにより、必要な治療を受けたか否かは性別適合手術を受けたか否かによって決まるものではなくなり、上記要件を課すことは、医学的にみて合理的関連性を欠くに至っているといわざるを得ない。」としており、同要件を課すことに医学的な合理性はないとしている。
岡正晶裁判官の補足意見には、「本決定を受けてなされる法改正に当たって、本件規定の削除にとどめるか、上記のように本件規定に代わる要件を設けるなどすることは、立法府に与えられた立法政策上の裁量権に全面的に委ねられているところ、立法府においてはかかる裁量権を合理的に行使することが期待される。」としており、規定を削除してもそれに代わる要件を立法府が設けることはできるとしている。
さらに、三浦守裁判官は、外性器除去手術等を要件とする規定も違憲であるとするが、「事業者が営む施設について不特定多数人が裸になって利用するという公衆浴場等の性質に照らし、このような身体的な外観に基づく男女の区分には相当な理由がある。厚生労働大臣の技術的助言やこれを踏まえた条例の基準も同様の意味に解され(令和5年6月23日付け薬生衛発第0623号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知参照)、上記男女の区分は、法律に基づく事業者の措置という形で社会生活上の規範を構成しているとみることができる。」とし、「上記のような身体的な外観に基づく規範の性質等に照らし、5号規定がなかったとしても、この規範が当然に変更されるものではなく、これに代わる規範が直ちに形成されるとも考え難い。」と述べている。また、「。利用者が安心して安全にトイレ等を利用できることは、全ての利用者にとって重要な問題であるが、各施設の性格(学校内、企業内、会員用、公衆用等)や利用の状況等は様々であり、個別の実情に応じ適切な対応が必要である。また、性同一性障害を有する者にとって生活上欠くことのできないトイレの利用は、性別変更審判の有無に関わらず、切実かつ困難な問題であり、多様な人々が共生する社会生活の在り方として、個別の実情に応じ適切な対応が求められる。」と述べている。
したがって、生殖能力喪失要件や外性器除去手術等要件がなくなっても女性の権利を侵害するとはいえない。
なお、草野耕一裁判官の反対意見に対しては「判決では『女性は男性器を見たくないのだろう』(=異性の性器を見せられる羞恥心)といった指摘があった。そうではない。女性は自分の身体を(元男性に)見られることに対し不安を感じている。ここが理解されていない。」という指摘がある。
草野裁判官については、判断の仕方も多数意見とは異なる。
多数意見は、「本件規定が必要かつ合理的な制約を課すものとして憲法13条に適合するか否かについては、本件規定の目的のために制約が必要とされる程度と、制約される自由の内容及び性質、具体的な制約の態様及び程度等を較量して判断されるべきものと解するのが相当である。」としている。
これに対し草野裁判官は「5号規定が合憲であるというためには、5号規定が上記の自由を制約していることの目的(以下、単に「制約目的」という。)に正当性があり、かつ、その目的を達成するために5号規定が選択した手段が制約目的に照らして相当なものといえることが必要である。」とし、「相当性問題についての判断を下すに当たりいかなる判断枠組みを用いるべきかについては講学上様々な見解がある。しかしながら、相当性問題の実質は、共通の指標によって大小を計ることができない関係者間の利益を比較衡量することであるところ、かかる比較衡量を普遍的ないしは類型的に行い得るような判断枠組みがアプリオリに存在するとは考え難く、相当性問題を考えるに当たって採り得る最善の思考方法は、結局のところ、判断の相当性を最も明確に示し得る視点を試行錯誤的に模索し、その結果として発見された「最善の視点」に立って問題を論じ判断を下すことであるように思える。そして、本事件において用い得る「最善の視点」は、5号規定が合憲とされる場合に現出されるであろう社会(以下「5号規定が合憲とされる社会」という。)と5号規定を違憲としてこれを排除した場合に現出されるであろう社会(以下「5号規定が違憲とされる社会」という。)を比較し、いずれの社会の方が、憲法が体現している諸理念に照らして、より善い社会であるといえるかを検討することであろう。」と述べている。
ところで、宇賀克也裁判官は、反対意見の中で「憲法13条以外で規定された基本的人権も、表現の自由や信教の自由を考えれば明らかなとおり、決してその外延は明確ではなく、憲法学者の研究の大部分は、憲法上基本的人権として明記された権利の外延についての様々な解釈の優劣に関するものといってよいと思われる。」と述べている。権利の行使が正当な範囲か否かを判断することが非常に難しいことについては、過去に投降した(なぜ行政は人権を守れないのか?|precious time (note.com))。
なお、LGBTQ理解増進法が制定された際も女性や子どもの権利を侵害するのではないかという批判があったが、同法は国民の権利及び義務を規定した法律ではない(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律に関するQ&A|政策統括官(政策調整担当) - 内閣府 (cao.go.jp))。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
