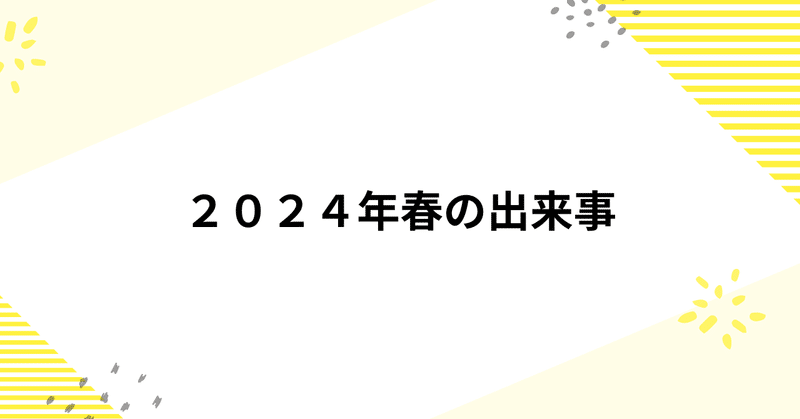
祖国の防衛とは
名古屋市の市長が「軍人として命を失っていくというのは、祖国のために命を捨てるというのは、相当高度な道徳的行為であるということは間違いないのね」と発言したことが話題になっている(河村市長「祖国のために命を捨てるのは道徳的行為」にノンフィクションライター 石戸諭氏「どんな歴史観を持っているのか?」 | 政治 | ABEMA TIMES | アベマタイムズ)。
まず、市長は「軍人」と述べているが、我が国は軍隊を持たない(憲法9条2項)ので軍人はいない。自衛隊は軍隊ではなく、自衛官は軍人ではないということになっている。そうすると、改憲を主張しているともとれるが、その点は明確ではない。
また、憲法上思想良心の自由が保障されている(同法19条)ので、祖国のために命を捨ていることが相当高度な道徳的行為なのかどうかは各人の判断による。
そのうえで「祖国のため」とは何を意味するのであろうか。
大日本帝国憲法の時代には、軍隊があったので市長がその時代の考え方が現在でも通用すると考えているのであれば、当時は天皇が主権者であるから祖国とは天皇のことである。
国民主権国家を前提としているのであれば、一体何を守るのであろうか。
国民の生命と考えるべきであろうか。この点、生命さえ無事ならよいと考えるのであれば、侵略されても抵抗しないという考え方もありうる。戦争をすれば必ず死者は出る。しかもそれは軍人に限らない。したがって、国民の生命を守ると考えると軍人も生命を捨てないほうがよいといえる。
では、領土、自然、建造物等の国民の財産と考えるべきであろうか。確かに、侵略されれば国民の財産は没収される危険がある。しかし、戦って負ければ同じことである。そうすると、勝てる見込みがないのであれば、条件交渉をしたうえで併合に応じるということもあり得る。敵国も犠牲は少ないほうがよいであろうから、犠牲が出る前であれば、負けるよりは有利な条件で合意ができる可能性はある。
さらに自由等の国民の人権と考えることもできる。たとえ生命があったとしても自由がなければ家畜と同じであり人間とはいえないから生命をかけてでも守らなければならないといえる。しかし、敵国が人権を保障していないのであれば、負ければ結局人権を失うことになる。
そうすると、戦争に負けないように憲法を改正して軍隊を置くべきであろうか。そこまでしなくとも自衛隊の防衛力を大幅に強化すべきであろうか。
おそらく防衛力を大幅に強化しても憲法を改正して軍隊を置いても他国に負けないだけの防衛力又は軍事力を持つことは難しい。なぜなら、唯一の被爆国である我が国が核兵器を持つという選択をすることは難しいからである。核兵器を持たない限り核兵器を持つ国と軍事力において対等にはならないであろう。我が国も核兵器を持つべきだという意見もあろうが、多数を形成するのは難しいであろう。
また、そもそも防衛力又は軍事力の強化は諸刃の剣でもある。防衛力の強化に反対する声に対して他国から攻められたらどうするのかという反論がある。しかし、この反論は実はそれほど説得力がない。なぜなら、もし我が国に今すぐ防衛力を大幅に増強しなければならないほどの脅威があるとすれば、防衛力を強化すると宣言するだけで敵国からの攻撃を誘発することになるからである。敵国からすれば、防衛力が強化されるのがわかっていながらそれを黙ってみている必要はない。その前に攻撃するほうがよい。つまり、攻められたらどうする以前に敵国に攻撃させる動機付けをしてしまうことになりかねない。
核兵器は持てないし、防衛力の大幅な増強も緊張を高めるからできないとすると防衛力の増強といっても自国のみで防衛することは難しい。そこで、集団的安全保障ということが検討されることになる。
ここで陸上自衛隊が「大東亜戦争」という用語を使ったことが報道され、のちに削除されたことについて触れる(なぜ「大東亜戦争」と呼んだのか 戦没者追悼式で自衛隊が投稿、浮き彫りにした課題:朝日新聞GLOBE+ (asahi.com))。
おそらく自衛隊自身はあまり考えずにこの用語を使ったのであろう。ただ、これをきっかけになぜ大東亜戦争と呼んではいけないのかと疑問に思う人もいるだろう。日本の侵略戦争だという見方は戦勝国の勝手な押し付けだという人もいるだろう。しかし、この用語を禁止したのがGHQであることからもわかるが、我が国が自国の防衛をするうえで頼りにしている日米同盟を考えれば、この用語を使うことには慎重であるべきであろう。欧米は歴史を修正することを認めないであろう。ちなみに、歴史学では記事にもあるように「アジア太平洋戦争」と呼ぶことが一般的である。これはアジアの開放が目的だったのか単なる侵略だったのかといった論争に触れない用語なので、どうしてもこだわりたいという人以外はこの用語を使うのが無難である。
ところで、防衛力の増強については、それを批判する見解についてもう少し掘り下げる必要がある。前述のように防衛力の増強は他国との関係で諸刃の剣なのであるが、それだけでは増強すべきではないとまでは言えないかもしれない。実はもう一つ重要な視点がある。
それは政治には表と裏があるということである。確かに、他国からの侵略を防ぐためには実力組織が必要であり、状況に応じて必要な装備も変わってくるが、中国、ミャンマー、イラク等で見られるように軍隊には治安の維持を名目に人民に向けられる危険があるということである。
日本ではそのようなことは起きないだろうと思う人もいるかもしれない。しかし、国会議員の民間事業者や自治体職員へのハラスメント(“パワハラ”指摘に汗かき謝罪 吉幾三氏指摘の長谷川岳参院議員「無自覚でやってきた」北海道知事「威圧的」|FNNプライムオンライン)、町長によるハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラ認定で辞意表明、愛知・東郷町長「無知を恥じ入るばかりだ」 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)、セクハラ認めた岐阜・池田町長、21年の任期を振り返り「独りよがりで裸の王様だった」 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp))に関する報道があり、権力者が権力を濫用すれば多くの犠牲者が出ることを物語っている。権力者がいったん暴走し始めるとそれを止めることは難しいのである。
同様のことは死刑制度についても言える。死刑廃止論については、なぜ犯罪者を庇うのかといった批判があるが、刑罰についても表と裏がある。国民の法益を守るというのが表であるが、外敵に対する実力組織と同様治安の維持という名目で善良な市民が犠牲になる危険がある。これが裏である。
現在でも黙秘権を無視した取り調べが行われており(取り調べで「ガキ」「僕ちゃん」 検察官発言、法廷で再生 黙秘権巡る訴訟・東京地裁 (youtube.com))、冤罪の危険はなくなっていない。
政治には表と裏があり、それがひっくり返らないようにするためには、立憲主義憲法を制定して権力を制限することが最低限必要であるが、それに加えて防衛力の増強、緊急事態条項の設置、死刑制度等についても批判的な検討をし続ける必要がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
