
第二信 悪意なく地球一周する人
<ブギーアイドルから赤帯への手紙>
こんばんにゃ
「こんばんにゃ」
「とうとう始まってしまいましたですね」
というのは1987年7月18日から7月19日の間にフジテレビ系列で放送された『FNSスーパースペシャル 一億人のテレビ夢列島』におけるタモリさん、明石家さんまさんの第一声です。後に「27時間」と称されるお祭りがついに途切れてしまった2020年にこのような企画が立ち上がり赤帯さんとやり取りできることは大変光栄です。そして素晴らしいヘッダー画像を描いてくださったスレンテンノイ!さん、本当にどうもありがとうございます。
noteの特性を存分に生かした長文だった為、公開後SNSでの反応が瞬時に来ることがなく、また直近の時事の話題がなかったことは大変ありがたかったです。今何が起こっているかを的確に判断し意見することが僕は苦手です。そして赤帯さんの家庭環境を知ることができるとは予想していなかったので本当にこれは「手紙」なのだと実感した次第です。改めて第一信どうもありがとうございました。
僕も幼少期から思春期の頃について何か書こうかと思ったのですがラジオを聴く~新星堂へ行く~楽器の練習をするといったこと以外思い出せず特に今と変わりがないことに気付きました。強いて書くならば1990年代は国立市、府中市でニッポン放送を受信することがかなり困難でした。radikoの恩恵でニッポン放送、ラジオ日本をクリアな音質で日常的に聴いている現在とはここが決定的に違います。
そんな僕の近況ですが音楽を作る側としては8月中旬に新作を作り終え、リスナー側としては1980年代後半から1990前半までの日本のポップス・歌謡曲の傍流のほとんどが『新蒸気波要点ガイド』(DU BOOKS 2019年)『オブスキュア・シティポップ・ディスクガイド』(DU BOOKS 2020年)にまとまってしまい燃え尽き気味です。18歳以降心のどこかでくすぶっていたYMO人脈、渋谷系人脈に対するコンプレックスが完全に晴れたことはありがたいのですがブックオフへ行くモチベーションがレンジャーキーやおもちゃ類になる日が来ようとは・・
そして第一信から第二信までの間に小林信吾さん、エディ・ヴァン・ヘイレン、筒美京平さん、近藤等則さんの訃報が相次ぎ20世紀に生きた人間にとって圧倒的な父性を失い、正気を保つふりをし続けなければならない日々です。やがて来るバート・バカラックの訃報、ポール・マッカートニーの訃報、ONの訃報、BIG3の訃報に怯えながら過ごしています。
第一信にクリスチャン・ラッセンについての話題がありましたが、昭和最後のスーパー戦隊『超獣戦隊ライブマン』(テレビ朝日 1988年~1989年放送)岬めぐみ役を演じられた森恵さんが現在トータルセラピスト、ヒーリングアーティストとして方舟光(はこぶねひかる)名義で初の個展を開催されていたので先日神田・文房堂ギャラリーカフェにお邪魔しました。遠目でも分かるほどの集中力で黒字のTシャツに翼を描かれていました。ラッセンにとってのイルカが方舟光さんにとっては翼のようです。僕は視覚芸術には疎い為ここでは個展に行ってきたという事実だけを書きとどめておきます。
『超獣戦隊ライブマン』について簡単に説明しますと「地球は真の天才、大教授ビアスを中心とした天才だけによって支配されねばならぬ」(監督:長谷多可男 脚本:曽田博久 第1話「友よ君たちはなぜ?!」より)という洗脳を受けた武装頭脳軍ボルトとライブマンのあまりにも壮絶な戦いの物語です。昭和63年・自粛ムードの中で放送された作品とはいえバブル期でもある訳ですが画面から華々しさはほとんど感じられません。そして武装頭脳軍ボルトの揺らぐことのない優生思想、第13話「燃えよ鋼鉄コロン」での無差別毒ガス攻撃の決行、第48話「誕生!!少年王ビアス!」での全人類が大教授ビアスを讃えひれ伏す描写は1995年を連想せずにはいられません。ソフト化が遅れに遅れ2011年にようやくDVDが発売された背景にはこういった描写の影響が少なからずあったのかもしれません。第一信にあった1995年の断層についての話題をこれで終わらせることはありませんので次回までにもう少し考える時間を頂けたらと思います。
最近ふと手にしたプロマジシャン・ゆうきともさん(本名・高橋知之)著『人はなぜ簡単にだまされるのか』(新潮新書 2006年)の中にこのような文章がありました。
どんなにチープな嘘でも、百回言えば説得力を生みます。そしてそれが、俗に「カリスマ」などと呼ばれる、要は常に堂々と自信にあふれたキャラクターの人物から発せられたものであるならばなおさらですし、そのような発言の根拠がオカルトや占いのような実体のないものだとすると、そこには反証する余地もないことになります。(p.169)
“あの本”が自分に与えた脱力感
『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』(DU BOOKS 2020年)については冒頭、細野晴臣さんと岡田拓朗さんの対談における「通奏低音」の誤用、「楽理」を「学理」と誤記する二点が商業的に全国流通される音楽書籍としてあまりにも杜撰なことに愕然としてそこから各章を読み進めるのが億劫というのが正直な感想です。対談部分を読んだ瞬間肩の力がガクっと抜けたことはいまだに忘れられません。発売から時間が経ち肯定的に考えるとすれば数多くのニューエイジ・ミュージックのレコードやCDライナーに書かれてきた「1/fゆらぎ」的疑似科学を現代に持ち込んだパロディなのかもしれません。そこまで計算した上での対談だとしたら「あっぱれ」の一言です。『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』に携わった方々がこの返信を閲覧しているとは思えないのでこちらに通奏低音の基礎についての動画リンクを貼ります。「A=440Hz」になる以前「A=415Hz」基準なのでチェンバロの調律が現在と比べおよそ半音下がっています。
細野さんと岡田さんの対談の中でニューエイジ・ミュージックとジャズについての言及がありますがポール・ウィンターについてはスルー、かつて細野さんと共同名義でアルバムを発表したビル・ラズウェルにについてもスルー※。対談時にはリリース情報がなかったのかもしれませんがマイルス・デイヴィス『In A Silent Way』のニューエイジ的側面を増幅させた新譜『AGAINST EMPIRE』(MODReloaded 2020年)があまりにも素晴らしかっただけに残念です。結局出てきた名前はデューク・エリントンという細野さんの過去のインタビューやラジオの発言に合わせた接待・忖度と言って差し支えない着地になっています。さらに岡田さんは「2020年代はアーティストたちにとって再び非理論的なもので何かできることを模索していく時代になるかと思っているんです」(p.Ⅹ)という自説を述べています。しつこく書きますが通奏低音を誤用するレベルのミュージシャンが考える「非理論的なもの」とは一体何なのか僕には一切不明ですし理解したくもありません。『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』が尾島由郎さんとスペンサー・ドランの対談から始まればどれだけ素晴らしい一冊になっただろうと思うと非常に残念です。
※ビル・ラズウェルについては音楽ナタリーの記事『細野ゼミ 1コマ目 細野晴臣とアンビエントミュージック(前編)』の中で言及されていました。
比較として生来のジャズ・ミュージシャンが例えばジョン・コルトレーンのように体系化されていない近年のジャズについて理論面からどのように語っていたのかを確認したいと思います。やや古い資料になるのですが山下洋輔さんと香取良彦さんの共著『山下洋輔のジャズの掟』(全音楽譜出版社 2008年)に収録されている座談会の中からドラマー・大阪昌彦さんの発言です。
ブラッド・メルドーが出て、その後にロバート・グラスパー。あの辺を聴いてると、彼らが好んで使う音形というか、割とランダムなんだけど四度飛ばしなんだよね。なんかそれって新たな理論、みたいな。名前はつけられないけどね。それは何か理屈があるような気がしてしょうがない(p.147)。
三小節目に鳴る「C/E」は筒美京平さんが作曲された元ロリポップ・ソニック・メンバーのソロ曲「それはちょっと」(東芝EMI 1995年)トリオ・バージョン(1997年)で渋谷毅さんも弾いてらっしゃったパターンですね。渋谷さんに限らずジャズの定石ですが思い出さずにはいられませんでした。
筒美京平さんの話題が出たので歌謡曲方面に話が逸れますが矢野利裕さん著『ジャニーズと日本』(講談社現代新書 2016年)の中で郷ひろみさん「男の子女の子」の「ヘイヘイヘイ」を三連符と誤記した部分(p.74)を読んだ時も肩の力がガクっと抜けました。インターネットの恩恵で音楽以外のジャンルの方でもメロディ譜程度なら読むことができる、例えば高橋由佳利さん、よしまさこさん、筒井康隆さん、和田誠さん、小林秀雄さんのような存在がもっと増えるのかと思いきや退行・逆行している現象は非常に面白いことだと思います。そんな矢野さんにヒップホップについての原稿を依頼するのが『ミュージック・マガジン』という雑誌です。はあ。
鈴木武幸が求め続ける「力」
いつからか僕は細野晴臣さんの音楽を能動的には聴かなくなりました。今現在僕が能動的に聴いている音楽のほとんどは東映特撮の主題歌・挿入歌・劇伴なのですがそれらに比べて細野さん主導の音楽は非常に弱いものに感じます。例えばグループ・サウンズや内田裕也さん一派のように「誰が一番喧嘩が強かったか」というエピソードが細野さん一派にはほぼ皆無ということも無関係ではないと思います。
AuDee(旧:JFN PARK)で放送・配信されている”歌う放送作家”植竹公和さんの番組『アカシック・ラジオ』で久々に荒井由実さん『MISSLIM』(Alfa 1974年)をA面・B面通して聴いたのですがSly & The Family Stone「In Time」を下地にした「あなただけのもの」のリズム・アプローチは大変丁寧な仕上がりでよくできています。ですがまるで小人が箱庭で演奏しているようにしか聴こえなかったのです。演奏メンバーの中で松任谷正隆さんはこの路線に乗り気ではなかったと知りホッとしました。そして時は流れ、1982年以降リンドラムの音色が世界中のチャートを席巻するようになったタイミングでドラマー活動休止を決めた林立夫さんの判断はひたすらジャンルを越境するという細野さんの判断よりも賢明だったように思えるのです。ポップスからの決別といえば大江千里さんが書かれたこのコラムにはもう二度とかつて自分がいた場所に戻って来ることはないという怖さを感じました。
元東映プロデューサー・鈴木武幸さんが書かれた『夢を追い続ける男』(講談社 2018年)という本があります。その中にスーパー戦隊番組主題歌について非常に気になる書き方をされていたので引用します。
これまでのスーパー戦隊シリーズの主題歌は唄いやすいのですが、どうも力が足りないと思っていた私は、力強い曲調の主題歌、シャッフルビートのリズムを使った曲にして欲しいと大野さんに注文を出したのです。(p.224)
『電撃戦隊チェンジマン』(テレビ朝日 1985年~1986年放送)主題歌の作曲を大野克夫さんにお願いする経緯でこの一文が出てくるのですがそれまでにスーパー戦隊主題歌を作曲した面々は渡辺宙明さん、京建輔さん、加瀬邦彦さんといずれも強靭なリズムとメロディを世に放ってきた面々です。特に『科学戦隊ダイナマン』オープニング曲は歌い出しまでに約15発(!!)のナパーム爆破SEが入ります。そういった主題歌を聴いてもなお鈴木さんは力を求め続けます。
『光戦隊マスクマン』(テレビ朝日 1987年~1988年放送)の章では劇伴を淡海悟郎さんにお願いする際(それにしても渋い人選)、淡海さんのご自宅に50台ほどのシンセサイザーが置かれていたことに鈴木さんは驚きます。実際の音源を聴くとストリングスのフレーズがシンセサイザーに代用される一方、リズムはドラムやシモンズの人力演奏と音楽的にどれだけ効果があったのかは不明です。しかし物量に対してあまりに素直に好意的な反応を示す鈴木さんの嗜好を知れたので資料としては充分です。このような方が未就学児をターゲットとする番組のプロデューサーであったことは非常に正しい人事だと思います。『夢を追い続ける男』はロボット五体合体の実現が常に著者のモチベーションである変わった自伝です。ちなみに『光戦隊マスクマン』ハルカ役を演じられた永田由紀さんは2020年11月22日、11月23日に開催される『癒しフェア 2020 in TOKYO』に立運推命学公認鑑定師として参加されるそうです。「鍛えあげろよオーラパワー」(©売野雅勇)。
東映およびスーパー戦隊が求め続けた「力」を見事に音楽として表現する能力を持つ小杉保夫さん、京田誠一さん、つのごうじさん、奥慶一さん、Project.Rの皆さん(特に山下康介さん、大橋恵さん、大石憲一郎さん)。このような方々が書かれた音楽を聴く時、僕は今一番心穏やかでいられます。
下記リンクは東映特撮YouTubeチャンネルで2020年10月から2021年4月まで無料公式配信されていた『特命戦隊ゴーバスターズ』(テレビ朝日 2012年~2013年放送)オープニング曲「バスターズ レディーゴー!」です。作曲・編曲は大石憲一郎さん。迫力あるドラムとベースのマッチング、一方で非常に緻密なコーラス、ストリングスのラインは何度聴いても飽きることがありません。今現在このようなリスナー生活なので、10代の僕が素直にDaisy Worldのカタログを追っていたことが幻のように思えるのです。
さて困った・・
機材全般、例えば第一信の話題でしたらハウス・ミュージックには欠かせないTR-808、TR-909、TB-303に対して僕は全く思い入れがなく情報として固有名詞を知るのみで心の底から夢中になった時期がありません。赤帯さんがかなりの分量をハウス・ミュージックに割いてくださったにも関わらず僕は特に多くを語ることはできず申し訳ないです。同じ四つ打ちでもディスコは心の底から夢中になり映画『皮ジャン反抗族』( 東映 監督:長谷部安春 主演: 舘ひろし 1978年)リバイバル上映に足を運んだほどです。
808state「Pacific」(ZTT 1989年)のようにサックスの音が鳴り、フュージョン的な質感のある音源は多少楽しみ方が分かるのですがThe Orbについては10代の頃義務的に『The Orb's Adventures Beyond The Ultraworld』(Island 1991年)を聴いた記憶があるのみでこの返信の為に改めて聴き返してもそれは何か違う気がするのでやめました。
理由は分からないのですがどうしても新川博さん、戸田誠司さん、コモリタミノル(小森田実)さん、長岡成貢さん、CHOKKAKUさん、松本晃彦さん、岩代太郎さんといった歌謡曲、ポップス、劇伴のフィルターを通した「ハウス風の別の何か」にならないと身体が反応しないのです。このような人間が高円寺4thでライブやDJを行なっていたのはよくよく考えると本当に失礼な行為だったと思います。
椹木野衣さん著『増補 シミュレーショニズムーハウスミュージックと盗用芸術』(ちくま学芸文庫 2001年)については約15年前にアニメ作家・漫画家の橋本新さんから勧められ読んだ記憶はあったのですが内容は覚えていませんでした。赤帯さんによる引用部分「ロックは最低のコンディションに陥っていた」という感覚はスタジアム・ロックやギターの早弾き(上岡龍太郎さんは”曲弾き”とおっしゃいますね)が大好きな僕にとって全く分からないものでしたが「われわれは(少なくとも僕は)とりたてて最高になりたいわけでもない」という感覚は確かにVaporwave、Future Funkに夢中になっていた2015年頃を想起させるものでした。スクラッチ・ノイズとカットアップが姿をくらましたかと思いきやレコード・ストア・デイが毎年ある程度の盛り上がりを見せ、カットアップを謳う必要がないほど当たり前に波形修正が施されたポップスがオンライン、オフライン上に溢れることになるとはさすがの椹木さんにとっても予想外だったのかもしれません。
ジャケット・デザインによるイメージ操作の力を一旦無視して冷静に考え直したいのがピンク・フロイド『Atom Heart Mother』(Harvest 1970年)において非常に重要な要素でありながらKLFが『CHILL OUT』(KLF Communications 1990年)制作時にスルーした音楽がブルースであることです。サンプリング対象としてギターの音色には接近している所が非常に巧妙だと思います。では『Atom Heart Mother』の抽象性と具体性の正当後継者は誰なのか。どのような作品なのか。1990年代後半から2000年代前半にかけて特に日本で顕著だったジョン・フェイヒィの再評価を経てコラージュとブルースの融合を成功させたのは武末亮さん『Six-O-Seven Blues』(EM Records 2013年)ではないかというのが僕の見立てです。ちなみに現在僕がオフラインで仲良くさせて頂いている方は原子心鯔さんというアカウント名でTwitterをやってらっしゃいます。鯔瀬史雄という名義で「ブックオフショートショート」という独自ジャンルの執筆活動をされています。
『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』においてジョン・フェイヒィは「ルーツ・オブ・ニューエイジ」の括りに入るそうです。生ギターのオープンCチューニング(日本ではURC時代の野沢享司さんがいち早く取り入れました)と並ぶ彼の代名詞であるコラージュについて柴崎祐二さんは「こうした批評的な視座や毒のようなものは例えば、William Ackermanなどには見出すことのできない類のもの」(p.154)と書かれていますがこの意見に対しては肯定も否定もせずもう少し長いスパンで考察したいです。「Windham Hill」の文字列を見て連想される完全に真っ白な無菌状態は時として「毒のようなもの」より危険かもしれませんから。
ボケとしての100%Electronica
Vaporwaveからジョージ・クラントンとネガティヴ・ジェミニのようなあまりにも人間味あふれる存在が登場したことは彼らの音楽以上に予想外の出来事として語るべきことなのかもしれません。結婚指輪を渡す瞬間をinstagramで公開するという”「あけすけに」色めいた”行為を堂々をやってのけたことは本当に素晴らしいと思います。マキタスポーツさんが本名・槙田雄司名義で書かれた『一億総ツッコミ時代』(星海社新書 2012年)の根幹である”「ツッコミ」ではなく「ボケ」に転身せよ。「メタ」的に物事を見るのではなく「ベタ」に生きろ”というメッセージが海を越え100%Electronicaと共鳴してしまったのは不思議です。
Deep Forestのカメラは自分だけにしか向いていない
第一信で赤帯さんが書かれていた”「ニューエイジ・ミュージック」の身体とエロティシズム、エクスタシーへの言及”についてですが・・確かに少ないですね。総じて他人への興味が無い人間が作る音楽がニューエイジ・ミュージックのような気がします。他人への興味の無さを漠然とした環境問題にすり替えたとしたら分かりやすいかもしれません。ここでは『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』においてただ一枚も(!!)取り上げられることのなかったDeep Forest(エリック・ムーケ)がどれだけ自分にしか関心がないのかを確認したいと思います。
Deep Forestといえばアルバムや楽曲以上に有名なのが上記リンクで民族音楽学者・塚田健一さんが言及されている無自覚に暴力的なサンプリング行為でしょう。ユネスコ相手でも無視する勇気。世界各国の音楽は自身の作曲の動機として存在すると言わんばかりの姿勢はVaporwave、Future Funkにおけるサンプリングのおおらかさとは程遠いものです。決して褒められた行為ではないことを理解しているつもりでしたが僕は2017年頃からDeep Forestの音楽に夢中になり機会があればDJで頻繁に流すようになりました。冒頭で引用したゆうきともさんの文章のような「堂々と自信にあふれたキャラクター」が発する雰囲気が僕にとって心地よいものだったのです。あらら・・。特に問題となった「Sweet Lullaby」を現在改めて聴き返すと単純にオートチューン的なケロ声が欲しかっただけなのかもしれません。当時きちんとした手続きを踏んでさえいればと思わずにはいられません。
21世紀以降のDeep Forestの音楽的興味はインドから始まりポルトガル〜トルコ~日本〜中国〜ブラジルを経由して台湾へと向かいます。これでもかなり端折って書いていますがヒヤヒヤするルートですね。アルバム『Music. Ditected_』(SONY 2002年)に収録されている「Will You Be Ready」という曲にはブレイク直後の元ちとせさんがフィーチャーされています。
2020年9月30日にリリースされたDeep Forest最新作『吼海』は冒頭「戰歌 cemavulid」でフィーチャーされている台湾のシンガーソングライター・戴曉君(ダイ・シャオジュン)さんの所属レーベル・風潮音樂(Wind Music)が楽曲権利を保有しています。1990年代前半に比べればフィーチャリングする側される側、双方の関係は良好と言えるでしょう。
台湾への音楽的興味と並行してDeep ForestはロシアのZarina Kopyrinaという歌手のアカペラ素材に作曲の動機を求めます。下記リンクの動画をご覧頂ければ分かる通り手法はエルメート・パスコアール「Tiruliruli」そのままですね。アハハ。
メディスン・マン??
Deep Forest以前に悪意なく音楽による地球一周を試みた人物と言えばジョー・ザヴィヌルでしょう。
ウェザー・リポート解散直前にリリースされたほぼザヴィヌル一人によるシンセサイザー多重録音アルバム『Dialects』(SONY 1986年)のジャケットに描かれているのはズバリ世界地図です。そして晩年まで活動の母体となったザヴィヌル・シンジケートのアルバム『BLACK WATER』(SONY 1989年)にはDr.ジョージ・バドラーによる非常に奇妙なライナーが収録されています。一介のレコード会社プロデューサー、A&Rが書いたとは思えない文章です。以下引用します(訳者クレジットなし。””内は曲名)。
ツアーを多くこなすジャズ・ミュージシャン、ジョー・ザビヌルは、世界中の様々な文化にある豊かな伝統音楽を吸収し、統合してきた。彼は、ヨーロッパにいた旅音楽師や、南北戦争後渡り歩いてきたアメリカ南部のブルース・マンの伝統を引き継いでいるのである。彼らは歌を、村から村へ、町から町へと、これらは人類に共通するものだと確信しながら、他の文化に分け与えていったのである。
(中略)“メディスン・マン”はザビヌル・パンテオンの祖型である。彼は問題を処理するーー苦しみの日常の中、歌と笑いで人々をむすびつける。もしよくいわれるように音楽が治療薬なら、“メディスン・マン”とはザビヌル自身であろう。
(中略)“イン・ザ・セイム・ボード”は我々は皆1つの生命のいかだーー地球ーーにしがみついているのであり、制限無しに資源を枯渇させペシャンコにしたり、戦争や、注意不足でパンクさせることになれば、からっぽの宇宙で破滅することになるという警告である。これは、各地を渡り歩き、生きて行く為の基本的なニーズや、日常の問題は、万国共通であるということに、気付いた者がよく示すことである。
あまりに安直な宇宙船地球号の言い換え、壮大過ぎて何を言いたいのかが分からないものすごいライナーです。そして引用した部分の先には「モンクの音楽はシンプルである」というジャズ制作に携わるプロデューサー、A&Rの肩書きを疑うような文章が収録されています。時にスクリャービンと同列に語られることもあるセロニアス・モンクの特異な和音の感覚は今なお研究対象であることは周知です。Dr.ジョージ・バドラーおそるべし。仕事はきちんとできる人だったようでウィントン+ブランフォードのマルサリス兄弟やハリー・コニックJr.のアルバムにもクレジットが確認できます。
Deep Forestの3rdアルバム『Comparsa』(SONY 1998年)には「Deep Weather」というあまりに直球なタイトルの曲が収録されています。この曲でゲストとしてアコーディオンを演奏しているのが誰あろう”メディスン・マン”ジョー・ザヴィヌルです。膨大なDeep Forest作品の中でおそらく唯一他者に敬意を払った曲だと思います。ほとんどのパートをKORG M1プリセット音が担っていることもザヴィヌルへの敬意の表れでしょう。
また話が逸れますがクラシック音楽の世界においてヒーリング・ミュージックはどのように語られてきたかの例として岡田暁生さん著『音楽の聴き方』(中公新書 2009年)から引用します。
時として私は奇怪な夢想をすることがある。そのうち脳波と情感の生理的メカニズムについての研究が進んで、どんな「感動」も思うままに電気刺激で再生刺激で再生が可能になる悪夢である(p.134)
ヒーリング・ミュージックの流行などに、どうにも危なっかしいものを感じてしまうのは、こうしたことと無関係ではない。少なくとも私にとって「音楽を聴く」とは、意味を探すこと、つまり他者を探すことなのだ(p.135)
クラシック音楽とモダン・ジャズについて、特に拍の取り方について新書の形式でここまで有益な情報を得て良いのかと思うほど贅沢な一冊なのですがヒーリング・ミュージックについては具体的なミュージシャンやレーベル名が出てこない批判の定形文のようなものです。しかし「他者」という言葉が出てきます。ヒーリング・ミュージック、ニューエイジ・ミュージックをどれだけ聴いても極端な個人の内面もしくは極端なスケールの大きさにしかたどり着かないことを岡田さんは瞬時に聴き取り読者に伝えたかったのかもしれません。
さらに話が逸れますが2008年8月7日、タモリさんから赤塚不二夫さんへの白紙弔辞には「他人」という言葉が出てきます。この弔辞における「他人」という言葉の重要性、全冷中関連の「他人」からの影響がほぼなくなった現在の「趣味人タモリ」とデビュー当時の「密室芸人タモリ」との比較については石川誠壱さん著『誠壱のタモリ論』(世田谷ボロ市 2013年)をぜひ読んで頂きたいです。全冷中関連のミュージシャンと言えば坂田明さんですが宴会芸でダイナミックな声帯・形態模写を行う一方、ライフワークのミジンコ研究においては「宇宙」という言葉を使いますがそれが主観であること、錯覚であることを自覚されている非常に慎重かつ繊細な方です。ニューエイジ・ミュージックとジャズの架け橋的存在として今後もっと聴き返し、考察したい作品がたくさんあります。
ヒューマン・トランポリン
Deep Forestの次は当然の流れとしてエンヤ、エニグマ、ヤニーについて書こうと思ったのですがニューエイジ・ミュージック、ジャズの比ではないポップスという大きな土俵おいて世界各国の旋律やリズムを自身の作曲の動機として取り込んできたポール・サイモンの存在を忘れていました。大き過ぎる存在は常に忘れがちです。
1985年、CBS時代の先輩や同世代のミュージシャンたちが次々と「SUN CITY」の思想に共鳴し、レコーディングに参加する中で一人逆行するかのようにポール・サイモンは南アフリカ共和国の音楽を表層的な範囲で取り込んだアルバム『GRACELAND』(Warner 1986年)制作に取りかかります。ラルフ・マクドナルドのパーカッションが占める割合も多い為どこまでがアフリカ的要素なのか線引きは難しいのでポール本人によるライナーを以下引用します(訳者:中川五郎)。
1984年の夏、僕は友人のひとりから、一枚のアルバムのテープを受け取った。GUMBOOTS:ACCORDION JIVE HITS,VOLUME Ⅱ。単純明快だったアトランティック・レコードの3コード・ポップ的な所があって、50年代のロックンロールをおぼろ気ながら彷彿とさせた。ボーベッツのミスター・リーやラバーン・ベイカーのジム・ダンディーたち。楽しく、アップ・ビートの音たちは、とても身近なもののように感じられながらも、とても、とても遠い国のようでもあった。アコーディオン、ベース、ドラムス、エレクトリック・ギターという楽器の組合せといい、ギャロ・レコードというレーベルのネームといい、多分、こいつはアメリカやイギリスのバンドじゃないだろうとは思っていたんだ。実は、その正体というのは、町のジャイブと呼ばれる、「ムバカンガ」というものだった。南アフリカのソウェトのストリート・ミュージックのことだ。
ワーナー・ブラザーズ・レコードの取計らいで、ヨハネスブルグ在住のレコード・プロデューサーである、ヒルトン・ローゼンタールと連絡がついた。彼は、黒人/白人混合のバンドとしては初めて南アで成功したジュルーカというグループをプロデュースしたことで知られる人物だ。彼が送ってくれた、トラディショナルからファンクに至るまでのブラック・ミュージックの様々なジャンルのレコード、20枚余りを聴き出すことで、僕は少しずつ南アフリカの音楽に興味を持ちはじめたんだ。
当時批判の対象となったのはリズムの搾取についてでしたが、このライナーにはまずコードの少なさについての言及があります。『Still Crazy After All These Years』(CBS 1975年)以降のジャズ的語法に疲れていたのかもしれません。結果的に『GRACELAND』が第29回グラミー賞「Album of the year」を受賞したことがニューエイジ・ミュージックに与えた影響は非常に大きいものだったのではという考えがこの返信を書いている間に膨らんで行きました。『GRACELAND』リリースから32年後にKC Lights、Marc Kinchenといった面々が参加した『GRACELAND-THE REMIXIES-』(SME 2018年)を聴くと全体的に1990年代的な、それこそDeep Forest的な雰囲気が漂っています。
※追記:2021年8月21日にポール・サイモンが自身のTwitterで『GRACELAND』レコーディング、編集時の思い出とマスターテープの写真をツイートしていました。今はなき名スタジオThe Hit Factoryの名前が確認できる貴重な資料です。
Deep Forest、ジョー・ザヴィヌル、ポール・サイモン・・うっかり地球を大きな歩幅で歩いてしまう音楽家は他にも沢山いますが、ここではクロード・ドビュッシーの作品群の中からおそらく現在曲名表記すら一発アウトな1909年の曲を紹介します。ペンタトニックと短七度の強調でラグタイムは一丁上がり。SNS時代にドビュッシーが生きていたらどうなったか想像するだに恐ろしい曲です。ジョージア出身のインガ・フィオリアによるピアノ演奏です。
ちなみに僕が度々クラシック音楽について言及するのは梶原一騎さんの過剰な文学コンプレックスに近いものなのでここまで読んで、聴いて頂いたとしたら大変申し訳ないです。
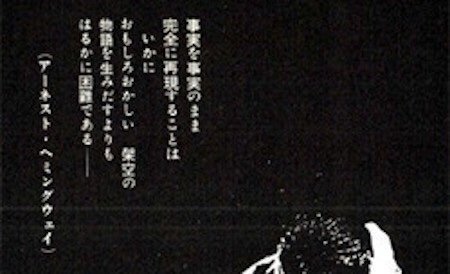
カネボウヒューマンスペシャル
第二信ではニューエイジ・ミュージックを軸とした「いい加減さ」について色々と書いてきました。最後に広義のニューエイジ思想として『TVガイド』誌(東京ニュース通信社)1991年2月22号を紹介します。巻頭特集は「今だから地球や人間愛を考えてみたい 見つめたい真実(ほんとう)の愛」。表紙を飾るのは山口智子さん。日本テレビ系列で1991年2月19日に放送されたカネボウヒューマンスペシャル第11弾『プサマカシ 若き助産婦のアフリカ熱中記』を軸にした壮大な特集です。テレビの視聴者が中川家や友近さんのような視点を得る以前、俳優さんや時の人が遠い異国の地で大切な「何か」を見つけるテレビ番組を真っ正面から見ていた時代についてもう少し資料を集めて今後の往復書簡の中で書いてみたいです。そしてかなり危険な案件ではありますが景山民夫さん著『遠い海から来たCOO』(角川文庫 1992年)も避けて通れない気がするので改めて読み返してみます。

ケーデンス
ここまで書いてきたことからまた話が逸れますが、筒美京平さんの訃報を受け生前京平さんが多用した「Ⅱ-Ⅴ-Ⅰ」の連結が美しい曲を聴きながら改めて偉大な功績に感謝したいと思います。例えば古賀政男さん、遠藤実さんのような一代限りのメロディではなく京平さんがシステム・構造に重きを置く作曲家であったことは残されたリスナーにとって数少ない希望の一つです。この点において京平さんは服部克久さん以上に服部良一さんのDNAが濃いのかもしれません。無理矢理な論法かもしれないのですがとにかく何かしら希望を探さなければ残されたリスナーは正気を保てないのです。
赤帯さんからの問いに対してほとんど答えていないのでまた次回よろしくお願い致します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
