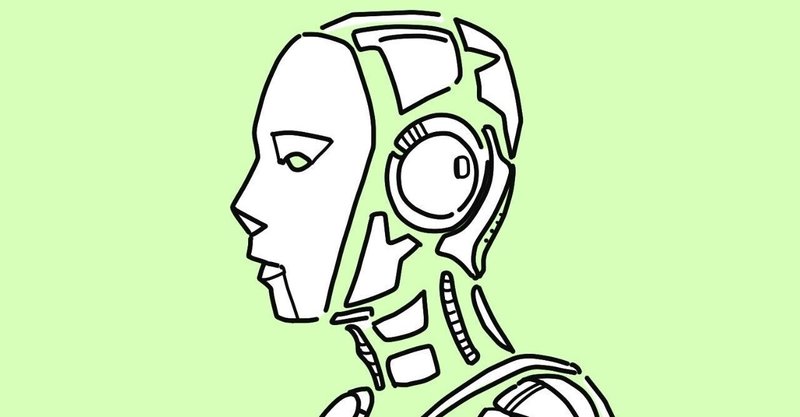
本日発表された第63回グラミー賞、Large Ensemble部門とINSTRUMENTAL COMPOSITION部門の2冠となったMaria Schneiderさんの最新作「Data Lords」について
はい、ビッグバンドファンです。本日発表された第63回グラミー賞で、ビッグバンドが表彰対象に含まれる「Large Ensemble部門」とインストの作曲に対する表彰部門「INSTRUMENTAL COMPOSITION部門」で2冠となったMaria Schneiderさんの最新作「Data Lords」について話していこうと思います。
デジタル世界と自然世界という2つの極に対し彼女なりの問題意識を2枚のCDに託した
最新作「Data Lords」は<The Digital World>と<Our Natural World>と題された2枚のCDで作られています。
AmazonやCDショップなどでも購入出来ますが、是非今回のタイトルは上記ArtistShareから購入されることをオススメします。こちらから購入しますと制作中の曲に対する構想を練っている段階の動画やリハーサル、プレイヤーとの対談等々様々な特典資料が全部手に入りますので。
さて、1枚目の<The Digital World>に関しては以下のように話しています。少し長いですが引用します。
私たちミュージシャンは、違法ダウンロードやファイル・シェアなど、初期段階からデジタル化された世界に搾取されてきた。私は米国議会の公聴会で証言をしたりと、長い間この問題と戦っています。今やビッグデータ・カンパニーは、人々の情報を集め、その嗜好をコントロールし、考えにも大きな影響を及ぼしている。その危険性を描いた “Don’t Be Evil”(2015年に取り下げられたグーグル社の非公式モットー) 、そして故スティーヴン・ホーキング博士が予言した、AIが人類を凌駕するシンギュラリティへの恐怖を表現した“Data Lords”。かつて人々の心にゆとりがあり、直接会話をしたり電話で話したりして交流するのがメインだった失われた世界への郷愁と、インターネットが発達し、自分と相反する意見を拒絶するキャンセル・カルチャーが跋扈する、現代社会の孤独感を込めた“A World Lost”。“CQ CQ, Is Anybody There?”は父に捧げた曲。かつての遠方とのコミュニケーション方法であり、亡き父がこよなく愛したハム無線とモールス信号をモチーフにしています。この曲は、デヴィッド・ボウイとのリズム・セクションとダニー・マッキャスリン(テナー・サックス)らとの実験的なリハーサル・セッションから生まれました。大国間から企業間へと移行した宇宙開発競争を12音階の変奏曲で表す“Sputnik”といった、今まで表現しなかった現代の社会問題をテーマにしています
2枚目の<Our Natural World>は1枚目と対になった世界観で作られており、2枚目の1曲目に収録されている「Sanzenin」は、2017年の来日コンサートの後に訪れた京都大原の三千院に魅了されて書いたものだそうです。また陶芸家ジャック・トロイの、小石の入った陶器を振って音を愉しむ作品「石の囁き」にヒントを得て創作し、Maria Schneider自身が「かつて書いたことのないタイプの曲で、このアルバムの中で最も気に入っている」と話す「Stone Song」。そして勿論結成から続くある意味伝統的なMaria Schneiderサウンドを前面に押し出した「Look Up」「Bluebirds」など、2枚目の方が1枚目に比べてかなりシンフォニックな作品が並びます。
この2枚はつまり、1枚目が現代社会の陰を、2枚目が陽を表したものということになります。なので、この辺りの設定抜きに聞くと、私には2枚目がかなりしっくりくるサウンドでした。ただこの辺は結構意見が分かれるところのようで、1枚目の方がしっくりくると言っている人もいます。かなり好みが分かれるところのようですが、逆に言えばMaria Schneider氏がきっちり色分けして作品を作り上げることが出来た証左とも言えます。要は設定抜きに聞いてもその違いが分かるということで、さすがです。
企業間の競争に米ソ冷戦構造を被せることで未来的でありながらも問題意識を提示
個人的に注目したい曲の1つ目は「Sputnik」です。この曲はINSTRUMENTAL COMPOSITION部門の受賞曲にもなりましたが、タイトルとMaria Schneider氏の意図する部分が面白いなと思いました。ご存じの通り「Sputnik」はかつて冷戦状態にあった米ソにおいて、ソ連側で作られたロケットの名前です。

しかし上に書いたようにこのアルバムは現代社会を表す目的で書かれている中、ある種違和感さえ感じる「Sputnik」というタイトルを敢えてつけたことに彼女の意思を感じます。事実Artist Shareより購入するとサイト内で制作過程を撮影したムービーを見ることが出来、この「Sputnik」のまだ制作初期段階でこんなことを言っています。
この作品の背景には、50年代後半にロシアが打ち上げたスプートニクという宇宙開発競争がありますが、それに加えて、ビッグデータ企業の宇宙開発競争があり、各社が宇宙で最も強力な場所を確保しようとしています。この曲では、人工衛星と私たちの情報が宇宙空間で飛び交っている様子を想像しています。
つまり米ソが競い合うように開発した時代の象徴ともいえる「Sputnik」というタイトルには、今度は米ソではなくGAFAやスペースXといった企業間の競争に移行していっていることを表している、そうした意図があったということで、なかなかよく考えるなぁと思います。
まるまる1曲Google「Don't be Evil」
あとは1枚目の2曲目「Don't be Evil」ですね。これは2015年には取り下げたそうですが、有名なGoogleのモットーです。つまり1曲まるごと使ってGoogleの歩みを描いているという意欲作なのですが、これも彼女自身が制作にあたりこんな痛烈な言葉を発しております。
私はこの作品のビジョンがあったので、それに忠実に取り組みました。ただ作品全体を聞いて最初とてもキュートに聞こえてしまい、不吉に聞こえなかったので、本当に狂ったようなビブラートをかけてほしいとお願いしました。これが実に役に立ちました。つまりGoogleや彼らのやっていることには何の面白みもありませんが、私は彼らをからかっているのです。もし彼らが「悪になるな」と言うのであれば、彼らは本当に自分たちが悪になる力を持っていることを示すべきです。
この言葉に出ているように「Don't be Evil」とタイトルに付けておきながら、サウンドはダークそのものという、なかなかに痛烈です。冒頭どこか調子外れな音を出しつつ全体的にファニーなサウンドが出てきます。聞いていると、ガレージに籠って検索エンジンの開発に勤しんでいただろうラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンの姿が見えてきそうです。まだ世の中の人間が相手にもしない小さな小さな会社で二人はひたすら開発に打ち込み、時に驚くような機能を、時に馬鹿げたようなアイディアも実装していく。やがて二人が開発した検索エンジンはインターネットの世界で広く使われるようになります。そしてそこにAdWordsという画期的な広告の仕組みを導入したことで一気に巨大企業への道をひた走るように。気づけばサウンドにおいても冒頭部の調子外れな音は鳴りを潜め、とても洗練されたサウンドになっています。その後巨大企業となったGoogleは検索だけに留まらず、メール、地図、カレンダー、動画等とその勢力を拡大し続けます。時に高額な報酬で技術者を雇い、時に会社ごと買収をするという形で。そんな巨大企業となったGoogleを彷彿とさせるようにサウンドも冒頭の頃の軽やかさがすっかり消え、いつの間にか重厚なサウンドに置き換わっている。やがて静かなピアノソロに入ります。淡々と弾いていくがやがてバンドのバッキングと共にそのフレーズが乱れていきます。そう、2012年、GoogleはAIにより機械に猫の画像を認識することに成功、ディープラーニングという手法を用いているということが分かり、その手法を効率よく実装出来る「Tensroflow」といったAIの技術もオープンにし、世界中の技術者が嬉々としてその技術を使い始めます。世界はついにAIという技術を手にするようになった。しかしこの喜びとどこに向かうか分からない不安、アンビバレントな感情を表すようにサウンドも盛り上がりつつ収束し、最後は未解決なままぶちっと終わる。
なんだか旧劇場版のエヴァンゲリオンを見た後のような、なんともいえない後味の悪さ。いや、かっこいいんだけどさ、でもなぁ。。。多分この後味の悪さを感じさせる為にこの曲を作ったんだろう、そう思う。
1枚目から一転、苔むす庭に陽の光が差し込む2枚目の1曲目「Sanzenin」
1枚目が現代社会の陰の部分を表したとするなら、2枚目は陽。なんだけど、これがまたセンスの良い始まり方をする。Maria Schneider氏の伝統芸ともいえるブラスと木管の混ざり合ったサウンド、人間の呼吸がそのまま音になったかのような不思議な透明感溢れるサウンドに鍵盤ハーモニカの軽やかなアドリブソロが重なる。これが実に写実的で、三千院の苔の緑に陽の光が差し込んでくる、その様がありありと思い浮かぶ、これぞ芸術という素晴らしい作品になっています。

実際にその分野で仕事をしている立場から
さて、あとは実際に聞いて頂くとして、ここからはちょっと私なりに感じたことをまとめていけたらと思います。私自身、実は企業のデータ活用の分野でシステム開発の仕事をさせてもらっています。俗にビッグデータなんて言われるようなデータを扱ったりもしますが、それ故に世間で言われているような安易なAI脅威論には正直辟易することもしばしばあります。またそういったことを周囲に吹聴しながら名をあげたりお金を集めたりしている人も知っているので、これも正直に言ってしまうと「マリア、お前もか・・・」と思ったりもしました。一方、マリア・シュナイダー程の人が久々のリリース作品にこのテーマを持ってきたということ、そこに何らかの意味があるのではないか?と思ったのも事実です。
構造主義と「別の可能性」
彼女は一体何を感じたのか?まず、この作品が「現代社会」をテーマにしている以上「現代をどのように捉えるか」そこが出発点になると考えました。そこで私はこれを「構造主義」の考え方から紐解いていくことにします。
もしかしたら今も多くの人が現代というものを進歩主義の進んだ先の姿、すなわち「ある社会(例:欧米的な社会、西洋の社会など)を模範とし至らない点がある場合はそれを改善していくことでやがて模範的な社会になる」そんな風に心のどこかで思っていないでしょうか?これに関して、フランスの社会人類学者、民族学者である「クロード・レヴィ=ストロース」という方が【構造主義】という考え方を打ち出し、明確に否定します。以下は2007年の知恵蔵の記述です。
戦後主にフランスで展開された20世紀を代表する思想の1つ。文化人類学者のレヴィ=ストロースを創始者とする。社会と文化の根底にあり、それを営む当人たちにも明確に自覚されていない構造を取り出す分析方法が構造主義である。レヴィ=ストロースは、近親相姦の禁止の背後には、女性の交換という構造が存在していることを明らかにした。女性は近親の男性と結婚することが許されず、他のグループの男性と結婚しなくてはならない。このことによって、グループ相互の女性の交換を通じたコミュニケーションが成立し、社会的なつながりが維持されるのである。こうしたレヴィ=ストロースの分析は、私たちの自覚的な意識や主体性に、いわば、無意識の秩序が先行していることを示している。この主張は、サルトルやヨーロッパ近代哲学が重視した主観や意識を批判する思想運動につながっていく。またレヴィ=ストロースは、『野生の思考』(1962年)で、それまで未開とされていた文化のなかにも緻密で秩序立った思考が存在することを示す。この意味で、彼の仕事はヨーロッパ文化の絶対性(ヨーロッパ中心主義)を批判する文化相対主義にも大きな影響を与えた。ただし、レヴィ=ストロース自身は、近親相姦の禁止のように、どのような文化にも共通する構造が存在することを認めており、たんなる相対主義者ではなく、普遍的な人間性を探求する意思をもっている。
つまりそれぞれの文明や社会の在り方は根底に共通した構造を有しつつ、そこからそれぞれ最適な在り方を模索することで社会や文明を構築しているというわけで、西洋近代文明もあくまで在り方の一つに過ぎないというわけです。この在り方の違い、これは現代でも話題になっている【多様性】というキーワードにもつながってきます。
一方我々が生きる現代社会は、30年後か50年後か100年後かは分かりませんが、今は人間が行っている仕事もAIやロボットに代替あるいはサポートを受けながら行っていく、そうした社会になると言われています。しかし先程の構造主義の考え方に則ればこれもまた在り方の一つといえるわけで、ならば「違う在り方もありえるのでは?」という問いも立てることが出来ます。
そもそも同じ地球上に生きていながら、何故そうした在り方の違いが生まれるのか?ニーチェの「神は死んだ」という言葉に象徴されるように、我々が生きている今の時代は「何が正しいか」ということが極めて曖昧な時代と言えます。それは「科学が神の代替になり得ないこと」にも繋がってきます。今、まさにコロナという未曾有の疫病に襲われていますが、「自分達の社会がたった1つの未知のウィルスにここまで揺るがされるものなのか」ということを一度は皆感じたのではないでしょうか?。更に言えば10年前の東日本大震災、25年前の阪神大震災、自然の前に為す術なく沢山の人間の命が一瞬で奪われていく。その圧倒的な理不尽と現実を前に自分達が生きているこの社会がいかに脆弱なものであるか、そんなことを一度は考えたことあるのではないでしょうか?
このような世界において、先程の問い、つまり「別の在り方」とはすなわち「別の可能性」と同義ともいえるわけです。何が正しいのか分からない以上、様々な在り方を許容することが生存戦略上の最適解ということです。
「別の可能性」とMaria Schneider
そのように考えるとMaria Schneiderという現代最高峰と言われるラージ・アンサンブルコンポーザーが、このタイミングで「Data Lords」というタイトルのアルバムを、しかも異なる世界観をもった2枚組のアルバムとしてリリースしたこと、これが彼女なりの「別の可能性の提示」なのではないか?と思えてくるわけです。
そして、わざわざ【構造主義】を持ち出してここまで話を進めてきたのは、ジャンルこそ違うものの同じく現代最高峰と言われる小説家「カズオ・イシグロ」が6年ぶりの新作として、同じく「AIと人間」をテーマに据えた作品を出したという話が入ってきたからです。
これが単なる偶然なのかシンクロニシティというべきものなのかは分かりません。ただどちらも現代最高レベルの感性をもった芸術家であることを踏まえれば、何かこの現代における普遍的な構造を感じ取ってそれぞれ作品という形で世に出した、そんな風にも思えるわけです。
いかがでしたでしょうか?今日はグラミー賞の発表があったということで、Large Ensemble部門とINSTRUMENTAL COMPOSITION部門に2冠となったMaria Schneiderさんの最新作「Data Lords」について、制作過程のインタビューや私なりの考えを交えながら深堀していきました。以上、ビッグバンドファンでした~、ばいばい~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
