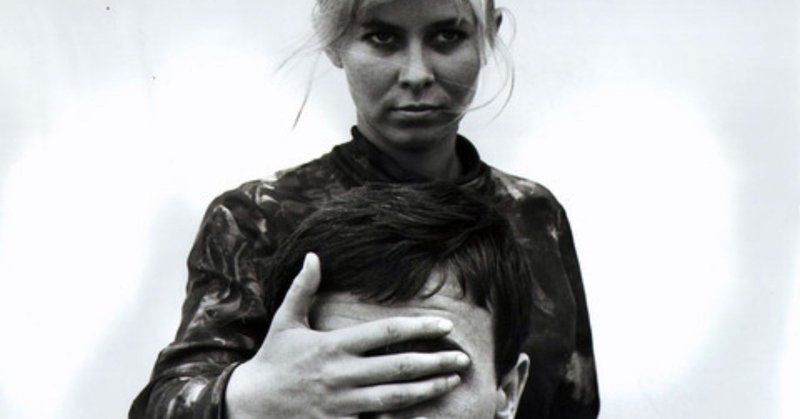
口が減らないイエジースコリモフスキー
好きな監督なんですよ、イエジースコリモフスキー。
ホントかウソか分かりませんが、ゴダールが「やけっぱちのヌーベルヴァーグ」と評した「バリエラ」なんて、好き過ぎて週に3回見に行ったくらいだから、「彷徨える反逆児」とも呼ばれるスコリモフスキーの力量は高く評価しているんです。
ただ、わりと最近になってからのインタビューで、「私の心の中にはいつもチブルスキーとクシシュトフコメダがいます」って言い出したの、オマエそれホントだな?ってちょっと眉に唾つく感じ。
チブルスキーの名前を出しておいたら自分的に有利だなって思惑が見え透いているみたいで、あまりこの発言は好きじゃないです。
おそらくクシシュトフコメダに関しては本心でしょう。
先にクシシュトフコメダの説明をします。
この方、当時のポーランドでは反体制とされていたジャズの演奏家です。
これもまたちょっとアレなんですが、東欧のミシェルルグランと呼ばれるほどの人物で、たくさんの映画音楽を残しています。
一番メジャーな作品では、ロマンポランスキーの長編第一作、「水の中のナイフ」でしょう。
このミニマムな作りの作品にはあの音楽がないと成立できなかったと思うほどの傑作です。
ただ、クシシュトフコメダもあまり長生きできず、70年代半ばにアメリカで亡くなっているはずです。
だから、それをもってのスコリモフスキーの発言なんですけれど、おそらく彼ら3人を結びつけたのは、アンジェイワイダが撮った「夜の終わりに」だと思うんです。
この作品は素晴らしいですよ。
ポーランド映画のどことなく漂うポリティかリズムが払拭された、単純におもしろい作品です。
コメディ映画ではもちろんありませんけれど。
ま、簡単に言ってしまうとワンナイトの話なんですけれど、アンジェイワイダは反体制と分かっていて確信犯的にジャズを主題に据えた作品作りをしたんです。
まったく、どこまでも抵抗する監督です。
ジャズと言えば当然、クシシュトフコメダが担当します。
チブルスキーも主人公の友人として出演しています。
で、若者言葉の指導って名目で、当時脚本家見習いかなんかだったスコリモフスキーが起用されているんですけれど、また言っちゃうんですよね。
「自分も拳闘選手の役で出たい」って。
アンジェイワイダがどう思ったかは知りませんが、スコリモフスキーの願いは叶って、拳闘選手の役でちょこっと出演しています。
そうやって考えるとこの作品は50年代のポーランド映画のオールスターキャストと言えるんじゃないでしょうか。
ポランスキーも脚本を担当していたはずです。
ちょっとテイストはズレますが、日活の「幕末太陽傳」みたいなもんですね。
「夜の終わりに」で一番オイシイ思いをしたのは、スコリモフスキーだと思うんですけれど、彼も祖国を追われて、世界中を彷徨い映画を撮り続けていました。
近年、再評価されて来ているみたいでうれしく思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
