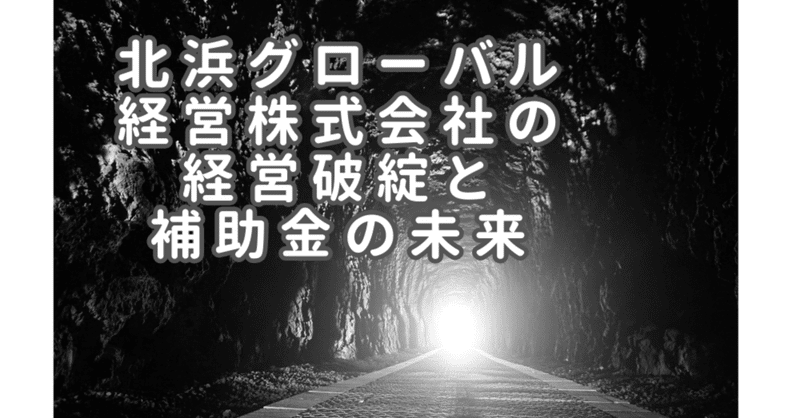
北浜グローバル経営㈱の破綻と補助金の未来
なぜ北浜グローバルは破綻したのか?
激震が走ったニュース
本日、補助金界隈に激震が走りました。
事業再構築補助金の支援では民間コンサルとして最大手といってもいい、北浜グローバル経営株式会社が経営破綻(自己破産)しました。
記事によれば、破綻の原因は審査の厳格化により、補助金の交付遅れ、補助金交付の却下などが増加したこととなっていますが、そうだったのでしょうか?

もう少し記事の中身を見てみると、2020年の売上が2.2億だったものが、事業再構築補助金の支援で急成長し、2023年には35.8億へ売上が10倍超となったと書かれています。
急成長にあわせ、豪華なオフィスに移転し、金融機関と提携し集客を行う、集まった案件をこなすために多くの従業員を雇用する。こうして、売上と企業規模、そして家賃や人件費などの固定費も大きくなっていきます。
当然、営利企業ですから成長=売上増加が悪ではありません。右肩上がりに案件が増え続け、補助金の採択により、想定通りに報酬が入ってくれば問題は起こらなかったはずです。
破綻の要因は・・・
しかし、幸か不幸か、長引きはしましたが、3年の時を経てコロナはほぼ終息し、2023年から補助金の潮目も変わりました。
・事業再構築補助金事務局そのものがポンコツで交付審査が遅々として進まなかったことに加え、
・交付審査の厳格化(介護や医療、障がい福祉関係の採択案件については過去にさかのぼった採択の取消、手引きに載っていない大量の資料要求とこれによる審査の大幅な遅延など)があり、
・さらに第11回の採択率は過去最低の20%台まで落ち込むなど
潮目が変わったことにより、補助金の支援報酬に売上の多くを依存している場合、高い固定費を維持することは困難になりました。この辺りが破綻の原因でしょうか。
北浜グローバルの事業再構築補助金支援実績
では、売上の中心だったと思われる北浜グローバル経営の事業再構築補助金採択状況を見てみましょう。

採択件数の最高は第8回の74件、採択率は58.3%と悪くない数字です。ただ、この数字は、認定支援機関に北浜グローバル経営がなった案件だけの件数です。提携する金融機関からの依頼で実質的には北浜グローバル経営が支援をし、認定支援機関は金融機関がなっているケースも含めれば、この数倍の支援実績があったでしょう。そうでなければ35億という売上が達成できるはずがありません。
ちなみに最高の採択件数74件を叩き出した第8回の採択結果発表は2023年4月です。この辺りが、今考えればですが、潮目だったでしょうか。
第9回も第8回同様127件を支援するものの、採択件数は45件にダウン。さらに第10回は150件を支援するも採択件数は半減して23件、採択率は15.3%。
第11回も109件の支援で採択は26件にとどまります。
この間、膨らんだ固定費の削減努力をされたのかもしれませんが、今回の経営破綻となった要因はやはり、
補助金の潮目が変わったことで、補助金支援業務の採算性(採択率の低下、報酬着金までの長期化や必要な工数=人件費負担の増加)が急速に悪化し、高止まりした固定費が吸収できず赤字となり、今後も改善の見通しが立たない
ということになると思います。
特定の企業を指すわけではないですが、北浜グローバル同様に、コロナ禍の事業再構築補助金等の補助金支援業務の増加の波に乗り、大幅に業容を拡大した企業もあるでしょう。上場を目指すという景気のいい話も聞こえてきます。
大幅に業容を拡大せずとも、多くの事業再構築補助金を扱う認定支援機関の採択件数は第8回あたりまでがピークで、その後急減しているはずです。直近の第11回の採択率は過去最低の20%台まで落ち込んだことを踏まえれば、それもやむをえません。
案件を選んで受注できる環境、または採択されやすい業種(製造業等)が多いなどの状況でない限り、全体の採択率に引っ張られる形で、多くの支援機関の採択率が低下しているのが現実ですが、これを踏まえて、補助金を利用される企業も、それを支援する側の支援者も前を向いて進んでいく必要があります。
北浜グローバル破綻の余波
少し話はそれますが、今日はこの経営破綻のニュースを受けて、提携していた金融機関にも大変な混乱が広がっていると思います。
私も数年前までメガバンクにいましたが、業績評価項目のひとつとして、ビジネスマッチングというものがありました。
しかし、このビジネスマッチング、当然、紹介はしても最後はお客様同士の取引なので、仮に紹介した先が破綻しても銀行には法的な責任はないですが…そうはいっても、売掛金が回収できなくなったお取引先の企業としてはこう思うはずです。
「銀行が紹介したから取引したのに…なんてところを紹介してくれたんだ!」
ということで、本当は一番ビジネスマッチングを必要としている業績が厳しい先=売上不振先(格付でいうと要注意先以下など)には紹介しにくいのが現実です。
その金融機関にとっては避けたい事態、紹介先の破綻がまさに起きてしまいました。
多少救いがあるとすれば、銀行が紹介したであろう先は、補助金の申請事業者であって、北浜グローバルが倒産したからと言って、売掛を払ってもらえないという面での実害(売掛金の回収不能)が発生しているケースは稀でしょう。
しかし、採択されたものの交付申請途中で(本当はダメですが)作業を北浜グローバルに丸投げしている方、同様に実績報告が途中の方などは、今後、北浜グローバルの支援は見込めないわけですから、当然、想定していない負担を強いられるわけです。
そういう意味では、金融機関としては紹介先に対して連絡を入れて、状況説明、今後の対応に追われることになっていると思われます。
北浜グローバルの従業員は同業に転職できるか
ちなみに、ここで企業の被保険者数を調べることができますが、北浜グローバルの被保険者数は226人。コンサルとしてはかなり多い方です。

当然、法人の自己破産ですから、お勤めの方は解雇となると思われますが、同じような補助金支援を行う同業に転職ができるでしょうか。
結論としては、同業も補助金支援業務による売上や収益性が悪化している状況は大きく変わらないわけですから、多くの方にとってはかなりの困難を伴うと思われます。
腕に自信がある方については、本来の利用方法ではないですが、認定支援機関の検索システムを転職サイトのように使って、支援件数上位かつ採択率や採択件数が直近でも落ち込んでいない企業等を見つけ出し、アプローチをかけるのも良いと思います。
私は接点はないですが、同じ大阪で上場も視野に入れている株式会社Staywayさんなんかは、全方位採用中なので、チャンスがあるかもしれません。このくらいの情報しか提供できませんが、北浜グローバルにお勤めだった方、応援しております。
北浜グローバルの委託先(下請先)はどうすべきか
もう1点、北浜グローバルもかなり自社で従業員を雇っていましたが、一部の支援業務は外注を使い対応していたと思われます。
契約内容によっては、業務は行ったものの、報酬がまだ支払われていないケース(北浜グローバルに売掛金があるケース)もあるでしょう。
この場合、委託先が売掛金を回収できるかと言うと、
・2023年の段階で借入が20億ある(帝国データより)
・業種柄、売掛金(未回収の支援報酬)を除き、換価できる資産(不動産等)を保有しているようにも思えない
・足元は赤字と推測
・従業員数が多く、労働債権も多額と推測
・売掛金も契約内容(交付決定時の請求等)によっては請求できないケースも考えられる
などの理由で、ほぼ破産配当はなく、回収が難しい状況と私は考えます。
民事再生などの再生型の法的整理であれば、多少回収率は期待できますが、残念ながら、それもかなわないくらい再生シナリオが描けなかったということだとすれば、ほぼ一般債権への配当はないものと考えたほうがよさそうです。
では、自分がその立場で、なんとか回収すべき方法はないかと考えるなら、北浜グローバルが経営破綻した今、補助金の申請者(事業者)にアプローチして支援契約を結ぶということをやってみますかね。
想像にはなりますが、北浜グローバルが外注していたのは、申請時の計画書の作成サポート、ヒアリングシートなどを元に10ページ~15ページ程度の計画書のたたき台を作成する業務でしょう。
北浜グローバルが正常な状況であればルール違反ですが、この状況下であれば、委託先は当然にサポートした企業が特定できるわけですから、直接連絡を取り、以後の支援業務が受託できないか交渉するのはありでしょう。
(もちろん業務委託契約書及び破産管財人への確認を行った方がベターです)
突然、認定支援機関がいなくなってしまう補助金申請者にとっても、計画内容を理解している支援者からの提案であれば、全く状況をわからないコンサルよりは、受け入れやすい面もあると思います。
補助金申請者のためにも外注を受けていた委託先の支援者におかれましては、補助金申請者のサポートを行いつつ、回収不能分を取り返す方法を探ってみてください。
そもそも経産省系の補助金はどうなる?補助金の未来は?
最後に今後の補助金はどうなるの?ということですが、下記で書いたように、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、事業承継引継補助金は事実上終了、IT補助金もあと数回の公募で終了でしょう。
すべては、年度内に補助金の支給まで終わらせる運営に切り替わったことで、通年での公募が見込めなくなっています。
(生産性革命推進事業の予算が大幅に余るので、追加公募の可能性はゼロではないですが…)
また、近年は50%前後で推移していたものづくり補助金ですが、直近の17次はオーダーメイド枠の採択率は29%と過去最低を更新しています。



通常枠の募集がなかったとはいえ、採択者数は16次の1割程度、採択者数に至っては同6.7%と大幅な市場縮小に見舞われている状況です。
補助金については都道府県や市区町村の補助金はある程度残ると思いますし、来年度以降、経産省系のメジャーな補助金がゼロになるとまでは考えていません。
しかし、予算の減少に加え、ものづくり補助金などで行われた申請要件の厳格化及び採択率の低下傾向は変わらないでしょう。
ジョークのような話ですが、事業再構築補助金などの補助金支援業務を主軸としていた支援企業自身が、売上の減少要件もなくなったこともあり、事業再構築補助金を活用せざるを得ない状況になっているともいえます。
そんな中ですが、先ほど挙げた株式会社staywayの補助金クラウドや、Nontitleで注目を集めたHOJOJOなど、新しい発想、アイデアで補助金支援業界をリードしそうな企業もでてきています。
全体感としては、引き続き、補助金支援の業界は厳しい環境が続きますが、コロナも明けたように、生き残れば、きっとその先には光が見えてくると信じて、今日も頑張って1日を過ごしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
