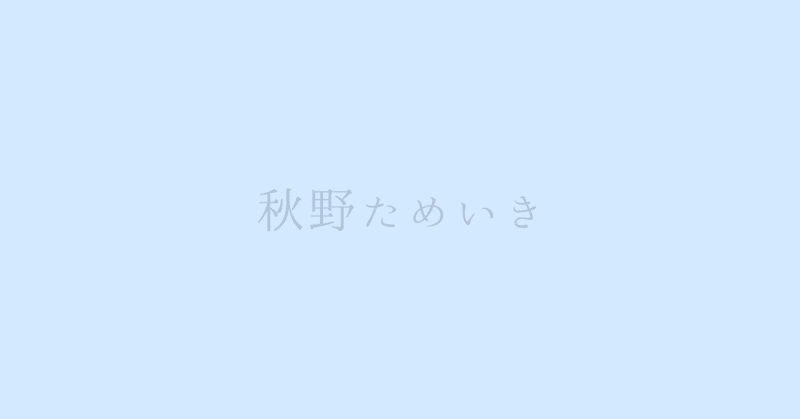
誇り高きクレープ屋店主とその作法
始めた時は特に深く考えていなかったが、最近このnoteは自分の中で、普段の自分とまるきり乖離したもののように感じている。
架空のだれかが、誰に届けるわけでもなく、自分のためだけに放送しているラジオに、たまたま周波数が合って、たまたま興味を持ってくれた人が、寝る前にこっそり聞き耳をたててくれるような存在だったらいいなと思うようになった。
それはきっと、記事を書く時、きまって音楽を聴いている影響も大いにあるだろう。
せっかくなのでよりラジオらしく、書く時に聴いていた曲を載せようと思う。
(気恥しいので、もう二度と載せないかもしれないです。)
1.
幼い頃からクレープという食べ物が好きだ。
小学3年生くらいから、中学受験の勉強を開始した。
教育熱心な母の願いも虚しく、自分はすぐ拒否反応を示した。学ぶことへの興味はあったが、それ以上にぎゅうぎゅうの部屋で誰かの話をじっと聞いていられない子どもだった。
ただ、当時口がうまかったので、さぼる口実を見つけては母を連れ出していた。
自分が暮らす街にはクレープ屋が2つある。
昔から変わらず、2つある。
自分はそのうち、大きな建物の中に入っているお店に母とよく行った。
青を基調としたお店で、ジェラート屋も兼ねているためクレープ屋にしては店内が広く、必ず母とテーブルを挟んで腰掛けて食べた。
当時まだ背の小さい自分はその高い椅子に背伸びして登るのが、特別な場所に来たようで楽しかった。
自分はクレープの包み紙を必ずぺりぺりと剥がしながら食べた。母はごみが出ないよう少しずつずらして食べる方法を教えてくれたが、クレープとともにあったものが目に見えてなくなっていく方が食べていて楽しかった。
夕飯の買い物のついでに立ち寄ることもあった。
そういうとき、母は決まって「こんな時間にこんなもの食べたらごはんが食べられなくなるよ」と言った。
そう言いながら、お決まりのバナナカスタードチョコを頬張る母はいつも楽しそうで、自分はその姿をいつまでも眺めていた。それが自分のささやかな幸せだった。
両手いっぱいになったばらばらの包み紙をごみ箱に運ぶまで、その時間は守られた。
クレープは幼い頃の自分にとって、息抜きの口実、母と過ごす少し悪い時間のお供という、当時の自分を癒す存在にほかならなかった。
結局、自分はその後中学受験に合格し、そのまま大学受験も経て同じ女子校に10年間通い、大学4年目の春、中途退学することになる。
それだけでも母は全く違う感性を持って生まれた娘に戸惑い、当時、自我の強さと、それに相反するように周りとの違いを自責するセンシティブな部分の同居をまだうまくコントロールし切れなかった自分を理解できず、許せなかったと思う。
当然親としてひどく落ち込んだのに、その上まさか娘が成人してからエンタメの道を志し、さらにお笑い養成所に通うなど、当時思いもしなかっただろう。
今も思うことはたくさんあるだろうに、近くで楽しそうに笑いながら一番の味方でいてくれている。
母と通ったクレープ屋はいまも同じ建物内に存在するが、場所を移し規模が大幅に縮小してしまった。
自分の思い出はあっけなく姿を変えた。
あの背の高い椅子に登ることは二度となくなってしまったのだった。
家までの帰り道一緒に食べることは今でもあるが、あの空間がなくなるとわかったとき、得も言われぬ喪失感におそわれた。
自分のなかでのクレープ屋の記憶は、長い間そこで止まっていた。
それが、最近になってまた動き出したのだ。
2つあるクレープ屋のうちのもうひとつ、外に店舗を構え、のぼりを立ててワゴンのような佇まいのその店は、いつも同じ、ひとりの番人によってかたく守られ、どんなときも営業している。
その店には、誇り高きクレープ屋店主がいるのだ。
幼い頃一度も行かなかったというわけではない。何度か心移りしたことはあったが、いつもあの青いクレープ屋に戻っていた。
青いクレープ屋がしっとり柔らかい生地なのに対し、ワゴンのクレープ屋はぱりぱりの生地だ。
最初にひとりで訪れたのがいつだったか、もう覚えていない。
ただ、そのときも不思議と一人で立ち寄ってみたくなったのだ。
2.
手術の帰り道、雨がやんで肌と外気の境があいまいになった夕方、ふらりとクレープ屋に足を運んだ。
彼は来客の気配を感じると、すっくと立ち上がって姿勢を正して待っていた。
ポロシャツのボタンを2つ開け、所々ほつれたベージュのズボンに裾をしまい、色あせた革のベルトをきっちりしめている。
メニューを見て悩むあいだも静かに待っていた。
「えっと、バナナチョコスペシャルを、お願いします」
「バナナチョコスペシャル、かしこまりました」
勇ましく、それでいて落ち着いた声でそう言うと、無駄のない動きで大きな鍋から生地をひとすくいし、鉄板に流した。
自分はこの時間がいちばん好きだ。
他のお店は皆、生地を流して、少ししたら裏返し、すぐまな板に移す。
彼は違う。
生地を鉄板に流し、すばやく円を描いてから、必ず「気をつけ」の姿勢をとるのだ。
腕を体の横にあて、生地をじっと眺める時間が存在する。空気が張りつめる。
初めて見た時は驚いた。生地をただ凝視している。私はその姿を見つめている。時間が止まったんだろうか?
違う。彼はその時をじっと待っているのだ。
彼の中で、今だ、というタイミングで、華麗にパレットナイフを滑らせる。
一度まな板に置いたあと、両手で生地の端を持ち、破れないように慎重に、ひらひらと冷ます。
バナナを房からひとつ取り、皮ごとナイフを通して半分に切ったあと、剥いた皮を目線はそのまま最短距離でゴミ箱に投げ入れる。
それがあまりに綺麗なので、おお、と声を出しそうになるのをぐっとこらえる。
切ったバナナを生地に乗せ、生クリームをしぼる。
これはこの日初めて気が付いたのだが、彼は、生クリームを寝かせない。
ショートケーキやパフェと同様、縦にうずまいて絞るのだ。
どうせ最後には包んでしまうのに、なぜあんなに美しく絞るんだろう?
ハッとした。
彼は、ただ、その姿を目の前で見ている私に対してのみ、全ての動作を美しくしているのだ。
彼はこの時間をショーと捉えている。
彼にとって厨房は舞台で、私は観客なのだ。
彼はいつだってエンターテインメントを提供しているという自覚があるのだ。驚いたと同時に、感銘を受けた。
何と気高いのだろう。
隣の冷凍庫からアイスクリームのパックを取り出し、力を込めてがりがりと削る。
このクレープをスペシャルたらしめている存在をそっと生地に乗せる。
最後にチョコレートソースを高い位置から絵を描くようにかけると、生地を半分に折りたたみ、くるくると筒状にまとめる。
彼の最後のこだわりとして、紙の巻き方にも細心の注意が払われる。
できる限り中の具材が美しく、上の部分がお花のように広がって見えるようにちょうどいい位置をしっかり見定めてから、するすると紙を巻く。
紙を巻いたあとにもう一度飾りのホイップを3か所にバランスよく配置し、スプーンと紙ナプキンを添えて手渡してくれる。
「生地がぱりぱりのうちに、お召し上がりください。」
この文言を口にする瞬間の力強いまなざし。
最後の最後まで手を抜かない彼の誇り高きパフォーマンスに、自分は心の中で立ち上がり、拍手を送る。
たいして言葉を交わしていないのに、彼がこの仕事がたまらなく好きで、それをこの地で続けることに誇りを持っていることがひしひしと伝わってくる。
誰に届けるわけでもない。
ただ、彼の誇りは彼の高潔な精神によって、長い間守られている。
自分はそれを、この瞬間だけはこの世で最もたたえられるべきそのパフォーマンスを、一瞬たりとも見逃さないように、ワゴンの開かれた扉からそっとのぞきこんでいる。
それが私にとっての、彼に対する精いっぱいの礼儀であり、心からのリスペクトであり、その作法であるからだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
