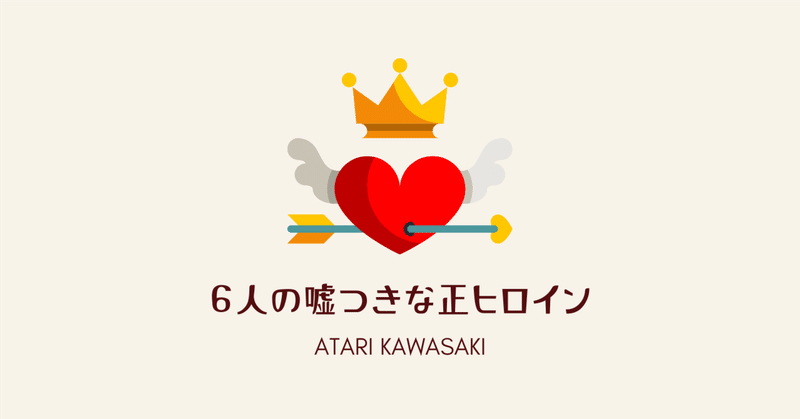
5 金持ちに調理実習は必要か
ところで、大都学園は進学校だ。
高校二年ともあれば受験も近いため、特に後期は勉強漬けになる。そのため、実習系の授業は前半に詰め込まれているらしい。なるほど、僕がこのタイミングで転校させられた理由もここにあるかもしれない。座学ばかりでは、クラスメイトとの親交はなかなか深められないだろう。
四時限目は調理実習で、この日はそのまま昼食も兼ねるとのこと。
先生により勝手に班分けされ、僕は誰と組もうかなとさまようことがなくて安心した。というか、おそらくこの班は何者かによる恣意的な強制力が働いている。
僕の班は四人で、僕、鐘梨珊瑚、独田苺、宮仕夢羽だった。ちなみに僕は二年三組。そのクラスのフィアンセ候補は、彼女たち三人で全員である。
「ええ、怜ちゃん包丁めっちゃ使えるやん。いいお嫁さんになりそやわ〜」
「お婿さんだろ」
王沢であれば、日々の一つ一つが優雅であって当然だ。
僕は高いところから包丁を振り下ろし、とんとんとーんと小気味よく皮の剥かれたにんじんを乱切りに捌ききった。なんとなくオリーブオイルを大量にかけたい衝動に駆られるが、残念ながら今日の材料にはないようだ。
その様子を珊瑚は楽しげに見てくれているが、少し不思議そうでもあった。
「なんや怜ちゃんってお坊ちゃんなんやろー? 料理ができるなんて意外やわ」
「うちは母子家庭なんだ。だから僕が料理する機会も多かったし、それに今だって月夜と一緒に住んでるんだけど、料理は全部僕だね」
「月夜くん付き人ちゃうんかい。てゆーか怜ちゃん母子家庭なん? まぁそらそやろなぁ。怜ちゃんのお父さんって、お母さんと結婚してもないんやろ? ちょっと上流階級の人のやることは庶民にはわからんわ」
「まったくその通りだよ。僕も父こそ有名人だけどさ、結局ずっと庶民としてくらしてるわけ。もう理解できないね」
「えー思ってたよりずっとウチら似てるとこあるかもやわ。嬉しいわぁ」
珊瑚はくしゃりと笑った。その飾らない笑顔は見ているだけで結婚後が想像できる。フィアンセ探しをしている身としては、どうしても結婚後の生活も意識せずにはいられなかった。
喋りながらも、珊瑚の料理の手際もとてもよかった。包丁で手元もあまり見ずにじゃがいもの皮を器用に剥いていく。剥かれた皮はとても薄く、ジャガイモの凹凸の本当に表面のみを剥がすのは本当に見事だ。
「上手だな」
「うち貧乏子沢山やねん。怜ちゃんと一緒で単純にする機会が多くてな、どんどん指先が器用になんねん」
「そうそういえば、イラストも上手だったな」
「せやろ〜。言わせたったわ」
言わせた、と言いながらも彼女はとても嬉しそう。珊瑚と喋っているときはいつも穏やかな気持ちになるなぁと、僕は感心した。
「ちょっと〜珊瑚ばっかりイチャイチャしてずるいであります!」
「いまはウチがいちゃいちゃする順番やね〜ん。苺も夢羽も朝イチャイチャしとったんやから、調理実習の時くらい遠慮しいや。夢羽もええやろ〜?」
夢羽はこくこくと頷いた。
それにしても、なぜか夢羽の前には大量の野菜が置かれている。僕たちの班のカレーとサラダにはいささか多いと思うのだけど、この野菜はどうしたのだろう。
見ると、夢羽はものすごいスピードで野菜をカレーの具材に変質させ、あるいはコールスローに生まれ変わらせていた。そして出来上がったそれを銀のバットに積み上げると、他の班へと運んでいる。「ありがとー」とお礼を言われ、彼女は「得意ですから」と頭を下げていた。初めて彼女がまともに喋った声をきいたかもしれない。というか授業の課題を奪うなよ。
「なんやねん、せっかく家庭的なとこ見せて怜ちゃんの得点稼ごうと思ーたのに、めっちゃすごい子おるやんけ」
「家庭的の領域を超えている気がするのであります」
ところで苺はと言えば、玉ねぎを切ろうとして皮の上を包丁が滑っている。やや手つきが危なっかしく、あまり料理は得意でないのかもしれなかった。
出来上がったカレーを一口食べると、僕は唸った。
「美味すぎる。なんだこれは」
そもそもカレーなんて、大抵の場合同じような味に仕上がるはずだ。なぜならば、市販のルーを使った場合、カレーは市販のルー味にならざるを得ない。それはすでに大抵の日本人の味覚にマッチするよう調整されており、当然美味しいと感じるのはわかる。
しかし、こんなに香り豊かになるものだろうか。
僕と一緒に震えている奴がいた。苺だ。
「美味しいであります。家庭科でこのレベルのカレーが作られるだなんて……」
震える僕と苺に、珊瑚が言った。
「野菜や。このカレーには具の野菜の他に、ペースト状になるまで刻まれた野菜が入っとる。にんじん、玉ねぎ、にんにくや。それを、あえて焦がすように炒めてから市販のルーを少なめの水で伸ばしとる。このカレーはただの水溶きルーと一線を画しとる。香味ペーストベースドカレーや!」
ばばん! と珊瑚が言い切った。
「この短時間に、そんなことが可能だなんて」
「ほんまに恐れ入るわ。ある材料でこれだけの工夫をしはるんやから」
どこにでもあるカレーの材料から至高のカレーが生まれるだなんて、まるで錬金術だ。そして、そのカレーを作った立役者はといえば、恥ずかしそうに俯いてスプーンを口に運んでいた。
「びっくりしたよ、こんな特技があっただなんて。なぁ、夢羽」
ふと、スプーンを持つ手が止まった。
どころか、そのスプーンが震え出し、「……ヒッヒッヒ」と特有の泣き声が調理実習室に響き渡った。
いや、なんでだよ……。
「なんなの? そんなに僕が怖い?」
「怜くん、圧迫面接はそこまでであります」
「……ううむ」
僕だって普通に夢羽と喋りたいだけなのに、それができないのはもどかしい。
「ほら、夢羽ちゃんはあっちの席に移動するであります。怜くんと離れれば落ち着くでありますよ」
そういって、苺と夢羽は別の席にいってしまう。
「怜ちゃんは気にする必要ないと思うわ。ただ夢羽ちゃんと相性悪いだけやねん」
「そうなのかなぁ」
釈然としないが、僕の前だと毎回泣いてしまう子なのである。その言葉は否定できなかった。
「まぁそれならそれでよかったやん」
「んん、何が?」
「だって怜ちゃん。フィアンセは一人に絞るんやろ? みんな同じくらい好きー言うて、みんなと付き合うたらあかんで」
「そんなことしないよ!」
「ふふ、信じてるわー」
僕は再びカレーを口に運ぶ。……美味すぎる。
ともかくとして、確かに珊瑚の言うことは一理ある。この『王沢の伴侶選び』は、少なくとも前半で言えば少女の中からもっとも好きな子を探すゲームではない。むしろ、絶対にうまくいかない子に別れを告げるゲームだ。
もし夢羽が、例えば親からこのゲームへの参加を強制させられているとして、そうであれば早めに別れを告げてあげることこそが一番の優しさだろう。
食事が終わり、お皿を洗う。汚れのついたお皿がツルツルになっていくのは気分が良くて、僕は結構この作業が好きだ。
「この学園に通うような子ーらは、普通食洗機かメイドさんやで」
が、珊瑚の言う通りなのかもしれない。これはもはや、お金持ちのご子息さまたちにはまったく将来の役にたたない作業かもしれない。
「もう全然自分には不要やなって、怜ちゃんは思わへん?」
「どうだろう……」
今のマンションには確かに食洗機がついているが、食事も二人分だし、なんとなく信用できないので自分で洗うことが多い。ちなみに月夜は洗ってくれない。
「なんとも言えないよ。僕はまだ王沢の後継者候補でしかないから、豪一郎に愛想を尽かされれば王沢とは無関係に生きていくんだろうし」
「ふふふ、ウチといっしょやね。今回怜ちゃんと結婚できひんかったらきっと貧乏暮らしや。やから、この実習めっちゃ役に立つねんで」
「もうできてるから無駄なのでは?」
少し悲しい話を楽しく話せるのは彼女の美点だろう。きっと彼女と一緒になれば、辛いことがあっても明るく乗り越えられる気がする。
ふと思う。
「そう言えば、珊瑚は玉の輿狙いでこのゲームに参加してるんだろ? じゃあさ、もし僕が後継者になれなかったら、すごく損をするんじゃない? この学園にはお金持ちも多いだろし、別の人を狙った方が勝率高いかもよ?」
珊瑚はため息をつく。
「怜ちゃんはわかっとらんなー」
「なにが?」
珊瑚は皿洗いの手先に視線を向けながら、小さな声で言った。
「玉の輿狙いなんて、照れ隠しやん」
頬を染めながらそんなことを言う彼女に、僕の心がときめいた。彼女は僕の中に、財産以外の何かを見出してくれているのだろうか。
動揺したが、僕こそ照れ隠しで言葉を探す。
「じ、実はさ、僕は元々貧乏暮らしだったから、この学園に馴染めるか不安なんだよ! 珊瑚はそういうの、平気だった?」
「ぜんぜん平気やったわ! 金持ち喧嘩ぜずってやつ? みんな優しい」
珊瑚はぱぁと笑った。
ああ、可愛いな。言葉を真に受けるなら、彼女はとても素敵なクラスメイトに囲まれたのだろう。
そんな素敵なお金持ちもいれば、結婚相手のリストを作り、息子にアピール競争させるような陰湿な金持ちもいるということだ。
鐘梨珊瑚は素敵な少女だ。だからこそ、こんなゲームに参加する必要はないように思えてしまう。
「珊瑚は、きっと幸せになるんだろうな」
ふと出てしまった言葉を、珊瑚に拾われる。
「……どういう意味?」
「い、いや、なんていうか、モテそうだなって思ったんだよ。だから、こんなふうに結婚相手を決める理由なんて、ないかなと思って」
「ええー、モテそやなんてっ! それって告白やん」
「違います」
「なんでやねん」
「……いやだって、僕たちはまだお互いのことをぜんぜん知らないし」
「じゃあ、教えてくれたらええやん。ウチも、全部教えられるし」
僕は十歳のときに自分が王沢豪一郎の息子だと知り、その事実は徐々に周りにも伝わった。それは他人の興味を引くことはあったが、その興味は王沢怜に対してではなく、王沢に対してだ。
だから、もしその言葉に相対するとき、僕の『怜の部分』は不要なのである。
僕は王沢。
だから尋ね返すとすれば、こうなる。
「珊瑚は、知られる価値があるの? 王沢である僕から」
やや冷たくなる僕の言葉に、珊瑚は小首を傾げた。
僕は王沢。
だから、そのための仕事はきっちりとはたさなければならない。
「ただの、玉の輿狙いなんだろ? どうして僕が、君のことを知っていかなきゃならないの?」
その言葉が少女を傷つけることは、半ば解っていたかもしれない。やってしまったかもしれない。
だが、僕は自分が王沢と同化するほどに、自然と煽るような言葉が出てきてしまう。ふと視線を感じる。月夜のものだ。またあとで文句を言われるかもしれない。
きっと珊瑚を傷つけてしまった。と、思った。
が、実際の目の前の彼女はまったく違った。彼女はきょとんとした表情から、イタズラっぽい笑顔に変わった。
「知らなあかんに決まってるやん。だってウチ、とっても刺激的な女の子やで」
お皿を洗い終えた彼女は、手にたっぷりとハンドクリームをつけていた。
「分けたげるわ」
突然僕の両手をつかむと、珊瑚の手を僕の手に擦り付けた。僕の手も彼女の手も皿洗いの直後で冷たかった。それが、彼女に擦られるほどに体温を取り戻してくれるように感じられた。ぬるぬるしていてくすぐったくて。
なんだろう、とても恥ずかしい!
僕はされるがままに体を硬直させていた。彼女の手のひらが、指先が、僕の神経の繊細な部分を弄ぶかのようだった。
珊瑚はぱっと手を離すと「ウチを知ってな!」と元気に言った。そして彼女は調理実習室から消えていった。
「ずいぶんお楽しみだったみたいじゃないですか、御坊ちゃま」
「いやいやいや、そんなことはないよ僕は真面目に調理実習を受けただけだから」
「あれれ? 手のひらからあまーい香りがしますが。ティオールなんて高級な趣味ですねぇ」
やっぱり見ていたのか。
「いやいやいや、これは珊瑚が勝手に――」
「お嬢様方が勝手に寄ってきて思う存分スキンシップをしてくださるだなんて、さすが王沢家のご子息様でいらっしゃいます。それにお嬢様に対してあんな態度だなんて、ねぇ」
「そ、それは反省してるんだけどさ……」
それにしても、女の子はわからない。結局のところ、僕は珊瑚が玉の輿狙いなのか、本当にただの冗談なのかまったく検討がつかないのだ。何を考えているかわからない少女に対して、どんな言葉を返せば正解なのかもまったくわからない。
なんとなく手の匂いをかぐ。これはそんなに良いハンドクリームだったのか。甘いスイーツみたいな香りがした。
「どうです? 珊瑚様の香りは。欲情しそうですか?」
「おまえ僕をなんだと思ってるわけ?」
ははは、と月夜は笑った。
「なかなか、大胆なお嬢様ですねぇ」
ふと、月夜の手を見ると、いつものように白い手袋がはめられていた。そういえば調理実習中もずっとはめていた気がする。
……こいつ、サボったな!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
