
烏賀陽弘道氏の動画についての反論
みなさん、おはこんばんちわ
今回は烏賀陽弘道氏がYouTubeにあげた動画について、私が調べた中での反論をまとめたいと思います。
烏賀陽弘道氏は「政府のデマ」というテーマに基づいて、「福島第一原発 ALPS水・海洋排水に関する12のディスインフォメーションを指摘する」という動画をYouTubeにアップしました。
この動画を見てから「言いたいことがあればどうぞ」と言われたので、めんどくさいけど全部見ました。
その上でこれから反論していきますので、よかったらご覧ください。
注意:長くなります。
当該動画
https://youtu.be/Q4199GGE20U?si=YybkCrt84D5qPMjq
排泄物の話について
烏賀陽氏は、処理水の海洋放出を、排泄物を薄めて公園に捨てることに例えています。
はっきり言って全然違います。
排泄物は、下水道を通り、下水処理施設で処理された上で放出されます。
下水道から下水処理施設に入る時点では、大腸菌が1mlあたり584,700のコロニーを形成しています。
コロニーの数は、一次処理で398,400に減り、消毒前で4,798まで減り、放流する時には387まで減ります。
ちなみに放出できる基準は、1mlあたり3,000コロニーです。
大腸菌コロニー郡が基準値いかになってから放流しますが、放流水に大腸菌のコロニーが0になっているわけではありません。
しかしながら、基準値以下であれば環境への影響がすくないわけで、そのための基準になっているのです。

ALPS処理水も同じです。
汚染水と処理水を同一視している方が、かなりいますが、下水処理水は汚染水だから放流するなと言っているのと変わりがないです。
これを理解できない人にどう説明してもおそらく理解していただけないでしょう。
余談
烏賀陽氏は「プロパガンダに騙せられない、アンチプロパガンダリテラシー、カウンターリテラシーを身につけて欲しい」とおっしゃっています。
このnoteは、彼の科学リテラシーや情報リテラシーが低いということを説明するために、公開データや議事録をもとに反論している「カウンター」です。
※二つ目の嘘と言っている時に指が3本になっているのは失笑です。

海洋投棄の他に、選択肢は無かったということについて
烏賀陽氏は、海に捨てなくても、陸地で処理する方法は二つあったとおっしゃっています。
一つ目はスリーマイル島の原発で行った自然乾燥について
二つ目はサバンナリバーサイドのモルタル固化について
です。
❶自然乾燥{蒸発処理)
動画では、「スリーマイルで行った自然乾燥を福島でも実施すればいい」と言っていますが、政府の処理水対策委員会でその話題について触れています。
つまり、選択肢が無かったわけではないのです。
その上でなぜ自然乾燥の選択をしなかったのかについて抜粋します。
①スリーマイルと福島を比較した場合、規模が全然違う。スリーマイルの場合は1基だけで結構落ち着いたが、福島の場合は今でも落ち着いていない
② トリチウムの濃度については、非常によく似ているというが、量については、福島のほうは相当多いということ
さらに、スリーマイルの場合は、沿岸から 160km離れていることを考えると、これを日本に当てはめると、ほぼ内立地の原子炉ぐらいに恐らくは相当するため、地理的な環境も相当違うなというふうな印象をもった
③フランスでは、トリチウムは、大気中に放出されるよりも液体の放出の方がかなり多くなっている。その理由は、トリチウムは液体でリリースされるより気体のほうが人体に対するインパクトが大きいからである
④スリーマイルの場合は、量的に非常に限られた量であったので、蒸発処理できたが、今回の場合は全然違うので、これは参考にならないと思う
という意見が出ています。
河川と海では水の絶対量がかなり異なることにも留意が必要です。
また、淡水魚も海の魚も餌とエラから放射性物質を取り込みますが、浸透圧の違いから淡水魚は海の魚と比べ、濃縮係数が少なく見積もって4倍高くなります。
このような点を踏まえると、スリーマイル島の場合、処理水を河川へ放出する場合、環境への負荷が高くなるため、自然乾燥せざるを得なかった状況があったのではないかと私は考えます。
詰まるところ、福島とスリーマイル島では異なる点があることを留意する必要があります。
❷モルタル固化
処理水にセメントを、混ぜてモルタル化してしまおうというのがこの案です。
モルタル固化についても検討していましたが、以下の理由により選択されていません。
①固化による発熱があるため、水分の蒸発(トリチウムの水蒸気放出)を伴うほか、新たな規制の設定が必要となる可能性があり、処分場の確保が課題となる。
こうした課題をクリアするために必要な期間を見通すことは難しく、時間的な制約も考慮する必要があります。
②このために、トリチウムの処分において前例のない地下埋設は、規制的、技術的、時間的な観点からより現実的な選択肢としては課題が多いとの指摘されている。
なお、サバンナリバーサイトの地下埋設(モルタル固化)については、固化した場合、体積が3〜6倍になるため敷地の確保が困難である。
③仮に、福島第一原発の既存の敷地内で設置するためには、3倍以上の高さ(40m以上:ビル 10階程度)の容器が必要となることから建設が困難である。
④固化する際に水分の10%程度が希釈されずに空気中へ蒸発するため、一部が水蒸気放出となることや、作業員の夜ばくについて、配慮が必要となること。
この様なことが見込まれることなどから、現実的な選択肢になるものとは考えていない。
としています。
上記のとおり、海洋放出ありきではなく選択肢にならなかった理由も述べているのです。
なお、りぷるんふくしまで固形化された廃棄物を埋め立てているとおっしゃっていますが、固形化しているのは汚染された除去土壌をモルタル固化するので、処理水のモルタル固化とはちがうのです。
画像の固形化対象物を見てもらえればわかると思うのですが、ばいじん、混合灰などと書いてあります。
対象が液体なのか、個体なのかということを考えもせず、セメント固形化してるから、処理水もできるという非常に浅はかな考え方だと思いました。
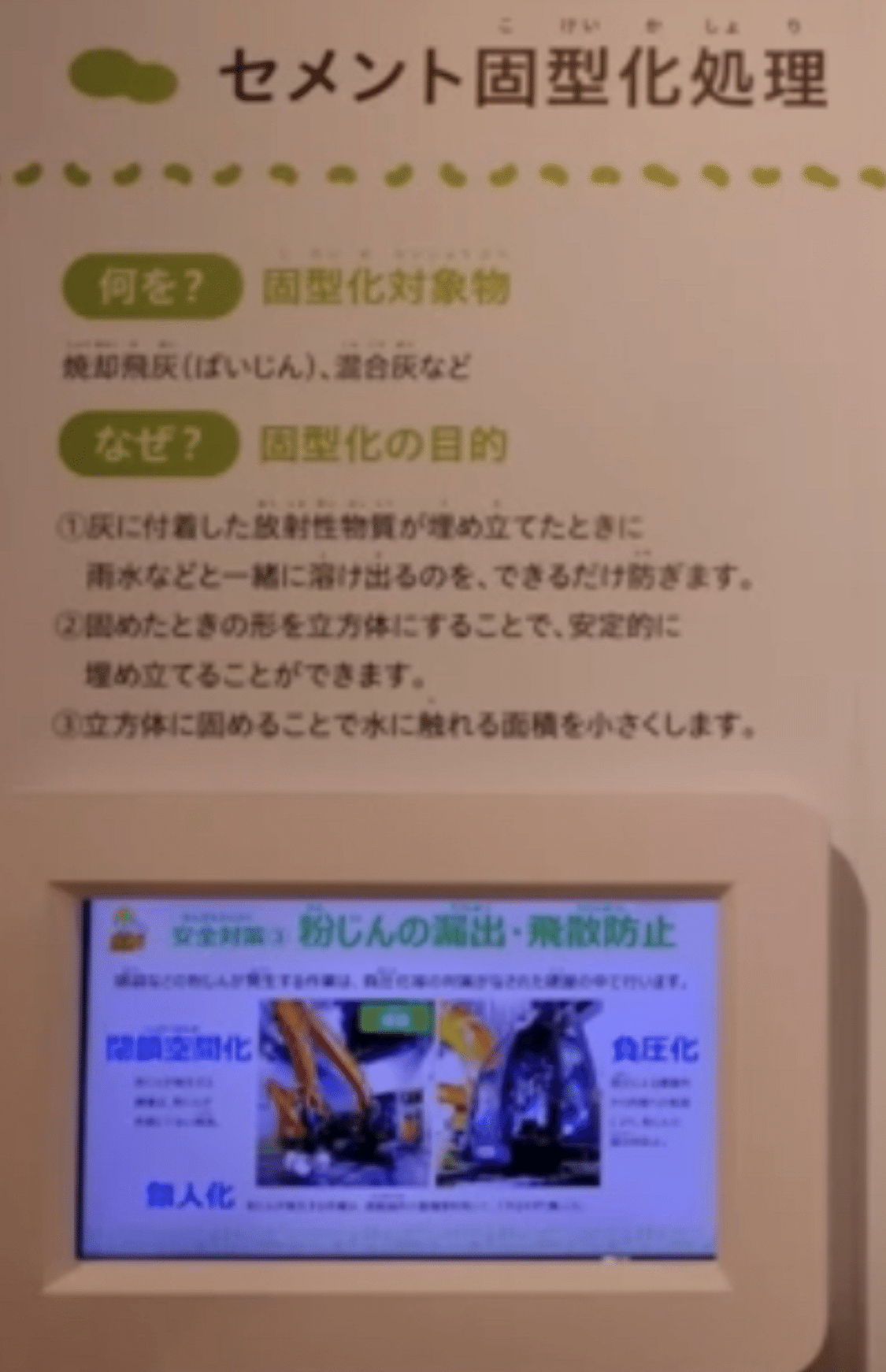
安直に、同一視するのは科学的な知見がないと言わざるをえません。
ちなみに動画でおっしゃっているように、烏賀陽氏はコンクリートとモルタルの違いもわからないくらいの知識しかありません。
処理水はトリチウム以外は残っていないということについて
たしかにトリチウム以外は残っています。
ただ、人体に影響がないほどレベルです。
さきほど下水処理水のなかで大腸菌コロニーが残っているという話と同じです。
それから、他国の原発からトリチウムが放出されていることと、日本の処理水を同列に扱うなといってますが、トリチウムにフォーカスを当てると世界中の原発の方が多く排出していると言ってるだけなんですよ。
つまり、
①トリチウムについては他国と同レベルかそれ以下の量である。
②それ以外の核種については基準値以下である。
③ALPS処理水のその他核種は人体や環境に影響がないレベルである。
これが事実であり、それ以上でも以下でもありません。
燃料棒に触れた水について
他国の排出している原発排水と、日本の汚染水との違いは燃料棒に触れているか否かという点で明確に違います。
その点は烏賀陽氏の言ってる通りです。
それゆえに、福島第一原発の汚染水はALPSによってトリチウム以外の核種の告示比総和が1以下になった処理水を放出するわけです。
他国の原発はトリチウムが多いが、燃料棒に触れていないためその他の核種が極めて少ない。
一方で、福島の処理水のトリチウムは他国の原発に比べて多いわけではないが、その他の核種が多く含まれるため、ALPSによって核種を取り除き、基準値以下にして放出するというわけです。
トリチウムの問題と、その他核種の問題を分けて考える必要があるんです。
トリチウムについては問題がないというのは、言わずもがなです。
ALPS処理水は飲料の基準なので基準そのものが間違っている
烏賀陽氏の動画で一番悪質なところがここです。
烏賀陽氏は人が飲む安全基準と、海洋放出する安全基準は全く違うとおっしゃっています。
政府や東電は、食物連鎖による生物濃縮について考えてないと烏賀陽氏は動画おっしゃっています。
はっきり申し上げますが、食物連鎖による生物濃縮に
ついて、トリチウム以外についても含めた上で、きちんと科学的な根拠を示して安全だと結論づけています。
東京電力ホールディングス株式会社の資料から抜粋します。
資料を見てわかる通り、生物濃縮を考えるときに核種の量ではなく、核種の海水中の濃度が重要なのです。
某国会議員が量が重要だとメディアで話していましたが、問題は海水中の濃度なんです。
※私は自分が知っている資料だけで、嘘だと決めつけるジャーナリストなぞ、もはやジャーナリストではなく、活動家だと思ってます。

処理水貯蔵タンクは消えないという発言について
烏賀陽氏は「貯蔵タンクで貯蔵されている処理水の3分の2は基準値以上だから放出できない」と言ってますが、間違いです。
正しく説明すると、処理水の3分の2は海洋放出の基準を満たしてはいないが、貯蔵するための基準をみたしており、その3分の2の処理途上水については、放出基準値以下になるまで処理を行ってから放出します。
つまり、放出基準と貯蔵基準は異なる基準だということを勘違いしてるんですよ。
勘違いならまだいいんですが、意図的にプロパガンダを流している可能性があるなと個人的に思いました。
彼は、「基準値以上の処理水だから放出できず、放出できないから貯蔵タンクはなくならないので、タンクがなくなるなんて嘘っぱち」というようなことをおっしゃっていますが、基準値以下になるまで処理を行ってから放出するので、処理が終わって全ての処理水を放出すればタンクはなくなります。
つまり、彼の言っていることが嘘っぱちなんです。
補足ですが、なぜ処理したのにも関わらず、放出基準値以上の処理水が3分の2残っているのかというと、
①初期にALPSの不具合が出たこと
②処理をしていない貯蔵基準値以上の汚染水を、貯蔵基準値以下にするために、除去率よりも処理量を優先したから
という2つの理由があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
