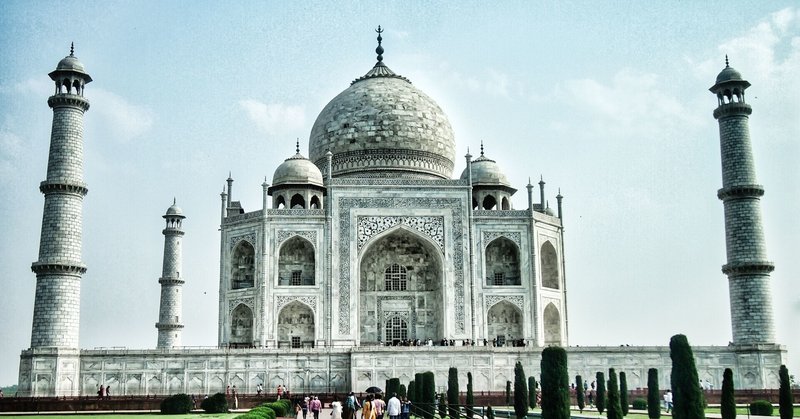
インド マルチスズキ
スズキのインド戦略 著者 R・C・バルガバ、監訳 島田 卓 2006年12月16日 第1刷 ㈱中経出版冊発行の書籍です。発行時期からすると16年前と古いのですが成功の軌跡をたどるのには最適な生きた教科書になると思います。「日本式経営」でトップに立った奇跡のビジネス戦略、著者はスズキのインド子会社マルチ・ウドヨグ社 元社長です。 監訳者島田 卓さんは当時東京銀行インドニューデリー支店次長として活躍された方でインドビジネスに精通されておられ、現在インド・ビジネス・センターの代表取締役社長です。
当時私は工作機械メーカーの海外営業担当として1986年ごろから会社の命によりインドに行き始めたのですが、当時は仕事を覚えるのと技術者の応援と通訳、新規開拓営業をしており、毎日が勉強の日が続いておりましたが街を走っている車は当時はカブトムシ型をしたアンバサダーとプレミアムモータのセダン型の乗用車が主流の時代でした。自動車の古さとエンストには閉口をしていたのですが、早く日本の車メーカーが来ないかなと思っていました。当時は現地代理店が手配してくれたアンバサダーで顧客を回る日々でした。走りすぎるとオーバーヒートして車を休めて水を補給して、それから運転手を座らせ、我々自らアンバサダーを後ろから押して日陰のある道端に移動させ、車が元気になるのを待ってから再度活動開始ということもありました。思い起こすとその時代のタイミングにスズキがインド市場に入ってきたと思います。それから以降はマルチスズキ社の車が町中に増えていった事を思い出します。今、マルチスズキの活躍がここまでになるとは思ってもいませんでした。
現在は自動車業界ではマルチ・スズキと韓国ヒュンダイの1強+2位メーカーがインド自動車市場をけん引しています。そのほかの自動車メーカーはCORONAの影響もありますがそのインドというマーケットが読みにくく減産や撤退を余儀なくさせられている状況です。韓国ヒュンダイインドに関しては当時自分が担当していて勤務先の工作機械をインドの製造拠点のチェンナイ工場に契約ができて、技術者と一緒に立ち上げたことを思い出します。 ヒュンダイの販売価格設定や現地に根差したサービス体制が功を奏しているのだと思われます。
背景としてはインドの国営自動車会社マルチウドヨグ社が1981年に設立され、その合弁会社をスズキと設立し、インドという特異なカーストを含む制度を持つ国の自動車メーカーとしてスタートしました。今があるのはのマルチ社、スズキ社の両社のトップのその時の判断とかかわる社員の努力と信頼関係以外にはこの成功がないと思います。身分制度や文化の違いを超えて根付いた「日本的経営」、大国インドで日本企業が進むべき道とは。創業期から現場の経営トップとして走り続けた著者によるインド戦略のすべてが記載されています。ここで述べたいのはその戦略は重要ですがそれよりもスズキの会長が言うのは著者と会えたことであると言われています。また同時に初代社長のクリシュナムルティさんという波長の合う方との出会いであると言われています。 技術的にはスズキは当時大手自動車メーカーではなく軽自動車とオートバイだけを作っていた中堅規模のメーカーで発展途上のアジア市場での進出がいいだろうとの考えもありました。 バルカバさんも一緒に成長できる企業かどうが重要なことであったそうです。
今回自分が得たポイントは人との出会い、関わり合いです。その時のタイミングと場面、きっかけがあった時にどのように判断、行動をとるかによって将来の自分の進むべき道がつくられていくことを認識できました。 よって今以上に人との関わり合いを重視し、その人との関わり合いを有機的な関係に発展できるようにしていきたいと考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
