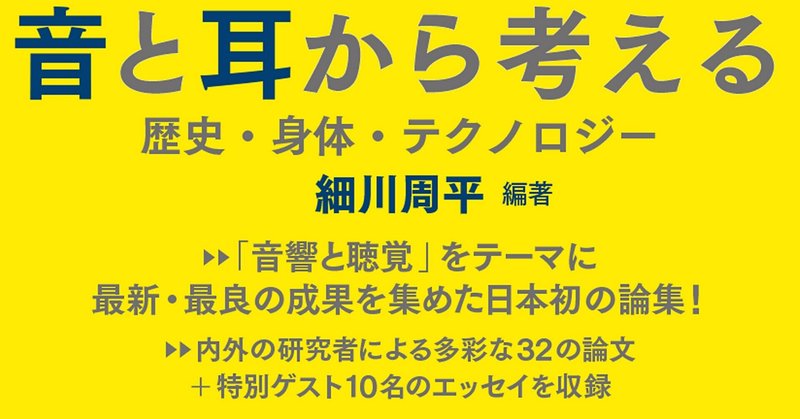
『音と耳から考える──歴史・身体・テクノロジー』から序文「音故知新 音と耳からの出発」細川周平|その5
第四部「音が作る共同体」は、対面関係の集団や地域で作られ聴かれる音を主題としている。第三部で主題とした複製技術に関わるが、精神病院、温泉地、農村に寄稿者は向かい、その文脈はだいぶ違う。聴き手は概して顔見知り同士で(少なくとも共通の目的でその場にいて)、いろいろなレベルで閉じた空間(病院、観光地、村)を共有している。近くの他人と同時に同じ音源を聴く体験が重要で、それぞれ治療、慰安、連絡の実用に供している。三人の著者は音(楽)が基本に持つコミュニケーション機能について、ふだんとは別の場所で考えている。
光平論文は、松沢病院の日誌から音楽を鑑賞したり、自ら楽器や歌に興じる「慰楽」が治療のプログラムに組み込まれていたことを明らかにしている。ある時期まで作業療法に含まれていた音楽弾奏は退き、慰安会が院内の唯一の音楽関連イベントになり、レコードコンサートや救世軍音楽会が随時開かれた。注目すべきは〈さくら音頭〉の替え歌〈松沢音頭〉で、医師と看護人と患者総出の祭りとなり、院内の人の間はもとより、塀の外の社会につながる歌として機能した。論文は「慰楽」という病院側の造語に、西洋語の翻訳として広まった「音楽」とは違うニュアンスを見出している。
葛西論文は、温泉地の音環境を調査している。温泉地の地元色の歌舞ショー自体は観光化と同じぐらい長い歴史がある。会場となる大広間は舞台と客席が正対する劇場とは異なる空間配置で、会話自由、出入り自由で散漫な聴取に向いている。著者は温泉場から観光音楽、聴取態度の混在という次のテーマを考えている。観光については、長尾エッセイが、おわら風の盆のうちの人の出の少ない「夜流し」に、フェルドのいう「重ねあげた響き」、空間と時間が積み重ねられた響きを感じ取っている。
細馬論文は、滋賀県の農村で利用されてきた有線放送の歴史から、双方向の放送が「共同体の声」として生活を活性化してきたことを掘り起こしている。この忘れられたメディアは、長﨑論文が論じた通常のラジオ、無線ネットワーク放送にケーブルがついたというのではない。地域の電話としても機能し、防災や学校や葬儀の実用に供されるほか、朗読や声の作品を募集してきた。町民は「聞き流し」ているというが、知人の声がほとんどつねに流れていることを拒まない。アーカイブが歌の記録、言語の発話や方言の記録、環境音の記録として今後、研究に値すると著者は展望を述べている。(6に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
