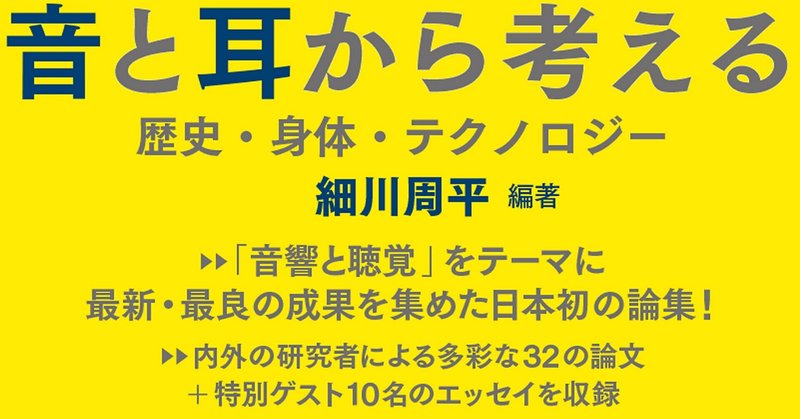
『音と耳から考える──歴史・身体・テクノロジー』から序文「音故知新 音と耳からの出発」細川周平|その4
第三部「戦前期昭和の音響メディア」は、民族音楽学、トーキー、ラジオの誕生を同時代の関連した出来事と捉え、複製技術のインパクトの大きさについて改めて考える。この時期の音楽や映像メディアの革新についてはさんざん議論されてきたが、ここでは音楽学者の現地録音、音響学者の視聴覚体験、大阪のラジオ番組という切り口から、時空間を超えて音を記録する、再現する、伝達するテクノロジーの初期の利用やイデオロギーについてまとめる。真空管工学とともに、軍政による中央集権化と国粋主義の台頭が全体に共通した下地といえる。
山内論文は、ジョナサン・スターンの「視聴覚連禱」批判を発展させ、〈北〉の〈視覚性〉が〈南〉の〈聴覚性〉に自己を投影してきた南北半球の植民地的格差に焦点を当てている。事例として挙げるのは、田辺尚雄による台湾先住民の録音で、「現地」の「未開人」の歌を文明人が採集するという姿勢が強い。これは日本人初のフィールド録音でもある(国内の民謡採集と同時代)。西/東という民族音楽学(比較音楽学)、そして近代日本の地勢図(知性図)が北/南に投影されている(これは阿部論文の話題でもある)。そして帝国主義下、彼を含めた音楽学者は、自民族中心的な「東亜の音楽」の樹立を目指した。その政治的提唱の根底に現地録音があったと山内は理論づけている。
フィールド録音については、柳沢エッセイが今日では作品として、独自の存在意義を持ってCDのかたちで流通していることを紹介している。個人録音の一種に違いなく、金子論文でいうオープンテープを用いた「市民による音づくり」が、テクノロジーを変えて、展開し続けているのだろう。
渡辺論文は、音響学者田口泖三郎が、環境音に耳を傾け聞き分けようとシェーファーに近い論を立てていたことを教えてくれる。田口の刺激となったのはラジオとトーキーで、劇映画よりも実写映画の長所短所を科学者の目と耳で述べ、制作側への提言を行っている。単に映像に音が加わったテクノロジーというより、「音と映像の関係性自体が問い直され」る事態を田口は熟知していた。そのような視聴覚複製技術のリテラシーがあって初めて、「耳に聴く近代戦」という当時の見出し言葉も、有名な「敵機爆音集」の録音や防空演習のラジオ放送も意味を持つ。著者は視聴覚感性史のなかで、田口の言説を読み解いている。
長﨑論文が論じる日本放送協会大阪放送局(BK)は、官僚主導の東京放送局(AK)とは異なり、当時の大大阪構想を念頭に置いて商人主導のかたちで設立された。たとえば日本初のスポーツ実況放送である甲子園球場からの中等学校野球大会を、巨額の技術投資によって実行した。放送用語や発音の標準化をAKに先んじて行った記録もある。論文はBKの独自性をけん引した二人のプロデューサー、奥野熊郎と西本三十二の業績に焦点をあてている。BKとAKの対立から地域性を打ち出す「文化」と、普遍性を打ち出す「文明」という大きな構図を、著者は読み取っている。(5に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
