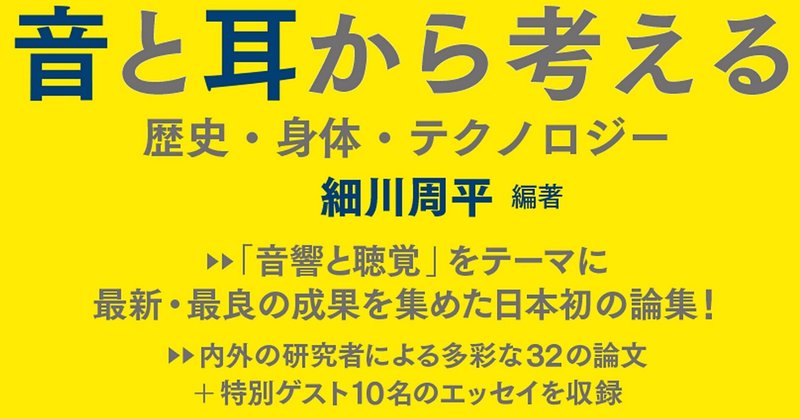
『音と耳から考える──歴史・身体・テクノロジー』から序文「音故知新 音と耳からの出発」細川周平|その7
第六部「鼓膜の拡張─音響テクノロジーの考古学」以降は、主にテクノロジーを介した音を扱い、まず一九世紀半ばに発明家の間で湧きあがった耳の補助具についての論をここに集める。この分野ではフリードリヒ・キットラーの『グラモフォン・フィルム・タイプライター』(筑摩書房、一九九九)、ジョナサン・スターンの『聞こえくる過去』(インスクリプト、二〇一五)が画期的で、歴史に残った完成品から見れば失敗のように見えても、発明する側に立てば、同時代の科学と仮説の精髄が込められていると論じた。考古学は事始め学ではない。現れては消える音を記録・固定する技術は、ヨーロッパでは中世より夢見られてきたが、一九世紀には音響学・工学の発展によって実現可能になった。上の二冊を経過した後の歴史観を持つ四人が、エジソンを脱中心化した立場から、音響器具の発明を振り返っている。
福田(裕)論文は、フォノグラフ以前の夢想家として知られるだけだったスコット・ド・マルタンヴィルのフォノートグラフ発明を、一次資料から復元している。論文は音の再生よりも音声の視覚化を目指した彼の写真術的発想を、同時代の物理学・工学の枠組みから見直している。また企業化される前のパトロン頼りの発明家の仕事ぶりもよくわかる。同じくエジソンに「敗れた」発明家を論じた著者の『シャルル・クロ』(水声社、二〇一四)をもう一歩遡る。
秋吉論文は、アレクサンダー・ベルの電話発明を「耳のフォノートグラフ化」として、その実現の足取りをたどっている。生理学の発展とも関わり、鼓膜に空気の振動を「書き込む」装置をベルは最初構想した。それが不成功に終わると、耳に外耳から振動を送る補助具(受話器)が考案され、今日の電話に結実した。同時期、音を拾う器具としてマイクロフォンが発明されたことも大きい。秋吉は身体機能を代替するテクノロジーという大きな見地に立って、電話に至るまでのジグザグを今日の人工内耳に至る潜在的な前段階と見ている。
福永論文は、蓄音器、ラジオ、電話と技術的に共通しながら、それ自体コンテンツも応答コミュニケーションもないためか、研究の蓄積の薄い拡声器について、日本で初めての文化史である。一八七〇年代の初期電話にも拡声器が補助的に実用化され、二〇世紀初頭にはアナウンスを遠くの聴衆に届けるPA装置の祖型ができあがった。もちろんそれを必要とする社会生活が前提にあるし、装置が新しい生活スタイルを作り出した面も大きく、アメリカ流のポピュリズムもドイツのナチズムも、日本の国民総動員体制も拡声器なしには実現しなかった。拡声器は受話器からラウドスピーカーへ、送話器からマイクロフォンへという技術史のミッシング・リンクではないか。論文は次なる展開を予告している。
瀬野論文は、拡声器と反対に静かな聴覚補正の技術、補聴器の歴史をスターン以降の聴覚理論に則って図解している。電話技術の発展からイヤフォンによって聴力が数値化(標準化)されたことを前提に、論文は「きこえ」という生理的な性能に障碍者自身がどう対処してきたのか、教育者、医師、技術者がどう接してきたのかという面にも詳しい。一九二〇年代には医学的に聴力は意義を持ち、教育や就職や徴兵の試験に用いられた。日本では戦後にアメリカ製の補聴器が採用された。
二一世紀に入って、障碍者研究は既存の諸感覚の図式に根本的な変革を迫っているが、「からだで聴く」現実についての木下エッセイ、吃音から声と耳の知覚連動について語る伊藤エッセイを収録し、その一端を示した。映画『リスニング』が描くろう者の「聴取」と「沈黙」について二人と会話できたことは、メンバーにとって大きな刺激だった。(8に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
