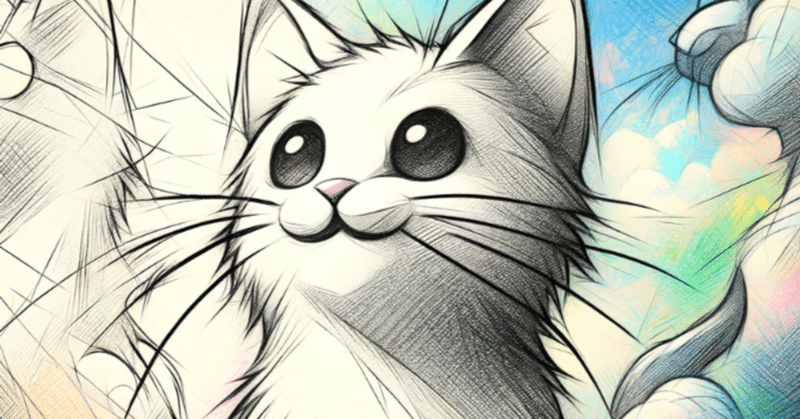
私の天皇の墳墓訪問経験値②
本日もご覧賜り、まことにありがとうございます。
いつものように、私の経験値をご紹介する時間がまいりました。
初めての方へ簡単に説明させていただきますと、この企画は自らの体験を基に、noteのリソースを活用しながら書き連ねていくマニアックな試みでございます。
些細な出来事かもしれませんが、こうした私なりの経験を書き留めることで、いつかは良き記録となるものと存じております。
どうぞ気恥ずかしい限りではございますが、温かい目で見守っていただければ幸甚でございます。
過去の投稿は↓
① 天武・持統天皇陵(檜隅大内陵)(奈良県明日香村)
天武天皇は、兄である天智天皇の遺志をつぎ、中央集権国家の形成を推し進めた。壬申の乱に勝利し皇位に就いたが、686年(朱鳥1)9月、病により崩御した。持統天皇は天武天皇の皇后であり天智天皇の娘である。天武天皇とともに中央集権国家の確立に尽力した。天武帝亡き後即位し藤原京の造営を行っている。
② 聖武天皇 佐保山南陵(奈良県奈良市)
災害や疫病(天然痘)が多発したため、聖武天皇は仏教に深く帰依し、天平13年(741年)には国分寺建立の詔を、天平15年(743年)には東大寺盧舎那仏像の造立の詔を出している。
光明皇后稜も近くにあります。
③ 佐紀高塚古墳(称徳・孝謙天皇陵)
史上6人目の女性天皇で、天武系からの最後の天皇である。この称徳天皇以降は、江戸時代初期に即位した第109代明正天皇(在位:1629年 - 1643年)に至るまで850余年、女性天皇が立てられることはなかった。
④ 光仁天皇 田原東陵(奈良県奈良市)
天皇の誕生日を祝う、天長節が始まったのが光仁天皇と言われています。
次期天皇の有力候補が次々と暗殺された政争激しい時代に、酒におぼれた日々を送り、わざと無能を装っていたそうな、、、、
バスで行きました。帰りの本数が少なかったのがビビりました。\(^o^)/
⑤ 市庭古墳(平城天皇 楊梅陵)(奈良県奈良市)
平城天皇は薬子の変で有名ですよね。テストに出るよ。
薬子の変、または平城太上天皇の変は、平安時代初期に起こった事件。810年に故桓武天皇皇子である平城上皇と嵯峨天皇が対立するが、嵯峨天皇側が迅速に兵を動かしたことによって、平城上皇が出家して決着する。
⑥ 醍醐天皇 後山科陵(京都市伏見区)
醍醐天皇は昌泰の変で有名です。
昌泰の変(しょうたいのへん)は、昌泰4年1月25日(901年2月16日)、左大臣藤原時平の讒言により醍醐天皇が右大臣菅原道真を大宰員外帥として大宰府へ左遷し、道真の子供や右近衛中将源善らを左遷または流罪にした事件
醍醐寺の近くにあるよ。
⑦ 朱雀天皇 醍醐陵(京都市伏見区)
朱雀天皇(すざくてんのう、923年9月7日〈延長元年7月24日〉- 952年9月6日〈天暦6年8月15日〉)は、日本の第61代天皇(在位:930年10月16日〈延長8年9月22日〉- 946年5月23日〈天慶9年4月20日〉)。諱は寛明(ゆたあきら)。 第60代醍醐天皇の第十一皇子。母は藤原基経の娘、中宮藤原穏子
醍醐寺の近くにあります。
⑧ 後鳥羽天皇 大原陵(京都市左京区大原)
後鳥羽天皇は、日本の第82代天皇。諱は尊成。 高倉天皇の第四皇子。母は、坊門信隆の娘・殖子。後白河天皇の孫で、安徳天皇の異母弟に当たる。 文武両道で、新古今和歌集の編纂でも知られる。鎌倉時代の1221年に、承久の乱で鎌倉幕府執権の北条義時に対して討伐の兵を挙げたが敗北し隠岐に配流され、1239年に同地で崩御した。
隠岐に流された後、戻ってこれなかったのですね。
遺骨が運ばれて京都市左京区大原にきました
⑨ 順徳天皇 大原稜(京都市左京区大原)
順徳天皇(じゅんとくてんのう、旧字体:順德天皇、1197年10月22日〈建久8年9月10日〉- 1242年10月7日〈仁治3年9月12日〉は、日本の第84代天皇(在位:1210年12月12日〈承元4年11月25日〉- 1221年5月13日〈承久3年4月20日〉)。諱は守成(もりなり)。 後鳥羽天皇の第三皇子。母は、藤原範季の娘・重子(修明門院)。承久の乱によって佐渡へ配流された。
⑩ 後堀河天皇 觀音寺陵(京都市伏見区)
⑪ 深草北陵(京都市伏見区)
後深草天皇、伏見天皇、後伏見天皇、(北朝の)後光厳天皇、(北朝の)後円融天皇、後小松天皇、称光天皇、後土御門天皇、後柏原天皇、後奈良天皇、正親町天皇、後陽成天皇 合計12名
と初代伏見宮の栄仁親王
⑫ 月輪陵(京都府京都市)
月輪陵(つきのわのみささぎ)と後月輪陵(のちのつきのわのみささぎ)および同じ墓域にある灰塚と墓(以上を本陵墓と記す)について記述する。
本陵墓には、四条天皇を始めとして14人の天皇を含む25陵、5人の天皇の灰塚、9人の皇族の墓が営まれる。元々は皇室の香華院(菩提寺)であった泉涌寺の境内にあって帝王陵と呼ばれていたが、明治時代の神仏分離により宮内省に上地された。本陵墓は、泉涌寺霊明殿の背後にあり、透壁と唐破風の門に囲まれ、その前の白砂地の庭が拝所となっている。名称は泉涌寺の月輪大師と、泉涌寺の背後にある月輪山に因む。 なお、本陵墓の近辺には後堀河天皇の観音寺陵、孝明天皇の後月輪東山陵、英照皇太后の後月輪東北陵がある。
見ていただきまことにありがとうございました。
本日も素敵な1日をお過ごしくださいませ。\(^o^)/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
