
頭痛の原因自律神経とホルモンバランスが影響する
今回は頭痛の原因編をまとめてみましたので、こちら参考にしてみてください。
最後に自律神経とホルモンの大事なところを解説しています。

①頭痛原因ストレスからの頭痛は本当なのか?
緊張型頭痛の場合はあるでしょう。
そもそもストレスとはなにか
ストレスは、外部からの刺激や内部の要因に対する身体や心の反応です。これは、生活の中でさまざまな状況や要因によって引き起こされ、個人によって異なる程度や対処能力を持ちます。以下はストレスの主な要素です
ストレス刺激(Stressor): ストレスの原因となる外部の要因や出来事を指します。これには、
仕事の圧力
例えば、よく会社であるのが、仕事を始めたが上司からの圧力。
仕事の量の圧力。
⏫この場合はかなり仕方ないですよね。
人間はそんな簡単に仕事ができるようになりませんからまあ1人前になるのは3年4年かかる人もいますからね🫡
まあ私だったらすぐ辞めますね。
自分が悪くても。思いたったらすぐ行動でやめます。笑

人間関係の問題

人間関係の問題はとても仕方ないですよね。
いい社長の下につけたと思ったら部長が最悪とかありますよね🫡
それは我慢するかやめるか、心に余裕を持って決断しましょう。こんな事で悩んで頭痛が来たらいやですやん?😅
健康上の懸念、

環境の変化、

環境の変化は実はデメリットよりもメリットの方が大きいですが、
よかった職場をやめ、悪い会社に勤めてしまったときなどはテンションさがりますよね。
そんな時よかった時のことを思い出して、悩んでしまうのがストレスになったりしますね。
経済的な困難など

不安からくるストレス頭痛ですよね。
身体的ストレス

ストレス刺激に対する身体的な反応は、
自律神経系とホルモンの放出に関連しています。

これには、心拍数の上昇、血圧の上昇、筋肉の緊張、呼吸の速化などが含まれます。
ここは大事なので最後に解説します。

心理的反応: ストレスは心理的な反応も引き起こします。不安、緊張、焦燥感、不安、集中力の低下などが心理的なストレス反応です。
対処能力: 個人のストレスへの対処能力は異なります。一部の人はストレスに対して効果的に対処でき、他の人は難しいと感じるかもしれません。個人の対処能力は遺伝的、環境的、および学習に影響を受けます。
長期的影響: 長期間にわたる慢性的なストレスは健康に悪影響を及ぼす可能性があります。これは心血管疾患、免疫系の弱化、心理的な問題(うつ病や不安障害など)、体重増加、睡眠障害などにつながることがあります。

脳の血管の変化: ストレスが脳の血管に影響を与え、血流の変化が頭痛を引き起こすことがあります。気をつけてください。

自律神経の乱れが頭痛に影響を与えることがあり、特に緊張型頭痛と片頭痛といった頭痛の種類に関連しています。以下に、自律神経の乱れが頭痛にどのように関連するかを説明します
交感神経と副交感神経のバランス自律神経は交感神経と副交感神経から成り立っており、

これらの神経系のバランスが重要です。交感神経は「戦闘または逃避」の反応を引き起こし、

副交感神経は「リラックスと回復」を促進します。これらの神経の過剰な刺激や不均衡は、頭痛を引き起こす可能性があります。

緊張型頭痛: 自律神経の不均衡が緊張型頭痛の原因とされています。長期間にわたるストレスや不安が、交感神経の過剰な活性化を引き起こし、頭痛や頭部の筋肉の緊張を誘発することがあります。
片頭痛: 片頭痛の一部の発作は自律神経の変化に関連しています。特に交感神経の活性化が片頭痛のトリガーとなることがあります。これにより、血管の収縮と拡張が生じ、頭痛が発生することがあります。
対処法: 自律神経の乱れによる頭痛を軽減するために、ストレス管理をきちんと行いましょう。
頭痛がある場合はその前にMRIの診断を病院で受診し、それでもわからない場合は整体院や接骨院、鍼灸院へ行ってみましょう。
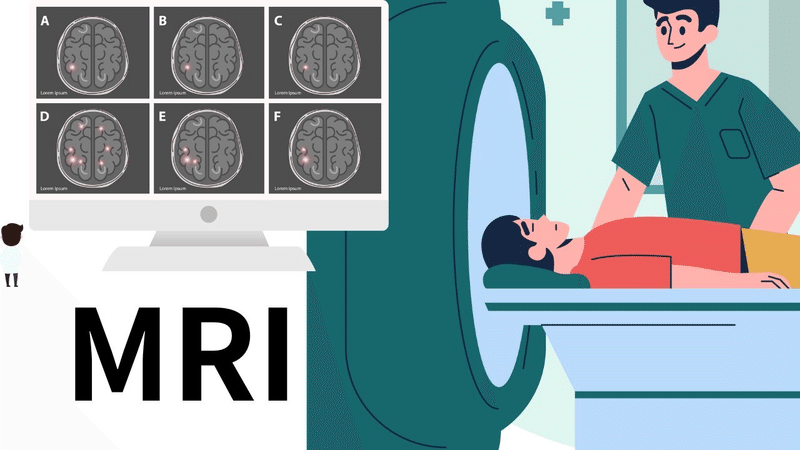
広島痛み専門整体院でも頭痛の治療が可能となっています。
広島痛み専門整体院での頭痛で圧倒的に多いのが首の付け根の板状筋や、後頭下筋が多いですね。70%原因不明の頭痛が多いですが、まずは自律神経と副交感神経の乱れから頭痛がくるということは血液の循環が滞り血液が筋肉に良い血を与えることができなくなり脳に血液が回らないので頭痛が起きやすくなるということが考えられるのではないかとおもいます。
少し図を用いて説明しましょう。
自律神経は全身の器官を支配していますなので、筋肉も支配しています。
この下の図は綺麗な血液や神経が筋肉に通っています。

①自律神経の乱れがおこるともちろん血流の低下につながります。詳しくするとこのような図になります。

②血液が通らないので栄養がもらえない。首の筋肉は緊張(硬くなる)
硬くなる

③血液が足りてない脳は栄養が回らなく、血管が細くなりやすい。そのことから頭痛がおきやすいのも一つの原因である。
↓図をみてください

頭痛は自律神経が問題な場合もあるが、そうではない頭痛もあります。
広島痛み専門整体院での治療は
脳と首の間をあたためる治療をしています。
筋肉は温めると緩んでくれたりします。
筋肉が緩く柔らかくなると温めると眠くなったりもします。この時副交感神経が優位になり、リラックスした筋肉がやわらかくなり細い血管から緩んだ血管になるため血が流れやすくなります。細胞には酸素や栄養素がいきやすくなるため、脳の血管は広がるので、頭痛がらくになるという簡単なイメージをもっていただけると幸いです。
頭痛の方はお気軽にご相談ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
