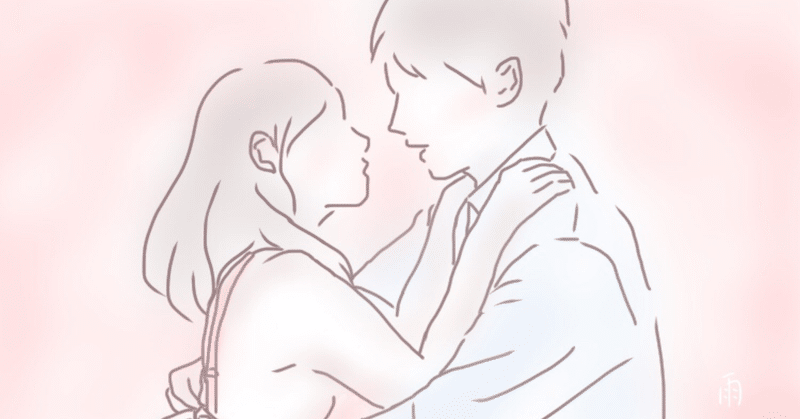
あいまいな季節
つなぐのか、つながないのか、骨ばった手の甲が意思を持って私の手の甲に当たるのに気づかないふりをしているうちに、駅から徒歩五分の彼の家に着いた。
おじゃまします、と言うと、はーい、と奥から声がする。今日はお母さんがいる日のようだ。玄関脇の扉から顔を出すと、まだ15時過ぎなのに、彼女は鶏肉を切っていた。
「いらっしゃい」
「すいません、毎週のように来てしまって」
「いいのいいの。大学はどう?楽しい?」
そうですね、と曖昧に笑う。楽しかったらこの家に毎週来ることはないだろう。
大学一年生の五月。附属ではない大学に進学した私に既知の友達はいなかった。授業と授業の合間には巨大なキャンパスを右往左往し、「すいません、一年生の方ですか?」という大量のサークル勧誘の声かけを愛想笑いでかわし、授業が終われば我先に教室を出て、街の本屋やサイゼリヤで暇をつぶす日々だった。
「今日は来るかなと思って、ケーキ買っといたよ」
「え、ありがとうございます!」
この人は私のことをどう思っているんだろう。息子の元彼女。かつては「お母さん」と呼ばれ、母の日や結婚記念日には花を贈られていた。別れたと聞いていたけど、なぜか大学に入った途端に毎週木曜日に家に来るようになった。付き合ってはいないらしい。
うーん、どうだろう、ウザいだろうな。
彼に促されて階段をのぼり、部屋の扉を閉める。
「今日は来ると思ったから、片付けておいたんだ」と彼は照れた顔を見せた。
私の授業が早く終わる木曜日を待って、お母さんはケーキを用意し、彼は部屋を片付ける。大学とは違う。私の家とも違う。この家だけは定位置を用意して私を待っていてくれる。
ただセックスしに来る女のために。
ベッドに隣り合わせに座って苺のショートケーキを食べ、テレビを見始めて早々に彼は私にキスをする。舌が入ってくる。人間の匂いだ。人間の肉だ。人間の滑りだ。彼と接すると私はすごく人間を感じた。大学や購買、レポート、出席確認のリアクションペーパーからは人間の匂いがしない。そういう機能的な日常と完全に切り離された、生々しい人間の匂いや味のするもの、私は当時セックスのことをそう感じていた。
組み敷かれ、ブラジャーの上から胸を揉まれる。別に何も感じなかった。彼の鼻息が私の首筋にかかる。あつい。人間の熱気だ。私はなるべく息を乱さないように、昨日観た映画のことをうっすらと考える。興奮や緊張を悟られたくなかったのだ。
思えば私は彼より余裕でいることにいつも気を配っていた。付き合っていた頃もそうだったし、セックスをしに通っていた頃も、そのあともしばらく。余裕でいることに必死になるなんて、一番かっこ悪いし、あまりに意味がない。それに気づくのはもうずっと後、何も取り戻せなくなってからだった。
「ねえ、気持ちいい?」
そう何度も聞いてしまうのは、自分が興奮するためではなくて、単に疑問だったからだ。家でたまに自慰をする程度の私はまだ自分の体にも無知で、男性の体のことは更に分からなかった。
私がそう聞くと彼は動きを止め、顔をこちらに近づけた。遮られていた五月の夕暮れが一気に差し込んでくる。今の私、たぶん可愛いだろうな、と思う。どんなチークやリップを塗りたくるより、夕焼けのクライマックスの発熱に染められる方が可愛いはずだ。いちいち話しかけるのには、私をもっと見てほしいという思いもあった。18歳の私を間近で目に焼き付けておいてくれるのは、世界に彼しか、いなかった。
「うん、気持ちいい」彼は切なげに言う。「こうやって止まっちゃうのが、その証拠だよ。たくさん動かすと、気持ちよすぎて、すぐイっちゃうから」
夕焼けを背負ったその男もまた泣けるほど美しかった。
やがて不意に呻き、射精すると、彼は鼓動を私の胸に押し付けながら、ごめん、と謝った。なんで謝るのか、私には全然分からなかった。別に長く挿入しようが一瞬で終わろうが、そんなことはどうでもいいことだった。
意識の穏やかな水面に浮き、少し沈み、また浮きあがる。つかの間の浅い睡眠から目覚めると真っ暗だった。テレビの前の時計を見ると18時半を過ぎている。
もぞもぞと動き始めた私を彼は後ろからきつく抱きしめた。
「結婚しよう」
私はしばらく時計の秒針がゆっくり滑らかにまわるのを見ていた。
「付き合ってもないのに?」
何の答えにもなってないし、何の意味もない返答をしていることは自分でも分かっていた。
「じゃあ、30歳になってもお互い独身だったら、結婚しよう」
「そうだね」
暗闇に目が慣れてきて、彼の机や早稲田大学と書かれたシャープペンシル、お母さんの手縫いのティッシュケースなどが、グレーの濃度に浮かび上がっていた。私たちはまだ18歳だった。結婚という言葉から浮かぶイメージは、この暗い部屋の物々の輪郭よりもずっとぼんやりしていた。
事後にファンタグレープを飲む瞬間は、まだ性器の感覚にピンときていなかった当時の私にとってはセックスよりも気持ちがよかった。乾いた喉に炭酸がぬきとおる。細胞が我先にと手を伸ばして水分を吸い取っていく感じがした。あんなにファンタグレープが美味しくて、あんなに夕焼けが美しかったのは、あの二階の小さな部屋で過ごした日々を最後に、もうないかもしれない。
お母さんに「ごはん食べていく?」と聞かれる前に急いで服を着て、階段を降りる。おじゃましました〜!と声をかけ、彼の自転車の荷台に跨る。段差を乗り越えるたび、震動が下半身に鈍痛を覚えさせる。悪い気はしなかった。
五月の夜風は皮膚に優しくなじむ。春はほとんど終わり、ついこの前まで側溝付近に汚く寄せられていた桜の花びらはいつのまにか消えていた。かといって夏の本体はまだずっと遠くにあった。大学の長い夏休みには英語のクラスで旅行にいく約束をしていた。春と夏の良いところを取り合ってあまく混ぜたような、あいまいで、一番気持ちのいい季節に、私たちは二人乗りでゆるやかな坂を下っていた。
彼は30歳になる少し前に、どこかの女性と結婚した。
サポートをいただけるとハーゲンダッツが買えます。
