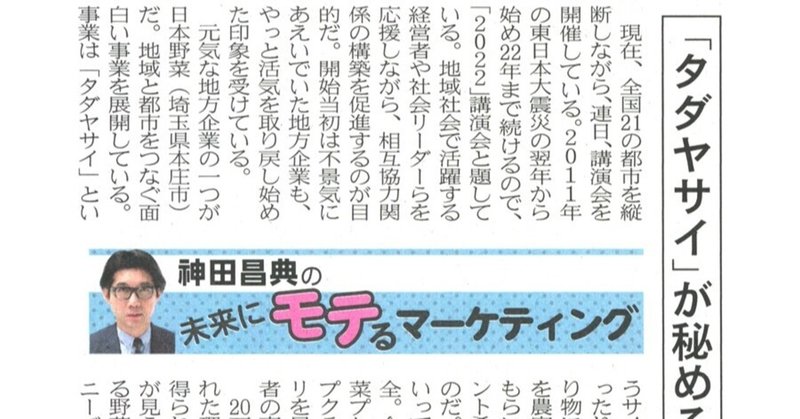
神田昌典の日経MJ連載コラム『タダヤサイ』が秘める価値 フードロスを付加価値に変える驚きビジネスとは?
「タダヤサイ」が秘める価値 ― 日経MJ連載「未来にモテるマーケティング」
現在、全国21の都市を縦断しながら、連日、講演会を開催している。
2011年の東日本大震災の翌年から始め22年まで続けるので、「2022」講演会と題している。
地域社会で活躍する経営者や社会リーダーらを応援しながら、相互協力関係の構築を促進するのが目的だ。
開始当初は不景気にあえいでいた地方企業も、やっと活気を取り戻し始めた印象を受けている。
元気な地方企業の一つが日本野菜(埼玉県本庄市)だ。
地域と都市をつなぐ面白い事業を展開している。
事業は「タダヤサイ」というサイトの運営で、
傷があったり形が悪かったり、売り物にならない野菜や果物を農家から無料で提供してもらい、
同サイトがプレゼント希望者を募るというものだ。
売り物にならないといっても、野菜は新鮮で安全。
会員数は20万人と、野菜プレゼントサイトでトップクラスだ。
「食のメルカリを目指している」と創業者の高橋栄治社長は言う。
20万人もの会員を集められた理由は、無料で野菜が得られるだけではない。
「顔が見える農家から安心できる野菜を買いたい」というニーズも満たしているからだ。
無料の野菜が気に入ったら、以後、その農家から購入もできる。
野菜の質もスタッフ対応も体験済みなので、非常に安心だ。
農家にとっても見込み客の開拓になる。
直接販売した場合、20%の手数料がかかるが、
固定客の獲得につながると考えれば、サイトを利用するメリットは大きい。
また、専業・兼業農家だけではなく、家庭菜園から収穫された野菜も、無料で提供が可能だ。
こちらもサイトのにぎわいを高めている。
タダヤサイは、プラットフォーム事業の構造を理解すると、
さらに収益性の高いモデルへと進化する可能性を秘めている。
この事業モデルは、野菜を提供する農家と野菜をもらう、あるいは買う生活者が、
同じプラットフォームのうえで「プレーヤー」として交流し、
運営者はその交流を促すプロデューサーという位置づけだ。
その交流から生まれるデータを元に大きな価値を生み出すのが、プラットフォーム・ビジネスの神髄だ。
タダヤサイも、交流を促すことで、
地方の農業と都市生活者をつなぐ多様なビジネスを生み出す土壌となれる。
たとえば、「生産者の顔がみえる朝どれ野菜を売りにした飲食店」「子ども向け体験型学習の提供」
「自然体験・レクリエーション」……。
さらにはひきこもり対策や、職場のストレス軽減のためのリハビリといった新しいニーズへの訴求も考えられそうだ。
米国では、地域社会を中心とした農業と都市との交流が進んでいて、
サステナブルな地域経済圏をつくりあげる「BALLE」という団体が広がっているが、
その日本版をつくるなどの展開もあり得る。
IT(情報技術)を活用し、地方農家と都市生活者をつなげば、
多くのデータが取得でき、より明確なニーズがあぶりだされる。
日本再興戦略の一環として、20年に6次産業の市場規模を10兆円に伸ばすという政府の後押しもある。
農業と都市をつなぐITビジネスの前途は有望だ。

神田昌典の日経MJ連載コラム『タダヤサイ』が秘める価値 フードロスを付加価値に変える驚きビジネスとは?
いかがでしたか?今回は、日経MJに掲載された、農産物をタダでプレゼント、及び販売をする新しいサイト『タダヤサイ』に関する記事を紹介します。
こんにちは!アルマクリエイション若手マーケッターの水落です!
『タダヤサイ』は、規格外の選果漏れした野菜を「捨てるくらいなら消費者にプレゼントしよう」という楽しいサイトのこと。
農家にすれば、せっかく一生懸命に育てた農産物が、ほんの少しのサイズや形の差で「ゴミ」になってしまうわけですから、自家消費できない物でも捨てたくないのは当然です。
そこで、そんな農産物の無駄なく活かそうと『タダヤサイ』のサイトが生まれました。

野菜は無料でも「タダでは終わらない」サイトの本質とは?
『タダヤサイ』のサイトでは、文字通り無料の野菜をプレゼントしています。
サイトに公開されている野菜で気に入った物があれば、申し込みをして当選すると、送料を負担するだけで新鮮な野菜が自宅に届くというシステムです。
しかしこれは、ただ単に「フードロスを減らそう」という試みではありません。生産者からすれば、捨てるしかなかった野菜を「お客様に試食していただく」機会を得ることができるからです。
実は『タダヤサイ』は新鮮な野菜を販売することが目的のサイトです。その中でDtoCの販売モデルを確立するには、本来は余程のブランド品を扱わないとECサイトとして機能しません。
そこで、生産者は自分の野菜の味を知ってもらってブランドを構築し、そこで野菜を貰ったり購入する消費者に対して、『タダヤサイ』はECサイトのブランドを構築できるというわけです。

農家の取り分は小売り価格の3割?DtoCなら8割の収入に!
農家が農協に出荷して通常の流通経路で販売した場合、農家の取り分は小売り価格の3割程度といわれています。
要するに、100円で売られている野菜の原価の内訳は、農家が3割で小売店が2割、残りの5割は物流や農協、卸売市場の経費というわけです。
これでは、農家の仕事が高品質な美味しい野菜作りよりも、とにかく規格に沿ったサイズの野菜をできるだけ低コストで大量に作るしかありません。
でも、DtoCのサイトで販売すれば、農家は売価の8割の収入を得ることができます。だからこそ、たとえ収穫量が減ったとしても「安全で美味しい野菜」を作ることに尽力できるのです。

本物の味と食への価値観はITが変える!
農家が収穫物を農協へ出荷するという従来の方式では、農家の取り分が少ないだけでなく、「味や安全」よりも決められた規格に合わせた「形とサイズ」で値段が決まってしまいます。
これでは、美味しい野菜作りよりも、見た目のキレイな野菜作りが目的になるのも仕方のないことです。
戦後の日本では、大量生産・大量消費、内需拡大がとにかく主眼となり、工業製品から農産物まで「同じ顔が良し」という風潮が強くありました。
それは野菜だけに限ったことではありません。洋服やブランドバッグ、車、髪型、お家まで「同じスタイル」がもてはやされた時代が長く続き、最近になってやっと「個性」が尊重されるようになったのです。
いま、そんな食への個性も強くなっていますが、生産者がせっかく精魂込めて作った食品も、売り手の管理や販売方法次第では台無しになることもあります。
そんな今、ITを駆使したDtoCサイトを活用することで、生産者の顔と想い、そして個性を消費者にダイレクトに届けることが可能になりました。
ECサイトでは、ただ商品を販売することにとどまることなく、その野菜の特徴や美味しい食べ方、生産地の文化や伝統など、これまで知ることの出来なかった歴史まで伝えることができます。
このようなITの活用は、都市部と田舎や過疎地の経済的な繋がりだけではなく、日本古来の味や伝統を後世に残すという大切な役目を果たすことでしょう。
いかがでしたか?このnoteを読んで「興味が出た!」と言う方は、ぜひ一度アルマ・クリエイション代表の神田昌典の「ヒトを動かすコトバ365」をお試ししてみてはいかがでしょうか?

日本のトップマーケッターである神田昌典が執筆しているその日にあったメールマガジンを配信しています。
神田があなたの目標に近づく原動力となる言葉を毎日紡ぎました。
この機会にぜひ、その日からあなたの仕事に役立つ情報をゲットしてみてくださいね!
↓こちらから30秒で簡単無料でお試し!↓
最後までお読みいただきありがとうございます。
それでは、また次回をおたのしみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
