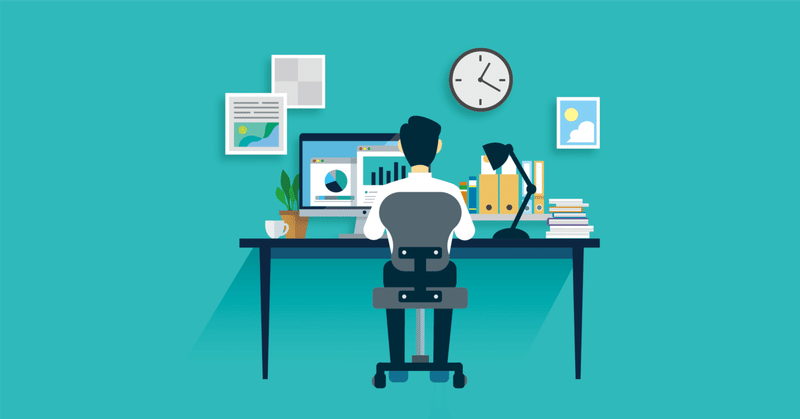
仕事ができるのは残業?定時上がり?
あの人がグループ長になったのは消去法だと思うんだよね
ふと今日パートナーと話していたときに彼が発した言葉だ。どうやら、繰り上がりでリーダー職を仰せつかったらしい。部下であるパートナーからの評価はあまりいいものではなかったので、私の思う「仕事ができる人」の定義を久しぶりに思い返して、noteに書き上げようと思う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
働き方改革が謳われ始めて数年。
ジョブ型雇用や実力主義が囁かれているけれど、今でもよく見るのは「年功序列」が大前提に潜んでいること。今でもどこかの会社でその慣習が引き継がれているのか。と思ったとき、妙な憤りを感じた。
私はすごくラッキーで年功序列(日系企業)と実力主義に近い外資系に勤めている。そして仕事ができる人の定義がこの2社に勤めたことで、わかりやすく私の中で変わっていった。
日系企業で働いていた時は、上司・先輩がいるうちは帰れない。
手持ち無沙汰になるけれど、存在だけはしている。先輩の仕事の一部を手伝ってみたり、今じゃなくてもいい掃除や片付けをやったりと無駄に動いて大体みんなで一斉に退勤するのだ。時間は普段から21時ごろ。
そして、勤怠は手書き。残業は20時間以内に納めろ、という会社の暗黙のルールでいい感じに調整して残業手当は最低限以下。
退職するにあたって、時間をちゃんと測ったら月70〜80時間やっていた。これにはびっくり。さすがにバカバカしくなって退職直前は勤務に支障がないくらいにはギリギリに出勤してたっけ。
転職を数回して、今務めているのが外資系。
日本にある外資系なので、労働基準法はもちろん日本の法律を遵守しているので、海外ドラマで見るような即日解雇はあまり見ることはない。
それでも「外資系」という言葉が引っかかって、入社当時オドオドしていたけれど、先輩・上司の仕事の進め方が前職と異なりすぎた。そこから私の中の働き方改革がスタートした。
営業事務としてチームで働いていた私は、いわゆるシェアードサービス(営業さんから飛んでくる依頼を手が空いているスタッフが緊急度に応じてどんどん捌いていく方式)で、夕方5時半以降に届いた依頼については一律翌日対応と部署内で線引きをしていた。
そうして、他の優先順位が高いものをこなして営業時間内に収めるものだった。この5時半ルールがあっても特にお咎めなし。なんなら残業は悪という前提でみんなが動いていたため、誰も文句は言わないのだ。
管理職の人間もまた残業をすると「早くあがりな」「夜遅くまで仕事するくらいなら、朝対応できるんだったら持ち越しな」とアドバイスをくれるまでだった。残業=仕事ができるの昔ながらの公式が実在しない環境だったのだ。
身をもってこれを体験してからの私は、以下に効率よく仕事を進めて定時で上がるかを考えるようになった。
もちろん残業が発生することもあれば、新人研修で思うように仕事が終わらないこともあったが、80時間ほどしていた残業は10時間以内に収まるようになった。
そして、定時で上がること5年。キャリアアップの話もあり、定時退社のまま役職がつくことに。今でも定時で上がるけど、正直成果さえあげていればいいのだ。
終身雇用が崩壊している今、本当に必要なのは上のいう通りに仕事をする人ではなく、定時あがりでも、成果を出している人が本来きちんとした評価を得るべき人間なのではないか。とまた一つ自分の考えが確信に変わった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
