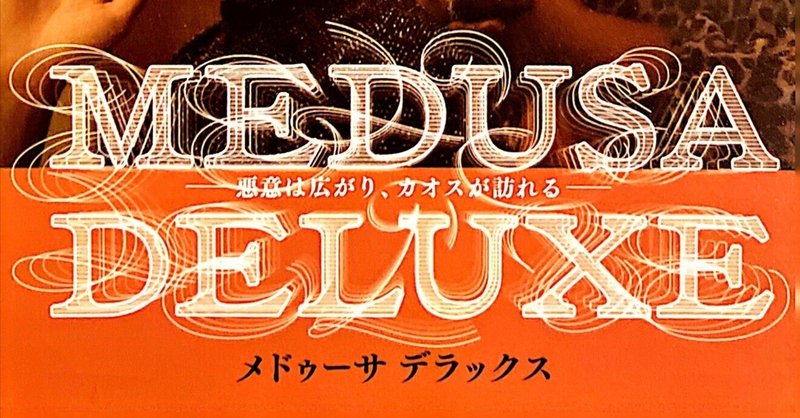
「メドゥーサ・デラックス」は、美容というダイバーシティで閉鎖的な世界を一刀両断した、ドキュメンタリー&ミステリーだった
トーマス・ハーディマン監督の最新作「メドゥーサ・デラックス」の試写を観た。
メドゥーサとは
タイトルの“メドゥーサ”とはギリシア神話に登場する怪物の名称で、頭髪は蛇、歯は猪、手は青銅で黄金の翼をもつと言われる。
その恐ろしい姿のため、見た者は石のように硬直してしまうことから“メドゥーサ伝説”が生まれた。
メドゥーサは英雄ペルセウスに首を切り落とされるが、その首からしたたり落ちる血を右と左の血管で分け2つの瓶に収めたところ、右の瓶の血には死者を蘇らせる力が、左の瓶には人を殺す力があったと言うから、「鬼滅の刃」に登場する鬼舞辻無惨を思わせるような強力キャラだ。
全編ワンショットの緊迫したカメラワーク
映画は殺人現場のシーンから始まる。場所は、年に一度、大々的に開催されるヘアコンテストの控え室。
優勝候補のスター美容師の変死体が、頭皮を剥ぎ取られるという猟奇的な姿で発見され、ショー本番を前に準備で忙しく立ち振る舞っていた関係者たちに衝撃が走る。このコンテストでの優勝がヘアデザイナーとしてのキャリアを大きく左右するとあって、被害者と対立していた立場の人が次々と画面に登場する。
こうしてミステリーの謎を解くための周辺情報を次々とワンショットで追っていき、観客を現場のギャラリーのひとりとしてストーリーへと引き込んでいく。
ミステリー作品として
本作も、ミステリー系のストーリーによく見られる「単純な事件・動機だと思っていたら次々と複雑な背景が表沙汰になっていく」というセオリーに準じた展開になっている。
特に美容師業界とヘアコンテストという設定が効いていて、人間関係の複雑さ、変則性を受け容れやすくしていると感じた。
それはまた、あえて“ヘアコンテスト”という特殊性を出し過ぎなくすることで(つまり美容業界の説明やヘアコンテストの権威付けを強要する演出を避けることも含めて)、日常に潜む人間関係の"闇"を普遍的に描くことが可能になっていたと思われる。
ヘアコンテストとして
本作のもうひとつの見どころは、ヘアデザイン。
ヘアスタイルとウィッグを担当したユージン・スレイマンは、多くのファッション・デザイナーに独創的なルックを提供するアーティストだ。
彼の作品が画面に映り込むことによって、このストーリーの背景に潜んでいた人間関係の多様性が具体的なカタチとなって見えた気がする。
この演出は特筆すべきだろう。
冒頭、ヘアメイクの用語が飛び交っていたので、いくつか紹介したい。
フォンタンジュは、「17世紀後半から18世紀初頭にフランス上流階級を中心に流行した女性の髪飾りおよび髪型のこと」で、ルイ14世の愛人フォンタンジュ侯爵夫人に由来する。
シニヨンは、「束ねた髪をサイドや後頭部でまとめたヘアスタイルのこと」。
遺体の頭皮が剥ぎ取られていたというエピソードも、ヘアスタイルのヴァリエーションと言えなくもないが……。
なお、劇中で“インディアン式”というセリフが出てくるが、アメリカ先住民に頭皮を剥ぎ取る風習はなく、統治側が持ち込んだものだったらしい。処刑や拷問としての皮剥ぎ行為は、古代から世界各地で行なわれている。
また、ガーナの髪型に対するこだわりにも触れていたが、これも西アフリカの文化としてヨーロッパには知られている“あるある話”のようだ。
このように、美容に興味がある人にとっては各所に興味をそそる“隠しアイテム”がちりばめられているので、二度も三度も美味しく楽しめるのではないだろうか。
最後に、音楽にも触れておきたい。
担当したのは、コアレス名儀で活動するエレクトロニック・ミュージックのプロデューサーで、感情を煽るような過剰な装飾を排しながらも無機質に陥らず、物語の時間軸が崩れないワンショットドラマを支える陰の演出家としての役割を全うしていると感じた。
名探偵も登場せず、トラップやミスリードも実はなかった(観客の混乱を誘う演出としてはもちろんあったが)という、シンプルにして多様な映画だった。
あ、パブロちゃんのカワイさに触れるの、忘れた。。。
映画「メドゥーサ・デラックス」公式サイト
Koress『Agor』(2021年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
