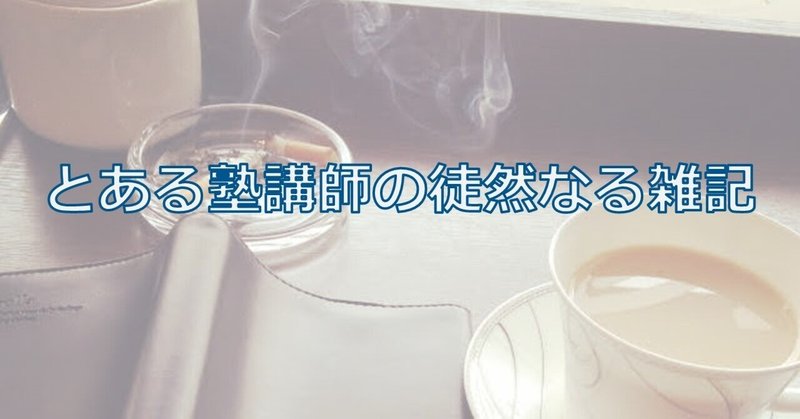
漢字の勉強法
どうも,とある塾講師です。
今日は漢字の勉強法について書いていきます。
漢字の勉強法をどの程度思いつきますか
普段教えている子どもたちに漢字の勉強法にはどんなものがあるか尋ねてみると,思った以上に答えが返ってきません。「漢字練習」とは出てくるもののそれ以上が出てくるのは稀です。また,保護者との面談で国語の話題になった際に,漢字の勉強法を聞いてみても同じように「漢字練習」が出てくる程度です。
皆さんは漢字の勉強法と聞いて何が思い浮かびますか。
私の考える漢字の勉強法
私が考える勉強法は6つあります。それぞれなぜその勉強法を実践するのか説明を交えて紹介します。
準備してほしいもの
勉強に取り掛かる前に準備をしてほしいものがあります。それは「国語辞典」と「漢字辞典」です。これは必須であると私は考えます。1つ注意してほしいことがあります。それは段階にあった辞典を準備することです。
国語辞典については大人も使うようなものでも構いませんが,意味の記載順には少し注意が必要です。例えば「広辞苑」は言葉の意味の古い順に意味が列挙されており,また,古語についても多く収録されているためあまりおすすめはしません。現代で使われている順に意味が列挙されているものの購入をおすすめします。
漢字辞典については学習者のレベルにあったものを準備することをおすすめします。その理由は,辞典に記載されている語彙や説明のレベルが大きく異なるからです。どうせ高校生になれば使うから,と中学生に対して高校生から社会人向けの漢和辞典を購入しても内容が難しすぎるだけだと思います。高校生以上の使用する漢和辞典は英和辞典同様に「漢文を日本語にするために」必要な辞典です。つまり,漢字辞典と漢和辞典の用途は大きく異なります。
中学生向けの漢字辞典でも「漢和辞典」と名の冠しているものもありますが,掲載されている語彙を見てみると,中学生が日常目にする可能性の多い語彙が中心に収録されています。一方の漢和辞典は,下手をすれば大人でも一生目にしないであろう語彙も収録れています。
そのため,小学生には小学生向けの漢字辞典,中学生には中学生向けの漢字辞典が必要になると考えます。小学生向けの漢字辞典を中学生が,中学生向けの漢字辞典を小学生が使うのは大きな弊害はないと思います。
電子辞書を使っても構いませんが,上記に注意をして段階にあったものを選んでください。
漢字の勉強で随時行ってほしいこと
今から紹介する勉強法の②~⑤までは専用のノートを用意して,書きためておき,日々復習も兼ねてそのノートを眺めてください。そして,記憶の怪しいものがあれば,再度漢字練習を行ってください。
前置きが長くなりましたが,本題の漢字の勉強法を紹介していきたいと思います。この漢字の勉強は教科の国語の教科書に新出漢字が出てきたタイミングと一緒に取り組んでいくのが効率がいいと思います。
①漢字練習
これは学校の宿題で出されることが多いと思います。学校の宿題として漢字の勉強というものはこれしかやられていないように思います。私自身も学校でこれ以外の漢字の勉強はやった記憶がありません。
あまり意味のない勉強法だと感じるのは,覚えたい漢字を何十回も練習帳に書くというものです。漢字練習はあくまで形を覚えるためのものだと私は思っています。当然反復は必要になると思いますが,1度の練習ではせいぜい10回程度が限度でとどめてください。
②音読み・訓読みの把握
何を当然のことをと思われるかもしれませんが,これは非常に重要なことだと思います。読み方のパターンを知っていることで,熟語の意味を推測することができます。簡単な例をあげれば,「読書」を「書を読む」のように訓読みにすることで意味が分かるといった具合です。
国語の読解問題で大切なことの一つに語彙力あります。普段の勉強でわからない言葉が出てきたときは,辞書を引けば済む話ですが,試験中に辞書を引くわけにはいきません。
また,これによって熟語の構成もわかりやすくなります。「書を読む」というのは何を「読む」のかを「書」によって詳しく(修飾)しているので,下の字が上の字を修飾していることがわかります。
この音読み・訓読みを調べるときには漢字辞典を使ってください。
③熟語を調べる
漢字辞典を使って音読み・訓読みを調べたら,そのままその漢字を熟語を調べてください。漢字辞典には,書き順,音読み・訓読み,成り立ち,漢字自体の意味,その漢字を使った熟語が載っています。
とは言っても,数多くの熟語があるのでノートに転記する熟語の数を絞るのが現実的かと思います。少なくとも転記をしてほしいのは,今までに目にしたことはあるが,意味があやふやなものです。
この熟語を調べることで,子どもが苦手とする同音異義の漢字にも強くなります。例えば,「おさめる」は「収める」,「納める」,「治める」,「修める」とあります。
「収める」は「収入(入れて収める)」とあるように何かを中に入れるときに使うというようなイメージがあります。
「納める」は「納税(税を納める)」とあるように引き渡すときに使うイメージがあります。
「治める」は「治水(水を治める)」とあるように支配のイメージがあります。
修める」は「修学(学問を修める)」とあるように自分のものにする,身に付けるというイメージがあります。
「収める」「納める」はどちらも中に入れるというような意味があるため,使い分けは難しいところでもありますが,「収める」は手に入れる,「納める」は(中に入れて)終わりにするというほうがわかりやすいかもしれません。
④熟語の意味を調べる
これは国語辞典でも漢字辞典のどちらを使っても構いません。類義語や対義語をのちに調べるため,国語辞典の方が効率がいいと思います。
③で調べた熟語の意味を調べます。その意味をノートへ転記します。このとき注意してほしいことは,1番目の意味のみを見て終わらないことです。語によっては複数の意味があるのでそれらにも目を通しましょう。
⑤例文まで読む
国語辞典でわからない言葉の意味は調べていても見逃しがちなのがこの例文。例文はいわば,言葉の取扱説明書。その言葉の使い方を示しています。どのような文脈でのその言葉が使われるのかがわからなければ,読むにも書くにも話すにも苦労します。
日常会話の中である程度の言葉のつながりの自然さは身に付きますが,見たことも聞いたこともないような言葉に出会ったときには,例文を見なければ使い方はわかりません。また,自身では自然だと思っていた言葉のつながりが実は間違っていたりする可能性もあります。
⑥対義語・類義語を調べる。
④の熟語の意味を調べた際には,対義語・類義語がないかも調べてしまいましょう。対義語・類義語がある場合には解説の最後に記載されていることが多いです。余裕があれば,対義語・類義語の意味,例文まで調べられるとと良いですね。
少しずつでもコツコツと
以上が私の思う漢字の勉強法です。漢字を勉強することは,文章の読解力向上にもつながります。単に漢字練習を繰り返すのは無駄です。断言します。単に漢字練習を繰り返すこと,それはただの作業でしかありません。
漢字は突然できるようになることはありません。日々コツコツと積み重ねることで完成するのが漢字です。
それではまたの機会に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
