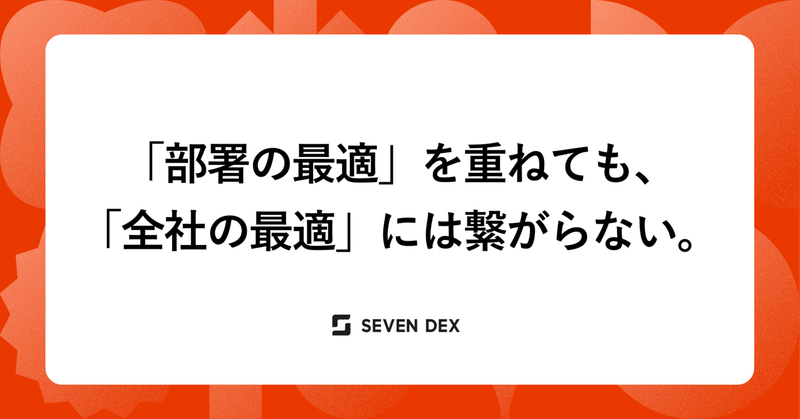
「部署の最適」を重ねても、「全社の最適」には繋がらない。
こんにちは、すぴすたです。現在セブンデックスという会社で、ディレクターと経営企画をしております。
これまで多くのクライアントを支援してきた中で、ここ最近感じていることを自分なりにnoteにまとめてみました。
企業の抱える事業課題が複雑化してきている
近年企業が抱える課題が複雑化しているように感じます。これはクライアントを支援する立場としても、経営企画として社内課題を解決する立場としても感じています。
そしてどちらにも共通して言えるのが、特定の部署のみで解決するのは難しく、様々な部署がコラボレーションする必要があるということです。
「部署の最適」だけでは越えられない壁
今の会社に入社した当初、ちょうどアサインできる案件がなかった私は当時専任者がいなかった社内のマーケティング担当者(自社の案件のリード獲得&育成)に任命していただきました。
試行錯誤を繰り返しながらも、半年後にはリード数が前年比300%超えの成長を遂げ、僭越ながらその期の全社MVPをいただきました。
実際リード数も潤沢になり、当時の自分としても手応えを感じてはいたものの、今経営企画として全社の課題が見える立場になってみると、ただ自分の部署の数字を伸ばしただけでは、不十分だったと感じています。
例えば、毎月のリード数が増えたことで、1件あたりの商談準備にかけれる時間が減って受注率が下がってしまったり、アサインできる人員がおらずお断りすることになってしまったりと、営業チームや案件執行チームなど他の部署との連携ができていないことで様々な課題が発生してしまい、結果として売上の向上にあまり寄与できなかったからです。
つまり、「部署の最適」しか考えておらず、「全社の最適」を考えれていなかったということです。
「部署の最適」だけで、会社が伸びる時代は終わった
先述したような例は今に始まった事ではありませんが、近年こういった事業課題は、事業自体の複雑化、技術革新の加速化、市場環境の激化、価値観の多様化、この4つの変化によって、より複雑化してきています。
事業自体の複雑化
インターネット黎明期と比較すると、ワンソリューションで解決できる課題が解き尽くされており、複雑化した巨大な産業のDX事業や、コンパウンドスタートアップのような複合的な事業などが主流になっていること。
技術革新の加速化
テクノロジーの発展速度が指数関数的に上がっていて、技術や手法、ツールなどがすぐに陳腐化してしまうこと。
市場環境の激化
インターネットやスマートフォンの普及によって、個人でもビジネス参入が容易になったり、グローバル化が進んだこと。またVCなどのリスクマネーも増えたことで競合となるスタートアップ企業が増えたこと。
価値観の多様化
推薦エンジンやSNSの台頭によって、各々の消費者が持つ価値観が多様化したこと。
技術革新の加速化と市場環境の激化に関しては、弊社がプロダクトデザインをご支援中の生成AI系のプロジェクトで、特に痛感しております。
生成AI市場はトレンドの移り変わりが早く、まだどのプラットフォームが覇権を取るかも、次のアップデートでどのような機能が追加されるかも分からないため、プロダクトの仕様も未確定なところが多い状況です。さらに、国内外含め多くのスタートアップが乱立し、最近では大手企業も生成AI事業を成長戦略の柱として掲げるところも少なくありません。

そういった状況下で弊社のあるデザイナーは、どのプラットフォームが覇権をとっても対応できるように、それぞれのプラットフォームに対応した画面や、これから追加されるであろう新しい機能を見越した画面を用意して、先方のPOを良い意味で驚かせていました。
実装されるかどうか分からない画面を用意するということは、「デザイナーの最適」を考えた時、自分の仕事を増やすだけなのでなかなかできません。しかし、「プロダクト全体での最適」を考えた時に、競合よりもいち早くプラットフォームに適した顧客体験やデザインを提供することで、事業の優位性を築けることを理解していれば、自然とこういった行動が生まれるのだと思います。
このように企業が近年の変化に対応していくためには、社員それぞれが「部署の最適」ではなく、「全社の最適」を考えていく必要があります。
社員一人一人が全社の最適を考えるために
社員それぞれが「全社の最適」を考えるためには、部署や役職による境界線を曖昧にして、部署間でのコラボレーションを活性化することが前提になってきます。
弊社セブンデックスではこの思想の元、2018年創業当初からクライアント支援事業の職種において、一般的に言われるセールス、クリエイティブディレクター、PM、UXリサーチャー、UIデザイナー、グラフィックデザイナー、マーケッター…などの区切りはなく、「ディレクター」と「デザイナー」のみでそれぞれの業務範囲は広く、境界線も曖昧になっています。
ディレクターの業務範囲
・顧客へのヒアリング、提案
・課題調査、特定
・解決策立案
・状態定義、体験設計
・ワイヤーフレーム作成/プロトタイピング
・ユーザーテスト
・リリース後のデータ分析
・チームマネジメント
・プロジェクト管理
など
デザイナーの業務範囲
・リサーチ、顧客定義、体験設計、要件定義
・UIデザイン
・ビジュアルデザイン
・デザインガイドライン作成
・アニメーション/インタラクション設計
・デザインメンバーの育成、クオリティチェック
など
また最近いくつかのベンチャー企業やスタートアップなどでは、部署間や事業間でのコラボレーションを促すために、ブリッジ型の職種やクロス型の職種を配置するケースも増えてきています。
ブリッジ型職種
部署と部署の橋渡しをするような役割を持つ職種
・PMM(プロダクト↔︎マーケティング)
・コミュニケーションデザイナー(デザイン↔︎マーケティング)
クロス型職種
複数のサービスや事業を横断する職種
・横断デザイナー(Aサービス、Bサービス、Cサービス)
・横断CXO(A事業、B事業、C事業)
加えて、コンサルティングファームや広告代理店も、今まで持っていたケイパビリティの隣接するケイパビリティを拡張することで、一部署だけに対しての分断的なソリューションではなく、全社に対して統合的なソリューションを提供しようとする動きが見られます。
アクセンチュア:Droga5やシグナルの買収により、広告・マーケティング領域のケイパビリティを拡張
電通:ドリームインキュベータに20%超出資や、イグニション・ポイントの買収、電通デジタルの設立で、コンサルティング領域のケイパビリティを拡張

この時代に成長する企業とは
事業課題が複雑化しているこの時代において、「部署の最適」を重ねても「全社の最適」には繋がりません。
この時代に成長する企業とは、社員それぞれが「部署の最適」ではなく、「全社の最適」を考えられる企業です。そしてそういった企業は、部署や役職の境界線が曖昧でコラボレーションが活発です。
手前味噌ですが、弊社セブンデックスはこれらを満たしている企業だと思います。そして、クライアント支援においても「全社の最適」とは何かを常に問い続ける理想的なパートナーであることを志向しています。
このnoteを読んでセブンデックスにご興味を持たれた、転職をお考えの方や支援パートナーをご検討されている担当者の方は、ぜひこちらもご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
