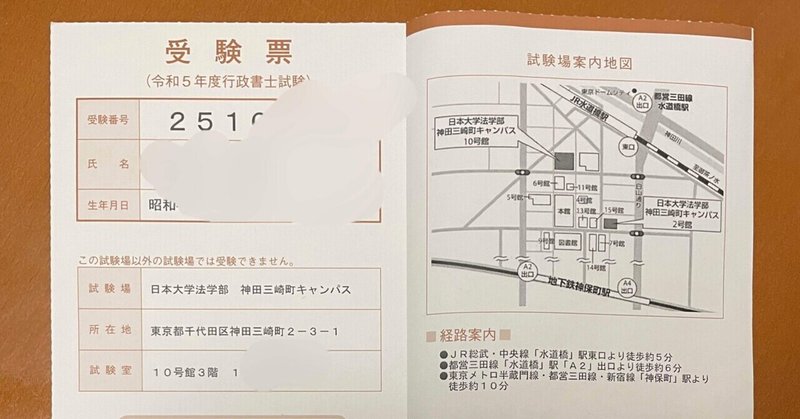
行政書士試験本番 前半
一般知識から解く。それがマイルールだ。難しい時でも足切りだけは避けなければならないし、思考力で解ける問題が多い場合なら、高得点が狙える可能性もある。だから頭がクリアで時間もたっぷりある冒頭の大切な時間を一般知識にあてるのだ。
「んっ、、、?」政経社が例年にも増して、完全に正解と判断できる問題が少ない。「足切りか、、、」冷や汗が滲んだ・・・。それでも情報分野を合わせて3〜4問は常識的に正解と判断できるものがあった。あとはラスト3問の文章理解の内、2問取れればほぼ足切りはクリアできるだろうと目処がついた。実際の文章理解は思いのほか簡単な問題だったから、一般知識を解き終えてようやく少し冷静になれた。
「さあ、法令問題に取り掛かろう。」と気持ちを新たにして時計を見ると、開始から45分ほどが経過していた。周りからはページをめくる音や中にはもう記述を書くコツコツとした音まで聞こえてくる。一般知識に想定より少し時間がかかってしまったから、基礎法学と憲法は少し巻いて行こうと決め試験冊子の頭に戻った。
問一。すぐに2つの選択肢に絞れた。・・・が、何度、読み返してみてもどちらが正解か判断できない。昨年までさんざん苦しめられた“最後の2択で不正解の方を選んでしまうやつ“が来た。こういうとき、どう選んだら正解確率が高まるのだろう。。。悩んだ挙句、何となく違う気がする方の肢を選んだ。昨年・一昨年の試験ではことごとく2択で不正解の方を選んだせいで、数点足らずで不合格だったから、自分な2択選択に自信が持てなかったから。
憲法に入ったが、やはり冷や汗が止まらない。条文知識で解けた1題は正解できたが、他の4題は細かい判例知識を要するイメージ。判例も過去問はかなり回してきたつもりだったが、歯が立たなかった。
一般知識・基礎法学・憲法を終えた時点で、これまでで一番厳しい戦いになっていると感じた。今振り返れば華麗にスルーすべき難問達に正面から向き合って時間を浪費する、という行政書士試験で一番やってはいけないことをしてしまった。巻いて15分くらいで通過しようと思った基礎法学・憲法の7問に25分くらいかけてしまった挙句、自信のある問題は2問だった。
次はいよいよこの試験の山場のひとつである行政法だ。19問もある。ここで17〜18問取れれば基礎法学・憲法のマイナスを挽回できる。模試では17問くらい取れていたから、無理な数字ではない、と思っていた。
問8から解き始めると、なんかサクサク行ける。組み合わせ問題も多いし、ズバリ選ぶ問題でも割と過去問知識でいけちゃう問題が多い。今年の問題は行政法でとらせてもらえるパターンなんだ、と思った。けれど、何か不気味でもあった。
国家賠償・地方自治法に入ってから、雲行きが怪しくなった。・・・来た。見たことのない判例や見たことのない細かい論点の問題が連続攻撃してくる。妙に長い問題文を読みながら、一瞬心が折れた。結局、行政法後半の6問中4問は正解がわからず適当にマークした。しかもじっくり時間をかけて検討した結果だ。。。またやってしまった。なぜ華麗にスルーできなかったのか。激しく後悔&自己嫌悪だ。試験時間はもう2時間が経とうとしていた。残り1時間で民法・商法・会社法・多肢選択そして記述式だ。良い歳こいたオジサンが心の中で泣きそうだった。どこで間違えた?解く順番か?難問への諦めの悪さか?いや、そもそもこの3年間の勉強の仕方そのものか?試験に関係のない雑念が湧いてきてしまった。こりゃヤバい、、、
0.9ミリのマーク用のシャーペンを一度机に置いた。目を閉じると、どこかの予備校の講師が動画で叱咤激励していた言葉が蘇ってきた。「どんなに苦しくても諦めたヤツはそこで負けだ!何度心が折れても最後の1秒まで喰らい付いて粘り倒せ!死ぬ気でそこを乗り越えた者にしか合格は与えられない!」ずいぶん大袈裟だなぁ、、、と冷やかに動画を見ていたはずの自分が、今、その言葉に突き動かされている。
残り1時間弱あるじゃないか。死ぬ気でやれば何とかなるはずだ!不思議と弱気は影を潜め、50歳を過ぎた頃から忘れかけていた戦闘モードのスイッチが入った。やってやる。
民法に取り掛かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
