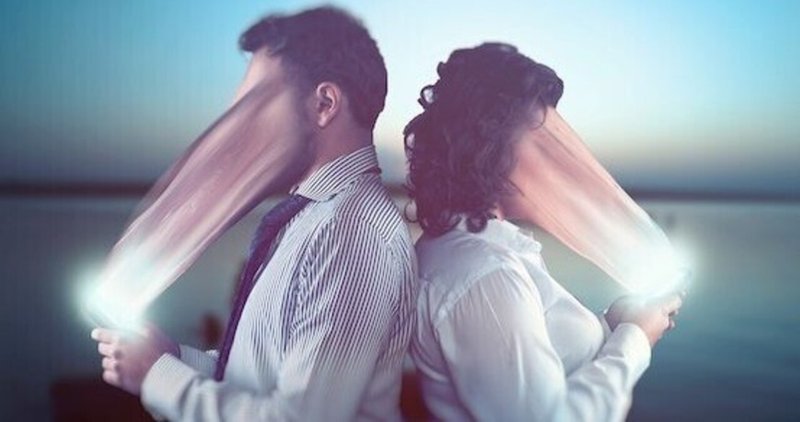
監視資本主義と人間の廃絶
C.S.ルイスの科学的世界観に関する古典的な分析が、私たちの現在の危機を照らし出している。
グレッグ・ライアン
2021年3月3日
The American Conservative
元記事はこちら。
https://www.theamericanconservative.com/articles/surveillance-capitalism-and-the-abolition-of-man/
C.S.ルイスは、『ナルニア国物語』などの児童文学や『純粋国家』のようなキリスト教の弁証論の著作でよく知られているが、鋭い社会評論家でもあり、その時代の社会力学に鋭い認識を示してきた人物であった。
その鋭い分析は、『人間の廃絶』(1944年)に代表されるように、常にユーモアに満ちているわけではない。ルイスは3つの短いセクションで、当時の支配的な教育観が、人間の崇高な概念をいかに弱めようとし、その代わりに、人間の知覚は客観的に証明できないので、完全に主観的であると主張することを説いている。
そして、このような取り組みによって、人類が歴史的に継承してきた価値観や健全な社会を維持するために不可欠な価値観を理解するための伝統的な教育が、やがてすべて排除されることになるという。
ルイスは、人類の古代の知恵を「タオ」と呼んでいる。タオを古代中国の「道」の概念に限定するのではなく、何世紀にもわたって東西両文明が収集したすべての知恵の略語として使っているのである。
ルイスは、人間の自然に対する征服が頂点に達し、「人間形成者」が「全能の国家と不可逆の科学技術」を所有し、「すべての後世を好きな形に切り取ることのできる調整者の一族」となる歴史の段階が来ることを想定している。
さらに、このコンディショニング・エリートは、タオを次世代に伝えることを放棄し、代わりに「単なる自然現象」としての価値を公布し、「コンディショニングの一環として弟子」に伝達することになる。
コンディショニングを行う者は、「良心の生み出し方を知り、どのような良心を生み出すかを決め」、「外側に、上に、自由に」立ち、「自分たちの正当な理由のために、どのような人工的なタオを人類に生み出すかを選ぶ」ことになるのである。
そして、条件付けのエリートの動機はどうだろうか。彼らは当初、自分たちを「人類の奉仕者、守護者」と考えていたかもしれないが、ルイスは彼らの善意が持続することはないと言う。
それはコンディショニング・エリートが悪い人間だからではなく、「彼らは人間ではない」という事実によるものだ。タオの外に出て、虚空に足を踏み入れてしまったのだ。
また、その対象は必ずしも不幸な人間ではない。彼らは人間ではない、人工物なのだ。人間の最終的な征服は、人間の廃絶であることが証明されている。
善が「論破」されると、残るのは無制限、無優先の欲望だけだからだ。「あらゆる価値判断の外に立つ者は、自らの衝動の一つを他の衝動より好む根拠を、その衝動の感情的強さ以外に持ち得ない」のである。
皮肉なことに、コンディショナーが人間の本性を捕らえることは、人間のために自然を手なずけるというタオの機能を失わせる代償となり、その結果、コンディショニングされる側とする側の両方にとって、人間の存在の状況を決定する上で自然が回帰する扉を広く開くことになる。
ショシャナ・ズボフが最近発表した監視資本主義の物語は、C.S.ルイスの不穏なビジョンを具体的に実現したものとして、その正当性を強く主張している。
彼女は、2019年に出版した『監視資本主義の時代』において、人間の自由に対する最大の脅威と21世紀の最も重要な問題を特定し、分類し、定義しようとすることで、私たち(とにかく私たちのほとんど)に対して大きな奉仕をしてくれているのです。
「権力の新境地における人間の自由への戦い」と副題が付けられたこの研究は、インタラクティブな技術が個人の自律性と社会の繁栄というこれまでの概念にもたらす挑戦について概説しています。
ビッグデータ、ビッグテック、そして彼女が「ビッグ・アザー」と呼ぶものの分析を通じて、ズボフは現代の包括的なダイナミクスに取り組み、電子的に媒介されたライフスタイルへの急速な移行から生じる、誰もが感じているがほぼ同じように誤解されている社会の苦境を明らかにする。
監視資本主義の時代』は、ルイスの『人間の廃絶』における分析に真っ向から一致するものである。
ズボフは、監視資本主義を、「人間の経験を、行動データに変換するための無料の原料として一方的に主張し、独自の行動余剰として宣言し、あなたが今、すぐに、そして後で何をするか予測する製品に作り上げる」現象であると述べている。
GoogleやFacebookなどの監視資本主義者は、経済史家カール・ポランニーの「二重の運動」を阻害し、自由市場が支配からの究極の保護を提供するというハイエクの主張を覆し、新封建制の時代を到来させる可能性を持っている。
ズボフは、ハンナ・アーレントの「所有権喪失」の概念を「デジタル所有権喪失」として更新し、過去四半世紀におけるインターネット活動の一見無害に見えることが、民間経済主体の領域内と国家権力に対する大規模かつ微妙な権力移譲に至ったことを説明している。
監視資本主義は、20世紀の経済的分業の代わりに、21世紀の「知識の分業」を生み出しました。監視資本家は自らのプライバシーに対する権利を保持する一方で、アルゴリズムによる分析と継続的な実験を通じて、デジタル社会的交流に携わる他のすべての人々のプライバシーをますます侵害し、結果として行動を捕らえ、エミール・デュルケムの「権力の極端な非対称性」に近い状況を生み出し、ルイスの構想である条件付け者と条件付けられた者の間の社会的隔たりにも類似するものにしています。もちろん、こうしたことはすべて、人間の善意と互恵性への啓蒙主義的な信仰に支えられ、科学による人類のどうしようもない進歩がもたらされたのである。
しかし、インターネットやオンライン・コミュニケーション、スマート・デバイスの普及により、「支配的な企業が成功しているのだから、その企業も正しいに違いない」という自然主義的な誤謬が蔓延するようになった。ズボフによれば、これは市民の「未来時制への権利」、つまり「まず事実を想像し、それを実現するために意志を持つ」能力に対する直接的な脅威である。電子的に接続され、観察される行動があまりにも一般的であるため、交渉や契約、信頼がもはや必要ない。あらゆる民間経済主体が(通常の大手ハイテク企業以外の)顧客の行動を十分に認識できる電子システムを獲得・展開し、許容できない行動と見なされたときにサービスを簡単に停止できるようになるからで、これはズボフが「無契約のディストピア」と呼ぶものに相当する。このようなプロセスがワープスピードで進むと、人間はますますアイデンティティを奪われる。だからズボフは、「監視資本主義によって形成された情報文明は、人間の本質を犠牲にして繁栄し、我々の人間性を失う恐れがある」と断言しているのだ。
全体主義が国家を支配するビッグブラザーの代わりに、西側社会は今、ビッグアザー-"人間の行動をレンダリングし、監視し、計算し、修正する感覚的で、計算的で、つながった人形 "に直面しているのだ。
監視資本主義の台頭は、100年前の全体主義の出現に似ている。今日も第一次世界大戦直後も、前例のない現象が、不可解な政治的展開とコミュニケーション技術の劇的進歩に支えられ、強く感じられるが定義も分類もできない新しい社会現実を生み出しているからである、とZuboffは主張している。
特に、監視資本主義が非国家主体によって推進され、政府権力を掌握し利用する可能性があるため、ファシストや全体主義国家に対する人間の自由のための闘いという20世紀の物語に染まった欧米の一般市民の監視の目には留まっているのだ。
ナショナリズムを自由への最強の脅威であり、大国間戦争の手段であると断じる西側社会の物語は、監視資本主義を、危機に対処するために喚起されなければならない必要なレベルの分析、懸念、解決策の模索から遠ざけている。
科学的な戦略によって自然を最高にしようとする人類の運命に関するルイスの広範な予言と、インターネット・メディアへの屈服に関するズボフの説明との間の重複は、明白であり、避けられないものである。
ズボフは監視資本主義に不可欠な条件付けの行為について言及し、ルイスは残りの私たちを最初に罠に誘い込む小さなエリートを特定するために「コンディショナー」という言葉を用いている。両者とも、クリストファー・マーロウの『ファウストゥス博士』を引き合いに出して、このダイナミズムを解明している。
ルイスは、「新しい時代(科学の時代)の主奏者」であるフランシス・ベーコンが、悪魔を召喚するファウストの後継者であると明言している。そして、おそらく最も痛烈なのは、ルイスもズボフも、目の前にある人間性への挑戦の巨大さを大胆に特徴付けていることである。ズボフにとって、監視資本主義は人間から自律性と自己決定を奪うことを目的としており、ルイスにとって、自然に対する勝利の宣言はまさに「人間の廃絶」を意味する。
ズボフ氏は救済策として、国民の問題意識が大きく高まり、監視資本主義を封じ込めるための法的制裁がなされることを期待している。しかし、近い将来、このような解決策がもたらされるとは思われない。
しかし、ひとつだけ確かなことは、このような条件付けに直面した場合、たとえ社会的距離を置く時代であっても、有機的で物理的な人間の共同体を維持するためにできる限りのことをしなければならない、ということです。
グレッグ・ライアン:テネシー州ジャクソンにあるユニオン大学の政治学准教授。元海軍情報将校で、著書に『中国、キューバ、イランに対する米国の外交政策』。The Politics of Recognition』(Routledge, 2018)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
