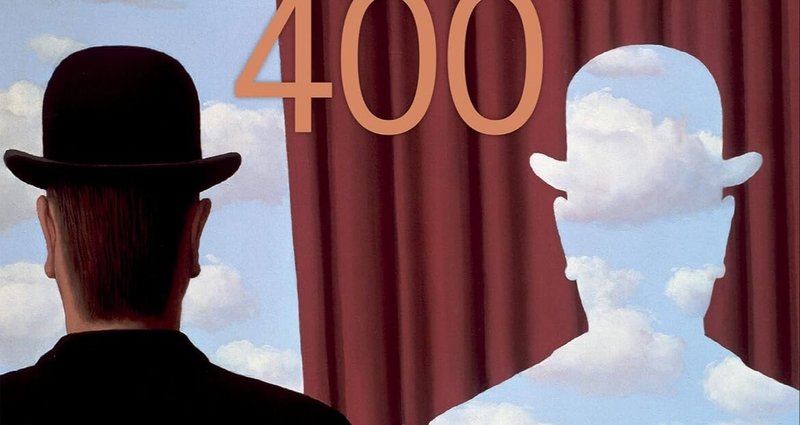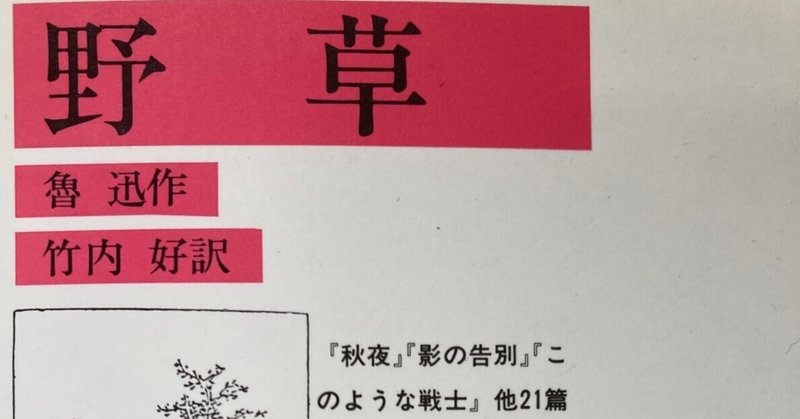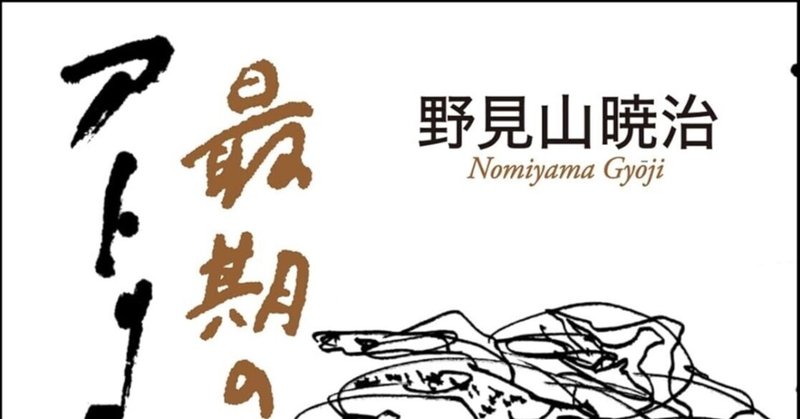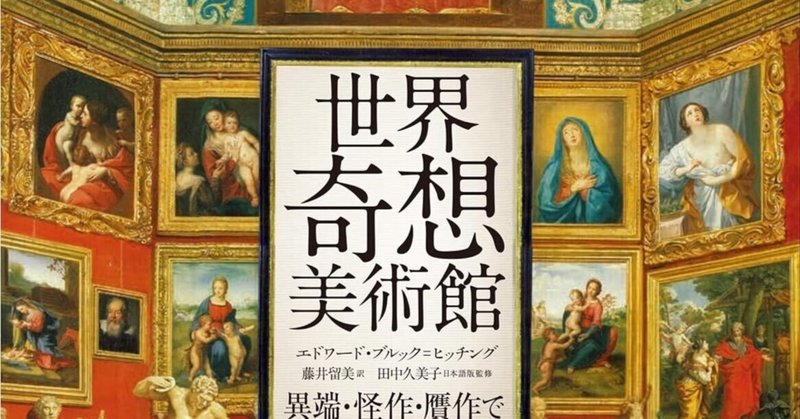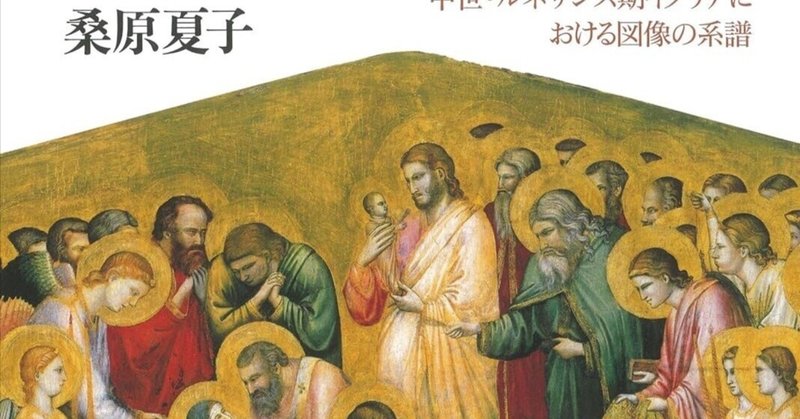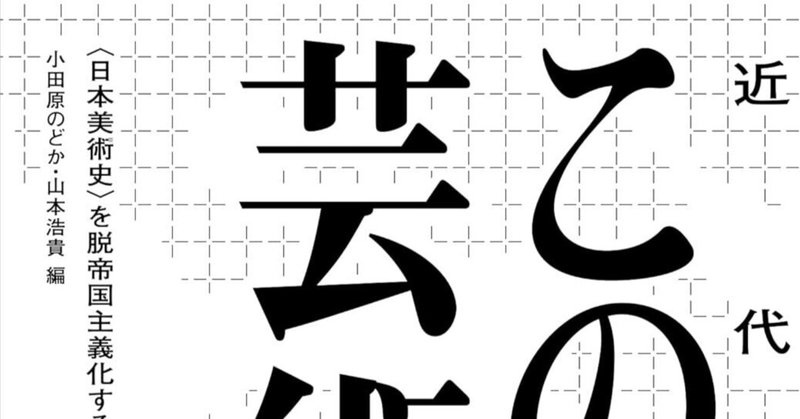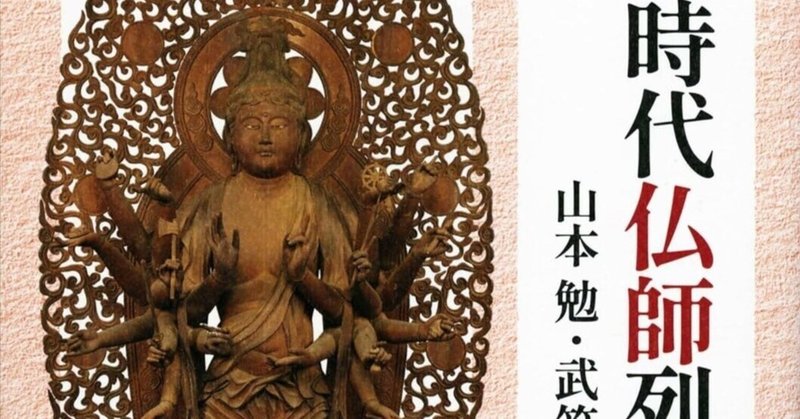2024年1月の記事一覧
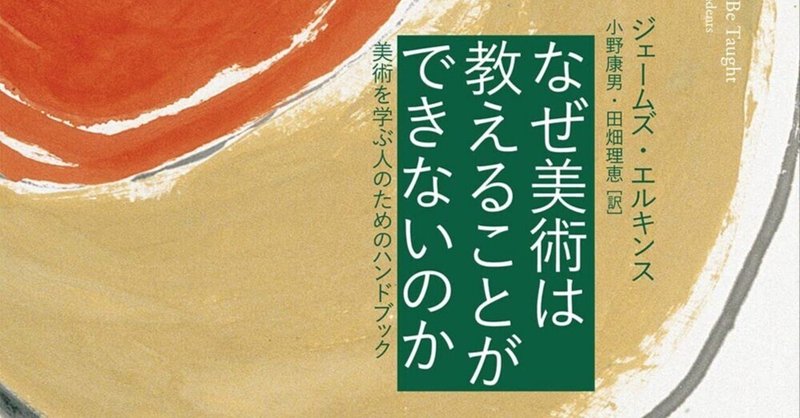
【美術ブックリスト】 『なぜ美術は教えることができないのか: 美術を学ぶ人のためのハンドブック』 ジェームズ・エルキンス著、 小野康男・ 田畑理恵訳
【概要】 「美術を教える」とはいったいどういうことなのかを、歴史を踏まえた上で美術教育の現場である美術大学のスタジオ(制作室、アトリエ)での活動の観察をもとに論究していく。 第1章「歴史」では古代の美術学校、中世の大学、ルネサンスのアカデミー、バロックのアカデミー、19世紀のアカデミー、バウハウスでどんな教育がなされていたかを解説。中世の工房が社会から知的に孤立していたことや、バウハウスのカリキュラムは普遍的な指導のようでありながら実はその根拠は不合理であることが示される。