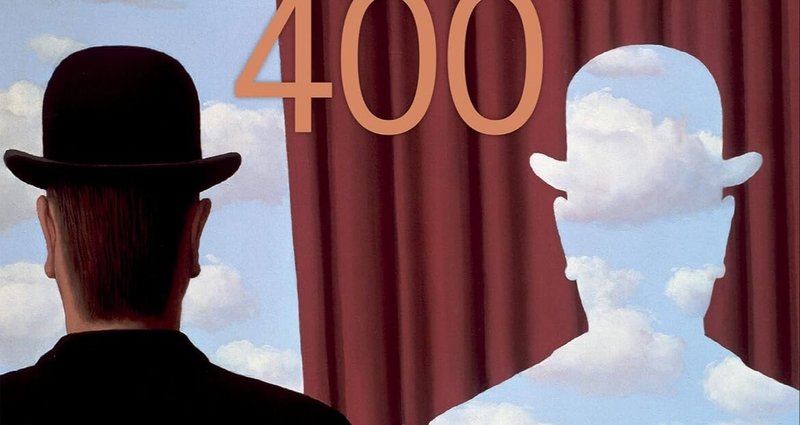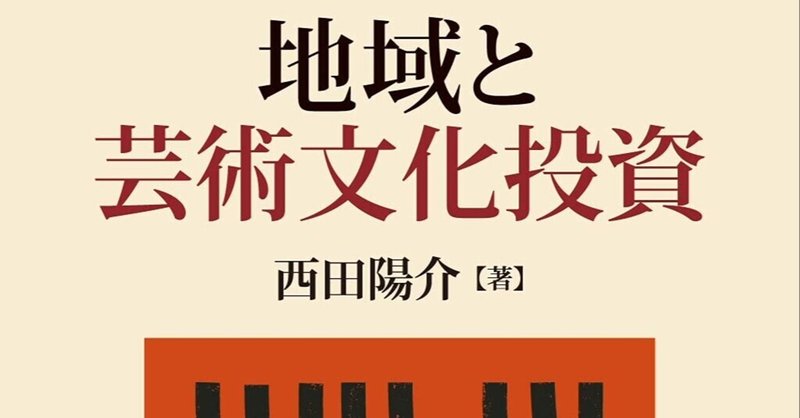2021年7月の記事一覧

【美術・アート系のブックリスト】とに〜著『名画たちのホンネ: あの美術品が「秘密」を語りだしたら…… 』三笠書房(王様文庫)
とに〜さんは元吉本興業の芸人さんで、「アートテラー」として活躍。アート系のイベントの司会やレポーターとしても美術業界でもよく知られています。昨年は、美術館を紹介する『東京のレトロ美術館』も出版されました。 本書は、有名絵画の絵の中の人物(風景や建物の場合も)が語るというユニークなアート本。史実に基づきながらも妄想の限りを尽くして語っています。俵屋宗達の「風神雷神」がサンドイッチマン風の漫才になっていたり、デュシャンの『泉』がヒロシ風に「便器です。・・・出品を拒否されたとです