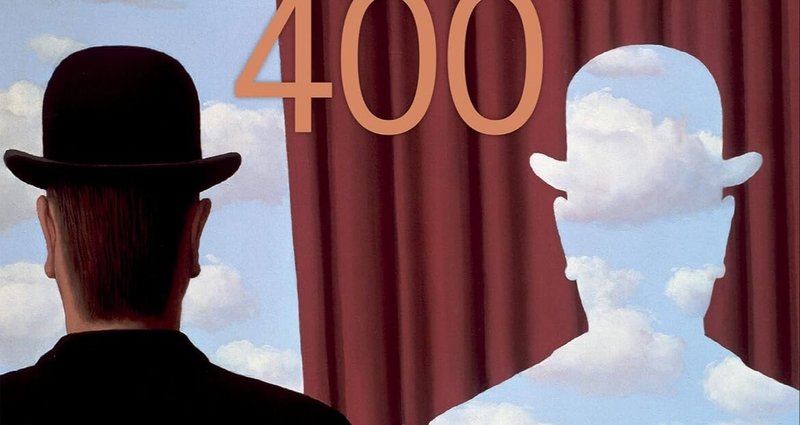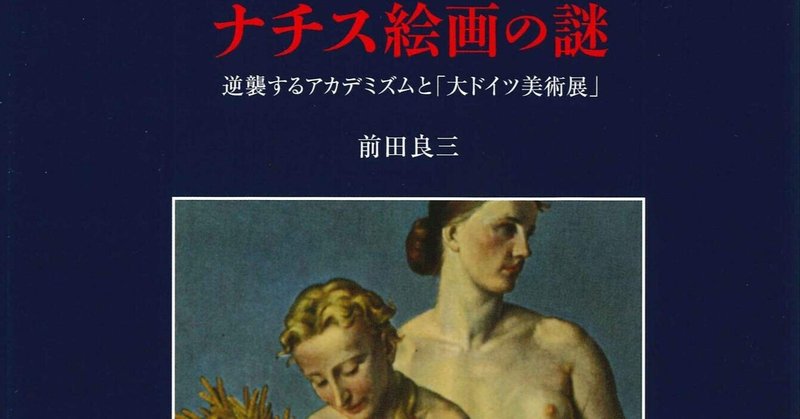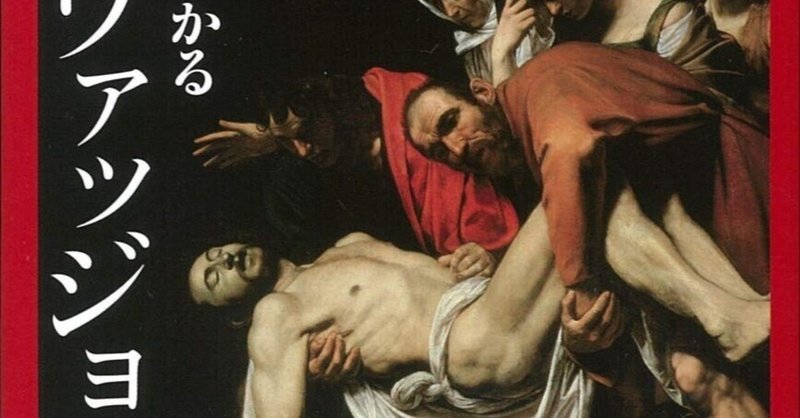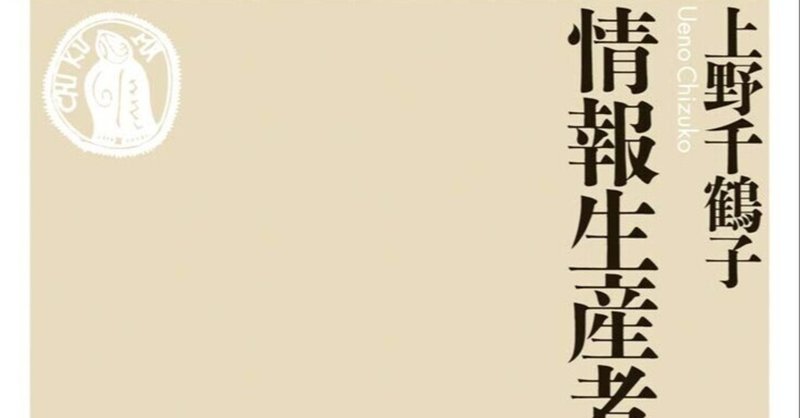2021年4月の記事一覧

【美術・アート系のブックリスト】コシノヒロコ著『コシノヒロコ HIROKO KOSHINO EX・VISION|To the Future 未来へ』青幻舎
4月8日から6月20日まで兵庫県立美術館で開催中の「コシノヒロコ展」の公式カタログ。 1937年大阪・岸和田に生まれ、兵庫・芦屋に在住。ファッションを年齢、性別、国籍、民族、社会的地位を超えるものとしてとらえて制作してきたそうです。展覧会では、コレクションで発表された洋服のほか、デザインの源としてきた絵画制作、若手アーティストとのコラボレーションなどを展示。日本を代表するデザイナーの一人の仕事の全貌を一望します。 確かにデザインされた洋服とドローイングを並べてみると、服に

【美術・アート系のブックリスト】 今村信隆著, 佐々木亨著『学芸員がミュージアムを変える! 公共文化施設の地域力 』(文化とまちづくり叢書)水曜社
ミュージアムと人、ミュージアムと町との長期的なかかわりを考えるのが目的。3年間にわたる北海道大学での研究プログラムをまとめたもので、主に美術館、博物館の学芸員が地域とどう関わるかをレポートしています。 これまでのような単なる教育ではなく、医療と博物館との連携を探る試みや障害者アートの展示、高齢者との連携、郷土の作家をどうアウトリーチ(利用の裾野を広げるため施設訪問など対外的に広報活動をすること)するか、また文化拠点としてまちづくりとどう関わるかなど、さまざまな事例がまとめら

【美術・アート系のブックリスト】Maria Brophy著『Art Money & Success: A complete and easy-to-follow system for the artist who wasn't born with a business mind. 』
訳すと、「アートとお金と成功と ビジネスマインド・ゼロの芸術家のためのデキル成功法」。 カリフォルニア在住のサーフボードに絵を描く画家の奥さんが、ご主人をマネージメントした経験をもとに、どうすれば芸術家として経済的に生活できるかを説明しています。 実際の体験をもとに、宣伝の仕方、作品の値付け、注文の取り方、価格交渉、契約書の具体的な文言まで平易な英語で説明してくれます。小規模な作品販売から大企業と契約、チャリティの申し出への対処など、さらに無料で描いて欲しいと頼まれた際の

【美術・アート系のブックリスト】Cory Huff著『How to Sell Your Art Online: Live a Successful Creative Life on Your Own Terms』 ペーパーバック
訳すと「自作をネットで売ろう」。 画廊を通さず、画家自身がインターネットなどで作品を販売して生計を立てるための指南書です。ここでいう画廊を通さず、というのは画商との交渉が苦手な場合もありますし、単に自分一人で活動したいという場合もあります。いずれにしても、オンラインツールをどう使えば顧客を獲得できるかが書いてあります。 この手の本に共通するのですが、芸術家は経済に無頓着で、経済から離れて暮らしたいと思っているという現実に対する処方から始まります。 Facebookのほか、
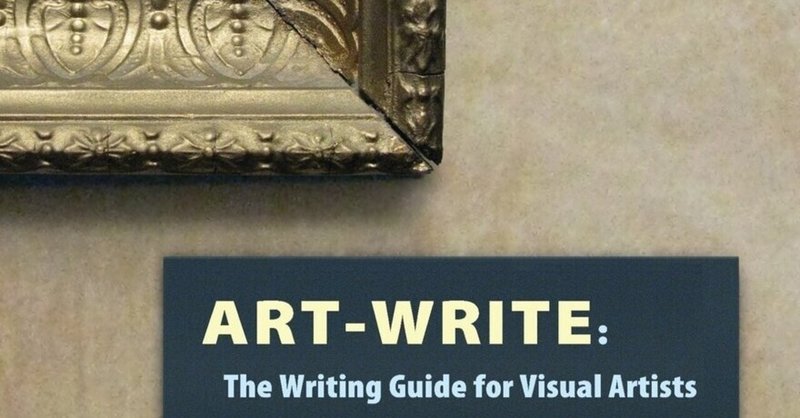
【美術・アート系のブックリスト】 Vicki Krohn Amorose著『Art-Write: The Writing Guide for Visual Artists: Crafting Effective Artist Statements and Promotional Materials』
アーティストステートメントの書き方指南書。なかなかうまくまとめてあり、私の考えとも多くの部分で重なります。特に作品制作を「What」「How」「Why」の三つの曲面で語るところは、昨年、東北芸術工科大学と広島市立大学で私が話した内容とほとんど同じでした。 作家の常套句である「説明できない」「見る人が自由に考えて」に対する批判も、「何も考えていないアーティストにとっての便利な言葉だ」と手厳しいですが、その一方で「言葉ですべてを語らなければならないいわけではない。作品理解の手助
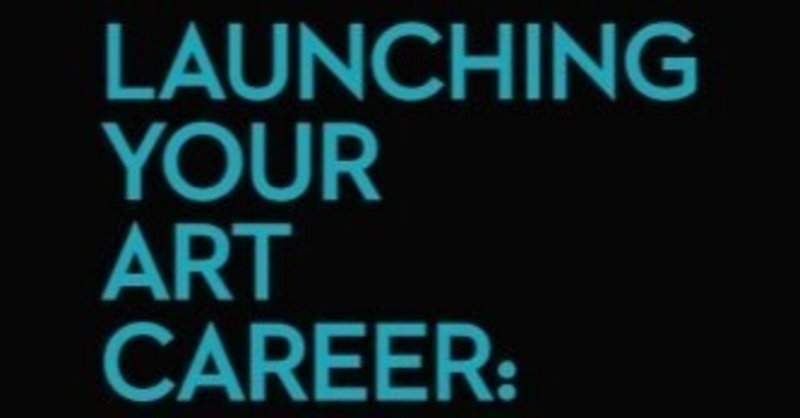
【美術・アート系のブックリスト】 Alix Sloan 著『Launching Your Art Career: A Practical Guide for Artists』
訳せば『さあアーティストを始めよう』というところか。 アーティストのための実践的ガイドというだけあって、アトリエの借り方、画廊へのアプローチ、展覧会の開き方、奨学金へのエントリー、美術業界の常識、売り上げの取り分、値付け、納税まで、これからアーティストになりたい人が知っておくべきことが一通り説明されている。最後に40人あまりの先輩アーティストや画商など業者からのアドバイス集があるが、概ね画商が夢を語り精神論が多いのに対して、アーティストのアドバイスが現実的なのが面白かった。