
『老アントニオのお話し』続編#3 第2部 (1996年1月~1998年8月) われわれの背後には、あなた方であるわれわれがいる
目次
まえがき
1 夢のお話(1996/1/2)
2 虹の話(1996/1/8)
3 フー・メン(1996/1/9)
4 種を播く(1996/1/10)
5 夜の太陽を探す(1996/4/6)
6 道と道を歩む人のお話(1996/4/7)
7 始まりと終わりのお話(1996/6/30)
8 道を創るお話(1996/7/6)
9 山に生きる死者たち(1996/7/27)
10 遠くと近くを見つめること(1996/7/31)
11 騒音と沈黙のお話(1997/2/17)
12 理性と力の話(1997/6/20)
13 沈黙の音(1997/7/1)
14 われわれは誰でもない(1997/12/15)
15 他者のお話(1998/1/21)
16 埋められた鍵のお話(1998/2/24)
17 上と下のテーブル(1998/2/26)
18 ライオンと鏡のお話(1998/7/17)
19 水のなかの魚(1998/7/17)
20 記憶の容器のお話(1998/8/28)
まえがき
今回の第2部のお話は、先住民全国フォーラムや「第一回新自由主義に反対する大陸間集会」が開催された1996年から、1997年12月のアクテアル虐殺に代表される抵抗を続ける先住民共同体への政府側の軍事的攻勢に対抗するため「先住民族の権利認知と殲滅戦争の停止」を求める全国協議が提起された第5ラカンドン密林宣言(1998年7月)の時期に発表されたものである。
第1部では、副司令マルコスが、トニータ、エバ、エリベルト、ベトといったサパティスタ共同体たちのこどもたちに語って聞かせたお話しというものがいくつもあった。第2部では、こどもたちはほとんど登場することはない。替わって、ラ・マールという副司令の恋人[実際は結婚し、こどもがいたが、数年後、別れたという]?が登場するようになる。ラ・マールは、当時のサパティスタが模索してした市民社会との連携を暗示するものと解釈することができそうである。
1 夢のお話(1996/1/2)
追伸-夢を見ること、それと同じだが、戦うことを教えよう
マチェーテを研ぎながら、老アントニオは小屋の入口で煙草を喫っていた。コオロギの鳴き声と疲労に包まれ、私は彼の横でウトウトしていた。老アントニオが細長い紫煙を立ち上がらせていたときから、10年前であれ、10年後であれ、空は夜の海のようだった。空は大きすぎた。どこで始まり、どこで終わるのか、わからなかった。
月は数分前に沈んだ。明るい雲が山の頂をくっきりと照らした。月の光で銀メッキを施された山の頂は、媚びを振りまくためのバルコニー、みごとな飛込みのための踏み板台、新しい飛行機便の滑走路のようだった。最後の一筋の黄金色の光は、それを待ちわびていた渓谷にむかってウィンクを投げ掛けた。その後、黄金色から銀色へと、そして真珠のような白色へと変わっていった。つぎはぎだらけの帆を膨らませ、光は上に向かって飛び出した。夜が航海を始めたのである。下界では、静けさとノスタルジーが待ち受けていた。
1975年、1985年、1995年の12月。海はいつも東に広がっていた。雨は降っていない。寒さで、衣服だけでなく、しだいに息苦しくなる浅い眠りに潜む不安にみちた夢までもが、濡れていた。私が目覚めたのを横目で確認すると、老アントニオはたずねた。
「何の夢を見ていたのだ?」
「いいえ、何にも」と返事し、弾薬帯にはさんだパイプと煙草を探した。
「そりゃ、ダメだ。夢を見ながら、人は夢を見て己れを知る。夢を見ながら理解する」
こう言った後、老アントニオはふたたび自分のマチェーテの薄刃をヤスリでゆっくりと研ぎはじめた。私はパイプに火をつけながらたずねた。
「ダメって?どうしてですか?」
老アントニオは研ぐのをやめ、刃の具合を確かめ、マチェーテを脇においた。手と唇を使って煙草を巻くと、お話を始めた。
夢のお話
「これからする話は誰かから聞いたものではない。たしかにわしの爺さんが話してくれた。だが、爺さんはわしにこう言った。夢を見なければこの話は理解できない。だから、おまえに語るのは爺さんがわしに語った話ではない。わしが夢見た話である」
老アントニオは足を伸ばし、疲れた膝をブラブラさせた。煙草の煙を吐き出した。その煙で、彼の脚に落ちた青味がかった葉に届く月の光が遮られた。そして、話は続いた…。
偉大な先祖たちの顔に刻まれている一本一本の皺に、われわれの神々は潜み、生きている。それはわれわれの時代まで続く悠久の時間である。その時間とともに、われわれの先祖たちの理性は歩んできた。もっとも昔の先祖たちのなかで、偉大な神々が話し、われわれはそれを聞いていた。雲が大地に横たわり、山々の手でつかまれる。それと同時に、男や女と遊ぶために、最初の神々は大地に降りたった。そして、彼らに真実のことを教えた。最初の神々はほとんど姿を現わさず、夜や雲の相貌となって現われるだけだ。夢とは、われわれがよい存在になることを夢見ることだった。
夢を通じて、最初の神々は、われわれに話しかけ、教えた。夢を見られない人間は、大いなる孤独感を抱き、自分の無知を恐れのなかに隠した。最初の神々は、トウモロコシの男女に夢見ることを教えた。それは、話すことができ、知ることができ、己れを知ることができるようするためである。そして、トウモロコシの男女が人生をともに歩めるようにナウァル[人と共通の魂をもつとされる守護動物]を授けた。
真の男女のナウァルは、ジャガー、鷲、コヨーテである。ジャガーは戦うため、鷲は夢を抱くため、コヨーテは考えをめぐらし権力者の欺瞞に騙されないためである。

ジャガー、鷲、コヨーテという3種のナワル
最初の神々、世界を形づくった神々の世界では、あらゆるものが夢だった。われわれが生き死にする大地は、夢を映している大きな鏡である。そこには神々が住んでいる。偉大な神々はそこでいっしょに住んでいる。誰もが同じように生きている。誰かが上で、誰かが下ということはない。
政府がおこなっている不正は、世界を解体するものであり、一部の少数者を上に、ほかの大多数を下においている元凶である。もともと、世界はそのようなものではなかった。真の世界、最初の神々、世界を誕生させた神々の夢を写す偉大な鏡は、とても巨大で、誰もが同じように入ることができた。少数者を上に鎮座させ、大多数のものを下に押し込めるため、小さくなってしまった今の世界とはまったく違っていた。今の世界は完璧ではない。最初の神々が住んでいる夢の世界を反映するよい鏡ではない。
神々はトウモロコシの人々に尊厳という鏡を贈った。その鏡では人間はすべて対等に映る。対等でないなら、反乱を起こすことになっている。こうして最初の先祖たちの反乱が始まった。今、彼らは死んでいる。だが、それによってわれわれは生きることができる。
尊厳という鏡は、暗闇をまき散らす悪魔を打ち負かすのに役立つ。暗闇の支配者は鏡に映ると形を失ってしまう。尊厳という鏡の前では、世界を不平等にする暗闇の支配者はその影も形もなくなる。
神々は四つの基点をつけた。それは世界が横になるためである。神々が疲れたからではない。男女がともに歩き、誰もが入り、人の上に人がいないようにするためである。飛ぶだけでなく、大地の上にいることができるように、神々は二つの基点をつけた。世界に意味をもたらし、真の男女に任務を与えるのは七つの点である。つまり、前と後、右と左、上と下である。そして七番目の点は、われわれが夢を見る道である。トウモロコシの男女、真の男女のたどるべき命運である。
新しい男女が夢で生きられるように、神々は女の胸に月を与えた。その夢から歴史と記憶は生まれる。夢なしでは忘却と死が巣くってしまう。われわれの偉大なる母である大地は二つの乳房をもつ。それは夢を見ることを学ぼうとする男女のためである。人は夢を見ることを覚えながら、成長や尊厳をもつこと、戦うことを学ぶ。だから、真の男女は「夢を見よう」と言い、「戦おう」と言う。
老アントニオは黙った。黙ったのは私が寝てしまったからである。私が夢を見ている夢、私が知っている夢、そして私が知っている夢を私は見ている…
頭上では、月の胸が天の川に乳を与えていた。夜明け前は女王だった。すべてが実行されて、夢を見ながら、戦うだけとなっている。
2 虹の話(1996/1/8)
この喜びに応えるために、皆さん[1996年1月初旬、サンクリストバル市で開催された先住民全国フォーラム参加者]にお願いしたい。あなた方のひとり、褐色の肌、先住民の血をもつある偉大な賢者から、10年前に私が聞いたお話をさせてください。
虹の話
すでに日は暮れ、夕闇が迫っていた。周囲は夜明け前にも見られる輝きを帯びた灰色に満ちていた。老アントニオはペルガミーノ種のコーヒーが入った二つの袋を詰め終え、私の傍に座っていた。同志のいない集落を通過する際に支援してくれる連絡員の到着を私は待っていた。村を通過するのは夜のはずだった。1986年が開けたばかりだった。後にわれわれの側になった人々からも身を隠さなければならない時期だった。私は太陽が沈む西を見ながら、パイプの煙をくよらせ、これまでとちがう明日を夢見ていた。

サパティスタのコーヒー畑
老アントニオはじっと黙っていた。煙草を喫いながらお話をする前、いつもの煙草を巻く作業の音だけが聞こえていた。老アントニオは口をあけなかった。彼を見つめていた私をじっと見つめ、私が話しだすのを待っていた。最後の煙をパイプの先から立ち上がらせながら、私はつぶやいた。
「いつまで、われわれはまわりの人から身を隠さねばならないのだろう?」
咳払いをした老アントニオはやっと煙草に火をつけ、話を始めた。希望の光が見えてきた人のように、夕闇に光をともすように、老アントニオはゆっくりと語りだした。
七つの虹の話
原初の時代、世界が創られた。それ以後、われわれのもっとも偉大な祖父母たち、もっとも偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々は、その世界を歩くようになった。そして、その神々はトウモロコシの男女と話すため、地上に降りた。それは、今のように雨が降り、チラチラとしか太陽の光が差し込まない寒い昼下がりだった。
いちばん最初の神々は、腰を据えてトウモロコシの男女と話しあった。それは、真の男女が歩くべき道に関する合意を結ぶためだった。この神々は、いちばん最初の神々、世界を誕生させた神々である。後にやってきた神々のようにいばり散らすことはなかった。最初の神々はいばり散らすこともなく、トウモロコシの男女とよい合意を結ぼうとした。神々は人間と協力し、よい合意、よい言葉とともに、良い道を探そうとした。そのときは、最初の世界の最初の時の昼下がり、やはり今のような昼下がりだった。もっとも偉大な神々は対等な存在としてトウモロコシの男女と話し合った。
神々は、ほかの男女、ほかの言葉、ほかの考え方とよい合意を探すという合意を結んだ。ほかの男女、ほかの色、ほかの心が理解できる言葉を探すため、トウモロコシの男女は自分の心の奥底まで歩かねばならなかった。
やがて、良い世界を創るため、トウモロコシの男女がすべき作業に関して、ひとつの合意が得られた。われわれを新しい存在に変えるための最初の重要な作業は七つである。そのような合意が得られた。世界を誕生させた最初の七つの神々は言った。話し合いながら、よい世界を創り、われわれを新しい存在に変えるため、遂行すべき作業は七つである。もっとも偉大な神々は、作業は七つになるはずだと言った。というのは、神々が世界に被せた屋根という大気、つまり天空は七つだったからである。七つの天空でもあった最初の神々は、遂行すべき作業は七つあると言った。
七番目の大気には、ノホチャックユム、偉大なる父チャックがいたた。
六番目の大気には、チャッコブ、雨の神がいた。
五番目の大気には、クイロブ・カッショブ、無住地の領主がいた。
四番目の大気には、動物の守護者たちがいた。
三番目の大気には、悪い精霊たちがいた。
二番目の大気には、風の神々がいた。
大地上の一番目の大気には、村と畑の十字架を守護するバラモブがいた。
そして大地の奥底には、キシン、地震と恐怖の神、すなわち悪魔がいた。
さらに最初の神々は言った。色の数は七つで、数えられた数は七である。

雨の神チャック
「先日、色の話をおまえに話した。もしおまえが耳を傾け、話せる時間と方法があれば、また後で七つの作業の話をしよう」こう言い終えると、老アントニオの煙草から最後の輝きが消えた。ふたたび煙と夢を紡ぐため、老アントニオが沈黙する時間になった。手にしたマッチに小さな稲妻が走り、やがて炎が立った。
さて、トウモロコシの男女は、よい世界にするための七つの作業を遂行することに同意した。そして、太陽と月が交互に仮眠する場所を見つめながら、彼らは最初の神々に次のような質問をした。新しい世界を創るための七つの作業を終えるためには、どれぐらい歩きつづけなければならないのか。最初の七つの神々の答えは、七つの作業は七つを七回歩くことというものだった。というのも、そのような形で登場した数は、どれも偶数でなかった。そのため、つねに別の数とペアを組む必要があることを知っていた。
わかりましたと答えながら、トウモロコシの男女は山を見つめた。
母なる大地の乳房を昼と夜に交互に保管している箱である山を見ながら、トウモロコシの男女は神々に質問した。どうして七という数字が歩むのは、七つを七回分であると知ったのか?最初の神々は自分たちも知らなかったと答えた。最初の神々だからといって、すべてを知るわけではない。神々とてまだ多くを学ばねばならなかった。だから、神々はその場を去らず、トウモロコシの男女と留まり、いっしょに新しいことを学ぼうとした。こうして、最初の神々とトウモロコシの男女の関係が成立した。世界を新しくするよい道をいっしょに探すため、彼らはいっしょに考えだした。
彼らはそんなことをしていた。つまり、自らのことを考え、自らを知り、自らについて語り、自らについて学んだ。雨は落下も上昇もせず、昼下がりの真ん中にぶら下がった状態になっていた。そのときまで、彼らはそこにいつづけた。彼らはそこにいつづけた。トウモロコシの男女も、最初の神々も、おたがいに見つめあった。
すると、そこから、多彩色の光と雲でできた架け橋が天空に描き出されはじめた。山から始まった架け橋は、谷へ向かって伸びた。光と雲でできた多彩色の架け橋は、どこへも向かわず、どこからも始まらず、雨と世界の上でじっとしていた。それがはっきりとわかるようになった。この光と雲でできた多彩色の架け橋は七色の帯をもっていた。
そこで、最初の神々とトウモロコシの男女は、もう一度おたがいに見つめ合った。その後、起点も終点もなく、そこに留まっている架け橋をもう一度眺めた。そして、光と雲でできた多彩色の架け橋は、自らが行ったり来たりするのではなく、行ったり来たりするために役立っていることがわかった。考え、学んでいた全員が。とても楽しい気分になった。その架け橋が、われわれを新しい存在に変えるよい世界が行き来するための架け橋となるのはよいことだとわかった。
音楽家はただちに楽器を取り出した。最初の神々と真の男女は、すっと立ち上がり、踊りだした。自らについて考え、知り、語り、学ぶことは、ほんの少ししかなかった。彼らは踊りを終わると、ふたたび集合した。七度を七回分とは、七色の七つの虹が重要な七つの作業を遂行するために歩まねばならない回数である。そのことを彼らは確認した。そして、ひとつの七が終わると、ほかの七が後に続くことも知った。なぜなら、雲でできた色と光の架け橋は、行きも来もせず、起点も終点もなく、始まりも終わりもせず、一方から別の側へと移動しつづけ、通り抜けるだけである。
最初の神々と真の男女が達した合意は、こうして残っている。だから、楽しくものごとを知ったその昼下がり以来、トウモロコシの男女、真の男女は、架け橋を作りながら、一生を過ごすのである。死んでからも架け橋を作る。それはつねに光と雲でできている多彩色の架け橋である。つねに一方から別の側へ行くための架け橋である。新しい世界、われわれを良い存在に変える世界を創る作業をするため、トウモロコシの男女、真の男女は、七度を七回分、道を歩む。彼らは架け橋を作りながら生き、そして死ぬ。
老アントニオは黙った。私はじっと彼を見つめた。われわれがいつまで身を隠しつづけねばならないのか。私の質問とその話はいったいどんな関係があるのか。そのことを彼にたずねようとした。そのときである。一筋の光が彼の視線を照らした。彼は微笑みながら、山の方、すなわち西の方角を指し示した。振り向くと、虹が見えた。それは行きもせず、来もせず、じっと留まり、世界を架け橋で結びつけ、夢に架け橋を架けている。

山に掛かる七色の虹
今日、新年となって七日目、すでに道には六つの虹が出現した。胸の中にある不安、以前からの不眠の残りや息苦しさと戦いながら、光と雲と多彩色の曲線の架け橋は、老アントニオや彼が話した七つの虹の話を六度も思い出させた。七番目の虹が出現することを期待しながら、私は道を歩んできた。そしてコレート[サンクリストバル市の別称]の肌寒さによって、世界を目覚めさせた褐色の人々の「もうたくさんだ!」の叫び声を爆撃や兵士で消そうとしたあの2年前のある夜明け前の記憶が私に蘇った。
3 フー・メン(1996/1/9)
1月の最初の数日間でその年の月がどうなるか。それを読み取る習慣がわれわれメキシコの数多くの先住民共同体にある。この知識は、土地を耕し、種を播き、収穫する時期を知るのに役立つ。もっとも古い時代のマヤの人々はこの知識をショック・キン、すなわち「日々の計算」と呼んでいた。

現代のフー・メン(ユカタン州プンタ・ラグナ)
今のわれわれの時代と同じように、昔もものごとをよく知っている男女がいた。フー・メン、すなわち「ものごとを知っている人」である。フー・メンは夢のなかで習得した多くの知識をもっていた。夢のなかで、神々はこの世界に関する知識をフー・メンに教授している。だからフー・メンは遺失物を探し出し、薬草や祈祷で病気を治し、聖なる石を凝視し、トウモロコシの粒を勘定して、未来を占うことができた。だが、その主要な責務と
関心事は、その指導で見事な収穫が確保できるようにすることだった。
今日、ここにわれわれのフー・メンがいる。ものごとをよく知る男女であり、尊厳ある平和を模索するEZLN顧問団の一翼を構成している。彼や彼女らの手で、このフォーラムが組織され、われわれはおたがいに出会い、七番目の虹の架け橋を架けることができた。
彼や彼女らは、世界、いちばん最初の世界を誕生させた偉大な神々の夢を見ながら、その夢のなかで神々の偉大な言葉や素晴らしい考えを習得したのである。彼や彼女らは、たとえば言葉、理性、無私、尊厳など失われたものを発見できた。彼や彼女らは、この世でもっとも致命的な病気、すなわち忘却と呼ばれる病気を治すことができた。彼や彼女たちは、自分たちの心が語るものを読み取り、現在の世界で心と呼ばれているトウモロコシの粒を勘定しながら、未来を読み取ることができる。
4 種を播く(1996/1/10)
われわれは種を播く準備をすべきである。われわれは雨を降らさねばならない。チャッコブ、すなわち雨の神々は、セノーテ[ユカタン半島のカルスト地帯にある湧泉]から出ると天空に集合し、水の入った聖なるヒョウタンを携え、馬にまたがり、大地のあちこちに雨を降らしていた。それは生命をもたらす雨を万物が享受できるようにするためである。われわれも同じことをすべきである。
雨が降らないなら、われわれは先祖のようにしゃがみ、雨が降る前の蛙のように合唱し、嵐の風が吹きつけるように木の枝を揺さぶらなければならない。誰かひとりが、稲妻の杖と聖なるヒョウタンを携えたクヌ・チャック、つまり雨の主神の役を演じることになる。
われわれは種を播き、自身の根を大地にしっかり張りめぐらすべきである。もはや、石が柔らかく、口笛を吹きながら勝手に動き、畑を開墾するためにあくせく働かなくても、一粒のトウモロコシで家族全員が養うことができた時代ではなくなった。
指導者がチチェン・イツァーで異邦人に打ち負かされた結果、良い時代は終わり、悪い時代が始まった。昔の指導者はトゥルムから東の海底の下まで伸びているトンネルに潜り込んだ。こうして異邦人、ツルが権力を掌握した。今まさに、われわれの土地で理性がもう一度支配権をもつようにするため、われわれは帰還すべきである。言葉の種を播きながら、われわれは帰還するだろう。
われわれの大地はわれわれそのものである。われわれは自分たちがどんな存在であるかよく知っている。われわれは大地そのものである。かつて、種を播く畑、われわれが耕作する畑は四つの精霊に守護されていた。また集落を守護するため、別の四つの精霊がいた。そして、集落の四隅に建っている十字架ごとにひとつの守護精霊がいた。
マセウァレス、太古のわれわれは、七つの方向をもっていた。最初の四つの方向とは、トウモロコシ畑、または集落の四つの隅を指している。五番目は中心である。それぞれの共同体は中心を十字架、また一般的にはセイバの木で示すというのが習わしだった。六番目と七番目は、上と下だった。
それぞれ畑と集落にいる四つの守護精霊のほかに、各個人も守護精霊をもっていた。四隅と一つの中心という五点を示すため、われわれの先祖は十字架を使った。時間とともに、五番目の点が立ち上がり、四隅が五隅となり、五つの頂点がある星になった。その星は人間や作付けされた畑の守護精霊を表わすものだった。
人々の守護者にして心であるボタン・サパタは、言葉の守護者にして心でもある。ボタン・サパタは人間であり、彼自身を表わす五つ頂点をもつ星である。今まで、われわれは語り合い、耳を傾けてきた。だから、人々の守護者にして心であるボタン・サパタの陽気な心はいつも以上に機嫌がよい。

サパティスタの五芒星
5 夜の太陽を探す(1996/4/6)
「人類のため、新自由主義に反対するアメリカ大陸集会」[1996年4月4~7日開催]の会場となったラ・レアリダーにいた老アントニオは気づいていた。この船に乗り込んでいる誰もが、これまでどの船からも排除されていた。だからこそ、彼らはこの船に乗ったのである。老アントニオは副司令官マルコスにこのように説明した。
これらの男女、青年、数名の囚人、大部分が先住民からなる人々は、「もう命令には従いたくない。参加して、船長や船員になりたい」のである。そして、真剣、かつ楽しく人々と出会いながら、この船をより素晴らしい未来に向かって前進させたいのだ。
そのとおりである。だが、次の煙草に火をつけながら、老アントニオは警告した。影がたくさんある。だから、深夜に太陽を探すのは、大変な労力がいるだろう。
「だが、深夜の太陽はそのまわりに言葉や希望を集めている。……だから、彼らに言いたい。どうか立ち去らないでほしい。ここにいれば見ることができる。月が太鼓のようにふくらみ、風は希望をかきたてる。地平線に次々と沈むことに抵抗している怠け者の星の数にくらべれば、コオロギなどは物の数ではない。ホタルは草の房飾りとなって光を放ち、夜のいちばん暗い場所でも光は見える。その様子を彼らは見ることができる」

サパティスタが乗り込んだ船
6 道と道を歩む人のお話(1996/4/7)
追伸-閉会式で言うべきだったが言わなかったことを恥ずかしながら告白する。なぜなら、それはきわめて重大な問題だからである。
皆さんに本当のことを言いたい。われわれは皆さんが立ち去ることを望んでいない。むしろ、ここラ・レアリダーにいつまでも留まってほしい。そうすれば、月の光がほんの睫毛ぐらいしかない夜、いつ、どのように、私の左手奥にあるセイバの木がスカートをたくし上げ、いつものように樹冠をすっと高く上げ、この牧草地の中央でサパテアードを踊りはじめるのか、皆さんも気づくだろう。私は首にパリアカテを粋に結わえ、二人でいっしょに旋回しはじめる。誰もがわれわれは酔っているというだろう。だが酔っているのは、われわれが知り合いにならないのを気にする月だけである。

セイバの木の下でのサパテアード
そして、いちばん暗い夜、いちばん偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々が集まるのを皆さんは目撃するだろう。ここで、最初の神々は、言葉を語り、驚嘆すべきこと、卑猥なことを語り、喜びや苦しみを語る。いちばん偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々は、涙と笑いを知っている。男女に語りかける方法が見つからないと絶望することもある。言うべきことが多く残っているとこぼすこともある。最初の神々は夜を歩みながら、老アントニオを探し、真の言葉を語って聞かせる。
すでに亡くなっているが、老アントニオは煙草を紙に巻くと、端を折り曲げて一服する。いちばん偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々は、煙に包まれた彼に語り聞かせることで歴史を記録する。そうして、トウモロコシでできた真の男女が歴史を知る方法を探せるようにする。いつも言うように、老アントニオがあんなに煙草をすうのは、神々が彼に語った歴史を忘れないようにするためである。彼が出歩くのはいつも夜である。夜になると、彼は私を探しにくる。私と話し煙草に火をつけるマッチを借りるためである。
昨晩も老アントニオは私と出会った。私はマッチをすった。その炎の明かりで、煙草に火をつけようと近づいた彼の顔が照らされた。私は彼の目を見つめ、その瞳に映る私の姿を見た。そこに映っていたのは私だけではない。胸がしめつけられ息苦しくなっていた10年前の4月の晩と同じように、座っている私の隣には老アントニオがいた。いつもどおり煙草を喫いながら、二人は焚火と足元だけを見つめていた。周囲にはそれ以外のものは見えなかった。焚火、煙草、パイプの煙を通して、二人は見つめあった。
そのときだったと私は思う。老アントニオは何かを思い出し、私に話しだした…
道と道を歩むもののお話
以前は、以後というものがなかった。時間は静かにとどまっていた。以前は、いちばん偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々しかいなかった。神々は座ったままで、歩いて行く場所はなかった。というのも、以前には、以後がなかったからである。だから動くこともなかった。以前はこちら側で以後はあちら側とは言えなかった。神々は以前からそんなふうにしていた。だから、世界が以前にずっと留まり、以後に行けなくてもさほど悲しくなかった。だが、やはり以後を発明すべきと考えるようになった。
そこで、七人の神々の一人が、別の神、つまり自分に向かって、いつまでも以前に留まらず、以後に到達する方法を発見すべきだと言った。それがいいと神々は合意した。以後を発見するのはきわめてよい考えだと言った。うれしくて踊ろうとしたが、神々はあまりうまく踊れなかった。というのは、同じ場所、つまり以前に留まりつづけたからである。同じ場所でしか踊れず、神々はたがいにぶつかりだした。踊る場所で、ある神はある方向へ、別の神はほかの方向へ跳ねまわった。
やがて以前は少しばかり幅が広くなった。しかしまだ小さく、七本の細い光線と一つの小さな星をともなって現われたにすぎない。だが、すでに以後を作り出していた。そのことに神々は気がついた。というのは、以前、すべての神々は一ヵ所にかたまっていた。だが、今、つまり以後では、ほんの少し離れていた。神々はおおいに満足して踊りだした。もともと、これらの神々は踊りたかったのである。マリンバを奏で、腰を振るための口実を探していた。だが、前進はできない。いまだに、以前がずいぶん近くにあり、以後がずいぶん小さいことに、神々は気づいた。神々はとても真剣な態度にもどり、状況をくわしく分析した。そして以後を大きくし、以前があまり近くに留まらないようにするにはどうすべきか、意見をまとめるため、以前の場所で再会することに合意した。
神々は準備会議の場に集った。どうして、自分たちがひとつの小さな星まで描いている七つの細かい光線になったのか。それを神々は考えはじめた。そして、いっしょに踊りだすと、たがいにぶつかり、あちこちに跳ねてしまったことを思い出した。それは以前のことである。以後になると、神々はおたがいに少し離れ、踊りだしてもぶつからず、あちこちに跳ねることはなかった。
神々はおおいに満足し、また踊りだした。すると、ふたたび神々はぶつかりだした。また神々は以後に留まり、おたがいに少し離れた。神々は真剣な態度にもどり、以前の場所で再会することにした。こうして、かなり長い期間、神々は、以前と以後を行き来した。真剣な態度と踊りを繰り返した。あいかわらず、以前も以後はとても狭かった。このようなことでもなければ、神々の頭にいい考えは浮かばなかっただろう。神々は、それぞれの神が赴くことになる以後に全員が同伴することに同意した。
神々はさらに踊り、ひと押しした。すると、最初の七本の細い光線のひとつから、別の七本の細い光線が現われた。その後、神々は別の光線にも同じことをした。神々はそれを七回繰り返した。
その後、神々はふたたび以前の場所で再会した。以後がほんの少しばかり以前から離れているのがわかった。以後は、七本の細い光線を七回分もっているが、あいかわらず小さかった。それ自体はいいけれど、まだまだ不十分である。以前と以後はおたがいに十分離れるべきだと神々は判断した。そして、最初の以前の以後である以前の以後で、今一度踊りを繰り返さねばならない。こうに神々は考えた。
その作業はたいへん複雑だが、まだ世界を創りださねばならないと神々は考えた。これらの神々は、もっとも偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々だった。
神々は踊る仕事を担当する神を創ることにした。神々は真剣な態度にもどって、再会し、以前と以後の間隔を開けるため、おたがいに離れることに合意した。そして、真剣な態度と踊りを繰り返すたびに出現する細い光線に名前をつけるべきだと、神々は言った。神々はそれらの光線を「道」、そして踊る仕事を担当する者を「道を歩むもの」と名づけた。
そして、彼らに仕事がどのようなものかを説明した。それは容易ではなかった。以後により遠方まで行くためには、そのたびに以前にもどって、踊ること、そして真剣になること、そしてもう一度再会することを習得しなければならなかった。
その後、踊ったり真剣になったりを何度も繰り返し、神々は疲れていた。もっとも偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々は、眠るためにいなくなった。道を歩む人に道を作るように命令した後、小さな星々が作り出す道を進む星を思い描きながら、神々は眠りについた。道と道を歩む人はこのようにして創られた。それらは、もっとも偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々が厳粛さと喜びのなかで創りだした。
老アントニオは沈黙した。足元を見るのをやめ、私は視線を上げた。すでに夜は明ける準備を始め、老アントニオがいないことに私は気づいた。老アントニオがいたのは以前のことだった。現在はそれ以後である。われわれは出会い、そのたびごとに以前へ帰りながら、真剣かつ楽しく、道をより大きくすべきである…。
7 始まりと終わりのお話(1996/6/30)
昨日、つまり10年前、120ヵ月前、3650日前。昨日……
昨日、雨はあらゆる場所にしみ込んだ。暴風雨のなか、老アントニオの小屋は雨よけとしてまったく役立たないように思われた。5月の硬い大地はとても長く続いた。そのため、トウモロコシは息を引き取りかけていた。6月になり暴風雨が到来すると、トウモロコシは活力を取り戻した。私は小屋の中と外のどちらにいたのか覚えていない。しかし、天井がないのとまったく同じだった。私はずぶ濡れだった。朝方の武器の手入れが無駄になり、武器が使えなくなるのを怖れ、私は武器が雨に濡れないようにした。
部屋のなかで発生した雷、つまり巻き煙草に火をつけるため老アントニオが起こした火花によって、私は思い出した。天井やひさしからの雨漏りはあるが、私は老アントニオの穀物小屋にいた。煙草を一服するため、私はパイプに火をつけようとした。しかし、大粒の雨でパイプの火皿の煙草はぬれ、台無しになった。老アントニオは、彼が思いついた最良の方法で私を慰めてくれた。それはお話をすることである。
始まりと終わりのお話
昨日が古くなり、世界の片隅に落ち着くまで、それなりの時間が必要だった。偉大なる神々、世界を誕生させた神々、最初の神々はずっと眠りこけていた。全員が踊り、歩き、質問し、疲れきっていた。最初の神々は眠りこけていた。真の男女と話し合い、歩きつづけるべきである。そのことに神々全員が合意した。歩きつづけることで世界は生きていた。偉大なる神々、世界を誕生させた神々、最初の神々はこう言った。
「いつまで歩きつづけるの?」とトウモロコシの男女はたずねた。
「いったい、いつから歩きだしたの?」と真の男女は自問した。彼らはある質問には別の質問で答えることを最初の神々から習っていた。
しかし、最初の神々が目を覚ましてしまった。偉大なる神々、世界を誕生させた神々は、先ほどの質問を聞くと、寝ていられなかった。神々は目を覚ますと、マリンバを演奏し、歌を歌った。質問を重ね合わせ、「われわれはいつまで歩きつづけるの?いつから歩きだしたの?」という歌を作り、踊ったり歌ったりした。もう神々は、十分に踊り、歌っただろうから、そろそろ自分たちの質問に回答して欲しい。こんなふうに真の男女が遠慮せずに神々に言わなかったら、神々はずっと踊り、歌いつづけただろう。

「5千年以上もトウモロコシ畑を大切にしてきた」
やおら、最初の神々は真剣な表情で言った。
「われわれがトウモロコシから創った男女は質問があると言っている。われわれからみると、この男女はあまり物分かりがよくない。回答が自分の後や前にあることに気づかず、よそばかり探している。この男女はトウモロコシの若穂のようにあまり物分かりがよくない」
こう言うと、最初の神々はまた踊りや歌を始めた。真の男女はまた怒り狂った。馬鹿にされるのはいいけど、自分たちの前と後に回答があるというのはどういうことだ。最初の神々は、背中と前方の視線に回答があると言った。トウモロコシの男女は見つめ合った。しかし何も理解していないことを自覚し、全員じっと黙っていた。
いちばん偉大な神々は彼らに言った。トウモロコシの男女たちは背中から出発した。トウモロコシが大地から芽生える時と同じように、横になって生まれた。背中から歩きはじめた。歩んでいる時も、静かに立ち止まっている時も、彼らの背中はいつも後にある。だから、背中こそが始まりである。彼らの歩みのなかでは昨日である」
真の男女はよく理解できなかった。しかし、始まりはもう始まり、昨日は過ぎ去ったことなので、そのことは気にならなかった。そこでたずねた。
「われわれはいつまで歩きつづけるのですか?」
「それなら簡単にわかる」と世界を誕生させた神々は言った。
「自分の視線で背中を見られるまでだ。丸く輪を描くように歩けば、それでいい。歩みを追いかけて一周し、自分に追つけばいい。十分に歩き、遠くからでも、自分の背中が見えるようになれば、歩かなくてもよい。ちっちゃな兄弟姉妹よ」
こう言って、最初の神々は眠りについた。
真の男女は満足した。背中を見るには円を描くように歩けばいい。それがわかったからである。彼らは背中が見えるように歩きながら、かなりの時間、丸く円を描くように歩いた。やがてちょっと立ち止まり、なぜ歩くことが終わらないのかを考えた。そして言った。
「終わりに到達するため、始めに到達することは、ずいぶん骨の折れる仕事だ。歩く仕事は終わらない。われわれの歩みを終えるため、始まりに到達するのはいつかと考える。そんなことをしても、苦悩は増えるだけだ」
男と女たちの一部はやる気をなくした。終わりに到達するための始まりに向かう歩みが終わらない。それに腹を立て、その場に座り込んで動かなくなった。しかし、別の男女は熱心に歩きつづけた。終わりに到達するため、始めに到達するのはいつかと考えることをやめた。自分たちが歩む道のことを考えるようにした。その歩みは円くなっていた。そこで、彼らは一周ごとにうまくなろうとした。実際、一周ごとに歩みがうまくなるのがわかり、彼らは満足した。彼らは歩くことにおおいに満足した。その後も、かなりの期間、彼らは歩きつづけた。そして歩きながら、言った。
「われわれがなっているこの道はたいへん楽しい。道をよりよくするため、われわれは歩いている。われわれはほかの人たちが行き来する道になっている。みんなには、それぞれの歩む道の始まりと終わりがある。しかし、道であるわれわれには、始めも終わりもない。すべてを皆のために、われわれは何もいらない。われわれは道である。だから、われわれは歩きつづけねばならない」
そのことを忘れないため、大地に円が描かれ、世界中の誰もが円のように丸く歩くようになった。真の男女は今も円のように丸くに歩く。道をよくする戦い、自分自身をよりよき者にする戦いをやめ、終わらせることはない。世界はもとから丸かった。しかし、それは今も丸くなっている。そのことを人間は信じはじめた。
世界というこの丸い球は、真の男女の戦いである。道そのものである。彼らはいつも歩きつづけ、自分たちが歩く歩みのなかで、道がよりよいものになることを願いつづける。歩きつづける彼らの歩みには、始めも終わりもない。真の男女は疲れない。彼らが望むのはいつも自分自身に到達することである。始まりを見出すため、自分の後を見つめ、自分の道の終わりに到達することである。彼らがそこに到達することはない。彼らもそれを知っている。だが、それはどうでもいい。彼らにとって唯一重要なことは、自分がいい道であること、よりよい道になろうと努める道となることである。…

歩む道には始まりも終りもない
老アントニオは静かになった。だが、雨は違った。この雨はいつやむのか。私は彼にたずねようとした。しかし、その場の雰囲気は、始めと終わりに関して質問できるものでなかった。私は老アントニオに別れを告げた。
新しい電池を入れたが、私の懐中電灯では何も見分けられない暗闇だった。しかし夜の雨が降りしきるなか、私は退去した。ぬかるみを歩くブーツがたてる音に邪魔され、私は老アントニオの別れの言葉を聞き取れなかった。
「自分の道がいつ終わるのかと質問することに疲れてはならない。昨日と明日が結びつく所で、おまえの道は終わるだろう」
歩きだそうと決意することは、私にとってかなりしんどかった。目の前のぬかるみで私が滑りこけるのはわかっていた。それがわかっていながら、私はその転倒を乗り越えて歩かねばならなかった。転倒は何度も続くだろう。歩くことはつまずくこと、転倒することである。それを私に教えたのは、老アントニオではない。山がそのことを教えた。試練はけっして簡単でない。そのことを私に確信させた。
今、皆さん[1996年6月30日からの国家改革フォーラム参加者]にお話したのは、昨日のことである。別の昨日、すなわち老アントニオの昨日ではない、もっと最近の昨日のように雨が降っていた。昨日……
8 道を創るお話(1996/7/6)
しかし、偉大なる神々は、主人たる騎士の偉業を語るという重い包みを担って歩むという無限の苦行から、どこかのデカ鼻の従者を解放することになる。
こうして偉大なる神々のことを話していると、最初の神々、世界を誕生させた神々にともなわれ、老アントニオが登場した。
老アントニオは、いつものように煙草を吸いながら、歩いたり、話したりしながら、あの晩、10年前のあの晩も、私のとなりに座っていた。彼、すなわち老アントニオだけでなく、褐色の血をたたえる尊厳に満ちた心臓をもつすべての男女が、私の脇に座っている。私の脇に座り、戦いのことをわれわれに説明しようと、彼らは私に言葉や声を投げ掛ける。われわれに説明するため、彼らは語り、私に話しかける。われわれに押しつけたり、われわれに強要したり、われわれを飲み込んでしまうためではない。雨が降り、寒々とした薄暗さが壁や天井となって立ちこめていた10年前のあの晩の戦い、彼らの生きた時代のことをわれわれに語るためである。
あの晩、老アントニオは、マチェーテを手に、泥土のなかを私といっしょに歩いていた。老アントニオは私といっしょに歩いていたと言ったかな?とすれば、嘘を言ったことになる。彼は私といっしょに歩いていなかった。私は彼の後を歩いていた。あの夜、最初は、そんなふうに歩いていなかった。まず、われわれは道に迷ってしまった。鹿を追いかけようと、老アントニオが私を誘ったのである。われわれは鹿を追いかけたが、追いつけなかった。気づくと雨が降りだし、夕闇が迫る密林の真ん中へわれわれは踏み込んでいた。
「迷ったかな」と虚しくつぶやいた。
「そうだな」と老アントニオはうなずいた。
だがさほど心配している様子はなかった。彼は一方の手で煙草に火をつけながら、一方の手を火にかざし、小さな風よけを作っていた。
「引き返す道を見つけないと」とつぶやく自分に気づき、付け加えた。「磁石があるので」と言った。まるで「ヒッチハイクをしたいなら、自動車があるよ」とでも言うようなものだった。 イニシアティブを私に譲り、私の後をついて行く。その気もちを示すように、もう一度、老アントニオは「そうだな」とつぶやいた。

密林では役に立たない「地上航法」
山中での2年間の経験をもつゲリラ戦士としての知識を披露する用意ができていると、私は挑戦を受けて立つかのように宣言した。一本の木の下に雨宿りをしながら、私は地図と高度計、そして磁石を取り出した。実際には老アントニオの前でこれ見よがしに見せびらかすためだった。私は、かん高い声で、海抜、地図上の水準点、気圧、何度何分、照準点など、われわれ軍人が「地上航法」と呼んでいる諸データについて説明した。老アントニオは黙ったまま、私の脇でじっとしていた。彼が煙草を吸いつづけていたので、私の言うことに耳を傾けていると思っていた。専門的で科学的なテクニックをしばらく誇示した後、私は立ち上がった。
そして、磁石をもったまま、夜の闇の一方向を指した。自信に満ちた声で「こっちの方向だ!」と言って、その方向に向かって歩きはじめた。
「そうだな」と老アントニオが相槌を打つと思っていた。だが、彼は何も言わなかった。自分の猟銃、リュック、マチェーテをまとめ、私の後を歩きだした。
かなりの時間歩いたが、われわれが知っている地点に辿りつけなかった。私は自慢の近代的テクニックが役立たなかったことが恥ずかしくなった。無言で私の後をついてきている老アントニオの方を振り返りたくなかった。やがて、われわれはスベスベした壁となってわれわれの進路をさえぎるように屹立する岩だらけの丘に到着した。
「ここから、どっちらに行けばいいのだろう?」
こう大声で言ったとき、私に残っていた誇りの最後の一片は木っ端みじんとなった。
そのとき、やっと老アントニオは口を開いた。最初にちょっと咳払いをし、煙草の破片を唾とともに吐き出した。その後、私は自分の後方で次のような彼の言葉を聞いた。
「次に進む方向がわからないなら、来た道を振り返って見ればいいのだ」
彼の言葉を文字どおりに解釈し、私は後を振り返った。といっても、それはわれわれがやって来た方向を確認するためではない。恥ずかしさ、懇願、苦悩の混じり合った目で、老アントニオを見るためだった。
老アントニオは一言も言わなかった。私をじっと見つめ、私の窮状を理解してくれた。マチェーテを取り出すと、薮に道を切り開きながら、別の方向に進みだした。
「こっちですか?」と私は虚ろな声でたずねた。
「そうだ」と答えながら、老アントニオは夜の暗闇のなか蔓や湿った空気を切り開いた。数分後、われわれは踏み分け道に戻った。目もくらむような稲光によって、老アントニオの住んでいる村の輪郭がくっきりと浮かび上がった。私はずぶぬれとなり、疲労困憊となって、老アントニオの小屋へ辿りついた。
ドニャ・フアニータはコーヒーを準備していた。われわれはカマドの火に身体を近づけた。老アントニオはぬれた服を脱ぎ、乾燥させるためにカマドの光の脇に置いた。室内の片隅にある地面に座ると、私に夕食を出してくれた。最初、私は固辞した。火から離れたくなかったからである。同時に、地図、磁石、高度計を無意味に誇示した恥ずかしさが残っていたからである。私はじっと座っていたかった。二人は煙草を吸いだした。私は沈黙を破り、どのように引き返す道を見つけたのか、彼に質問した。
「帰り道を見つけたのはわしじゃあない」と老アントニオは答えた。
「そこに道があったのではない。道を見つけたのではない。道を作ったのだ。それは自然にできたのだ。それを歩いただけだ。おまえは、道はどこかにあり、おまえの器材を駆使すれば、どこに道があるかを明らかにできると考えていた。だが、そうでなかった。わしがどこに道があるかを知っているはずだから、わしについて行こうと、おまえは考えた。だが、それも違っていた。どこに道があるかなんて、わしは知らなかった。わかっていたのは、われわれは共同して道を作らねばならないことだった。だから、われわれは共同して道を作った。その結果、われわれが目指していた場所に到着できた。われわれが道を作ったのだ。そこに道があったからではない」
「しかし、どうして次に進む方向がわからないなら、後を振り返って見ればいいと、言ったのですか?帰り道を発見するためではなかったのですか?」と私はたずねた。
「そうじゃない」と老アントニオは答えた。
「道を発見するためではない。それより前に、おまえがどこにいて、どのようなことが起き、おまえが何を望んでいたかを知るためだ」
「どうして?」と私は恥も外聞も捨ててたずねた。
「そうだな。後を見るために振り返りながら、自分がどこにいたのか、気がついたはずだ。そうすれば、おまえがうまく作れなかった道を見ることができる。後を振り返れば、おまえも気づくはずだ。おまえが望んでいたのは帰ることだった。だが、すべきことは帰り道を発見することだった。わしが返事したのはそのことだ。それが問題なのだ。おまえは存在しない道を探そうとした。自分で道を作らねばならなかったのだ」
老アントニオは満足そうに微笑んだ。
「どうしてわれわれが道を作ったと言うのですか。道を作ったのはあなたです。私はあなたの後を歩いただけです」と、少しバツが悪そうに言った。
「そうじゃない」と老アントニオは微笑みながら言った。
「わし一人で道を作ったのではない。おまえも一定の区間は道を歩いた。だから、おまえも道を作ったことになる」
「でも、その道は何の役にも立たなかったのでは」と口を挟んだ。
「そうじゃない。その道も役に立った。その道が役に立たないなら、われわれは二度とその道を歩かないし、作りもしない。望んでいない場所にわれわれを連れていったのだから。望んでいる場所にわれわれを連れていく別の道をわれわれは作れるのだから」
こう言った老アントニオをしばらく見ていたが、思い切ってたずねた。
「自分が作っている道を進むとここに着くと、わかっていなかったのですか?」
「そうだ。歩いていたら着いたのだ。働き、戦いながら。働くことは戦うことだ。こう言ったのは、もっとも偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々だ」
こう言うと、老アントニオは立ち上がった。そして弁証法をマチェーテと同じぐらいきわめて上手に操りながら付け加えた。
「神々はほかにもいろんなことを言った。働けるように戦わねばならないことがある。また、戦えるように働かねばならないこともある」
このように私が老アントニオの後を歩いたのは、10年前のあの夜のことである。老アントニオの後を歩いたと言ったかな?とすれば、私は嘘をついたことになる。私は彼の後を歩いたのではない。彼といっしょに歩いたのである。10年前のあの夜である。
今夜はそれから10年後の夜である。私を通じて、この大地の最良の存在、最初に戦い働いた者、過去の最良の時間、先住民の褐色の血が声と言葉を発する。彼らの苦悩と戦いの上に、メキシコという国が建てられたのである。
9 山に生きる死者たち(1996/7/26)

1996年7月の国際集会で発言するアナ・マリア
皆さん、自己紹介させてください。われわれはEZLNである。この10年間、われわれは戦争の準備をしながらこの山中で生きてきた。この山中でわれわれは軍隊を創ってきた。
下の世界、都会や大農園では、われわれは存在しなかった。われわれの生命の値段は機械や動物にも劣っていた。われわれは道端の石ころや植物程度の価値しかなかった。われわれは言葉をもっていなかった。顔も名前もなかった。明日もなかった。われわれは存在していなかったのである。
今日、世界のいたるところで新自由主義という名前で登場している権力からみれば、われわれはまったく勘定に入っていなかった。われわれは生産したり、物を買ったり売ったりしなかった。巨大資本の勘定書では、われわれはまったく無価値の存在だった。
そこでわれわれは山に入った。われわれ自身がよき存在になるためである。そして石や植物のように忘れ去られた存在であるわれわれの苦しみを和らげるものを見いだせるかどうかを確かめるためであった。
ここメキシコ南東部の山中にはわれわれの死者が生きている。山中で生きているわれわれの死者は多くのことを知っていた。自らの死についてわれわれに語り、われわれはそれに耳を傾けた。語る小箱は昨日からきて明日に向かっている別のお話をわれわれに話してくれた。山はわれわれに話しかけた。われわれふつうのありきたりの人間であるマセウァルに話しかけた。われわれは素朴な人間である。権力者が言うとおりである。
過ぎゆくあらゆる昼と夜、権力者はわれわれにシュトルを踊らせ、野蛮な征服戦争を繰り返そうとしている。カツ・ツル、偽りの人間はわれわれの大地を支配し、巨大な戦争機械をもち、われわれに苦悩と死をばらまいている。その戦争機械は、半分がピューマ、残る半分が馬という体のボーブに似ている。政府という偽りの存在は、われわれにアルーシュ、われわれの人々を騙し忘却を送りつける大嘘つきを派遣している。
それゆえ、われわれは兵士になった。そして、兵士であり続けている。われわれはわれわれのこれ以上の死や嘘を望んではいない。われわれは忘れ去られたくない。
山はわれわれに話しかけた。声をもつためには武器を手にすること、顔をもつためには顔を隠すこと、名前を呼ばれるためにはわれわれの名前を忘れること、明日を手にするために、われわれの過去を隠すことを語った。
山中には、死者たち、われわれの死者たちが生きている。これらの死者とともに、ボタンとイカル、光と闇、湿気と乾燥、大地と風、雨と火が生きている。山はハラッチ・ウイニック、真の人間、高位の指揮者が暮らす家である。われわれは、われわれであること、真の男女であることをこの山の中で学び、しっかり記憶している。
声で武装し、顔をもって再生し、新たに名前をもったわれわれの昨日は、バラム・ナーのチャン・サンタクルスにある四つの点の中央にとどまり、ひとつの星を誕生させた。その星は人間をかたどり、世界を創る部分が五つからできていることを思い起させる。
雨を降らしながらチャーコブが騎乗していた時間、われわれは仲間と話し合った。そして、種を播く時期を教える暴風雨を準備するため、われわれは山から下りることにした。白い年とともに、われわれは戦争を開始し、この道を歩みはじめた。その道はわれわれをあなた方の心に導く。その道は、今日、あなた方をわれわれの心に導いてきた。
それがわれわれである。EZLNである。耳を傾けてもらうため、武装した声。自己表明するため、隠した顔。名前を呼ばれるため、黙した名前。耳を傾けてもらい、見てもらい、名前を呼ばれるため、人や世界に呼びかける赤い星である。昨日に収穫される明日である。
われわれの黒い顔の背後、われわれの武装した声の背後、われわれの名前のない名前の背後、あなた方が見ているわれわれの背後には、あなた方でもあるわれわれがいる。どの民族にも存在し、あらゆる色の、あらゆる言語を話し、あらゆる場所に住んでいる単純であたりまえの男と女であるわれわれがいる。
同じように忘れ去られた男女たち。同じように排除された者たち。同じように許されざる者たち。同じように迫害される者たち。われわれはあなた方と同じ存在である。
われわれの背後には、あなた方であるわれわれがいる。
…兄弟姉妹の皆さん。
山中では、語る小箱がわれわれに話しかけた。われわれの苦悩や反逆を記憶する昔のお話をわれわれに語った。われわれが糧として生きている夢は尽きないだろう。われわれは旗を降ろしはしない。われわれの死はつねに生きつづけるだろう。
われわれに話しかける山々はこのように言っている。チャン・サンタクルスで輝いている星はこのように語っている。クルソブ、反逆者はけっして敗北しない。人の住んでいるこの星にいるすべての人々とともに自らの道を歩みつづける。このようにわれわれに言っている。赤い人間、チャチャク・マック、そして世界が自由になるのを手助けする赤い星がやってくるとも言っている。山である星がわれわれに言っている。
五つの人民で構成される人民、あらゆる人民の星である人民、人であると同時に世界のあらゆる人民である人民が、人を創り出すいくつもの世界の戦いを支援するために到来するだろう。真の男女が苦しまずに生き、そして石が軟らかくなるように。
あなた方全員がチャチャック・マックである。全世界、すべての人民、あらゆる人々のなかの五つの部分で創られている人を助けるために到来する人民である。あなた方全員がわれわれのなかに鏡をもっている赤い星である。われわれであるあなた方がわれわれとともに歩むことができるなら、われわれはよい道を歩むことができるだろう。
兄弟姉妹の皆さん。
われわれ人民のなかでもっとも年配の物知りたちは、星の形をした十字架を、生命をもたらす水が生まれる場所に据えた。このように生命の開始は山のなかにある星によって記されている。語る星、われわれのチャン・サンタクルスの声を運ぶ小川は、こうして誕生し、山から流れ下りるのである。
山の声は語った。真の男女は自由に生きることができるだろうと言いつづけた。彼らが五つの頂点のある星が約束するすべてのものになるなら。五大陸の人民が星のなかでひとつになるなら。世界である人間の五つの部分がおたがい出会い、ほかのものに出会えるなら。五つであるすべてが自分の場所と他者の場所を発見できるなら。

第1回新自由主義に反対する大陸間集会のポスター
10 遠くと近くを見つめること(1996/7/31)
雨が横たわるように降っている。つまり、腰を折るような風が吹くと、雨は横向きに吹きつけるということである。その夜、老アントニオと私は小屋から出発した。老アントニオは畑で芽を出したトウモロコシを盗もうとするアナグマを仕留めるつもりだった。われわれはアナグマを待っていた。しかし、アナグマではなく、雨と風がやってきたので、われわれはほとんど何もない穀物庫に避難することになった。

テホン(アナグマ)はトウモロコシや家禽をねらう
老アントニオは奥の隅に座り、私は入口の敷居に座り込んだ。二人とも煙草を一服した。老アントニオはひと眠りしたが、私といえば、いつも以上に気まぐれに舞っている風の方向によって、雨があちこちから吹きつける様子を眺めていた。やがて、気ままな風の舞は終わり、どこか別の場所に行った。雨が止むと、すぐさまコオロギと蛙の耳をつんざく合唱合戦だけが残った。音を立てて老アントニオを起こさないように、私は穀物庫から出た。欲望による身体の踊りが終わったときように、大気は湿って熱かった。
「あれを見ろ」と老アントニオが言った。彼の手は西の空に広がる雲の幕間にのぞいている星を指し示した。私はその星を見つめた。よくわからないが、何かが胸に引っ掛かっているような気がした。それは悲しく苦渋に満ちた孤独感のようなものだった。
だが、老アントニオが質問する機先を制し、私は微笑みながら言った。
「『指で太陽を指差すと、間抜けな者は指を見る』という諺を思い出しました」

指月のたとえ『月を指せば指を認む』
老アントニオは、心の底から笑いながら、「太陽を見る奴がいるなら、それ以上に間抜けだよ。目が見えなくなる」と私に言った。
諺の言わんとすることを説明しようと思った私は、老アントニオの論理に打ちのめされ、口ごもった。老アントニオは笑いつづけた。彼が笑っていたのは、私自身か、私の説明か、指が指している太陽を見ようとした間抜けな奴のことか。私にはわからない。
老アントニオは座ると、単発式猟銃をかたわらにおいた。そして、古びた穀物庫から取り出したトウモロコシの葉で煙草を巻いた。黙って耳を傾けるときと、私は悟った。私も横に腰を下ろし、パイプに火をつけた。老アントニオは紙巻き煙草を二・三服すると、言葉の雨を降らせはじめた。その言葉の落下に付き添うのは煙だけだった。
「さっきしようとしたのはおまえに星を指差すことではない。わしの手で天上にあるあの星に触るには、どれぐらい歩いて行かなければならないのか。それを考えていた。わしの手と星のあいだの距離を計算してくれと、言おうとしていた。だが、おまえは、出し抜けに指と太陽の話をもち出した。おまえにわしの手や星を指したのではない。おまえの諺に登場する間抜けな奴は、賢明な代替案をもち合わせていないようだ。太陽を見た結果、目が見えなくならなかったとしても、上ばかり見ていると、やたらに転んでしまう。一方、指ばかり見ていると、自分の進む道がわからなくなる。つまり、立ち止まったままで、指の後しか歩けなくなる。要するに、太陽を見る奴も指を見る奴も、どちらも間抜けだ。
歩きながら生きることは、偉大な真実を自分の手にすることではない。計測してみると、そんなものはずいぶん小さなことがわかる。昼に到達するため、われわれが歩きだそうとする夜が到来しようとしている。近くだけを見ていると、われわれはこの辺りをウロウロするだけだ。遠方だけを見ていると、われわれはつまずき、道に迷ってしまう」
老アントニオはいったん喋るのを止めた。そこで私はたずねた。
「どうすれば、遠くと近くを同時に見ることができますか?」
紙巻き煙草をくわえると、老アントニオは話しはじめた。
「話し合いながら、耳を傾けるのだ。近くにいる者と話し合い、耳を傾けるのだ。遠くにいる者と話し合い、耳を傾けるのだ」
ふたたび、老アントニオは星に手を延ばした。手を見ながら老アントニオは言った。
「夢を見るとき、はるか彼方の天上にある星を見なければならない。しかし、戦うときには、星を指差している手を見つめねばならない。それが生きることである。継続して視線を上げ下げするのだ」
われわれは老アントニオの村に帰った。われわれが別れの挨拶をする頃、深夜も夜明けの衣装をまといはじめていた。牧草地の門まで老アントニオは私に付き添ってくれた。鉄条網の外側に出ると、私は老アントニオを振り返り、次のように言った。
「アントニオ爺さん。星に手を伸ばしたとき、私はあなたの手も星も見ていなかった」
老アントニオは口をはさんだ。
「そうか。よろしい。おまえは二つのあいだの空間を見ていたのだな」
「いいえ。二つのあいだの空間も見ていません」と彼に言った。
「じゃあ、何を見ていたのだ?」
私は微笑んだ。そして立ち去りながら、老アントニオにむかって叫んだ。
「あなたの手と星のあいだにいるアナグマを見ていたのです」
老アントニオは地面を見つめ、何か私に投げつけるものがないかと探していた。それを見つけられなかったのか、それとも彼の手が私に届くには、遠くすぎる所まで私が行ってしまったのか。それは私にはわからない。いずれにせよ、彼の単発式猟銃を担がなくてもよかったのは、私にとっては幸運だった。
私はゆっくりと歩きながら立ち去り、近くと遠くを見ようとした。上でも下でも、光は昼と夜とを出会わせようとしていた。雨は7月と8月を結びつけていた。泥や転ぶこともそれほどは苦痛でなくなっていた。
10年後、われわれは、遠くの存在でしかないと思っていた人たち、つまり…あなたたちと話し合い、耳を傾けはじめるだろう。
11 騒音と沈黙のお話(1997/2/14)
追伸:そう言われるに値すると、どこで言われている?
雨が降りしきっていた。愛の贈り物である心地よい疲労で、ラ・マールはまどろんでいた。カセットから、メルセデス・ソーサの「私に多くのものくれた人生よ、ありがとう」という歌詞が紡ぎ出されていた。その夜明け前、哨戒中の飛行機がメキシコ南東部の山々の上空で、死の唸り声をたてていた。私はパブロ・ネルーダと名乗ったネフタリ・レジェスを思い出していた。
「まさにその瞬間、時は時刻どおりにやってくる。人民は人気のない街路を新鮮で堅牢な規模で充たす。ここに、その時に備えた私の優しさがある。その優しさをあなたたちは知っている。私にはほかの旗がない[El Pueblo Victoriosoの歌詞]」

1987年発売の『人生よありがとう』のカセット
戦争の時計は「1997年2月14日」を指している。10年前の1987年、そのときも同じように大雨だった。ラ・マール、ラジカセ、警戒飛行機もなかった。しかし、われわれゲリラのキャンプ宿営地のまわりには、夜明けが忍びこんでいた。老アントニオは残って話し込んだ。午後になり、彼はトスターダの袋をもってきた。キャンプの調理場にはわれわれ二人しかいなかった。カマドの残り火から昇る煙と競い合うかのように、パイプとトウモロコシの葉で巻いた煙草から紫煙が立ち上がった。
だが、大声で叫ばないかぎり、会話はできなかった。静寂が支配しているようだが、激しい雨音は夜の隅々まで侵入していた。雨音以外には何もなかった。激しい雨音は、山を覆う木々の樹冠だけでなく、地面からも聞こえた。上方の木々から落ちてくる雨音、地面を叩きつける雨音によって、下からの雨音は倍になっていた。その中間でも別の雨音がしていた。密林に降り注ぐ2月の雨が、ビニールテントに当っている雨音だった。上で下も、そして中間でも、激しい雨音がした。言葉の入り込む余地はどこにもなかった。
だから、老アントニオの声がはっきり聞こえたとき、私は驚いた。彼はトウモロコシの葉で巻いた何本目かの煙草を唇にはさみ、次のお話を始めた。
騒音と沈黙のお話
時間がまだ数えられていなかった時代にも、ひとつの時間があった。その時代、もっとも偉大な神々、世界を誕生させた神々は、最初の神々がもともと歩んでいたように、つまり踊りながら、道を歩んでいた。その時代、多くの騒音があった。あらゆる方向から、声や叫び声が聞こえた。騒音が多すぎ、何も理解できなかった。その当時の騒音は、何かを理解するためのものではなく、何も理解できなくするための騒音だった。当初、最初の神々は、騒音は音楽と踊りのためのものと思っていた。すぐさま自分の相手を探すと、こんな風に踊りはじめた。
こう言いながら、老アントニオは立ち上がり、最初に片脚に、次に別の脚に重心を移すという風にバランスをとりながら踊りのステップを示した。

騒音に合わせては、楽しく踊れない
しかし、騒音は音楽でも、踊りでもない。それが判明した。騒音は騒音でしかない。騒音では踊れず、楽しい気もちになれなかった。聞こえてくる騒音は、何を意味するのか。それを知ろうと、もっとも偉大な神々は注意深く耳をすました。だが、何も理解できなかった。結局、騒音は騒音でしかなかった。騒音では踊れなかった。だから、最初の神々、世界を誕生させた神々は歩けなくなった。最初の神々は、踊りながら歩いていたからである。彼らは立ち止まった。歩けなくなり、彼らはとても悲しくなった。それほど、これらの神々、もっとも偉大な最初の神々は、歩くのが大好きだった。
やがて、一部の神々は歩こうとした。この騒音にあわせて踊ろうとした。しかし、それは無理だった。歩き方を忘れ、道に迷い、おたがいに衝突し、転倒し、木や石につまずき、これらの神々はひどく傷ついた。
老アントニオはいったん話を中断すると、雨と騒音によって消えた煙草に火をつけた。火がつき、紫煙が立ち上がった。その後から言葉が出てきた。
そこで、今一度、針路を定めるため、神々は沈黙を探すことにした。しかし、神々は沈黙をどこにも発見することはできなかった。沈黙が立ち去った場所には、当然ながら、多くの騒音だけが残っていた。もっとも偉大な神々は絶望的になってしまった。道を発見するための沈黙を発見できなかったからである。
そこで、神々は集会を開くことに同意した。集会では、神々はきわめて激しい議論を展開した。そこで生じた騒音はとてつもなく大きかった。神々は最終的に合意に到達した。それは各自が歩む道を発見するため、沈黙を探そうというものだった。神々は自分たちが行った合意に満足した。しかし、その満足度はそれほどでもなかった。まだ多くの騒音があったからである。
そこで、それぞれ自分を発見するため、神々は沈黙を探した。神々は四周を探したが、何もなかった。上にはなかった。下にもなかった。沈黙を探せる場所がなくなった。そこで、神々は自分の内部を探すことにした。神々は自分の内側を見つめはじめた。こうして神々は沈黙を探しだし、ついに沈黙を発見した。もっとも偉大な神々、世界を誕生させた神々、最初の神々は、自分の内部でおたがい出会い、そこで自分たちの道を再発見した。
老アントニオは黙った。雨音はなくなった。しばらく静寂は続いた。だが、すぐにコオロギが鳴きはじめ、10年前の2月14日の夜の最後の静寂は打ち破られた。山の夜は明けた。老アントニオは「もう、行くよ」と別れの挨拶をした。
一人残された私は、夜明けとともにメキシコ南東部の山中に置き去りにされた静寂の最後の断片を吸い込んだ。

副司令マルコスとラ・マールのモデルとされるグロリア・ムニョス
12 理性と力の話(1997/6/20)
追伸-愛が巣を作る夢について話そう
私の傍らにラ・マールが横たわっている。われわれは、ずっと前から、苦悩、躊躇、少なからぬ夢を共有してきた。今は密林の暑い夜を私とともに寝ている。夢のなかで、私は彼女の騒ぎ立つ小麦の穂のような髪の毛を見ていた。ほんのりと暖かく瑞々しいラ・マールは、いつものように私のかたわらにあった。その姿を見て、私は今一度驚いた。息苦しくなって、私はベッドから抜け出した。何年も前と同じように、老アントニオを現在に連れ出すため、私はペンをとった。

横たわるラ・マール
川の下流の探索に同行してほしいと、私は老アントニオに頼んだ。われわれが食料として携帯したのは、ほんの小量のポソーレだった。何時間も、気ままな流れを下だるうちに、空腹と暑さはしだいに募ってきた。午後はずっとイノシシの群れの後を辿ることになった。夕方、われわれはやっとイノシシの群れに追いついた。
しかし、一匹の巨大な雄イノシシ(野生の豚)が群れから離れ、われわれに襲いかかった。私といえば、ありったけの軍事知識を引き合いに出し、自分の銃を放り出し、いちばん近くの木によじ登った。老アントニオはイノシシの攻撃にまったく無防備であった。しかし、彼は逃げることなく、蔓が繁茂している薮に身を隠した。巨大なイノシシは、正面から全力で彼を攻撃した。しかし、蔓や棘に絡めとられた。イノシシが薮から脱出する前に、老アントニオは手もちの古い単発式猟銃を取り出すと、イノシシの頭を撃った。それで、その日の夕食の問題は解決した。
私が自分の近代的な自動小銃(口径5.56㎜のM16銃、発射速度セレクター付き、実効射程距離460メートル、照準スコープに脚付き、90発の「弾倉」カートリッジ装備)の手入れを終了した頃には、もう夜明け近くなっていた。実際に起きたことを全部省き、私は野戦日記に次のことだけメモした。
「イノシシと遭遇。アントニオが一匹仕留める。海抜350メートル。雨は降らず」
われわれは肉が煮えるのを待った。割当て肉をキャンプ地で準備中のお祭りに提供すると、老アントニオに伝えた。火をかきたてながら、彼はたずねた。「お祭りだって?」
「そう。何月かは無関係です。いつも何か祝うことがあります」と私は返答した。
その後、自説は歴史的な暦とサパティスタの祝賀行事に関する最高の考察であることを強調し話をつづけた。老アントニオは黙って聞いていた。しかし、彼に興味がないことがわかり、私は横になって寝ることにした。
私は、老アントニオが私のノートを取り出し、何か書いているのを夢のなかで見た。翌朝の朝食後、われわれは肉を分配し、それぞれ帰途についた。自分のキャンプに戻ると、私は司令官に報告した。実際に起きたことを知ってもらうため、野帳を見せた。司令官はノートのある頁を私に見せながら言った。「これはおまえの字じゃないな」
前日の私のメモの後に、老アントニオは大きな文字で書いていた。
「理性と力の両方を手にできないなら、理性を選ぶのだ。力は敵にくれてやれ。力は数多くの戦闘で勝利を収めるだろう。しかし、闘争全体で勝利するのは理性である。権力者は力から理性を取り出せないが、われわれは理性から力を獲得できる」
最下段には、とても小さな文字が書いてあった。
「お祭りを楽しんでくれ」
理由は言うまでもない。私の空腹はどこかに消えてしまっていた。いつもどおり、お祭りはとても陽気だった。幸いなことに、「赤い髪飾りの娘」[Los Pedrenalesのクンビア・ノルテーニャ]は、サパティスタのヒットパレードにはまだのりそうもなかった。

『赤い髪飾りの娘』のジャケット
13 沈黙の音(1997/7/1)
はるか昔の神々のなかで最長老のものが、天空と大地を読むことを人間に教えた。このように老アントニオは言った。世界という本を構成する偉大な二枚の頁(老アントニオよると、もっとも偉大な神々、世界を誕生させた神々はこのように表現していた)のなかで、真の男女は、自分たちが歩むべき方向を読み取ることができる。
天空が沈黙し、太陽と月が黙って統治し、大地が堅牢な地面の内側に自らの任務を隠すとき、トウモロコシの男女は言葉をしまっておく。そして、言葉を考えながら働く。大地の天井が、雲や雨、風とともに叫び、月と太陽が少しの時間だけ顔をのぞかせ、大地が緑と生命で満たされるとき、言葉のすみかであり道でもある山のなかで、真の男女はふたたび言葉を紡ぎ出す。
この数日間、われわれ(われわれだけではない)は沈黙した。われわれの内面を見つめるためである。新しい種を播くためである。より強くなるためである。心と言葉が自らを実現できる新しい場所を見出すためである。そのため、われわれの沈黙が響いた。
一部の人たち、胸の左側に心と希望をもっている人々の大半は、騒音と沈黙の時間があることを理解した。そして、その時間が上から強制され押し寄せるときには、沈黙はより力強く共鳴することを学んでいた。
別の人たちは話すことを要求していた。今、黙ってしまえば、勝ち取った空間を明け渡すこと、あるいはわれわれの敗北の上に権力者が作っているもとから幸せな勘定をさらに盛り上げることになると、言っている。
別の人たちは、われわれに、黙って「慎ましくしろ」とか、「迷惑をかけるな」と要求してきた。EZLNの先住民の登場時間でないことをわきまえろ。政党の時間であることを理解せよと言ってきた。慎ましい人たちに慎ましさ、無口な人たちに沈黙を求めてきた。
軍隊は、われわれの沈黙のなかに、自分たちの手持ちの道具である政治的な包囲作戦が決して成功しないことを聴き取っている。最高権力者たちは、サパティスタ内部でおぞましい分裂や粛清が起きていると妄想(願望)していた。それゆえ、この沈黙を利用して、連邦政府や地方政府は、叛乱する共同体に対する軍事的圧力を高め、包囲網を強化してきた。選挙キャンペーンが広報しだした危機を緩和するため、連中の手持ちのすべての力を行使して、われわれを挑発しようとしてきた。
われわれは抵抗する。沈黙しながら我々にふさわしい明日を織り込んでいる。権力者の勇猛さと傲慢さは、尊厳と呼ばれるものと幾度も衝突してきた。 今、権力者はもっとも弱くなっている。われわれは少しだが強くなっている。それがわれわれの沈黙の力である。

『下の左に心がある』
14 われわれは誰でもない(1997/12/15)
追伸-ギリシア悲劇を現代風にしよう
夜間の軍偵察飛行機が発している脅迫的な音がとどろいた後、茶色のタツノオトシゴがラ・マールの胸に寄り掛かっている。夜明け前は、ものごとを習得する時である。そこで、霧を驚かせ、寒さを和らげるために、老アントニオがやってきた。
老アントニオ(理由は説明できないが、エウリピデスの愛読者)は、戦いと未来に関する独自の理論をもっている。「権力者は歴史の転換とともに名称を変える」
私に向かってこう言うと、彼は巻き煙草に火をつけた。
「権力者に反対する闘争、権力が全能であり、権力者による支配のない未来はありえ
ない。それをめぐる権力者の見解が、何度も、われわれに繰り返され、販売されてきた。犯罪を美しく見せかけ、嘘には寛大である黄金の鏡の前で、権力者は、『誰も私を打倒できない』と何度も言っている。小さな時から、われわれはこのように歴史を教え込まれた。だから、誰も権力者を打ち負かせないと、われわれは思い込んでいる」
老アントニオはこう言うと、吐き出した長い紫煙で嘘の大きさを描いた。そして、火のついた巻き煙草の小さな光は真実の重さを物語っている。
「われわれ、下のものはいつも同じ名前をもっている。歴史の転換など大した意味をもたない。われわれ、小さき者は誰でもない…」
上空では、夜明けが近いことが予告されている。ともあれ、かくも長い夜の後には、朝と呼ばれるものがやってくる。下では…ラ・マールが寝ている。

ラ・マールのタツノオトシゴのイヤリング
15 他者のお話(1998/1/21)
あなた方に関してですが、われわれの希望は大きくなり、われわれはよくなっている。なぜなら、われわれは人の意見に耳を傾けることができるからである。老アントニオも言っていた。人の意見を聞ける人は大きくなり、自らの歩みを時間とともに進めることができる。その歩みは遠くまで及び、多くの様々な道に増えていく。
***
平和と人類のための戦いは国際的である。この点について、われわれは皆さんと意見が一致する。なぜなら、異なっている他者がいない人生は虚しく、活力はなくなってしまうからである。真価を認められていないが、偉大なる国際主義者である老アントニオも、そのように言っている。そのことが、人類のため、新自由主義に反対する国際的な戦いと、どんな関係があるのか?よろしい、それを皆さん[1998年1月12日メキシコ市での集会]に説明するのに最適と思われるお話を私は知っている……

1998年1月3日、政府軍を素手で追い返すチアパス州ショエップの女性たち

1998年1月12日のメキシコ市での集会
また、ある夜明け前のことである。威嚇するように上空を偵察飛行機が飛んでいた。しかし、短いロウソクのほのかな灯りで、ラ・マールは一冊の詩の本を読もうとしていた。私は個人的に面識がない人物に手紙を走り書きしていた。その人物は、おそらく外国語を話し、別の文化を有し、おそらく外国人である。肌の色も異なり、きっと別の歴史を有しているはずである。飛行機が通り過ぎたので、私は走り書きをやめた。そうしたのは、詩を読んでいるラ・マールの声にちょっと耳を傾けようと思ったからである。だが本当は、異なる他者に手紙を書くという問題を解決する時間を稼ぐためだった。
そのとき、高い山にかかっている霧を抜け、ラ・マールのあいだから予告もなしに、老アントニオが私の側にやってきた。私の背中を二・三度たたくと、煙草に火をつけて…
他者のお話
この大地に住みついた最長老たちは話した。それによると、いちばん偉大な神々、この世界を誕生させた神々は、皆でいっしょに考えることはなかった。神々は同じ考えをもたず、それぞれが独自の考えをもっていた。おたがい尊重しあい、おたがいの意見に耳を傾けた。最長老が言うには、神々はもとからそうだった。そうでなければ、この世界はけっして誕生しなかっただろう。最初の神々は戦うことにすべての時間を費やしたはずである。神々がそれぞれ感じていた考え方は異なっていたからである。
最長老たちは言った。
いちばん偉大な神々、最初の神々の心のなかにあった考えと同じように、世界は多くの色や形をもって誕生した。いちばん偉大な神々は七つだった。それぞれの神がもった考えは七つだった。世界を彩ったのは、七かけ七の色と形だった。
老アントニオは私に話した。
「神々がおたがい感じている考え方はずいぶん異なっているのに、最初の神々はどのように話し合い合意できたのですか?」と、老アントニオは最長老たちにたずねた。老アントニオが私に語ったところによると、最長老たちは次のように答えた。七名の神々はそれぞれ七つの異なる考え方をもち寄り会合を開いた。その集会でひとつの合意を導き出した。
老アントニオは話した。
最長老が言うには、最初の神々、世界を創造した神々が集った集会は大昔だった。時間がまだ存在しない時代だった。この集会で、最初の神々はそれぞれ独自の言葉を発した。「私の感じている考え方は他者の考え方と異なっている」と、すべての神々が言った。そこで神々は黙り込んだ。誰かが「他者」と言うとき、おたがいに異なった「他者」のことを話している。そのことに神々は気づいたのである。
しばらく沈黙が続いた。だが、最初の神々はすでに最初の合意ができたことに気がついていた。その合意とは「他者」が存在するということである。しかもこの「他者」はたがいに異なっているものだった。いちばん最初の神々が手にした最初の合意は、たがいの相違を認め、他者の存在を受け入れることだった。最初の神々は、全員がもともと神だった。だから、それ以外のやり方はなかった。それを受け入れるしかなかった。多かれ少なかれ、他者でない存在はありえなかった。おたがいに異なっていても歩かざるをえなかった。
この最初の合意の後も、神々の議論は続いた。なぜなら、異なった他者がいることを認めることと、そうした他者を尊敬することは、まったく別問題だったからである。かなりの期間、お互いがどのように異なるかについて、神々は話し合い議論した。こうした議論に時間がかかるのは、神々にとり大した問題ではなかった。そのとき、まだ時間はなかったからである。
すべての神々が沈黙した後、それぞれが自分の相違点について話した。その話を聞いていたほかの神々は、他者の相違点に耳を傾け、相違点を確認しながら、違ったものをもっていること自体を自覚することが最善であることに気づいた。
こうしてすべての神々は大いに満足し、踊りだした。ずいぶん遅れたが、神々は気にしなかった。なぜなら、まだ時間がなかったからである。没頭していた踊りが終わり、神々はひとつの合意を導き出した。
異なる他者がいることはよいことであり、自分自身を知るためにも、他者の意見に耳を傾けるべきであるという合意だった。この合意が結ばれた後、神々は寝るために立ち去った。踊りすぎたため、神々は疲れていた。話に疲れたのではない。これらの最初の神々、世界を誕生させた神々は、話をするのがとても好きだった。神々は他者の話に耳を傾けることをやっと習得したばかりだった。

自分とは異なる他者の存在
老アントニオがいつ立ち去ったのか、まったく気づかなかった。ラ・マールはもう寝ていた。ロウソクの小さな芯は溶け、歪んだパラフィンの塊になった。上空では、明け方の光の中、天空の黒い空の色は徐々に薄まりはじめた……
このお話は、皆さんに手紙を書こうとしていたとき、老アントニオが私にしてくれたものである。私は確信している。われわれが皆さんに言うべきいちばん重要なことは、つまるところ、われわれが皆さんに耳を傾け、認め合い、尊重することである。
16 埋められた鍵のお話(1998/2/24)
歴史-下にある大地を見ることを理解することである
ラ・マールが一休みしている雲の海岸(四番目の鍵)では、満月はオレンジ色をした星のようである。膨張した満月の縁はきれいに磨かれている。われわれはいつものように横になっている。私はラ・マールに話をしている。その話とは、今朝と同じような夜明け前、老アントニオが煙草の煙で雲を補充しながら、私に話したものである。
煙草の煙を渦巻き状に吐きながら、われわれは月に向けて吹き出した煙の環を見つめていた。おたがい口に出さなかったが、われわれはその紫煙の環に空にかかる月を固定しようとした。だが無駄だった。押し寄せる時間や雲を打ち破るように、月は前進しつづけた。われわれは黙ってテペスクィントレ[小型げっ歯類]を待ち伏せしていた。満月のもとでも、テペスクィントレを「照明」できることを証明しようかと、老アントニオは私に提案した。
「あそこだ!見えたか?」と老アントニオはつぶやくように言った。
「ああ、見えた」と嘘をつきながら、私は老アントニオのかざすランプの光の束によって浮き出ているはずのエメラルド色の両眼を探した。しかし、無理だった。
単発式猟銃は乾いた音を発し、火を噴いた。しかし、すぐにその音はコオロギの発する太鼓のような執拗な音にかき消された。私は老アントニオがランプで指し示した地点へ駆け出した。50㎝ぐらいのテペスクィントレが怯えて立ちすくんでいた。マチェーテの平らな背で、テペスクィントレに一撃を加えた。それによって、私は老アントニオの単発式猟銃の一撃とともに始まった食事の準備を完成させた。私はテペスクィントレをつかみ、老アントニオが新しい巻き煙草を作っている場所に運んだ。

テペスクィントレ
私を見ずに彼はつぶやいた。「おまえは何も見ていなかったな」
実際は、私といえば、月が都合よく沈むのを期待し、『耳をそばだてて』いただけである。またも、平然と嘘をつくことになった。「ちゃんと見ていました」
マッチの光で、老アントニオの微笑みと口にくわえた巻き煙草が照らしだされた。話題を変えようと、私は質問した。
「いつランプを灯し、どこを照らすのか、どうしてわかったのですか?」
「この下で見たのだ」と、老アントニオは身振りで地面を指差した。
「地面の下で見たですって?」と私は冷やかすようにたずねた。
老アントニオは質問に答えなかった。直接は答えず、横になってお話を始めた。
埋められた鍵のお話
いちばん最初の神々、世界を誕生させた神々は、たいへん物覚えが悪かったと言われている。神々は、自分たちが行なったことや、言ったことをすぐに忘れていた。ある人が言うには、物覚えが悪かったのは、いちばん偉大な神々は何も覚える必要がなかったからである。時間が時間をもっていなかった時代から、神々はそうだった。つまり、彼らの前には何もなかった。前に何もないから、記憶すべきものはいっさいなかった。はっきりしたことは誰にもわからない。いずれにせよ、神々は何もかも忘れていた。これまで世界に存在したすべての統治者はこの悪癖を引き継いできた。
しかし、いちばん偉大な神々、最初の神々はよく知っていた。記憶は未来の鍵である。だから、大地、家、歴史を世話するため、記憶も世話しなければならない。健忘症になるのを防止するため、最初の神々、世界を誕生させた神々は、自分たちが行なったことや知っていることすべてについてコピーを作った。地上にあるものと混同されないように、神々はコピーを地面の下に隠した。だから、大地の地面の下に地上と同じ別の世界がある。それは地上の世界と同じ歴史をもつ。最初の世界はこの大地の下にある。
「地下にある世界はわれわれが知っている世界と同じものですか?」と、私は老アントニオに質問した。「昔はそうだった。だが、今は違う」と老アントニオは答えた。彼の説明では、時間が経つにつれ、地上の世界は秩序が崩れ、居心地が悪くなった。
いちばん最初の神々がいなくなった。すると、どの統治者も、居心地の悪くなったものを調整するため、下を見つめることを忘れた。自分が接している世界だけが世界で、ほかの世界など存在するはずはない。このように新しい世代の支配者たちは考えた。大地の下のものは、大地の上のものと同じだが、その形態は違うようになった」
だから、新生児のヘソの緒を大地に埋めることが、真の男女の習慣となっているのだと、老アントニオは言った。そうするのは、世界の真実の歴史を見つめ、世界をあるべき姿に再適合させるため、新しい人間が戦えるようにするためである。この下には世界があるだけではない。よりよい世界の可能性がある。
「じゃあ、私たちは下の世界でも二人なの?」とラ・マールは眠そうにたずねた。「当然、いっしょだよ」と私は答えた。「あなたの言うことは信用できないわ」と、ラ・マールは言った。そして、淑やかに横たわっている向きを変えると、小石で地面にできた小さな窪みを覗いた。「潜望鏡があれば、われわれも覗けるさ」と、ラ・マールに言った。「潜望鏡ですって?」と、彼女はつぶやいた。
「そう、潜望鏡だよ。逆立ちした……潜望鏡だ」と私は言った。
***
結局、老アントニオの言うことは正しい。私にはそう思われる。われわれが今苦しんでいる世界にくらべ、はるかによい世界がこのわれわれの下にある。記憶は未来の鍵であると、老アントニオは言う。しかも(私が付け加えるなら)、歴史は逆立ちした…潜望鏡そのものである。
17 上と下のテーブル(1998/2/26)
上のテーブル:恐怖と退廃の静止写真
「目覚めていない者たちを目覚めさすことになる。七日間の儚い支配、夢のように過ぎ去った支配、支配が続いた七つの太陽の期間にも目覚めないままでいる者たちを。その配下の連中は、オリル・オッチ、オポッサム[トラクアチェ]の姿をしている。しかし、むだなことだが、ジャガーの皮で偽装し、統治するだろう」
『チラム・バラム諸本の書』
……コラージュだって?まあ、いいさ。これで、あなた方はメキシコの権力のおぞましい七匹の野獣のイメージをもつことができる。大きなテーブルの上では、国家政党体制というヒドラと、組織犯罪者というメドゥーサがのさばっている。それには、オポッサムの政治屋、ネズミの知識人、蛇の銀行家、悪魔の宗教家、ハイエナの軍人が連なる。……

こどもを背負ったオポッサム(トラクアチェ)
下のテーブル:これから撮られる写真
「世界の人々は幸せになるだろう。あらゆる大地の人々は繁栄するだろう。臣民の血をすするアリクイ、カボチュ(ジャガランディ)、メス狐、チャマコブ、イタチは終わりを迎えるだろう。さもしい支配者やさもしい政府はなくなるだろう。王侯の追従者たちもなくなり、彼らに代わるものを求める者もいなくなるだろう。これは、12アハフ・カトゥンが指し示している責務である……世界の喜びのため、正当な領主たちの命令は正当なものであり、誰もがそれに従うだろう」
『チラム・バラム諸本の書』
……下のテーブルは雑然とし、サービスも不十分である。会食し、人々と出会うためにそこに座っている人はまだ少ない。会食者は、あちこちバラバラに座っている。…… 下のテーブルは、まだまだ空席がいっぱいある。テーブルに着くには、尊厳だけあればよいと言われている。…それと潜望鏡が?……

『資本主義というヒドラに対する批判的思考』
(2015年刊)
18 ライオンと鏡のお話(1998/7/17)
憔悴した毛沢東主義に対抗する老アントニオ
老アントニオは話してくれた。彼がまだ若かった頃、彼の父ドン・アントニオは、銃を使わずにライオンを殺す方法を教えてくれた。老アントニオによると、彼が若いアントニオで、彼の父親が老アントニオだった頃、彼の父親が彼にそのお話をした。老アントニオは私にそのお話をしてくれた。だから、ラ・マールも私の口を通して語られるこのお話を知ることができる。老アントニオは私にそのお話をしたにすぎない。だが私は題をつけた。
ライオンと鏡のお話
ライオンはまず獲物の身体を八つ裂きにする。その後で、獲物の心臓を食べながら、血をすする。残りの部分はソピローテ[ハゲタカの一種]のものになる。ライオンの力に対抗できるものはいない。ライオンに立ち向かう動物はいない。人間でも逃げ出す。ライオンを倒せるのは、ライオンと同じように野蛮で血に飢えた強力な力だけである。

死肉をあさるソピローテ
当時の若いアントニオから見ると当時の老アントニオにあたる父親は、トウモロコシの葉で巻き煙草を作った。そして、カマドの火のなかで光り輝く星のようにパチパチと燃えている木の幹を見つめながら、若いアントニオの方を横目でちらりと見た。老アントニオの予想に反し、すぐに若いアントニオがたずねた。「ライオンを打ち倒すほど強大な力とは、どのようなものですか?」
当時の老アントニオは、当時の若いアントニオに鏡を手渡した。「僕にですか?」と、当時の若いアントニオは、円い手鏡に映る自分の姿を覗き込んだ。当時の老アントニオは楽しそうに微笑むと(当時の若いアントニオはこう言った)、彼から鏡を取り上げた。「ちがう。おまえじゃない」と老アントニオは言った。「鏡を見せたのは、ライオンを倒せる力は、ライオン自身の力と言いたかったからだ。ライオンを倒せるのはライオンだけだ」
当時の若いアントニオは何か言おうとしたが、「そうですか」とつぶやいた。当時の老アントニオは、若いアントニオが何もわかっていないことを知っていたが、お話を続けた。
ライオンを倒すことができるのはライオンである。それがわかったので、われわれはライオンがライオンに立ち向かうようにするにはどうしたらよいかと考えはじめた。共同体の最長老たちはライオンのことをよく知らなければならないと言って、ひとりの若者を任命した。そして、ライオンを知るという任務を彼に課した。
「あなただったの?」と当時の若いアントニオは口をはさんだ。当時の老アントニオは黙って座り、カマドで燃える木の幹を調整した。そして続けた。
最長老たちは、若者をセイバの木の頂に登らせると、木の根元に子牛を縛った。若者は、ライオンがどのように子牛を扱うかを観察し、ライオンが立ち去るまで木の上で待機しなければならなかった。共同体に帰って、見たことを説明しなければならなかった。若者が待っていると、ライオンがきた。ライオンは子牛を殺し、八つ裂きにした。その後、心臓を食べながら血をすすり、立ち去った。ソピローテは分け前を待ちながら飛び跳ねていた。
若者は共同体に戻り、自分が見たことを説明した。最長老たちはしばらく考え込んだ。「マタドールがもたらす死は自らの死である」と言った。そして鏡と釘、一匹の子牛を若者に与えた。「明日の夜、裁きを実行しよう」と言うと、長老たちは考えを巡らしだした。
若者はわかっていなかった。小屋に帰った彼はしばらく遊びを見物していた。そこに彼の父親が帰ってきた。父親は何が起きたのか質問した。若者は父親にすべてを説明した。若者の父親は黙っていたが、やがて話しだした。若者は微笑みながら、父親の話を聞いた。
翌日、夕暮の空が黄金色となり、灰色の夜の帳が木々の樹冠を覆っていった。若者は共同体を離れ、子牛を連れてセイバの木の根元に行った。母なる木の根元に着くと、子牛を殺し、心臓を取り出した。鏡を粉々に砕き、その破片を血で心臓に貼りつけた。その後、心臓を開け、そのなかに釘を詰め込んだ。心臓を子牛の胸に戻すと、子牛が生きているように立たせ、杭を使って骨組みを作った。若者はセイバに木の頂に登ると、そこでじっと待っていた。天上では、夜の帳が木々から地上にまで降りていた。
「マタドールがもたらす死は自らの死である」という父の言葉を若者は思い出した。
下の世界が完全に夜になった頃、ライオンがきた。子牛に近づき、一撃を加え、八つ裂きにした。心臓を舐めたとき、ライオンは血が乾いているのが気になった。だが、鏡の破片でライオンの舌が傷つき、出血しだした。自分の口の血は子牛の心臓の血である。こう判断したライオンは興奮のあまり一気に心臓にかぶりついた。釘によってさらに出血はひどくなった。ライオンは自分の口についた血は子牛の心臓の血だと思った。何度も噛んだので、ライオンはますます傷ついた。さらに大量の血が流れ、ライオンは噛みつづけた。ライオンは噛みつづけ、出血で死んでしまった。
若者はライオンの爪を首飾りとして戻ってきた。共同体の長老中の最長老にライオンの爪を指し示した。長老は微笑みながら、若者に助言した。「ライオンの爪を勝利の記念杯としてではなく、鏡として保管すべきである」
このように老アントニオはライオンが死んだお話をしてくれた。
彼は小さな鏡だけでなく古い単発式猟銃をいつも身につけている。彼は微笑みながら片目でウィンクして言った。「ライオンが歴史を知らないのは当然である」
次はラ・マールが付け加えたものである。
「ライオンだけでなく、オリベ[アドルフォ・オリベ、1970年~80年代前半にチアパス農村部で影響力のあったプロレタリア路線指導者]もね」
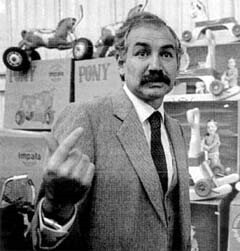
アドルフォ・オリベ
[1970年~80年代前半にプロレタリア路線指導者]
19 水のなかの魚(1998/7/17)
老アントニオは、元左翼の元毛沢東主義者や元急進主義者でありながら、現在は右翼の犯罪者たちの輝かしき顧問に就任している連中(棘あるサボテンのように話していたくせ、今では身を隠すためにダチョウの真似をしている)について話してくれた。それともに、こうした革命家連中と大衆の関係に関して、水のなかの魚にたとえて、独自の解釈を展開した。同時に、慌てふためく政府の顧問たちが推奨している「魚から水を奪え」という反乱鎮圧作戦の戦略について持論を展開した。老アントニオは、共同体の最長老たちがしたお話をしてくれた。そのお話は次のような内容である。
水のなかの魚
むかし、川に一匹のとてもきれいな魚がすんでいた。それを見たライオンはその魚が食べたくなった。ライオンは川に行った。しかし泳げなかったので、魚を攻撃できなかった。ライオンはオポッサムに援助を要請した。オポッサムはライオンに言った。「簡単です。魚は水がなければ動けません。あなたは川の水を飲み干せばいいのです。そうすれば魚は動けなくなり、あなたは魚を攻撃し、食べられます」ライオンはオポッサムの助言に満足して、彼の王国のポストを割り当てた。ライオンは川岸に行き、水を飲み干しだした。腹が水で一杯になり、ライオンは死んだ。オポッサムは職を失った。タンタン。

タネ元の『オポッサムと虎(ジャガー)』のお話し
20 記憶の容器のお話(1998/8/28)
ラ・マールは自分のお腹にいる私の夢をみていた。そのとき、数日後(8月28日)、下から発生するものすべてがそうであるように、最初は小さいがしだいに成長した運動の20周年をドニャたち[政治犯の釈放や行方不明者の究明を要求し1978年8月28日からハンストを始めた女性たち、ロサリオ・イバラはそのシンボル的存在]が祝うことになることを私は思い出した。20年前、(権力からみれば)頑固で厄介な女や男たちが、政治犯の釈放と行方不明者の所在解明を要求して、ハンストを開始した。

1978年8月、ハンストを始めた『エウレカ』のドニャ達
(右端がロサリオ・イバラ)
われわれ、そして現在は歴史をもっていない他者たちは、この強固な慈愛に満ちた女性たちに多くのことを負っている。唯一というわけではないが、そのひとつは明日のことである。ドニャたちのように、記憶は休息も降伏もしないし、尊厳には年齢や大きさがない。われわれはそのことをよく知っている。そのことを明日は自分自身とわれわれに約束している。
そして、老アントニオはラ・マールのため贈り物を携えてきた。そして、お話をするためだけにお話をした………。

記憶の容器としてのヒカラ
記憶の容器のお話
われわれの最長老たちは次のように語った。
いちばん最初の神々、この世界を誕生させた神々は、世界を歩んでいる男女に記憶を分配した。いちばん偉大な神々は次のように言い聞かせた。
「記憶とはいいものだ。なぜなら、記憶は、現在を理解し、未来を約束するのを手助けしてくれる鏡である」
いちばん最初の神々は、記憶を分配する容器をヒカラの実 [ヒカロ:フクベノキになる実] で作った。あらゆる男と女が記憶の容器を受け取りにきた。だが、一部の男や女はほかの男や女より大きかった。だから、記憶の容器はすべての人々にとって対等ではないように思われた。より小さき者は自分の記憶の容器を完全に輝かせていた。しかし、より大きな者の容器はくすんでいた。それゆえ、小さき者のあいだでこそ、記憶はいちばん大きく強固になる。逆に、強大な者のなかで、記憶を見いだすのは困難となる。
だから、男や女は老いるにつれてますます小さくなる。それは記憶をより輝かせるためである。最長老たちの任務は、記憶を偉大にすることと言われている。さらに、尊厳とは生きている記憶であると言われている。
そういうことだ。

多様なデザインのヒカラ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
