
【Project_Gutenberg_200im】「THE BOOK OF TEA」その1【I. The Cup of Humanity】
〜〜【Project_Gutenberg】→Web翻訳版→【Project_Gutenberg_200im】
〜
THE BOOK OF TEA
By Kakuzo Okakura
〜
【Contents】
I. The Cup of Humanity ←今回の紹介
II. The Schools of Tea.
III. Taoism and Zennism
IV. The Tea-Room
V. Art Appreciation
VI. Flowers
VII. Tea-Masters
〜
〜〜
〜〜[上記【Project_Gutenberg】の翻訳は以下の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]
〜
茶の本
岡倉覚三著
〜
内容
I.人類の杯 ←今回の紹介
II.お茶の学校
III.道教と禅教
IV.茶室
V.芸術鑑賞
VI.花
VII.茶人
〜
〜〜
【出所】URL> https://www.gutenberg.org/files/769/769-h/769-h.htm
〜〜【Project_Gutenberg】THE BOOK OF TEA
〜
I. The Cup of Humanity
Tea began as a medicine and grew into a beverage. In China, in the eighth century, it entered the realm of poetry as one of the polite amusements. The fifteenth century saw Japan ennoble it into a religion of aestheticism—Teaism. Teaism is a cult founded on the adoration of the beautiful among the sordid facts of everyday existence. It inculcates purity and harmony, the mystery of mutual charity, the romanticism of the social order. It is essentially a worship of the Imperfect, as it is a tender attempt to accomplish something possible in this impossible thing we know as life.
The Philosophy of Tea is not mere aestheticism in the ordinary acceptance of the term, for it expresses conjointly with ethics and religion our whole point of view about man and nature. It is hygiene, for it enforces cleanliness; it is economics, for it shows comfort in simplicity rather than in the complex and costly; it is moral geometry, inasmuch as it defines our sense of proportion to the universe. It represents the true spirit of Eastern democracy by making all its votaries aristocrats in taste.
The long isolation of Japan from the rest of the world, so conducive to introspection, has been highly favourable to the development of Teaism. Our home and habits, costume and cuisine, porcelain, lacquer, painting—our very literature—all have been subject to its influence. No student of Japanese culture could ever ignore its presence. It has permeated the elegance of noble boudoirs, and entered the abode of the humble. Our peasants have learned to arrange flowers, our meanest labourer to offer his salutation to the rocks and waters. In our common parlance we speak of the man "with no tea" in him, when he is insusceptible to the serio-comic interests of the personal drama. Again we stigmatise the untamed aesthete who, regardless of the mundane tragedy, runs riot in the springtide of emancipated emotions, as one "with too much tea" in him.
The outsider may indeed wonder at this seeming much ado about nothing. What a tempest in a tea-cup! he will say. But when we consider how small after all the cup of human enjoyment is, how soon overflowed with tears, how easily drained to the dregs in our quenchless thirst for infinity, we shall not blame ourselves for making so much of the tea-cup. Mankind has done worse. In the worship of Bacchus, we have sacrificed too freely; and we have even transfigured the gory image of Mars. Why not consecrate ourselves to the queen of the Camelias, and revel in the warm stream of sympathy that flows from her altar? In the liquid amber within the ivory-porcelain, the initiated may touch the sweet reticence of Confucius, the piquancy of Laotse, and the ethereal aroma of Sakyamuni himself.
Those who cannot feel the littleness of great things in themselves are apt to overlook the greatness of little things in others. The average Westerner, in his sleek complacency, will see in the tea ceremony but another instance of the thousand and one oddities which constitute the quaintness and childishness of the East to him. He was wont to regard Japan as barbarous while she indulged in the gentle arts of peace: he calls her civilised since she began to commit wholesale slaughter on Manchurian battlefields. Much comment has been given lately to the Code of the Samurai,—the Art of Death which makes our soldiers exult in self-sacrifice; but scarcely any attention has been drawn to Teaism, which represents so much of our Art of Life. Fain would we remain barbarians, if our claim to civilisation were to be based on the gruesome glory of war. Fain would we await the time when due respect shall be paid to our art and ideals.
When will the West understand, or try to understand, the East? We Asiatics are often appalled by the curious web of facts and fancies which has been woven concerning us. We are pictured as living on the perfume of the lotus, if not on mice and cockroaches. It is either impotent fanaticism or else abject voluptuousness. Indian spirituality has been derided as ignorance, Chinese sobriety as stupidity, Japanese patriotism as the result of fatalism. It has been said that we are less sensible to pain and wounds on account of the callousness of our nervous organisation!
Why not amuse yourselves at our expense? Asia returns the compliment. There would be further food for merriment if you were to know all that we have imagined and written about you. All the glamour of the perspective is there, all the unconscious homage of wonder, all the silent resentment of the new and undefined. You have been loaded with virtues too refined to be envied, and accused of crimes too picturesque to be condemned. Our writers in the past—the wise men who knew—informed us that you had bushy tails somewhere hidden in your garments, and often dined off a fricassee of newborn babes! Nay, we had something worse against you: we used to think you the most impracticable people on the earth, for you were said to preach what you never practiced.
Such misconceptions are fast vanishing amongst us. Commerce has forced the European tongues on many an Eastern port. Asiatic youths are flocking to Western colleges for the equipment of modern education. Our insight does not penetrate your culture deeply, but at least we are willing to learn. Some of my compatriots have adopted too much of your customs and too much of your etiquette, in the delusion that the acquisition of stiff collars and tall silk hats comprised the attainment of your civilisation. Pathetic and deplorable as such affectations are, they evince our willingness to approach the West on our knees. Unfortunately the Western attitude is unfavourable to the understanding of the East. The Christian missionary goes to impart, but not to receive. Your information is based on the meagre translations of our immense literature, if not on the unreliable anecdotes of passing travellers. It is rarely that the chivalrous pen of a Lafcadio Hearn or that of the author of "The Web of Indian Life" enlivens the Oriental darkness with the torch of our own sentiments.
Perhaps I betray my own ignorance of the Tea Cult by being so outspoken. Its very spirit of politeness exacts that you say what you are expected to say, and no more. But I am not to be a polite Teaist. So much harm has been done already by the mutual misunderstanding of the New World and the Old, that one need not apologise for contributing his tithe to the furtherance of a better understanding. The beginning of the twentieth century would have been spared the spectacle of sanguinary warfare if Russia had condescended to know Japan better. What dire consequences to humanity lie in the contemptuous ignoring of Eastern problems! European imperialism, which does not disdain to raise the absurd cry of the Yellow Peril, fails to realise that Asia may also awaken to the cruel sense of the White Disaster. You may laugh at us for having "too much tea," but may we not suspect that you of the West have "no tea" in your constitution?
Let us stop the continents from hurling epigrams at each other, and be sadder if not wiser by the mutual gain of half a hemisphere. We have developed along different lines, but there is no reason why one should not supplement the other. You have gained expansion at the cost of restlessness; we have created a harmony which is weak against aggression. Will you believe it?—the East is better off in some respects than the West!
Strangely enough humanity has so far met in the tea-cup. It is the only Asiatic ceremonial which commands universal esteem. The white man has scoffed at our religion and our morals, but has accepted the brown beverage without hesitation. The afternoon tea is now an important function in Western society. In the delicate clatter of trays and saucers, in the soft rustle of feminine hospitality, in the common catechism about cream and sugar, we know that the Worship of Tea is established beyond question. The philosophic resignation of the guest to the fate awaiting him in the dubious decoction proclaims that in this single instance the Oriental spirit reigns supreme.
The earliest record of tea in European writing is said to be found in the statement of an Arabian traveller, that after the year 879 the main sources of revenue in Canton were the duties on salt and tea. Marco Polo records the deposition of a Chinese minister of finance in 1285 for his arbitrary augmentation of the tea-taxes. It was at the period of the great discoveries that the European people began to know more about the extreme Orient. At the end of the sixteenth century the Hollanders brought the news that a pleasant drink was made in the East from the leaves of a bush. The travellers Giovanni Batista Ramusio (1559), L. Almeida (1576), Maffeno (1588), Tareira (1610), also mentioned tea. In the last-named year ships of the Dutch East India Company brought the first tea into Europe. It was known in France in 1636, and reached Russia in 1638. England welcomed it in 1650 and spoke of it as "That excellent and by all physicians approved China drink, called by the Chineans Tcha, and by other nations Tay, alias Tee."
Like all good things of the world, the propaganda of Tea met with opposition. Heretics like Henry Saville (1678) denounced drinking it as a filthy custom. Jonas Hanway (Essay on Tea, 1756) said that men seemed to lose their stature and comeliness, women their beauty through the use of tea. Its cost at the start (about fifteen or sixteen shillings a pound) forbade popular consumption, and made it "regalia for high treatments and entertainments, presents being made thereof to princes and grandees." Yet in spite of such drawbacks tea-drinking spread with marvelous rapidity. The coffee-houses of London in the early half of the eighteenth century became, in fact, tea-houses, the resort of wits like Addison and Steele, who beguiled themselves over their "dish of tea." The beverage soon became a necessity of life—a taxable matter. We are reminded in this connection what an important part it plays in modern history. Colonial America resigned herself to oppression until human endurance gave way before the heavy duties laid on Tea. American independence dates from the throwing of tea-chests into Boston harbour.
There is a subtle charm in the taste of tea which makes it irresistible and capable of idealisation. Western humourists were not slow to mingle the fragrance of their thought with its aroma. It has not the arrogance of wine, the self-consciousness of coffee, nor the simpering innocence of cocoa. Already in 1711, says the Spectator: "I would therefore in a particular manner recommend these my speculations to all well-regulated families that set apart an hour every morning for tea, bread and butter; and would earnestly advise them for their good to order this paper to be punctually served up and to be looked upon as a part of the tea-equipage." Samuel Johnson draws his own portrait as "a hardened and shameless tea drinker, who for twenty years diluted his meals with only the infusion of the fascinating plant; who with tea amused the evening, with tea solaced the midnight, and with tea welcomed the morning."
Charles Lamb, a professed devotee, sounded the true note of Teaism when he wrote that the greatest pleasure he knew was to do a good action by stealth, and to have it found out by accident. For Teaism is the art of concealing beauty that you may discover it, of suggesting what you dare not reveal. It is the noble secret of laughing at yourself, calmly yet thoroughly, and is thus humour itself,—the smile of philosophy. All genuine humourists may in this sense be called tea-philosophers, Thackeray, for instance, and of course, Shakespeare. The poets of the Decadence (when was not the world in decadence?), in their protests against materialism, have, to a certain extent, also opened the way to Teaism. Perhaps nowadays it is our demure contemplation of the Imperfect that the West and the East can meet in mutual consolation.
The Taoists relate that at the great beginning of the No-Beginning, Spirit and Matter met in mortal combat. At last the Yellow Emperor, the Sun of Heaven, triumphed over Shuhyung, the demon of darkness and earth. The Titan, in his death agony, struck his head against the solar vault and shivered the blue dome of jade into fragments. The stars lost their nests, the moon wandered aimlessly among the wild chasms of the night. In despair the Yellow Emperor sought far and wide for the repairer of the Heavens. He had not to search in vain. Out of the Eastern sea rose a queen, the divine Niuka, horn-crowned and dragon-tailed, resplendent in her armor of fire. She welded the five-coloured rainbow in her magic cauldron and rebuilt the Chinese sky. But it is told that Niuka forgot to fill two tiny crevices in the blue firmament. Thus began the dualism of love—two souls rolling through space and never at rest until they join together to complete the universe. Everyone has to build anew his sky of hope and peace.
The heaven of modern humanity is indeed shattered in the Cyclopean struggle for wealth and power. The world is groping in the shadow of egotism and vulgarity. Knowledge is bought through a bad conscience, benevolence practiced for the sake of utility. The East and the West, like two dragons tossed in a sea of ferment, in vain strive to regain the jewel of life. We need a Niuka again to repair the grand devastation; we await the great Avatar. Meanwhile, let us have a sip of tea. The afternoon glow is brightening the bamboos, the fountains are bubbling with delight, the soughing of the pines is heard in our kettle. Let us dream of evanescence, and linger in the beautiful foolishness of things.
〜
〜
II. The Schools of Tea. ←次回紹介予定
〜
〜〜
〜〜【Project_Gutenberg】“THE BOOK OF TEA”「茶の本」
〜〜 翻訳はアプリ「DeepL」を使用。
〜
I.人類の杯
茶は薬として始まり、飲料に成長した。中国では8世紀、礼儀正しい娯楽のひとつとして詩歌の領域に入った。15世紀の日本では、茶は耽美主義の宗教-茶教-へと昇華した。茶道は、日常生活の汚れた事実の中にある美しいものへの崇拝を土台とする教団である。純粋さと調和、相互慈愛の神秘、社会秩序のロマンチシズムを教え込む。それは本質的に不完全なものへの崇拝であり、人生という不可能なものの中で可能なことを成し遂げようとする優しい試みである。
紅茶の哲学は、普通の言葉で言うところの単なる美学ではなく、倫理や宗教とともに、人間と自然についての私たちの考え方全体を表現している。それは衛生学であり、清潔さを強制するからである。それは経済学であり、複雑で高価なものよりもむしろシンプルなものの中に快適さを示すからである。東洋の民主主義の真の精神を象徴するものであり、すべての支持者を趣味の貴族にするものである。
日本が長い間世界から孤立していたことは、内省に非常に適しており、茶の湯の発展に非常に有利であった。日本の家庭、習慣、衣装、料理、磁器、漆、絵画、そして文学のすべてが、茶の影響を受けてきた。日本文化を学ぶ者なら、その存在を無視することはできないだろう。それは高貴な寝室の優雅さに浸透し、謙虚な人の住まいにも入り込んでいる。農民は花を生けることを学び、最も卑しい労働者は岩や水に敬意を捧げることを学んだ。私たちの一般的な言い回しでは、個人的なドラマのシリアスな喜劇的興味に鈍感な人のことを「お茶のない」人と呼ぶ。また、俗世間の悲劇に関係なく、解放された感情の春潮の中で暴れまわる未開の美学者を、私たちは「お茶が多すぎる」人間だと非難する。
部外者は確かに、この何でもないような大騒ぎを不思議に思うかもしれない。茶碗の中の大騒動だ!」と言うだろう。しかし、人間の楽しみのコップがいかに小さく、いかにすぐに涙であふれ、いかに簡単に無限の渇きで飲み干されてしまうかを考えれば、ティーカップで大騒ぎする自分を責めることはないだろう。人類はもっと悪いことをしてきた。バッカスを崇拝するあまり、私たちはあまりにも自由に生贄を捧げてきた。カメリアの女王に身を捧げ、彼女の祭壇から流れ出る温かい同情の流れに酔いしれるのはどうだろう。象牙磁器の中の琥珀色の液体の中で、入門者は孔子の甘い寡黙さ、老子の辛味、釈迦牟尼自身の幽玄な香りに触れることができる。
自分の中にある偉大なものの小ささを感じられない人は、他人の中にある小さなものの偉大さを見落としがちである。平均的な西洋人は、そのなめらかな自己満足の中で、茶道の中に、東洋の古風さと幼稚さを構成する千差万別の奇妙さのもうひとつの例を見るだけだろう。彼は、日本が穏やかな平和の術に耽っている間は野蛮だと見なすのが常であったが、満州の戦場で大規模な殺戮を行うようになってからは文明的だと言う。最近、武士の掟、つまり兵士たちに自己犠牲を歓喜させる「死の芸術」については多くの論評がなされているが、われわれの「生の芸術」の多くを代表する「茶道」についてはほとんど注目されていない。もしわれわれの文明化の主張が戦争の陰惨な栄光に基づくものであるなら、われわれは野蛮人のままでいたいと思うだろう。我々の芸術と理想に正当な敬意が払われる時が来るのを待ちたい。
西洋が東洋を理解し、理解しようとするのはいつのことだろうか。私たちアジア人は、私たちに関する事実と空想が織り成す不思議な網にしばしば愕然とさせられる。ネズミやゴキブリはともかく、私たちは蓮の香水で生きているように描かれている。無気力な狂信か、あるいは絶望的な耽溺である。インドの精神性は無知と揶揄され、中国の節制は愚かさと揶揄され、日本の愛国心は宿命論の結果と揶揄されてきた。私たちが痛みや傷に対して鈍感なのは、神経組織が無慈悲だからだと言われてきた!
私たちの費用で、あなたたちを楽しませたらどうですか?アジアは賛辞を返す。もし私たちがあなたについて想像し、書いたことをすべて知ったら、もっと楽しいことがあるでしょう。そこにあるのは、遠近法の魅力、驚嘆の無意識の賛辞、新しく未確定なものへの無言の憤りなど、すべてだ。あなたには、うらやましがられるにはあまりに洗練された美徳があり、非難されるにはあまりに絵に描いたような罪がある。かつての文豪たちは、あなたたちの尻尾は衣服のどこかに隠されていて、生まれたばかりの赤ん坊のフリカッセをよく食べていたと教えてくれた!いや、私たちはもっと悪いことに、あなた方をこの世で最も非現実的な人間だと考えていた。
そのような誤解は、私たちの間では急速に消えつつある。商業は、東洋の港の多くにヨーロッパの舌を押し付けている。アジアの若者たちは、近代教育の設備を求めて西洋の大学に集まっている。私たちの見識はあなた方の文化を深く理解することはできないが、少なくとも私たちは学ぼうとしている。私の同胞の中には、あなた方の習慣やエチケットを取り入れすぎて、堅苦しい襟や背の高いシルクハットを身につけることがあなた方の文明に到達することだと錯覚している者もいる。そのような気取った態度は、哀れで嘆かわしいものではあるが、私たちが西洋にひざまずいて近づこうとする意思の表れである。残念ながら、西洋の態度は東洋を理解する上で好ましくない。キリスト教の宣教師は、教えるために行くのであって、受け取るために行くのではない。あなたの情報は、私たちの膨大な文献のわずかな翻訳、あるいは通りすがりの旅行者の信頼できない逸話に基づいている。ラフカディオ・ハーンや "The Web of Indian Life "の著者の騎士道精神にあふれた筆が、東洋の暗闇を私たち自身の感情のたいまつで照らしてくれることはめったにない。
おそらく、これほど率直に言うことで、ティーカルトに対する自分の無知を裏切っているのだろう。カルトの礼儀正しさの精神は、期待されていることを言うことであり、それ以上のことは言わないことである。しかし、私は礼儀正しい茶道家になるつもりはない。新世界と旧世界の相互誤解によって、すでに多くの害がもたらされている。20世紀初頭、ロシアが日本をもっとよく知るよう斟酌していれば、悲惨な戦争の光景を目にすることはなかっただろう。東洋の問題を軽んじて無視することは、人類にどんな悲惨な結果をもたらすだろう!ヨーロッパ帝国主義は、黄禍という不条理な叫びを上げることを蔑ろにしないが、アジアもまた白禍という残酷な感覚に目覚める可能性があることに気づいていない。あなた方は私たちを「お茶の飲み過ぎ」だと笑うかもしれないが、西側のあなた方の体質には「お茶がない」のではないかと疑ってはならないだろうか。
大陸同士が互いに卑語を浴びせるのをやめ、半球の相互利益によって賢くなることはないにしても、より悲しくなろう。我々は異なる路線で発展してきたが、一方が他方を補完しない理由はない。あなた方は、落ち着きのなさを代償に膨張を手に入れた。私たちは、侵略に弱い調和を作り上げたのだ。東洋の方が西洋よりも恵まれている面もある!
不思議なことに、人類はこれまで茶碗で出会ってきた。アジアで唯一、万人の尊敬を集める儀式である。白人は私たちの宗教や道徳を嘲笑してきたが、茶色の飲み物は躊躇なく受け入れてきた。アフタヌーンティーは今や西洋社会の重要な行事である。トレイとソーサーの繊細な音、女性らしいもてなしの柔らかなざわめき、クリームと砂糖についての一般的なカテキズムの中に、紅茶の崇拝が疑問の余地なく確立されていることがわかる。怪しげな煎じ薬に待ち受ける運命に対する客の哲学的な諦観は、この一例において東洋の精神が最高位に君臨していることを宣言している。
ヨーロッパの文献における茶の最古の記録は、あるアラビアの旅行者の記述にあると言われている。879年以降、広東の主な収入源は塩と茶の関税であった。マルコ・ポーロは、1285年に中国の大蔵大臣が茶税を恣意的に増額したために退陣させられたことを記録している。ヨーロッパの人々が東洋の極地について知るようになったのは、大航海時代のことである。16世紀末、オランダ人が、東洋では灌木の葉から心地よい飲み物が作られているという知らせをもたらした。ジョヴァンニ・バティスタ・ラムージオ(1559年)、L.アルメイダ(1576年)、マフェーノ(1588年)、タレイラ(1610年)らも茶について言及している。この年、オランダ東インド会社の船がヨーロッパに初めて茶を持ち込んだ。1636年にはフランスで知られるようになり、1638年にはロシアに渡った。イギリスは1650年にこれを歓迎し、"中国人がチャと呼び、他の国々がテイ、別名ティーと呼ぶ、素晴らしく、すべての医師が承認した中国の飲み物 "と語った。
世の中のあらゆる良いものがそうであるように、紅茶の宣伝も反対を受けた。ヘンリー・サヴィル(1678年)のような異端者は、紅茶を飲むことは不潔な習慣だと非難した。ジョナス・ハンウェイ(Essay on Tea, 1756)は、紅茶を飲むことによって、男性は背筋が伸び、かっこよくなり、女性は美しさを失うようだと述べている。当初はその値段(1ポンド約15、16シリング)から大衆の飲用は禁じられ、「高貴な待遇や接待のための礼装であり、王侯や侯爵に贈られるもの」とされた。しかし、そのような欠点にもかかわらず、紅茶の飲用は驚くべき速さで広まった。18世紀前半のロンドンのコーヒー・ハウスは、アディソンやスティールのような知恵者たちの保養地となり、"一皿の紅茶 "を嗜むようになった。紅茶はやがて生活必需品となり、課税対象となった。現代史において、紅茶がいかに重要な役割を担っているかを思い知らされる。植民地時代のアメリカは、紅茶に課された重税の前に人間の忍耐力が屈するまで、抑圧に耐えていた。アメリカの独立は、ボストン港に茶箱を投げ入れたことに始まる。
紅茶の味には微妙な魅力があり、それが紅茶を魅力的で理想的なものにする。西洋のユーモア作家たちは、自分たちの思想の香りを紅茶の香りと混ぜ合わせるのに時間がかからなかった。紅茶には、ワインのような傲慢さも、コーヒーのような自意識過剰さも、ココアのような無邪気さもない。すでに1711年、『スペクテイター』誌は言う:「したがって、毎朝1時間、お茶とパンとバターのために時間を割いているすべてのきちんとした家庭に、この私の思索を特別に勧めたい。サミュエル・ジョンソンは彼自身の肖像画を描いている。"20年もの間、魅力的な植物の煎じ汁だけで食事を薄めた、堅物で恥知らずの茶飲み。""茶で夜を楽しませ、茶で真夜中を慰め、茶で朝を迎えた。"
チャールズ・ラムは、彼の知る最大の喜びは、善い行いをこっそりと行い、それが偶然に発見されることだと書いている。ティー・イズムとは、美を隠すことでそれを発見する技術であり、あえて明かさないことを示唆する技術である。それは、自分自身を冷静に、しかし徹底的に笑い飛ばす崇高な秘訣であり、ユーモアそのものであり、哲学の微笑みである。たとえばサッカレーや、もちろんシェイクスピアもそうだ。デカダンスの詩人たち(世界はいつデカダンスに陥ったのだろうか)は、唯物論に対する抗議の中で、ある程度、紅茶主義への道を開いた。今日、西洋と東洋が互いに慰め合うことができるのは、不完全なものに対する私たちの控えめな思索なのかもしれない。
道家は、無始の大いなる始まりにおいて、精神と物質が死闘を繰り広げたと伝えている。ついに天の太陽である黄帝が、闇と大地の悪魔である朱亨に勝利した。タイタンは死の苦しみの中、太陽穹窿に頭を打ちつけ、翡翠の青いドームを粉々に砕いた。星々は巣を失い、月は夜の荒々しい裂け目の中をあてもなくさまよった。黄帝は絶望に打ちひしがれ、天界の修復者を探し求めた。その探しも無駄ではなかった。東の海から、角の冠と竜の尾を持ち、炎の鎧に身を包んだ女王ニウカが現れた。彼女は魔法の釜で五色の虹を溶接し、中国の空を再建した。しかし、ニウカは青い大空に2つの小さな隙間を埋めるのを忘れてしまったと伝えられている。こうして愛の二元論が始まった。2つの魂は宇宙空間を転がり、宇宙を完成させるために結合するまで決して休まることはない。誰もが希望と平和の空を新たに築かなければならない。
富と権力をめぐるサイクロペ的な闘争の中で、現代人の天空は確かに砕け散っている。世界はエゴイズムと低俗さの影で手探りしている。知識は悪い良心によって買われ、博愛は実用のために実践されている。東洋と西洋は、発酵の海に翻弄される2匹の竜のように、生命の宝石を取り戻そうと無駄な努力を重ねている。私たちは偉大なるアバターを待っている。その間、お茶を一口飲もう。午後の光が竹を照らし、泉が歓喜に沸き立ち、松のさえずりが釜の中で聞こえる。儚さを夢想し、物事の美しい愚かさに思いを馳せよう。
〜
〜
II.お茶の学校 ( II. The Schools of Tea. ) ← この続きは下記〈リンク①〉で紹介。
〜
〜
〜〜
【参考】
【青空文庫】「茶の本」(The Book of Tea) 英文著者: 岡倉覚三, 翻訳: 村岡博
URL> https://www.aozora.gr.jp/cards/000238/card1276.html
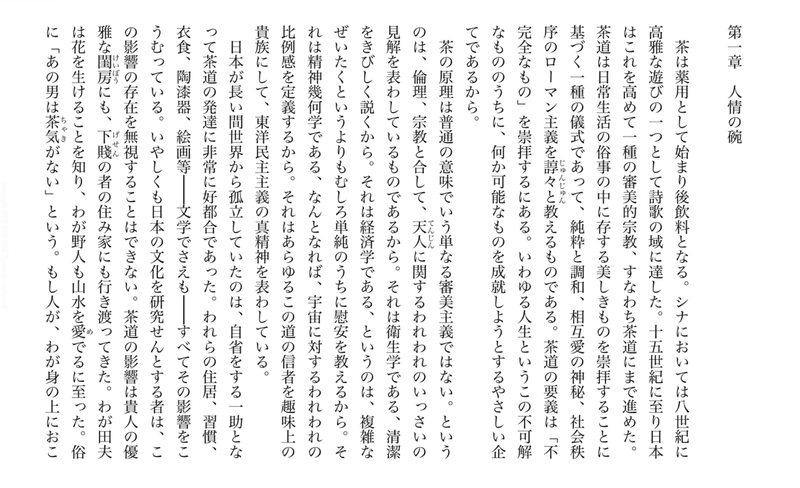
第1章 人情の碗 先頭ページ

第1章 人情の碗 最終ページ
〈リンク①〉
【Project_Gutenberg_200im】「THE BOOK OF TEA」その2【II. The Schools of Tea】
〈リンク②〉
【Project_Gutenberg_200im】「THE BOOK OF TEA」By Kakuzo Okakura 【Contents】
〈リンク③〉
【Charles Lamb】あれこれ →「茶の本」(The Book of Tea) など
・茶の本」(The Book of Tea) の第1章( I. The Cup of Humanity )に出てくる
“Charles Lamb”について、あれこれ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
