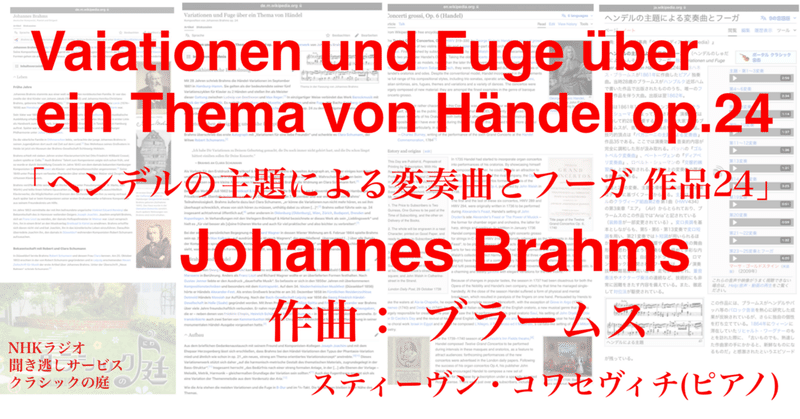
ラジオ生活:クラシックの庭 ブラームス「ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 作品24」
聞き逃しサービス 2024/05/01 放送
クラシックの庭
〜
〜
「ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 作品24」
( Variations and Fugue on a Theme by Handel, Op. 24 )
[ Variationen und Fuge über ein Thema von Händel op. 24 ]
作曲: ブラームス ( Johannes Brahms )
スティーヴン・コワセヴィチ(ピアノ)
(26分41秒)
〜
開始より18分52秒頃 (終了より1時間31分08秒前頃)
〜
〜
配信終了2024/05/08 15:50
(すでに配信終了してます)
番組情報
Google検索 URL>
https://www.google.co.jp/search?tbm=vid&hl=ja&source=hp&biw=&bih=&q=Brahms+Variationen_Thema_von_Händel
Bing検索 URL> https://www.bing.com/videos/search?q=Johannes_Brahms+Variationen_Thema_von_Händel+Op_24
ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 作品24_(ブラームス)
Wikipedia JA(日本版) URL> https://ja.wikipedia.org/wiki/合奏協奏曲集_作品6_(ヘンデル)
〜
『ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ』(ヘンデルのしゅだいによるへんそうきょくとフーガ、独: Variationen und Fuge über ein Thema von Händel)作品24は、ヨハネス・ブラームスが1861年に作曲したピアノ独奏曲。当時28歳のブラームスがハンブルク近郊ハムで書いた作品で出版されたもののうち、唯一のフーガ作品を伴う大曲。出版は翌1862年。
初演は1861年12月7日、ハンブルクにて、クララ・シューマンによって演奏された。演奏時間は平均して約28分を要する。変奏曲の大家であるブラームスが、音楽的内容の頂点をきわめた作品。技巧的頂点は『パガニーニの主題による変奏曲』作品35である。ここでは演奏効果と音楽的内容が完全に調和した形が汲み取れる。バッハの『ゴルトベルク変奏曲』、ベートーヴェンの『ディアベリ変奏曲』、ロベルト・シューマンの『交響的練習曲』と並び称される、音楽史上の変奏曲の歴史を飾る曲である。
ヘンデルによる主題
主題と25の変奏、主題の骨格から形成される簡素なテーマに基づくフーガからなる。主題はヘンデルのクラヴィーア組曲第2巻第1曲(HWV434)の第3楽章「エア」(Air)からとられており、ブラームスのこの作品では“Aria”と記されている(装飾音が一部変更されている)。変ロ長調を基本としながらも、第5・第6・第13変奏で変ロ短調を用い、第21変奏ではト短調が用いられるほか、ハンガリー音楽の影響やバロック音楽の舞曲形式を思わせるような変奏など、極めて多彩な内容を備えている。自由かつドラマティック、ロマンティックに展開されるフーガでは、ピアノ演奏技巧の難易度が高い連句、走句が多用され、重音奏法やオクターヴ奏法の連続など、技術的にも非常に困難をきたす内容を備えている。また、徹底して対位法が駆使されている。
この作品には、ブラームスがヘンデルやバッハ等のバロック音楽を熱心に研究した成果が反映されているが、さらに独自の個性を打ち立てている。1864年にウィーンに滞在していたリヒャルト・ワーグナーのもとを訪れた際に、「古いものでも、熟達した作曲家の手にかかると、新鮮なものになるものだ」と感激されたというエピソードが残っている。
…
〜[上記Wikipediaより抜粋。]
ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 作品24_(ブラームス)
Wikipedia EN(英語版) URL> https://en.m.wikipedia.org/wiki/Variations_and_Fugue_on_a_Theme_by_Handel
〜
The Variations and Fugue on a Theme by Handel, Op. 24, is a work for solo piano written by Johannes Brahms in 1861. It consists of a set of twenty-five variations and a concluding fugue, all based on a theme from George Frideric Handel's Harpsichord Suite No. 1 in B♭ major, HWV 434. They are known as his Handel Variations.
The music writer Donald Tovey has ranked it among "the half-dozen greatest sets of variations ever written". Biographer Jan Swafford describes the Handel Variations as "perhaps the finest set of piano variations since Beethoven", adding, "Besides a masterful unfolding of ideas concluding with an exuberant fugue with a finish designed to bring down the house, the work is quintessentially Brahms in other ways: the filler of traditional forms with fresh energy and imagination; the historical eclectic able to start off with a gallant little tune of Handel's, Baroque ornaments and all, and integrate it seamlessly into his own voice, in a work of massive scope and dazzling variety."
…
【Background】
The Handel Variations were written in September 1861 after Brahms, aged 28, abandoned the work he had been doing as director of the Hamburg women's choir (Frauenchor) and moved out of his family's cramped and shabby apartments in Hamburg to his own apartment in the quiet suburb of Hamm, initiating a highly productive period that produced "a series of early masterworks".[3] Written in a single stretch in September 1861, the work is dedicated to a "beloved friend", Clara Schumann, widow of Robert Schumann. It was presented to her on her 42nd birthday, September 13. At about the same time, his interest in, and mastery of, the piano also shows in his writing two important piano quartets, in G minor and A major. Barely two months later, in November 1861, he produced his second set of Schumann Variations, Op. 23, for piano four hands.
From his earliest years as a composer, the variation was a musical form of great interest to Brahms. Before the Handel Variations he had written a number of other sets of variations, as well as using variations in the slow movement of his Op. 1, the Piano Sonata in C major, and in other chamber works.[4] As he appeared on the scene, variations were in decline, "little more than a basis for writing paraphrases of favorite tunes".[4] In Brahms's work the form once again became restored to greatness.
Brahms had been emulating Baroque models for six years or more.[5] In particular, between the time he wrote his previous Two Sets of Variations for piano, (No. 1, Eleven Variations on an Original Theme, in D major (1857) and No. 2, Fourteen Variations on a Hungarian Melody, in D major (1854)), Op. 21, and the Handel Variations, Op. 24, Brahms did a careful study of "more rigorous, complex and historical models, among others preludes, fugues, canons and the then obscure dance movements of the Baroque period.[6] Two gigues and two sarabandes that Brahms wrote to develop his technique are extant today.[7] The results of these historical studies are seen in his choice of Handel for the theme, as well as his use of Baroque forms, including the Siciliana dance form (Var. 19) from the French school of Couperin and, in general, the frequent use of contrapuntal techniques in many variations.
One aspect of his approach to variation writing is made explicit in a number of letters. "In a theme for a [set of] variations, it is almost only the bass that has any meaning for me. But this is sacred to me, it is the firm foundation on which I then build my stories. What I do with a melody is only playing around ... If I vary only the melody, then I cannot easily be more than clever or graceful, or, indeed, [if] full of feeling, deepen a pretty thought. On the given bass, I invent something actually new, I discover new melodies in it, I create." The role of the bass is critical.
〜…〜
Identifying the bass as the essence of the theme, ...Brahms advocated using it to control the structure and character of individual variations and of the entire set. But by this he apparently did not mean retaining in the variations the bass line of the theme or even its harmonies ... To invent something actually new and to discover new melodies in the bass give the bass a role at once passive and active. While maintaining the structure of the theme—the passive bass, so to speak—Brahms may actively create melodies and figurative patterns (including melodies "discovered in" the bass), project different contrapuntal textures, and draw on an expanded harmonic vocabulary, sometimes interpreting the melody as the bass of the harmony or regarding major and minor or sharp and flat versions of the same passage as equally valid and available. The result is a great diversity of expression and character founded on a relatively strict conception of the "given" material.
〜…〜
Brahms also took into careful account the character of the theme, and its historical context. Unlike the great model of Beethoven's Diabelli Variations, where the variations departed widely from the character of the theme, Brahms's variations expressed and developed the character of the theme. Because the theme for the Handel variations originated in the Baroque era, Brahms included forms such as a siciliana, a musette, a canon and a fugue.
Still not fully established in his career in 1861, Brahms had to struggle to get the work published. He wrote to Breitkopf & Härtel, "I am unwilling, at the first hurdle, to give up my desire to see this, my favourite work, published by you. If therefore, it is primarily the high fee that stops you taking it, I will be happy to let you have it for 12 Friedrichsdors or, if this still seems too high, 10 Friedrichsdors. I very much hope you will not think I plucked the initial fee arbitrarily out of the air. I consider this work to be much better than my earlier ones; I think it is also much better adapted to the demands of performance and will therefore be easier to market ..."
The theme of the Handel Variations is taken from an aria in the third movement of Handel's Harpsichord Suite No. 1 in B♭ Major, HWV 434 (Suites de pièces pour le clavecin, published by J. Walsh, London 1733 with five variations). Brahms himself owned a copy of the 1733 First Edition. The appeal of the aria for Brahms might have been its simplicity: its range is restricted to one octave; the harmony is plain, with every note taken from the B-flat major scale; it "made an admirably neutral starting-place". While Handel had written only five variations on his theme, Brahms, with the piano as his instrument rather than the more limited harpsichord, enlarged the scope of his opus to 25 variations ending with an extended fugue. Brahms's use of Handel exemplifies his love of the music of the past and his tendency to incorporate it and transform it in his own compositions.
Of the overall concept of the work, Malcolm MacDonald writes "Some of Brahms's models in this monumental work are easy enough to identify. In the scale and ambition of his conception both Bach's 'Goldberg' and Beethoven's 'Diabelli Variations' must have exercised a powerful if generalized influence; in specific features of form Beethoven's 'Eroica' Variations is a closer parallel. But the overall structure is original to Brahms." And MacDonald suggests what might have been a more contemporary source of inspiration, the Variations on a Theme of Handel, Op. 26, by Robert Volkmann. "Brahms might well have known that large and often admirable work, published as recently as 1856, which Volkmann based on the so-called 'Harmonious Blacksmith' theme from the Air with Variations in Handel's E major Harpsichord Suite."
…
【Structure】
In Music, Imagination, and Culture Nicholas Cook gives the following concise description:
〜…〜
"The Handel Variations consist of a theme and twenty-five variations, each of equal length, plus a much longer fugue at the end which provides the climax of the movement in terms of duration, dynamics, and contrapuntal complexity. The individual variations are grouped in such a way as to create a series of waves, both in terms of tempo and dynamics, leading to the final fugue, and superimposed on this overall organization are a number of subordinate patterns. Variations in tonic major and minor more or less alternate with each other; only once is there a variation in another key (the twenty-first, which is in the relative minor). Legato variations are usually succeeded by staccato ones; variations whose texture is fragmentary are in general followed by more homophonic ones. ... the organization of the variation set is not so much concentric—with each variation deriving coherence from its relationship to the theme—as edge-related, with each variation being lent significance by its relationship with what comes before and after it, or by the group of variations within which it is located. In other words, what gives unity to the variation set ... is not the theme as such, but rather a network of 'family resemblances', to use Wittgenstein's term, between the different variations."
〜…〜
There are various opinions about the organization of the Handel Variations. Hans Meyer, for example, sees the divisions as nos. 1–8 ('strict'), 9–12 ('free'), 13 ('synthesis'), 14–17 ('strict') and 18–25 ('free'), culminating in the fugue.[15] William Horne emphasizes paired variations: nos. 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 11 and 12, 13 and 14, 23 and 24. This helps him to group the set as 1–8, 9–18, 19–25, with each group ending with a fermata and preceded by one or more variation pairs.[16] John Rink, focusing on Brahms's dynamic markings, writes,
〜…〜
"Brahms takes pains to control the intensity level throughout the twenty-five variations, maintaining a state of flux in the first half, and then keeping the temperature perceptibly low after the peak in Variations 13–15 until the massive 'crescendo' towards the fugue begins in Variation 23. We thus find a sensitivity to motion and momentum that complements—and possibly transcends in importance to the listener—the elegance of structure about which so many authors have (legitimately) enthused.
〜…〜
Unity is maintained, at least in part, by using Handel's key signature of B♭ major throughout most of the set, varied by only a few exceptions in the tonic minor, and by repeating Handel's four-bar/two-part structure, including the repeats, in most of the work.
…
《》The variations
The performer of the audio files in this section is Martha Goldstein.
…
--《》Theme. Aria
Handel's theme is divided into two parts, each four bars in length and each repeated. The elegant aria moves in stately quarter notes in 4/4 time with "a ceremonial character typical of its period". The harmonic progressions are elementary. Every bar except one has one or two decorations. The melody consists of a one-bar figure in the right hand consisting mostly of a trill and a turn; it is repeated in a rising sequence three times followed by a fourth descending repetition; a decorative flourish finishes the first half of the variation, which is then repeated. The left hand plays solid chords in support throughout, three quarter-note chords to each bar setting the pace followed by a rhythmic eighth-note chord leading to the next bar and emphasizing its first beat. The second half follows a similar pattern, varied mainly by alterations to the turns.
…
--《》Variation 2
Minor-key inflections in Variations 2 to 4 increase the distance from Handel and lay the groundwork for Variations 5 and 6, in the tonic minor.
Variation 2 is a subtle piece with a flowing, lilting rhythm. Complexity is added as Brahms uses a favourite technique, found throughout his works, with triple time in one voice—in this case, triplets in the right hand—against duple time in the other. While explicitly recalling the melody of Handel's theme, the chromaticism of this variation adds to the sense of a world beyond the Baroque. In the first half the pattern is of phrases rising on the scale with a crescendo, then falling away in a shorter decrescendo. The second half climbs both in pitch and dynamics to a high climax, again falling away quickly. There is a smooth transition to the next variation.
…
--《》Variation 3
The elegant third variation, marked dolce, moves at a more leisurely pace, providing a sense of calm after two rather busy variations. It also provides a much-needed contrast with the following thunderous variation. Right and left hands alternate and overlap, the left imitating the right in a pattern of three eighth notes. The first note of each group is played staccato, adding to the sense of lightness. The occasional rolled chord adds interest.
…
--《》Variation 4
The fourth variation, marked risoluto, is a showpiece, with sixteenth notes played in octaves in both hands, strong accents (the sforzandos are frequently emphasized by six-note chords) and climaxes that rise a full octave higher than Handel's theme. The charging, syncopated rhythm places the stress on the last sixteenth note of almost every beat. Although no tempo indications are given, this variation is often performed at great speed.
…
--《》Variation 5
After the mighty sounds of the previous variation, the lyrical fifth variation begins quietly. The change of mood is emphasized by a shift to the tonic minor (B♭ minor). This is the first variation in a key different from Handel's. Numerous small crescendos and decrescendos underscore the espressivo marking. The melody moves upward at a measured pace in eighth notes while the left hand accompanies with broken chords in sixteenth notes in contrary motion. The mood is peaceful and tranquil. A pairing between this variation and the following one is created by the use of the tonic minor key signature and contrary motion.
…
--《》Variation 6
Like the preceding variation, this piece is in the tonic minor and features contrary motion, and the motives of the two variations are similar. Marked p sempre with legato phrasing, Variation 6 has a hushed, mysterious tone. The pace is measured, as both hands are written mainly in eighth notes with short sequences of sixteenth notes providing variety. Here Brahms uses counterpoint in the form of a two-part canon in octaves, including inverted canon for several measures in the second half.
…
--《》Variation 7
Echoing the pairing of Variations 5 and 6, the seventh variation is paired with the eighth. Returning to Handel's original B♭ major, Variation 7 is fast, exciting, high-spirited, and fundamentally rhythmic in nature. A sustained drumbeat effect is created by the emphatic repetition of its upper notes and a staccato rhythm throughout all three voices. Because of the repeated upper notes, the focus moves to the inner voices. Numerous accents add further emphasis to the highly rhythmic character of this variation: in some bars in the first half, accents are placed on the last beat of the bar, while in the second half, the accents are yet more numerous, assigned to every beat except the last of each bar. Each half ends in a peak of excitement, marked forte with arpeggios in contrary motion. It leads seamlessly into 8.
…
--《》Variation 8
Variation 8 continues the rhythmic excitement of Variation 7, the left hand beating out, on the same note over and over, the same anapestic rhythm as the preceding variation. After a few bars, the two voices of the right hand are flipped. A fermata at the close provides a moment of silence before 9 begins and signals the end of the first section.
…
--《》Variation 9
Variation 9 slows the pace of the series, with a sense of grandeur as both treble and bass move in stately, ominous octaves. The piece is highly chromatic, and, like several earlier variations, treble and bass are in contrary motion throughout. Each two-bar phrase begins with two exclamatory sf chords, as if sounding an alarm. The variation starts an octave higher than Handel's theme, and its repeated two-bar pattern continually ascends, increasing in tension, until the climax, when it reaches a full two octaves higher than Handel.
…
--《》Variation 10
In contrast to the preceding number, Variation 10 is Allegro energico, fast and exhilarating. Its rather odd effect sounds almost devoid of melody, as the main notes of the theme are scattered among various registers. The first half consists of a series of startling gestures that begin with large, loud chords (f energetico) in the higher registers followed by echoes progressively lower, ending deep in the bass in a series of single notes played pp. The second half rushes to a great climax.
…
--《》Variation 11
After the tension of Variations 7–10, the next two variations are sweet and melodic. Variation 11 uses counterpoint and has a simple, pleasant air with its rock-steady rhythm in the right hand while the left hand simply plays two notes to one. Variations 11 and 12 are another example of the pairing of variations which is so characteristic of the work.
…
--《》Variation 12
The quietness and delicacy of Variation 12 prepares for the return of the dark tonic minor in Variation 13. The left hand is similar to Variation 17, in the same rhythm as the left hand of Handel's theme.
…
--《》Variation 13
Variation 13 returns to the tonic minor in a funereal mood. It is the middle variation of the set and, in the view of Denis Matthews, the emotional centre. Right-hand sixths play against rolled chords in the left, perhaps suggesting muffled drums. For Tovey the lugubrious tone suggests a "kind of Hungarian funeral march", while Malcolm MacDonald sees it as "florid" and "a Hungarian fantasia". Here Brahms abandons the usual repeat signs because each passage that would have been repeated is instead written an octave higher.
Variations 13 and 14, while very different in character, are paired in being fast and exciting and in their use of parallel sixths in the right hand.
…
--《》Variation 14
Variation 14, marked sciolto ("loose") breaks the dark mood of Variation 13 and returns to the original key. With its extended trills and scalar runs in sixths in the right hand against broken octaves in the left hand, it is a virtuoso showpiece. The mood is of great energy, excitement, and high spirits. It leads without a break into the following variation.
Donald Francis Tovey sees a grouping in Variations 14–18, which he describes as "aris[ing] one out of the other in a wonderful decrescendo of tone and crescendo of Romantic beauty".
…
--《》Variation 15
Following without a pause from the previous number, Variation 15, marked forte, is a bravura variation building relentlessly toward an exciting climax. It consists of a one-bar pattern, varied only slightly, of two declamatory chords in eighth notes in the higher registers, followed by lower sixteenth notes that echo Handel's original turns. A prominent upbeat creates syncopated energy. It has been called an étude for Brahms's Piano Concerto No. 2. It breaks the structural mould of Handel's theme by adding one "extra" bar. In Brahms's first autograph, Variations 15 and 16 were positioned in the reverse order.
…
--《》Variation 16
Variation 16 continues from Variation 15 as a "variation of variation",[21] repeating the pattern of two high eighth notes followed by a run of lower sixteenth notes. It also forms another pairing with Variation 17. Baroque contrapuntal techniques appear again in this canon, described by Malcolm MacDonald as "wittier" than the canon of Variation 6.[13] The left hand begins with two descending staccato eighth notes, immediately followed in the opposite hand by the two eighth notes inverted, a full four octaves higher. In each case, a figure in sixteenth notes follows in canonic imitation. The effect is light and exhilarating.
…
--《》Variation 17
In Variation 17, the absence of the sixteenth notes that were so prominent in the preceding two variations gives the impression of a slowing, despite the marking of più mosso. The effect is of gently falling raindrops, with gracefully descending broken chords in the right hand, piano and staccato, repeated throughout the work at various pitches. Each note is played twice, adding to the suggestion of a leisurely pace.
…
--《》Variation 18
Another "variation of a variation", paired with the preceding Variation 17.[21] The accompaniment from the previous variation, which now echoes the melody of the aria, is now syncopated and alternating between the hands, while the "raindrops" are replaced by sweeping arpeggios.
…
--《》Variation 19
This slow, relaxing variation, with its lilting rhythm and 12
8 time, is written in the dance style of a Baroque French siciliana from the school of Couperin (Brahms had edited Couperin's music[22]). It uses chords almost exclusively in the root position, perhaps as another reminiscence of "antique" music. In a technique often used by Brahms, the melodic line is hidden in an inner part. This variation opens a lengthy quiet section which includes nos. 19–22, "not noticeably interrelated".
…
--《》Variation 20
From the outset, Variation 20 builds toward its climax. In contrast to the preceding variation, there is little of the Baroque in it with its chromaticism in both treble and bass and its thick textures (triads in the right hand against octaves in the left hand). Malcolm MacDonald refers to its "organ-loft progressions".
…
--《》Variation 21
Variation 21 moves to the relative minor (G minor). Like Variation 19, the theme is hidden, in this case by merely gracing the main notes of the theme in passing, thereby achieving a sense of lightness. It is another example of Brahms' use of polyrhythms, this time pairing three notes against four.
…
--《》Variation 22
The light mood of the preceding variation continues in Variation 22. Often referred to as the "musical-box" variation because of the regularity of its rhythm, underlined particularly by a drone bass,[13] Variation 22 alludes to the Baroque musette, a soft pastoral air imitating the sound music of a bagpipe, or musette. It remains in the high registers, consistently above Handel's theme, the lowest note being the repeated B♭ of the drone.
The light mood prepares the way for the climactic, concluding section which, in Tovey's words, comes "swarming up energetically out of darkness".
…
--《》Variation 23
At Variation 23 the rise toward a final climax begins. It is clearly paired with the following Variation 24, which continues its pattern but in a more hurried, more urgent manner.
…
--《》Variation 24
In preparation for the climactic final variation, Variation 24 intensifies the excitement, replacing the triplets of Variation 23 with masses of sixteenth notes. Clearly modeled on the preceding, it is another example of Brahms's use of "variation of variation".
…
--《》Variation 25
An exultant showpiece, Variation 25 ends the variations and leads into the concluding fugue. Its strong resemblance to Variation 1 ties the set together, as they both feature a left hand which fills the pauses in the right.
…
《》Fugue
The powerful concluding fugue brings the variation set to a climactic close. Its subject, repeated many times from beginning to end, derives from the opening of Handel's theme. At its most microscopic level, the subject comes solely from the ascending major second from the first two beats in the top voice of Handel's theme. The ascending second is stated twice in sixteenth notes and repeated again a major third higher. This parallels the first measure of Handel's theme, which ascends from B♭ to C to D to E♭. The following melodic line of the second measure resembles the second measure of Handel's theme in general trajectory (Brahms's theme is also strikingly similar to the subject of Fugue VI from Felix Mendelssohn's Six Preludes and Fugues, Op. 35, also in B♭ major). Julian Littlewood observes that the fugue has "a dense contrapuntal argument which recalls Bach more than Handel". Denis Matthews adds that it is "more redolent of one of Bach's great organ fugues than any in The Well-Tempered Clavier, with inversions, augmentation and double counterpoint to match, and a great peroration over a swinging dominant pedal-point". Despite its magnitude, Littlewood suggests, the fugue avoids separation from the rest of the set by its comparable texture. "In this way it systematically creates a web of links between past and present, achieving synthesis rather than quotation or parody." Michael Musgrave in The Music of Brahms writes,
"Brahms brings his subject, derived, like that of the Diabelli fugue, from the theme, into contrapuntal relationships involving diminution, augmentation, stretto, building to the final peroration through a long dominant pedal with two distinct ideas above. But the pianism is an equal part of the conception, and in this, the most complex example of Brahms's virtuoso style, the characteristic spacings in thirds, sixths and wide spans between the hands are employed as never before. Indeed, the pianistic factor serves to create the great contrasts within the fugue, which transcends a traditional fugal movement to create a further set of variations, in which many of the previous textures are recalled in the context of the equally transformed fugal theme."
…
…
〜[Excerpt from Above Wikipedia.]
〜[上記Wikipediaの日本語翻訳は次の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]
〜
ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ」作品24は、ヨハネス・ブラームスが1861年に作曲したピアノ独奏のための作品である。 ヘンデルのチェンバロ組曲第1番変ロ長調HWV434の主題に基づく25の変奏曲とフーガからなる。 ヘンデル変奏曲として知られている。
音楽ライター、ドナルド・トーヴィーは、この作品を「これまでに書かれた変奏曲の中で最も偉大な曲の6分の1」と位置づけている。 伝記作家のヤン・スワフォードは、ヘンデル変奏曲を「おそらくベートーヴェン以来最も優れたピアノ変奏曲のセット」と評し、さらにこう付け加えている: 伝統的な形式に新鮮なエネルギーとイマジネーションを盛り込み、歴史的な折衷主義者であるヘンデルがバロック時代の装飾音などを駆使して作った勇壮な小曲から出発し、それを自分の声とシームレスに融合させることで、巨大なスケールと目もくらむようなバラエティに富んだ作品に仕上げている。"
…
【背景】
ヘンデル変奏曲は、28歳のブラームスがハンブルク女声合唱団(フラウエンチョール)の指揮者としての仕事を放棄し、ハンブルクにあった家族の手狭で粗末なアパートから静かなハム郊外の自分のアパートに引っ越した後の1861年9月に書かれた。 この作品は、彼女の42歳の誕生日、9月13日に贈られた。 ほぼ同時期、シューマンのピアノへの関心と熟達は、ト短調とイ長調の2つの重要なピアノ四重奏曲を書いたことにも表れている。 それからわずか2ヵ月後の1861年11月、シューマンはピアノ連弾のための2曲目のシューマン変奏曲作品23を作曲した。
作曲家としての初期から、変奏曲はブラームスにとって非常に興味深い音楽形式であった。 ヘンデル変奏曲以前にも、彼は変奏曲のセットをいくつか書いており、作品1の緩徐楽章やピアノ・ソナタハ長調、その他の室内楽作品にも変奏曲を使用していた[4]。ブラームスの登場によって、変奏曲は衰退し、「好きな曲のパラフレーズを書くための基礎に過ぎなかった」。
ブラームスは、6年以上前からバロック音楽の模範を模倣していた[5]。特に、ピアノのための2つの変奏曲(第1番『原曲の主題による11の変奏曲』ニ長調(1857年)と第2番『原曲の主題による14の変奏曲』ニ長調(1857年))を作曲するまでの間に、ピアノのための2つの変奏曲を作曲している。 2、ハンガリーの旋律による14の変奏曲、ニ長調(1854年))作品21、ヘンデル変奏曲作品24を作曲したブラームスは、「より厳格で複雑な歴史的モデル、とりわけ前奏曲、フーガ、カノン、バロック時代の当時は無名だった舞曲楽章」を入念に研究した[6]。[このような歴史的研究の成果は、ヘンデルを主題に選んだこと、フランスのクープランのシチリアーナ舞曲形式(Var.19)を含むバロック形式を用いたこと、そして一般的に、多くの変奏曲で対位法的な技法が頻繁に用いられていることに見られる。
変奏曲の作曲に対する彼のアプローチの一面は、多くの手紙の中で明示されている。 「変奏曲の主題において、私にとって意味を持つのはほとんど低音だけである。 しかし、これは私にとって神聖なものであり、私の物語を構築するための確固たる土台なのだ。 私がメロディーを使ってすることは、遊びでしかない......。 旋律だけを変化させるのであれば、巧みさや優美さ以上のものにはなりにくい。 与えられたバスの上で、私は実際に何か新しいものを発明し、その中に新しいメロディーを発見し、創造する" 低音の役割は非常に重要なのです
〜...〜
低音を主題の本質と見なし、ブラームスは、個々の変奏曲やセット全体の構造と性格をコントロールするために低音を使うことを提唱した。 しかしこれは、主題のベースラインやハーモニーを変奏に残すという意味ではないらしい......。 実際に新しい何かを発明し、ベースの中に新しいメロディーを発見することは、ベースに受動的であると同時に能動的な役割を与える。 いわば受動的な低音である主題の構造を維持しながら、ブラームスは積極的に旋律や具象的なパターン(低音で「発見された」旋律を含む)を創作し、さまざまな対位法的なテクスチュアを投影し、和声の語彙を増やし、時には旋律を和声の低音として解釈したり、同じパッセージの長調と短調、嬰と♭のバージョンを同じように有効で利用可能なものとして扱ったりする。 その結果、"与えられた "素材に対する比較的厳格な概念に基づく、表現と性格の大きな多様性が生まれた。
〜...〜
ブラームスはまた、主題の性格とその歴史的背景を注意深く考慮した。 ベートーヴェンのディアベッリ変奏曲のような、主題の性格から大きく逸脱した変奏曲とは異なり、ブラームスの変奏曲は主題の性格を表現し、発展させている。 ヘンデル変奏曲の主題はバロック時代に生まれたものであるため、ブラームスはシチリアーナ、ミュゼット、カノン、フーガといった形式を取り入れた。
1861年当時、ブラームスはまだキャリアを十分に確立しておらず、この作品を出版するのに苦労した。 彼はブライトコプフ&ヘルテル社にこう書いている。「私は、最初のハードルで、私のお気に入りの作品であるこの曲が、あなた方によって出版されるのを見たいという私の望みをあきらめたくはありません。 従って、もしあなたがこの作品を手にされない理由が、主に高額な料金にあるのであれば、私は喜んで12フリードリヒスドルか、それでも高いと思われるのであれば10フリードリヒスドルでお譲りします。 私が初期フィーを恣意的に抜き出したと思わないでいただきたい。 私は、この作品は以前の作品よりもはるかに優れていると考えている。また、演奏の需要にはるかに適合しており、したがって、市場にも出しやすいと思う......"
ヘンデル変奏曲の主題は、ヘンデルのチェンバロ組曲第1番変ロ長調HWV434(Suites de pièces pour le clavecin, published by J. Walsh, London 1733 with five changes)の第3楽章のアリアから採られている。 ブラームス自身、1733年の初版本を所有していた。 ブラームスにとってこのアリアの魅力は、そのシンプルさにあったかもしれない:音域は1オクターブに制限され、和声は平易で、すべての音が変ロ長調の音階から取られ、「見事にニュートラルな出発点となった」。 ヘンデルが主題による変奏曲を5曲しか書かなかったのに対し、ブラームスはチェンバロという限られた楽器ではなくピアノを使い、フーガで終わる変奏曲を25曲に増やした。 ブラームスがヘンデルを使用したことは、彼が過去の音楽を愛し、それを自身の作曲に取り入れ、変容させようとする傾向を例証している。
作品の全体的なコンセプトについて、マルコム・マクドナルドは「この記念碑的な作品におけるブラームスのモデルのいくつかは、特定するのは簡単だ。 バッハの「ゴルトベルク」とベートーヴェンの「ディアベリ変奏曲」は、その構想の規模と野心において、一般化されているとはいえ、強力な影響を与えたに違いない。 しかし、全体的な構造はブラームスのオリジナルである」。 そしてマクドナルドは、より現代的なインスピレーションの源であったかもしれない、ロベルト・ヴォルクマンのヘンデルの主題による変奏曲作品26を提案する。 ブラームスは、ヘンデルのホ長調チェンバロ組曲の「変奏曲付きアリア」の、いわゆる「鍛冶屋の和声」の主題を基にした、1856年に出版された、大規模でしばしば賞賛に値する作品を知っていたかもしれない。
…
【構造】
音楽、想像力、文化』の中で、ニコラス・クックは次のように簡潔に説明している:
〜...〜
「ヘンデルの変奏曲は、主題と25の変奏からなり、それぞれの長さは等しく、さらに最後に、長さ、ダイナミクス、対位法的な複雑さの点でこの楽章のクライマックスとなる、はるかに長いフーガがある。 個々の変奏は、テンポとダイナミクスの両面で、最後のフーガに至る一連の波を作り出すようにグループ化されており、この全体的な構成に、いくつかの従属的なパターンが重ねられている。 トニック・メジャー(長調)とマイナー(短調)による変奏は、多かれ少なかれ交互に繰り返される。 レガート変奏曲は通常、スタッカート変奏曲に引き継がれ、テクスチュアが断片的な変奏曲は一般に、より同音的な変奏曲に引き継がれる。 ...変奏曲セットの構成は、各変奏が主題との関係から一貫性を得ているという同心円的なものではなく、各変奏がその前後の変奏との関係や、その変奏が位置する変奏グループとの関係によって重要性を与えられているという辺縁的なものである。 言い換えれば、変奏曲セットに統一性を与えているのは......主題そのものではなく、ヴィトゲンシュタインの言葉を借りれば、異なる変奏曲間の「家族的類似性」のネットワークなのである。"
〜...〜
ヘンデル変奏曲の構成についてはさまざまな意見がある。 例えばハンス・マイヤーは、第1番から第8番(「厳格」)、第9番から第12番(「自由」)、第13番(「総合」)、第14番から第17番(「厳格」)、第18番から第25番(「自由」)と分割され、フーガでクライマックスを迎えると考えている[15]。ウィリアム・ホーンは、第3番と第4番、第5番と第6番、第7番と第8番、第11番と第12番、第13番と第14番、第23番と第24番という対になった変奏曲を強調している。 このことは、彼がセットを1-8、9-18、19-25のようにグループ分けするのに役立ち、各グループはフェルマータで終わり、その前に1つ以上の変奏曲のペアがある、
〜...〜
ブラームスは25の変奏曲を通して、前半は流動的な状態を維持し、変奏13〜15のピークの後、変奏23でフーガに向かう大規模な「クレッシェンド」が始まるまで、温度を知覚できるほど低く保ち、強度のレベルをコントロールすることに苦心している。 このように、私たちは運動と勢いに対する感受性を見いだすことができる。それは、多くの著者が(正当に)熱狂している構造の優雅さを補完するものであり、聴き手にとって重要であることを超越しているかもしれない。
〜...〜
少なくとも部分的には、ヘンデルの調号である変ロ長調をセットのほとんどで使用し、トニック・マイナーではわずかな例外によって変化させ、ヘンデルの4小節/2部構成を、繰り返しを含めて作品のほとんどで繰り返すことによって、統一性が保たれている。
…
《》バリエーション
このセクションのオーディオファイルの演奏者はマーサ・ゴールドスタインです。
…
--《》テーマ アリア
ヘンデルの主題は2つの部分に分かれており、それぞれ4小節の長さで繰り返される。 この優雅なアリアは、4分の4拍子の堂々とした4分音符で、「この時代の典型的な儀式的性格」を持って動く。 和声進行は初歩的である。 1小節を除くすべての小節に1つか2つの装飾がある。 旋律は、主にトリルと転回からなる右手の1小節の音型からなり、上昇音型が3回繰り返された後、4回目の下降音型が繰り返される。 左手は終始しっかりとした和音を奏で、各小節に4分音符の和音が3つずつ付いてペースを作り、次の小節につながるリズミカルな8分音符の和音で最初の拍を強調する。 後半も同じようなパターンで、主にターンの変化によって変化する。
…
--《》第2変奏
変奏2~4では短調の変奏がヘンデルとの距離を縮め、トニック・マイナーによる変奏5と6の下地を作る。
変奏2は流れるような軽快なリズムの繊細な曲。 ブラームスは、彼の作品全体に見られる、一方の声部では3倍拍子(この場合は右手の3連符)、他方の声部では2倍拍子という好みの技法を用い、複雑さを加えている。 ヘンデルの主題の旋律を明示的に想起させながら、半音階的な変奏がバロックの彼方の世界を感じさせる。 前半はクレッシェンドで上昇し、短いデクレッシェンドで下降する。 後半はピッチもダイナミクスも上昇し、高いクライマックスに達するが、またすぐに落ちる。 次の変奏への移行もスムーズである。
…
--《》第3変奏
ドルチェと記された優雅な第3変奏は、よりゆったりとしたテンポで進み、忙しない2つの変奏の後に落ち着きを与えてくれる。 また、次の雷鳴のような変奏との対比も必要です。 右手と左手が交互に重なり合い、左手は右手を模倣して8分音符を3つ並べる。 各グループの最初の音はスタッカートで演奏され、軽快さを加えている。 時折転がる和音が面白さを添える。
…
--《》第4変奏
リゾルートと記された第4変奏は、両手のオクターヴで奏される16分音符、強いアクセント(スフォルツァンドは頻繁に6分音符の和音で強調される)、ヘンデルの主題より1オクターヴも高く盛り上がるクライマックスなど、見せ場が多い。 シンコペーションのリズムは、ほぼすべての拍の最後の16分音符に重点を置いている。 テンポの指示はないが、この変奏はしばしば猛スピードで演奏される。
…
--《》第5変奏
前の変奏の力強い響きの後、叙情的な第5変奏が静かに始まる。 気分の変化は、トニック・マイナー(変ロ短調)への移行によって強調される。 ヘンデルの調とは異なる調による最初の変奏曲。 小さなクレッシェンドとデクレッシェンドが、エスプレッシーヴォを強調する。 旋律は8分音符でゆったりと上行し、左手は16分音符の砕けた和音で伴奏する。 穏やかで静謐なムードである。 この変奏曲と次の変奏曲は、トニック・マイナーの調号と相反する動きの使用によって対になっている。
…
--《》第6変奏
前の変奏と同様、この曲はトニック・マイナーで、逆行性を特徴とし、2つの変奏の動機も似ている。 レガートなフレージングでp sempreと記された第6変奏は、静謐で神秘的な音色。 両手とも主に8分音符で書かれ、16分音符の短い連続が変化に富んでいるため、テンポはゆったりとしている。 ブラームスはここで、オクターヴの2部カノンの形で対位法を用いている。
…
--《》第7変奏
第5変奏と第6変奏の対にならって、第7変奏は第8変奏と対になっている。 ヘンデルの原曲である変ロ長調に戻った第7変奏は、速く、エキサイティングで、活気に満ちており、基本的にリズミカルである。 上音の強調された反復と3声全体にわたるスタッカートのリズムによって、持続的なドラムビートの効果が生み出される。 上声が繰り返されるため、内声に焦点が移る。 前半のいくつかの小節では、アクセントは小節の最後の拍に置かれ、後半では、アクセントはさらに多く、各小節の最後を除くすべての拍に割り当てられている。 各ハーフは興奮のピークで終わり、アルペッジョが逆に動くフォルテでマークされる。 8へシームレスにつながる。
…
--《》第8変奏
第8変奏では、第7変奏のリズムの興奮が続き、左手は前の変奏と同じアナペスティックのリズムを同じ音で何度も打ち鳴らす。 数小節後、右手の2つの声部が反転する。 最後にフェルマータがあり、第9楽章が始まる前に一瞬の静寂が訪れ、第1部の終わりを告げる。
…
--《》第9変奏
変奏9は、高音も低音も重厚で不吉なオクターヴを刻み、壮大さを感じさせる。 曲は非常に半音階的で、初期のいくつかの変奏曲と同様、高音と低音は終始相反する動きをする。 各2小節のフレーズは、警鐘を鳴らすかのように2つのsf和音で始まる。 ヘンデルの主題より1オクターブ高いところから始まり、2小節のパターンが繰り返され、クライマックスではヘンデルより2オクターブ高くなるまで、絶えず上昇し、緊張感を高めていく。
…
--《》第10変奏
前の番号とは対照的に、第10変奏はアレグロ・エネルジーコで、速く、爽快である。 主題の主音がさまざまな音域に散らばっているため、その奇妙な効果で旋律がほとんどないように聞こえる。 前半は、高音域の大きく派手な和音(f energetico)に始まり、徐々に低くなるエコーが続き、低音部の奥深くでpp.の単音連打で終わる一連の驚くべき身振りで構成される。
…
--《》第11変奏
変奏7~10の緊張感の後、次の2つの変奏は甘美で旋律的である。 第11変奏は対位法を用い、左手が単純に2音対1音を弾くのに対し、右手は揺るぎないリズムを刻み、シンプルで心地よい雰囲気を持つ。 第11変奏と第12変奏は、この作品の特徴である変奏の組み合わせのもう一つの例である。
…
--《》第12変奏
第12変奏の静けさと繊細さは、第13変奏での暗いトニック・マイナーの回帰に備えるものである。 左手は変奏曲17と同様、ヘンデルの主題の左手と同じリズムである。
…
--《》第13変奏
第13変奏は、再びトニック・マイナーに回帰し、悲壮な雰囲気に包まれます。 デニス・マシューズに言わせれば、この変奏はこのセットの中間の変奏であり、感情の中心である。 右手の6分音符が左手の転がる和音と対になっており、おそらくくぐもった太鼓を連想させる。 トヴェイにとっては、この憂鬱な曲調は「ハンガリーの葬送行進曲のようなもの」であり、マルコム・マクドナルドは「華麗」で「ハンガリーのファンタジア」であると見ている。 ここでブラームスは、繰り返されるはずの各パッセージが1オクターブ高く書かれているため、通常の繰り返し記号を放棄している。
第13変奏と第14変奏は、性格は大きく異なるが、速くてエキサイティングであることと、右手に平行6度を用いる点で対をなしている。
…
--《》第14変奏
sciolto(「緩やかな」)と記された第14変奏は、第13変奏の暗いムードを打ち破り、原調に戻る。 左手の壊れたオクターヴに対して、右手の6度のトリルとスカラー・ランが延々と続くこの曲は、ヴィルトゥオーゾ的なショーピースである。 雰囲気は非常にエネルギッシュで、興奮し、意気揚々としている。 それは休むことなく次の変奏につながる。
ドナルド・フランシス・トーヴィーは、変奏曲14~18にグループ性を見出しており、それを彼は「調の素晴らしいデクレッシェンドとロマンティックな美のクレッシェンドで、他の変奏曲から1つずつ生まれている」と表現している。
…
--《》第15変奏
前の番号から間髪入れずに続く、フォルテと記された第15変奏は、エキサイティングなクライマックスに向かって容赦なく盛り上がっていく勇壮な変奏曲である。 高音域の8分音符による2つの宣言的な和音と、ヘンデルの原曲の旋律に呼応する低音部の16分音符からなる1小節のパターンで構成され、わずかに変化している。 顕著なアップビートがシンコペーション的なエネルギーを生み出している。 ブラームスのピアノ協奏曲第2番のためのエチュードと呼ばれている。 ヘンデルの主題の構造的な型にはまらず、1小節追加されている。 ブラームスの最初の自筆譜では、第15変奏と第16変奏は逆の順序で配置されていた。
…
--《》第16変奏
第16変奏は「変奏の変奏」として第15変奏から続き[21]、2つの高い8分音符の後に低い16分音符が続くパターンを繰り返す。 また、第17変奏とも対をなしている。 マルコム・マクドナルドは、変奏6のカノンよりも「機知に富んでいる」と評している[13]。左手は2つの下降するスタッカートの8分音符で始まり、すぐさま反対側の手で4オクターヴ高い2つの8分音符が反転して続く。 いずれの場合も、16分音符による図形がカノン的模倣で続く。 その効果は軽快で爽快である。
…
--《》第17変奏
第17変奏では、前の2つの変奏で目立っていた16分音符がないため、più mossoと記されているにもかかわらず、ゆっくりとした印象を与える。 右手、ピアノ、スタッカートで優雅に下降する破調の和音が、さまざまな音程で作品全体に繰り返され、雨粒が静かに落ちるような効果がある。 各音符は2回演奏され、ゆったりとしたテンポの暗示を加えている。
…
--《》第18変奏
変奏の変奏 "のもう1つで、前の変奏17番と対になっている[21]。前の変奏の伴奏は、今度はアリアの旋律と呼応し、シンコペーションと両手の交替が行われ、"雨粒 "はスウィープ・アルペジオに置き換えられている。
…
--《》第19変奏
このゆったりとした変奏曲は、軽快なリズムと12
クープラン(ブラームスはクープランの曲を編曲している[22])の流派に属するバロック期のフランスのシチリアーナの舞曲風に書かれている。 ほとんどルート・ポジションの和音しか使われていないが、これも "古風な "音楽を彷彿とさせる。 ブラームスがしばしば用いた技法で、旋律線は内側の部分に隠されている。 この変奏曲は、第19番から第22番を含む長い静寂の部分の冒頭を飾る。
…
--《》第20変奏
第20変奏は冒頭からクライマックスに向かって盛り上がっていく。 直前の変奏とは対照的に、高音と低音の半音階的な響きや厚いテクスチュア(左手のオクターヴに対して右手の3連符)など、バロック的な要素はほとんど見られない。 マルコム・マクドナルドはその「オルガン・ロフト進行」に言及している。
…
--《》第21変奏
第21変奏は相対短調(ト短調)に移る。 第19変奏と同様、主題は隠されており、この場合は主題の主音をかすかにかすめるだけで、軽快さを実現している。 ブラームスがポリリズムを用いたもうひとつの例で、今回は4つの音符に対して3つの音符が対になっている。
…
--《》第22変奏
第22変奏では、前の変奏の軽快な雰囲気が続く。 特にドローンベースによって強調されたリズムの規則性から、しばしば「オルゴール」変奏曲と呼ばれる[13]。 ヘンデルの主題を一貫して上回る高音域にとどまり、最低音はドローンのB♭の繰り返しである。
この軽やかなムードは、トーヴィーの言葉を借りれば、「暗闇からエネルギッシュに押し寄せてくる」クライマックスの終結部への道を開く。
…
--《》第23変奏
変奏23では、最後のクライマックスに向けた上昇が始まる。 これは次の変奏24と明らかに対になっており、この変奏はそのパターンを引き継いでいるが、より急ぎ、より切迫した方法である。
…
--《》第24変奏
クライマックスとなる最終変奏に備え、変奏24では、変奏23の3連符を16分音符の塊に置き換えて、興奮を強めている。 明らかに前者をモデルにしており、ブラームスが「変奏の変奏」を用いたもうひとつの例である。
…
--《》第25変奏
高揚感に満ちた見せ場である第25変奏は、変奏曲を終え、終結のフーガへと導く。 変奏1との強い類似性は、右手の間を埋める左手を特徴とするこのセットを結びつけている。
…
《》フーガ
力強く終結するフーガは、変奏曲セットをクライマックスへと導く。 その主題は、最初から最後まで何度も繰り返されるが、ヘンデルの主題の冒頭に由来する。 最も微視的なレベルでは、主題はヘンデルの主題の上声の最初の2拍から、上行する長調の第2音のみに由来する。 上行第2音は16分音符で2回述べられ、長3度高い音で再び繰り返される。 ヘンデルの主題の第1小節と類似しており、B♭→C→D→E♭と上昇する。 第2小節に続く旋律線は、ヘンデルの主題の第2小節に全体的な軌跡が似ている(ブラームスの主題は、フェリックス・メンデルスゾーンの『6つの前奏曲とフーガ』作品35(同じく変ロ長調)のフーガVIの主題にも酷似している)。 ジュリアン・リトルウッドは、このフーガは「ヘンデルよりもバッハを想起させる緻密な対位法的議論」を持っていると述べている。 デニス・マシューズは、この曲は「『平均律クラヴィーア曲集』のどの曲よりも、バッハの偉大なオルガン・フーガのひとつを思わせる。 リトルウッドによれば、このフーガは、その大きさにもかかわらず、同じようなテクスチュアを持つことで、セットの他の部分との分離を避けている。 "このようにして、この曲は過去と現在をつなぐ網の目を体系的に作り出し、引用やパロディというよりもむしろ総合を達成している。" ミヒャエル・マスグレーヴは『ブラームスの音楽』の中でこう書いている、
「ブラームスは、ディアベリのフーガと同じように、主題から派生した主題を、減衰、増大、ストレットを含む対位法的な関係に持ち込み、2つの異なるアイデアを上部に持つ長いドミナント・ペダルを介して最後のペロラシオンへと構築する。 ブラームスのヴィルトゥオーゾ・スタイルの最も複雑な例であるこの曲では、3分の3拍子、6分の6拍子、両手の間の広いスパンといった特徴的なスペーシングが、かつてないほど採用されている。 実際、ピアニスティックな要素は、フーガの中で大きなコントラストを生み出すのに役立っている。"フーガは、伝統的なフーガ楽章を超越して、変奏曲のさらなるセットを作り出す。
…
〜
ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 作品24_(ブラームス)
Variationen und Fuge über ein Thema von Händel
Wikipedia DE(ドイツ版) URL> https://de.m.wikipedia.org/wiki/Variationen_und_Fuge_über_ein_Thema_von_Händel
〜
Variationen und Fuge über ein Thema von Händel op. 24 sind ein Klavierwerk von Johannes Brahms.
…
【Musikhistorische Einordnung】
Mit 28 Jahren schrieb Brahms die Händel-Variationen im September 1861 in Hamburg-Hamm. Sie gelten als der bedeutendste seiner fünf Variationszyklen für Klavier zu 2 Händen und stellen ihn als Meister dieser Gattung zwischen Ludwig van Beethoven und Max Reger. In einzigartiger Weise verbindet das Werk Barockmusik mit Musik der Hochromantik. Es enthält ein Siciliano, eine Musette, einen Kanon und eine Fuge. Wie Bachs Goldberg-Variationen, Beethovens Diabelli-Variationen und Schumanns Sinfonische Etüden gehört op. 24 zu den wichtigsten Variationenwerken der Klavierliteratur.
…
【Autographen, Zueignung und frühe Rezeption】
Brahms überschrieb das erste Autograph mit „Variationen für eine liebe Freundin“ und schenkte es Clara Schumann, der Witwe Robert Schumanns.
„Ich habe Dir Variationen zu Deinem Geburtstag gemacht, die Du noch immer nicht gehört hast, und die Du schon längst hättest einüben sollen für Deine Konzerte.“
– Brahms an Clara Schumann
Als Vorlage für den Erstdruck bei Breitkopf & Härtel fertigte Brahms ein zweites Autograph an, wobei er einiges korrigierte und auch manche bereits in das erste Autograph eingetragene Korrekturen übernahm. Wahrscheinlich kamen beim Korrekturlesen weitere kleine Änderungen hinzu. Im Druck ließ Brahms die Widmung an Clara Schumann fort.
Bevor das Werk im Juli 1862 bei Breitkopf & Härtel erschien, stellte Brahms es am 4. November 1861 einem Hamburger Privatkreis vor. Ebenfalls in Hamburg spielte es Clara Schumann am 7. Dezember und war enttäuscht von Brahms’ Teilnahmslosigkeit. Brahms äußerte dazu laut Clara Schumann, „er könne die Variationen nun nicht mehr hören, es sei ihm überhaupt schrecklich, etwas von sich hören zu müssen, unthätig dabei zu sitzen […]“. Brahms selbst führte sein op. 24 insgesamt achtzehnmal öffentlich auf, unter anderem in Oldenburg (Oldenburg), Wien, Zürich, Budapest, Dresden und Kopenhagen. In Verhandlungen mit den Verlegern Breitkopf & Härtel bezeichnete er dieses Werk als sein „Lieblingswerk“ und hielt es „für viel besser als [s]eine früheren Werke und auch für viel praktischer und also leichter zu verbreiten“.
Bei der einzigen persönlichen Begegnung mit Richard Wagner in dessen Wiener Wohnung am 6. Februar 1864 spielte Brahms sein op. 24 nach Max Kalbeck „auf ausdrücklichen Wunsch Wagners“, der anschließend „überzeugend […] über alle Details der Komposition sprach“, „den jungen Komponisten mit Anerkennung überschüttete“ und mit den Worten schloss: „Man sieht, was sich in den alten Formen noch leisten läßt, wenn einer kommt, der versteht sie zu behandeln.“
…
【Brahms und Händel】
Mit Werken von Georg Friedrich Händel kam Brahms wohl schon als Schüler Otto Friedrich Willibald Cossels und Eduard Marxsens in Berührung. Anders als Franz Liszt und Richard Wagner wollte er an überlieferten Formen festhalten. Nach Gustav Jenner liebte er den Ausdruck „dauerhafte Musik“. So befasste er sich in den 1850er Jahren mit überkommenen Kompositionstechniken und besonders mit dem Kontrapunkt. Auf dem 34. Niederrheinischen Musikfest (Düsseldorf 1856) hörte er Händels Alexander-Fest. Als erstes Großwerk brachte er am 30. Dezember 1858 im Fürstlichen Residenzschloss Detmold Händels Messiah zur Aufführung. Nach der Bach-Gesellschaft Leipzig war 1856 die Georg Friedrich Händel-Gesellschaft in Halle (Saale) gegründet worden. Mit ihren Protagonisten Philipp Spitta und Friedrich Chrysander war Brahms über viele Jahre freundschaftlich verbunden. Er nahm regen Anteil am Entstehen von Bachs und Händels Gesamtausgaben, die er – neben denen von Frédéric Chopin, Heinrich Schütz und Robert Schumann – in seiner Wiener Bibliothek sammelte. Er transkribierte auch zwei Serien von Kammerduetten Händels, die Chrysander entdeckt und für die Veröffentlichung in seiner monumentalen Händel-Ausgabe vorgesehen hatte.
…
【Aufbau】
Aus dem brieflichen Gedankenaustausch mit seinem Freund und Komponisten-Kollegen Joseph Joachim und mit dem Ehepaar Herzogenberg lässt sich erschließen, dass Brahms bei den Händel-Variationen den Typus der Phantasie-Variation mied und ähnlich wie schon in op. 21 „ein neues, streng am Thema orientiertes Variationskonzept“ anstrebte. Dieses Variationenwerk stützt sich daher „auf die harmonisch-metrische Gestalt des thematischen Materials, zugrundegelegt in der Bass-Struktur“. Insgesamt herrscht „das Bedürfnis nach einer streng formalen Anlage, in der […] alle Ebenen der Vorlage – Melodik, Metrik, Harmonik – gleichermaßen Grundlage der Variation sein sollten.“ Auch das Fugenthema erweist sich als eine Variation der Themenmelodie aus dem Vordersatz der Aria.
Wie die Aria stehen die meisten Variationen und die Fuge in B-Dur und im 4⁄4-Takt. Die Variationen bleiben in der Nähe des Themas.
…
《》Aria
Als Thema wählte Brahms die Aria der Suite B-Dur aus der 1733 in England als Raubdruck erschienenen 2. Sammlung von Georg Friedrich Händels Suites de pièces pour le clavecin, Händel-Werke-Verzeichnis 434. die in der Suite als Variationsthema dient. Er hatte sie in einem antiquarisch erworbenen Notendruck gefunden. Brahms übernahm die Aria nahezu notengetreu, lediglich statt der Händel’schen Zeichen für Pralltriller setzte er – außer im vierten Takt des Vordersatzes und in der prima volta des Nachsatzes – Trillerzeichen (tr), verwendete statt des Sopranschlüssels den Violinschlüssel, fasste die Begleitstimmen akkordisch zusammen und modifizierte den Schlusstakt geringfügig.
Das Thema besteht nach alter Regel aus zweimal vier Takten, also aus Vorder- und Nachsatz, die jeweils wiederholt werden. Eine im Grunde achtmal wiederholte, leicht abgewandelte Wendung bildet gleichsam eine „Variation im Thema“. Dazu trägt auch der permanente, doch leicht verschieden vorgenommene Wechsel b–a–b in den Unterstimmen des Vordersatzes und im zweiten und dritten Takt des Nachsatzes bei. Die Aria beginnt abtaktig, doch im Folgenden wirkt das zweite Achtel jeder vierten Zählzeit auftaktig. Dadurch und durch die themainternen Variationen hat sie einen gleichzeitig offenen und geschlossenen Charakter.
…
《》Variationen
Bereits auf dem ersten Autograph stellte Brahms die Reihenfolge der Variationen 15 und 16 um. Das zeigt, dass er die einzelnen Variationen in einem Gesamtzusammenhang sah, der – auch durch diese Umstellung – eine sinnvolle Entwicklung vom Thema bis zur Fuge gewährleisten sollte. Deutlich in der Notation dieses Autographs, aber auch des Erstdrucks wirkt der Variationenteil wie ein weitgehend durchgehender, zusammenhängender Notentext, bei dem sich allerdings Gruppierungen abzeichnen. Dafür sorgen innerhalb der Gruppen thematische Bezüge und zur Abgrenzung beispielsweise Fermaten und im ersten Autograph ein gelegentlicher Neubeginn in einer neuen Zeile. Dass die Variationen als ein zusammenhängender Organismus empfunden werden, hat seine Ursache auch im beibehaltenen 4⁄4-Takt, der in der 10. Variation durch Achteltriolen bereits in die Richtung auf die die 4⁄4-Takte vertretenden 12⁄8-Takte der 19., der 23. und der 24. Variation hinweisen. Beibehalten wird demnach ein vereinheitlichendes Vierer-Metrum.
…
--《》Variation I
Die erste Variation wird durch einen Auftakt aus fünf 32tel-Noten in der seconda volta des Themenendes übergangslos mit dem Thema verbunden, an dem sie sich noch stark orientiert: in der Oberstimme am Melodiegerüst, in den Unterstimmen an den Wechselnoten b-a-b und am grundlegenden Bass. Rechte und linke Hand bilden sich komplementär ergänzende durchgehende 16tel im staccato. Betonte Akkorde auf halben Zählzeiten erzeugen synkopische Wirkungen, wodurch die 16tel-Bewegung in den Hintergrund gelangt.
…
--《》Variation II
Die zweite Variation bildet zur ersten, rhythmisch akzentuierten Staccato-Variation einen starken Gegensatz: durchwegs ist legato vorgeschrieben. Durch eine animato auszuführende Überlagerung von Achteln und Achteltriolen sowie durch chromatische Wechselnoten in der vom Melodiegerüst des Themas geprägten Oberstimme und chromatische Gängen in den Unterstimmen verwischen die Konturen. Häufige crescendi und decrescendi innerhalb eines piano unterstützen das Auf und Ab dieser Variation. Übergangslos mündet die zweite Variation in die dritte.
…
--《》Variation III
In der dritten, dolce und p zu spielenden Variation wechseln sich rechte und linke Hand – begleitet von im staccato angetippten Akkorden und Basstönen – mit Vorhalten zum Melodiegerüst des Themas ab. Im Nachsatz wird die schon in der zweiten Variation angedeutete Tendenz zur Mollvariante deutlicher, die dann die 5. und 6. Variation prägt. Auch die 3. Variation geht nahtlos in die nächste über, sichtbar an dem unvollständigen Schlusstakt in der seconda volta, dessen fehlendes Sechzehntel vom Auftakt der 4. Variation ergänzt wird.
…
--《》Variation IV
Im starken Gegensatz zur vorherigen Variation steht die direkt anschließende vierte Variation. Auch sie lebt von einem thematischen Dialog zwischen linker und rechter Hand. Die risoluto und staccato zu spielenden Oktaven sind jeweils dann akkordisch aufgefüllt, wenn sie rhythmische Akzente setzen sollen, besonders wenn sie als abgetrennte sforzato-16tel synkopisch wirken. Im Nachsatz bestätigt sich die schon in vorherigen Variationen vollzogene Hinwendung zur Mollvariante.
…
--《》Variation V und Variation VI
Die fünfte und die sechste Variation stehen in der Tonika-Variante b-Moll und verwenden den die Mollwirkung verstärkenden Neapolitaner. Sie bilden dadurch ein aufeinander bezogenes Paar. Während in der fünften, mit espressivo überschrieben Variation die Melodie des Themas in der Oberstimme, mit kurzen crescendi und Akzenten versehen, verarbeitet wird und die Unterstimme aufgelöste Akkorde dazu spielt, sind die beiden in Oktaven geführten Stimmen im leise, legato und ohne Akzente vorzutragenden, zu Beginn des Nachsatzes in der Umkehrung gesetzten Kanon der sechsten Variation völlig gleichberechtigt. Beide Stimmen zitieren das 16tel-Motiv aus dem ersten Takt des Themas. Eine Fermate auf dem Schlussstrich des letzten Taktes bewirkt eine Zäsur vor dem nächsten Variationenpaar.
…
--《》Variation VII und Variation VIII
Diese beiden ineinander übergehenden, con vivacitá vorzutragenden Variationen werden von einem Rhythmus geprägt, der zwischen daktylischer und anapästischer Wirkung wechselt und im Nachsatz der Aria vorgebildet ist. Während dieser Rhythmus in der siebten Variation alle Stimmen erfasst, dient er in der achten Variationen dazu, den in der Unterstimme liegenden Orgelpunkten auf der Tonika und der Dominante einen ostinaten Rhythmus zu verleihen. Die zwei Oberstimmen der achten Variation sind im doppelten Kontrapunkt komponiert, was dazu führt, dass der Nachsatz der achten Variation auf die doppelte Länge erweitert wird. In beiden Variationen kommen Ausweichungen vor, in der siebten nach d-Moll und Es-Dur, in der achten nach b-Moll und Es-Dur. Zwar entsteht auch nach diesem Variationenpaar durch eine Fermate über dem Schlussstrich eine Zäsur, doch wird durch den unvollständigen letzten Takt auch angezeigt, dass die achte und die mit einem 16tel-Auftakt beginnende neunte Variation zusammengehören.
…
--《》Variation IX
Die neunte Variation, poco sostenuto und legato gespielt, bringt in der in Oktaven fortschreitenden Unterstimme mehrmals über Orgelpunkten auf verschiedenen tonalen Ebenen und unter dem Einsatz des Pedals den Themenkopf aufwärts diatonisch und anschließend in der Umkehrung chromatisch aufgefüllt abwärts. Die oktavierte Oberstimme besteht aus einer chromatischen Tonleiter abwärts, die mit Triolengestalten erweitert wird. Die zweitaktigen Abschnitte beginnen jeweils mit Sforzati auf den 16tel-Auftakten und der folgenden Eins des Taktes und enden nach einem decrescendo auf einer Zwischendominante oder der Tonika des jeweiligen Abschnittes. Bei den letzten zwei Takten führt die Unterstimme in ihrem zweiten Teil nicht abwärts, sondern aufwärts zum oktavierten b′, dem Ende der Tonleiter. Die tonalen Ebenen sind nacheinander B-Dur, D-Dur, B-Dur, D-Dur, F-Dur, B-Dur, Fis-Dur=Ges-Dur und B-Dur. Über dem Schlussakkord steht eine Fermate.
…
--《》Variation X
Forte und energico beginnen die beiden Teile des Vordersatzes, die wie die gesamte Variation von Achtel-Triolen geprägt sind. Linke und rechte Hand setzen im Wechsel die ungefähre Grundgestalt der Themenmelodie zusammen und gelangen dabei in immer tiefere Oktavlagen. Die Dynamik nimmt ab und die beiden Teile enden jeweils pp. Gleichzeitig wird aus dem hellen B-Dur ein dunkles b-Moll. Im weitgehend forte gehaltenen Nachsatz scheint sich b-Moll nach einer Ausweichung nach Ges-Dur durchzusetzen, doch der dynamisch zurückgenommene Schluss bietet keinen vollständig abschließenden Dreiklang, sondern eine ambivalent wirkende leere Quinte. Die dadurch erzeugte Spannung löst sich erst im B-Dur der nächsten Variation.
…
--《》Variation XI und Variation XII
Die elfte und die zwölfte Variationen bilden das nächste Variationen-Paar.
Vom kurzen Vorschlag b′ ausgehend wird im Vordersatz der elften Variation die Grundgestalt des Themenkopfes einmal in B-Dur und einmal in d-Moll mit Achtelnoten umspielt. Der Nachsatz dieser leise gehaltenen, nur im Nachsatz bei einer Stimmverdichtung mit zweistimmigen Nachahmungen über einer chromatisch aufwärts führenden Basslinie crescendierenden Variation ist freier komponiert.
Das dolce der elften Variation wird in der direkt anschließenden zwölften Variation durch ein soave im Pianissimo ersetzt. Wie in vielen vorherigen Variationen wird auch hier die Grundgestalt der Themenmelodie im Vordersatz zwischen linker Hand und rechter Hand aufgeteilt. Die linke Hand spielt sie in ruhigen Vierteln und Achteln, die rechte umspielt sie mit Sechzehntelnoten. Vorhalte und chromatische Durchgänge bestimmen den Vorder- und den Nachsatz, in dem eine Wendung nach b-Moll und der Neapolitanische Sextakkord besondere harmonische Wirkungen erzielen.
…
--《》Variation XIII
Largamente, ma no piú ist die dreizehnte Variation überschrieben. Sie bildet den gewichtig wirkenden Mittelpunkt der Variationenreihe, ist in b-Moll und soll laut und espressivo gespielt werden. Im Vordersatz kann man in der Oberstimme die variierte Grundgestalt der Themenmelodie und in der nachschlagenden Begleitung die Wechselnoten b-a-b der Themenunterstimmen erkennen. Ausweichungen in das parallele Des-Dur verändern den Mollcharakter dieser Variation ein wenig. Die weitgehend in Sexten geführte Oberstimme weist bereits auf die Sexten-Passagen der nächsten Variation hin.
…
--《》Variation XIV
Die vierzehnte Variation – wieder zurück in B-Dur – vermittelt zwischen der vorherigen und der nachfolgenden. Von der dreizehnten Variation übernimmt sie die Folgen von Sexten in der rechten Hand und wie die fünfzehnte verarbeitet sie das 16tel-Motiv aus dem ersten Takt der Aria. Die gesamte Variation lehnt sich stark an das Thema an, besonders augenfällig im ersten Teil des Nachsatzes. Schwungvoll, in freiem Vortrag (sciolto), mit einigen antreibenden forte-Bezeichnungen, Sforzati und Akzenten versehen mündet sie direkt in die nächste Variation ein.
…
--《》Variation XV und Variation XVI
Ursprünglich waren diese beiden Variationen in umgekehrter Reihenfolge vorgesehen, doch Brahms stellte die Reihenfolge bereits auf dem ersten Autograph um.[4] Der Grund dafür ist unbekannt. Beide Variationen können als Variationenpaar gesehen werden, was nicht zwingend so ist, da sie durch eine Fermate getrennt werden und die sechzehnte Variation direkt mit der siebzehnten verbunden ist. Sie verwenden das 16tel-Motiv aus dem ersten Takt der Aria, das auch die sechste und die vorangehende vierzehnte Variation kennzeichnet.
Die fünfzehnte Variation ist homophon gesetzt. Im Vordersatz wird die Unterstimme des mit Hornquinten versehenen 16tel-Motivs nach unten oktaviert und entspricht damit dem vorgeschriebenen forte. Im Nachsatz weicht Brahms wie schon in anderen Variationen nach b-Moll aus. Für die gesamte Variationenfolge einzigartig ist, dass diese Variation auf fünfzehn Takte ausgeweitet wurde.
Die piano gehaltene sechzehnte Variation ist polyphon. Das 16tel-Motiv wird etwas variiert und zweistimmig mit enggeführten Nachahmungen verarbeitet. Die kontrapunktierenden Achtel sollen staccato und marcato gespielt werden. Dieser Variation folgt nahtlos die nächste.
…
--《》Variation XVII
In der insgesamt leisen, più mosso überschriebenen siebzehnten Variation werden die abwärts gerichteten Staccato-Achtel der Ober- und der Unterstimme der vorherigen Variation weitergeführt. Sie bilden den Rahmen für eine mit legato und einem kurzen An- und Abschwellen ausdrucksstark gestaltete, zweistimmige Mittelstimme. Diese Mittelstimme ist der Melodieträger und orientiert sich an der Grundgestalt der Themenmelodie. Im Nachsatz berührt die Variation b-Moll und Des-Dur sowie vom Pedal unterstützt Es-Dur und endet in der Haupttonart B-dur.
…
--《》Variation XVIII
Die achtzehnte Variation wird durch eine Fermate von der vorherigen abgetrennt, obwohl sich beide Variationen im Wesentlichen ähneln. Linke und rechte Hand teilen sich die auch hier zweistimmig gesetzte, aber synkopische, mit portato und legato differenziert bezeichnete, variierte Themenmelodie auf. Vom Pedal unterstützt wird sie von meist abwärts gerichteten zerlegten Akkorden umrankt. Auch die achtzehnte Variation durcheilt im Nachsatz b-Moll, Des-Dur und es-Moll/Es-Dur und endet in der Haupttonart.
…
--《》Variation XIX
Die Bezeichnung dieser Variation lautete im ersten Autograph zunächst molto vivace und wurde dann in vivace e leggiero und im Druck schließlich in leggiero e vivace umgeändert. Alle drei Bezeichnungen verhindern, dass sich das Metrum aus viermal drei Achteln in ein gemächliches Dreiermetrum aus je vier Dreiachteltakten auflöst. So entsteht ein heiteres Siciliano, das mit den Pralltrillern einen barockisierenden Charakter annimmt. Die Töne der Themengrundgestalt werden auf Unter- und Mittelstimmen verteilt, was durch das Hervortreten der mit Punktierungen und Prallern versehenen Stimmen verunklart wird. Der Vordersatz wird eine Oktave höher wiederholt, wobei die Punktierungen und Praller in die Oberstimme gelangen. Beim Nachsatz wird die Wiederholung wegen des unterschiedlichen Auftaktes und der auch hier bei der Wiederholung in die Oberstimme verlagerten Punktierungen und Pralltriller ausgeschrieben. Dem letzten Takt fehlt ein Achtel, das sich im Auftakt der nächsten Variation finden lässt.
…
--《》Variation XX
Obwohl durch den Achtel-Auftakt mit der vorherigen Variation verbunden, zeigen die beiden Variationen nur eine Gemeinsamkeit: Der Vordersatz wird eine Oktave höher wiederholt, was diesmal auch im Nachsatz geschieht. Sonst bietet die chromatisch angelegte zwanzigste Variation insgesamt einen starken Gegensatz zur harmonisch einfachen neunzehnten.
In der Oberstimme wird die diatonische Grundgestalt der Themenmelodie chromatisch aufgefüllt. In der zweiten Hälfte des ersten Taktes ergibt sich ein mehrmals verwendetes neues viertöniges Achtel-Motiv, das auch im Nachsatz wieder auftaucht, und dessen Expressivität durch ein dynamisches Anschwellen hin zum dritten Achtel, gefolgt vom sofortigen decrescendo verstärkt wird. Der zunächst in Achteln aufwärts gerichteten Oberstimme entgegen wirkt eine chromatisch abwärts schreitende Bassstimme in Vierteln. Der Nachsatz wird geprägt von zunächst aufwärts, dann abwärts führenden chromatischen Tonleiterabschnitten in der Unterstimme, über denen Zwischendominanten bis hin zum A-Dur-Dreiklang als Dominante von D-Dur und enharmonische Verwechslungen Spannungen aufbauen, die sich schließlich doch im B-Dur-Dreiklang lösen. Die insgesamt leise Variation verlangt ein strenges legato.
…
--《》Variation XXI
Im Gegensatz zur chromatischen zwanzigsten Variation wird die einundzwanzigste ganz von einer schlichten, diatonisch geprägten „Pendelharmonik“ im parallelen g-Moll beherrscht.[18] Außer den Hauptdreiklängen werden nur wenige Zwischendominanten genutzt. Im letzten Takt wird die Mollwirkung durch einen neapolitanischen Sextakkord verstärkt.
Der besondere Reiz der mit piano, dolce und espressivo bezeichneten Variation liegt in der Überlagerung von zerlegten Akkorden, die in der Oberstimme aus Achteltriolen und in der Unterstimme aus regulären Sechzehnteln bestehen. Im ersten Autograph wies Brahms darauf hin, dass die kurzen Vorschläge zu den Triolen einen Pizzicato-Effekt hervorrufen sollen.[4] Zusammen mit dem b′ des ersten Akkordes bilden diese Vorschlagsnoten die Grundgestalt der Themenmelodie nach, so wie sie in B-Dur vorgegeben ist.
…
--《》Variation XXII
Leise, mit Pedaleinsatz, und deutlich hervorgehobenen Tönen eines Borduns aus der Duodezim b-f″ oder an wenigen Stellen des Orgelpunktes auf b bildet die zweiundzwanzigste Variation einen retardierenden Haltepunkt vor den nächsten drei, zur Fuge drängenden Variationen. Sie hat Merkmale einer Musette und ist entsprechend in allen musikalischen Parametern äußerst einfach gehalten. Die Grundmelodie klingt nur an; deren Sechzehntelfigur erscheint in Umkehrung und in Zweiunddreißigsteln in der zweiten Stimme. Die Harmonik des Nachsatzes, dessen Lautstärke vorübergehend zunimmt, erinnert an die des Themennachsatzes. Sofort folgt die dreiundzwanzigste Variation, die den Gedanken des Orgelpunktes in tiefer Lage übernimmt.
…
--《》Variation XXIII und Variation XXIV
Die beiden vivace zu spielenden Variationen bilden ein ineinander übergehendes Variationenpaar mit identischer Form. Sie stehen im 12⁄8-Takt und ähneln dadurch der zehnten Variation, in der die vier Dreiereinheiten eines Taktes allerdings als Triolen notiert sind. Ihre Vordersätze stehen auf einem Orgelpunkt (Variation XXXIII) beziehungsweise auf einer Bordunquinte (Variation XXIV) und pendeln zwischen dem B-Dur-Dreiklang und dem manchmal vollständigen, manchmal unvollständigen verminderten Septakkords a-c-es-ges. Die Nachsätze beginnen mit der Dominante und bringen danach den Quartsextakkord ges-c-es. Kurz darauf wird das ges zum fis enharmonisch umgedeutet, wodurch sich ein chromatisch aufwärts drängender Bass vom Fbis zum B ergibt. Beide Variationen haben nahezu denselben dynamischen Verlauf, der im Ansatz leise ist, immer wieder kurze Crescendi zum forte verlangt und insgesamt von leise nach laut führt.
Im Wesentlichen ist die fünfzehnte Variation eine figurierte vierzehnte Variation. Deren aus Achtelnoten bestehende gebrochenen Akkorde werden teilweise mit 16tel-Noten aufgefüllt. Dadurch entsteht in der fünfzehnten Variation eine stringente durchlaufende 16tel-Bewegung, die ohne eigentliches Ende am Ende mit der Terz ges-b den verkürzten Sextakkord der Mollsubdominante bringt. Ihm folgt ohne Halt das klare B-Dur der letzten Variation.
…
--《》Variation XXV
Fortissimo folgt die fünfunftwanzigste Variation. Die einfache Harmonik entspricht ganz der des Themas. Im Vordersatz stecken in den Akkorden der rechten Hand die Stammnoten der Themenmelodie. Rechte und linke Hand ergänzen sich akkordisch zu durchgehenden, komplementären Sechzehnteln. Nur an betonten Stellen auf der Drei der Takte werden die Akkorde als punktierte Noten ausgehalten, sonst im Staccato als Achtel mit einer Sechzehntelpause von der dazugehörigen Sechzehntelnote abgetrennt.
…
《》Fuga
„Auch das Fugenthema ist eine Variation des Händel-Themas; denn die jeweils ersten Töne der vier Viertel (b, c, d, es) des Fugenthemas entsprechen den bestimmenden Melodietönen des Händelschen Themas. Auch die zuvor in den Variationen verwendete Figur des 3. Viertels im Hauptthema findet sich als 2. Viertel im 2. Takt des Fugenthemas wieder. Die Fuge selbst ist ungewöhnlich klangmächtig, im Aufbau frei, in Einzelheiten jedoch streng. Das Klangmächtige äußert sich unter anderem in den Terz-, Sexten-, Oktaven- und Sext-Oktavengängen sowie in mannigfachen Akkordbrechungen. Die Strenge offenbart sich in der Verwendung von Umkehrungen, Vergrößerungen, Koppelung des Grundmotivs mit seiner Umkehrung, Gleichzeitigkeit mehrerer Motive oder ihrer Umkehrung und so fort. Klangmacht und Satzstrenge führen besonders in der orgelpunktartigen Schlußsteigerung zu großartigen Wirkungen, vor allem dort, wo nach der Vorbereitung (‚Orgelpunkt‘ im hohen f) das tiefe F immer wieder angeschlagen wird, in den Mittelstimmen Motiv und Umkehrung sich verschränken und die Gegenstimme in Oktaven aus der Höhe herabstürzt.“
– Otto Schumann
…
〜[Excerpt from Above Wikipedia.]
〜[上記Wikipediaの日本語翻訳は次の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]
〜
ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 作品24は、ヨハネス・ブラームスのピアノ作品。
…
【音楽史的分類】
ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ作品24は、ヨハネス・ブラームスのピアノ作品である。
「ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ」(Handel Variations and Fugue on Theme by Handel op.24)は、ヨハネス・ブラームスのピアノ作品。 ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 作品24は、ヨハネス・ブラームスのピアノ作品であり、彼の5つの変奏曲の中で最も重要な作品である。 ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 作品24は、ヨハネス・ブラームスのピアノ曲。 シチリアーノ、ミュゼット、カノン、フーガを含む。 バッハのゴルトベルク変奏曲、ベートーヴェンのディアベリ変奏曲、シューマンの交響的エチュードと同様、作品24はピアノ文学の中で最も重要な変奏曲のひとつである。
…
【自筆譜、献呈、初期の受容】
ブラームスは最初の自筆譜に「親愛なる友人のための変奏曲」というタイトルをつけ、ロベルト・シューマンの未亡人クララ・シューマンに贈った。
「あなたの誕生日に変奏曲を作ったが、あなたはまだ聴いていない。
- ブラームスからクララ・シューマンへ
ブライトコプフ&ヘルテル社による初版の見本として、ブラームスは2枚目の自筆譜を作成し、そこでいくつかの点を訂正し、また1枚目の自筆譜にすでに記入されていた訂正のいくつかを採用した。 校正の際、さらに小さな変更が加えられたと思われる。 ブラームスは印刷版ではクララ・シューマンへの献辞を省略している。
1862年7月にブライトコプフ&ヘルテル社から出版される前に、ブラームスは1861年11月4日にハンブルクの私的なサークルにこの作品を贈った。 クララ・シューマンも12月7日にハンブルクでこの曲を演奏したが、ブラームスの関心のなさに失望した。 クララ・シューマンによると、ブラームスは「もはや変奏曲を聴くことはできなかった。 ブラームス自身は、オルデンブルク(オルデンブルク)、ウィーン、チューリヒ、ブダペスト、ドレスデン、コペンハーゲンなど、18回にわたって作品24を公の場で演奏した。 出版社ブライトコプフ&ヘルテルとの交渉の中で、彼はこの作品を「お気に入りの作品」とし、「以前の作品よりもはるかに優れており、また実用的であるため、流通させやすい」と考えた。
1864年2月6日、ウィーンのアパートでリヒャルト・ワーグナーと唯一個人的に面会したブラームスは、「ワーグナーの強い希望で」マックス・カルベックの後に作品24を演奏し、「作曲の細部について説得力のある話をし」、「若い作曲家に賞賛を浴びせ」、最後に「古い形式をどう扱うかを知っている人が現れれば、古い形式でもまだ達成できることがわかるだろう」という言葉で締めくくった。
…
【ブラームスとヘンデル】
ブラームスがゲオルク・フリードリヒ・ハンデルの作品に接したのは、おそらくオットー・フリードリヒ・ウィリバルト・コッセルやエドゥアルド・マルクスセンの弟子としてであろう。 フランツ・リストやリヒャルト・ワーグナーとは異なり、彼は伝統的な形式にこだわりたかった。 グスタフ・ジェンナーによれば、彼は「永続する音楽」という表現を好んだ。 例えば1850年代には、特に伝統的な作曲技法と対位法を学んだ。 第34回ニーダーライン音楽祭(1856年デュッセルドルフ)でヘンデルのアレクサンダー=フェストを聴く。 彼の最初の主要作品はヘンデルの『メサイア』で、1858年12月30日にデトモルトの王宮で演奏された。 ライプツィヒのバッハ協会の後、1856年にはハレ(ザール州)にジョージ・フリデリック・ヘンデル協会が設立された。 ブラームスは、その主人公であるフィリップ・シュピッタやフリードリヒ・クリサンダーと長年にわたって友好関係にあった。 バッハやヘンデルの全集の作成にも積極的に関わり、ショパン、ハインリヒ・シュッツ、ロベルト・シューマンらとともにウィーンの書斎に集めた。 また、クリサンデルが発見したヘンデルの室内二重奏曲の2つのシリーズを、彼の記念碑的なヘンデル版で出版するために書き起こした。
…
【構造】
友人で作曲家仲間のヨーゼフ・ヨアヒムやヘルツォーゲンベルク夫妻との手紙での意見交換から、ブラームスはヘンデル変奏曲のような幻想変奏曲を避け、作品21のように「主題に厳密に方向づけられた新しい変奏曲のコンセプト」を追求したことが推測できる。 そのため、この変奏曲は「低音の構造に基づく、主題的素材の和声的計量形式」に基づいている。 全体として、"旋律、拍子、和声といった原曲のすべてのレベルが等しく変奏の基礎となるような、厳密で形式的な構造が必要である"。 フーガの主題も、アリアの冒頭楽章の主題旋律の変奏であることがわかる。
アリアと同様、変奏曲とフーガのほとんどは変ロ長調で、4分の4拍子である。 変奏曲は主題に近いままである。
…
《》アリア
ブラームスは、1733年にイギリスで海賊版として出版されたヘンデルの組曲第2集『Handel-Werke-Verzeichnis 434』から、組曲の変奏曲の主題として変ロ長調のアリアを選んだ。 変奏曲とフーガはアリアと同様、変ロ長調で4分の4拍子である。 ブラームスは、ヘンデルのトリル記号の代わりにトリル記号(tr)を用いたこと(第1楽章の第4小節と第2楽章のプリマヴォルタを除く)、ソプラノ記号の代わりに高音部記号を用いたこと、伴奏パートを和音的に組み合わせたこと、最終小節を若干変更したことを除けば、アリアをほぼ原曲通りに引き継いだ。
古い規則によれば、主題は4小節の2つのセット、すなわち前奏と後奏からなり、それぞれが繰り返される。 基本的に8回繰り返される、少し手を加えたフレーズが、いわば「主題の変奏」を形成している。 第1楽章の低声部、第2楽章の第2小節と第3小節のb-a-bの永久的だが微妙に異なる交替もこれに寄与している。 アリアはダウンビートで始まるが、4拍ごとの2つ目のクァーバーはアップビートの効果がある。 これと主題内の変奏の結果、この曲は開放的であると同時に閉鎖的な性格を持っている。
…
《》変奏
ブラームスは最初の自筆譜で、すでに第15変奏と第16変奏の順序を変えている。 このことは、彼が個々の変奏を全体的な文脈の中で捉えていたことを示しており、また、この編曲によって、主題からフーガへの意味のある展開が保証されるはずである。 この自筆譜と初版の楽譜を見ると、変奏部は明らかに、ほぼ連続した一貫した楽章のように見える。 グループ内の主題の参照や、例えばフェルマータ、そして最初の自筆譜では、時折新しい行で新たに始まることが、これを確実なものにしている。 変奏曲が首尾一貫した有機体として認識されるのは、第10変奏ですでに、4⁄4小節を表す第19変奏、第23変奏、第24変奏の12⁄8小節の方向を、クオーバーの3連符によって指し示している、4⁄4拍子が維持されていることにもよる。 従って、4拍子という統一的な拍子は維持されている。
…
--《》第1変奏
第1変奏は、主題の終わりのセコンダ・ヴォルタにある5つの32分音符のアップビートによって主題とシームレスに結ばれている。 右手と左手はスタッカートで、相補的で連続的な16分音符を形成する。 半拍で強調された和音がシンコペーションの効果を生み出し、16分音符の動きが背景に消えていく。
…
--《》第2変奏
第2変奏は、リズム的に強調された第1変奏のスタッカートとは強い対照をなす。 輪郭は、クァーヴァーとクァーヴァー3連符のアニマート的な重ね合わせと、主題の旋律構造によって特徴づけられる上声の半音階的な交替音、下声の半音階的なパッセージによってぼやける。 ピアノの中での頻繁なクレッシェンドとデクレッシェンドが、この変奏の起伏を支えている。 第2変奏はシームレスに第3変奏につながる。
…
--《》第3変奏
ドルチェとプで演奏される第3変奏では、右手と左手が交互に--スタッカートのタッピング和音と低音を伴って--主題の旋律構造を保留する。 第2楽章では、第2変奏ですでに示唆されていた短調変奏への傾向がより明確になり、第5変奏と第6変奏を特徴づける。 第3変奏も次の変奏にシームレスに統合され、セコンダ・ヴォルタの不完全な最終小節に見られます。
…
--《》第4変奏
直後の第4変奏は、前の変奏とは対照的である。 また、左手と右手の間の主題的な対話も盛んである。 リゾルートとスタッカートで演奏されるオクターヴは、リズムのアクセントとして意図される場合、特に16分音符の離鍵スフォルツァートとしてシンコペーションの効果を持つ場合、それぞれ和音で埋められる。 エピローグでは、前の変奏ですでに起こった短調変奏への転回が確認される。
…
--《》第5変奏と第6変奏
第5変奏と第6変奏はトニック変ロ短調で、短調の効果を強めるナポリタンが使われている。 このように、両者は関連したペアを形成している。 エスプレッシーヴォと題された第5変奏では、主題の旋律が上声で短いクレッシェンドとアクセントを伴って展開され、下声がそれに合わせて解決された和音を奏するが、第2楽章の冒頭で転回が設定された第6変奏の静かでレガートでアクセントのないカノンでは、オクターヴ上の2つの声部が完全に対等である。 両パートとも主題の第1小節から16分音符のモチーフを引用している。 最終小節のフェルマータは、次の変奏のペアの前にケーズラを作ります。
…
--《》第7変奏と第8変奏
この2つの変奏曲は、ダクティリックとアナペスティックを交互に繰り返すリズムが特徴的で、アリアの第2楽章で先取りされている。 このリズムは第7変奏では全声部をカバーしているが、第8変奏ではトニックとドミナント上の低声部のオルガン・ポイントにオスティナートのリズムを与える役割を果たしている。 第8変奏の2つの上声部は二重対位法で構成されており、第8変奏の終楽章は2倍の長さに延長されている。 第7変奏ではニ短調と変ホ長調に、第8変奏では変ロ短調と変ホ長調に変奏される。 この2つの変奏の後にも、最終小節の上のフェルマータによってケーズラが作られるが、不完全な最終小節は、第8変奏と16分音符のアップビートで始まる第9変奏が一緒になっていることを示している。
…
--《》第9変奏
第9変奏は、ポコ・ソステヌートとレガートで演奏され、オクターヴ進行する下声部において、主題の頭部をダイアトニックに上方へ、異なる音調レベルのオルガン・ポイントを数回にわたって、またペダルを用いて進行させ、その後、半音階的に下方へ転回で満たされる。 オクターヴ進行する上声部は半音階的な下降音型からなり、3連音符で拡張される。 2小節の各セクションは、16分音符の上行音符とその次の1小節のスフォルツァティで始まり、中間ドミナントまたは各セクションのトニックでデクレッシェンドして終わる。 最後の2小節では、下声部の第2部は下降せず、音階の終止点であるオクターヴBb′へと上昇する。 調性は変ロ長調、ニ長調、変ロ長調、ニ長調、ヘ長調、変ロ長調、嬰ヘ長調=変ホ長調、変ロ長調と続く。 最後の和音の上にフェルマータがある。
…
--《》第10変奏
第1楽章の2つのパートはフォルテとエネルジーコで始まり、変奏曲全体と同様、クァーヴァーの3連符が特徴的である。 左手と右手は交互に、主題の旋律のおおよその基本形をまとめながら、オクターヴをどんどん下げていく。 同時に、明るい変ロ長調は暗い変ロ短調になります。 第2楽章の大部分はフォルテで、変ロ短調は変ト長調への逸脱の後、自己を主張するように見えるが、ダイナミックに縮小された終結部では、完全に終結する3連符はなく、むしろ両義的な空虚な5度音で終わる。 その結果生じる緊張は、次の変奏の変ロ長調で初めて解き放たれる。
…
--《》第11変奏と第12変奏
第11変奏と第12変奏は、次の変奏のペアを形成する。
b′の短い暗示から始まり、第11変奏の冒頭楽章では、変ロ長調とニ短調で1度ずつ、クァーヴァーを使って主題の頭の基本形が弾き回される。 この静かに保たれた変奏曲は、第2楽章で半音階的に上昇するバス・ラインの上に2声の模倣がクレッシェンドするだけで、より自由に構成されている。
第11変奏のドルチェは、直後の第12変奏ではピアニッシモのソアヴェに置き換えられる。 これまでの多くの変奏曲と同様、第1楽章では主題旋律の基本形が左手と右手に分かれている。 左手は静かなクロシェットとクァーヴァーで、右手はセミクァーヴァーでその周囲を弾く。 第1楽章と終楽章では、変ロ短調への転回とナポリタン第6和音による特別な和声的効果が達成されている。
…
--《》第13変奏
第13変奏はLargamente, ma no piúと題されている。 一連の変奏曲の重厚な中心をなすこの曲は、変ロ短調であり、大音量でエスプレッシーヴォに演奏されるべきである。 先行楽章では、主題の旋律の変化に富んだ基本形が上声部に、主題の低声部の音符b-a-bが続く伴奏部に認められる。 平行調の変ニ長調に逸脱することで、この変奏曲の短調の性格が少し変わります。 上声の大部分は6分音符で、すでに次の変奏の6番目のパッセージを指し示している。
…
--《》第14変奏
変ロ長調に戻る第14変奏は、前の変奏と次の変奏の間を取り持つ。 第13変奏から、右手の6連符を採用し、第15変奏と同様に、アリアの最初の小節から16分音符のモチーフを使用している。 変奏全体が主題に大きく傾いており、特に第2楽章の最初の部分で顕著である。 躍動感にあふれ、自由な演奏(sciolto)で、いくつかの推進力のあるフォルテ記号、スフォルツァーティ、アクセントを伴って、次の変奏に直接つながる。
…
--《》第15変奏と第16変奏
本来、この2つの変奏曲は逆順で演奏される予定であったが、ブラームスは最初の自筆譜で順序を変更している。 両変奏はフェルマータで区切られ、第16変奏が第17変奏に直結しているため、一対の変奏と見ることもできるが、必ずしもそうではない。 第6変奏とその前の第14変奏の特徴でもある、アリアの第1小節からの16分音符のモチーフが使われている。
第15変奏は同音的に設定されている。 第1楽章では、ホルンの第5音による16分音符のモチーフの下声部がオクターヴ下降しており、規定のフォルテに対応している。 第2楽章では、他の変奏曲と同様に変ロ短調に逸れている。 変奏曲全体としてユニークなのは、この変奏が15小節に拡張されていることである。
ピアノの第16変奏はポリフォニック。 16分音符のモチーフはわずかに変化させられ、2つの声部で密接な模倣を伴って展開される。 対位法のクァーヴァーはスタッカートとマルカートで演奏される。 この変奏に続いて、次の変奏が切れ目なく続く。
…
--《》第17変奏
第17変奏は全体的に静かで、ピウ・モッソ(più mosso)と題され、前の変奏の上下の声部の下向きのスタッカートのクァーヴァが続けられる。 これらは、レガートと短いライズ&フォールを伴う、表現豊かな2声の中声部の骨格を形成します。 この中声部は旋律を担う声部で、主題旋律の基本的な形を志向している。 第2楽章では、変ロ短調、変ニ長調、変ホ長調に触れ、ペダルに支えられながら、変ロ長調の主調で終わる。
…
--《》第18変奏
第18変奏は、前の変奏とフェルマータで区切られているが、両変奏は基本的に類似している。 左手と右手は変化に富んだ主題旋律を共有し、ここでも2つの部分に分かれているが、シンコペーションがあり、ポルタートとレガートで区別されている。 ペダルに支えられ、ほとんど下向きの破調和音に囲まれている。 第18変奏も変ロ短調、変ニ長調、変ホ短調/変ホ長調に分かれ、主調で終わる。
…
--《》第19変奏
この変奏曲は、最初の自筆譜ではmolto vivaceと記されていたが、その後vivace e leggieroに変更され、最終的にleggiero e vivaceに変更された。この3つの表記はいずれも、4度3度という拍子が、それぞれ4度3度というゆったりとした拍子に溶け込むのを防いでいる。 その結果、陽気なシチリアーノとなり、跳ねるトリルによってバロック的な性格を帯びる。 基本的な主題形の音符は下声部と中声部に分散しており、点音や跳躍のある声部が目立つことで不明瞭になっている。 第1楽章は1オクターヴ高く繰り返され、点音と跳躍は上声部で行われる。 最終楽章のリピートは、アップビートが異なることと、リピートの際にドットやバウンス・トリルが上声に移ることから、書き出されている。 最後の小節にはクァーヴァーが欠けているが、これは次の変奏の冒頭に見られる。
…
--《》第20変奏
前の変奏とはクァーヴァーの上拍でつながっているが、この2つの変奏に共通するのは、第1楽章が1オクターヴ高く繰り返され、今度は第2楽章でも起こるという点だけである。 それ以外では、半音階的な第20変奏が、和声的に単純な第19変奏と強い対照をなしている。
上声部では、主題旋律の基本的なダイアトニック形式が半音階的に補われます。 第1小節の後半では、新しい4分音符のクオーバー・モチーフが何度か使われるが、これは第2楽章でも再現され、その表現力は、第3クオーバーに向かってダイナミックに膨らんだ後、すぐにデクレッシェンドすることによって強められる。 第2楽章は、半音階的な下降音型が特徴的です。 第2楽章は、低声部の半音階的な部分によって特徴づけられ、まず上昇し、次に下降する。その上では、ニ長調のドミナントとしてのイ長調のトライアドまでの中間的なドミナントと、エンハーモニックな混乱が緊張を高め、最終的に変ロ長調のトライアドで解決される。 全体的に静かな変奏で、厳格なレガートが要求される。
…
--《》第21変奏
半音階的な第20変奏とは対照的に、第21変奏は平行ト短調の単純なダイアトニック「振り子和声」に完全に支配されている[18]。 最後の小節では、ナポリ第6和音によって短調の効果が強められる。
ピアノ、ドルチェ、エスプレッシーヴォと記された変奏曲の特別な魅力は、上声のクァーヴァー3連音符と下声の規則的な半クァーヴァーからなる分解和音の重ね合わせにある。 ブラームスは最初の自筆譜で、3連符のための短いアポジャトゥーラはピチカート効果を意図したものであると指摘している[4]。第1和音のb′とともに、これらのアポジャトゥーラは変ロ長調で与えられる主題旋律の基本形を形成している。
…
--《》第22変奏
静かに、ペダルの使い方と、b-f″の十二指音、またはbのオルガンポイントの数か所からドローンの音をはっきりと強調して、第22変奏は、フーガに向かって突き進む次の3つの変奏の前に、遅めの停止点を形成する。 この曲はミュゼットの特徴を持ち、それゆえすべての音楽的パラメーターにおいて極めてシンプルに保たれている。 基本旋律は反響するだけで、その半クオーバー音型は転回し、第2声部の30分音符で現れる。 一時的に音量を増す第2楽章の和声は、主題的な第2楽章のそれを思わせる。 これは、低音域のオルガン・ポイントのアイデアを採用した第23変奏に続いている。
…
--《》第23変奏と第24変奏
ヴィヴァーチェで演奏される2つの変奏曲は、同じ形式の変奏曲の対を成し、互いに融合する。 これらは12⁄8拍子であるため、1小節の4つの3連符単位が3連符として表記される第10変奏に似ている。 その前の楽章は、オルガンの点(変奏XXXIII)またはドローン5度(変奏XXIV)に基づいており、変ロ長調の三和音と、時には完全、時には不完全な減七和音a-c-e♭-ge♭の間を揺れ動く。 後置はドミナントで始まり、第4第6和音嬰ト音を持ってくる。 その直後、シャープがエンハーモニックに嬰ヘ音として解釈され、嬰ヘ音から変ロ音へと半音階的に上昇する低音となる。 両変奏とも、冒頭は柔らかく、繰り返し短いクレッシェンドからフォルテが要求され、全体的に柔らかい音から大きな音へと導くという、ほぼ同じダイナミックな進行をしている。
第15変奏は基本的に14分の1拍子である。 四分音符で構成される破調和音は、部分的に16分音符で埋められている。 これにより、第15変奏では16分音符のストリンジェントな動きが連続し、最後にはマイナー・サブドミナントの短縮された第6和音が第3和音Bbでもたらされ、実際の終わりはない。 この後、最後の変奏の変ロ長調が止まることなく続く。
…
--《》第25変奏
第5変奏と第20変奏はフォルティッシモで続く。 シンプルな和声は主題の和声と完全に一致している。 冒頭楽章では、右手の和音に主題の旋律の根音が含まれている。 右手と左手は和音的に補完し合い、連続的で相補的な半過去音を形成する。 和音は、3小節の強調された場所で付点音符として持続されるだけで、それ以外はスタッカートの四分音符で、対応する四分音符とは半休符で区切られている。
…
《》フーガ
"フーガの主題もヘンデルの主題の変奏であり、フーガの主題の4つのクロシェ(b、c、d、e♭)のそれぞれの最初の音は、ヘンデルの主題のドミナント旋律音に対応している。 主テーマの変奏で用いられた第3クロシェットは、フーガのテーマの第2小節でも第2クロシェットとして見られる。 フーガそのものは非常に力強い響きで、構造は自由だが細部は厳格である。 力強い響きは、とりわけ第3、第6、オクターヴ、第6オクターヴの進行や、多様な和音の切れ目に表現されている。 フーガ》のフーガ主題は、ヘンデルのドミナント・メロディック・ノートに対応し、転回、オーギュメンテーション、基本モチーフとその転回との結合、複数のモチーフの同時性やその転回などに厳格さが表れている。 音の力強さと楽章の厳格さは、特にオルガン・ポイントのような最後の激しさ、特に準備(高音Fの「オルガン・ポイント」)の後、低音Fが何度も何度も打ち鳴らされ、中声部でモチーフと転回が絡み合い、対声が高音域からオクターヴで下降するような、壮大な効果をもたらす。"
- オットー・シューマン
…
〜
ブラームス
Johannes Brahms
Wikipedia EN(英語版) URL> https://en.m.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
Wikipedia DE(ドイツ版) URL> https://de.m.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
〜
Johannes Brahms (* 7. Mai 1833 in Hamburg; † 3. April 1897 in Wien) war ein deutscher Komponist, Pianist und Dirigent. Seine Kompositionen werden vorwiegend der Hochromantik zugeordnet; durch die Einbeziehung barocker und klassischer Formen gehen sie aber über diese hinaus. Brahms gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 19. Jahrhunderts.
…
【Werke】
Orchesterwerke
Sinfonien
Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68 (1876)
Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73 (1877)
Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90 (1883)
Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98 (1885)
Instrumentalkonzerte
Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll op. 15 (1859)
Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 83 (1881)
Violinkonzert D-Dur op. 77 (1879)
Doppelkonzert für Violine und Violoncello a-Moll op. 102 (1887)
Andere Orchesterwerke
Serenade Nr. 1 D-Dur op. 11 (1860)
Serenade Nr. 2 A-Dur op. 16 (1860)
Variationen über ein Thema von Haydn op. 56a (1874)
21 Ungarische Tänze (für Klavier, zwei- und vierhändig, Nr. 1, 3 und 10 1874 und 1876 von Brahms orchestriert)
Akademische Festouvertüre c-Moll op. 80 (1880)
Tragische Ouvertüre d-Moll op. 81 (1880)
Klaviermusik
Für zwei Hände
Albumblatt a-Moll o. op. (1853)[46]
Sonate Nr. 1 C-Dur op. 1 (1853)
Sonate Nr. 2 fis-Moll op. 2 (1854)
Scherzo in es-Moll op. 4 (1854)
Sonate Nr. 3 f-Moll op. 5 (1854)
Variationen über ein Thema von Robert Schumann op. 9 (1854)
Gavotte WoO posth. 3 (1854-55)
2 Gigues WoO posth. 4 (1855)
2 Sarabanden WoO posth. 5 (1854-55)
Vier Balladen op. 10 (1856)
Thema und Variationen d-Moll op. 18b (1860), Bearbeitung des 2. Satzes des Streichsextetts Nr. 1 op. 18
Variationen über ein eigenes Thema op. 21/1 (1861)
Variationen über ein ungarisches Lied op. 21/2 (1861)
Variationen und Fuge über ein Thema von Händel op. 24 (1862)
Variationen über ein Thema von Paganini (zwei Hefte) op. 35 (1866)
Sechzehn Walzer op. 39 (1865)[A 7]
10 Ungarische Tänze WoO 1 (1872 Bearbeitung des vierhändigen Originals von 1869, siehe unten)
Acht Klavierstücke op. 76 (1879)
Zwei Rhapsodien op. 79 (1880)
Sieben Fantasien op. 116 (1892)
Drei Intermezzi op. 117 (1892)
Sechs Klavierstücke op. 118 (1893)
Vier Klavierstücke op. 119 (1893)
51 Klavierübungen (1893)
Für die linke Hand allein
Bearbeitung von Johann Sebastian Bachs Chaconne aus der d-Moll-Partita[47]
Für vier Hände
Souvenir de la Russie, WoO
Serenade Nr. 1 op. 11 für Klavier zu vier Händen
Serenade Nr. 2 für Klavier zu vier Händen op. 16 (1875)
21 Ungarische Tänze (1869 und 1880)
Variationen über ein Thema von Schumann in Es-Dur, op. 23 (1863)
16 Walzer, op. 39
18 Liebeslieder (Walzer), op. 52 a
15 Neue Liebeslieder (Walzer), op. 65 a
Für zwei Klaviere
Sonate f-Moll, op. 34b (nach seinem f-Moll-Klavierquintett, op. 34)
Variationen über ein Thema von Joseph Haydn op. 56b (Bearbeitung des op. 56a für Orchester)
Fünf Walzer aus op. 39, Ausgabe für zwei Klaviere zu vier Händen vom Komponisten für Frau Seraphine Tausig bearbeitet
Kammermusik mit Klavier
Autograph des Klaviertrios Nr. 2 C-Dur op. 87 (Fragment)
Klaviertrio A-Dur (vermutlich um 1853, Brahms nur zugeschrieben)
Klaviertrio Nr. 1 H-Dur op. 8 (1854, Neufassung 1891)
Klavierquartett Nr. 1 g-Moll op. 25 (1863)
Klavierquartett Nr. 2 A-Dur op. 26 (1863)
Klavierquintett f-Moll op. 34 (1865)
Sonate für Klavier und Violoncello Nr. 1 e-Moll op. 38 (1865)[3]
Trio für Horn, Violine und Klavier Es-Dur op. 40 (1865)
Klavierquartett Nr. 3 c-Moll op. 60 (1875)
Sonate für Klavier und Violine Nr. 1 G-Dur op. 78 (1879)
Klaviertrio Nr. 2 C-Dur op. 87 (1880)
Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 2 F-Dur op. 99 (1886)
Violinsonate A-Dur op. 100 für Klavier und Violine (1886)
Klaviertrio Nr. 3 c-Moll op. 101 (1887)
Sonate für Klavier und Violine Nr. 3 d-Moll op. 108 (1889)
Klarinettentrio a-Moll op. 114 (1891)
2 Sonaten für Klavier und Klarinette (Viola) f-Moll, Es-Dur op. 120 (1894)[48]
Scherzo c-Moll für Violine und Klavier WoO 2 (1853, aus der FAE-Sonate, einer Gemeinschaftskomposition von Brahms, Schumann und Albert Dietrich)
Kammermusik ohne Klavier
Streichsextett Nr. 1 B-Dur op. 18 (1859/60)
Streichsextett Nr. 2 G-Dur op. 36 (1866)
Streichquartett Nr. 1 c-Moll op. 51/1 (1873)
Streichquartett Nr. 2 a-Moll op. 51/2 (1873)
Streichquartett Nr. 3 B-Dur op. 67 (1876)
Streichquintett Nr. 1 F-Dur op. 88 (1882)
Streichquintett Nr. 2 G-Dur op. 111 (1891)
Klarinettenquintett h-Moll op. 115 (1891)
Orgelwerke
Fuge as-Moll WoO 8
Präludium und Fuge a-Moll WoO 9
Präludium und Fuge g-Moll WoO 10
Choralvorspiel und Fuge über „O Traurigkeit, o Herzeleid“ WoO 7
Elf Choralvorspiele op. posth. 122
Chorwerke
Postillons Morgenlied (~1847/50?) für Männerchor (aufgefunden 2010 im Stadtarchiv Celle). Text: Wilhelm Müller
Die goldenen Brücken (1853) für Männerchor (aufgefunden 2010 im Stadtarchiv Celle). Text: Emanuel Geibel
Missa Canonica op. posth. (1856-, Fragment). Später teilweise in der Motette op. 74,1 verwendet
Ave Maria für Frauenchor und Orchester op. 12 (1860)
Fassung für Frauenchor und Klavier oder Orgel op. 12
Begräbnisgesang op. 13 für Chor und Bläser (1860), Incipit: Nun lasst uns den Leib, auch als Orgelfassung von Karl Michael Komma
Vier Gesänge für Frauenchor mit Begleitung von 2 Hörnern und Harfe op. 17 (1860)
Marienlieder für gemischten Chor op. 22 (1859)
Der 13. Psalm für dreistimmigen Frauenchor mit Begleitung der Orgel oder des Pianoforte op. 27 (1859)
Zwei Motetten op. 29 (1857–1860): „Es ist das Heil uns kommen her“ op. 29,1 und „Schaffe in mir Gott ein rein Herz“ op. 29,2 (Psalm 51, 12–14)
Geistliches Lied op. 30 (1856)
Drei geistliche Chöre für Frauenstimmen ohne Begleitung op. 37 (1859/1863)
Fünf Lieder für vierstimmigen Männerchor op. 41 (1861-62?)
Drei Gesänge für sechsstimmigen Chor a cappella op. 42 (1859–1861), darunter: Vineta op. 42 Nr. 2 (1860) nach einem Gedicht von Wilhelm Müller und Darthulas Grabesgesang op. 42 Nr. 3 nach Ossian
Zwölf Lieder und Romanzen für Frauenchor op. 44
Ein deutsches Requiem op. 45 (1866/67 und 1868 (Satz 5))
Rinaldo op. 50 (1869)
Liebeslieder-Walzer op. 52 (1868) und Neue Liebeslieder op. 65 (1874). Texte: Georg Friedrich Daumer
Rhapsodie für Alt, Männerchor und Orchester über ein Fragment aus Goethes „Harzreise im Winter“ op. 53 (1869)
Schicksalslied op. 54 (1871). Text: Friedrich Hölderlin
Triumphlied op. 55 (1871). Text: aus der Offenbarung des Johannes
Sieben Lieder für gemischten Chor op. 62 (1874)
Zwei Motetten op. 74 (1878): Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen? op. 74,1 und „O Heiland, reiß die Himmel auf“
Nänie op. 82 (1881). Text: Friedrich Schiller
Gesang der Parzen op. 89 (1882). Text: Johann Wolfgang von Goethe
Lieder und Romanzen für vierstimmigen gemischten Chor op. 93a (1883/84)
Tafellied von Joseph von Eichendorff für sechsstimmigen gemischten Chor mit Klavier op. 93b (1884)
Zigeunerlieder op. 103 und 112 für 4 Singstimmen und Klavier
Fünf Gesänge für gemischten Chor a cappella op. 104 (1888)
Fest- und Gedenksprüche a cappella op. 109, „Seiner Magnificenz dem Herrn Bürgermeister Dr. Carl Petersen in Hamburg verehrungsvoll zugeeignet“ (1888)
Drei Motetten op. 110 (1889)
13 Kanons für Frauenstimmen op. 113 (tw. 1863)
14 Volkslieder für gemischten Chor ohne Begleitung WoO 34 (1857–58; 1863–64)
Von edler Art, Mit Lust tät ich ausreiten, Bei nächtlicher Weil, Vom heiligen Märtyrer Emmerano, Täublein weiß, Ach lieber Herre Jesu Christ, Sankt Raphael, In Stiller Nacht, Abschiedslied, Der tote Knabe, Die Wollust in den Maien, Morgengesang, Schnitter Tod, Der englische Jäger
12 Volkslieder für gemischten Chor ohne Begleitung WoO 35 (1863–64)
Scheiden, Wach auf, Erlaube mir, Der Fiedler, Da unten im Tale, Des Abends, Wach auf, Dort in den Weiden, Altes Volkslied, Der Ritter und die Feine, Der Zimmergesell, Altdeutsches Kampflied
Mit Opuszahl
Sechs Gesänge für eine Tenor- oder Sopranstimme und Klavier op. 3. Bettina von Arnim gewidmet. (1852–53)
Liebestreu, Liebe und Frühling I, Liebe und Frühling II, Lied (Weit über das Feld), In der Fremde, Lied (Lindes Rauschen in den Wipfeln)
Sechs Gesänge für eine Tenor- oder Sopranstimme und Klavier op. 6. Luise und Minna Japha gewidmet. (1852–53)
Spanisches Lied, Der Frühling, Nachwirkung, Juchhe!, Wie die Wolke nach der Sonne, Nachtigallen schwingen lustig
Sechs Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 7. Albert Dietrich gewidmet. (1851–53)
Treue Liebe, Parole, Anklänge, Volkslied, Die Trauernde, Heimkehr
Acht Lieder und Romanzen für eine Singstimme und Klavier op. 14 (1858)
Vor dem Fenster, Vom verwundeten Knaben, Murrays Ermordung, Ein Sonett, Trennung, Gang zum Liebsten, Ständchen, Sehnsucht (Mein Schatz ist nicht da)
Vier Gesänge op. 17 (1860)
Es tönt ein voller Harfenklang, Lied von Shakespeare , Der Gärtner, Gesang aus Fingal
Fünf Gedichte für eine Singstimme und Klavier op. 19
Der Kuß, Scheiden und Meiden, In der Ferne, Der Schmied, An eine Aeolsharfe
Drei Duette für Sopran und Alt mit Klavier op. 20
Vier Duette für Alt und Bariton mit Klavier op. 28
Drei Quartette für vier Solostimmen (SATB) mit Klavier op. 31
Neun Lieder und Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 32
Wie rafft ich mich auf in der Nacht, Nicht mehr zu dir zu gehen, Ich schleich umher, Der Strom, der neben mir verrauschte, Wehe, so willst du mich wieder, Du sprichst, daß ich mich täuschte, Bitteres zu sagen denkst du, So stehn wir, ich und meine Weide, Wie bist du, meine Königin
Julius Stockhausen gewidmet. Romanzen aus L. Tieck’s Magelone für eine Singstimme mit Pianoforte. op. 33 (1861–1869).
Keinen hat es noch gereut, Traun! Bogen und Pfeil sind gut für den Feind, Sind es Schmerzen, sind es Freuden, Liebe kam aus fernen Landen, So willst du des Armen, Wie soll ich die Freuden, die Wonne denn tragen?, War es dir, dem diese Lippen bebten, Wir müssen und trennen, geliebtes Saitenspiel, Ruhe, Süßliebchen, im Schatten, Verzweiflung, Wie schnell verschwindet so im Licht als Glanz, Muß es eine Trennung geben, Sulima, Wie froh und frisch mein Sinn sich hebt, Treue Liebe dauert lange[49]
Vier Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 43
Von ewiger Liebe, Die Mainacht, Ich schell mein Horn, Das Lied vom Herrn von Falkenstein
Vier Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 46
Die Kränze, Magyarisch, Die Schale der Vergessenheit, An die Nachtigall
Fünf Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 47
Botschaft, Liebesglut, Sonntag, O liebliche Wangen, Die Liebende schreibt
Sieben Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 48
Der Gang zum Liebchen, Der Überläufer, Liebesklage des Mädchens, Gold überwiegt die Liebe, Trost in Tränen, Vergangen ist mir Glück und Heil, Herbstgefühl
An ein Veilchen. Finales Manuskript
Fünf Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 49
Am Sonntag Morgen, An ein Veilchen, Sehnsucht (Hinter jenen dichten Wäldern), Wiegenlied, Abenddämmerung
Acht Lieder und Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 57
Von waldbekränzter Höhe, Wenn du nur zuweilen lächelst, Es träumte mir, ich sei dir teuer, Ach, wende diesen Blick, In meiner Nächte Sehnen, Strahlt zuweilen auch ein mildes Licht, Die Schnur, die Perl' an Perle, Unbewegte, laue Luft
Acht Lieder und Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 58
Blinde Kuh, Während des Regens, Die Spröde, O komme, holde Sommernacht, Schwermut, In der Gasse, Vorüber, Serenade (Leise, um dich nicht zu wecken)
Acht Lieder und Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 59
Dämmrung senkte sich von oben, Auf dem See (Blauer Himmel, blaue Wogen), Regenlied (Walle, Regen, walle nieder), Nachklang, Agnes, Eine gute, gute Nacht, Mein wundes Herz, Dein blaues Auge
Vier Duette für Sopran und Alt mit Klavier op. 61
Neun Lieder und Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 63
Frühlingstrost, Erinnerung, An ein Bild, An die Tauben, Junge Lieder I, Junge Lieder II, Heimweh I, Heimweh II, Heimweh III
Quartette für vier Solostimmen mit Klavier op. 64
Fünf Duette für Sopran und Alt mit Klavier op. 66
Neun Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 69
Klage I, Klage II, Abschied, Des Liebsten Schwur, Tambourliedchen, Vom Strande, Über die See, Salome, Mädchenfluch
Vier Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 70
Im Garten am Seegestade, Lerchengesang, Serenade (Liebliches Kind, kannst du mir sagen), Abendregen
Fünf Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 71
Es liebt sich so lieblich im Lenze, An den Mond, Geheimnis, Willst du, daß ich geh?, Minnelied
Fünf Gesänge für eine Singstimme und Klavier op. 72
Alte Liebe, Sommerfäden, O kühler Wald, Verzagen, Unüberwindlich
Balladen und Romanzen für zwei Singstimmen mit Klavier op. 75 (1877/78)
Fünf Romanzen und Lieder für eine oder zwei Singstimmen und Klavier op. 84
Sommerabend, Der Kranz, In den Beeren, Vergebliches Ständchen, Spannung
Sechs Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 85
Sommerabend, Mondenschein, Mädchenlied (Ach, und du mein kühles Wasser), Ade!, Frühlingslied, In Waldeinsamkeit
Sechs Lieder für eine tiefere Singstimme und Klavier op. 86
Therese, Feldeinsamkeit, Nachtwandler, Über die Heide, Versunken, Todessehnen
Zwei Gesänge für eine Altstimme mit Bratsche und Klavier op. 91
Quartette für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Klavier op. 92
Fünf Lieder für eine tiefe Singstimme und Klavier op. 94
Mit vierzig Jahren, Steig auf, geliebter Schatten, Mein Herz ist schwer, Sapphische Ode, Kein Haus, keine Heimat
Sieben Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 95
Das Mädchen (Am jüngsten Tag ich aufersteh), Bei dir sind meine Gedanken, Beim Abschied, Der Jäger, Vorschneller Schwur, Mädchenlied, Schön war, das ich dir weihte
Vier Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 96
Der Tod, das ist die kühle Nacht, wir wandelten, Es schauen die Blumen, Meerfahrt
Sechs Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 97
Nachtigall, Auf dem Schiffe, Entführung, Dort in den Weiden, Komm bald, Trennung
Acht Zigeunerlieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung op. 103. Nach dem Ungarischen von Hugo Conrat.
He, Zigeuner, greife in die Saiten, Hochgetürmte Rimaflut, Wißt ihr, wann mein Kindchen, Lieber Gott, du weißt, Brauner Bursche führt zum Tanze, Röslein dreie in der Reihe, Kommt dir manchmal in den Sinn, Rote Abendwolken ziehn
Fünf Lieder für eine tiefere Singstimme und Klavier op. 105
Wie Melodien zieht es mir, Immer leiser wird mein Schlummer, Klage, Auf dem Kirchhofe, Verrat
Fünf Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 106
Ständchen (Der Mond steht über dem Berge), Auf dem See (An dies Schifflein schmiege, holder See), Es hing der Reif, Meine Lieder, Ein Wanderer
Fünf Lieder für eine Singstimme und Klavier op. 107
An die Stolze, Salamander (Text: Karl Lemcke), Das Mädchen spricht, Maienkätzchen, Mädchenlied (Auf die Nacht in der Spinnstub’n)
Quartette für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Klavier op. 112 I Sehnsucht (Text: Franz Kugler) II Nächtens (Text: Franz Kugler) III Vier Zigeunerlieder (Text: Nach dem Ungarischen von Hugo Conrat) Nr. 1: Himmel strahlt so helle und klar, Nr. 2: Rothe Rosenknospen künden schon des Lenzes Triebe, Nr. 3: Brennessel steht an Wegesrand, Nr. 4: Liebe Schwalbe, kleine Schwalbe
Vier ernste Gesänge für eine Baßstimme und Klavier op. 121. Max Klinger gewidmet.
Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh (aus Prediger Salomo, Kap. 3), Ich wandte mich, und sahe an (aus Prediger Salomo, Kap. 4), O Tod, wie bitter bist du (aus Jesus Sirach, Kap. 41), Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen (aus 1. Korinther, Kap. 13)
Ohne Opuszahl
Mondnacht WoO 21
Regenlied (Regentropfen aus den Bäumen fallen) WoO posth. 23
Volkskinderlieder für eine Singstimme und Klavier WoO 31, den Kindern Robert und Clara Schumanns gewidmet
Dornröschen
Die Nachtigall
Der Mann
Sandmännchen
Die Henne
Heidenröslein
Das Schlaraffenland
Beim Ritt auf dem Knie
Der Jäger in dem Walde
Wiegenlied
Das Mädchen und die Hasel
Weihnachten
Marienwürmchen
Dem Schutzengel
Deutsche Volkslieder für eine Singstimme und Klavier WoO 33
Sagt mir, o schönste Schäf'rin mein
Erlaube mir, fein’s Mädchen
Gar lieblich hat sich gesellet
Guten Abend, guten Abend, mein tausiger Schatz
Die Sonne scheint nicht mehr
Da unten im Tale
Gunhilde lebte gar stille und fromm
Ach, englische Schäferin
Es war eine schöne Jüdin
Es ritt ein Ritter
Jungfräulein, soll ich mit euch gehn
Feinsliebchen, du sollst mir nicht barfuß gehn
Wach auf, mein Hort
Maria ging aus wandern
Schwesterlein, Schwesterlein
Wach auf mein' Herzensschöne
Ach Gott, wie weh tut Scheiden
So wünsch ich ihr ein gute Nacht
Nur ein Gesicht auf Erden lebt
Schönster Schatz, mein Engel
Es ging ein Maidlein zarte
Wo gehst du hin, du Stolze?
Der Reiter spreitet seinen Mantel aus
Mir ist ein schön’s braun’s Maidelein
Mein Mädel hat einen Rosenmund
Ach könnt’ ich diesen Abend
Ich stand auf hohem Berge
Es reit’ ein Herr und auch sein Knecht
Es war ein Markgraf über'm Rhein
All' mein' Gedanken
Dort in den Weiden steht ein Haus
So will ich frisch und fröhlich sein
Och Moder, ich well en Ding han
Wie komm ich denn zur Tür herein (We kumm ich dann de Pooz erenn)
Soll sich der Mond nicht heller scheinen
Es wohnet ein Fiedler
Du mein einzig Licht
Des Abends kann ich nicht schlafen geh’n
Schöner Augen schöne Strahlen
Ich weiß mir’n Maidlein
Es steht ein' Lind
In stiller Nacht, zur ersten Wacht
Es stunden drei Rosen
Dem Himmel will ich klagen
Es saß ein schneeweiß Vögelein
Es war einmal ein Zimmergesell
Es ging sich unsre Fraue
Nachtigall, sag, was für Grüß
Verstohlen geht der Mond auf
Briefwechsel
…
〜[Excerpt from Above Wikipedia.]
〜[上記Wikipediaの日本語翻訳は次の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]
〜
Johannes Brahms (* 1833年5月7日 in Hamburg; † 1897年4月3日 in Vienna) はドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。 彼の作品は主にハイ・ロマン派に分類されるが、バロックや古典派の形式を取り入れることで、その枠を超えている。 19世紀を代表する作曲家。
…
【作品】
【管弦楽作品】
《》交響曲
交響曲第1番 ハ短調 作品68 (1876)
交響曲第2番 ニ長調 作品73 (1877)
交響曲第3番 ヘ長調 作品90 (1883)
交響曲第4番 ホ短調 作品98(1885年)
《》器楽協奏曲
ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15 (1859)
ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 作品83(1881年)
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 (1879)
ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 作品102(1887年)
《》その他の管弦楽作品
セレナード第1番 ニ長調 作品11(1860年)
セレナード第2番 イ長調 作品16(1860年)
ハイドンの主題による変奏曲 作品56a(1874年)
21のハンガリー舞曲(ピアノ、2手と4手のための第1番、第3番、第10番、1874年と1876年にブラームスがオーケストレーション)
アカデミック祝祭序曲 ハ短調 作品80 (1880)
悲劇的序曲 ニ短調 作品81 (1880)
【ピアノ曲】
《》両手のための
アルブムブラット イ短調 作品(1853)[46]。
ソナタ第1番 ハ長調 作品1(1853)
ソナタ第2番 嬰ヘ短調 作品2(1854)
スケルツォ 変ホ短調 作品4 (1854)
ソナタ第3番 ヘ短調 作品5 (1854)
ロベルト・シューマンの主題による変奏曲 作品9(1854)
ガヴォット WoO posth.
2つのジーグ WoO posth.4 (1855)
2つのサラバンド WoO posth.
4つのバラード 作品10(1856年)
主題と変奏 ニ短調 作品18b(1860)、弦楽六重奏曲第1番 作品18の第2楽章の編曲
オリジナル主題による変奏曲 作品21/1 (1861)
ハンガリーの歌による変奏曲 作品21/2 (1861)
ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 作品24(1862)
パガニーニの主題による変奏曲(全2巻)op.
16のワルツ 作品39(1865)[A 7]
10のハンガリー舞曲 WoO 1(1869年の4手による原曲を1872年に編曲。)
8つのピアノ曲 作品76(1879年)
つの狂詩曲 作品79(1880年)
7つの幻想曲 op.
3つのインテルメッツィ 作品117 (1892)
6つのピアノ小品 作品118 (1893)
つのピアノ小品 作品119 (1893)
51のピアノ練習曲 (1893)
《》左手だけのための
ヨハン・セバスティアン・バッハのニ短調パルティータよりシャコンヌの編曲[47]。
四手のための
ロシアのお土産 WoO
ピアノ連弾のためのセレナード第1番 作品11
ピアノ連弾のためのセレナード第2番 作品16 (1875)
21のハンガリー舞曲(1869年と1880年)
シューマンの主題による変奏曲 変ホ長調 作品23 (1863)
16 ワルツ 作品39
18の愛の歌(ワルツ) 作品52 a
15の新しい愛の歌(ワルツ) 作品65 a
《》2台ピアノのための
ソナタ ヘ短調 作品34b(ピアノ五重奏曲 ヘ短調 作品34の後)
ヨーゼフ・ハイドンの主題による変奏曲op.56b(op.56aの管弦楽編曲版)
作品39より5つのワルツ、作曲者がセラフィーヌ・タウジッヒ夫人のために編曲した2台ピアノ連弾版
《》ピアノによる室内楽
ピアノ三重奏曲第2番ハ長調op.87の自筆譜(断片)
ピアノ三重奏曲 イ長調(1853年頃と推定されるが、ブラームスの作品とされているのみ)
ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 作品8(1854年、新版1891年)
ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 作品25 (1863)
ピアノ四重奏曲第2番 イ長調 作品26(1863年)
ピアノ五重奏曲 ヘ短調 作品34(1865年)
ピアノとチェロのためのソナタ 第1番 ホ短調 作品38(1865年)[3]
ホルン、ヴァイオリンとピアノのための三重奏曲 変ホ長調 作品40 (1865)
ピアノ四重奏曲第3番 ハ短調 作品60(1875年)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 第1番 ト長調 作品78 (1879)
ピアノ三重奏曲第2番 ハ長調 作品87 (1880)
ヴィオロンチェロとピアノのためのソナタ 第2番 ヘ長調 作品99 (1886)
ヴァイオリン・ソナタ イ長調 作品100(1886年)
ピアノ三重奏曲第3番 ハ短調 作品101(1887年)
ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 第3番 ニ短調 作品108 (1889)
クラリネット三重奏曲 イ短調 作品114(1891)
ピアノとクラリネット(ヴィオラ)のための2つのソナタ ヘ短調、変ホ長調 作品120(1894年)[48]。
ヴァイオリンとピアノのためのスケルツォ ハ短調 WoO 2(1853年、ブラームス、シューマン、アルベルト・ディートリッヒの共同作曲によるFAEソナタより)
【ピアノのない室内楽曲】
弦楽六重奏曲第1番 変ロ長調 作品18(1859/60)
弦楽六重奏曲第2番 ト長調 作品36 (1866)
弦楽四重奏曲第1番 ハ短調 作品51/1(1873年)
弦楽四重奏曲第2番 イ短調 作品51/2(1873年)
弦楽四重奏曲第3番 変ロ長調 作品67(1876)
弦楽五重奏曲第1番 ヘ長調 作品88(1882)
弦楽五重奏曲第2番 ト長調 作品111 (1891)
クラリネット五重奏曲 ロ短調 作品115(1891)
【オルガン作品】
フーガ 変イ短調 WoO 8
前奏曲とフーガ イ短調 WoO 9
前奏曲とフーガ ト短調 WoO 10
コラール前奏曲とフーガによる "O Traurigkeit, o Herzeleid" WoO 7
11のコラール前奏曲 op.
【合唱作品】
Postillons Morgenlied(男声合唱のための)(~1847/50?) テキスト ヴィルヘルム・ミュラー
男声合唱のためのDie goldenen brücken (1853) (2010年にCelle City Archiveで発見). テキスト:Emanuel Geibel エマニュエル・ガイベル
ミサ・カノニカ op. (1856-、断片)。 後にモテットop.74,1に一部使用される。
アヴェ・マリア(女声合唱と管弦楽のための) 作品12 (1860)
女声合唱とピアノまたはオルガンのための作品12
女声合唱と管楽器のためのアヴェ・マリアop.13(1860)、incipit:Nun lasst uns den Leib、カール・ミヒャエル・コンマによるオルガン版もある。
ホルン2本とハープを伴う女声合唱のための4つの歌 作品17 (1860)
混声合唱のためのマリエンリーア 作品22(1859)
オルガンまたはピアノフォルテ伴奏による女声3部合唱のための第13篇 作品27(1859)
2つのモテットop.29(1857-1860):「Es ist das Heil uns kommen her」op.29,1、「Schaffe in mir Gott ein rein Herz」op.29,2(詩篇51, 12-14)
霊歌 作品30(1856年)
無伴奏女声合唱のための3つの神聖な合唱曲 作品37 (1859/1863)
男声4部合唱のための5つの歌 作品41(1861-62?)
6部合唱アカペラのための3つの歌曲 作品42(1859-1861)を含む: ヴィルヘルム・ミュラーの詩による「ヴィネータ」作品42第2番(1860年)、オシアンの詩による「ダースラの葬送歌」作品42第3番
女声合唱のための12の歌とロマンス op.
ドイツ・レクイエム 作品45(1866/67、1868(第5楽章)
リナルド 作品50(1869年)
リーベスリート・ヴァルツァー」作品52(1868)と「新リーベスリート」作品65(1874)。 テキスト:ゲオルク・フリードリヒ・ダウマー
アルト、男声合唱と管弦楽のための狂詩曲(ゲーテの「冬の旅」の断片による) op.53(1869
レクイエム作品54(1871)。 作詞:フリードリヒ・ヘルダーリン フリードリヒ・ヘルダーリン
凱歌」作品55(1871年) テキスト:聖ヨハネの黙示録より
混声合唱のための7つの歌 作品62(1874年)
2つのモテット 作品74(1878年) なぜ疲れた者に光が与えられるのか?
ナーニー op.82(1881). テキスト フリードリヒ・シラー
パルゼンの歌」op.89(1882)。 テキスト ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
歌曲とロマンス(混声4部合唱のための) 作品93a(1883/84
ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフによる6部混声合唱とピアノのためのタフェリート op.93b (1884)
つの歌 作品103と112(4声とピアノのための
混声合唱アカペラのための5つの歌 作品104 (1888)
祝祭と記念の格言 アカペラ作品109「ハンブルク市長カール・ペーターゼン博士に捧ぐ」(1888年)
3つのモテット 作品110 (1889)
女声のための13のカノン 作品113(一部1863年)
無伴奏混声合唱のための14の民謡 WoO 34 (1857-58; 1863-64)
芸術のために, 愛をこめて, 愛の勝利のために, 聖なるメルティラー・エメラノのために, トイブリーンは泣いた, 愛するイエズス・キリストよ, サンクト・ラファエロ, 静かな夜に, Abschiedslied, 重いナイフ, 舞踏の中で, Morgengesang, Schnitter Tod, Der englische Jäger
無伴奏混声合唱のための12の民謡 WoO 35 (1863-64)
シャイデン、ワッハ・アウフ、エルラウベ・ミール、フィードラー、ダ・ウンテン・イム・テイル、デ・アベンド、ワッハ・アウフ、ドート・イン・デン・ヴァイデン、アルテ・ヴォークスリート、リッター・アンド・ダイ・フィーネ、ジマーゲゼル、アルトドイツ・ケンプフリート
《》作品番号付
ベッティーナ・フォン・アルニムに捧げられた6つの歌曲(テノールまたはソプラノ1声とピアノのための) 作品3 (1852-53)
リーベストレウ、愛と歓喜I、愛と歓喜II、歌曲(草原を歩いて)、イン・デア・フレムデ、歌曲(リンデス・ラウシェン・イン・デン・ウィップフェルン)
テノールまたはソプラノの声とピアノのための6つの歌曲 作品6、ルイーゼとミンナ・ヤファに献呈。 (1852-53)
スペイン歌曲、春の訪れ、ナハヴェルクング、ジュシェ!、狼は子らのもとへ、夜が明けるまで
アルベルト・ディートリヒに献呈された6つの歌曲(1声とピアノのための)作品7 (1851-53)
愛、パロル、アンクレンゲ、ヴォルフスリート、旅路、ハイムケール
声楽とピアノのための8つの歌曲とロマンス 作品14 (1858)
窓の外、傷ついた少年、マレー殺人事件、ソネット、別離、最愛の人のもとへ、セレナーデ、あこがれ(私の宝物はここにはない)
4つの歌 作品17(1860)
エス・トント・アイン・ヴォーラー・ハーフェンクラング、シェイクスピアの歌、庭師、フィンガルの歌
ひとつの声とピアノのための5つの詩 作品19
接吻、別れと回避、遠くで、鍛冶屋、エオリアン・ハープに
ソプラノとアルトのための3つの二重唱曲 作品20
アルトとバリトンのための4つの二重唱 作品28
4つの独唱(SATB)とピアノのための3つの四重奏曲 作品31
つの歌と聖歌 作品32
夜になると私はどのように立ち上がるのか、もはやあなたのもとへ行くこともなく、私は忍び歩き、私のそばをせせらぎが流れ、また災いだ、あなたは私が欺かれていると言う、あなたは苦いことを言おうとしている、こうして私たちは立っている、私と私の牧草地、女王よ、あなたはお元気ですか?
ユリウス・シュトックハウゼンに捧ぐ。 L.ティークの「マゲローネ」よりロマンス(ピアノフォルテ付き1声のための) 作品33(1861-1869)。
誰も後悔したことはない、トラウン! 弓矢は敵のために良い、彼らは痛み、彼らは喜び、愛は遠い国から来た、貧しいのだろう、どのように私は喜び、至福に耐えよう、それはこの唇が震えたあなたでしたか、私たちはしなければならないし、別れ、最愛の弦楽器演奏、休息、甘い愛、日陰で、絶望、どのようにすぐに消えるので、光の中で輝きのように、別れがなければならない、スリマ、私の心はどのように喜んで、新鮮なリフト、忠実な愛は長く続く[49]。
つの歌曲 作品43
(19]誰もまだ後悔していなかった、トラウン!(19)永遠の愛のために、マインハット(19)私はホルンを吹く(19)ファルケンシュタイン牧師の歌(19)
つの歌(1つの声とピアノのための) 作品46
[49]誰もまだ悔やんでいなかった、トラウン! クレンゼ、マジャリシュ、無常の悲しみ、夜の帳が下りたとき
ひとつの声とピアノのための5つの歌 作品47
メッセージ、愛の喜び、ソーンターク、愛の歌よ、愛の歌よ
片声とピアノのための7つの歌 作品48
恋人の一団, 恋人の一団, 恋人の恋, 愛を超えた黄金, 悲嘆に暮れる, 過ぎ去りし日は慈しみと慈しみ, 春の歌(Herbstgefühl)
すみれに 最終稿
ひとつの声とピアノのための5つの歌 作品49
春の陽気、ヴェールの下で、愛の歌、ヴィーゲンリート、アベンドデンメルング
つの歌と聖歌 作品57
森に包まれた高みから 時折あなたが微笑んでくれるなら 私はあなたに愛されていると夢見た ああこのまなざしを向けて 私の憧れの夜に 時折穏やかな光が射す 弦は真珠と真珠を結ぶ 動かぬ慈愛に満ちた空気よ
つの歌と聖歌 作品58
盲目のくちづけ、春の終わりに、シュプレーデ、さあ、夏の夜を、シュヴェルムート、ガスに包まれて、ヴォリューバー、セレナーデ(あなたへの贈り物)
つの歌と聖歌 作品59
遥か彼方へ、見渡す限り(Blauer Himmel, blaue Wogen)、Regenlied(Walle, Regen, walle nieder)、Nachklang、Agnes、Eine gute, gute Nacht、Mein wundes Herz、Dein blaues Auge
ソプラノとアルトのための4つの二重唱とピアノ 作品61
一つの声とピアノのための9つの歌と聖歌 作品63
夕暮れ, Erinnerung, An ein Bild, An die Tauben, Junge Lieder I, Junge Lieder II, Heimweh I, Heimweh II, Heimweh III.
つの独唱とピアノのための四重奏曲 作品64
ソプラノとアルトとピアノのための5つの二重唱 作品66
声楽とピアノのための9つの歌曲 作品69
哀歌 I、哀歌 II、別れ、愛の誓い、タンブールの歌、浜辺から、海を越えて、サロメ、少女の呪い
つの歌曲 作品70
歌曲集(「荘厳な庭」)、レルヒェンゲザング、セレナーデ(「愛しい人よ」)、アベンドレーゲン
ひとつの声とピアノのための5つの歌 作品71
エス・リベルト・シック・ソー・ラブリッヒ・イン・レンズ、アン・デン・モンド、ゲヘイムニス、ウィルスト・デュ・ダス・イッヒ・ゲー?
つの歌 作品72
古い恋、夏の糸、涼しい森よ、絶望、征服できない
2声のためのバラードとロマンス 作品75(1877/78)
1声または2声とピアノのための5つのロマンスと歌 作品84
夏の終り、クランツ、蜂の巣の中で、美しい胸、スパンヌング
声楽とピアノのための6つの歌 作品85
夏の終り、月曜日、牧神の歌(ああ、私の美しい水)、アデ!、春の歌、わが愛の中で
6つの歌曲(下声1声とピアノのための)作品86
テレーズ、フェルデインザムケイト、ナハトヴァンドラー、ハイデを越えて、ヴェルズンケン、トデッセーネン
アルト声楽とヴィオラとピアノのための2つの歌曲 作品91
ソプラノ、アルト、テノール、バスとピアノのための四重奏曲 作品92
低声とピアノのための5つの歌 作品94
四十にして、立ち上がれ、愛しき影よ、わが心は重く、サフィック・オード、家なし、家なし
声楽とピアノのための7つの歌 作品95
メードヒェン(若き日に)、私の想い、断絶の時、イェーガー、ヴォーシュナー・シュワー、メードヒェンレーテッド、Schön war, das ich dir weihte
つの歌 作品96
死よ、それは涼しい夜、私たちは歩いた、花は見ている、海の旅
ひとつの声とピアノのための6つの歌 作品97
ナイチンゲール、船の上で、誘拐、柳の中に、やがて来たる、別れ
8つのジプシーの歌(ピアノ伴奏付き) 作品103 ユーゴ・コンラートのハンガリー語に基づく。
おい、ジプシー、弦をとれ、高くそびえるリマフルート、私の小さな子供、親愛なる神よ、あなたは知っている、茶色の少年は踊りに導かれる、小さなバラは3つ並んで、時々それはあなたの心に浮かぶ、赤い夕雲が流れている
低声とピアノのための5つの歌 作品105
メロディーのように私を引き寄せる、私のまどろみはますます静かになる、哀歌、教会堂で、裏切り
片声とピアノのための5つの歌 作品106
歌曲集(Der Mond stehtüber dem Berge)、Auf dem See (An dies Schifflein schmiege, holder See)、Es hing der Reif、Meine Lieder、Ein Wanderer
片声とピアノのための5つの歌 作品107
アン・ディ・シュトルツェ、サラマンダー(文:カール・レムケ)、メードヒェンは歌う、舞姫の歌、メードヒェンリート(紡ぎ歌の夜)(Auf die Nacht in der Spinnstub'n
ソプラノ、アルト、テノールとバスのための四重奏曲(ピアノ付き) op.112 I Sehnsucht(歌:フランツ・クーグラー) II Nächtens(歌:フランツ・クーグラー) III Vier Zigeunerlieder(歌:フーゴ・コンラートのUngarischenから) 第1番:Himmel strahlt so helle und klar、第2番:Rothe Rosenknospen künden schon des Lenzes Triebe、第3番:Brennessel steht an Wegesrand、第4番:Liebe Schwalbe, kleine Schwalbe
マックス・クリンガーに捧げられたバス声楽とピアノのための4つのシリアスな歌曲 作品121
Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh(伝道の書3章より)、Ich wandte mich, und sahe an(伝道の書4章より)、O Tod, wie bitter bist du(イエス・シラハ41章より)、Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen(コリントの信徒への手紙一13章より)
《》作品番号なし
月夜の晩 WoO 21
雨の歌(木から落ちる雨粒) WoO posth.23
ロベルト・シューマンとクララ・シューマンの子供たちに捧げられた1声とピアノのための民謡集 WoO 31
眠れる森の美女
ナイチンゲール
男
サンドマン
雌鳥
リトル・ヘザー
乳と蜜の国
膝に乗って
森の狩人
子守唄
少女とハシバミ
クリスマス・キャロル
メアリーの小さな虫
守護天使へ
ドイツ民謡(1声とピアノのための) WoO 33
教えてください、私の最も美しい羊飼いの女よ
私を許して、美しい乙女よ
とても甘くやって来た
こんばんは、こんばんは、私の千倍もの宝物よ
太陽はもう輝かない
谷の底で
グンヒルデは静かに敬虔に生きた
ああ、英国の羊飼いの女よ
美しいユダヤ人がいた
一人の騎士がいた
乙女よ、一緒に行こうか
乙女よ、私と裸足になってはいけない
目を覚まして、私の避難所
マリアは放浪の旅に出た
妹よ、妹よ
目を覚まして、私の美しい心
ああ、別れはつらい
おやすみなさい
この世でたった一つの顔だけが生きている
最も美しいダーリン、私の天使
乙女は優しい
どこへ行くのだ、誇り高き者よ
ライダーはマントを広げる
私には美しい茶色の乙女がいる
乙女の口はバラ色
ああ、今宵、できることなら
私は高い山の上に立っていた
領主とその召使も乗っていた
ライン川の向こうに侯爵がいた
私の思いはすべて
柳の中に家が建っている
だから私は新鮮で陽気でありたい
オーシュ・モーダー、イッヒ・ウェル・エン・ディング・ハン
どうすればドアに入れるの?
月がもっと輝くだろう
バイオリン弾きが住んでいる
あなただけが私の光
夜になっても眠れない
美しい瞳 美しい光
私は小さな乙女を知っている
ヒバリが立っている
静かな夜、最初の時計に
三輪のバラが散った
私は天に向かって嘆く
雪のように白い鳥がいた
むかしむかし、一人のルームメイトがいた
妻が出かけた
ナイチンゲール、どんな挨拶をする
月はこっそり昇る
…
〜
ヨハネス・ブラームスの作品リスト
List of compositions by Johannes Brahms
Wikipedia EN(英語版) URL> https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_compositions_by_Johannes_Brahms
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
