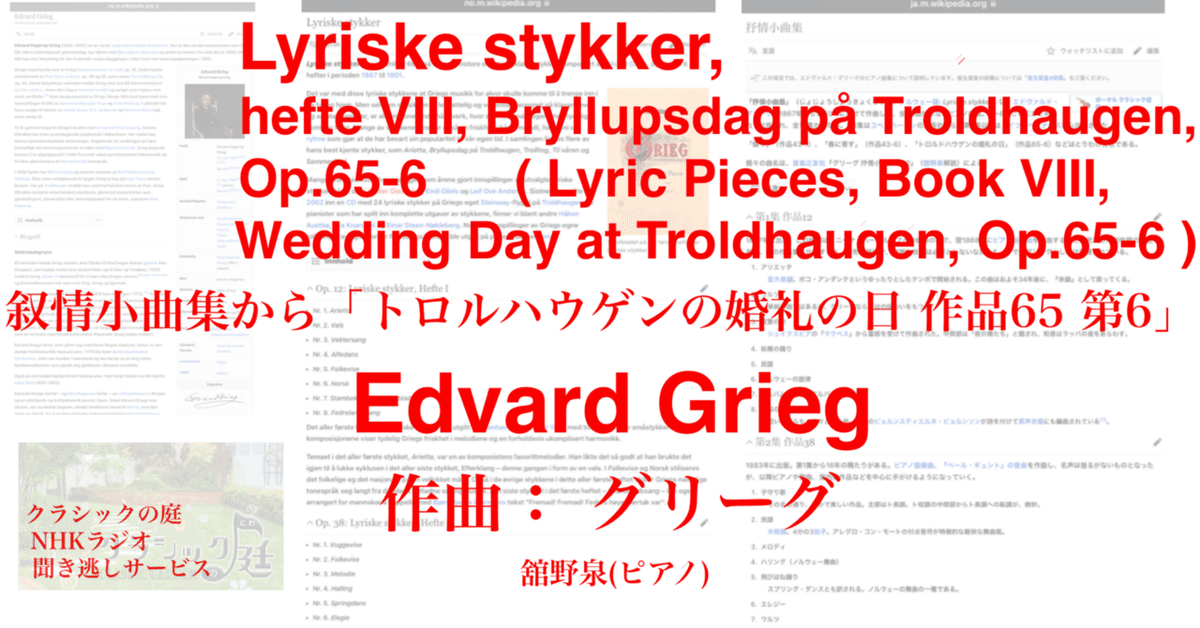
ラジオ生活:クラシックの庭 グリーグ「叙情小曲集」から「トロルハウゲンの婚礼の日 作品65 第6」
聞き逃しサービス 2024/06/17 放送
クラシックの庭
〜
〜
「叙情小曲集」から「トロルハウゲンの婚礼の日 作品65 第6」
( Lyric Pieces, Book VIII, Wedding Day at Troldhaugen, Op.65-6 )
[ Lyriske stykker, hefte VIII, Bryllupsdag på Troldhaugen, Op.65-6 ]
作曲: グリーグ ( Edvard Grieg )
舘野泉(ピアノ)
(5分33秒)
〜
開始より55分54秒頃 (終了より54分06秒前頃)
〜…〜
ちなみに、
・「叙情小曲集」から「こもり歌 作品38 第1」(3分7秒)
開始より48分35秒頃 (終了より1時間01分25秒前頃)
・「叙情小曲集」から「メロディー 作品47 第3」(4分6秒)
開始より51分43秒頃 (終了より58分17秒前頃)
〜
〜
配信終了 2024/06/24 15:50
番組情報
Google検索 URL>
https://www.google.co.jp/search?tbm=vid&hl=ja&source=hp&biw=&bih=&q=Edvard_Grieg+Wedding_Day_at_Troldhaugen_Op_65_6
Bing検索 URL> https://www.bing.com/videos/search?q=Edvard_Grieg+Bryllupsdag_på_Troldhaugen_Op_65_6
叙情小曲集 ( Lyriske_stykker )
Bing検索 URL> https://www.bing.com/videos/search?q=Edvard_Grieg+Lyriske_stykker
〜
〜〜
〜〜〜
☆★☆ グリーグ「叙情小曲集」について【目次】☆★☆
〜〜〜
〜〜
1. グリーグ「叙情小曲集」について
1.1 Wikipedia JA(日本版)の抜粋
1.2 Wikipedia NO(ノルウェー版)の抜粋、および、その日本語翻訳
〜〜
〜
〜〜
2. 作曲者:グリーグについて
2.1 Wikipedia NO(ノルウェー版)の抜粋、および、その日本語翻訳
2.2 グリーグの作品リストへのリンク・Wikipedia EN(英語版)
〜〜
〜
<<< 以下、参照しているWikipediaなどへのリンクはそれぞれの先頭あたりで紹介してます。>>>
〜
〜〜
1. グリーグ「叙情小曲集」について
1.1 Wikipedia JA(日本版)の抜粋
〜〜
〜
Wikipedia JA(日本版) URL> https://ja.m.wikipedia.org/wiki/抒情小曲集
〜
『抒情小曲集』(じょじょうしょうきょくしゅう、ノルウェー語: Lyriske stykker)は、エドヴァルド・グリーグが1867年から1903年にかけて作曲した、全66曲からなるピアノ曲集。6~8曲ごとにまとめられて出版され、全10集からなる。第1集はコペンハーゲンの出版社から、第2集以降はドイツのペータースから出版された。
「蝶々」(作品43-1)、「春に寄す」(作品43-6)、「トロルドハウゲンの婚礼の日」(作品65-6)などはとりわけ有名である。
個々の曲名は、音楽之友社『グリーグ 抒情小曲集 1・2』(舘野泉解説)による。
…
【第1集 作品12】
1867年に出版。この時期は、ニーナ・ハーゲルップとの結婚の年で、翌1868年にピアノ協奏曲を作曲するなど、充実した創作期の作品である。後の作品集と比較すると、音形は単純で、複雑な技巧は必要としないながらも、すでにグリーグらしさは発揮されている。
1. アリエッタ
変ホ長調。ポコ・アンダンテというゆったりとしたテンポで開始される。この曲はおよそ34年後に、『余韻』として戻ってくる。
2. ワルツ
単純な曲ではあるが、グリーグならではの味わいをもつ。
3. 夜警の歌
シェイクスピアの『マクベス』から霊感を受けて作曲された。中間部は「夜の精たち」と題され、和音はラッパの音をあらわす。
4. 妖精の踊り
5. 民謡
6. ノルウェーの旋律
7. アルバムの綴り(アルバムリーフ)
8. 祖国の歌
短いながらも、堂々とした曲。友人のビョルンスティエルネ・ビョルンソンが詩を付けて男声合唱にも編曲されている。
…
【第2集 作品38】
1883年に出版。第1集から16年の隔たりがある。ピアノ協奏曲、『ペール・ギュント』の音楽を作曲し、名声は揺るがないものとなったが、以降ピアノや歌曲、室内楽作品などを中心に手がけるようになっていく。
1. 子守り歌
その名の通り、静かで美しい作品。主部はト長調。ト短調の中間部からト長調への転調が、絶妙。
2. 民謡
ホ短調。4分の3拍子。アレグロ・コン・モートの付点音符が特徴的な軽快な舞曲風。
3. メロディ
4. ハリング(ノルウェー舞曲)
5. 飛びはね踊り
スプリング・ダンスとも訳される。ノルウェーの舞曲の一種である。
6. エレジー
7. ワルツ
ホ短調。ポコ・アレグロ。
8. カノン
起伏の大きな、左右の手の対旋律による進行。シューマンの影響がうかがえる。
…
【第3集 作品43】
第2集の翌年に作曲されたが、出版は1886年。ヨーロッパ各地への演奏旅行の合間に書かれた曲。全体的に春の喜びに溢れている。
1. ちょうちょう(蝶々)
細かい流れるような音列が蝶々の飛翔を表現している。分散された音符の中からしっとりわき上がるメロディは、優しさにあふれている。
2. 孤独なさすらい人
3. 故郷にて
4. 小鳥
32分音符のトレモロが小鳥のさえずりを表現している。アレグロ・レッジェーロ(軽やかに)。
5. 愛の歌
非常に甘美な旋律をたっぷりと歌いながら演奏する。
6. 春に寄す
4分の6拍子。右手の和音の連打のもとに、左手の旋律が浮かび上がる。このリズム感は、シベリウスの交響曲第2番の冒頭と共通する点がある。
…
【第4集 作品47】
1888年に出版。作品は1885年に遡るものもある。「アルバムの綴り」、「ハリング」、「飛びはね踊り」など、他の曲集と重複する名前の曲がある。
1. 即興的ワルツ
2. アルバムの綴り
3. メロディ
4. ハリング
5. メランコリー
6. 飛びはね踊り
7. 悲歌(エレジー)
…
【第5集 作品54】
1891年に出版。『抒情小曲集』の中心をなす完成度の高いもの。最初の4曲は作曲者により『抒情組曲』として管弦楽へ編曲されている。
1. 羊飼いの少年
憂いをおびたフルートの響きを模した旋律。
2. ノルウェーの農民行進曲
3. 小人の行進
原曲名は「トロルの行進」であるが、巨大なトロルではなく、茶目っけのある子供のようなトロルをイメージしている。
4. 夜想曲
5. スケルツォ
6. 鐘の音
空虚五度の響きを中心にした実験的な作品。
『抒情組曲』の原型となったアントン・ザイドル編曲による『ノルウェー組曲』の一曲に含まれていた。作曲者自身が組曲を編み直した際に外され、代わりに「羊飼いの少年」が加えられたが、「鐘の音」もザイドル編曲作品として時折単独で演奏される。
…
【第6集 作品57】
1893年に出版。フランスの保養地マントンで作曲された。祖国への郷愁とヨーロッパ的なスタイルが同居している。
1. 過ぎ去った日々
2. ガーデ(ゲーゼ)
デンマークの作曲家ニルス・ゲーゼ没後の回想として作曲された。
3. 幻影
4. 秘密
5. 彼女は踊る
6. 郷愁
ノルウェーの山峡地帯の山羊笛の音を模した旋律。
…
【第7集 作品62】
1895年に出版。トロルドハウゲンで作曲された。体調が次第に悪化していった時期の作品。第5、6集と比べ地味なため玉石混淆と言われることもあるが、むしろ芸術性は高まり、グリーグ後期の繊細で洗練された自然美が描かれる。
1. 風の精
2. 感謝
3. フランス風セレナード
4. 小川
5. 夢想
6. 家路
3部形式。家路を急ぐ主部と、過去を回想するカンタービレの中間部とからなる。
…
【第8集 作品65】
1896年に書かれ、1897年に出版。ピアニストの舘野泉によれば、第5曲をはじめとして「バラード調」の曲が多い。
1. 青春の日々から
哀愁を帯びたメロディと、躍動的な中間部が対照的な、やや大規模の曲。
2. 農民の歌
3. 憂うつ
4. サロン
5. バラード調で
6. トロルドハウゲンの婚礼の日
全曲中もっとも大規模で、人気のある曲。管弦楽編曲もされて親しまれる。
元来はグリーグ家の友人の誕生祝いとして作曲されたが、出版時には出版社の意向もあって、グリーグ夫妻の結婚30周年祝賀の意味が込められることになった。
…
【第9集 作品68】
1898年から1899年初めに書かれ、1899年に出版。2~3分の小さな曲ばかり。第4曲と第5曲は1899年にグリーグ自身が管弦楽(基本は弦楽合奏だが第4曲のみオーボエとホルンを1本ずつ使用)に編曲している。
1. 水夫の歌
輪郭のはっきりした快活な曲。2分の2拍子、ハ長調というのもわかりやすい。
2. おばあさんのメヌエット
おばあさんにしては軽快で動きの激しいメヌエット。
3. あなたのそばに
ロマンティックで甘美なメロディ。愛妻ニーナへの想いを綴った曲。
4. 山の夕べ
山羊笛を摸す単音のメロディが続き(管弦楽版ではこれをオーボエが延々と吹く)、中間部ではffで最高潮に達する。
5. ゆりかごの歌
ホ長調。アレグロ・トランキラメンテ。pの目立つ曲。グリーグ夫妻はひとり娘をわずか1歳で失った(その後は子供に恵まれなかった)。その子への追想の曲となっている。
6. 憂うつなワルツ
…
【第10集 作品71】
20世紀に入り、1901年5月に5曲を作曲。同年に出版。
1. 昔々
スウェーデン民謡とノルウェー舞曲による3部形式の曲。
2. 夏の夕べ
ノルウェーの夏の夕暮れをグリーグらしい独特な曲で仕上げている、とても美しく抒情的な曲である。
3. 小妖精
こちらの駆け回る妖精は、おなじみのトロルではなく、パックである。
4. 森の静けさ
レントの落ち着いた曲。ppで始まり、pppで終わる。
5. ハリング
6. 過去
半音ずつの下降で、抒情小曲集全体の終わりを告げる。
7. 余韻
第1集第1曲の「アリエッタ」を3拍子に変奏したワルツ。最初のト音および終結のト音にはフェルマータが付けられ、余韻を残す。
…
〜[上記Wikipediaより抜粋。]
〜
〜〜
1. グリーグ「叙情小曲集」について
1.2 Wikipedia NO(ノルウェー版)の抜粋、および、その日本語翻訳
〜〜
〜
グリーグ「叙情小曲集」
Lyriske_stykker_( Edvard Grieg )
Wikipedia NO(ノルウェー版) URL> https://no.m.wikipedia.org/wiki/Lyriske_stykker
〜
Lyriske stykker er en samling 66 små til mellomstore ensatsige klaverstykker komponert av Edvard Grieg, og utgitt i ti hefter i perioden 1867 til 1901.
Det var med disse lyriske stykkene at Griegs musikk for alvor skulle komme til å trenge inn i de tusen hjem. Men selv om musikken er lettfattelig og vesentlig beregnet på klaverelever og amatørpianister, er alle imponerende håndverk, hvor den nasjonale egenarten tydelig kommer frem. Mange av stykkene innehar også en friskhet i både melodi, harmoni og rytme som gjør at de har bevart sin popularitet til vår egen tid. I samlingen finnes flere av hans best kjente stykker, som Arietta, Bryllupsdag på Troldhaugen, Trolltog, Til våren og Sommerfugl.
Mange store pianister har opp i gjennom årene gjort innspillinger av utvalgte lyriske stykker, blant dem Walter Gieseking, Emil Gilels og Leif Ove Andsnes. Sistnevnte spilte i 2002 inn en CD med 24 lyriske stykker på Griegs eget Steinway-flygel på Troldhaugen. Av pianister som har spilt inn komplette utgaver av stykkene, finner vi blant andre Håkon Austbø, Eva Knardahl og Einar Steen-Nøkleberg. Noen få innspillinger av Griegs egne tolkninger av egne verker finnes også. Disse ble utgitt på plateselskapet Simax.
…
【Op. 12: Lyriske stykker, Hefte I】
・Nr. 1. Arietta
・Nr. 2. Vals
・Nr. 3. Vektersang
・Nr. 4. Alfedans
・Nr. 5. Folkevise
・Nr. 6. Norsk
・Nr. 7. Stamboksblad (Albumblad)
・Nr. 8. Fedrelandssang
Det aller første heftet med lyriske stykker ble utgitt i København i desember 1867 med tittelen Lyriske småstykker. Alle komposisjonene viser tydelig Griegs friskhet i melodiene og en forholdsvis ukomplisert harmonikk.
Temaet i det aller første stykket, Arietta, var en av komponistens favorittmelodier. Han likte det så godt at han brukte det igjen til å lukke syklusen i det aller siste stykket, Efterklang – denne gangen i form av en vals. I Folkevise og Norsk stiliseres det folkelige og det nasjonale på en vellykket måte. Også i de øvrige stykkene i dette aller første heftet skiller Griegs naturlige tonespråk seg langt fra datidens søtladne salongmusikk. Det siste stykket i det første heftet – Fedrelandssang – ble også arrangert for mannskor a cappella med Bjørnstjerne Bjørnsons tekst "Fremad! Fremad! Fedres høye hærtak var".
…
【Op. 38: Lyriske stykker, Hefte II】
・Nr. 1. Vuggevise
・Nr. 2. Folkevise
・Nr. 3. Melodie
・Nr. 4. Halling
・Nr. 5. Springdans
・Nr. 6. Elegie
・Nr. 7. Vals
・Nr. 8. Kanon
Det skulle gå 16 år fra opus 12 til opus 38 ble utgitt. Det var derfor stor forventning knyttet til Griegs utgivelse av sitt andre hefte Lyriske Stykker. I 1883 kom altså hans "Nye Lyriske Stykker for Pianoforte", opus 38 ut på Peters Verlag i Leipzig. I likhet med sitt første hefte består også dette av åtte forskjellige stykker, men til forskjell fra opus 12 er stykkene i opus 38 komponert over lang tid. "Vals" ble for eksempel komponert så tidlig som i 1866, altså før opus 12 ble utgitt. Opus 38 viser at Grieg har modnet som komponist, han er mer trygg på seg selv og dette gjør at han våger å uttrykke seg med flere toner enn han gjør i opus 12. Det første stykket "Vuggevise", eller "Berceuse" som Grieg også kalte det, kjennetegnes ved en vuggende rytme som gjenspeiler tittelen på en mesterlig måte. Som i opus 12 tar han også i dette heftet med noen eksempler på sine stiliserte folkemelodier, "Halling" og "Springdans". I stykkene "Melodi" og "Kanon" merker man at Edvard Grieg fremdeles komponerer pianomusikk påvirket av Robert Schumann.
…
【Op. 43: Lyriske stykker, Hefte III】
・Nr. 1. Sommerfugl
・Nr. 2. Ensom vandrer
・Nr. 3. I hjemlandet
・Nr. 4. Liten fugl
・Nr. 5. Erotik
・Nr. 6. Til våren
I sitt tredje hefte med Lyriske Stykker når Grieg nye høyder som komponist av lyriske musikalske miniatyrer. Heftet består av seks stykker som alle er blant Griegs aller mest populære verk. Selv om stykkene hver for seg er musikalske mesterverk, utgjør de også en helhet som en ikke finner i de to første heftene. Opus 43 ble utgitt i Leipzig i 1886 og ble i hovedsak til under et opphold i Danmark. "Sommerfugl" og "Liten Fugl" viser komponistens evne til å gjenskape sine inntrykk fra naturen omkring seg. "I Hjemmet" ble ifølge Grieg inspirert av den hjemlengsel han følte mens han skrev et brev til Frants Beyer i Bergen: " Hvad sier Du om en stille Formiddag i Båden eller ude mellem Skjær og Klipper! Forleden Dag blev jeg så fuld av denne Længsel, at det formede sig i et mildt Taknemmelighedskvad. Der er Intet Nyt i det, men det er ægte og da er det igrunden ikke andet end et Brev til Dig, så lad det stå her". Selv om Grieg sa til sin forlegger i Tyskland at alle stykkene i opus 43 var inspirert av våren, er det kun det siste stykket "Til Foråret" som direkte gjenspeiler dette. Det er ikke vanskelig å forstå at nettopp dette stykket er blitt en av de mest spilte av Griegs Lyriske Stykker. Her bruser formelig vestlandsvåren frem i all sin fylde, det er som om Grieg allerede er hjemme på Troldhaugen, men i virkeligheten befinner han seg kun på båten fra Danmark til Norge.
…
【Op. 47: Lyriske stykker, Hefte IV】
・Nr. 1. Valse-Impromptu
・Nr. 2. Albumblad
・Nr. 3. Melodi
・Nr. 4. Halling
・Nr. 5. Melankoli
・Nr. 6. Springdans
・Nr. 7. Elegi
Det fjerde hefte med Lyriske Stykker, som utkom i 1888, er av en mer ujevn kvalitet enn det foregående. I likhet med de tre tidligere utgitte heftene er det også her tatt med to stiliserte folkemelodier "Halling" og "Springdans". Dette heftet er blitt kritisert for å være mer "salongpreget" enn de tidligere heftene. Riktignok er stykkene som utgjør opus 47 lettere og mindre konkrete enn tidligere, men i den stillferdig reflekterende stilen finnes uttrykk som på sin måte bidrar til å få frem de uhåndgripelige følelsene i stykker som "Melodi" og Elegi".
…
【Op. 54: Lyriske stykker, Hefte V】
・Nr. 1. Gjetergutt
・Nr. 2. Gangar
・Nr. 3. Trolltog
・Nr. 4. Notturno
・Nr. 5. Scherzo
・Nr. 6. Klokkeklang
Etter det mer anonyme opus 47, slår Grieg til med det mange mener er det beste heftet med Lyriske Stykker. I hefte V møter vi Edvard Grieg på sitt aller beste, det musikalske uttrykk har fått mer tyngde, han uttrykker seg med en klarhet og originalitet som fremhever hans egen personlighet og det nasjonale særpreg. De nasjonalt inspirerte ideene er hevet til et høyere harmonisk plan, og harmonikken er også blitt mer avansert. Inntrykk fra naturen har gitt inspirasjon til åpningsstykket "Gjetergutt". Det er som om en kommer opp i fjellene og får puste inn den rene, friske luften, man er i det hele tatt langt fra de salonger man kritiserte Grieg for å komponere for i tidligere hefter. I "Gangar" når Grieg et høydepunkt når det gjelder å komponere stiliserte folkeviser- og danser. "Troldtog" og "Nocturno" er sikre vinnere på enhver pianists repertoar. I "Troldtog" myldrer fjellets små troll frem, gjemmer seg for solen i midtpartiet, for til slutt å myldre frem som aldri før. "Notturno" gjenskaper med sine rolige, dempede toner sommernattens vesen. Grieg velger den italienske måten å skrive Nocturno på, noe som også bidrar til å føre tankene til de italienske sommernettene. "Klokkeklang" er et impresjonistisk verk som er nesten 20 år forut for sin tid.
…
【Op. 57: Lyriske stykker, Hefte VI】
・Nr. 1. Svundne dager
・Nr. 2. Gade
・Nr. 3. Illusjon
・Nr. 4. Hemmelighet
・Nr. 5. Hun danser
・Nr. 6. Hjemve
I 1893, på den franske Riviera, nærmere bestemt i Menton, komponerer Edvard Grieg sitt sjette hefte med lyriske stykker. Mange vil hevde at dette er det svakeste av de ti heftene. Avstanden til Norge og Troldhaugen gjør at det er europeeren Grieg som komponerer, og dette gir en stil som på mange måter kan minne om Johannes Brahms. Grieg fører en "bredere pensel", bassene blir dype og akkordene tykke, det er som det har lagt seg en skygge over det klare uttrykk i opus 54. I to av stykkene, "Svunne Dager" og "Hjemve" finner Grieg likevel frem til sin "norske" måte å komponere på med springartakter i midtpartiet i begge stykkene. "Gade" er et lite minnesmerke over den danske komponisten Niels W. Gade (1817–90)
…
【Op. 62: Lyriske stykker, Hefte VII】
・Nr. 1. Sylfide
・Nr. 2. Takk
・Nr. 3. Fransk serenade
・Nr. 4. Bekken
・Nr. 5. Drømmesyn
・Nr. 6. Hjemad
Etter de mørke fargene som preger opus 57 finner Grieg frem de lyse fargene i sitt syvende hefte Lyriske Stykker i 1895. "Sylfide", "Takk" og "Drømmesyn" er alle typiske salongstykker komponert i en litt forfinet stil. Det er først i "Hjemve" og særlig "Bekken" han vender tilbake til den stil som bragte suksessene i opus 43 og 54. "Bekken" er noe av det teknisk sett vanskeligste han har skrevet av lyriske stykker.
…
【Op. 65: Lyriske stykker, Hefte VIII】
・Nr. 1. Fra ungdomsdagene - allegro moderato e tranquillo
・Nr. 2. Bondens sang - andante simplice
・Nr. 3. Tungsinn - andante espressivo
・Nr. 4. Salon - allegretto con grazia
・Nr. 5. I balladetone - lento lugubre
・Nr. 6. Bryllupsdag på Troldhaugen - tempo di marcia un poco vivace
Opus 65 blir først og fremst husket på grunn av avslutningen med det mest berømte lyriske stykke "Bryllupsdag på Troldhaugen". Opprinnelig het stykket "Gratulantene kommer", men til minne om den storartede feiringen av sitt og Ninas sølvbryllup fem år tidligere 11. juni 1892 endret han tittelen til "Bryllupsdag på Troldhaugen". Men heftet inneholder også andre interessante stykker som "Fra Ungdomsdagene" og "I Balladetone". I det første ser Grieg tilbake til sin egen ungdom med en god porsjon melankoli. "I Balladetone" og "Bondens Sang" er de to stykkene hvor Grieg følger opp sin tradisjon med stiliserte folkemelodier.
…
【Op. 68: Lyriske stykker, Hefte IX】
・Nr. 1. Matrosenes oppsang
・Nr. 2. Bestemors menuett
・Nr. 3. For dine føtter
・Nr. 4. Aften på høyfjellet
・Nr. 5. Bådnlåt
・Nr. 6. Valse mélankolique
I 1899 utgikk stykkene til Edvard Grieg hefte nummer ni med lyriske stykker. De inneholder alt fra det typisk salongpregete som "Valse Mélancolique" og "For dine Føtter" til eksperimenter som "Aften på Høyfjellet". Grieg sendte en tidlig utgave av "Aften på Høyfjellet" til sin venn Frants Beyer med følgende påskrift: "Kan tenkes som en Kveldsstemning på Skogadalsbøen". Det er et meget spesielt stykke, hvor melodilinjen spilles alene i første del, bare siste del er harmonisert og da med enkle akkorder. Melodien gir en vár naturskildring ved klangen av bukkehorn, toner som hadde fortryllet Edvard Grieg og Frants Beyer på deres tur i Jotunheimen i 1887. Senere arrangerte Grieg to av stykkene i opus 68 for orkester; "Aften på Høyfjellet" for obo, valthorn og strykeorkester og "Bådnlåt" for strykeorkester.
…
【Op. 71: Lyriske stykker, Hefte X】
・Nr. 1. Det var engang
・Nr. 2. Sommeraften
・Nr. 3. Småtroll
・Nr. 4. Skogstillhet
・Nr. 5. Halling
・Nr. 6. Forbi
・Nr. 7. Efterklang
Edvard Grieg avsluttet sin serie av lyriske stykker i 1901 med opus 71. Titler som "Det var engang", "Forbi" og "Efterklang" slår fast at dette er de absolutte siste lyriske stykker. Han satte et endelig punktum ved å bruke sitt aller første lyriske stykke "Arietta" i ¾-takt som avslutning på opus 71. "Arietta" er omarbeidet til en skjør, melankolsk vals som passer perfekt som en "siste dans". I "Halling" bruker han et tema fra "Brudefølget drar forbi", opus 19, og gjør det om til et av de teknisk mest krevende stykkene å spille. Grieg har satt opus 71 sammen på en mesterlig måte, dette er kanskje det heftet som passer aller best å spille som en helhet.
…
〜[Excerpt from above wikipedia.]
〜[上記wikipediaの日本語翻訳は次の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]
〜
Lyriske stykker(抒情小曲集)は、エドヴァルド・グリーグが作曲し、1867年から1901年の間に10冊の小冊子として出版された、66曲の小・中編成の1楽章からなるピアノ小品集である。
グリーグの音楽が何千人もの家庭に浸透し始めたのは、これらの叙情的な小品からだった。 しかし、曲はわかりやすく、基本的にはピアノ学習者やアマチュア・ピアニスト向けのものだが、どれも国民性がはっきりと表れている印象的な職人技の作品である。 旋律、和声、リズムに新鮮さがあり、今日まで人気を保っている作品が多い。 この曲集には、Arietta、Bryllupsdag på Troldhaugen、Trolltog、Til våren、Sommerfuglなど、彼の代表作がいくつか含まれている。
長年にわたり、ワルター・ギーゼキング、エミール・ギレル、レイフ・オヴェ・アンドスネスなど、多くの偉大なピアニストが抒情小品を選んで録音している。 2002年、後者はトロルドハウゲンにあるグリーグ自身のスタインウェイ・グランドピアノで24曲の叙情詩を収録したCDを録音した。 この曲の全曲版を録音したピアニストには、ホーコン・オーストボ、エヴァ・クナルダール、アイナー・スティーン・ノクレベリなどがいる。 グリーグ自身による自作品解釈の録音もいくつかある。 これらはSimaxレコード・レーベルからリリースされた。
…
【作品 12: 叙情的小品集 第1巻】
・第1番 アリエッタ
・第2番 ワルツ
・第3番 衛兵の歌
・第4番 妖精の踊り
・第5番 民謡
・第6番 ノルウェー語
・第7番 血統書の葉(アルバムの葉)
・第8番 フェドレランドサング
1867年12月、コペンハーゲンで「Lyriske småstykker」というタイトルで、抒情小品の最初の小冊子が出版された。 どの曲にもグリーグの新鮮な旋律と比較的単純でない和声がはっきりと表れている。
第1曲「アリエッタ」の主題は、作曲者のお気に入りのメロディーのひとつであった。 彼はこの曲をとても気に入り、最後の曲『エフタークラング』(Efterklang)のサイクルを締めくくるのに再びこの曲を使った。 FolkeviseとNorskでは、大衆的なものと民族的なものがうまく様式化されている。 この最初の小冊子に収められている他の作品でも、グリーグの自然な調性表現は、当時の甘ったるいパーラー音楽とは大きく異なっている。 最初のブックレットに収録されている最後の曲「Fedrelandssang」も男声合唱のアカペラ用に編曲されたもので、ビョルンストイェルネ・ビョルンソン(Bjørnstjerne Bjørnson)のテキスト「Fremad! 前へ フェードルの高い軍隊の天井は」。
…
【作品 38: 叙情的小曲集 第2巻】
・第1番 子守唄
・第2番 民謡
・第3番 メロディ
・第4番 ホール
・第5番 ジャンピング・ダンス
・第6番 エレジー
・第7番 ワルツ
・第8番 カノン
作品12から作品38が出版されるまで16年かかった。 そのため、グリーグが2冊目の小冊子『Lyriske Stykker』を出版することには大きな期待が寄せられていた。 1883年、ライプツィヒのペータース出版社から「ピアノフォルテのための新抒情小品集」作品38が出版された。 これも最初の小冊子と同じく8曲から成るが、作品12とは異なり、作品38の小品は長い期間をかけて作曲された。 例えば「ワルツ」は、作品12が出版される前の1866年には作曲されている。 作品38は、グリーグが作曲家として成熟し、自分に自信を持ち、作品12よりもあえて多くの音符を使って表現していることを示している。 第1曲「Vuggevise」(グリーグは「Berceuse」とも呼んだ)は、タイトルを見事に反映した揺れ動くリズムが特徴的である。 作品12と同様、グリーグはこの小冊子にも、彼の様式化された民俗旋律の例である「ハリング」と「スプリングダンス」を収録している。 メロディ」と「カノン」では、エドヴァルド・グリーグがロベルト・シューマンの影響を受けながらピアノ曲を作曲していることがわかる。
…
【作品 43: 抒情的小品集 第3巻】
・第1番 蝶々
・第2番 孤独なさすらい人
・第3番 故郷にて
・第4番 小鳥
・第5番 エロティシズム
・第6番 春まで
抒情小曲集第3巻で、グリーグは抒情的な音楽小曲の作曲家として新たな高みに到達した。 このブックレットは6曲からなり、いずれもグリーグの代表作のひとつである。 これらの小品はそれ自体が傑作であるが、第1巻と第2巻では得られない全体像を形成している。 作品43は1886年にライプツィヒで出版され、主にデンマーク滞在中に作曲された。 「蝶々」と「小鳥」は、彼を取り巻く自然界の印象を再現する作曲家の能力を示している。 グリーグによれば、この《I Hjemmet》は、ベルゲンのフランツ・バイエルに手紙を書いているときに感じたホームシックから着想を得たという: 「ボートの中や、岩や渓谷の中で過ごす静かな朝に、あなたは何を言うだろう! 先日、私はこの憧れでいっぱいになり、穏やかな感謝の歌という形になった。 目新しいことは何もないが、本物であり、あなたへの手紙以外の何ものでもないから、ここに立たせておいてほしい」。 グリーグはドイツの出版社に、作品43の全曲は春に触発されたものだと語っているが、それを直接反映しているのは最後の曲「Til Foråret」だけである。 この曲がグリーグの抒情的な曲の中で最も演奏される曲のひとつとなった理由も理解できなくはない。 ここでは、ノルウェーの西にある春が、文字どおり満ち溢れている。グリーグはすでにトロルドハウゲンの我が家にいるかのようだが、実際にはデンマークからノルウェーに向かう船の上にいるだけなのだ。
…
【作品 47: 叙情的小品集 第4巻】
・第1番 ワルツ-即興曲
・第2番 アルバム・リーフ
・第3番 メロディ
・第4番 ホール
・第5番 メランコリー
・第6番 ジャンピングジャック
・第7番 エレジー
1888年に出版された『抒情小曲集』第4巻は、前作に比べ、より品質にばらつきがある。 先に出版された3冊の小冊子と同様に、2つの様式化された民謡旋律「ハリング」と「スプリングダンス」もここに収録されている。 この小冊子は、以前のものに比べて「サロン的」であるとの批判がある。 作品47を構成する小品は、確かに以前より軽快で具体性に欠けるが、静かに内省的な作風の中に、それなりに「メロディ」や「エレジー」のような作品の無形の感情を引き出すのに役立つ表現がある。
…
【作品 54: 叙情的小曲集 第5巻】
・第1番 羊飼いの少年
・第2番 ガンガー
・第3番 トロール列車
・第4番 ノットゥルノ
・第5番 スケルツォ
・第6番 鐘の音
より無名な作品47の後、グリーグは多くの人が最高の小品集だと信じている「叙情小曲集」を発表した。 小冊子Vでは、エドヴァルド・グリーグの最高傑作に出会うことができる。音楽的表現はより重みを増し、彼自身の個性と国民性を強調する明快さと独創性をもって表現されている。 民族的な発想がより高い和声レベルに引き上げられ、和声もより高度になっている。 自然から受けた印象が、冒頭曲「Gjetergutt」にインスピレーションを与えた。 まるで山奥にたどり着いたかのように、澄んだ新鮮な空気を吸い込むことができる。前巻でグリーグが作曲を批判されたサロンからは遠く離れている。 ガンガー》では、グリーグは様式化された民謡や舞曲の作曲において高みに達している。 「Troldtog」と「Nocturno」は、ピアニストのレパートリーの中で確実に勝者となる曲である。 Troldtog "では、山の小さなトロールが群れをなして前進し、中央部では太陽から隠れ、最後にはかつてないほど姿を現す。 「ノットゥルノ "は、夏の夜のエッセンスを、穏やかで控えめな音色で再現している。 グリーグはノクターノをイタリア風に書いているが、これもイタリアの夏の夜を思い起こさせるのに役立っている。 「クロッケクラング」は、ほぼ20年先を行く印象派的な作品である。
…
【作品 57: 抒情的小曲集 第6巻】
・第1番 過ぎ去りし日々
・第2番 ストリート
・第3番 イリュージョン
・第4番 秘密
・第5番 彼女は踊っている
・第6番 望郷の念
1893年、フランスのリビエラ、正確にはマントンで、エドヴァルド・グリーグは6冊目の叙情小品集を作曲した。これは10曲の小冊子の中で最も弱いという意見が多いだろう。 ノルウェーとトロルドハウゲンが離れているため、作曲するのはヨーロッパのグリーグであり、その結果、多くの点でヨハネス・ブラームス(Johannes Brahms)を彷彿とさせる作風となった。 グリーグは「より広い筆」を使い、低音は深く、和音は厚くなり、作品54の明瞭な表現に影が差したかのようである。 Svunne Dager "と "Hjemve "の2曲で、グリーグは「ノルウェー」流の作曲法を発見している。 「ゲーデ」はデンマークの作曲家ニールス・W・ゲーデ(1817-90)へのささやかな追悼である。
…
【作品 62: 叙情的小曲集 第7巻】
・第1番 Sylph.
・第2番 感謝
・第3番 フレンチ・セレナーデ
・第4番 クリーク
・第5番 夢幻
・第6番 ヒェマド
作品57を特徴づける暗い色彩の後、グリーグは1895年の第7曲「Lyriske Stykker」に明るい色彩を見出す。 「Sylphide"、"Takk"、"Drømmesyn "はいずれも、やや洗練されたスタイルで作曲された典型的なサロン小品である。 作品43と54の成功をもたらした作風に戻るのは、《ヒェムヴェ》と特に《ベッケン》からである。
…
【作品 65: 抒情的小曲集 第8巻】
・第1番 青春の日々より~アレグロ・モデラート・エ・トランキッロ
・第2番 農夫の歌~アンダンテ・シンプリーチェ
・第3番 ユーモアのセンス~アンダンテ・エスプレッシーヴォ
・第4番 サロン~アレグレット・コン・グラツィア
・第5番 I balladetone - lento lugubre ・・・No.
・第6番 トロルドハウゲンでの結婚記念日 - tempo di marcia un poco vivace
作品65は、最も有名な叙情的小品 "Bryllupsdag på Troldhaugen "で締めくくられたことで知られている。 この曲はもともと "Gratulantene kommer "というタイトルだったが、5年前の1892年6月11日にニーナとの銀婚式を盛大に祝ったことを記念して、タイトルを "Bryllupsdag på Troldhaugen "に変更した。 しかし、このブックレットには他にも「Fra Ungdomsdagene」や「I Balladetone」といった興味深い作品が収録されている。 第1番では、グリーグが自身の青春時代を哀愁たっぷりに振り返っている。 「バラッド・トーン》と《ボンデンスの歌》は、グリーグが様式化された民俗メロディーの伝統を受け継ぐ2曲である。
…
【作品 68: 抒情的小曲集 第9巻】
・第1番 水夫たちの反乱
・第2番 祖母のメヌエット
・第3番 あなたの足元で
・第4番 山の夕べ
・第5番 舟歌
・第6番 ヴァルス・メランコリック
1899年、エドヴァルド・グリーグの作品は、叙情的な小品を集めた冊子第9号として出版された。 Valse Mélancolique "や "For dine Føtter "のような典型的なサロン曲から、"Aften på Høyfjellet "のような実験的な曲までが収録されている。 グリーグは《Aften på Høyfjellet》の初期版を友人のフランツ・バイエルに送り、次のように書き添えている: 「Skogadalsbøenの夕暮れ時の気分と考えることができる」。 この曲は非常に特殊な曲で、メロディーラインは最初の部分だけで演奏される。 1887年にエドヴァルド・グリーグとフランツ・バイエルがヨトゥンヘイメンへの旅で魅了されたフェヌグリークの音色を通して、自然を優しく描写するメロディーを提供している。 オーボエ、フレンチホルンと弦楽オーケストラのための「Aften på Høyfjellet」と弦楽オーケストラのための「Bådnlåt」である。
…
【作品 71: 叙情的小曲集 第10巻】
・第1番 むかしむかし
・第2番 夏の夕べ
・第3番 小さなトロール
・第4番 森の静寂
・第5番 ホール
・第6番 過去
・第7番 残響
エドヴァルド・グリーグは1901年、作品71で一連の叙情小品を完結させた。 Det var engang」(昔々)、「Forbi」(過去)、「Efterklang」(残響)といったタイトルは、これらが絶対的に最後の抒情小品であることを明らかにしている。 アリエッタ》は儚くメランコリックなワルツに仕立て直され、「ラストダンス」として完璧である。 Halling》では、作品19の《Brudefølget drar forbi》の主題を使用し、最も技術的に難しい曲のひとつに仕上げている。 グリーグは作品71を見事な方法でまとめており、全体として演奏するのに最も適したブックレットであろう。
…
〜
〜
〜〜
2. 作曲者:グリーグ について
2.1 Wikipedia NO(ノルウェー版)の抜粋、および、その日本語翻訳
〜〜
〜
Edvard Grieg
Wikipedia NO(ノルウェー版) URL>
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg
〜
Edvard Hagerup Grieg (1843–1907) var en norsk nasjonalromantisk komponist. Han er den norske komponisten som har fått størst internasjonalt gjennomslag, og i likhet med Bjørnstjerne Bjørnson og andre kunstnere fra siste del av 1800-tallet fikk han stor betydning for den kulturelle nasjonsbyggingen i tiden fram mot unionsoppløsningen i 1905.
Griegs mest kjente verk er trolig klaverkonserten i a-moll, op. 16. Andre kjente orkesterverk er Peer Gynt-suitene, op. 46 og 55, samt suiten Fra Holbergs tid, op. 40. Størst betydning i samtiden hadde Grieg med sine 66 klaverminiatyrer Lyriske stykker, mens det i dag er kammermusikk og sanger som regnes som mest verdifulle. Som sangkomponist er Grieg i Norge blitt mest kjent med sine tonesettinger til dikt av Aasmund Olavsson Vinje og Arne Garborg. I utlandet ble hans sanger til tekster av Henrik Ibsen, H.C. Andersen og Heinrich Heine lagt mest merke til.
15 år gammel begynte Grieg å studere ved konservatoriet i Leipzig. Senere tilbrakte han noen grunnleggende ungdomsår i København. Her møtte han tidens nasjonalromantiske strømninger. Avgjørende for utviklingen av hans personlige stil som komponist var et møte med Rikard Nordraak. Grieg begynte bevisst å ta utgangspunkt i trekk fra norsk vokal og instrumental folkemusikk og lot dem gjennomsyre et høyromantisk tonespråk.
I 1866 flyttet han til Christiania og overtok ledelsen av Det Philharmoniske Selskab. Etter noen omflakkende år bygde Grieg et hus på Hop i Fana utenfor Bergen. Her på Troldhaugen bodde han i sommerhalvåret resten av livet. Grieg tilbrakte vanligvis vinterhalvåret utenlands, gjerne på konsertreiser som gjestedirigent, klaversolist eller akkompagnatør for sin kone, sopranen Nina Hagerup.
…
〜[Excerpt from above wikipedia]
〜[上記wikipediaの日本語翻訳は次の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]
〜
エドヴァルド・ヘーゲルップ・グリーグ(1843〜1907)はノルウェーの国民的ロマン派作曲家。 最も国際的な影響を与えたノルウェーの作曲家であり、ビョルンストイェルネ・ビョルンソンをはじめとする19世紀後半の芸術家たちと同様、1905年のノルウェー連邦解体までの文化的な国民形成に大きな影響を与えた。
グリーグの最もよく知られた作品はピアノ協奏曲イ短調作品16であろう。 他によく知られている管弦楽曲は、ペール・ギュント組曲作品46と55、ホルベルクの時代からの組曲作品40である。 当時グリーグが最も重要視されたのは66曲のピアノ小品集『叙情小曲集』(Lyriske stykker)であったが、今日では室内楽曲と歌曲が最も価値があると考えられている。歌曲作曲家としてのグリーグは、ノルウェー国内ではアースムンド・オラヴソン・ヴィニエ(Aasmund Olavsson Vinje)とアルネ・ガルボルグ(Arne Garborg)の詩の作曲で最もよく知られている。 ヘンリック・イプセン、ハンス・クリスチャン・アンデルセン、ハインリッヒ・ハイネの詩による歌曲は、海外でも高く評価されている。
グリーグは15歳でライプツィヒ音楽院に入学。 その後、彼はコペンハーゲンで形成期を過ごす。 ここで彼は当時の国民的ロマン派の潮流に遭遇した。 作曲家としての個人的なスタイルを確立する上で重要だったのは、リカルド・ノルドレイクとの出会いだった。 グリーグは、ノルウェーの声楽や器楽の民俗音楽の特徴を意識的に取り入れ始め、高度にロマンティックな調性言語を浸透させた。
1866年にクリスチャニアに移り、フィルハーモニー協会の経営を引き継いだ。 数年の放浪の後、グリーグはベルゲン郊外ファナのホップに家を建てた。 このトロルドハウゲンで、グリーグは夏の間、生涯を過ごすことになる。 グリーグは冬の間はたいてい海外で過ごし、しばしば客演指揮者、ピアノ・ソリスト、妻でソプラノ歌手のニーナ・ハーゲルップの伴奏者としてコンサートに参加した。
…
〜
〜
〜〜
2. 作曲者:グリーグ について
2.2 グリーグの作品リスト・へのリンク・Wikipedia EN(英語版)
〜〜
〜
グリーグの作品リスト
List of compositions by Edvard Grieg
Wikipedia EN(英語版) URL> https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_compositions_by_Edvard_Grieg
〜
〜〜
〜〜〜
〜〜
〜
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
