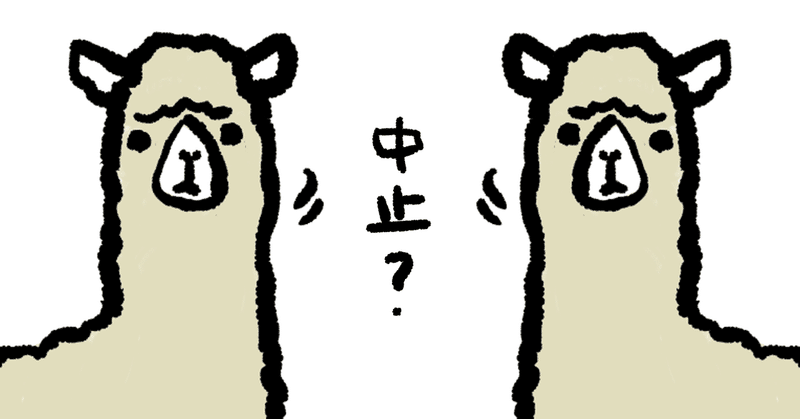
生産中止と供給責任の有無
工場閉鎖に伴い、当該工場で製造していた製品の生産を取りやめることになりましたが、代替する製造業者が見当たりません。当該工場で製造していた製品について業界団体等で供給年限が定められているということはありませんが、取引基本契約を締結して長年部品を納入している先から、「供給責任違反」であるとして、生産継続または損害賠償が求められました。応じる理由はあるでしょうか。
結論
取引基本契約に「供給義務」を定めていない限り、「供給義務」は生じず、仮に製造を止めたとしても、あくまでも製造業者としてのレピュテーションリスクの問題にとどまる。
ただし、特段の経過措置も設けずに製造を止めた場合には、信義則上の義務に反したとして損害賠償義務を負うこともありえる。
解説
①供給責任について
取引基本契約において、メーカーの供給義務として、一定期間に一定の数量を供給することが定められている場合には、供給義務が生じる。
しかし、そのような規定が取引基本契約に定められていない場合、つまり受注するか否かの裁量がメーカーにある(請書の発行によりはじめて受発注の個別契約が成立する)場合には、個別契約の受注を拒んでも何ら取引基本契約への違反にはならず、「供給責任」も認められない。
長年供給していたとしても、それだけで法律上「供給責任」がメーカーに生じることはなく、あくまでも当事者間の契約関係に基づいて権利義務が生じるのが基本である。
したがって、すでに個別契約として受注しているものについては、その個別契約の履行責任があるものの、いまだ個別契約が成立していないものについては履行責任がないので、損害賠償責任もないこととなる。
②信義則上の損害賠償
取引基本契約に「供給義務」が定められていない限り、取引を止めたとしても、メーカーとしてのレピュテーションリスクがあるにすぎない。
もっとも、メーカー側が、製造の打ち切りについて一定の猶予期間をもって通知せず、特段の経過措置を設けなかったことにより、突然に供給を打ち切られた取引先に不測の損害を生じさせた場合には、信義則上の義務に違反したとして損害賠償義務が認められることも考えられる。
まとめ
長年にわたって製品を供給していたメーカーが、製造コストと利益を見比べて、採算があわないので供給を打ち切るということは珍しくない。
そのときに、まずは取引基本契約に「供給義務」が定められていないかを確認する必要がある。
そして、取引基本契約に「供給義務」が定められていない場合には、一定の猶予期間をもって供給を打ち切る旨を取引先に通知して、取引先が必要とする在庫の発注に応じるなどの措置を講じるなどの対応をしていれば、後日紛争になったとしても、信義則違反となる可能性が低くなるものと思われる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
