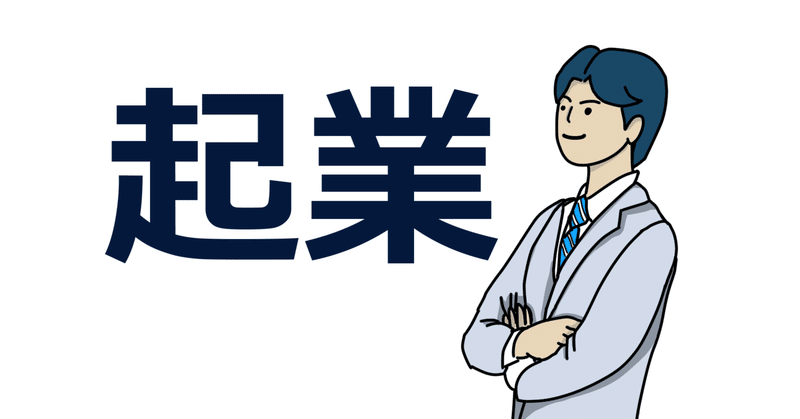
取締役⑥ー競業避止義務(1)
取締役は、株式会社に対して善管注意義務(会社法330条、民法644条)・忠実義務(会社法355条)を負っています。
そのため、取締役は、会社の利益を犠牲にして、自己(第三者を含む)の利益を得てはならない義務を負います。
そこで、会社法では、会社と取締役の利害が対立する「競業取引」「利益相反取引」「報酬」について、会社の利益を保護するため、特別の規制を置いています。
意義・趣旨
(1)意義
競業取引とは、『取締役』が、『自分または第三者のために』、『会社の事業と同じか、それに類する取引』をいいます。
(2)趣旨
取締役は、会社の事業に深く関与し、ノウハウや顧客情報などの企業秘密にも触れることができます。
そのため、取締役が自分の利益を追求しようとすると、会社の犠牲のもとに取締役が利益を得ることができてしまいます。
その一方で、会社が自社と同じような事業の経営者を、自社の取締役に迎えたいということもありえます。
そのため、会社法は競業取引を禁止するのではなく、会社の承認を得なければならないとしたのです。
要件
(1)取締役
承認を受けるべき「取締役」には、すべての取締役が含まれます。
つまり、代表取締役かどうかや、業務を担当しているかどうかは関係ありません。
一時取締役や職務代行者も、取締役と同様に取り扱います。
(2)自己または第三者のため
「自己または第三者のため」とは、取締役または第三者が実質的な利益の帰属主体となるという意味であるとする見解(計算説)と、取締役が自己または第三者の名義で取引をする(自己または第三者が権利義務の主体となる)という意味であるとする見解(名義説)があります。
計算説が多数説です。
これは、会社法432条2項で、適法な承認手続を経ずに競業取引が行われた場合、取締役(第三者)が得た利益を会社の存在と推定する規定があることから、会社法が、本来なら会社に帰属すべき利益が、会社に帰属しないことに着目しているためです。
(3)会社の事業の部類に属する取引
「会社の事業の部類に属する取引」(競業)とは、「現実に会社が行っている取引」や「会社が行う可能性の高い取引」と、「目的物(商品・役務の種類)」や「市場(地域・流通段階等)」が競合する取引です。
そもそも、競業取引規制は、取締役が会社の秘密情報を自分の利益のために利用することにより、会社に損害が生じるのを防止することが目的です。
そうであれば、定款に定めがある事業目的のうち、実際に会社が取引を行っている取引や行う可能性の高い取引(のうち目的物や市場が競合する取引)だけを規制すれば、会社に損害が生じないので十分といえます。
例えば、定款に複合機器のリースを事業目的に定めていても、会社が複合機器のリースを行う予定が全くなければ、取締役が個人事業として行う分には競業取引には該当しません。
逆に、会社が関東地方だけで活動しているのに対して、取締役が関西地方で取引をする場合、会社が関西地方への進出を予定していて、市場調査を行うなど具体的な準備を行っている場合には、取締役が行う関西地方での同一商品の販売は、「今後、会社が行う可能性が高い取引」として、競業取引に該当します(東京地判昭和56年3月26日〔山崎製パン事件〕)。
対象となる「取引」とは何か?
条文上、取引を「しようとするとき」に承認が必要とされているので、以下の行為には、承認の対象となる「取引」には該当しない。
・競業会社を設立すること
・競業会社の代表取締役に就任すること
そして、個々の取引が承認手続の対象となります。
ただし、取締役が競業会社の代表取締役に就任した場合、個々の取引の都度、いちいち会社の承認を得るのは大変です。
そこで、実務的には、代表取締役の就任時に、包括的な承諾を得ることが多いです。
承認手続
(1)事前手続
取締役が競業取引を行う場合、以下の機関による承認が必要です(会社法356条1項、365条1項)。
・取締役会設置会社 ⇒ 取締役会
・取締役会非設置会社 ⇒ 株主総会
なお、取締役会決議の際、競業取引を行う取締役は、特別利害関係人に該当し、決議に参加できません(会社法369条2項)。
(2)事後手続
取締役会設置会社の場合、取締役は、競業取引後、遅滞なく「重要な事実」を、取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。
ここでいう「重要な事実」とは、当該競業取引が会社の事業にどのような影響を及ぼすかを判断するために必要な事実であり、例えば、取引の相手方や目的物、数量、価格などを指します。
適法な承認のない競業取引の効果
適法な承認手続を経ていない競業取引も有効です。
なぜなら、取締役の競業取引の相手方にとって、その取引が競業に該当するかは必ずしも明らかではないからです。
会社としても、競業取引の効力を否定しても、会社に利益を帰属させることができるわけではないので、むしろ、取引の効果を維持して、取締役が得た利益を、損害賠償請求により会社に帰属させるべきだからです。
そのため、取締役が、会社の承認を得ないで競業取引をしたときは、その取引によって取締役や第三者が得た利益の額を会社に生じた損害額と推定し、会社は取締役に対して損害賠償を請求できます(会社法423条1項2項)。
参考文献
江頭憲治郎『株式会社法〔第8版〕』p453-456
高橋美加ほか『会社法〔第3版〕』p199-202
田中亘『会社法〔第3版〕』p250-252
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
